08/13�̓��L
05�F53
�y�{���z�g�ِ��E�h�ɓ��݂��ޏ[���̃Z�~�i�[�\�\7/28-29 �C�[�n�g�[�u�قɂ�(2)
---------------
.
 �@
�@
�{���C�[�n�g�[�u�ف@�@�@
�@������ (º.-)���
�g�ِ��E�h�ɓ��݂��ޏ[���̃Z�~�i�[�\�\7/28-29 �C�[�n�g�[�u�قɂ�(1)
�@����̂Â��ł��B
�@�y�Q�z�@�{���ɂ�����u�����̉��P�v�\�\�Z�̂���S�ۃX�P�b�`�ց@�\�\�\�@�H�}���ۂ���
�@�H�}����̌������\�́A�C�x���g�̃e�[�}�g�ِ��E�h�ɗ��߂Č����A����猫���ւƎp���ꂽ�s�ِ��E�̐S�ہt�@���A���n�����w�j�Ƃ��Ę_������̂������Ǝv���܂��B���̂��Ƃ́A��茧���w�j���A���{���w�j�̏d�v�Ȉ�x�����`�����Ă������オ�������Ƃ������Ƃł���A����͓����i����������吳����j�̓��{���w�j�̎咲�ł��������R��`�A������`���͂邩�ɒ����āA���㎍�ɂȂ����čs���悤�Ȑ��I�ȕ��݂ł������ƌ����܂��B
�@�������A��͂��́s�ِ��E�t�ւ̊J��ɐG�����ꂽ�g�V�������A�Z�́h�̔������A���̂܂܂̌`�ŕ\�������̂ł͂Ȃ��A�u�H��ӂׂ����v�Ƃ����A��≡�ɃV�t�g�������R��`�I�A������`�I�Ȍ����ɂ���āA���Ԃɖ₤���̂ł����B�����āA��i���̂��A�����I�ȓ���̈������ӂ����̂ɑg�ݑւ��A���Ԃɗ�������Ȃ��悤�ȁg�[���̐��E�h�ɂ͊W�����Č��\�����̂ł��B�����ɂ́A��̓V�˂������܌������E�������ɂ́A�Ȃ������I�������铖���̎Љ�ɑ��āA��������ꂳ���邽�߂ɑ�����A���̂ɂ��ނ悤�ȍs�Ղ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�@����ɂ��Ă��A�����ɂ́@�䂪����܂��B��̏��ɐ�����ꂽ�����̏W�̏����]�_��ʂ��āA�����㊥ 13-14�̌������A���̐[���̃��`�[�t�ɂ܂ők���Đێ悵���p���邱�Ƃ��A�ǂ����Ăł����̂��낤���H�d�Ƃ�����ł��B���̓_�ɂ��ẮA�̂��قnj����̓`�L�I�����ɗ��߂āA�M�g���̐����ƒ��z���q�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B
�@�H�}���ۂ���Ɋւ��ẮA��������Ŕ��m�_�����瑽�����p�����Ă��������āA�w�t�ƏC���E��P�W�x�̌㔼�����̓ǂݍ��݂�i�߂����Ƃ�����܂����B
�@�����H�}����́A�w�t�ƏC���E��P�W�x�Ɓw�����̑��������X�x,�u�y�_�Ƃ��ˁv�ȂǁA�����̐��U�̎����Ƃ��ẮA�_�w�Z���t����̑O������ȑΏۂɂ��Ă����܂����B���݂ł́A�����Ɏ���s�S�ۃX�P�b�`�t�̌`�������A�\�\�g���w�h�Պ��h����Z�́E�����U���̎�����Ώۂɂ��Ă�����悤�ł��B
�@�����āA��ɂ���āA�g�������h�O�̍L�ĂȎ��ӎ����\�\������̏��ʘ_���A�V���A�G�����������_�l�ɂ���āA���̎����ɂ��Ă��O�l�����̋��n�����܂��B
�@�H�}����́A���łɁw�{�� Annual�xVol.25 �Ɂu�{���̒Z�̂Ɗ�茧�̕��w���� �\�\ �S�ۃX�P�b�`�ւ̓����x�A�w�_�� �{���x16��,2018�N3�� �Ɂu�w��薈���V���x�u���|���v����ъ֘A�L���Ɍ��镶���`�d�̏��� ���̂Q �\�\ 1910�N��̕��������A�{���̕��w�h�Պ��Ɛΐ��Ɋւ����l�@�x�Ƃ����_���\����A���N 6��2���ɂ́A�w�����{��������x�̗��ŁA�u��ؕ��w�̓��B�_�ƌ����̐S�ۃX�P�b�`�v�Ƃ����W��Ō������\���Ȃ����Ă��܂��B����̍u���́A������A�̌����܂��āA����猫���Z�́E�U�����ւ́g�[�w�h�̗�����A����Ɍ@�艺���Ę_����ꂽ���̂Ǝv���܂��B
�@�{���́A���Ȃ��Ƃ���L�̂Q�_����ǂ����ŁA����̂��u�����܂Ƃ߂�ׂ��Ȃ̂ł����A�ӂ��Ȃ���M�g���͂܂������̘_����ǂ�ł���܂���B���̂��߁A�ȉ��̂��Љ�́A�������������̌����ȉ����ӂ���ł��܂����낤�Ɨ\�z�����̂ł������A�Ƃ肠�����́y����z�Ƃ��Ă��ǂ݂�������������킢�ł��B

�C�[�n�g�[�u�ى��ɂāB
�@�܂��͍u���̑�ӂ��d
�@�ΐ����̏W�w�ꈬ�̍��x�s�����̂� 1910�N12��1���A�{���́w�̍e�`�x�́A�� 1911�N1������n�܂��Ă��܂��B����͋��R�̈�v�ł͂���܂���B��������̒Z�̂Ɏh������A�͂��߂͂����͕킵�A�₪�ēƎ��̉̂����悤�ɂȂ������Ƃ͗�R�Ƃ��Ă��܂��B
�@�������A�����́A��ؒZ�̂���e�����������łȂ��A��̕]�_��������w�_�Ǝv����ێ悵�Ă����Ǝv���܂��B
�@��́A�g�\���������̂��A������ς��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��h�Ǝ咣���Ă��܂����B����́A���w�����H�ƂЂƂȂ���̂��̂Ƃ��Č���Ƃ����l�����ɂȂ��āA�����Ɏp���ꂽ�ƌ����܂��B
�@�܂��A��́A1909�N11-12�����\�́w�H��ӂׂ����x�ŁA
�u���͏������ł����Ă͉��Ȃ��B�l�Ԃ̊�����k�c�l�̕ω��̌����Ȃ���A�����Ȃ���L�łȂ���Ȃ�ʁB�]���Ēf�ГI�łȂ���Ȃ�ʁB�v
�@�Ə����Ă��܂��B�{���̗L���ȕ\���F
�u�O�Ɏ��̎���ŏo�����w�t�ƏC���x���A�����ꂩ�炠�Ƒ����܂ŏ����t���Ă�����̂��A�����݂͂�ȓ��ꎍ�ł͂���܂���B�������ꂩ��A���Ƃ������������Ǝv���ċ���܂��A����S���w�I�Ȏd���̎x�x�ɁA�����ȕ��̋�����Ȃ��ԁA�����̋�������A�@��̂���x���ɁA���낢��ȏ����̉��ŏ�������Ēu���A�ق�̑e�d�ȐS�ۂ̃X�P�b�`�ł�������܂���B�v
�{������[200]1925.2.9.�X���ꈶ�B
�u�킽�����͂��Ƃŕ�����Ƃ��̎d�x�ɂ����ꂼ��̐S���������̂Ƃق�Ȋw�I�ɋL�ڂ��Ēu���܂����B���̈ꕔ�����킽�����͕��ɂ��Ȃ���N�̏t�{�ɂ����̂ł��B�S�ۃX�P�b�`�t�ƏC���Ƃ����Ƃ��肵���k�c�l�v
�{������[214a]1925.12.20.��g�ΗY���B
�@�́A��̑�̒Ɍĉ�������̂ł��傤�B���̂Ƃ��ǂ��ɕ����ӎ��E����Ƃ��̕ω��̗�����u�Ȋw�I�v�Ɂu�����v�Ɂu�����v�ɋL�ڂ���Ƃ������Ƃ��A���҂ɋ��ʂ��鎍��̊�}�ł��B�����āA��̏ꍇ�ɂ́A���̂Ƃ��ǂ��̒f�ГI�Ȋ�����L�^����̂ɓK�����Z���`�Ƃ��āA�Z�̂��d�p���܂����B�����̏ꍇ�ɂ́A����ɂ���������u��u�̊�����Ȃ��ŁA�Z�̘̂A�삩�玩�R���̒����`�Ɉڂ��čs�����ƌ����܂��B
�@�������A�s�̎������⊇�ʕt���s�𑽗p�����̂��A�����������������������u��u�̊���̘A�Ȃ���A�ł��邩����u���̂Ƃق�Ȋw�I�ɋL�ځv���邽�߂̍H�v�������̂ł��B
�@��̌����g�����̉��P�h�Ƃ́A���X�̐����̂Ȃ��œݖ��������o���Đ������A�u���Q���v��v����u�V�N�Ȃ�S�v�����߂����Ƃ������ƌ����܂��B1910�N1���́w�X�o���x�Ɍf�ڂ����]�_�w�������x�̂Ȃ��ŁA��͎��̂悤�ɏ����Ă��܂��F
�u��X�̗����́A���̋ߑ㐶���̕a���k�����̐������u�V�N�Ȃ�S�v�������Ă��邽�߂Ɂu�����̔�J�v������ɔ����Ԃɂ��邱�Ɓ\�\�\�H�}���l���������A��U���A���͂��A�����đ��a�������Â˂āA��É�X�l�Ԃ������ė����Ƃ���̂�����T�z���̂āA���ő��T�z�̗U���ƂȂ�A���ʂƂȂ����Ƃ���̉�X�̎Љ����̂����錇�ׂƖ����Ɣw���Ƃ���A�����āA���Ȃ��Ƃ���r�I������^�ւ�Ƃ���̐V������������ׂ߁A�������P�̓w�͂��N�������߂邾���̗p���Ȃ����ʂ��̂ł��낤���B�v
�@�����Ƃ��A��͂����ŁA�u��X���Љ����������錇�ׂƖ����Ɣw���Ƃ���v�ƌ����Ă���A�Љ�̖����Ɛ키���Ƃւ̊S���A�ނ̏ꍇ�ɂ͂Ђ��傤�ɋ������������Ƃ�z�N�����܂��B
�@����ɑ��āA�{���̏ꍇ�ɂ͂ǂ��������̂��H ��Ɉ��p�������Ȃ��������ł́A�Љ�I�S����͈���ނ��āA�l�ԐS���̖��Ƃ��ĒT�����邱�ƂɎ�ȊS������悤�ɂ������܂��B���������̈���ŁA�������܂��A���w���g���H�ƂЂƂȂ���̂��́h�Ƃ��đ����Ă����ƁA�H�}����͎w�E����܂��B
�@�����́A��̂悤�ɎЉ�I�S���X�g���[�g�ɕ\������l�ł͂���܂���ł������A������Ƃ����āA���ꂪ���������Ƃ��f��ł��܂���B���̓_�́A�̂��قlj������Y����̃R�����g���Љ��ۂɁA�ēx�l���Ă݂����Ǝv���܂��B
�@
�@����u�l�Ԃ̊�����̕ω��v�ƌ����A�������u���ꂼ��̐S�����v�ƌ����Ƃ��A���̎��ۂ̓��e�́A���Ȃ炸�����������̓���I�Ȑ�������A����Ώ����I�Ȑ����̈����ƃC�R�[���ł͂���܂���ł����B���҂Ƃ��ɁA���̔]���ɋ�������s�S�ہt�́A�����Ɂs�ِ��E�t�I�Ȃ��̂����삵�Ă����ƌ����܂��B
�@��ň��p������g�ΗY���Č������Ȃ̎�O�̕����ɂ́F
�u�Z���N�O������j�₻�̘_���A�����̊����邻�̂ق��̋�ԂƂ��ӂ₤�Ȃ��Ƃɂ��Ăǂ����������Ȋ����₤�����Ă��܂�܂���ł����B�v
�@�Ə�����Ă���̂ł��B���́u�������Ȋ����悤�v���A�u���ꂼ��̐S�����v�̓��e�ɂق��Ȃ�܂���B
�@�H�}����̍���̍u���ł́A���̓_���K�������\���ɘ_�����Ă͂��Ȃ������悤�Ɋ����܂����B�ȉ��ł́A���ŏH�}���z�z���ꂽ���������ƂɁA�M�g���̂���_���e�G�Ȑ������܂����āA��̓_���������������Ă݂����Ǝv���܂��B
�u��� 1908�N4���A�Ƒ���u���ĒP�g���H����㋞�A�V���ȑn�슈������}���ď����\���n�߂����̂̂��ꂪ�����ꂸ�A�n���ɂ��������ōĂђZ�̂������n�߂��B�w�����x�p���̗��N�A1909�N1���Ɂw�X�o���x��n���A3���ɓ��������o�ŎЂ̍Z���W�̐E�ɂ����ƂɂȂ������A�Ȃ��Ȃ��Ƒ����Ăъ邱�Ƃ��ł����A�k�c�l6���ɑQ���Ƒ����}�������A10��2���A��Ƃ̕s�a�ɂ��Ȑߎq���Əo���Ď��ƂɋA��A���̌���͂̐����ɂ���� 10��26���ɋA����B�w�H��ӂׂ����x�́A�����̑����̌ォ�珑���ꂽ���̂ł���B�v
�H�}���ہF�w�_�� �{���x16�����B
�@�ΐ��́A�P�g�㋞���Ă܂��Ȃ��A�����I�Ȑ����ŒZ�̂����͂��߂�̂ł����A1908�N6���ɏ����ꂽ���M�̍e�w�Ƀi���x���₳��Ă��܂��B
�@
�u�@�Έ�����ĕ����ʂ������낵���ƎR��c��J�̂Ƃǂ낫
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�瘾�̒J���X�Ɩ�ėN���킭�J�̋��т��r
�@�A�l�݂Ȃ��|��Ĕ`���S��ɉ䕽�R�Ɣn���ē���
�@�B�Ɨ���Ƌ���N���Ɩ�ӂ܂Ȃ������ߒ��镢�ʂ̐l
�@�C�����̎R�̂��Ȃ��ɉ����̓������߂��悠����v��
�@�D���g�ɐԂ��{���Ďւ����ސl��߂ɂ݂ĕa�������
�@�E�����ւ���q�Ȃ�����}�n�i�܂�����j�ɖk�ɑ����d���̐�
�@�F�w���Â�s���x�w�N�Ɖ䂪����k�ɂ̕X�̊�ɍ��܂ނƂ䂭�x
�@�G�������܂������䂭��މ䂪�S�ĂЂƂ苹�̌˂��o��
�@�H��ɂ����Ж�����܂��ē앗�ɌN���₩�ނƉ̐�����
�@�I���̏���͂邩�ɓV��̓��̐I�����ĉ䂪�_���a��
�@�J�q�����̋{�̔@���ɂ���������ޗ��u���ݔ��e�𓊂��r
�@�K�S���̉�������x�ɐ����Ԃ��傢�Ȃ鑫����ɗ���
�@�L�䎞�ɓV��ɂ���ߌ��̖ڂɂɂ�܂�Ė���\�͂�
�@�M���̎��ɗ��̗l�Ȃ����ɕ����Ď�������߂�
�@�N�킪�F�͖k�̕l�ӂ̍��R�̕l�֎q�̍��Ɏ��ɂĂ���ɂ�
�@�O��\�㗢�Â���l�̔����Ɉ�H�̌����ނƍs���v
�@���H�}���I�яo���ꂽ�����̂Ȃ�����A�����16���I��ł݂܂����B�ەt�������́A�����̕X�̂��߂ɃM�g�����t�������̂ł��B
�@�@�`�B�C�G�́A�����́g���ӎ��h�̐[�w��`���������Ƃ��Ă����̈ӎ��̔��f�ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B�C�ȉ��́A�������Č@��N�����Ă����[�w�̑��d�d���Ȃ킿�s�S�ہt�̃X�P�b�`�ł��傤�B�E�́u����}�n�܂�����ɖk�ɑ����d���v�́A�������ɂ��悭����郂�`�[�t�ł��B���Ƃ��F
�u���������Ȃ薾�邭�Ȃ�
�@�̂͂炪�ςƂЂ炯���
�@������Ȃ�������Ȃ����ꂭ���͓��ɔR��
�@�d�M����͂₳���������V�q�����
�@�x�[�����O�s�܂łÂ��Ƃ����͂��v
�{���w�t�ƏC���x�u��{�ؖ�v���B
�@�C�D�C�I�́A���R�̕��i�����قȂ������ŕ\��Ă��܂��B��̏ꍇ�A�����͐[��ɐQ���ʼnr�ƋL����Ă��܂�����A���i����������s�����肵�ăX�P�b�`�������̂Ƃ͈Ⴂ�܂����A����ɂ�������炸�A�����Z�̂ƂЂ��傤�ɂ悭�����ӂ��������Ȃ��ł��傤���H
�@�F�C�H�C�N�O�́A����̐e�����l�Ƃ̑Ό��z���v�킹�܂��B�e�F�����l���͂킩��܂��A����̐l�Ƃ̋��ڂ����ł����悤�Ƃ��Ă���悤�ȁA�S�C������̂�����܂��B
�@�J�`�M�́A��������Ă����Љ�̈��́A���邢�́u�����v�I���͂̈����ƁA��̔��t�S���v�킹�܂��B�������A�������s�S�ہt�̑��Ƃ��Ċ�ɉf�������̂ɂ���������܂���B
�@����G������́A1973�N�ɁA���́w�Ƀi���x�����グ�āA
�u�ΐ��̖��ӎ��̐��E�A�[�w�S���݂��Ȃ��̂��������Ȍ`�ŏo�Ă�����̂Ƃ��ĂƂ炦��ƁA���ɂ������낢��ł��ˁB�v
�@�Əq�ׂĂ��܂��B�����ꂽ�Ȋw�҂Ȃ�ł͂��v��ƌ����ׂ��ł��傤�B
�@��؎��g�A�w�X�o���x(1910�N1���j�f�ڂ̕]�_�u�������v�ŁA�u�ے����v�ɂ��ā����̂悤�ɘ_���Ă���̂ł��F
�u��ÁA�ے����ׂ������������āA�R���ɏے��Ƃ��ӎ�i���p�Ђ��ׂ��ł���B�����Ă��́w�������x�́A�K�����Ԃł͌��t�ɂ��`�ɂ��\�͂����Ȃ��A���[�����ł��Ƃ���̈Ӗ��i�k�c�l��X�͈��Ӗ�����������ɓ��āA�����̏�ɋ���ꍇ������A����ɐێ悷��ꍇ������j�łȂ���Ȃ�ʁB
�@�Ⴕ���ے��Ƃ��ӎ����A�P�Ɍ`��ςցA���t��ςւĕ\�͂��Ƃ��ӎ��ɉ߂��Ȃ�����A����͖��p�̎�i�ł���B���t�̗V�Y�ł���B�܂₩���ł���B�v
�@�����̏��N����̒Z�̂�A���̌�́s�S�ۃX�P�b�`�t�ɂЂ��傤�ɋ߂��A�����̑����Z�̂̈ꕔ�́A�������ꂽ�w�ꈬ�̍��x�̖`���ɒu���ꂽ�u���R�\��v�ɂ��̂��Ă��܂����A�啔���͊�������A�s�ِ��E�t��`�����悤�Ȃ��ǂ남�ǂ낵�����̂́A�����ł͌��\����Ȃ������̂ł��B����ӎ��ɋ߂����̂������̗p���ꂽ�ƌ����Ă悢�Ǝv���܂��B
�@�����Ƃ��A�w�Ƀi���x�Ɓw�ꈬ�̍��x�̂������ɁA�G���w�����x�Ɂu�Δj�W�v�Ƃ��Čf�ڂ��ꂽ���̂������āA�����ɂ͐[�w�S���I�Ȃ��̂������̗p����Ă��܂��B
�@�����ŁA�ЂƂ^��Ɏv���̂́A�w�ꈬ�̍��x���s���� 14�̒��w�Q�N���������������A�ǂ̂悤�ɂ��đ�́g�[�w�Z�́h�̉e�����邱�Ƃ��ł����̂��d�Ƃ������Ƃł��B
�u 4 �~�ƂȂ�ď��i����j�݂ȍ��ގR��ɗ[�z�����тĔ����ƌ��Ă�
�@17 ���炢��̂ւт������������Ȃ�����w�Z�̏t�̉����Ȃ肵��
�@19 �҂���ΊD�F�̉Ƌu�ɂ��Ă肳�Ă����т����u�ɖ��Ȃ�
�@21 �₤�₭�Ɏ��Ԃ�ދu�̕ӂɊ���������l�ɂ��Ђ���
�@22 ���͂ꌩ�挎������R�̐�͎Ⴋ�M�l�̎��X�Ɏ�����v
�{���w�̍e�`�x�k�����`�l���B
�@�����݂͂ȁA1911�N�i14-15�j�̍�Ȃ̂ł��B�\���ɂ܂��ق��_������܂����A��N�ɂ��đ������[�w�ӎ��ɕ��������Ă��邳�܂��M���܂��B�����₩�ȁu���炢��̂ւсv�������̂��߂����̂́A���F�͒N����ɂ��Ă��Ȃ��A�����������������ƌ������̂Ś}��ꂽ�Ƃ������Ƃł��傤�B
�@1912-13�N�ɂȂ�ƁA�����̂悤�ɁA��������āA�����Ǝ��̋�������킵�Ă��Ă���悤�Ɍ����܂��F
 �@
�@
�u26 ��������͈ꂷ�����Ƃɂ킪�����Ђ����T���ɂĂ��܂藈���
�@28 ���Ƃ��́T�ЁU���̂��Ƃ��ق������͗҂�������������킩����
�@32 ���͐Ԃ��������_����Ă������炫�������T��Ȃ��Ȃ�
�@37 �����Ȃ���k�ɂ͂��䂭���Ȃǂ̂���ׂ���̂��͂ЂȂ炸��
�@38 �������܂��h��͂Â�̊�Ԃ�����Ȃ͂ЂƂ�߂�������ւ�
�@39 �[�ݍs���Ă͂Ă͒�Ȃ����ƂȂ�[�邼������Ђ��Ȃ���
�@49 �킪�܂ɖ�������Ăӂ肻�T�����錎���ɂނ炳���ɂ��U�₯��
�@52 ���ȂǂƂ����Ăӂ��ތ����̏d���ɂЂ����R�̖X
�@53 ���_�͂ЂƂ��ʓ��肵����s�`�ƂЁU���������̉���
�@54 ���肽��͂��˂̋�̏����ɂƂ�ꂶ�ƂȂ����̂��炷��
�@
�@68 �����킵���@���������Đ�����̉��̈�ڂ������炵�Č���
�@69 ������̂���̈�ڂ���߂��������Ȃ��߂ĂƂ��ÂނȂ�
�@70 ���s�̐��傽�����̉��ɂ��U�₫���Â鐯�����肯��
�@71 ���p�̉�͕��X�����Čł߂��X�̂���������y��
�@
�@72 ����͔]�̉��܂ł��݂Ƃق�ɂ݉��F�̔g�������
�@73 �����ɗ��Ă���ɑ�����������A���J���F�̉_�悩�Ȃ���
�@74 ���Ȃ�l�̂��˂����͂ВJ�͂܂��낭���܂�ɂ���v
�w�̍e�`�x�k�����`�l���B
�@���w��w�N�̌������A�w�ꈬ�̍��x�ȑO����A�G���w�����x��w�X�o���x��ʂ��đ�ɐe����ł����Ƃ͍l���ɂ����ł��傤�B��������ƁA��ƌ����̊ԂŁA����g���n���h�������l���������̂ł͂Ȃ����d�d�Ƃ������Ƃ��l�����Ă���Ǝv���܂��B
�@�����������A�����́g���d�h�ɂ́A���̂悤�ȒZ�̂�]������ӂ��͖��������悤�Ȃ̂ł��B�H�}���Љ�ꂽ�w��薈���V���x�̕��|���i1912�N�j�ł́A���R�̕��i�����̂܂܉r�Z�̂́A��҂̗�������̋��ӂ�ǂݎ�����̂ł����Ă��A���]����Ă��܂����B��������ƁA�������A�w�Z�̐�y��n���̉̐l����A���̎�́g�[�w�Z�́h�̎�قǂ������Ƃ͎v���Ȃ��̂ł��B
�@�����ŁA�g���n���h�Ƃ��Ē��ڂ����̂��A�g�����@�h�ł��B
�@�����́A1910�N�ɓ����O����w�Z�𑲋ƌ�A���N4���Ɍ����̂����������w�Z�ɉp��̏����u�t�Ƃ��ĕ��C���܂������A�����̂��߂ɓ��N11���ސE���āA�̋��̓������ɖ߂��Ă��܂��B
�@�����̒��W���܂��Ȃ����邱�Ƃ́A�i�ʏ�́j���Ǝ��̒��������ɂ���ė\�ߔ����Ă����͂��ł�����A�{�l�ɉ��̂̂Ȃ���茧�̐������w�ɖN�Ԃ������C�������Ƃ́A�ƂĂ���Ȃ��ƂɎv����̂ł��B�����ŁA�����ɂȂ�܂����A���͑�ɂ��������g���w�N�h�ŁA��̕�Z�E�������w�Z�ŕ���O�̈ꎞ�����߂������߂ɐ����ɗ����̂ł͂Ȃ����ƍl������̂ł��B
�@���́A�������I������A���s���Ŗ@�w�Ȃǂ��w�тȂ����A���̌�̐l���͑�p�A���F�ւƁA�I��܂ł��O�n�ʼn߂������悤�ł��B�I�펞�͓얞�B�S��������Ђ̏햱������ł������A���S�l�̒lj��ɂ��ƁA�����ւ��̍L���l�ŁA�܂����a��`�҂������ƌ����܂��B�N���ɑ�ɌX�|�������Ƃ��l������l�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�u�@�@�@�����@�𑗂�
�@�@�@
�@�H�J�ɂ��ƁU�����ʂ�
�@����炩�ɖjዂ���
�@�t�͂��܂����̑�����
�@���U�ЂƂ肨���藈�܂���
�@�r���ւ��ӂ͌Q��
�@��冋o�k���݁l�����Ԃ����˂�
�@���݂̂��̈ꂷ������
�@�Ђ�����ɉJ�͑�����
�@�F�悳�͎t���ȌĂы��Ђ�
�@�����܂��邩�̏����̂�
�@������[��]��R�k�������l�ɍs����
�@�t�̂��݂̖j�̂���ӂ���v
�{���w���ꎍ����e�x���k�����e(��)�l
�@������͔ӔN�̎��ł����A���ɑ��鐒�q�ɋ߂��Ǒz���A20�N�ȏ�̂��܂Ō����̔]���ɂ͏Ă��t���Ă����̂ł��傤�B
�@���̍�́A�����̓������Ə㋉�����l�Ɂg�����@�h�������āA��∫�V��̊��R�֓o�R�������̎v���o�����ƂɂȂ��Ă��܂��B���k�����̔��肪���o�R�ɓ��s�����Ƃ������Ƃ́A���k�����̊Ԃɓ����Đe������������l�����܂����A�����Ƃ��e���������ł��傤�B�u�F�悳�͎t���ȌĂы��Ђ��v�ƌ������v�����炢�A�ނ���A�����ȏ㋉�������ɂ��r�߂��Ă����Ƃ����v���܂��B
�@������������������1910�N11���Ƃ����A�w�ꈬ�̍��x���o�ł����O�̌��ł����B���������ɁA��ɂ��ĂȂɂ��b�����Ƃ���A�w�����x�w�X�o���x�ɔ��\���ꂽ�Z�́A�����A�]�_��ʂ��Ēm������ł��������ƂɂȂ�܂��B���̂Ȃ��ɂ́A�w�Ƀi���x���܂܂�Ă����ƍl�����܂��B
�@������ƌ����̊Ԃ́g���n���h�������Ƃ������ڂ̏؋���L�q�����͉����Ȃ��̂ł����A�M�g���ɂ́A�����ւ肤�邱�Ƃ̂悤�Ɏv����̂ł��B
�@���āA�H�}����̂��b�́A���o�g�̒����ƁE�ݓS�ܘY�ɂ��y��ŁA�n�����w�E�|�p�j�̂Ȃ��ɋ{�����ʒu�Â���X�P�[���œW�J���ꂽ�̂ł����A�����܂ł��Љ��]�T������܂���ł����B
�@����́A�����̂R�l�ځA�M���N�Y����̍u�����܂Ƃ߁A�ł���Ώ����̃R�����e�[�^�[�������v����̃R�����g�܂ň�����Ǝv���܂��B

�@�@�@������ւÂ���
�@�g�ِ��E�h�ɓ��݂��ޏ[���̃Z�~�i�[�\�\7/28-29 �C�[�n�g�[�u�قɂ�(3)
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@

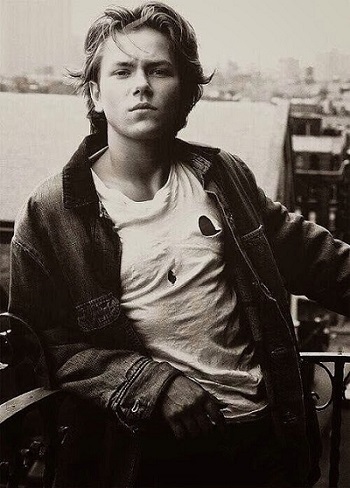
 �@
�@
 �c
�c