01/12の日記
09:09
【吉本隆明】の宮沢賢治論――文語詩の発見(2)
---------------
.
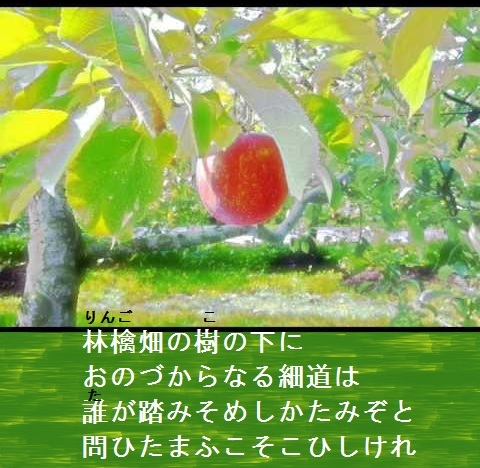
島崎藤村『若菜集』「初恋」より
こんにちは (º_-)☆ノ
明治まで、日本語では、伝統的に、7音と5音の組み合わせによる音数律が、韻律の“決定論”だった。
「日本の近代詩が複雑になった文明開化の意識を7・5調の決定論の形式に盛り込もうと試みたのは当然だった。」
「近代の詩が西欧近代を文明開化として受け入れようとしたとき、詩人たちは7・5調の長歌の伝統的な形式を基にして新しい内容の叙事・叙情詩を作ろうと試みた。」
近代初期の詩人たちは、伝統的な7・5調の形式の中に、西欧近代の意識を盛り込もうとして苦心した。
「文芸のうえで西欧近代の特徴は何か。要素的に考えれば単純に言うことができる。
言語表記のうえの人物、その情念などは、たとえ一人称で記されていても記している作者その人とは別と考えるべきこと。そして作中人物のあいだの関わり方は、外からも内からも描写して物語化することができること。その舞台となる場は、物語とは別の次元にある地の文で行われていること。そして作品全体を見渡せば、かならず作者の人間像を浮び上がらせることができるが、登場する人物の像と、作者の人間像がどんなに似ているように思われるときも、短絡して結びつけることができないこと。
これくらいの条件が揃っていれば、西欧近代の文芸の条件を具えていると考えていい。」
しかし、7・5調の流れに載せて、これらの条件をそなえた内容を歌い上げる試みは、じっさいには困難を極めた。
「西欧近代の精神秩序を重んじて表現すれば、7・5音律の秩序は乱れることになるし、7・5調の形式秩序を固執しようとすれば、西欧近代の精神秩序は、形式の枠組みから制約されることになる。たとえば北村透谷の『蓬莱曲』のような長編譚詩は前者の例であり、藤村の『若菜集』の詩篇は後者の例にあたるといってよい。」
吉本隆明「詩学叙説―――七・五調の喪失と日本近代詩の百年」, in:吉本隆明『詩学叙説』,2006,思潮社,pp.11-12.
こうして、7・5調に西欧近代の意識を盛り込む試みは挫折した。透谷は、7・5調を棄てざるをえなかったし、藤村は7・5調を厳格に守ったかわり、そこに盛られた抒情意識は不満の多いものとなってしまった。
「藤村が精根を費やしたような意味では、7・5調の音数律の伝統形式と西欧的近代の心事とを調和させようとする試みは失敗に帰し、7・5の音数律は次第に近代詩から影を潜めるようになった。」
op.cit.,pp.14-15.
藤村の近体詩の問題点を、吉本氏が挙げている“比喩”の場合について見ますと、たとえば:
夕波くらく啼く千鳥
われは千鳥にあらねども
心の羽をうちふりて
さみしきかたに飛べるかな
若き心の一筋に
なぐさめもなくなげきわび
胸の氷のむすぼれて
とけて涙となりにけり
蘆葉を洗ふ白波の
流れて巌を出づるごと
思ひあまりて草枕
まくらのかずの今いくつ
かなしいかなや人の身の
なきなぐさめを尋ね佗び
道なき森に分け入りて
などなき道をもとむらん
〔…〕
道なき今の身なればか
われは道なき野を慕ひ
思ひ乱れてみちのくの
宮城野にまで迷ひきぬ
心の宿の宮城野よ
乱れて熱き吾身には
日影も薄く草枯れて
荒れたる野こそうれしけれ
「心の羽をうちふりて」「胸の氷のむすぼれて/とけて涙となりにけり」「蘆葉を洗ふ白波の/流れて巌を出づるごと」「草枕/まくらのかずの今いくつ」「道なき森」「なき道」「心の宿」といった比喩表現は、たしかに使われているのですが、吉本氏によれば、それら藤村苦心の表現は、
「単に比喩としかいえず暗喩になりえなかった。〔…〕
『心の羽』はわが身を夕波千鳥になぞらえたために加えられた比喩、『心の宿』は住んだ宮城野の『仙台』の町を精神の住み家とした比喩としてしか成り立っていない。」
吉本隆明『詩学叙説』,pp.12-13.
吉本氏の書いている意味が、いまいちわからない点もありますが、たしかにこれらの比喩は、あまりにも表面をなでさすっているような感じしか与えないのです。たとえば、「心の羽」という喩え方が、あてもない旅にでかけた作者の動機とどうつながっているのか、よくわかりません。いや、じっさいには作者の中での内的つながりなどはなく、単に歌の掛け合い言葉の都合でそう言っているだけのようにも見えてしまいます。「胸の氷」以下についても同じことが言えます。
そのために、これだけたくさんの比喩が使われていながら、具体的にこのとき作者は、どういうきっかけで、どんな気持ちを抱いて旅に出、車窓をつぎつぎに過ぎる風物から、それぞれどんな感慨を得たのか、‥このとき一回かぎりの個性的な体験のイメージが、まったく伝わって来ないのです。
そして結局、すべては形のない通りいっぺんの哀愁のなかに流しこまれてしまいます。作者の心の状態について、具体的に推し量ることのできる表現は、「乱れて熱き吾身」という、あまりに漠然とした一句があるきりです。
つぎに、北村透谷の場合はどうかと言うと:
「透谷は、それほど7・5調に固執せず、自分が信じた近代の悩みを物語性(譚詩)として具象化した。政治的挫折や幽閉の切実さであったり、愛する女性との別れであったり、世間に背をむけたための悩みであったり、少くとも物語性をもたせることで具象化してみせた。」
吉本隆明『詩学叙説』,p.14.
そこで、つぎに宮沢賢治の定型詩について言及があるのですが、残念ながらここでは1行未満です:
「音数律を形式として固執するかぎり、詩歌の近代化は不可能だったと言いきれるかどうかはわからない。後になって萩原朔太郎は自己の形而上的な思念を文語詩で試みてみせたし、
宮沢賢治は、人物と自然との交感を物語として仮構することで伝統的な叙情とは異質の文語詩を創り出してみせた。」
a.a.O.
つまり、宮沢賢治は、伝統的な7・5調の形式で近代的精神秩序を表現することに成功した、と理解してよさそうです。
いかにして、それができたのかというと、吉本氏によれば、「人物と自然との交感を物語として仮構すること」によってだったと言うのです。
この“物語性”“フィクション(仮構)性”という指摘は、賢治の文語詩の特徴づけとしては意外な感じがします。しかし、そうなのかもしれないし、そこに着目して読むのがよいのかもしれない。
たしかに、“物語”の場面のようなふんいきがあることは、前回とりあげた文語詩諸篇に共通していたと思います。小説になるほどの筋書きはないし、完結性もありません。しかし、“物語”のワン・シーンとして見れば、なるほどと思われます。
賢治が、文語詩への推敲・改作にあたって、「わたし」を消去することに心がけていたように思われることも、“物語性”“フィクション性”の強調と関係があるのかもしれません。
しかし、日本近代詩全体としては、7・5調などの音数律が放棄されたことによって、散文との区別があいまいになってきます。“詩は、行を分けて書いた散文と、いったいどう違うのか”という疑問が、私たちの頭をつねにとらえることになります。
「韻律からみれば、詩だと思って書いているから詩だ、とか、記述の呼吸にリズムがあるから詩だ、というところまで追いつめられた近代詩の概念に、まるで違う〈転換〉の仕方を導入して活路をひらいた試みが行われた。それは近代の日本語の詩が何であるかを端的に示すものでもあった。〔…〕
ふつう1行目のつぎにどんな2行目がくるか、そのつぎにどんな3行目がくるか、また第1節のつぎにどんな2節目がくるか、こういった〈転換〉の仕方は、詩の芸術性をもたらす重要な要素のひとつだといえる。それは詩の展開の密度と距離感を決定するからだ。このことは半分は無意識のうちに詩人の資質をきめている。〔…〕
はじめに自然でいちばん近い距離の〈転換〉の例をあげてみる。」
吉本隆明『詩学叙説』,p.16.
ここで吉本氏は、「いちばん近い距離の〈転換〉」の例として、宮沢賢治の文語詩「岩手公園」を掲載しています:
岩手公園
「かなた」と老いしタピングは、 杖をはるかにゆびさせど、
東はるかに散乱の、 さびしき銀は声もなし。
なみなす丘はぼうぼうと、 青きりんごの色に暮れ、
大学生のタピングは、 口笛軽く吹きにけり。
老いたるミセスタッピング、 「去年(こぞ)なが姉はこゝにして、
中学生の一組に、 花のことばを教へしか。」
弧光燈(アークライト)にめくるめき、 羽虫の群のあつまりつ、
川と銀行木のみどり、 まちはしづかにたそがるゝ。
宮沢賢治『文語詩稿一百篇』より
「盛岡のキリスト教会の牧師タピング一家が岩手公園に散策中、何ごとか語り合っている光景を唱っている、その様子を描いた文語詩と解される。〈転換〉は素直にはじめの1節は牧師タピングの様子を、2節目は息子の大学生タピングの姿を描写し、3節目に息子の姉について息子に語るタピング老婦人の様子を唱っている。自然な順序で一節ごとの〈転換〉を巧みに叙している例にあたる。もちろん第1行と第2行の、といった各行ごとのこまかい転換もある。」
吉本隆明『詩学叙説』,p.18.
)

もりおか 啄木・賢治 青春館
「各行ごとのこまかい転換」を見てゆくと、たしかに、1行目で父タッピングが杖で「はるか」を指し、2行目では、はるか東方の空のようすが描写されます。
3行目では、より近景の「丘」のようすが描かれ、4行目で、作者の視線は、かたわらの息子タッピングに移ります。
1行目の最初の老タッピングの言葉「かなた」は、詩の最初という位置からして、有意味な象徴であるはずです。ここには、“死後の世界を思え”(モメント・モリ)が含意されています。
しかし、老人の指す「かなた」は、余人には、「散乱の、/さびしき銀」「ぼうぼうと、/青きりんごの色に暮れ」る「丘」としか見えないのです。大学生の息子は、「口笛軽く吹きにけり」。―――『銀河鉄道の夜』の、ジョバンニとカムパネルラの“別れ”の場面を思い出させないでしょうか?‥『夜』では、意思疎通の障害を思わせる・さびしい「口笛」ですが、ここでの「口笛」は、おやじが何を言っているかい?というような若者の軽快な無関心を表していると思います。(神学を勉強しているとはいえ、アメリカの若者ですから‥)
つぎの第3節、通算5〜6行目で、作者の視線は老婦人に移り、彼女は、長女が中学生たちに、ここで「花のことば」を教えたと語ります。「花のことば」は、息子の目に映っている「青きりんごの色」の「丘」とともに、より近くにある“まことの幸せの世界”の存在を語っているかのようです。それを極端にまで観念すれば、『法華経』「如来壽量品」にある“心がけしだいで、この世界がそのまま浄土にも地獄にもなる”という思想に行きつくでしょう。「こゝにして」という一句に注目したいと思います。
そして、最後の第4節で、アーク灯の光に集まる羽虫の群れを描き、死者を次の生へと媒介するダルマ(業)の塵(⇒:ルバイヤートと宮沢賢治(6) ルバイヤートと宮沢賢治(7))を象徴します。
このように、この文語詩は、場面(視線)の流れとしても、思想の流れとしても、ひじょうに自然にスムースに〈転換〉してゆくように、よく計算されています。賢治の文語詩は、藤村の『若菜集』にも劣らない緻密な構成をもっていると言えます。
緻密な構成によって、この詩は、作者の死生観を、読者の前に総合的に提示しているのです。それは、『法華経』信仰を基本としながらも、キリスト教をふくんだ「はるか」「かなた」へ、遠い視線を向けています。

岩手公園 本丸跡から紫波山塊を望む。
岩手公園(盛岡城址公園)は、盛岡市にある南部藩居城の跡を公園にしたもので、天守閣などの建物は明治はじめに撤去されていますが、城郭(本丸、二の丸などの雛壇)はそのまま残されています。⇒:モリーオ(1) ⇒:>モリーオ(3)
この詩のもとになったのは、1918年6月、高等農林学校助手時代に書いた短歌群で、そこにはタッピング一家は、まったく登場していません。高等農林学校の助手として化学分析の仕事に忙殺されていた賢治が、ひとりでこの公園に来て風景を眺めているさまが描かれています:
公園の薄明
青みわび流るゝ雲の淵に立ちて六月に入る薄明のぶな
暮れざるに険しき雲の下に立ち白みいらだつアーク燈かな
黒みねを険しき雲の往くときはこゝろはやくもみねを越えつゝ
暮れそむるアーク燈の辺(べ)雲たるゝ黒山に向ひおかれしベンチ
黒みねを我がとびゆけば銀雲のひかりけはしく流れ寄るかな
『歌稿A』#652-656.
↑これを詩稿の形に改作したのが、↓つぎの草稿です。「起伏の丘はゆるやかに/青きりんごの色に暮れ」など、最終稿の「岩手公園」の表現も加えられていますが、タッピング一家は、まだまったく登場しません。
弧光燈(アークライト)に灯は下りて
しらしらしらと苛だてど
南はるかに散乱の
さびしき銀は声もなし
白堊いろなる物産館は
つゝましく黄にかゞやきてあり
起伏の丘はゆるやかに
青きりんごの色に暮れ
高洞山の焼け痕は
蓴菜にこそ似たりけり
小学校の窓ガラス
窓きれぎれに薄明の
黄ばらを浮べて夜に入り行く
「岩手公園」〔下書稿(一)〕
このあと3次にわたって書き直しが行なわれ、第3次稿には、いったん「了」の印が付けられたあと、第4次稿(定稿)ではじめてタッピング一家が書きこまれるのです。この定稿の用紙は、賢治が没年1933年に弟・清六氏に依頼して印刷所に発注した特製の詩稿用紙に書かれているので、タッピング一家が書きこまれた改訂は 1933年と見られます。
そうすると、宮沢賢治は、高農助手時代 1918年の短歌をもとに、第3次稿(《無罫詩稿用紙》に書かれていることなどから、1929年頃の成立と推定される)までの文語詩稿をまとめ、いったん文語詩として完成したと見なしていた。これを、「岩手公園」の前身となった作品として、「ウーア岩手公園」と仮称しましょう。「ウーア岩手公園」は、作者がひとりで岩手公園にたたずんでいるようすを描いており、助手時代の苦悩が詩のテーマだった。
しかし、没年の 1933年になって、なにかの理由で、高農学生時代 1915-17年のタッピング一家の思い出を文語詩にまとめたいと思い、その際に、1918年の短歌に基づく文語詩「ウーア岩手公園」を利用することにした。
文語詩「岩手公園」の成立過程は、このように推定することができます。

バプテスト内丸教会 左奥が幼稚園。
ヘンリー・タッピング(Henry Topping: 1857-1942)は、米国バプテスト派の宣教師で、1895年来日、1907年盛岡バプテスト教会(現在のバプテスト内丸教会)に赴任し、1919年まで同教会で活動した。宮沢賢治の盛岡中学・盛岡高等農林在学中は、ずっと、タッピングも盛岡にいたのである。そして、1907年〜1909年9月は、盛岡中学嘱託として英語を教えた。1909年4月に入学した賢治が、タッピングの授業を受けたかどうかは不明だが、遅くとも高等農林在学時には、内丸教会に通ってタッピング師の聖書購読を聴講している。1922年に再来日して横浜で伝道、1927年宣教師を引退した後は賀川豊彦の伝道・社会事業を支援し、日本で没した。
ヘンリーの妻ジェネヴィーヴ(Genevieve Faville: 1863-1942)は、夫没後も帰米を拒否、1953年日本で没。長女ヘレン(Helen Faville Topping: 1889-1981)も宣教師を務めた後、神戸YWCA初代総主事として活動、のち両親とともに賀川の活動を支援したほか、フィリピンで教育事業に従事した。長男ウィラード(Willard Faville Topping :1899-1959)も、宣教師として横浜、瀬戸内海で伝道に従事、また関東学院教員・理事を務めた。一家4名とも多磨霊園に墓地がある。
盛岡のタッピング一家については、女優の長岡輝子さんが、↓つぎのようなエピソードを伝えています:
「私が盛岡で幼稚園児だったころ盛岡に来られたミスター・ヘンリー・タッピング先生も、お若い時に不動産に手を出して騙され、大きな借財を抱えました。それを自力で全部返された後、自分の使命は聖職であると痛感し、シカゴ大学を出て、ニューヨークの神学校に新婚の夫人と共に学び、更に別な神学校在学中に娘ヘレンが誕生したのです。」
長岡輝子の母は、フレーベルの教育法を学んでおり、盛岡高等女学校教諭として来盛してから、高女の雨天体操場と校庭を週三日間使って私設の保育会をやっていた。
「しかし、校長が変わると同時に、そこを立ち退かされる事になってしまい、困り切っていました。そこにタッピング夫妻が盛岡に来られて母の話を聞かれるや、さっそくその保育会を引き受けて自宅を開放し、盛岡幼稚園として発足させる事になりました。これが今日も続いている内丸幼稚園で、明治42年3月に県に正式認可されたのです。
タッピング家の二人の子どものヘレンと、ウィラードの教育は、アメリカで受けていたので、ヘレンもウィラードも、休暇には盛岡の家に来ていたようでした。タッピング夫妻は、大正9年〔1920年。1919年とする資料もある。―――ギトン注〕に幼稚園を新しい園長に任せ、ご自分達は帰米して5年後〔他の資料によれば 1922年―――ギトン注〕に再び来日され、横浜に新しく家を建てられ、関東学院で教師をされたり、A・ライシャワー牧師(ライシャワー元駐日大使の父)の仕事を手伝われたりしていました。」
「すでに成人していた娘のヘレンも盛岡中学で英語を教え、中学から正規教員になってほしいと申し出があったと、父親のタッピングは手紙に書いている。」
↑この、ヘレンが盛岡中学で英語を教えていた(正式採用ではなかったようだが)というのが、いつごろのことなのか、よくわからないのですが、
ヘレンは、1909年に 20歳。1911年コロンビア大学を卒業し、宣教師となって再来日、1916年にミッションから引退し、神戸YWCAで働いたとあります(↑「タッピング家の人々」)。1919年には、父タッピングも内丸教会を辞めて、夫妻は一旦帰米。タッピング一家が盛岡にいたのは 1919年までです。したがって、ヘレンの盛岡中学来講は、1911年と 1916年の間ではないかと思われます。
宮沢賢治は、1914年に盛岡中学を卒業していますから、中学では、1年次の1学期に嘱託講師だった父タッピングよりも、3〜5年次に実際上教えに来ていたヘレン・タッピングに、英語を習った可能性が高いと思います。高等農林時代に内丸教会に通って父タッピングの聖書購読に出るようになったのも、ヘレンのつながりからではないでしょうか。
「長岡輝子は盛岡における自身の少女時代の思い出を語る際に、次のように記している。
『……父(長岡拡,当時は盛岡中学英語教諭)の英語教育法は独特で、英語の会話のためにタピングさんのお嬢さんのヘレンさんを招いて学生達と岩手公園に散歩に行き、その間絶対に日本語を使わせなかったという事を聞き、賢治の詩のあの一節の裏には私の父も関係していた事を父の死後何十年目かに知らされた事に不思議な感動を覚えました。』」
文語詩「岩手公園」には、
老いたるミセスタッピング、 「去年(こぞ)なが姉はこゝにして、
中学生の一組に、 花のことばを教へしか。」
という一節がありますが、ヘレンが、「中学生の一組に、/花のことばを教」えたというのは、盛岡中学の生徒たちを連れての↑上記の“校外授業”を想起して書いているように思われます。「花のことばを教」えたとは、花言葉などではなくて、公園の植物・景物を題材にして英語を教え、花木や草花の英語名なども教えた、という意味でしょう。
賢治は、みずから中学生としてヘレンの“校外授業”を受けたのか、それとも、他の生徒が受けていることを、学校や教会の誰かから聞いたのかはわかりませんが、ともかく高等農林時代までには、それを知っていたと考えられます。そして、20年ほどのちにタッピング一家の思い出を書こうとした際に、それを思い出して書きこんだのではないでしょうか。
つぎに、
大学生のタピングは、 口笛軽く吹きにけり。
ですが、長男ウィラードが大学生だった 20歳前後は 1919年前後になります。ウィラードはアメリカの大学にいましたが、夏休みには盛岡に戻っていたと、↑長岡輝子さんが書いています。1919年に、父タッピングは 62歳、タッピング夫人は 56歳。「老いしタピング」「老いたるミセスタッピング」とまで言える年齢かどうかわかりませんが、十数年後の賢治の“思い出”の中で、夫妻が「老いた」存在として思い出されたとしても不自然ではありません。
小林功芳「タッピング家の人々」(PDF)によれば、ヘレンは、1911年コロンビア大学を卒業し、宣教師となって再来日、1916年にミッションから引退し、神戸YWCAで働いたとあります。
したがって、賢治の詩のなかでタッピング夫人が「去年」と言っているのは、ヘレンが盛岡にいた 1911-16年、おそらく 1916年頃ということになります。
そうすると、この詩に登場する父タッピング、夫人、息子の3人での岩手公園散策が、賢治がじっさいに同行したとか、見かけたとかした体験だと仮定してみると、それは、1916年か 17年だったことになります。この時期、ちょうど賢治は、高等農林の学生として、内丸教会の聖書購読にも行っていた時期ですから(資料があるのは 1915年2学期:上田哲『宮沢賢治――その理想世界への道程』,p.262)、うまいぐあいに話は合うことになりますw
したがって、「岩手公園」のタッピング一家の部分は、宮沢賢治の実体験の回想で、それを 16〜17年後に思い出して、「ウーア岩手公園」の叙景枠組みに嵌めこんだ―――と推定してもよいかもしれません。
しかし、無理にそう決めつけなくてもよいと思います。
そのように完結した思い出場面でなくとも、1916-18年ころのタッピング一家に関する見聞や体験の思い出を、夫妻と息子の散策・会話という場面に構成して、「ウーア岩手公園」に嵌めこんだとしても、おかしくはないのです。
吉本氏が指摘したように、賢治の文語詩は、“物語”であり“フィクション”として構想され組み立てられたものなのですから、さまざまな見聞や体験の思い出を組み合わせて場面を構成することは自在なのです。
宮沢賢治は、1919年にタッピング一家が盛岡から離れた後は、彼らとの個人的な交際はなかったようです。しかし、タッピング一家は、内丸教会に隣接してタッピングが創立した「内丸幼稚園」とは、その後もつながりがあって、タッピング氏か、家族の誰かか、「内丸幼稚園」を訪問しに来ている記録があります(『新校本宮澤賢治全集』「年譜」,p.248 [1922年])
賢治も、「内丸幼稚園」の関係者とは、タッピングが盛岡を去った後まで交流があったようで、「年譜」によると、1922年12月に仙台へ行く列車の中で、「内丸幼稚園」を引き継いで園長になっていたミス・ギフォード(Miss Gifford)と偶然に出会って懇談しています。偶然に出会ったということは、この年(7月以前)に来日・来盛したミス・ギフォードと、あらかじめ面識があったことになります。賢治は、当時しばしば幼稚園を訪れていたのかもしれません。
「年譜」によれば、賢治は、翌 1923年5〜6月にも、ミス・ギフォードを訪問しています。研究者の推定によると、賢治とミス・ギフォードの間の話題は、来世・天上に関することであったようです(その会話を記したかと思われる、英語の対話を含む賢治詩稿があります)。
1922年12月〜1923年といえば、トシを失った(1922.11.死去)直後ですから、これはありうることだと思います。
トシの死後、賢治は、死生観の迷いから、キリスト教にも関心を向け、バプテスト関連のミス・ギフォードとも懇談した。そうしたキリスト教への関心が広がって行った時期に書かれたのが、『銀河鉄道の夜』の最初期稿で、最初期稿がキリスト教に関心の深い時期に書かれたために、この童話は、その後も最終形にいたるまで、キリスト教色の顕著な普遍宗教的童話として成長して行った―――
そういう仮説が成り立つのではないかと。。。 これはちょっとおもしろそうですね。
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]
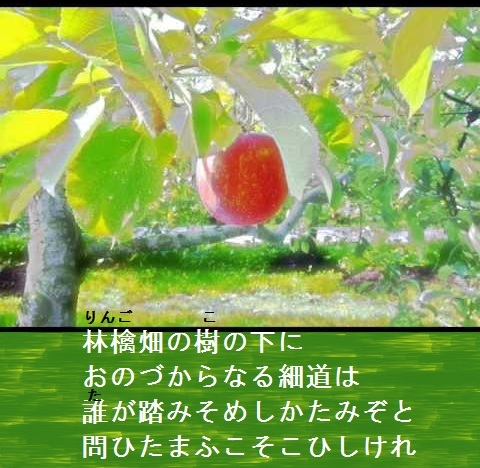
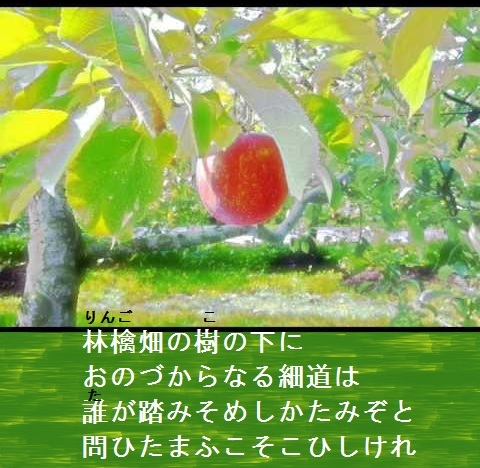



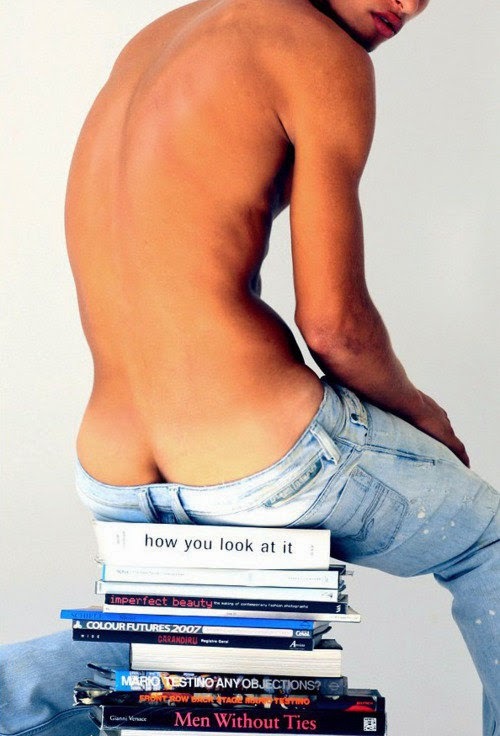
 彡
彡