07/14�̓��L
11�F56
�y���[���V�A�z�w�N�w�̕n���x�m�[�g(1)
---------------
.
 �@
�@
�M���X�^���E�N�[���x�u�v���[�h���Ǝq�������v�@�@
�@�����́B(º.-)���
�@�}���N�X���w�N�w�̕n���\�\�v���[�h�����́u�n���̓N�w�v�ւ̉x�́A�v���[�h���w�n���̓N�w�x(1846�j�ɑ���ᔻ�̏��Ƃ��� 1847�N�Ƀt�����X��Ō������ꂽ�B
�@�������A�����̐������O�Ƀ}���N�X�̓v���[�h���ɁA�w���`�ғ����x�\�\�w���Y��`�ғ����x�̑O�g�\�\�ւ̎Q����v�����Ēf���Ă���B�v���[�h���́A���̕ԐM�̂Ȃ��ŁA�u�^���̍őO���ɂ��邩��Ƃ����āA�V���ȕs���e�̎w���҂ɂȂ�̂͂�߂܂��傤�v�ƒ������Ă���B�܂��A�v���[�h���́u�A�� assotiation�v�Љ��`�\�z�́A��N�Ɏ���܂Ń}���N�X�ɐ[���e�����y�ڂ��������ƌ����Ă���B
�@���������A�}���N�X�́w�N�w�̕n���x�̑O�����i47�N6��15���t�j�ŁA
�u�v���[�h�����́A�s�K�Ȃ��ƂɁA��Ɍ������Ă���B�v
�@�Əq�ׂăv���[�h����i�삵�A���̒��́A�v���[�h���ɑ������ɍR�c���A�ނ���u�h�C�c�N�w��ᔻ���A����Ɠ����Ɍo�ϊw�̊T�v����邱�Ɓv��ړI�Ƃ��ď������ƒf���Ă���B�܂��{�����ŁA�v���[�h���ɂ͏�Ɍh�́u���b�V���[�v��t���Ă���B�u�O�����v�́A���̂悤�ɒ��߂�������F
�u�v���[�h�����̒�����k�c�l�ʏ�̏����ł͂Ȃ��B����͐����̂��Ƃ��e�N�X�g�ł���B�k�c�l�ǎ҂��������ƂƂ��Ɂw�n���L�x�̖��������œ�߂����w���ɂ������o������߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̌�ŁA�v���[�h�����ƂƂ��Ɂw��-�Љ��`�x�̗슴�ɂ݂�������֔��Ă���悢�̂��B�v
�@�}���N�X�́A�v���[�h���̎v�z�̂��镔���ɋ������āw�����x�ɗU�������A�f��ꂽ�̂ŁA�����̂��܂�ߒ��ւ̌���ᔻ�����������A���Ƃ��Ƌ������Ă��������ŁA�����ł͔ᔻ���Ȃ��璆�g�͔ᔻ�ɂȂ��Ă��Ȃ��悤�Ȃ��̂��ł��������Ă��܂����B����ƁA�t�����X�Ō��Ђ̍����v���[�h�����掂��Ė{������Ȃ��Ȃ��Ă�����Ǝv���A�u�ق�Ƃ͔ᔻ����Ȃ���ł���v�݂����ȃS���j�����������z�����\�\�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��낤���B
�@���������킯�ŁA�w�N�w�̕n���x�ɂ́A�}���N�X���v���[�h������u�A�\�V�A�V�I���v�\�z���p�����Ƃ������L�q������̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��āA�R�����Ă݂��̂����A�c�O�Ȃ��炻�̂悤�ȕ����͌�������Ȃ������B
�@���e�̑啔���́A�v���[�h���̃w�[�Q�������̌��ɑ���w�E�A����э����o�ϊw�ɑ��闝���̕s�\�����̎w�E�Ɛ����ɔ�₳��Ă���B
�@�ǂ�ł݂ėL�v�������̂́A�����̒��w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�ł͂͂�����\��Ă��Ȃ������u�B���j�ρv�̍\�z���A�}���N�X���悤�₭�ł߂��Ǝv����L�q���U������邱�Ƃ��B�u���Y���v�u���Y�l���v�Ƃ����������I�p�ꂪ����Ă���B�u�����v�ɂ��Ă��A�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�������m�Ș_���ň����Ă���B�������A������Ƃ����āA������ӓ|�ł�����_�ł��Ȃ����Ƃ��A�ǂ�ł݂�Ɖ���B
�@�}�����[�w�}���N�X�E�R���N�V�����U�x�̒ˌ��j�E�����m�i����g�p�����B�u��P�� ��̉Ȋw�I�����@��P�� ���p���l�ƌ������l�̑Η��v�u��Q�� �o�ϊw�̌`����w�@��P�� ���@�v�u��S�� ���L�Ȃ����n��v���珴�^����B��Q�͑�P�߂܂ł͒ˌ����A��S�߂͍������̖�ł���B
�@���Ȃ݂ɁA���݁A�l�b�g�⏑�X�̒[���Łw�N�w�̕n���x�̖�{����������ƁA�܂ƂE���^���̖��o�Ă��Ȃ��B���̖͕i��̂悤�����A�}�g�o��͂����߂��Ȃ��B�g����h�Ŗ������}���N�X�ƃv���[�h�����߂Â��悤�Ƃ��Ă���炵���A�u���p���l�v���u�g�p���l�v�ƖȂǂ̌��i�̈ӂ̌������ƌ����̂��H�j���ڗ��B���������A���̖{�͒��g�̂��ɍ�������B�ǎ҂�n���ɂ��Ȃ��ƋC�����܂Ȃ��̂��낤���H
�@���́u�m�[�g�v�́A��ɂ���āA����̓��e��v�邱�Ƃ��A���҂�̎v�z��`���邱�Ƃ��ړI�Ƃ��Ă��܂���B�����܂ł��A���l�̎v���̂��߂̏��^�ƁA�K�������e�N�X�g�ɂƂ���Ȃ��R�����g���c�����߂̂��̂ł��B
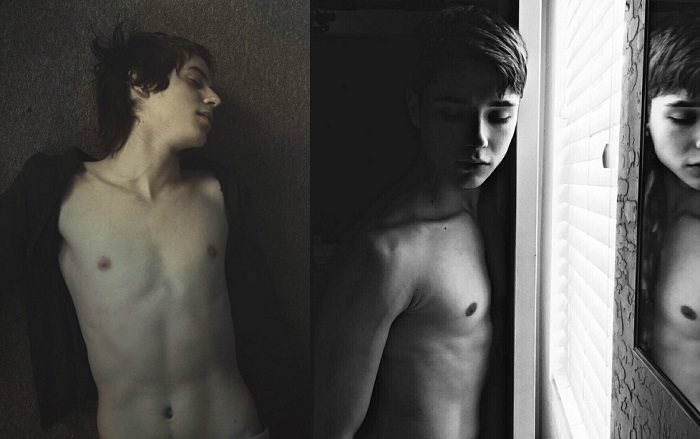
�@�y�P�z��P�͑�P�߁\�\�\�u���p���l���������l�̑Η��v
�u�w���R���ł���Y�Ƃ̎Y���ł���A���ׂĂ̐��Y���������Ă���l�Ԃ̐����ɖ𗧂\�͂́A�Ƃ�킯���p���l�ivaleur d'utilité�j�Ɩ��Â�����B����炪�������ɂ݂������^�������\�͂́A�����k��p�l���l�ivaleur en échange�j�ł���c�c�B���p���l�͂ǂ̂悤�ɂ����������l�ɂȂ�̂��c�c�B�k�c�l�����K�v�Ƃ��镨�̑啔���́A���R�ɂ͂������āA���邢�͂܂��������݂��Ȃ��̂�����A���͑���Ȃ����̂̐��Y�ɗ͂�݂��Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B���̍ہA���������ł͑����̂��ƂɎ���o���Ȃ��̂ŁA���͎����ȊO�̐l�Ԃ����i���l�ȐE����c�ގ��̋����҂����j�ɁA���̐��Y���ƌ����ɔނ�̐��Y���̈ꕔ�������ɏ��n����悤��Ă��邾�낤�B�x�i�v���[�h���k�w�n���̓N�w�x�B�ȉ������l�A��1����2�́j
�@�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�命���̐��Y���͎��R�ɂ͑��݂����A�Y�Ƃ̌��ʂƂ��Đ�����B���v�����R�̎����I���Y���Ă���Ƃ���A�l�Ԃ͎Y�Ƃɂ�鐶�Y�ɗ��炴������Ȃ����A�v���[�h���̐��ł́A�k�c�l�P�Ƃ̐l�Ԃ́A�����̂��̂��K�v�ɂȂ��Ă��w�����̂��ƂɎ���o���Ȃ��x�B�����̕K�v���~���ibesoin�j�����ɂ́A�����̂��̂Y���邱�Ƃ��O��ƂȂ�\�\���Y�Ȃ��ɐ��Y���͑��݂��Ȃ��̂��B�\�\�����̂��̂Y���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���łɒP�Ƃ̐l�Ԃ̎�ł����Y����ȏ�̏�ʂ�O��Ƃ��Ă���B�Ƃ���ŁA���Y�̂��߂ɁA�P�Ƃ̐l�Ԉȏ�̎��O���ЂƂ́A���̂Ƃ����łɎY�ƑS�̂�������y��Ƃ���Ƃ����O��ɗ����Ă���̂ł���B�������āA�v���[�h�����z�肷��悤�ɁA�K�v���~�����ꎩ�̂��S�ʓI��������O��Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ�B������O��Ƃ��邱�ƂŁA�����ƁA���̌��ʂƂ��Ă��������l�ivaleur d'échange�j��������B����������A���̂悤�Ȏ���炵���������l�̑��݂�O��Ƃ����ق����悢�ƍl������̂ł���B�v
�w�N�w�̕n���x,in�F�����m�i�E����w�}���N�X�E�R���N�V�����x,2008,�}�����[,pp.167-168.
�@�}���N�X�͂܂��A�v���[�h���̋c�_�͂ǂ�Ȃ��̂���������Ă���B
�@�u���v�����R�̎����I���Y���Ă���Ƃ���v�\�\�u���R�̐��Y�v�Ƃ����l�����́A�v���[�h���́u�����̂��Ƃ��v�_��I�\����������������Ȃ����A�}���N�X�Ƃ��ẮA�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�œW�J���������G��I��b�������Ă����B
�@�v���[�h���́A�l�́u���p�v����o�����āA�u�����v���K�{�ƂȂ铹���������Ƃ��Ă���B�������A�}���N�X�Ɍ��킹��A�v���[�h�����ŏ��ɍl���Ă���u�l�v�́u�~���v�́A�Y�Ƃ����B��������́u�~���v�ł���A���W�����u�����v��O��Ƃ�����̂Ȃ̂��B�܂�A�v���[�h���́A�u�����������v����u�����������v���Ƃ������X��������Ă���B
�@�������傭�A�v���[�h���̋c�_���ƁA�u�����v���u�����v���A�����ɑΉ�����悤�ȁu�~���v���A�l�ԂɂƂ��Ă͉i���̏������A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�����́A���j�I�ɔ������Ă����A�Ƃ������Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�@�d�v�Ȃ��Ƃ́A�u�~���v�͑��傷��A�Ȃ�����������Ƃ������Ƃ��B�͂��߂̏������~�������Y�Ɓu�����v�̔��B�𑣂��A�u�����v�ƌ�ʂ̌`�Ԃ���蕡�G�Ȃ��̂ɔ��W�����A�������đ��l�������Y���̋������A�u�~���v���g�傳����B�������āA���X����ł͂Ȃ��X�p�C�����Ȕ��W���͂��܂�B
�u�v�悤�B���ɂ������������ɂ��ƂÂ��K�v���~��������B�����̕K�v���~����O��Ƃ��āA�v���[�h�����������������l�����肵���k�c�l
�@�v���[�h���͘_�q�̏������t�ɂ����ق����悩�����͂����B�������Ă����A�ނ̌��_�͐��������̂ɂȂ������낤�B�������l��������邽�߂ɂ́A�܂��������̂��̂��K�v�ł���B������������邽�߂ɂ́A�������K�v�ɂȂ�B�����āA�����������炷�̂͏��X�̕K�v���~���ł����āA�����̕K�v���~����������邽�߂ɂ́A�K�v���~���̑��ݎ��̂��w�z��x����K�v������B�v
�w�N�w�̕n���x,in�F�����m�i�E����w�}���N�X�E�R���N�V�����x,2008,�}�����[,p.169.
�@�܂�A�u�~���v�́u�z��v�������̂Ȃ̂��B�u�����v�̂悤�Ɋ�Ɍ�������̂ł��A�����ɑ��݂�����̂ł��Ȃ��B�����āA�u�~���v���z�肳�ꂽ��A��������o�����āA��O�̎��ԁ\�\�u�����v�Ɓu�������l�v���̂��B
�@
�u�����͓Ǝ��̗��j�����ߒ��ł����āA���܂��܂Ȓi�K���o�߂��Č��݂ɂ������Ă���B���ẮA�����̂悤�ɁA�]�肷�Ȃ킿����ɂ������鐶�Y�̉ߏ蕪������������Ȃ����オ�������B
�@���邢�́A�]�肾���łȂ��A�S���Y���A�Y�Ƃɂ�邷�ׂĂ̐��ʂ���������Ɉڍs���A�Y�ƑS�̂������Ɉˑ����Ă���������������B�k�c�l
�@�Ō�ɖK�ꂽ����́A�l�Ԃ���������n���Ȃ����̂Ƃ݂Ȃ��Ă�����������̂������Ǝ���̑ΏۂƂ��k�c�l��i�K�ł���B�k�c�l�^�����͂������A�������Ĕ����Ȃ��������́A�l������͂������A�������Ĕ����Ȃ��������́\�\�����A����A���_�A�m���A�ǐS�Ȃǁ\�\�A�����������̂̂��ׂĂ����ɓI�ɏ�������Ɉڍs����i�K���B���ꂱ�������������鎞��A���K�W�����Չ�����鎞��ł���A�o�ϊw�̗p��Ō��Ȃ�A���_�I�Ȃ��̂ł��ꕨ���I�Ȃ��̂ł���A��������̂����K�I���l�ƂȂ��Ďs��ɂ������܂�A���̂����Ƃ������ȉ��i�ŕ]������鎞��ł���B�v
�w�N�w�̕n���x,in�F�����m�i�E����w�}���N�X�E�R���N�V�����x,2008,�}�����[,pp.170-171.
�@�������A�����Œ��ӂ������̂́A�u�����v�́g���W�h�́A�P���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�G���g���s�[�����傷��悤�ɕs�t�ɑ����Ă䂭�ω��ł͂Ȃ��̂��B
�@���Ƃ��A�k�C���A�C�k�́A���Ă͔��_���A�܂��͔����ŁA�قڎ��������������������Ă������A���}�g����̌��Ո��͂����܂�ɂ�A���l�������k�C���������ɐi�o���āA���p�̖є���Ƃ������ɓ��������B�є�ƌ����Ɏ�H�̕Ă���ɓ���Đ�������悤�ɂȂ����̂��B
�@���̂悤�ɁA���n��́u���W�o�H�v�����A�u���S�̎����v�̂悤�ȋ�ԓI�\���̂ق����d�v�ȋǖʂ�����B�u���W�i�K�v�Ƃ������t�͌���������B�u�i�K�v�����Ȃ�A�u�\���v�S�̂́u�i�K�v����ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���_�ɏ���߂��u�\���v�́A�]�`���邩���A�͈͂�ς��āA�܂��V���ȁu�\�����v���n�܂�B
�@�y�Q�z�u��Q�� �o�ϊw�̌`����w�@��P�� ���@�v�\�\�\�ُؖ@
�u�ꌬ�̉Ƃ�����I�ȕ�������������������Ă䂫�A���̉Ƃ��\������ޗ���A���̉Ƃ��ۗ������Ă���`�ۂ𒊏ۂ��Ă䂭�ƁA�k�c�l�₪�ċ�Ԃ����c��Ȃ��Ȃ�\�\�Ō�ɁA���̋�Ԃ̏������𒊏ۂ��Ă䂭�ƁA�����ɂ͌��ǂ܂����������ȗʂƂ����_���I�J�e�S���[�����c��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�k�c�l�������āA�������̂���A��������������A����������̂��Ȃ����̂��A�l�Ԃ��������A���ׂĒ��ۂ��Ă��܂��A�ŏI�I���ۂ̌��ʁA���̂Ƃ��Ďc��̂͘_���I�J�e�S���[�����ł���B�k�c�l
�@����������̂��ׂāA�n��Ɛ����ɐ�������̂��ׂẮA�Ȃ�炩�̉^���������Ă������݂��Ȃ����A�����Ă͂��Ȃ��B�������āA���j�̉^���͎Љ�W�ݏo���A�Y�Ƃ̉^���͎Y�Ɛ��i���X�������炷�̂ł���B
�@���ۂ̍�p�ɂ���āA����ꂪ�����鎖����_���I�J�e�S���[�ɕϊ������悤�ɁA���ۓI��Ԃ̉^���A�����Ɍ`���I�ȉ^���A�^���̏����ɘ_���I�Ȍ����ɓ��B���邽�߂ɂ́A���܂��܂ȉ^���̂��킾�������i�����ׂĒ��ۂ���������悢�B�_���I�J�e�S���[�̂Ȃ��ɉ^���̎��̂����o�����Ƃ���A�^���̘_���I�����̂Ȃ��ɂ����鎖����������邾���łȂ��A�����̉^���������܂ނ悤�ȁA��ΓI���@�����o�����Ƒz�����邱�ƂɂȂ�B
�@�@�@�@�@�@�k�c�l
�@����ł́A���̐�ΓI���@�Ƃ͉����B�^���̒��ۂł���B�k�c�l�^���̏����ɘ_���I�Ȍ������邢�͏��������̉^���ł���B���������̉^���Ƃ͉��̂��Ƃ��B���Ȃ��ʒu�Â��A�Βu���A�g�����邱�ƁA�藧�A���藧�A�����Ƃ��Č��������邱�ƁA���Ȃ��m�肵�A�ے肵�A���Ȃ̔ے��ے肷�邱�Ƃł���B
�@�k�c�l�������ЂƂ��ђ藧�����Ȃ�A���̒藧�A���̎v�z�͂��ꎩ�̂ɑΒu����A�m��Ɣے�A�E�C�ƃm���Ƃ�����̖��������v�z�ɕ���B������̓w���I�v�f�̓������A���藧�̂����Ɋ܂݂��܂�āA�ُؖ@�I�^�����\������B�k�c�l������̖�������v�z�̗Z���́A�����Ƃ����V���Ȏv�z���\������B���̐V���Ȏv�z�́A�܂����Ă���̖�������v�z�ɕ��A���x�́A�܂��ʂ̐V���ȑ������\�z�����B�k�c�l���̈�Q�̎v�z�́A�P���ȃJ�e�S���[�Ɠ����ُؖ@�I�^�������ǂ�A���藧�Ƃ��āA���������Q���Ƃ��Ȃ����ƂɂȂ�B������̎v�z�Q����A�����̑����ł���V�����v�z�Q�����܂��B
�@�P���ȃJ�e�S���[�ُؖ̕@�I�^������ЂƂ̌Q�����܂��悤�ɁA�Q�ُؖ̕@�I�^������n���܂�A�n��ُؖ̕@�I�^������̌n�S�̂����܂��v
�w�N�w�̕n���x,in�F�����m�i�E����w�}���N�X�E�R���N�V�����x,2008,�}�����[,pp.260-263.
�@���w�[�Q���ُؖ̕@��������Ă���B
�u�v���[�h���́A�^�̓N�w�҂Ƃ��Ă͂��̂��Ƃ��t�ɗ������Ă���̂ŁA�����̏��W���o�ϊw�I������J�e�S���[�̋�̉��Ƃ��Ă������悤�Ƃ��Ȃ��B�N�w�҃v���[�h�����A�܂����Ă������Ɍ������Ƃɂ��A�����̌�����J�e�S���[�́w�l�ނ̔�l�i�I�����x�̉���ɖ����Ă������̂Ȃ̂��B
�@�o�ϊw�҃v���[�h���́A�l�Ԃ��������Y�W�ɂ����ăE�[���┿�z�⌦�z�����邱�Ƃ��A���ɂ悭�������Ă����B�������A�ނ��������Ȃ��������ƁA����͂����������̎Љ�W���܂����z��l�����X�̂悤�ɁA�l�Ԃɂ���Ă�����Ƃ������Ƃ��B
�@�Љ�W�����Y���Ɩ��ڂɌ��т��Ă���B�V�������Y�����l�����邱�ƂŁA�l�Ԃ����Y�l����ω�������B���Y�l����������̓���@��ς��邱�ƂŁA�l�Ԃ͂�����Љ�W��ω�������̂ł���B��łЂ��P�͕����̎�̂���Љ�������炵�A���C�̉P�͎Y�Ǝ��{�Ƃ̂���Љ�������炷���낤�B
�@�����I���Y���ɉ����ĎЉ�W���m������A�����l�Ԃ��A�ނ�̎Љ�W�ɉ����āA������ϔO��J�e�S���[�Y����̂ł���B�k�c�l
�@���Y���ɂ͑�����߂����A���Y�W�ɂ͔j����߂����A�ϔO�ɂ͌`�����߂����A�����I�ȉ^�������݂��Ă���B�v
�w�N�w�̕n���x,in�F�����m�i�E����w�}���N�X�E�R���N�V�����x,2008,�}�����[,pp.264-265.
�@���Y�W�́u�l�Ԃɂ���Ă�����v�u�l�Ԃ����Y�l����ω�������v�\�\�ƌ����Ȃ���A������ł́A�u��łЂ��P�͕����̎�̂���Љ�������炵�A���C�̉P�͎Y�Ǝ��{�Ƃ̂���Љ�������炷���낤�v�ƌ����B�s���Y�������`�t���߂������炢�����邪�A�Ƃ������A�u���Y���v�̔��W�������u���Y�W�v�Ɩ������A�u���Y�l���v��ς��Ă䂭�Ƃ����u�B���j�ρv�̘_���́A�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�e�������m�ɏq�ׂ��Ă���B
�@�y�R�z�u��Q�͑�P�� ���@�v�\�\�\�z�ꐧ�A�������ƃu���W�����W�[
�u�����Ŗ��Ƃ����̂͒��ړI�z�ꐧ�A�X���i����u���W����k�A�����J�암���B�̍��l�z�ꐧ�̂��Ƃ����ł���B
�@���ړI�z�ꐧ�́A�@�B��M�p�ȂǂƂƂ��ɁA�u���W�����Y�Ƃ̐����ł���B�z�ꐧ���Ȃ���A�ȉԂ͎�ɓ���Ȃ��B�ȉԂ��Ȃ���A�ߑ�Y�Ƃ͐��藧���Ȃ��B�A���n�ɉ��l�������炵���͓̂z�ꐧ�ł���A���E�I�������n�������̂͐A���n�ł����k�c�l
�@�z�ꐧ���Ȃ���A�����Ƃ��i���I�ȍ��ł���k�A�����J�́A�����I�ȍ��ɕϖe���邾�낤�B�k�A�����J�𐢊E�n�}���疕������B��������A�ߑ㏤����Ƌߑ㕶���́A�����{��ԂƊ��S�ȑޔp�Ɋׂ邾�낤�B�k�c�l
�@�z�ꐧ�́A���ꂪ�ЂƂ̌o�ϓI�J�e�S���[�ł���ȏ�A�˂ɏ������̐��x�̂����ɑ��݂��Ă����B�ߑ�̏������́A�������ł����z�ꐧ�x���B�����Ƃ��ł��Ȃ������B�V���E�ł́A�ނ�͕ϑ��Ȃ��ɓz�ꐧ�����������B�v
�w�N�w�̕n���x,in�F�����m�i�E����w�}���N�X�E�R���N�V�����x,2008,�}�����[,p.267.
�@�z�ꐧ�́A�ߑ㎑�{��`�́u�����ł���v�B�\�\�܂Ƃ��Ɏ咣���Ă���̂ł���A�g�z�ꐧ�A���������玑�{��`�ւ̌p�N�I���W�h�ȂǂƂ����}���͐��藧���Ȃ��Ȃ�B�\���I�ϓ_�ŎƂ߂�A�g�}���h�Ƃ͖������Ȃ���������Ȃ��B�������A�ނ���A�u�p�N�I���W�̖@���v�Ȃǂ͑��݂��Ȃ��Ƃ����ׂ����B
�@�}���N�X�������Ō����Ă���̂́A�z�ꐧ�Ȃ����ċߑ㎑�{��`�͐������Ȃ������A�z�ꐧ�͋ߑ㎑�{��`�̕K�{�̍\���v�f���\�\�Ƃ������ƂȂ̂��B
�@�ߑ㎑�{��`�̐����ɓz�ꐧ�̑��݂���^�����̂́g���R���h�ƌ����Ȃ�A�g�z�ꐧ�A���������玑�{��`�ւ̌p�N�I���W�h�\�\���ꂪ�j���������Ƃ��ā\�\���g���R�h�łȂ��ĉ��Ȃ̂��H ������u���R�v�Ə̂��A�������u�K�R�v�Ə̂��鍪���́A���ӈȊO�ɂ͂Ȃ��B
 �@
�@
�u�o�ϊw�҂����͊�Ș_�̐i�ߕ�������B�ނ�ɂƂ��ẮA�l�ׂ̐��x�Ǝ��R�̐��x�Ƃ̓�̐��x�������݂��Ȃ��B�������x�͐l�דI�Ȑ��x�ł���A�u���W�����W�[�̐��x�͎��R�I�Ȑ��x�ł���B�k�c�l���݂̊W�\�\�܂�A�u���W�����I���Y�W�\�\�����R�I�ł���ƌ������Ƃɂ���āA�o�ϊw�҂����́A�x���n������A���Y�������W���邱�̊W�����R�̖@���ɏ]���Ă���̂��ƌ��������̂ł���B������A���̊W���̂����Ԃ̉e������Ɨ��������R�̖@�����Ƃ������ƂɂȂ�B����́A�Љ���˂ɊǗ�����͂��̉i���̖@���ł���B�k�c�l
�@�k�v���[�h���ɂ��l�����I���Y���A��̑Η�����v�f�������Ă����B��������͂�A�������̗��h�Ȗ��k�u�R�m���v�u�ƒ��I���������v�u�_���Ɠ��H�Ɓv�u���E�g���E�e�����x�v�ɂ��Y�Ɣ��W�l�ƈ������k�u�_�z���A�������A�����{��ԁv�l�Ɩ��Â����邪�A���̂����A�ŏI�I�ɂ́A�����ʂ��˂ɗ��h�Ȗʂɏ����������Ƃ��l������Ă͂��Ȃ��B�������\�����āA���j������^���ݏo���̂́A�����ʂ̂ق��Ȃ̂ł���B�k�c�l
�@���Y�l���A���Y���������̂Ȃ��Ŕ��W����W�͉i���̖@���ǂ���ł͂Ȃ��B�����͐l�ԂƂ������Y�����̈��̔��W�ɑΉ����Ă���̂ł���A�l�Ԃ����Y�����ɐ�����ω����A���Y�W�̕ω���K�R�I�ɂ����炷�̂��ƌ����Ă��A���������ł͂Ȃ����낤�B�����̉ʎ���l�����ꂽ���Y����D���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��A�������d�v�ł���ȏ�A���������Y�������ݏo���ꂽ�`���I�Ȍ`�Ԃ�j�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v
�w�N�w�̕n���x,in�F�����m�i�E����w�}���N�X�E�R���N�V�����x,2008,�}�����[,pp.278-279.
�@�u�l�Ԃ����Y�����ɐ�����ω����A���Y�W�̕ω���K�R�I�ɂ����炷�̂��ƌ����Ă��A���������ł͂Ȃ����낤�B�v�\�\�\�\�u�K�R�I�ɂ����炷�B�v�Ƃ����f��I�Ȍ����������Ă��Ȃ��B�}���N�X�́A�����܂ł��A�����̊ώ@���璊�ۂ�����ʓI�ȌX���Ƃ��ďq�ׂĂ���̂��B����_�I�@�����l�Ԃ��x�z���Ă���Ƃ��A�Љ�S�̂��x�z���Ă���Ƃ��A�ނ͏q�ׂĂ��Ȃ��I�I
�@�u���̏ꍇ�ɂ́A�K�R�I�ɂ����Ȃ����Ǝv���Ă��������炢�ł���B����قǁA���̓�̗v�f�̌��т��͖��ڂł������悤�Ɍ�����B�v�\�\�����́A�}���N�X�̎������A���̂悤�Ɏ��ׂ����B�������A�Љ�̎����I�ω��ɉe����^������q�i�������j�͑�������B���̂����́u��v�����o���Ċώ@�����ɂ����Ȃ��̂��B�����āA���́E����̒n��́E����̎�����Ԃɂ����ẮA����u��v�̈��q�̂������ɁA���̈��q�̉e���ɏ��閧�ڂȂȂ��肪������A�Ƃ������ƂȂ̂��B
�u�u���W�����W�[�́A���ꎩ�g����������̃v�����^���A�[�g�̎c��ł���v�����^���A�[�g�ƂƂ��Ɏn�܂�B���j�I���W�̉ߒ��ŁA�k�c�l�u���W�����W�[�����W����ɂ�āA���̓����ɐV���ȃv�����^���A�[�g�A�ߑ�v�����^���A�[�g�����W���A�v�����^���A�K���ƃu���W�����K���Ƃ̓������W�J�����B�k�c�l�x�����Y����铯���W�̂Ȃ��ŕn�������ݏo����邱�ƁA���Y�������W���铯���W�̂Ȃ��ɗ}������͂����݂��邱���A�����̊W�́A���̊K�����\�����郁���o�[�̕x���������������ăv�����^���A���˂ɑ��������邱�Ƃ�ʂ��Ă����u���W�����I�x�i�܂�u���W�����K���̕x�j�Y�����Ȃ����Ƃ��A�܂����炩�ɂȂ�̂ł���B�v
�w�N�w�̕n���x,in�F�����m�i�E����w�}���N�X�E�R���N�V�����x,2008,�}�����[,p.280.
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@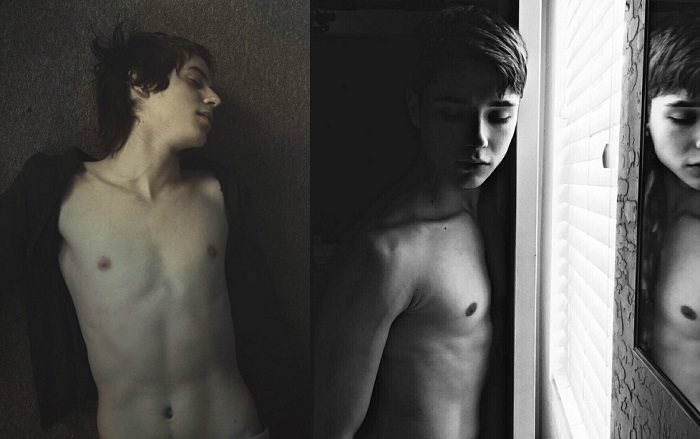

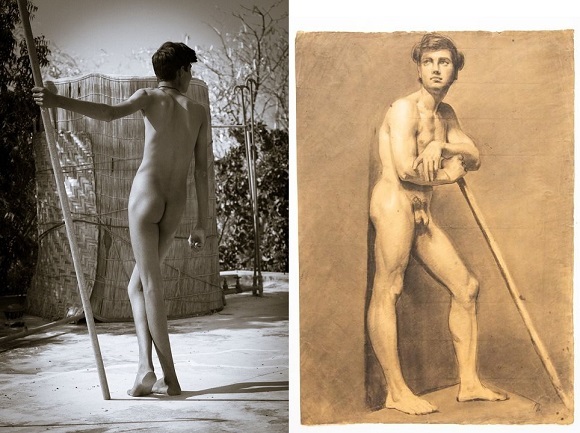
 �@
�@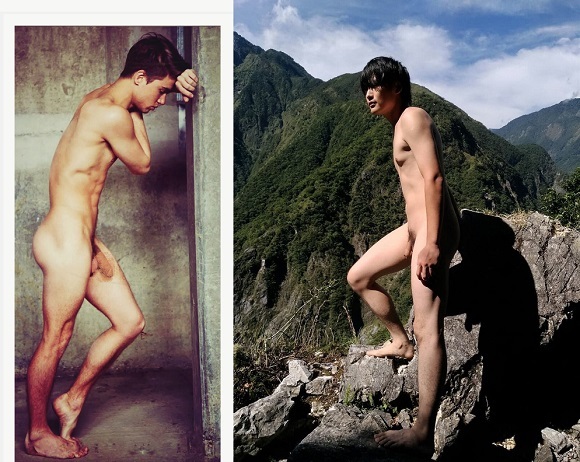
 �c
�c