09/04の日記
08:32
【ユーラシア】『ドイツ・イデオロギー』ノート(14)
---------------
.
こんばんは。(º.-)☆ノ
【ユーラシア】『ドイツ・イデオロギー』ノート(13)からのつづきです。
⇒:このシリーズの初回 【ユーラシア】『ドイツ・イデオロギー』ノート(1)へ。
マルクス/エンゲルスの共著『ドイツ・イデオロギー』は、編集中途の草稿の状態で遺された未完成の著作です。内容的に未完成で、さまざまに矛盾する主張を含んでいますが、それこそがこの作品の魅力でもあります。また、内容だけでなく、形式面でも大きな混沌をはらんだテクストであるため、字句はもちろん篇別構成・断片の順序に至るまで、編集者の介入を必要としており、版本によって相異があります。ここでは、廣松渉・編訳,小林昌人・補訳『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,2002,岩波文庫. をテクストとして使用します。
上記岩波文庫版からの引用中、青字はマルクスの筆跡、それ以外(白字)はエンゲルスの筆跡。草稿の抹消箇所は下線付きで、追記・挿入は斜体で示します。
「エンゲルスの筆跡エンゲマルクスの筆跡ルスの筆跡」
「人間を動物から区別するのは、生産するみたいな感じでことによってである。」
「人間が自らを動物から区別するのは、道具を用いて生産することによってである。」
この「ノート」は、著作の内容を要約することも、著者らの思想を伝えることも目的としていません。あくまでも、私個人の思索のための抄録と、必ずしもテクストにとらわれないコメントを残すためのものです。
【36】「本論三2」――マルクスの構想メモ
「フォイエルバッハ」篇,「大きい束」の末尾には、マルクスの筆跡で、この篇の?構想メモが記されている。書込みのための右余白ではなく、本文の欄に記されているので、全面的な改稿をめざして計画を記したもののように思われる。
最近の研究によると(大村泉・編著『唯物史観と新MEGA版「ドイツ・イデオロギー」』,2018,社会評論社,pp.34-36 [Alex Demirović 執筆].)、『ドイツ・イデオロギー』の名のもとに集められている草稿群は、当初は、モーゼス・ヘスらとの季刊誌の発行計画にからんで、そこに掲載する原稿として、1845年に書きはじめられた。しかし、この季刊誌発行は頓挫し、途中まで書かれた(「第1篇 フォイエルバッハ」以外の諸篇は完成していた)マルクス、エンゲルス、ヘスの草稿を2巻本として出版する計画が立てられた。その計画も難しくなったため、ヘス執筆部分はヘスに返却。ヘスはそれを他の雑誌に寄稿して発表している。その後、マルクス/エンゲルスは自分たちの原稿だけで1巻本を出す計画を立て、1846年6月に「第1篇」の執筆を再開した。しかし、それも遅くとも 1847年12月までに頓挫している。
つまり、①季刊誌⇒2巻本、②1巻本、という2回の刊行計画があり、その度に執筆が行なわれた。↓以下で検討する「大きい束」末尾のマルクス・メモは、①のために中途まで書かれた草稿(「大きい束」)の末尾に、②のための改稿・執筆の方針を記したものであろう。
しかし、このメモに従って始められた②の新原稿の執筆作業は、ほとんど書かれないうちに中断したと思われる。「小さい束」のうち <{1?}>-<{2?}>-<{5}> は、もしかすると(それが、「大きい束」より新しい草稿だとすると)、②新原稿の冒頭部であったかもしれない。以下で見るように、<{1?}>-<{2?}>-<{5}> の内容は、メモの一部の項目に対応している。
「分業の学問への影響。
国家、法、道徳などの場合に抑圧、ところのものは。★
ブルジョアたちは階級として支配する以上、法律のなかで自分たちに普遍的な表現を与えなければならない、なければならない。★
自然科学と歴史。
政治、法、学問等芸術、宗教等の歴史は存在しない。
古代国家、封建制度、絶対王政において現れるような『共同体』に、すなわちこの紐帯に対して、カト〔リック教が〕宗教的諸表象が照応する。◆
――――――☆」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,pp.208-210.
★:いずれも、文として未完成または文法的に混乱。
◆:この行は欄外書込み。
☆:この引用全体は、河出版の原文を参照して改訳。
「自然科学と歴史。/政治、法、学問等芸術、宗教等の歴史は存在しない。」――<{1?}>-<{2?}>-<{5}> に書かれている内容と対応している。自然史を含む《人間と自然の物質代謝》の歴史としての“史観”構想。および、「存在は意識に先立つ」
「なぜイデオローグたちはすべてを逆立ちさせるのか。
修道士、法律家、政治家。
法律家、政治家(要職にある者一般)、道徳家、修道士。
一階級内部の・これらイデオロギー的下位区分については、1.分業による職業の自立化;2.各人が自分の手仕事を真なるものとみなす。2.そのうえ、こいつらは自分の手仕事が現実に対してもつ関係について、彼らは幻想を抱くが、これはもう手仕事じたいの本性によって条件づけられていることなので、それだけ当然に幻想を抱くこととなるのである。諸関係は、現実法律学、政治学等のなかで〔諸概念〕と意識の中で諸概念となる;彼らはこれら諸関係を超え出てはいないので、彼らの頭の中にあるこれら諸関係の諸概念も、固定した諸概念である。たとえば、裁判官は法典を適用するのだから、彼は、立法を真の規定能働的運転者 der wahre aktive Treiber と見なしている。自分らの商品に対する尊敬;なぜなら、彼らの職業は普遍的なものに関わっているのだから。
法の理念。国家の理念。日常の意識では、事態は逆立ちさせられている。
――――――
宗教は最初から超越の意識であって、現実の諸力から生ずる。これをもっと通俗的に。━ ━ ━
――――――
法、宗教などにとっての伝統。☆」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,pp.208-210.
☆:この引用全体は、河出版の原文を参照して改訳。
「法、宗教などにとっての伝統。」――冒頭で↑「政治、法、学問等芸術、宗教等の(独自の)歴史は存在しない」と断言しながら、このボーゲンの末尾では、それらの独自の「伝統」を問題にしている。『ドイツ・イデオロギー』全体に、“土台が上部構造を決定する”とのテーゼが強く打ち出されているが、このように、それと逆方向に反省する思考もある。
現存の「第1篇 フォイエルバッハ」草稿には、宗教に関する叙述があまり見られないが、この構想メモを見ると、宗教に関してもっと書き込む改稿を予定していたようだ。
「Ⅰ
フォイエルバッハ
唯物論的見方と観念論的見方の対立
諸個人は常に自分たちから出発してきたし、出発する。彼らの諸関係のもとで彼らがは、彼らの現実的生活過程の諸関係であるのは、どのようにしてそうなるのか。彼らの諸関係が彼らに対抗して自立化する事態は、どこから生じてくるのか? 彼ら自身の生の威力が諸威力として彼らを凌駕してしまう事態は?
一語で言えば:分業、自然発生的な。発達した・その時々の生産力に依存する〔各〕段階の分業〔によって生ずるのである〕。
土地所有。共同体的所有、封建的な。近代的な。
身分的所有。マニュファクチュア所有。産業資本。★」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,pp.211-212.
★:この引用全体は、河出版の原文を参照して改訳。
ここで、「大きい束」の手稿が終っている。
「彼らの諸関係が彼らに対抗して自立化する事態は、どこから生じてくるのか? 彼ら自身の生の威力が彼らを凌駕してしまう事態は?」――――これが、マルクス/エンゲルスが“分業史”を叙述した問題意識であった。すなわち、「物象化」(⇒所有形態,国家形態)の歴史的変遷(深化)過程の解明である。
以上で、岩波文庫版『ドイツ・イデオロギー』の検討は終ったが、このあと、訳書を変えて、「第3篇 聖マックス」の一部を見たい。そこにも、歴史叙述が多少あるらしい。

【37】断章――「第3篇 聖マックス」から
フランスのブルジョワジーが革命を通じて支配層へと躍進して、ヨーロッパを征服し、イギリスのブルジョワジーが産業革命を遂行しつつ、インドを植民地化し、全世界を貿易によって服属させたあいだに、ドイツの市民は、カント哲学の他には何も生み出さなかった。英仏の諸思想が、彼らの現実を透明に反映し、また歴史的現実に対して実践的な意味を持っていたのに対して、ドイツの思想は現実離れした観念論であり、現実の反映を、普遍的な観念にしか作り上げなかった。
「前世紀の終わりのドイツの状況は、カントの『実践理性批判』に丸ごと反映している。〔…〕カントは、たんなる『善意志』で――それによってどんな帰結も伴わない場合でも――安心してしまい、この善意志の実現、つまり、この善意志と個人の欲求や衝動のあいだの調和である実現を、彼岸へと押しやってしまった。〔…〕
ドイツ市民たちのけちくさい関心では、彼らがひとつの階級として共同の、そして国民としての関心にまでまとまる能力をもつことはけっしてなかった。それゆえ、彼らは他の諸国民のブルジョワたちにたえず搾取され続けてきたのである。〔…〕
亜麻布マニュファクチュア、つまり紡車と手動織機に頼る産業がドイツである程度の重要度を帯びるようになったちょうどその頃、もうイギリスでは、こうした頼りない産業が機械によって追い払われてしまった。〔…〕オランダはハンザ同盟〔…〕から脱け出し、二つの港(ハンブルクとブレーメン)を除いてドイツを世界貿易から切り離し、それ以来ドイツにおける交易のすべてを支配することになったのである。〔…〕小さなオランダのブルジョワジーたちは、彼らの階級的利害が発展していた〔一国のブルジョワ階級としてまとまっていた〕ので、〔…〕さまざまに四分五裂した利害けちな利害だけだったドイツ市民たちよりも強力だった。〔ドイツは、ブルジョワジーの〕利害が四分五裂だったのに応じて、政治組織も、小さな諸侯や帝国自由都市に分かれ、同じく四分五裂状態だった。政治的集中のための経済的条件がいっさい存在しないというのに、どうして集中が可能だろうか。どの生活領域も〔まとまった「身分」も「階級」も成立しようがないから、こう言うほかはない〕無力である以上、〔…〕そのどれひとつとして排他的支配力を得ることはかなわなかった。
その必然的帰結は、ここドイツではきわめて跛行的な、半ば家父長的な形態をとった絶対君主制の時代に、公的利害の行政管理を分業上担当すべき特定の領野〔行政の分野〕が異常に自立化し、さらには近代官僚制のなかでこの自立化がさらに激しくなったことにある。その結果、国家が、見かけ上は自立した権力となった。〔…〕
現実の階級利害に依拠したフランス・リベラリズム」に対して、その「ドイツ版」はパロディでしかなかったが、その代表者はカントだ。「カントはドイツ市民層の言葉巧みな代弁者であるが、〔…〕フランスのブルジョワたちにおいては物質的動機を有していた意志の諸規定を、『自由意志』の純粋な自己規定へと変えてしまい、〔…〕こうして意志を、純粋にイデオロギー的な概念規定および道徳的要請なるものに変容させてしまったのである。フランスの過激なブルジョワ・リベラリズムが、恐怖政治や、また露骨なブルジョワ的営利の形をとるやいなや、ドイツの小市民たちはたちまち恐れをなしてしまったのも、そのせいであった。
〔…〕
七月革命とともに〔…〕十分に出来上がったブルジョワジーに相応した政治形態が外部からドイツ人に押しつけられることになった。ところが、ドイツの経済的状況は、こうした政治形態に対応するような発展段階にはとうてい達していなかった。それゆえ、市民たちはこの政治形態をただ抽象的な理念として受容しただけなのである。〔…〕それゆえドイツ市民たちはこの新しい政治形態に対して、他の諸国民よりもずっと倫理的に、そして利害にこだわらない〔理想主義的な〕態度で対応した〔…〕結局は何の成果もあげることはなかったのである。
だがついには、外国との競争がますます激しくなり、世界貿易からも離れていることがしだいに不可能になって、〔…〕四分五裂していたドイツがある種の共通性をもった存在へとまとまってきた。ドイツの市民たちは、とくに 1840年以降、こうした共通の利害を守ることを考えはじめた。彼らはナショナルかつリベラルな思考を始め、保護関税と憲法を要求しだした。彼らはどうやら 1789年のフランス・ブルジョワジーの段階にほぼ達したのである。〔これはドイツ西部の状況――ギトン註〕
ところが〔ドイツ東部の〕ベルリンのイデオローグたちは、〔…〕リベラリズムを、その〔英仏での――ギトン註〕発生の理由である現実の利害、それによってこそリベラリズムが本当に存在しうる利害との関係で見ることをしない。〔…〕リベラリズムの内容を、なんと簡単に、哲学に、純粋の概念規定なるものに、『理性認識』なるものに変えてしまっていることか! 〔…これでは〕聖人たちの国にふさわしい結論にしか到達しないのも当然であろう。」
『ドイツ・イデオロギー』,in:フランソワ・フュレ・編著,今村仁司・他訳『マルクスとフランス革命』,2008,法政大学出版局,pp.228-233.
「国家が、見かけ上は自立した権力となった」――国家の自立化は、フュレによれば、ドイツに限ったことではなかった。単に「見かけ」でもなく、絶対主義から市民革命後にまで一貫した中央集権的行政国家の発展過程であった。
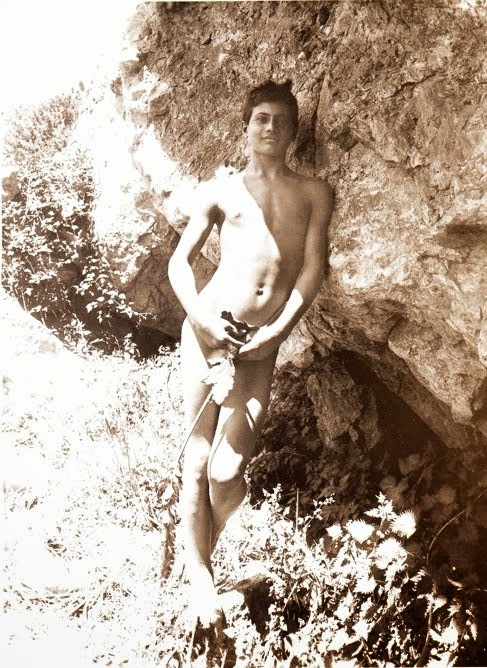
「フランソワ・フュレ(François Furet、1927 - 1997)はフランスの歴史学者。政治思想史、フランス革命史およびフランス革命の研究史(史学史)を専門とし、恐怖政治を『革命からの逸脱』として論争を巻き起こした研究書『革命』、革命の『脱神話化』を目指す著書『フランス革命を考える』、革命を『現象』として捉えた『フランス革命事典』などを著した。1989年の東欧革命以降は、共産主義の『幻想』の歴史を読み解き、共産主義とファシズムを20世紀における2つの全体主義として、両者の闘争の軌跡を描いた『幻想の過去 - 20世紀の全体主義』を発表した。
第二次大戦中、フュレは対独レジスタンスに参加した。1949年に共産党に入党し、同時に、第二次大戦中に共産党主導の対独レジスタンスに参加した共産主義者、キリスト教徒、自由思想家らによって1948年に結成された『平和運動』に参加した。彼は1956年のハンガリー動乱に対するソ連軍の介入を機に共産党を離れた。サルトルら『レ・タン・モデルヌ』誌の知識人が結成した『左派クラブ』と接触を持ったことで、共産党の監視委員会に出頭を命じられた。1982年には、非共産主義の立場から左派の思想的基盤を作り直すと同時に、自由主義の観点から時事問題に取り組むための大学教員、政治家、財界人の話し合いの場として歴史学者・社会学者のピエール・ロザンヴァロンとともに『サン=シモン財団』を創設し、会長を務めた。
歴史学者としてのフュレは、アナール学派として出発したが、1980年代に入って『アナール学派の外で』フランス革命について研究を始めた。これは、アナール学派的な多様性が他方において歴史の細分化につながり、『歴史がパン屑のように散らばってしまった』と考えたからである。
フュレは後にソルジェニーツィンに言及し、ジャコバンはボリシェヴィキを想起させる、強制収容所グラグは恐怖政治を想起させる、同じ目的で作られた機構だからだと批判に応えている。『フランス革命を考える』はフランス革命の記述ではなく、フランス革命が歴史学者によってどのように記述されてきたかをたどる、フランス革命の研究史(史学史)であり、過去の歴史学者によって「歪められた」革命像を批判的に検証し、トクヴィルとオーギュスタン・コシャンの研究に基づいて革命の『脱神話化』を目指すものである。
1995年に『幻想の過去 - 20世紀の全体主義』を発表した。『フランス革命を考える』においてフランス革命の神話化を指摘したのと同様に、20世紀の共産主義についても『非常に強いカセクシス(備給、心的エネルギーが特定の対象に向かい、そこに貯留されること])』が働いていたとし、これをソ連の歴史や共産主義の歴史ではなく、宗教的な幻想と同様の『共産主義の幻想の歴史』として読み解き、共産主義とファシズムを20世紀における2つの全体主義として、両者の闘争の軌跡を描いている。」(Wiki)
編者フランソワ・フュレによる・上記引用部の解説↓。
「マルクスが強調しているのは、およそ革命的な階級が〔…〕優位に立ってきた階級の転覆をはかるには、革命的な観念を養うと同時にそれらに普遍主義的な形式や野心を与える必要があるということ、しかも、社会全体の代弁者としてふるまい、いっそう広範な支持基盤の上に自己の支配を打ち立てるしかたでそうしなければならないということである。〔…〕ドイツのブルジョワジーと同様に、フランスのブルジョワジーも人間一般の名において語る。フランスのブルジョワジーは、みずからの利害を偽るとともに、みずからが社会に打ち立てたいと思っている新たな支配を、普遍性に訴えることによって偽装している。
ただし両者の違いは、フランスのブルジョワジーが語る言葉のなかには社会のラディカルな変革をめざす革命の企図が実際に含まれていたのに対し、ドイツのブルジョワジーはばらばらで優柔不断で未熟なために国民という観点からものを考えることができず、極端なまでに普遍主義的な抽象によってみずからの欺瞞的性格を強化してしまった点にある。
マルクスはこうして、一方ではイギリス経済に対する、他方ではフランス革命に対するドイツの立ち遅れという強迫観念を理論化する、新たな思考図式を見出した。いつもながら極端なやり方で、〔…〕マルクスは、ドイツの一切の哲学的遺産とりわけカント主義を棄却する。これ以降、カント主義は、ドイツのブルジョワジーの無能さを哲学的に隠蔽するものと見なされることとなる。
〔…〕こうした単純化のせいで、マルクスは、」これらドイツのイデオローグの諸々の欠陥を「自分の思考だけは免れているという幻想を抱くようになる。それは、彼の理論のおそらく核心にある哲学的一貫性欠如のはじまりであった。」
フランソワ・フュレ編著,今村仁司・他訳『マルクスとフランス革命』,2008,法政大学出版局,pp.52-54. MEW Ⅲ SS.176-180.
フュレによれば、マルクスは、階級利害に着目することによって、18世紀フランスの社会的現実の中に、自由主義が理論体系化され、ついで実行に移される「歴史的必然性」を示すような「明確な図式が存在することを発見する。」しかし、その「発見」は、マルクスが自ら 18世紀の諸思想を研究して確信したわけではなく、ギゾーの歴史著述から剽窃したにすぎない。ギゾーは、「マルクスよりも以前に、アンシャン・レジームの最後の世紀を解釈する鍵は、貴族に対するブルジョワジーの勝利にあることを確信していた。」(フュレ, p.54)
「議会はこの動議〔1789年7月4日にタレーランが国民議会で提議した動議。議員に対する選出母体からの命令的委任の廃止を求めるもの。〕を採用して、昔の三部会の封建的性格を払い落とした。そのうえ、この時期には国民代表の正当な理論とは何かなどはまったく問題になっておらず、避けることのできないきわめて実践的な問題が重要であった。ブロイの軍隊はパリを追い詰め、毎日少しずつパリに迫っていた。パリは上へ下への大騒ぎになっていた〔…〕宮廷と多数の貴族や聖職者は国民議会に反抗する陰謀を企てていた。最後に、飢饉がほとんどすべての地方を襲ったが、これは地方の封建的関税の存続と封建的農業条件全体との結果であった。〔…〕
タレーランの動議によって国民議会は自立を宣言し、議会が必要とする権力を奪取した。〔…〕国民議会は、その背後にいる無数の大衆に押されるようにして、一歩前進することを余儀なくされた。こうしたからといって、国民議会が〔シュティルナーの言うように〕『右顧左眄せず臍の緒を断ち切ってまったくエゴイスト的な議会に』変わったわけではない。むしろこのふるまいによってはじめて国民議会は大多数のフランス人の現実的機関へ変わったのである。もしそうでなかったなら、大衆は議会をふみつぶしていたことだろう。〔…〕ところが聖マックスは、〔…〕ここに理論的問題だけを見る。彼はバスティーユ襲撃の6日前の立憲議会を、教義上の一点をめぐって論議する教父たちの会議のごときものと思っているのだ! 〔…〕立憲議会が理論的見地から見ても決着をつけたものは、支配階級の代表と支配的身分の代表との区別である。そしてブルジョワ階級の政治的支配は、当時の生産諸関係によって制約されていたから、各個人の生活状態によっても制約されていた。代表制は近代ブルジョワ社会のまったく特殊な産物であって、近代の孤立した個人がブルジョワ社会から切り離せないのと同様に、代表制はブルジョワ社会から切り離せないのである。」
『ドイツ・イデオロギー』,in:フランソワ・フュレ編著,今村仁司・他訳『マルクスとフランス革命』,2008,法政大学出版局,p.235. MEW Ⅲ S.181.
↑「生産関係」という言葉が初めて現れている。
しかし、「このふるまいによってはじめて国民議会は大多数のフランス人の現実的機関へ変わった」――――「ブルジョワ階級の機関」とは言っていない。『ドイツ・イデオロギー』ではマルクスは、「国家=支配階級の機関」説をとっていない。
タレーランは、第一身分(聖職者)として『三部会』議員に選出されたが、「球戯場の誓い」(6.23.第三身分が「国民議会」として自立)、国王臨席会議による「国民議会」無効宣言(6.23)、国王一転して聖職者・貴族身分に「国民議会」合流を勧告(6.27)、……という一連のできごとを通じて、一貫して第三身分と行動を伴にしていた。
聖職者議員の大半と貴族議員の一部は、立憲君主制などの第三身分の改革的意見に同調していたが、彼らの選出母体である教会・貴族団体の「命令委任」が有効だとすると、彼らは自己の意思に反して第三身分に反対しなければならない。タレーランの演説と動議は、この障碍を除去する意味があった。提議に従って「国民議会」は「命令委任の廃止」を宣言したので、改革的意見が過半数を超えるようになり、7月9日には「国民議会」は自ら「憲法制定国民議会」と改称する。
『第二章では、1789年7月に国民議会で行われたタレーランの演説に着目し、その歴史的意義について考察した。この演説は、命令的委任の廃止を求める内容だった。国民議会が旧来の代表理論の転換を名実ともに成し遂げ、国民議会主導の改革を進めていくためには、命令的委任の廃止を明確にする必要があった。革命の流れを押しとどめようとしていた「反革命派」は、命令的委任を根拠にして抵抗した。しかし、緻密な論理で組み立てられたタレーランの演説の前に彼らは敗北し、代議制を目指す革命の潮流は決定づけられた。このようなタレーランの演説の歴史的意義を、議会内討論や「反革命」貴族のパンフレットとの比較を通じて明らかにした。』(山岸拓郎「憲法制定国民議会とタレーラン」https://www.senshu-u.ac.jp/School/hist/daigakuin-ronbun-yamagishi.html)
このタレーラン動議の意義について、シュティルナーは、「所有者」「エゴイスト」としての個人の自覚の観点から、代表制理論(自由委任)の問題として論じる。
これに対してマルクスは、動議の背景は理論的問題ではなかったとし、タレーランは、「国民議会」がブルジョワジーの利益のために行動できるようにすることだけをめざしていたとする(つまり、タレーランは、階級的な目的を隠して、「代議制理論」という偽装的論理を組み立て「緻密な論理による演説」で他の議員を動かしたとする)。パリと農村における階級的危機の進行が、「国民議会」に、迅速な行動を要求していた。タレーランを急き立てていたのは、この「現実」の動きだったとする。
しかし、シュティルナーのように、社会の動きと切り離して、国民代表制度や個人主義の理論的問題としてのみ考えるのも、マルクスのように、社会⇒政治 の一方通行だけを見るのも、間違えだろう。
タレーラン演説によって開始された「国民議会」の「改革」行動が、7月14日のバスチーユ襲撃に至る都市民衆の行動を刺激した面も考慮する必要がある。

「1789年やその4月から8月にかけてブルジョワジーが果した役割〔…〕まさしくこの数か月のあいだに、彼〔マルクス――ギトン註〕のいう封建社会すなわち諸身分と諸社団からなる社会構造が破壊される。この決定的な時期における歴史の主人公たちのふるまいは、哲学者〔マルクス――訳者註〕が彼らに割り当てた役割に厳密に対応している。つまり、ブルジョワジーはブルジョワ革命を実現するのである。〔…〕彼らの行動は、ブルジョワ階級が担う歴史的義務を客観的に果たすこと以外の何ものでもない。ただしそれは、国民の名においてなされるのである。〔…〕マルクスは、6月に主権が国王から全国三部会へと移ることの重要性を強調している。なぜなら、そのときまさに、旧い封建的な制度〔「三部会」を指す〕が国民議会へと変貌するからである。すなわちそれは、近代的公民性が誕生する瞬間であり、また同時に、ブルジョワ的所有が誕生する瞬間でもある。さらにそれは、旧い代表の概念を根底から変えてしまう。
ブルジョワジーが有産者による新たな社会支配を普遍性の旗印によって隠蔽するとき、彼らは同時に、貴族や宮廷に対抗する自分たちが都市や農村部の民衆に立脚しているということを十分に自覚している。7月14日の都市革命と農民反乱を経験した国民議会は、速やかに八月政会を布告してアンシャン・レジーム社会を一掃する。〔…〕
〔かつて〕青年マルクスがジャコバン的恐怖政治や総裁政府やナポレオン独裁に関心を抱いたのは、〔…〕民主国家の生成は彼にとってフランス革命の本質をなしていたからである。
ところが、1845年以後のマルクスは逆に、フランス革命全体をブルジョワ市民社会の誕生へと還元してしまい、ブルジョアジーとは無関係な事件までもがその誕生に寄与するものとされる。〔…〕恐怖政治の『ハンマー』の存在理由は、1789年とまったく同様に、『怖気づいた』ブルジョワジーによって裏切られたブルジョワ革命を実現する必然性と、最後まで残った『封建制の遺物』をフランスの地から一掃する必要性によって説明されるのである。かくしてマルクスによれば、ブルジョワたちが民衆に取って代わられるのはブルジョワ自身の弱さのせいなのだが、しかしそのことはたいして重要ではない。なぜなら、革命国家はもはや社会的決定に完全に従属するプロセスにおける単なる副産物にすぎなくなるからである。〔…〕フランス革命を構成する政治的変化のすべては、これ以降、ブルジョワ支配という共通の尺度によって測られるのである。
〔…〕ギゾーは、〔…〕持続的な代議政体の創設をもってフランス革命の終わり fin〔終点、すなわち目標――ギトン註〕とするのである。〔…〕
マルクスは、代議政体の問題に関心を示さない。マルクスから見れば、代議政体とは、イギリスの革命を通じて権力の座に就いたばかりの一階級が、編みだしたものにすぎず、1世紀のちに別の革命によって生み出されたものと同じである〔つまり、マルクスは、歴史的事象の個性を認めない〕。
ギゾーにとってブルジョワジーの勝利が普遍的意味をもつのは、それが自由な諸制度を打ち立てたからである。つまり、その勝利は歴史の真の終焉〔目的――訳者註〕なのである。
他方、マルクスにとってブルジョワジーの勝利とは、諸利害の支配という究極の現実と不可分であり、この現実は、さまざまな体制や理念によって多かれ少なかれあからさまに隠蔽されているのである。政治的なものの背後に経済的なものを発見しなければ気がすまないマルクスは、イギリス革命が宗教的な性格をもっていたことや、それがより古い伝統を復興させるという逆説的な意志をともなっていたとするギゾーの見解を認めない。」
フランソワ・フュレ編著,今村仁司・他訳『マルクスとフランス革命』,2008,法政大学出版局,pp.241-243.
「国民の名においてなされる」――これだけなら、階級支配の手段を、全国民の普遍的利益と見誤らせる「幻想」だが、じっさいには、「国民議会」はサンキュロットや農民の動きに圧されて行動しているとマルクスは見ており、彼らの利益になる施策も部分的に徐々に実施されていく。もっとも、マルクスはそれらを、もっぱらブルジョワジ−の利益にだけ奉仕するものだと、カテゴリックに理由づける。いずれにしろ、「国民議会」は、全国民のための改革を、やるぞ、やるぞ、と旗印をなびかせるだけで、やることの大部分はブルジョワのためか、「個人」「公民」「自由」等啓蒙的理念のためなので、期待が大きくなったサンキュロットの動きはますます激しくなり、“追いかけっこ”が続くことになる。
まず社会階層そのものの分析を行なって、その結果に基づいて政治情勢を解明するのではなく、逆に、見かけ上の政治勢力間の争いの“本質”――とマルクスが思い込んだかなり俗流な偏見――を説明するのに都合がよいように、社会階層を空想的にこしらえてしまう。そして、政治上の各勢力は、しかじかの社会階級の利害を代弁しているのだ、と強弁する。
しかし、政治情勢が変れば、この説明は苦しくなるので、こじつけをしたり、社会階層の性格をそのたびに変えてしまったりする。ご都合主義の歴史記述はマルクスに始まる。
政治勢力と社会階層は1対1対応するものではないし、政治勢力が社会階層の欲望を忠実に反映するわけでもない。普通選挙が行われていてさえそうなのだから、まして普通選挙以前の時代は言うまでもない。
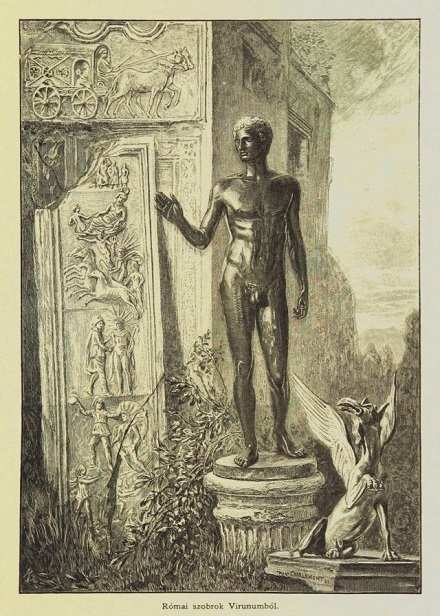
「ずっと前の箇所でフォイエルバッハに反対して論じたことから明らかなように、分業の枠内でこれまでに起きた種々の革命は必ず新しい政治制度に行き着いた。同様にそこで明らかにされたように、分業を廃棄するコミューン型共同社会をめざす革命は結局のところ政治制度の消滅に行き着くのである。最後に、コミューン型共同社会をめざす革命は『才知ある改革者たちの社会的構想力』に導かれるのではなく、生産諸力の状態によって導かれることも明らかになる。」
『ドイツ・イデオロギー』,in:フランソワ・フュレ編著,今村仁司・他訳『マルクスとフランス革命』,2008,法政大学出版局,pp.239-240. MEW Ⅲ SS.362-364.
「1789年やそれ以前のフランス・ブルジョワジーについて、マルクスはより正確には何を考え、また何を言っているのか。〔…〕彼は、イギリスとフランスの功利主義哲学を論じるために、これら2国の経済・社会状態を比較しながら、彼のいう『発展途上にある闘争中のブルジョワジー』〔ホッブズ、ロック、エルヴェシウス、ドルバック〕を『成長を終えて勝利したブルジョワジー』〔J・S・ミル、ベンサム〕と対置している。〔…〕これらの記述は正確さを欠くうえに、フランス史に関するマルクス主義的分析の目的論的性格をいたずらに強調することに終始している。」
フランソワ・フュレ編著,今村仁司・他訳『マルクスとフランス革命』,2008,法政大学出版局,pp.81.
「効用の理論と開発〔搾取〕の理論の進歩とそれらのさまざまな段階は、ブルジョワジーの進化の種々の段階と相互にぴったりと依存しあっている。エルヴェシウスとドルバックの場合、この理論は、〔…〕現実の実践であるよりは、むしろあらゆる関係を開発〔搾取〕関係に還元し、交換を物質的欲求や欲求を満たすやり方によって説明しようとする願望であった。〔…〕
ホッブズとロックは、オランダのブルジョワジーの初期の発展を眼前に見ていて、〔…〕とくにロックは、〔…〕株式会社、英国銀行が生まれ、イギリスの海外制覇が判然としてきた時期に著作活動を行なった〔…〕とりわけロックにおいては、開発〔搾取〕の理論はまだ経済的内容に直結していた。
エルヴェシウスとドルバックが眼にしていたのは、イギリスの理論や英蘭両国のブルジョワジーがすでになしとげた発展はもとより、自分の自由な発展のために闘っているフランスのブルジョワジーの姿であった。18世紀のパリは、あらゆる国籍をもつ個人が個人的関係を結ぶことのできる唯一の世界都市〔…〕であった。エルヴェシウスとドルバックの理論に普遍的性格というこのフランス特有の色彩が付着して、イギリス人にはまだみられた積極的な経済的内容が消去される。〔…〕一箇の哲学体系へと成長していく。事実的内容の消失を伴うこの普遍的性格は〔…〕、ベンサムやミルのなかではじめて出会うような・具体的事実に養われた普遍性とは根本的に違う。前者は闘争し発展しつつあるブルジョワジーに対応し、後者はその成長を終えて勝利したブルジョワジーに対応する。
エルヴェシウスとドルバックが無視した開発〔搾取〕の理論の内容は、ドルバックが著作活動を行なっていた時期に、フィジオクラートにより発展させられ体系化された。しかし〔…〕この時期のフランスでは、土地所有を第一義とする封建制度がまだ打破されていなかったから〔…〕彼らフィジオクラートたちは、土地所有と農業労働をあらゆる社会のかたちを決定する生産力とみなす点でまだ封建的な見方にとらわれていた。
開発〔搾取〕の理論はその後、〔…〕ベンサムが発展させた。ベンサムは、ブルジョワジーがイギリスでもフランスでも影響力を広げていくのと同時並行して、フランス人が無視した経済的内容を少しずつ理論のなかに取り入れていった。〔…〕最後に、J・S・ミルのなかには効用理論と経済学との完全な融合が見られる。〔…〕ベンサムにおいてはじめて、現存するすべての関係は効用関係に従属させられることになった。〔…〕ベンサムの時代には、フランス革命と大工業の発展の後で、〔…〕」
『ドイツ・イデオロギー』,in:フランソワ・フュレ編著,今村仁司・他訳『マルクスとフランス革命』,2008,法政大学出版局,pp.241-243. MEW Ⅲ SS.396-398.
18世紀の「フランスでは、土地所有を第一義とする封建制度がまだ打破されていなかったから」――――――まず、事実認識が誤り。大革命前には、封建的土地所有は名目化し、むしろ重要なのはブルジョワ的大土地所有(地主小作制度)だった。そればかりでなく、重農主義者が「土地所有と農業労働」を分析の主軸に据えたのは、工業の発達がまだ無かったからで、「封建的な見方」のためではない。
フュレによると、マルクスが大革命期およびに先立つ 18世紀のブルジョワジー、または啓蒙主義の思想家に多少ともくわしく言及したテクストは、↑これが唯一。しかもエンゲルスの筆跡だ。けっきょく、マルクスは、大革命について基礎的な研究をなに一つしないで、ギゾーを都合よく虫食いして自説にしているだけなのだ!
しかも↑この唯一の箇所においても、3組の思想家の理論を「ブルジョワジーの進化の種々の段階」だけで無理やり説明しようとする。歴史に対する「暴虐」(フュレ)としか言いようがない。
エルヴェシウスは、人の全 faculties を身体感覚に還元し、快苦のみが人間の判断の基礎であるとする。人間にとって、善悪の判断は自由におこなえるわけではなく、ただ習俗によってのみ判断しうる、と。
感覚的自由主義のなかで、この「習俗」の重視は重要。アダム・スミス(なぜマルクスは言及しないのか?!)のように、無制限の欲望の発揮が、「市場」によって自ずと調和に導かれる、というのではなく、欲望の発揮と経済活動には、「習俗」というおのずからの制限があるとする。vgl.ポランニー、アリストテレス。エルヴェシウスは、資本主義の一歩手前の・商品生産者の社会に対応するのではないか?

Claude Adrien Helvétius (/hɛlˈviːʃəs/; French: [klod adʁijɛ̃ ɛlvesjys]; 26 January 1715 – 26 December 1771) was a French philosopher, freemason and littérateur.
Psychological egoism
Further information: ⇒Psychological egoism
Helvétius' philosophy belongs to the Egoist school:
1 All man's faculties may be reduced to physical sensation, even memory, comparison, judgment. Our only difference from the lower animals lies in our external organization.
2 Self-interest, founded on the love of pleasure and the fear of pain, is the sole spring of judgment, action, and affection. Human beings are motivated solely by the pursuit of pleasure and the avoidance of pain. "These two," he says, "are, and always will be, the only principles of action in man."[6] Self-sacrifice is prompted by the fact that the sensation of pleasure outweighs the accompanying pain and is thus the result of deliberate calculation.
3 We have no freedom of choice between good and evil. There is no such thing as absolute right – ideas of justice and injustice change according to customs.
This view of man was largely Hobbesian – man is a system deterministically controllable by a suitable combination of reward and punishment, and the ends of government are to ensure the maximization of pleasure.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Adrien_Helv%C3%A9tius)
Psychological egoism is the view that humans are always motivated by self-interest and selfishness, even in what seem to be acts of altruism. It claims that, when people choose to help others, they do so ultimately because of the personal benefits that they themselves expect to obtain, directly or indirectly, from so doing.
This is a descriptive rather than normative view, since it only makes claims about how things are, not how they “ought to be” according to some. It is, however, related to several other normative forms of egoism, such as ethical egoism and rational egoism.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_egoism)
【38】附録――フュレ『マルクスとフランス革命』から、『ドイデ』以後
「19世紀フランスはこのように、マルクスに対して未来のプロレタリア革命と過去のブルジョワ革命とを同時に提示し続ける。だが、この両者は、革命という歴史的行為が複数の内容を持ちうるということや、フランス人がとりわけこうした形式のもとで政治闘争を展開する伝統を持つということを認めさえすれば、けっして両立不可能ではない。なぜなら、これらの政治闘争はその起源ないし母胎をフランス革命に見出しているからである。事実マルクスは、近代フランスのこうした目覚ましい特殊性にどれほど感銘を受けているかを何度も示唆する。だが他方で、同じ革命が何度も繰り返されるという考え方は、ブルジョワ革命かプロレタリア革命かという二者択一にとらわれている彼の概念図式には無縁のものである。」
フランソワ・フュレ編著,今村仁司・他訳『マルクスとフランス革命』,2008,法政大学出版局,pp.103-104.
つまり、19世紀の諸革命――マルクスにとって近過去ないし現在――について、マルクスの歴史把握は支離滅裂なものとならざるをえない。相互に矛盾した評価を打ち出しながら、いつも最後には、千篇一律の強引な定式化を繰り返すのだ。
マルクスによると、「ブルジョワ国家の歴史は定義によって、それが隠蔽するものすなわちブルジョワの階級利害によって支配され続けており、国家はこの利害の代理人にほかならない。だが、共和政が生んだ普通選挙という偉大な新機軸は、そこにかつてない駆け引きの余地をもたらした〔とマルクスは言う〕。つまり、被搾取階級――労働者階級、農民、小ブルジョワジー――がみずからの自立や反乱を誇示する機会が周期的に訪れるのである。」
ところが、そう言っておきながら、「ルイ・ナポレオン・ボナパルト〔ナポレオン3世〕を共和国大統領に選出した 1848年12月10日」の大統領選挙は、「被搾取階級の反乱誇示」だったのか、それとも「ブルジョワジーの勝利」だったのか、という点になると、マルクスは、そうでもあったし、そうでなくもあった、‥式の両論併記になってしまう。「一方で、マルクスはこの選挙を、ブルジョワの共和国とその富その課税その政治屋に対抗するためにナポレオン伝説を利用した『農民反乱』として分析する。」ところが、選挙の結果はルイ・ナポレオンの圧倒的勝利で、「プロレタリアートと小ブルジョワジーを合わせた民衆票の大部分のみならず、大ブルジョワジー票の大半も取り込んでしまう。」そこでマルクスは、いつもの公式に従って、全ブルジョワジーは連合して 1948年「2月革命」の「革命的プロレタリアート」を粉砕したあと、さらに支配を確実にすべく、共和主義右派などよりも確実な保証を得るために、ルイ・ナポレオンのもとで「ブルジョワの利害の統一」をはかったのだ、ということになる。
「たがいに矛盾し異なる・さまざまな利害によっていくつもの分派に分かれているブルジョワジーという考えは、〔…〕この種の解釈にありがちな弱点をかかえている。なぜならこうした考え方は、政治闘争の観察から導き出される一方で、その当の闘争を説明するとみなされるからである。」つまり、論点先取、堂々巡りの論証になってしまう。主張は恣意的なものにならざるをえない。たとえば、「七月王政」と「産業ブルジョワジー」の関係。マルクスは、論文のあるところでは、「七月王政」は「金融貴族」が握っていて、「産業ブルジョワジー」はそこから排除されていたと言う。そのすぐ先では、「七月王政においては金融貴族と産業ブルジョワジー」が権力を独占していたと言う。また、1948年6月の「叛徒」たちを、マルクスは「プロレタリアート」と規定するが、彼らは実際には工場労働者でも何でもない。「パリでバリケードを築いていた下層民たちは、近代的な労働者階級とはあまり関係がない〔…〕。マルクスの分析は非常に多くの点で、〔…〕当時の政治的幻想――そこには、彼自身が生み出したものも含まれる――にとらわれているのである。」以上は、マルクス『フランスにおける階級闘争』による。
フランソワ・フュレ編著,今村仁司・他訳『マルクスとフランス革命』,2008,法政大学出版局,pp.109-111,143註(11).
このように、マルクスは「ナポレオン3世」(共和国大統領から、さらに国民投票を経て皇帝に即位した)の執権をも、「階級闘争」論理で説明しようと四苦八苦している。ところが、その後の論考『ブリュメール18日』になると、今度は一転して、「国家が社会に対して自立し、社会を服従させたようにみえる」と言い、そのすぐ後では、また「階級闘争史観」に戻って、「ナポレオン3世」は、「フランスで一番数の多い階級、分割地農民を代表している」などと断定する。
絶対王政期以来の国家行政機構の拡充を、マルクスは、「ブルジョワ階級による支配」に資するもの、という一貫した論理に収めようとして、さまざまに強弁する↓:
「巨大な官僚組織、軍事組織をもった〔…〕国家機構、すなわち 50万人の夥しい官吏と 50万人の軍隊をもつこの執行権力は、網の目のようにフランス社会の身体に絡みつき〔…〕ているこの恐るべき寄生体は、封建制の衰亡の際、絶対王政時代に生れたもので、封建制の衰亡の加速に力を貸したのだった。地主と都市の領主特権は、そっくり国家権力の特権に変わり、封建制下の高位者は有給の官吏に、相矛盾した中世的諸絶対権の雑多な見本は、仕事が工場生産的に分業化、集中化された整然たる国家権力構想に変わった。
第一次フランス革命は、国民の市民的統一を創出するために、地方的、領地的、都市的な特殊権力を打ち砕く使命を帯びて、絶対君主制がはじめた〔…〕集権化を発展させなくてはならなかったが、おまけに行政権力の規模、特権、手先も拡大しなくてはならなかった。ナポレオンはこの国家機構を完成した。正統王政復古と七月王政は、分業の拡大以外何も付け加えなかった。分業が市民社会内に新しい利害集団を、したがって国家行政の新しい分野を生み出すにつれて、分業が拡大した。
共通の利害はみな、村の橋、校舎、公共財産から、フランスの鉄道、国有財産、国立大学に至るまで、たちまち社会から切り離され、より高い一般的な利害として社会に対立させられ、〔…〕政府の活動の対象にされたのである。議会共和政はついに、革命と闘う過程で、弾圧措置によって行政権力の手段を増強し、その集中化を進めざるをえなかった。〔…〕
しかし絶対君主制下でも、第一次革命期でも、ナポレオン治下でも、官僚機構は、ブルジョワジーの階級支配を準備するための手段にすぎなかった。王政復古、ルイ=フィリップ、議会共和政のもとでは、官僚機構がどれほど独自の権力の獲得に努めたにせよ、それは支配階級の道具だった。
二代目ボナパルトのもとではじめて、国家が社会に対して自立し、社会を服従させたようにみえる。〔…〕
そうは言っても、国家権力というものは宙に浮いているものではない。ボナパルト〔3世〕は、〔…〕フランスで一番数の多い階級、分割地農民を代表しているのだ。
〔…〕ボナパルト家は、農民の、すなわち、フランスの国民大衆の王朝なのである。ブルジョワ議会に服従したボナパルトではなく、ブルジョワ議会を追い散らしたボナパルトが、農民の選んだ人物である。」
『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』,in:フランソワ・フュレ・編著,今村仁司・他訳『マルクスとフランス革命』,2008,法政大学出版局,pp.302-304. MEW Ⅷ SS.196-198.
「農民」という一体化した階層が存在するという認識は、重要だ。現実から幻想に至る濃淡さまざまの「共同体」の絆が、おそらく「農民」の一体性の基盤だ。たとえば戦後日本なら、毎年の政府買い上げ米価を決める「農政審議会」に大挙参上して圧力をかけた「農協」傘下の農民たち。そのパワーは、労働組合などよりずっと大きく、しかも一糸乱れずに、まとまっていた。
『ドイツ・イデオロギー』ノート ――――終り。
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]




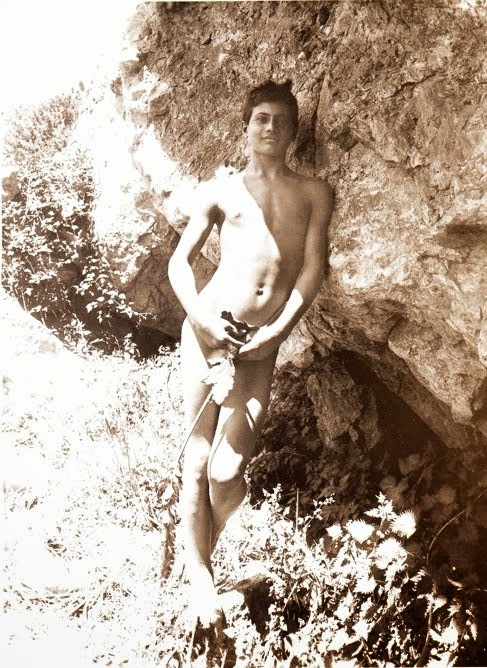


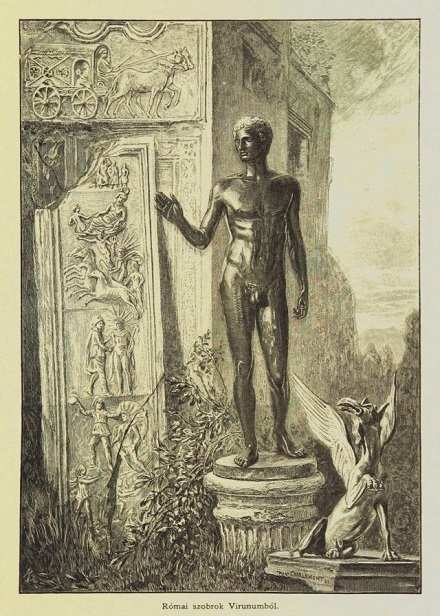



 彡
彡