08/21の日記
22:47
【ユーラシア】『ドイツ・イデオロギー』ノート(12)
---------------
.
こんばんは。(º.-)☆ノ
【ユーラシア】『ドイツ・イデオロギー』ノート(11)からのつづきです。
マルクス/エンゲルスの共著『ドイツ・イデオロギー』は、編集中途の草稿の状態で遺された未完成の著作です。内容的に未完成で、さまざまに矛盾する主張を含んでいますが、それこそがこの作品の魅力でもあります。また、内容だけでなく、形式面でも大きな混沌をはらんだテクストであるため、字句はもちろん篇別構成・断片の順序に至るまで、編集者の介入を必要としており、版本によって相異があります。ここでは、廣松渉・編訳,小林昌人・補訳『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,2002,岩波文庫. をテクストとして使用します。
上記岩波文庫版からの引用中、青字はマルクスの筆跡、それ以外(白字)はエンゲルスの筆跡。草稿の抹消箇所は下線付きで、追記・挿入は斜体で示します。
「エンゲルスの筆跡エンゲマルクスの筆跡ルスの筆跡」
「人間を動物から区別するのは、生産するみたいな感じでことによってである。」
「人間が自らを動物から区別するのは、道具を用いて生産することによってである。」
この「ノート」は、著作の内容を要約することも、著者らの思想を伝えることも目的としていません。あくまでも、私個人の思索のための抄録と、必ずしもテクストにとらわれないコメントを残すためのものです。
【31】「本論三2」――プロレタリアの領有と「自己活動」
「こうして、いまや事態は、諸個人が眼前の生産諸力を領有しなければならない――彼らの自己活動に至るためにも、そればかりか、そもそも彼らの生存を確保するためにすら――ところにまで来ている。この領有 Aneignung は、まず〔第一に〕、領有されるべき対象――発展して一総体となり、普遍的な一交通の内部でのみ実存する生産諸力――によって条件づけられている。それゆえこの領有は、この側面からしてもすでに、生産諸力と交通に照応する普遍的な性格をもたざるをえない。これらの諸力を領有するということそのものが、物質的な生産諸用具に照応する個人的諸能力の発展に他ならない。〔…〕この領有は、さらに〔第二に〕、領有する側の諸個人によって条件づけられている。いっさいの自己活動から完全に閉め出された現代のプロレタリアたちだけが、もはや局限されない nicht mehr bornierte 彼らの完全な自己活動――それは生産力の一総体の領有とこれに伴っておきる諸能力の一総体の発展のうちにある――を実現することができる。
すべての従来の革命的な領有は、局限されたものであった。制約された生産用具と制約された交通のためにその自己活動が局限されていた諸個人は、この制約された生産用具を領有したのであって、それゆえただ新たな被制約性にたどりついただけだった。彼らの生産用具は彼らの所有物 Eigentum になったが、彼ら自身は分業の下に、そして彼ら自身の生産用具の下に、服属させられたままであった。これまでの領有は、すべて、多数の諸個人がただ一つの生産用具に服属させられた状態が続いた;
しかし、プロレタリアたちの領有の場合には、大量の生産諸用具が各個人の下に unter jedes Individuum、そして所有 das Eigentum がすべての諸個人の下に服属させられねばならない。近代の普遍的な交通を諸個人の下に服属させるということは、すべての諸個人の下に服属させる以外不可能である。
領有はさらに〔第三に〕、それが遂行されることになる方式によって条件づけられている。領有は、プロレタリアート自身の性格からして普遍的なものとなるほかはない結合 Vereinigung、および革命によって遂行されなければならない。この革命のなかで、一方ではこれまでの生産様式、交通様式、および社会的編制・の威力が打倒され、他方ではプロレタリアートの普遍的性格と領有完遂に必要なエネルギーが発展し、さらにプロレタリアートは、これまでの社会的地位から引きずってきたすべてを一掃する。」
廣松渉・編訳,小林昌人・補訳『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,2002,岩波文庫,pp.197-199.
「これまでの領有は、すべて、多数の諸個人がただ一つの生産用具に服属させられた状態が続いた;しかし、プロレタリアたちの領有の場合には、……」――――どう考えても歴史的事実とは違うことを述べている。ドイツ・イデオローグ特有の“極端言説”と見るほかはないだろう。「唯一者」(生ま身の現実的個人)がすべてを「所有」するという、シュティルナーの支離滅裂言説を引き継いでいるのかもしれない。
「プロレタリアートは、これまでの社会的地位から引きずってきたすべてを一掃する」などなど、“社会主義”国家の暴虐をもたらした言説のすべてが、この支離滅裂な“哲学的妄想”と相即して称揚されていることが、よくわかる。
「この段階で初めて、自己活動が物質的生と合致するようになる。このことは、諸個人の総体的な諸個人 zu totalen Individuen への発展と、一切の自然発生的なものの一掃に照応する。ここにおいて und dann、労働の自己活動への転化と、これまでの条件づけられた交通の・諸個人の交通そのものへの転化とが、互いに照応する。結合した諸個人による・総体的な生産諸力の領有とともに、私的所有は終わる。
これまでの歴史では常に或る特殊な条件が偶然のものとして現われたが、いまや、諸個人の分離そのもの、各人の特殊な私的営み Privaterwerb そのものが偶然的なものとなっている。
もはや分業に服属させられない諸個人を、哲学者たちは、理想として『人間』の名のもとに表象し、われわれがこれまで展開してきた過程全体を『人間なるもの』の発展過程として捉えた。〔…〕これは元をただせば、後の段階の平均的個人が次々と前の段階に押し込まれ、後代の意識が前代の個人に押し込まれることに由来する。」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,pp.199-200.
「諸個人の・総体的な諸個人への発展」など、これまでに述べられてきた抽象的で空虚な“哲学的言辞”のすべてが、「革命」によるプロレタリアートの生産手段「領有」(獲得)によって、実現するものとされる。その結果、目立つ事象としては、「一切の自然発生的なものの一掃」「私的所有は終わる」「各人の特殊な私的営み(私企業)」の「偶然化」→けっきょく禁止!……が、もたらされる。「絶対的必然」と合致する「絶対的“自由”」以外に、どんな自由があると言うのか?!
【32】断章――決定論と「自由」
廣松氏は、「河流」の例を持ち出す。重力によって下流へ向って流れる・河水全体の運動を、“歴史法則の貫徹”になぞらえ、河水の個々の分子の運動を、個人の意識的行為になぞらえる。しかし、この比喩は適切ではない。河水の流れる流体運動は、河床の地形によって“あらかじめ”決定されている。しかし、人類の歴史は、(廣松氏の言においても)そうではない。そもそも、「歴史法則の貫徹」などを持ち出すのは、自ら設定した問いを自ら破壊し、自らの主張を最初から放棄しているに等しい。
「河が時速数キロの速さで流れるためには、水の分子の"自由運動"を前提する。すなわち、個々の分子があらゆる方向にあらゆる速度で運動しうるということを前提する。〔…〕個々の分子の運動は、河流の〔流体運動の〕法則に対して"偶然的"〔ランダム〕である。まさしくかかる“偶然的”な“自由運動”の『合成力』としてのみ河流が存立する。
〔…〕歴史法則と諸個人の行為との関係は、まさしくかくのごときものであった。
マルクスは、『経済学批判要綱』のなかで次のように書いている。
『こうした運動の全体が社会的過程として現われ〔…〕過程の総体は、〔…〕意識した個人の相互作用から出てくるものであるとはいえ、彼らの意識のうちにもなく、全体として彼ら個人に従属せしめられることもない客観的な連関として現われる。諸個人自身の相互的衝突が、彼らの上に立つ、無縁な社会的力を彼らに対して生み出す』(高木幸二郎訳,p.116)」
廣松渉『マルクス主義の地平』,1969,勁草書房,pp.172-173.
「“偶然的”な“自由運動”の『合成力』としてのみ河流が存立する」――と言うが、『合成』されない「自由運動」もある。たとえば、スピン運動を主とする熱振動。
「河が……流れるためには、水の分子の"自由運動"を前提する」――という前提が、そもそも技巧的である。水分子は、純然たる自由運動をしているのではない。地球の重力と河床からの応力によって、流れ下る運動を与えられている。それを、個々の分子運動の一部として算入することももちろん可能ではあるが、あまりに技巧的だ。それは、分子の「自由運動」と重なるだけで、「自由運動」には何ら影響を与えないからだ。
自然現象から例を採るなら、廣松氏自身も後に取りあげた“林相の遷移”のほうがよい。森林は、たとえ極相に達した場合でも、完全な純林には決してならない。すべての森林が極相に向かうわけではなく、中途の状態でモザイク状を呈して周期的変化を繰り返すようになる場合もある。生物集団の場合、「法則」とは一般的傾向、ないし諸個体が集団として常に保持する一種の衝動のようなものにすぎない。スキーム化された系列を、きれいにたどって遷移する場合もあるが、そうでない場合も多い。そもそも樹種というものが、完全に固定したカテゴリーではない。なるほど、廣松氏は“遷移”を取りあげて論じているが、教科書に書かれた“遷移”系列のスキーム(図式)だけを問題にしており、流動的な部分に眼が届いていない。実際の“遷移”が、教科書に書かれているような図式的なキレイなものでないことは、実際に野山を歩いて観察すれば、誰にでもわかることなのだが。

「マルクス主義的自由の概念を積極的に措定するためには、法則性の側から、それと諸個人の行為との関係をみるのではなく、視点を"歴史・内・的"にとりなおして、いわば人間の側〔個人、ないし不定数の諸個人の側〕からアプローチしなければならない。
〔…〕『自由』の問題についても、たとえそれが超絶的な視座からすれば『自由』の名に値せぬにせよ、"歴史・内・存在"にとって有意義性をもちうる限りで、把えかえさねばならない。
歴史的・社会的法則性が存立するのは、〔…〕諸個人の営為が物象化することを通じてであって、vorherbestimmt ではない。
諸個人の活動が『自然生的に分掌されている限り、人間自身の行為が、彼にとって、疎遠な、対抗的な力となる。人間がそれを支配するのではなく、それが人間を従属させるような力となる。社会的活動のこの自己撞着 Sich-fest-setzen、われわれ人間自身の産物が凝固してわれわれの統御をはみだし、われわれの予期に齟齬をきたしめ、われわれの目算を狂わせてしまう物象的な力となること』、この故に『人間が歴史をつくる』とはいえ、意慾された企図どおりにならず、『逆にこの力のほうが、人の意思や動向から独立な、いや、人間の意思や動向を統御し』、『固有の道順をたどる一連の展相』を現出せしめるのである。
〔…〕
われわれが"人間的自由"を語る場合、それは超越的な視点からすれば『自由』の名に値しえないという可能性に対して、常に開いていなければならない。"人間的事実"に定位し、歴史内的に立場をとる限り、それが形而上学的見地からはよしんば"私念された自由"にすぎないとしても、われわれに対して無意味ではない。」
廣松渉『マルクス主義の地平』,1969,勁草書房,pp.189,190,193.
「人間の側」「"人間的自由"」と言えばいかにも聞こえが良いが、その「人間的」には、言うほどの内実が込められているのかどうか。「"人間的事実"に定位し」とは言うものの、氏の立場も考察も不十分と言わざるをえない。諸個人とも、ナマの歴史的事実とも無関係に形而上学的に措定された"歴史法則"を、そのまま証明抜きの前提としたうえで、いくら「人間的事実」などという言葉だけを唱えても、しょせんは空念仏でしかない。
「現実的諸個人から出発する」との前提を置いているマルクス/エンゲルスのほうが、よほどまともであろう。
「諸個人」から出発した歴史的事実を、あるいは個人の「自由」な諸行為、諸行動を整理しつつ、"歴史法則"の真偽を検証し、あるいはお仕着せの"歴史法則"などは否定し去って、あらたに即事的な論理を探ってゆくのでなければ、「人間の側からアプローチ」したとは言えない。
「私念された自由」に定位し、そこから「法則」を見直す視点が必要だ。
「自由」は「意識的」行為と切り離せないが、どちらの方向へ向かって「意識」するかが個人の判断に委ねられているのでなければ「自由」とは言えない。おのおのは「好き勝手に」ふるまってよいが、けっきょくのところ全体の行く方向はあらかじめ決まっている、などというのは「自由」ではない。
そのような「自由」は、人びとを「好き勝手に」走り回らせて疲れさせ、"ガス抜き"をしたうえで、予め定められた"全体の発展方向"に従わせるための策略でしかない。
そのような“お釈迦さまの手の内の”自由ではなく、個々の人間の自由な行為を社会と歴史の出発点とする「自由」。こうした「自由」の価値概念が、どこからどのようにして生じて来たのか、そして、このような意味の「自由」概念の・将来にわたる有効性は、はたしてどこまでなのか?‥これが、探究されるべき提題である。
「『アンチ・デューリング』を援用して言えば、『意志の自由とは事実の知識によって決意することのできる Fähigkeit にほかならない』。"本能的行動"から区別されたこのような意志行為、語の日常的な意味での"自由行為"、〔…〕"目標を選択的に選びとり、それを決意を媒介として実現する"ところの"自由意志的行為"〔…〕
歴史的実践のこの次元では、それを意識すること、そして決意すること、これが実践を、従ってまた、それの対象化を通じての歴史的法則の貫徹をたしかに左右する。」
廣松渉『マルクス主義の地平』,1969,勁草書房,p.194.
ただし、重要な点は、「それを意識すること」の「それ」、「決意する」方向、また「目的」は、予め定められていない、最終的には個人にのみ委ねられている、ということである。あらかじめ定められた軌道からは、道徳的強制と、"逸脱"に対する警戒・畏怖しか結果しない。
「歴史的法則の貫徹」とは言っても、「貫徹」する「法則」は、行為者が予想したものとはまったく異なるものであることが、むしろ通常なのだ。
この本は 1969年に発刊された古いもので、廣松氏としても旧論考なので、その叙述を詮索して批判するのは公平でないかもしれない。この書はこのくらいにして、氏のもっと後の著作に移ることとしよう。
【33】「本論三2」――「所有」と国家
「市民社会は、生産諸力の一定の発展段階の内部での諸個人の物質的交通の全体を包括する。それは一つの段階の商工業生活の全体を包括し、その限りにおいて国家や国民を超え出る――もっとも、他面では、市民社会の側でも、対外的には国民的なものとして自己を押し出し、対内的には国家として自己を編制せざるをえないのだが。
市民社会という言葉が登場するのは 18世紀、つまり所有諸関係がすでに古代的ないし中世的な共同体から脱却しおえた時である。市民社会としての市民社会はブルジョアジーとともにようやく発展するが、しかし、生産と交通から直接に発展する社会的組織――どの時代にもこれが国家およびその他の観念論的上部構造の土台をなしている――はいつもこの名で呼ばれてきた。
━━」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,pp.200-201.
「国家および法の所有との関係。――所有の最初の形態は、古代世界でも中世でも部族所有であり、それは、ローマ人の場合には主として戦争によって、ゲルマン人の場合には牧畜によって、条件づけられていた。古代の諸民族(特にローマとスパルタ)の場合は、一つの都市にいくつかの部族が一緒に住んでいる
〔支配部族と被支配部族――ギトン註〕ため、部族所有は国家所有として、そしてそれに対する〔支配部族員――ギトン註〕個々人の権利は単なる占有として、現われる。ただし、この占有は、部族所有が一般にそうであるように、土地所有の場面に限られている。本来の私的所有は、古代の諸民族の場合も、〔…〕動産所有とともに始まる。――(奴隷制と共同体)(ローマ市民法に基づく所有権)。
中世になって登場する諸民族の場合は、部族所有は種々の段階――封建的土地所有、同職組合的動産所有、マニュファクチュア資本――を経て、大工業と普遍的競争に条件づけられる近代的な資本へと、すなわち、共同体の外見をことごとく脱ぎ捨て、所有の発展に対する国家の干渉をことごとく排除してしまった純粋な私的所有へと、発展する。この近代的私的所有に照応するのが近代国家であるが、これは、租税を通して次第に私的所有者たちに買い取られ、国債制度を通して完全に彼らの手中に落ち、その存亡は、〔…〕ブルジョアたちが国家に与える商業信用に全面的に依存するようになってしまっている。ブルジョアジーは、〔…〕もはや地方的にではなく国民的に自己を組織するよう余儀なくされ、自らの平均的利害に一つに普遍的形式を与えるよう余儀なくされている。私的所有が共同体から解き放たれたことで、国家は、市民社会と並ぶ、そしてその外部にある、特別な一存在となった。とはいえ、それは、ブルジョアたちが対外的にも対内的にも自身の所有と利害を相互に保証するために自分たちに与える必要のある、組織の形式以上の何ものでもない。」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,pp.201-203.
「所有の発展に対する国家の干渉を排除してしまった純粋な私的所有」――少し前の引用部で述べられていた「幻想的共同体」国家観とは異なる近代国家観が述べられている。「幻想的共同体」としての国家の場合には、国家は被支配階級をも含めた諸個人全部を「公民」とし、彼ら全員の権利を保護するものとして幻想される。国家は、「公民」(国民)――すべての諸個人が所属する共同体と見なされる。たとえば、国民皆兵制度は、このような幻想的「共同体国家」のもとでのみ可能である。この国家のもとで、国民は私的所有権を保障されるが、それは実際には、支配階級の生産手段に対する占有を、国家の暴力によって「所有権」に高めていることにほかならない。資本家の生産手段所有は、国家の暴力によって支えられなければ排他的・絶対的権利として機能しないのであり、したがって、本質的には国家的所有なのである。
これに対して、ここで述べられているブルジョア国家観によれば、近代国家は、ブルジョアジーが被支配階級を支配するための機関にすぎない。「国家とは、支配階級の諸個人がそういう形で彼らの共通の利害を押し通す……形式である」(p.204)。
朝鮮植民地について言えば、「幻想的共同体」国家観の有効性が高いように思われる。「土地調査事業」は、民族の区別なく近代的所有権(排他的絶対的所有権)を保障することを標榜して実施された。しかし、同時に「朝鮮会社令」によって、朝鮮人の会社設立は禁止された。こうして、資本家の生産手段に対する排他的所有を保障するという「幻想的共同体」国家の機能は、朝鮮人資本家の生産手段に対する所有を排除して、民族支配機関としての機能と一致した。
「国家の自立性が今日でもなお見られるのは、身分がまだ完全には階級にまで発展していない国々、〔…〕身分がまだある役割を演じていて混合状態が現存しており、したがって住民のどの部分も他の諸部分を制して支配するということがまだできずにいるような、そういう国々ぐらいである。これは、とりわけドイツに当てはまる。
近代国家の最も完成された例は北アメリカである。近年のフランス、イギリス、アメリカの著述家たちはみな、国家は私的所有のためにだけ存在するものだという意見をそろって口にしているので、これはもう通常の意識の中に行き渡っている。
国家とは、支配階級の諸個人がそういう形で彼らの共通の利害を押し通す、そして一時代の市民社会全体がそういう形で自己を総括する形式であるから、共通の諸制度はすべて国家によって媒介され、政治的な形式をもたされることになる。ここから、法律があたかも意志に、しかもその実在的な土台から引き剥がされた自由意志に、基づくものであるかのような幻想が生じる。そうなれば今度は、法〔=権利〕das Recht も同様に、法律に還元される。」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,pp.203-204.
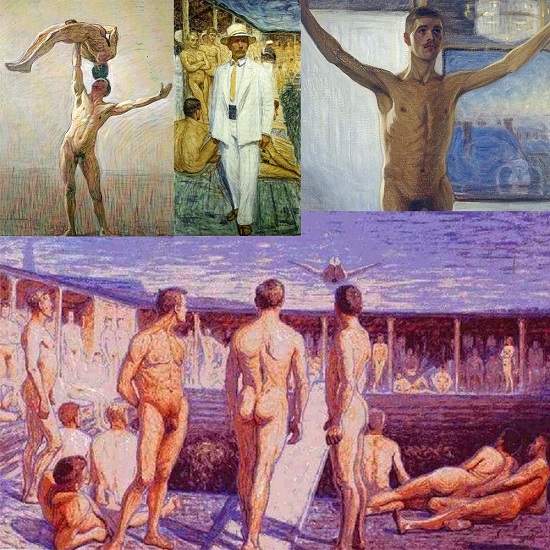
Eugene Jansson
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]






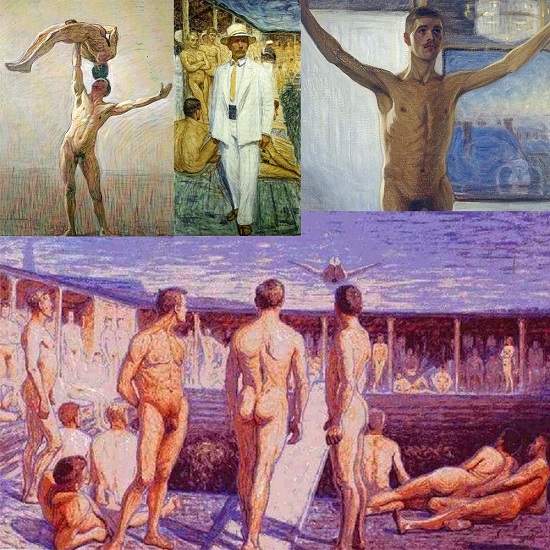
 彡
彡