08/14�̓��L
06�F26
�y���[���V�A�z�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�m�[�g(11)
---------------
.
 �@
�@
�@�����́B(º.-)���
�@�y���[���V�A�z�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�m�[�g(10)����̂Â��ł��B
�@�@�}���N�X/�G���Q���X�̋����w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�́A�ҏW���r�̑��e�̏�Ԃň₳�ꂽ�������̒���ł��B���e�I�ɖ������ŁA���܂��܂ɖ�������咣���܂�ł��܂����A���ꂱ�������̍�i�̖��͂ł�����܂��B�܂��A���e�����łȂ��A�`���ʂł��傫�ȍ��ׂ��͂�e�N�X�g�ł��邽�߁A����͂������ѕʍ\���E�f�Ђ̏����Ɏ���܂ŁA�ҏW�҂̉����K�v�Ƃ��Ă���A�Ŗ{�ɂ���đ��ق�����܂��B�����ł́A�A���E�Җ�C���я��l�E���w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,2002,��g����. ���e�N�X�g�Ƃ��Ďg�p���܂��B
�@��L��g���ɔł���̈��p���A���̓}���N�X�̕M�ՁA����ȊO�i�����j�̓G���Q���X�̕M�ՁB���e�̖����ӏ��͉����t���ŁA�NjL�E�}���͎Α̂Ŏ����܂��B
�u�G���Q���X�̕M�ՃG���Q�}���N�X�̕M�����X�̕M�Ձv
�u�l�Ԃ������ʂ���̂́A���Y�����݂����Ȋ��������Ƃɂ���Ăł���B�v
�u�l���������������ʂ���̂́A�����p�������Y���邱�Ƃɂ���Ăł���B�v
�@���́u�m�[�g�v�́A����̓��e��v�邱�Ƃ��A���҂�̎v�z��`���邱�Ƃ��ړI�Ƃ��Ă��܂���B�����܂ł��A���l�̎v���̂��߂̏��^�ƁA�K�������e�N�X�g�ɂƂ���Ȃ��R�����g���c�����߂̂��̂ł��B
�@�y28�z�u�{�_�O�Q�v�\�\�A���A����������`�Ԃ̔��W
�u����ɑ��āA�k�A�����J�̂悤�ȁA���łɔ��W�𐋂������j�i�K�ɂ����đ����ݏo�����X�ł́A���W�͔��ɑ����i�ށB���̂悤�ȍ��X�́A�������`�����������ɈڏZ���Ă��鏔�l�A�������A�ނ���~���ɏƉ����Ȃ��E�������X������`�ԂɁE��������Ă���ė������l�ȊO�ɂ��������ق��A�����Ȃ鎩�R�����I�ȑO��������Ȃ��B������䂦�����̍��X�́A�������X�̂����Ƃ��i���������l�ƂƂ��ɁA���������Ă���珔�l�ɏƉ���������Ƃ����W��������`�ԂƂƂ��ɁA�o������B��������`�Ԃ��A�������X�Ŏ����ł���悤�ɂȂ���O�ɁA���������o������̂ł���B����́A�ǂ̐A���n�ɂ��Ă��A���ꂪ�P�Ȃ�R����n�⏤�Ɗ�n�łȂ�����A�����邱�Ƃł���B�J���^�S�A�M���V���̏��A���n�A11,12���I�̃A�C�X�����h�������̎���ł���B
�@�ގ��̊W�������̏ꍇ�ɂ�������B����́A�ʂ̓y�n�Ŕ��W��������`�Ԃ��A�o���オ�����`�Ŕ퐪���n�Ɏ������܂��ꍇ�ł���B��������`�Ԃ́A�{���ł͂܂��O�ォ��̏����Q�⏔�W�ɂ܂Ƃ�����Ă����̂ɑ��A���ꂪ�������܂ꂽ�Ƃ���ł͊��S�ɁA�W�����邱�ƂȂ��������ꂤ�����A�����҂����Ɏ����I�ȈЗ͂�ۏႷ��Ƃ����ړI���炵�Ă���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�m���}���l�ɂ�鐪����̃C�M���X�ƃi�|���B�����̒n�́A�������ɕ����I�g�D�̍ł��������ꂽ�`�Ԃ�������B�j�\�\�\�\�\�\�v
�A���E�Җ�C���я��l�E���w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,2002,��g����,pp.188-189.
�����F�u����ɑ��āv���炱���܂ŁA�A���E���і�͌����܂ނ��߁i�u�`�ȊO�v�� als ���u�`�Ƃ��āv�ƖȂǁj�A�A���E�͏o�ł̌����Əa�J����Q�Ƃ��āA�������B
�@�����E�A���ɂ���āA�A���҂́A���Ƌ����Љ�̍ł����W�����u����`�ԁv����������ŁA���Ƌ����Љ�ɂ������~���ɖW�����邱�ƂȂ��A�V�����y�n�ł����W�J����A㋐�\�\�Ƃ����ꍇ�B
�@�V�����y�n�̐�Z�����L���Ă����u����`�ԁv�ɂ͖W�����Ȃ��̂��H �Ȃ����H �����ɂ���ė}������ł��܂����炩�H
�@���N�A���n�̏ꍇ�A�����̓��{�ɑ������Ő�[�́u����`�ԁv���������܂�āg���R���h�W�J���������낤���H �ނ���t�ł͂Ȃ����H ㋐�ɂȂ�Ȃ������Ƃ�����A�Ȃ��Ȃ̂��H
�@���{��`�i�K�ł́A㋐�͐������Ȃ��̂��H �鍑��`�i�K������H �ʉ݉��v�A�u�y�n�������Ɓv�Ȃǂ́A�����������x����������ŁA��R�𐧈����A���x���̂͂��������蒅�����B�i�u��Z���v�ɂƂ��ẮA���̎�̎������܂ꂽ�ߑ㉻�����x���̂��A���̑ΏۂƂȂ����j
�@�������A�_�Ƃɖ��������Ă݂悤�B�������傭�������܂ꂽ�̂́A���n�̍ł��x�ꂽ�����Ƃ���锼�����I�s�ݒn�吧�ł͂Ȃ��������H
�@���{��`�́u�O�����v�B�܂��A�{���I�~�ρB�ƁA�ǂ������W�ɂȂ�̂��H
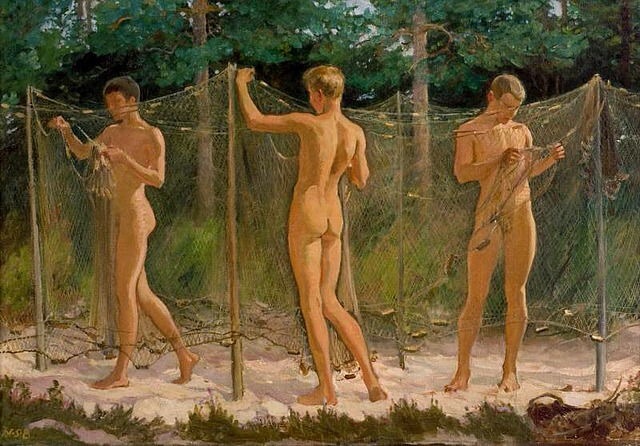
�u�����Ƃ��������́A���̗��j�ϑS�̂Ɩ������邩�̂悤�Ɍ�����B����܂ł́A�\���A�푈�A���D�A�����E�l�A���X�����j�̌����͂Ƃ������Ƃɂ���Ă����B�����͂����ł͎�v�ȓ_�����q�ׂ�悢���낤�B�����ŁA�ł������ȗ�\�\���������̔ؑ��ɂ��j��ƁA���̌�������Ĉꂩ��`�����n�܂�V�����Љ�̐��\�\���������グ�Ă������B�i���[�}�Ɣؑ��A�������ƃK���A�A�����[�}�鍑�ƃg���R�l�B�j
�@�������s�Ȃ��ؑ��ɂ����ẮA��Ɏ������Ă������悤�ɁA�푈���̂��̂��܂��ʏ������`�Ԃ̈�ł���B�`�����A�����Ĕނ�ɂƂ��ėB��\�������e��Ȑ��Y�l���ɂ����āA�l���̑������V���Ȑ��Y��i�ւ��~���傳���������قǁA�܂��܂��M�S�ɂ�������`�Ԃ����p�����B
�@�C�^���A�ł́A����ɔ����āA�y�n���L�̏W���i����͔���߂╉�ɂ��ق��A�����ɂ���Ă��������B�Ƃ����̂́A�͂Ȃ͂��������c�Ƃ܂�Ȍ����̂��߂ɁA�������ƌn���������Ɏ��ɐ₦�āA���̍��Y�������҂̂��̂ɂȂ�������ł���j�ƁA���̕��q�n�ւ̓]���i����́A�����ł����Ă͂܂�ʏ�̌o�ϓI�����ɂ��ق��A���D���ꂽ�����ƍv�[�����̗����A����т��̌��ʐ������C�^���A�Y�����ɑ������҂̕s���Ɍ������������j�ɂ���āA���R���Z���͂قƂ�ǎp�������Ă��܂����B�z�ꂻ�̂��̂͌J��Ԃ����ɐ₦�A��ɐV���ȓz��ŕ�[����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�z�ꐧ�́A�S���Y�̓y��ł��葱�����B���R���Ɠz��̊ԂɈʒu���镽�� Plebejer �́A�����ă����y���E�v�����^���A�[�g���Ȃ������B�����������[�}���k�P�Ȃ�l�s�s�̈���o�����Ƃ��Ȃ��A�����B�Ƃ͂قƂ�ǐ����I�A�ւɂ��������Ă��Ȃ������B���̘A�ւ́A���R�̂��ƂȂ���A�����I�����̂��тɒ��f���ꂦ���̂ł���B
�@�\�\�\�\�\�\�@�\�\�\�\�\�\�@�\�\�\�\�\�\��
�@���j�ɂ����Ă͂���܂ŗ��悾������肾�����A�Ƃ����\�ۂقǂ���ӂꂽ���̂͂Ȃ��B�ؑ������[�}�鍑�𗪎悵���B�����Ă��̗���Ƃ��������ŁA�Ñ㐢�E���畕�����ւ̈ڍs�����������B�������A�ؑ��ɂ�������̏ꍇ�ɖ��ƂȂ�̂́A��̂���鑤�̖������k��̂����ɐ旧���ā\�\�M�g�����l�A�ߑ�̏������Ɍ�����悤�ɁA�H�ƓI���Y���͂W�����Ă����̂��A����Ƃ��A�ނ�̐��Y���͎͂�Ƃ��Ĕނ�̌��� Vereinigung ���\�Ȕ͈͂ł̋��������� Gemeinwesen �Ɋ�Â����̂ł����Ȃ����A�Ƃ������Ƃł���B
�@����͂���ɁA���悳���Ώۂɏ����Â����Ă���B���̌`�ő��݂�����s�Ƃ̎��Y�́A���悷��҂����悳��鍑�̐��Y�������E����������ɋ������邱�ƂȂ��ɂ́A�������ė��悳�ꂦ�Ȃ��B�ߑ�̍H�ƍ��̑S�Y�Ǝ��{�ɂ��Ă��A���l�ł���B�����āA���ǂ̂Ƃ��뗪��͂ǂ��ł������܂��I���Ă��܂��B���悷����̂��Ȃ��Ȃ�ΐ��Y���n�߂�ق��͂Ȃ��B�������Ă����܂������鐶�Y�̕K�v������A��Z���鐪���҂��Ƃ鋤���̂̌`�Ԃ́A�k���̒n�́\�\�M�g�����l�����̐��Y���͂̔��W�i�K�ɏƉ��������̂ƂȂ�A���Ƃ����ʂ���B���邢�́A�����ŏ����炻���͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�����k�����҂̋����̌`�ԁl�́A�k�퐪���n�́l���Y���͂ɕ���ĕω����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������A�����ړ���̎���ɂ͂ǂ��ł�����ꂽ�Ƃ���鎖���A���Ȃ킿�A�l�i�����ׁj�����i���邶�j�ƂȂ�A�����҂����[�}�����ꂽ�퐪���҂̌���A���{�A����яK���������܂����ꂽ�������܂��A���������B�\�\�\�\
�@�������́A�����āA�h�C�c���犮�����ꂽ���̂��������܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��B�������́A�����̍Œ��ɂ������k�Q���}���l�R���̐�m�c�g�D�ɐ����ґ��̋N���������A���ꂪ�A������ɁA�퐪�������Ɍ����������Y���͂̉e�����āA�͂��߂Ė{���̕������ւƔ��W�����̂ł���B�����k�����ҋ����̂́l�`�Ԃ��A������k�퐪���n�́l���Y���͂ɂ���āA�ǂ�قNj��������Â����Ă������́A�Ñネ�[�}�̎c������N���o�鑼�̏��`�Ԃ��������悤�Ƃ��Ĕj�]�����E���X�̎��݂������Ă���i�J�[�����A���X�j�\�\�\�\�\�\
�@�����Ƒ����邱�Ɓ\�\�\�\�\�\�@�\�\�\�\�\�\�@�\�\�\�\�\�\�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,pp.189-192.
�����F�ȉ��A���̈��p�̍Ō�܂ŁA�͏o�ł̌������Q�Ƃ��ĉ����B
�@�O�̈��p�����Ƃ͋t�ɁA��Ƃ��Ĕ퐪���n�̎Љ�ɂ������E�i�u����`�ԁv����A����ɐi�`�Ԃ����܂��ꍇ�B�����҂́A�ނ���u��Z���v�́u����`�ԁv��吞�ݍ��܂��B
�@�u��̂���鑤�̖������c�c����̏������Ɍ�����悤�ɁA�H�ƓI���Y���͂W�����Ă����v�\�\���W�����Y���������i���J�����ɂ���āj��̂��ꂽ�ꍇ�A��̎҂́A���̍��̌o�ϐ��x�i����`�ԁj�ɏ]���A���̒��ɓ��荞��ŗ�����s�Ȃ����ƂɂȂ�B���̍����A�����I�_�Ƌ����̂̒i�K�ɂ���ꍇ�ɂ́A��̎҂́A���̊O���ɗ����āA�v�d�̌`�ŕx�����D����B
�@�������A��҂̏ꍇ���A�������傭�́A�����҂̋����̂́A�퐪�����̔��W�i�K�ɏƉ��������̂ɕω����Ă�����������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A��Z���Ďx�z�𑱂��Ă����ɂ́A�퐪���҂́i�i�j���W�i�K�Ɍ������������̌`�Ԃ��A������Ƃ�˂Ȃ�Ȃ�����ł���B
�@���Ō�̒i���́A�Q���}���l�ɂ��K���A�����ƃt�����N�������݂��O���ɂ���B���łɃ��[�}�����Ă����K���A�̏Z������A�Q���}���l�i�t�����N���j�����҂́A���e����ƃ��[�}�I���{���w�сA���[�}�鍑�ɕ���Ď��������̋����́i�x�z�g�D�j��Ґ����悤�Ƃ������A�����҂̋����̂́A�������傭�́A�i���[�}�ł͂Ȃ��j�K���A�̔��W�i�K�ɋK��i�����Â��j���ꂴ��������A���[�}�鍑���ċ����悤�Ƃ����J�[�����̎��݂͎��s�����i�R�����ɕ����j�B
�@���̏ꍇ�A�K���A�̓��[�}�����A�z�ꐧ�̔��W�i�K�͒Ⴂ�ɂ�������炸�A�������ւ̔��W�ɂ����ẮA���[�}�����L���ȏ����������Ă����A�Ƃ������ƂɂȂ�B�܂�A���[�}�ƃK���A�̈Ⴂ�́A�P����̒i�K�̐��ł͂Ȃ��A�^�C�v�I���Ⴞ�A�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@
�@�y29�z�u�{�_�O�Q�v�\�\��H���A���Y�͂Ə��l
�u��H���Ƌ����ɂ����ẮA
�@���X�̔퐧�A���X�̈�ʐ�
���l�̂��ׂĂ̐����������́A��̍ł��P���Ȍ`�ԁA���I���L�ƘJ���ɁA�Z������Ă��܂��Ă���B�ݕ��ɂ���āA�ǂ�����`�Ԃ��A����ǂ��납������̂��̂��A���l�ɂƂ������R�I�Ȃ��̂ɂ���Ă��܂��Ă���B���������āA�ݕ��̓��ɂ͂��łɁA�]��������͂��ׂāA���̏������̉��ɂ��鏔�l������ł����Ȃ��A���l�Ƃ��Ă̏��l������ł͂Ȃ������A�Ƃ������Ƃ��܈ӂ���Ă���B���̈��̏������́A�~�ς��ꂽ�J�����Ȃ킿���I���L���A����Ƃ������I�J�����\�\�Ƃ�����ɂɊҌ�����Ă��܂��Ă���̂��B�����̈�ɂł������Ȃ�A����͓r�₷��B�ߑ�̌o�ϊw�҂������g�A�Ⴆ�A�V�X�����f�B�A�V�F���r�����G���A���l�̘A�� assiciation des individus �������{�̘A�� association des capitaux �ɑΒu���Ă���B
�@���ʂł́A���l���g�����S�������ɕ����������Ă���A����ɂ���āA�����ȑ��݈ˑ���Ԃɒu����Ă���B���I���L�́A�J���̓����ŘJ���ƌ��������Ă��邤���́A�~�ς̕K�v���Ƃ��Č�������甭�W���A�����͂Ȃ��ǂ��炩�Ƃ��������� Gemeinwesen �̌`�Ԃ������Ă��邪�A�������������������������W����ɂ�A�܂��܂����I���L�̋ߑ�I�`�Ԃɋ߂Â��B�����ɂ���āA���łɍŏ�����J���������A�p��ƍޗ��̕������^������A����ɂ���āA�~�ς��ꂽ���{�́A��X�����L�҂ւ̕���A����ɂ���Ď��{�ƘJ���Ƃ̕���A��������L���̂��̂̎�X�̌`�Ԃ��^������Ă���B����������ɐi�݁A�~�ς�����ɑ��傷��ɂ�A���̕��������ɐ�s������B�J�����̂��̂��A���̕����O��Ƃ��Ă̂ݑ���������̂ł���B���v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,pp.192-194.
�����F���̈��p�S�̂ɁA�͏o�ł̌������Q�Ƃ��Ď����ꂽ�B
�@�u�]��������͂��ׂāA���̏������̉��ɂ��鏔�l������ł����Ȃ��A���l�Ƃ��Ă̏��l������ł͂Ȃ������v�\�\���{��`�Љ���A����ȑO�̎Љ���A�ݕ����x�z���Ă������A�u���l�Ƃ��Ă̏��l������v�͂��肦�Ȃ��B�Ƃ����Ӗ��B
�u�������āA�����ɓ�̎�����������B���ɁA���Y���͂����l�������剝�����ꂽ�܂������Ɨ��̂��̂Ƃ��āA���l�ƕ��ԓƎ��̐��E�Ƃ��āA������B���̂��Ƃ̍���ɂ���̂́A���l�̏��͂��������Y���͂ł���̂ɁA�ނ�͕��đ��ݑΗ��̒��Ő������Ă��邱�ƁA�Ƃ��낪�����A���̏��͔͂ނ������ƘA�ւ̒��ł��������I�ȗ͂Ƃ͂Ȃ�Ȃ����ƁA�����������Ԃł���B
�@�������āA����̑��ɂ͐��Y���͂̈ꑍ�� eine Totalität �������A���Y���͂��������� gleichsam ���ۓI�Ȏp eine sachliche Gestalt ��g�ɑттĂ��� angenommen haben�A���l�̑����炷�����͂��͂⏔�l�̗͂ł͂Ȃ��A���I���L�̏��͂ł���B����䂦�A���ꂪ���l�̏��͂ł���̂́A���l�����I���L�҂ł������ɂ����Ăł���B�ȑO�̂ǂ̎���ɂ��A���Y���͂����l�Ƃ��Ă̏��l������ɂƂ��Ăǂ��ł������悤�ȁA����Ȏp���������Ƃ͂Ȃ��B����́A�ނ��������̂��̂��܂��nj����ꂽ���� ein bornierter ����������ł���B��
�@�����̑��ɂ́A���̂悤�Ȑ��Y���͂ƌ��������킹�ɏ��l�̑命���������A���̏��͂��ނ炩�������������Ă��邽�߂ɔނ�͈�̌����I�Ȑ������e��D���A���ۓI�ȏ��l�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B�������A�܂��ɂ��̂��Ƃɂ���āA�ނ�͍��⏉�߂āA���l�Ƃ��đ��݂Ɍ����W�ɓ��邱�Ƃ��ł��闧��ɗ������ꂽ�̂ł���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,pp.195-196.
�����F���̒i���̂݁A�͏o�ł̌������Q�Ƃ��ĉ���Bborniert: ���ȁA���ʂȁA����̋����B
�@�A����́A�����O�̃N�_���ł͊낤���������A���̕����ł͂����ւm�ŁA�������肵�Ă���B�����������e�\�\���ۉ��_�\�\�ɁA���̊S���W�����Ă��邩�炾�낤�B

�@�u���ۉ��v�ݏo���Ă��鎖�ԂƂ́H�F�u���ۉ��v�́u����ɂ���̂́A���l�̏��͂��������Y���͂ł���̂ɁA�ނ�͕��đ��ݑΗ��̒��Ő������Ă��邱�ƁA�Ƃ��낪�����A���̏��͔͂ނ������ƘA�ւ̒��ł��������I�ȗ͂Ƃ͂Ȃ�Ȃ����ƁA�����������Ԃł���v�\�\�\�\
�@�u���Y�� Produktivkräfte�v�Ƃ́A�u���l�̏��� Kräfte der Individuen�v�ɂق��Ȃ�Ȃ��i�Ƃ����Ă��A�o���o���Ȍl�̂��ꂼ��̗͂̑��a�d�Ȃ̂ł͂Ȃ��A���l�̋��� Zusammenwirken �\�\�܂Ƃ܂������������ł���A�i�[�L�[�ɘA�ւ������������ł���\�\�ɂ���Đ�����E����Ɍ����������́j�B���������āA���R�̂��ƂȂ���A�u���Y�́v���Ȃ킿�u���l�� Kräfte�v�́A���l�́u����ƘA�ւ̒��ł����v���������Ȃ��B�Ƃ��낪�A���́u����ƘA�ցv�́A�����ݑΗ����������l�ɂ���āA�A�i�[�L�[�ɐ��s�����B����ł��A�����͂́A�����������݂ɐ��ݏo����邵�A���ɁA���x�Ȑ����̐��Y��������������o�����Ă���̂����A���̓������������������A���ǂ��ς�邩�\�z���������悤�Ȃ��̂ł��邵�A���l���g�ɂƂ��ẮA�܂�����������̎��R�ɂ͂Ȃ�Ȃ��A������Ƃ͕ʌ̋���ȁg�������́h�ɂ��������Ȃ��B
�@���҂�́A���{��`�̂��Ƃł́E�����������ۉ��̍V�g�ɊS���W�������Ă��邯��ǂ��A�����������Ԃ́A�v�����ȑO�̎Љ�ɂ����Ă����݂������̂ł���B���̏ꍇ�ɏd�v�Ȃ̂́A���́g���l�������́h�̑��݂Ƃӂ�܂����A�l�Ԃ����ɑ����s���R�t�̂ӂ�܂��ɂ悭���Ă��邱�Ƃł���B���́g���ۉ��������́h���A�l�тƂ́A����ꍇ�ɂ́g�����h�Ƃ��āA����ꍇ�ɂ͏@���I�Ȍ`�ۂƂ��Ĕc�������낤����ǂ��A�ނ�ɂƂ��ẮA����珔�͂́A�s���R�t�̈З͂Ƒ���������̂ł������B
�@���@�����āA���{��`���̏ꍇ�Ƃ������̂́A�l�тƂ́i�e�X�̗���ɉ����ĈقȂ���x�Łj�����ꏭ�Ȃ���A���́g���ۉ������́h���A���������ɂȂ�����̂Ƃ��Ċ����A���̓��Ɉ��S���� Gemütlichkeit �����o�����Ƃ��ł����_�ł���B��_�Ɩ��A�V�s�̖��A�Ƃ������g�����Ă����������h�����a�O���ꂽ�W�c�قǁA����͌����ł������B����䂦�ɂ����A�ނ�̒���|�\�́A�l�X�𖣗������̂��B
�@�g�_�Ƃ͐l�Ԏ��g�ł���h�g�����Ƃ́A�Љ�Ƃ͐l�Ԏ��g�ł���h�Ƃ����A�t�H�C�G���o�b�n���V���e�B���i�[�̖��肪�A�}���N�X/�G���Q���X�̂��̋c�_�̔w��ɋ����Ă���B
�@�l�тƂ́A�u��̌����I�Ȑ������e��D���A���ۓI�ȏ��l�ɂȂ��Ă��܂��v�����A�u�܂��ɂ��̂��Ƃɂ���āA�ނ�͍��⏉�߂āA���l�Ƃ��đ��݂Ɍ����W�ɓ��邱�Ƃ��ł��闧��ɗ������ꂽ�̂ł���B�v�\�\�\�\���Y��i�̐�L����r������A�g��d�����R�h�ɂȂ����������ŁA�����̂̑��������������ꂽ�A�����V���Ȍ����̉\�����l�������c�c�Ƃ������Ƃ������Ă���̂��H
�u�k���̎����B�l���l�����Y���͂���єނ玩�g�̐����Ƃ��낤���Ċւ���ۂ��Ă���B��̘A�ցA���Ȃ킿�J�����A�ނ�̑��ł����Ȋ����̋P�������Ƃ��Ƃ������Ă��܂��A�J���͂����ނ�̐�����s���ɂ����邱�Ƃɂ���Ĕނ�̐������x���邾���ɂȂ�B�ȑO�̂ǂ̎���ł����Ȋ����ƕ����I�Ȑ��̑n�o�Ƃ͕������Ă������A����͑o�����ʁX�̐l���Ɋ���U���Ă������Ƃɂ��̂ł����āA�����I�Ȑ��̑n�o�k���Ȃ킿�L�`�̘J���l�͂܂��\�\���l���g�̋nj����̂��߁\�\���x�͒Ⴂ���������Ȋ����Ƃ݂Ȃ��ꂽ�B����ɑ��č����ł́A�������������I�Ȑ����ړI�Ƃ��Č����A���̕����I�Ȑ��̑n�o�A���Ȃ킿�J���i���ꂪ�����ł͗B��\�ȁA��������ꂪ�����悤�ɔے�I�ȁA���Ȋ����̌`�ԂȂ̂ł���j����i�Ƃ��Č�����قǂɁA���Ȋ����ƕ����I�Ȑ��̑n�o�Ƃ͗��ꗣ��ɂȂ��Ă���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,pp.196-197.
�@�ߑ�ȑO�ɂ́A�i�{���́u���Ȋ����v�ɋ߂��j�u�����I���̑n�o�v�����Y�������F�ړI
�@���{��`�̉��ł́A�@�@�@�u�����I�Ȑ��v�F�ړI
�@�@�@�u�����I���̑n�o�v���i�]���I�j�J���F��i�B
�@�܂��A���̃N�_������A�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�̎��_�ł́A�u�J���v�Ƃ������t���A�l�Ԃ̓���������ʁA���Y������ʁi�������̓w�X�ɕ���āu(����)�����v�ƌĂ�ł���j�ł͂Ȃ��A���̓���̈ꕔ���w���Ďg���Ă��邱�Ƃ��킩��B�����炭�A�ٗp�J���Ȃ����]���J���̈Ӗ��Ŏg���Ă���B
�@������A�u�J���̔p�~�v�Ƃ́A�]���J����p�~����Ƃ����Ӗ��B
�@�V���e�B���i�[�́w�B��҂Ƃ��̏��L�x�̂Ȃ��ŁA
�u�����́A�J���̓z�ꐧ�ɂ��ƂÂ��Ă���B�J�������R�ɂȂ�A���̂Ƃ��A���������ł���B�v
�@�Əq�ׂĂ����B�}���N�X/�G���Q���X�́A����ɔ��_���āA�u�J���v�������̂�������Y��i������u���R�v�ɂȂ邱�Ƃ������A�u���W���A�������x�����Ղ��A�Ǝ咣�����B������A�܂��Ƃ��ȋc�_������Ȃ�A�ނ�́A�V���e�B���i�[�̌����u���R�v�̈Ӗ�����ɂ��ׂ��������B�Ƃ��낪�}���N�X/�G���Q���X�́A�u�J���v�����R�ɂȂ��Ă������͏��ł��Ȃ��B�u�J���v�����ł��Ȃ���������͏��ł��Ȃ��B����A�_���K�R�ł͂Ȃ����A�Ǝ咣�����̂��B
�@�V���e�B���i�[���u�J���v���ǂ�ȈӖ��ŗp���Ă������͂킩��Ȃ��B�]���J���Ɍ��炸�A��H�Ɛe����Ɨ��_���̘J���i�܂�u���R�v�ȘJ���j�܂Ŋ܂�ł�����������Ȃ��B�������A�}���N�X/�G���Q���X�́A���̂悤�Ȍ`���_���I�Ȗ����Ȕ��_���������ʂƂ��āA�����ł́u�J���v�̈Ӗ�������������������Ȃ��Ȃ��Ă���B�i�w�A������W�x,��11��,pp.361-362.�j
�@�u���R�v�̈Ӗ�������Ȃ��������Ƃ́A�ނ�̖����Љ�̍\�z�ɉe�𗎂Ƃ����ƂɂȂ��Ă��܂����B�u���R�v�̈Ӗ������I�ɖ���邱�Ƃ��Ȃ����߂ɁA�Љ��`�����⋤�Y��`�Љ�ɂ����āA�ǂ̂悤�Ɂu���R�v���m�ۂ��A�u�����v�̈ێ��Ɨ��������Ă䂭�̂��A�Ƃ����ϓ_�������邱�ƂɂȂ����B�u�����v�ȎЉ�Ґ��Ɨ���������x�ł̂݁u���R�v�̗]�n���F�߂��A����ɂ���Ďa��̂Ă��镔���́A�u�u���W���A�I�v�Ȉӎ��`�Ԃł��苤�����z�ɂ����Ȃ��ƌ����čς܂��B�����������Ղ���܂�Ȃ��E���s���{�ʂ̍��\�I�u���R�v�ς���绂��邱�ƂƂȂ����B
 �@
�@
�@�y30�z�f�́\�\����_�Ɣ�_
�@�����͂��łɁA�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�ɂ�����ނ�̌�������A�}���N�X/�G���Q���X���A���Ȃ��Ƃ��l�Ԃ̎Љ�A����ѐl�ԎЉ�̗��j�Ɋւ��ẮA���Ȃ炸��������_���̂��Ă��Ȃ����Ƃ����Ă����B���Ƃ��A{5}d�F
�u�������āA�v�ق̂�ނƂ���A�k�c�l�l�Ԃ����̎��H�I�Ȋ����A���H�I�Ȕ��W�ߒ��̏��q���A�n�܂�B�k�c�l
�@���������q�����A�����I�ȓN�w�́A�����̏�������B����ɑ����ēo�ꂵ����̂́A���������A�l�Ԃ̗��j�I���W�̍l�@���璊�ۂ���邲����ʓI�Ȍ��_�̑������炢�ł����Ȃ��B�������ۂ��ꂽ�����́A����P�Ƃł́A�܂茻���̗��j����藣����ẮA�S�������l�ł���B����͂����A���̐l�X�ɗ��j�̍l�@�̂��߂����j�I�j�������₷�����A�j�����X�̐��w�������Â���֊s��^����̂ɖ𗧂Ă邱�Ƃ��ł��邾���ł���B���ۂ��ꂽ�����́A�������A�N�w�̂悤�ɁA����ɏ]���Η��j�̊e���オ���܂��萷��ł���Ƃ���������Ⳃ�}����^���Ă������̂ł͌����ĂȂ��B
�@�ނ���A�j���̍l�@����ɁA���܂��܂Ȑ��w�̌����I�E�����I�ȘA�ւ̒T���ɁA���肷���������k�c�l�A�����I�ȏ��q�ɒ��肷��A���̏�ʂ��珉�߂č���n�܂�B���̍���������������ƂȂ鏔�O��́A�k�c�l�e����̊e�l�̌����I�����ߒ��Ǝ��H�I�c�ׂƂ��������邱�Ƃ�ʂ��āA���߂Ă��̂����疾�炩�ɂȂ�B�����͂����ŁA��������ۂ��ꂽ�����̎�����o���\�\����������̓C�f�I���M�[�ɑΒu���ėp����\�\�������j�I����ɑ����Đ������邱�Ƃɂ��悤�B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.32-33.
�@�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�̗��j���q�\�\�ނ�̌����u���W�ߒ��v�̏��q�\�\�́A���̂悤�ɑO�u�����āA�J�n�����B����́A�U��Ԃ��Ă݂�u���W�v���Ă������Ƃ��킩��A�Ƃ��������̂��Ƃł����āA�l�ނ́u�@���v�ɂ̂��Ƃ��ĕK���R�I�Ɂu���W�v����Ƃ��A�^����ꂽ���������ɂ���āA�u���W�v�̌o�H�Ƒ��x�����肳���A�ȂǂƂ������Ƃł͂Ȃ��B
�@�������ɁA�ނ炪�A���́u���Y�͎����`�v��Ă����i�K�ł́A�u���W�v�ɉ��l��ǂݍ��݁A�u���W�v�������قǁA�܂��u���W�v�́E���i�i�K�قlj��l�������Ƃ���ϔO�ɐN����Ă������Ƃ́A�ے�ł��Ȃ��B�������A����ɂ��Ă����́u���W�v�́A���l�́u�ӎ��I�v�s�ׁ\�\���Y�����A���̑��u���Ȋ����v�\�\�̏W�ςɂ��̂ł����āA���l�́A���炩�́u�@���v�Ɂg����h����čs������킯�ł͂Ȃ��B�����̂Ȃ��F�����u�@���v�ɂ��������Đi�s���A�����⓮�����u�{�\�v�ɂ��������čs������Ƃ��Ă��A�l�Ԃ����͎���u�ӎ��v�����s���R�t�Ƃ̌������s�Ȃ��A���̌��ʂƂ��āA�l�Ԃ��s���R�t�Ƃ̊W�A����єނ�l�Ԃ̎Љ�Ґ��\�\����������\�\�������Ă䂭�A�Ƃ����̂��A���̒i�K�ł��łɔނ炪�l�����Ă����F���ł������B���̉ߒ����A���ʂƂ��āE����u���W�v�o�H��`���Ă����悤�Ɍ�����Ƃ��Ă��A����͎���I�Ɍ��āE�����Ȃ̂ł����āA�g�_�̐ۗ��h�̂悤�ȁA���邢�̓w�[�Q���́g���E�����h�̂悤�ȁA���炩�́u�@���v�Ɏx�z����Đi��ŗ����킯�ł͂Ȃ��B
�@����ł��A�u����_�v�Ɓu��_�v�́A�����ł��Љ�_��̑傫�Ș_�_�ƂȂ肤��B�A�����ɂ��A�@�q�ϓI�u�@���v���A��l�ЂƂ�̐l�Ԃ̈ꋓ���������肵�Ă��邩�̂悤�ȋɒ[�ȁu����_�v�ƁA�A�l�Ԃ͂��̎�ϓI�ӎv�ɂ���āA�Ȃɂ��Ƃ����Ȃ����邩�̂悤�ȋɒ[�ȁu��_�v�Ƃ������ɂ��A����̐l�X���x�z���Ă��邽�߂ɁA���ɂ̖����́A����܂łɂȂ�����ȗڂ����o�����Ă���B�������A���̗��ɒ[�͂ǂ�����A�Ȋw�����ĂȂ�����Ȏx�z�͂�l�Ԃɗ^���Ă���c�c����̐l�Ԃ������A�����v������ł��邽�߂ɐ����Ă��錻�ۂɂق��Ȃ�Ȃ��B
�u�������[���b�p�̃L���X�g���_�w�ɂ����ẮA����ł͐_�̐�ΓI�E�S��I�Ȏx�z���咣�����B�_�ɂ�邱�ƂȂ����Ă͉����������Ȃ��Ƃ����B���̈Ӗ��ɂ����āA�_�̈ӎu�ɂ��X�����ۂ̑S�ʓI�Ȍ���_�����Ă���B�v
�A���w�}���N�X��`�̒n���x,1969,�������[,p.156.
�@�������A�����Ȃ�ƁA���l�̂ǂ�Ȕƍߍs�ׂ��_�����肵���s�ׂ��Ƃ������ƂɂȂ�A�t�ɁA�ǂ�ȑ������w���I���������悤�Ƃ��A�_�̌���ɂ��������Ă��邾�����A�Ƃ������ƂŐ���������Ă��܂��B�u���̕s�s����������邽�߂ɂ́A���炩�̎d���Ől�Ԃ����R�ӎu�����F����Ȃ���Ȃ�v�Ȃ��Ƃ����W�����}��������B
�@�u���R�Ȃ����ĐӔC�Ȃ��B�v�w���s�ׁA�ƍߍs�ׂɔ��������邽�߂ɂ́A�u�������̍����Ƃ������R�ӎu�A��_���v�������v�ip.157�j
�@�u�ߑ�Ȋw�̗v���v�B���Ƃ��ƁA���_�����ł����n�L���X�g���ł��A�܂��M���V���l�̉^���ςł��A�u�l�Ԃ̉^������߂��Ă���̂͌����ł����āA���̋A���Ɏ���܂ł̉ߒ��͕K��������`�I�ɔ팈��I�Ƃ͌���Ȃ������v�i�A���w�}���N�X��`�̗��H�x,p.226�j�B�������ɁA�A���X�g�e���X�̐����V�̂̉^�s�͈�`�I�O���Ƒ��x�ɂ�邯��ǂ��A����͂܂������u�n��E�Ƃ͒������قɂ���V��E�v�̌��ۂ�����ł������iibid.,p.227�j�B
�u�w�u���C�Y���̌��^�ɂ�����_�Ƃ��̖��Ƃ̊W�́A�k�c�l�q�v�Ɖƒ{�̊W�ɂȂ��炦�āv�������邱�Ƃ��ł���B�r�̌Q�ꂪ�u�s��������͖q�v�ɂ���Ē�߂��Ă���B�������A�r�͓�����H������A�ꎞ�I�ɍs�H�𗣂ꂽ��A���ɂ���Ă͖q�v�̈ӂɔ������肷�邱�Ƃ��\�Ȃ̂ł����āA�k�c�l�����ɂ͉ߒ��I�g���R�h�̗]�n���c����Ă����B�v
�A���w�}���N�X��`�̗��H�x,1974,�������[,p.227.
�@���̂悤�ȌÑ�E�����l�́g�펯�h���傫���ω������̂́A�u�ߑ�Ȋw�̗v���v�ɂ��Ƃ��낪�傫���B
�u���ۂ����@���I�ɐ��N����Ƃ����v�z�́A���̌��^�ɑk��A���z�I�ȗL�ӓI�Ȏ�Ɏ��k�Ⴆ�A�L���X�g���̐_�l�ɂ��x�z�Ƃ����v�z����ϐ��������̂ł��낤�B���̌��^�ɂ����ẮA���N���鎖�ۂ͂��Ƃ��Ƃ����z�I�Ȏ�Ɏ҂̈ӎu�E�v��̎������Ǝv�O�����B�k�c�l�ߑ�I�Ȕ��z�̊m���ɂƂ��Ȃ��āA�L�ӓI�l�i�̎�Ɏ҂���������A���z�I�Ȍv�悪���E�ɓ��݂���@�����ƂȂ�A�����̐��E����A�j�}������������ɋy�сA�@���͒P�Ȃ�"�H��"�ȏ�̂��̂ƂȂ�B�k�c�l
�@�@���͂��͂�P�Ȃ�H���ł͂Ȃ����āA����~�T�C����U������r�[���̂悤�ɁA���ۂ������ɑ����Đi�s����悤�A�k�c�l���炩�̋K��I�ȍ�p���y�ڂ����̂ł��邩�̂悤�ɕ\�ۂ��ꂪ���ł���B�v
�A���w�}���N�X��`�̒n���x,1969,�������[,pp.167-168.
�u�ߑ�Ȋw�͒��z�I�ӎu�̒����I�����k�����ɋC�܂���ȁB�����F���́A�����������Đ_���̊���ɑi����K�v������l�⎖���ɓ��݂���썰�̈ӎu��r�����āA���ۂ�͊w�I�Ȗ@�����ɕ������߂�B�����A���ۂ��K�R�I�Ȗ@�����ɕ����Ă��Ȃ���A�Ȋw�I�T���͖��Ӗ��ɂȂ��Ă��܂��Ǝv�O�����B�k�c�l
�@�k�������A�l���̍ۗ��ӂ��ׂ����Ƃ́A���R�����R�����݂��Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ȋw���̂��̂͌����ďؖ��������킯�ł͂Ȃ��A����͂����܂Ō��� Postulat ���Ƃ������Ƃł���B�v
�A���w�}���N�X��`�̒n���x,1969,�������[,pp.157-158.
�@���Ƃ��A�M�Ɋւ���@���́A���v�I�E�吔�I�ɂ����������Ȃ��B�X�̕��q�̍s���܂ł͗\�����x�z���ł��Ȃ��B
�@�����Ƃ����̏ꍇ�A���_�I�ɂ́A�X�̕��q���͊w�Ɠd���C�̖@���Ɍ����ɏ]���Ă���Ƃ����B�X�̕��q�̈ʒu�⑬�x��\���ł��Ȃ��̂́A���������𐳊m�ɑ���ł��Ȃ����߂ɂ����Ȃ��Ƃ����B
�@����ł��A�f���q���x���̔����ȒP�ʂ̌������i��ł���ƁA�u�s�m�萫�����v����q�̔g�����A�ϑ����̂悤�ȁg�ق���сh�������Ă���B
�@�X�̕��q��f���q����`�I�Ȗ@���ɂ��������Ă���Ƃ����̂́A���߂ɂ����Ȃ��B
�@�͈͂��L���āA�����E�A�n���E�̏����ۂɂȂ�ƁA�g��O�̂Ȃ��@���͂Ȃ��h�ƌ�����قǂł���B�g�@���̎x�z�h�́A�����̎w�j�ł���A�K�v�ȉ���ɂ����Ȃ��B
�u"���V�A�E�}���N�X��`"�́A���̉Ȋw��`�I���z����A����_�ƁA���ʗ��̏��F�Ƃl�����A�w���ʗ������F����ȏ�A�}���N�X��`������_�̗�����Ƃ�͓̂��R�ł���x�Ə̂���B�k�c�l�����đ��ʂł́A�v���I���H�̓����k������`�I�ȁI�l�������Â��悤�Ƃ����k�c�l���ꎩ���Ɋׂ�v
�A���w�}���N�X��`�̒n���x,1969,�������[,p.161.
�@�������A�g���R�Ȋw�I���ʊW�h�ƌ����Ƃ��A���F�\�Ȃ̂́A�u�o�����݂���p���N����v�ł͂Ȃ��A�u�o�����݂��Ȃ���p�͋N���Ȃ��v�u�o�Ȃ���p�Ȃ��v�����ł���B�܂�A�u�K�v�����ł���v�Ƃ������Ƃ������A�u�����v�Ƃ������̂́E�F�߂���B��̂�����ł���B�Ȃ��Ȃ�A���R�E�ł́A�����ЂƂ̌����ɂ���ĕK���R�I�ɋN���錋�ʂƂ������̂͑��݂��Ȃ�����B�����鎖�ۂ́A�����̏����̌��ʂƂ��Đ�����B���ꂪ���R�E�Ƃ������̂ł���B�܂��āA�l�ԎЉ�͡��
�@�u�o�Ȃ�p�v�����藧�̂́A���`�����i�g�[�g���W�[�j�̏ꍇ�����ł���B���ׂĂ̐��w�I����͓��`�����ł��邪�䂦�ɁA���w�ɂ����Ắu�o�Ȃ�p�v�����藧�B
�@����ɐl�ԎЉ�ɂ����Ĉ��ʗ������藧�Ƃ��Ă��A�\�\���͐��藧���Ȃ��B���ԂɁu�l�Ԃ̈ӎu�v���������ꍇ�Ɉ��ʗ���F�߂�@���_�Ȃǂ͑��݂��Ȃ��B����ȋ������l���ōٔ����s�Ȃ�����A���̒��͂߂���߂���ɂȂ��Ă��܂�����ł���\�\���ꂾ���猈��_�I�@�������藧�A�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�@"���V�A�E�}���N�X��`"�́A���̑O�炵�đS���̌�T�̏W�ςł���B
�@�����āA�u���ꎩ���v�Ɋׂ����ނ�u�}���N�X��`�v�ҁ\�\�g���V�A�h�Ƃ͌���Ȃ��\�\�́A�u�q�ϓI�v�Ɓu��̓I�v�Ȃ���̗̂����g�����n�߂�B�ǂ��܂ł��A���s����`�ƕ����_���݂̂��ނ�̐M���ł���B�@
�@
�u�J���g�́A�X�l�����R�ӎv�ɂ��ƂÂ��s�ׂł����Ă��A�����S�̓I���v�I�ɂ݂�Γ��v�I�K�R���ɏ]���Ă���Ƃ����v�z�������͂₭�ł��o���Ă���v
�A���w�}���N�X��`�̒n���x,1969,�������[,p.163.
�@�J���g�́A�u�����A�o�Y�A���S�v�̐��̑����ɂ��āA�u�����̌��ۂ��K�����������ݕ������Ă��邱�Ƃ�������B�v�u�ӎu�̌��ہA���Ȃ킿�l�Ԃ̍s�ׂ́A���̂����鎩�R���ۂƓ��l�A���ՓI�Ȗ@���ɂ���ċK�肳��Ă���B�v�ƌ��i�w���E�����̌��n�ɂ������ʗ��j�̍l�@�x�j�B�A�����́A������A���v�͊w��ʎq�͊w�́u���v�I�K�R���v�Ɠ��l�̖@�����x�z���邩�̂悤�Ɍ����̂����A����������g�ł͂Ȃ����B���q��f���q�͈ӎu�������Ȃ����A�������ۂ͔����\�����A���j���ۂ͂����ł͂Ȃ�����ł���B
�@�������A����ȏ�ɒ��ӂ��ׂ��_�́A�X�l�́A�o�������グ�悤�Ƃ��Č����A�o�Y����킯�ł͂Ȃ����i�����������I�ɒNj����邱�Ƃ͂����Ă��A�Ӑ}����������Ƃ͌���Ȃ��j�A�X�l�̈ӎ�����ړI�ƁA���v�I�Ɋώ@�����g�X���h�Ƃ́A�܂����������͂Ȃꂽ���̂ł���A�Ƃ����������B
�@�܂��A�J���g�������̂Ƃ͈���āA���������Ɋώ@�����̂́A�u�@���v�Ƃ������A���������ςȁu�X���v�ł��낤�B�����@���̂悤�ɁA�����̏o�����̐��l��\�����邱�ƂȂǂ͕s�\�ł���B
�@�Ƃ������A�h�C�c�E�C�f�I���[�O�̌����́A�ɒ[�������B�V�F�����O�ɂȂ�ƁA���̂悤�Ɍ����i�w�l�ԓI���R�̖{���x�j�F
�u�w�m�I���݂́A���ꎩ�g�̓��I���R�{���ɏ]���Ă̂ݍs�ׂ��邱�Ƃ��ł���B�k�c�l��ΓI�K�R���݂̂��A�܂���ΓI���R�ł���B�Ȃ��Ȃ�A���Ȏ��g�̖{���̏��@���ɏ]���Ă̂ݍs�ׂ��A���Ȃ̓��O���킸�A���̂����Ȃ���̂ɂ���Ă����肳��Ȃ����̂����A���R������ł���B�k�c�l
�@���I�K�R�����Ƃ���Ȃ��������R�Ȃ̂ł���A�k�c�l�K�R�����R�́A��̖{���Ƃ��ėZ������B�x�v
�A���w�}���N�X��`�̒n���x,1969,�������[,pp.163-164.
�@���́u���I�{���v�u���I�K�R���v�́A�w�[�Q���ɂȂ�ƁA�u��Η��O�v�Ƃ����A�l�̊O�ɂ���q�ϓI�Ȏ��̂ƂȂ�B�����āA�u��������Η��O�ɑS���K�肳��Ă���̂��Ƃ������Ƃ�m��̂��l�Ԃ̍ō��̎������k���R�l�ł���v�Ƃ���B
�@�����A�w�[�Q���̏ꍇ�ɂ́A�u��Η��O�v�u���E���_�v�́A�X�l���ǂ�ȈӐ}�������čs�ׂ��邩�Ɋւ�炸�A���l�S�̂ɂ���Ď��Ȃ��ѓO����i�u�������q�v�j�B�������ɁA�J���g�����łɁA�e�l���u�����̈Ӑ}�𐋍s���悤�Ɠw�߂邱�Ƃɂ���āA�c�c�ގ��g�̒m��Ȃ��E���R�̈Ӑ}�𑣐i����v���ƂɂȂ�ƌ����Ă����B
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
�u�w�������q���ǂ������_�ɂ��邩�Ƃ����x�w�[�Q������������Ă����w�k�c�l�_�͂��܂��܂̓���Ȍ����S�������Ă���l�тƂ��D������ɂ����Ă����B�������A���̌��ʂƂ��Đ����Ă�����̂͐_�̈Ӑ}�̎����ł����āA����͐_����i�Ƃ��ėp���Ă���l�тƂ��Nj����Ă������̂Ƃ͑S���ʂ̂��̂ł���x
�@���̐��E�����̈Ӑ}��Ύ��I�ɒm��A��Η��O�ɑS��I�ɋK�肳��Ă��邱�Ƃ�m��̂��A�l�Ԃ̍ō��̎������ł���A�k�c�l�_�ւ̒m�I���ɂق��Ȃ�Ȃ��B�K�R���̓��@�����R���Ƃ����w�[�Q���̎v�z�́A���̂悤�ȓ��������B�k�c�l
�@�ʓI��̂�"���R�s��"�\�\�k�c�l���̌ʓI�Ȏ��ہA�k�c�l���R�I�ȏ����ۂ��S�̂Ƃ��Ă͑�@�����ѓO�����߂�Ƃ������z�ł���B
�@�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�����Ƃ����l�Ԃ̍s�ׂ��͂Ȃ�ĕ��������ȉ^������킯�ł͂Ȃ��B�k�c�l"���ʓI"�K��W�����������邽�߂ɂ́A�l�Ԃ̈ӎ��I�ȍs�ׂ��k�ɂ���āH�l�}���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂������A�w�l�Ԃ̈ӎu�s�ׂȂ����Ă͉��������N���Ȃ��x�B�k�c�l
�@�k�������A�l�l�тƂ�"�K�����i"�ȉ��Ŕ��邱�Ƃ��A"�K�����i"�ȏ�Ŕ������Ƃ��ł���B���̌���A�l�тƂ̔����s�ׂ́A�����W�Ǝ����@���ɂ���Ĉꗥ�ɗ�O�Ȃ��x�z����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�k�c�l�e���^���̖@���ȂǂƂ͌���I�ɈقȂ�B�����@�����������x�z����Ƃ����Ă��A�k�c�l�W�����ۂƂ��Ă̔������i���A�S�̂Ƃ��Č��ʓI�E���v�I�ɂ́A"�����@��"�ɂ��Ȃ��Ă���Ƃ��������ł���B�k�c�l�����@�����ѓO�����悤�ƈӎu����l�͑��݂��Ȃ��B�k�c�l�e�l�̈ӎ����e��ڕW�́A�����W�ƒ��ړI�ȊW�������Ă��Ȃ��B�k�c�l������̂̍s�ׂ͎����@���ɑ��āA�k�c�l���R�I�ł���B�k�c����ǂ��납�l�����@�������������邽�߂ɂ́A�������P��"���R�I"�ł���ɂƂǂ܂炸"���R"�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�k�c�l
�@�E�̎����@���ɂ݂��鎖��͗��j�@���̊ѓO�l����ʂɐ��y���邱�Ƃ��ł��悤�B�����āA����𐄋y����Ƃ��A���j�@����"�K�R��"�Ə��l��"���R�s��"�Ƃ̊Ԃɂ́A�w�[�Q���̂����w�������q�x���霂��炵�߂���̂��Ȃ��ł��낤���H
�@�k�c�l�l�тƂ́A�e�l�̖{���ɏ]���āA���܂��܂ȊS���M�������Ċ������A"�D������"�ɐU�������Ƃ�ʂ��āA�S�̓I�E���ʓI�ɁA�����̖ړI���������Ă����̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�G���Q���X�͂����B�w�Љ�̗��j�ɂ����ẮA�s�҂́c�c���̖ڕW���߂����Ċ������Ă���l�Ԃł���B�c�c�������A���̍s�ׂ��猻���ɋA�����鐬�ʂ́A�ӗ|����Ă������̂ł͂Ȃ��c�c�k�c�l�~������Ă������̂Ƃ͂��悻�قȂ������̂ł���B�k�c�l�x
�@�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�G���Q���X�͑����Ă����B�w�k�c�l���j�I�ɍs�ׂ��Ă���l�Ԃ́A�\�ʏ�́A�����Ă܂������̍쓮���Ă��铮���́A�����ė��j�I�o�����̋��ɓI�Ȍ����ł͂Ȃ����ƁA���̓����̔w��ɁA�ʂ̉��͂��������Ă���̂ł����āA�����T�����ׂ����Ƃ��������k�c�l�x�v
�A���w�}���N�X��`�̒n���x,1969,�������[,pp.165-166,170-172,174.
�@�u�K�����i�v�\�\�ύt���i�̂��Ƃ��낤�B�ύt���i���������锄���A��������������̂��Ƃ��q�ׂ��Ă��邪�A���ꂼ��̎���i�ɂ𑁂��͂���K�v������Ȃǁj��헪�������Ă̂��Ƃ��낤�B�������A���������s�����S�̂̎����ɑ��Ă͝����v���ƂȂ��āA�킸���ȝ������S�̂̓�����傫�����E���邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����H �������A����͈Ӑ}���Đ��������邱�Ƃ��ł���悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B
�@�����@���̂Ƃ炦�����A���܂�ɂ��P���Ō�����`�I���B
�@���j��ʂɂ��Ă����l�Ɍ����邾�낤�B�u�������q�v�ƌ������A�u�������q�v���g���s�h����ꍇ�����X����悤�Ɏv���B�˂Ɂu�@���v�ǂ���ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��B����A�u�@���v�́u�ѓO�v���Ȃ����Ƃ���Ԃ��ƍl����ׂ��ł͂Ȃ����H �܂��A�u�@���v���̂��A����ȂɒP���Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���܂��܂ȗv���̉e�����āA���ʂ͑傫���قȂ������̂ɂȂ�B
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@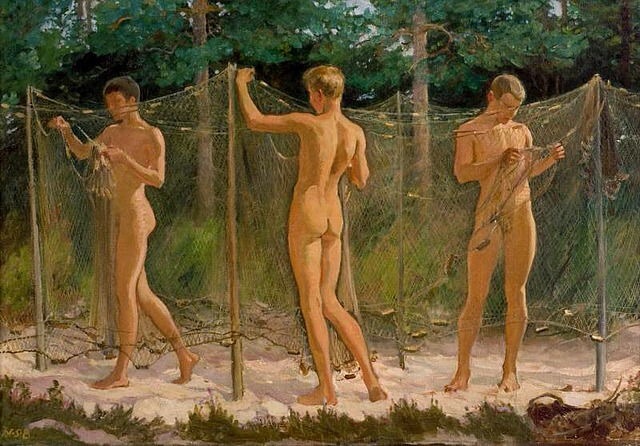


 �@
�@

 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
 �c
�c