04/20の日記
03:31
【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(7)
---------------
.
こんばんは。(º.-)☆ノ
【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(6)からのつづきです。
おもに①のテクストを使用し、場合によって②で補います:
①⇒ ジャン・コクトー,山上昌子・訳『白書』,1994,求龍堂.
②⇒ ジャン・コクトー,江口清・訳「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,1999,国書刊行会,pp.33-59.
【13】婚約者の弟
「恐ろしいほどの孤独の中でも、私は教会に戻ろうとは思わなかった。〔…〕
後は結婚という手段が残っていた。〔…〕
私はソルボンヌ大学で、ド・S嬢と知り合いになっていた。ボーイッシュなところが気に入り、もし結婚せねばならぬとしたら、他の誰よりこの人がよい、としばしば考えたものだった。私は彼女と再び付き合い始め、彼女が母親と暮らしているオートゥイユ★の家を頻繁に訪れた。〔…〕私たちは難なく婚約した。」
山上昌子・訳『白書』,pp.95-97.
★「オートゥイユ」:パリ西部、ブーローニュ森とセーヌ川にはさまれた高級住宅地。「ド」という貴族の血統を表す苗字と相俟って、良家の娘であることがわかる。
ところが、ちょうどその時、ロンドンのカレッジに留学していた彼女の弟が、卒業して戻って来ます。コクトーがソルボンヌで姉と知り合った頃は、ずっとカレッジの学寮にいたので、コクトーとは初対面でした。
「いつも同じさだめをさまざまな外観でごまかす運命、その新たな悪戯(いたずら)を、私はなぜ見破れなかったのか。姉のうちに私が愛していた点が、弟には燦然と、あまりにも鮮やかな形で認められた。一目で私は悲劇を悟り、穏健な暮らしはこの先も私に許されることはないのだと理解した。間もなくわかったことだが、イギリスの学校で事情には通じていた★この弟の方でも、私に会った時、正真正銘の一目惚れで恋に落ちていたのである。この青年は自分自身を熱愛していた。私を愛することで、彼は自分を裏切っているのだ。私たちは人に隠れて会い、こうして避け難い事態に立ち至った。」
山上昌子・訳『白書』,pp.97-99.
★「イギリスの学校で事情には通じていた」:イギリスでも、男子校の寮を中心に《同性愛》が事実上許容されていた。チューリング、E・M・フォースター、オーデン等は、このゲイ文化から輩出している。
コクトーが弟と内密に関係するようになると、彼らの「家の空気は悪意の電気を帯びた」。姉のほうでは、二人の関係にまったく気づいていなかったので、険悪なふんいきの理由がわからず、かえって不安になりました。
「ついには、彼女の弟が私に寄せた愛は激しい情念に変わった。この情念の裏には、あるいは、秘めた破壊欲があったのだろうか。彼は姉を憎んでいた。約束〔婚約〕を取り消してほしい。結婚はやめてほしいと私に懇願するのだった。私はできる限りブレーキをかけた。〔…〕それは破局を遅らせたにすぎなかった。
ある晩、姉の方を訪ねていくと、ドア越しに泣きうめく声が聞えた。哀れな娘は口にハンカチを押し込み、髪を乱して床に伏していた。その前に立って弟がわめていていた。『あの人はぼくのものだ! ぼくのもの、ぼくのものなんだよ! 意気地〔いくじ〕がなくて姉さんに言えずにいるんだから、代わりにぼくがお知らせする!』
こんな光景には耐えられなかった。彼の声も目付きもあまりに冷酷だったので、私はその顔を殴った。『こんなことをして、永久に後悔するといい』と叫ぶと、彼は部屋に閉じこもった。
犠牲になった娘を正気づかせようと介抱していると、銃声が聞こえた。私は大急ぎで駆けつけた。部屋のドアを開けた。手遅れだった。姿見のついた洋服ダンスのところで、彼は床に倒れていた。鏡には顔の高さに、唇を押し当てた跡と、息で曇った霧がまだ見えた。」
山上昌子・訳『白書』,pp.99-102.
愛情の対象である「私」から邪険な拒絶を受けた「弟」は、自死というよりも自分自身と“心中”したのでしょう。
ナルシズムと《同性愛》の関係は、私にはいまひとつよくわからないのです。ナルシズム(ナルシシズム)は、「うぬぼれ」や自己中心主義、エゴイズムと同一視されることが多く、コクトーの表現のはしばしにも、それがうかがえます。しかし、性的意味でのナルシズムは、エゴイズム、利己主義、自信過剰などとはまったく別のことです。ナルシストでない利己主義者は、いくらでもいます。他者への共感に欠けないナルシストも、決して少なくはない。“ナルシストだからエゴイストだ”、という推論は、偏見にすぎません。
しかし、ナルシズムと《同性愛》のあいだには、深いつながりが――生理的にも?――あるかもしれません、《同性愛者》は、同性の相手に対して、自分と同じものを求めるからです。あるいは、自分が相手と同じになろうとします。
この章のコクトーの試みと、それがもたらした結果について言えば、‥自分で“ふたまた”をかけたんだから、こうなって当然じゃないか。突き放して言えば、ただそれだけのことです。
ともかく、結婚と、結婚相手の弟との“愛の追求”は、両立しません。これは、異性愛者で、弟でなく妹の場合でも同じことです。《同性愛》に特有の問題、というわけではありません。
しかし、コクトーは、この体験から、自分は《同性愛者》として社会から拒絶されている――と感じるのです。
【14】最後の“出会い”――最も絶望的な。
「不運と喪とが待ち伏せしているこの世に、もう生きていくことはできなかった。」
山上昌子・訳『白書』,p.102.
こうして「私」は、世を捨てて修道院に入ろうと考えはじめます。
「Ⅹ神父に相談したところ、そのような決心は性急にするものではない、戒律は大変厳しいのだし、M修道院で黙想によって信仰の強さを試してみるべきだろうとの答えだった。」
a.a.O.
つまり、いきなり修道士になるのではなく、Ⅹ神父の知り合いの修道院で、さしあたって短期間の入門コースを受けてみてはどうか、ということです。コクトーは、Ⅹ神父が書いてくれた紹介状を持って、M修道院へおもむきます。
「修道院に着いた時は凍えるような寒さだった。雪は溶けて冷たい雨と泥に変わろうとしていた。門番修士が案内につけてくれた修道士の傍で、私は黙って拱廊★を進んでいった。」
a.a.O.
★「拱廊」:きょうろう。アーチ状の側面の続いている廊下。アーケード。

拱 廊
「聖務の時間を尋ねて彼〔案内の修道士〕が答えた時、私はおののいた。私が耳にした声、それは一人の青年の年齢と美について、顔や体よりもっとよく教えてくれる、そんな声だったのである。
彼は頭巾を下ろした。横顔の輪郭が壁にくっきりと浮かび上がっていた。それは、アルフレッドの、Hの、ローズの、ジャンヌの、ダルジュロスの、パ・ド・シャンスの、ギュスターヴの、農家の作男の横顔だった★。
私は気力も失せて、ドン・Z師〔修道院長〕☆の執務室の前に着いた。」
山上昌子・訳『白書』,pp.102-103.
★「アルフレッドの、……の横顔」:これまで読んできた人には明らかだが、この小説の各章で登場した「私」の性愛の相手。
☆「ドン・Z」:「ドン」はスペイン語の敬称。英語のミスターにあたる。
「私」は、この世で生活するかぎりどこへ行っても、そこに気を惹く若い男を見いだし、悲劇と混乱をひきおこすほかはない。修道院とて例外ではない――「私」は、そう悟ったのです。
「『神父様、色々訳あって、その戒律はそれでもまだ、私には甘すぎると思われるのです。〔…〕』」
山上昌子・訳『白書』,p.103.
温かく迎えてくれたZ師に対して、「私」は入門を辞退し、修道院を去って行きます。
「そう、修道院もまた他所(よそ)同様、私を排斥しているのだった。では、私は旅立たねばなるまい。砂漠で燃え尽きる『ペール・ブラン』★、その愛が敬虔な自死である、あの白衣の修道士たちに倣わねばなるまい。しかし神は、人がこんな風に神を愛することまでお許しになるのだろうか。
ともあれ、私は発ち、この本を残していく。もし誰かが見つけたら出版してもらいたい。〔…〕」
山上昌子・訳『白書』,pp.103-104.
★「ペール・ブラン(pères blancs)」:「白衣の神父たち」。フランス人のアルジェリア大司教ラヴィジュリー(Lavigerie, のち枢機卿)によって 1868年に設立された「アフリカ宣教師団」。団員は終身の奉仕を義務づけられ、「現地の人々の言語、衣服、文化を尊重する」趣旨から、白衣(北アフリカの民族服)をユニフォームとしてまとった。ヨーロッパでは、奴隷制に反対する論陣を張った。その伝道は、アルジェリア、チュニジアから、サハラ砂漠を超えてマリ、ウガンダ、中央アフリカ、モザンビークにまで達した。⇒:Wiki 英語版 独語版 仏語版。現在も活動中である⇒:公式HP。
アフリカに伝道に行くことが、どうして「自死」になってしまうのか、首をかしげますがw、‥当時のヨーロッパ人にとっては、ヨーロッパだけが「この世」であったのでしょう。ヨーロッパでの名声を捨ててアラビア方面へ行ったアルチュール・ランボーも、その神話的な遁世のイメージとはうらはらに、現地の商人に騙されて財産を失い、身体も壊してヨーロッパに戻って死亡しています。世界中どこへ移住したって、人びとのなかで生きる人は、人びとのなかで生きるほかないのであって、どこで暮そうと問題を先延ばしにしてゆくだけです。
コクトーの文章は、「私」の結末が宣教師団に入ることであったのか、単なるアフリカ旅行であったのか、あいまいにしていますが、いずれにしろフィクションです。コクトー自身は、この小説を書いたあと 1930年代に、ジュール・ベルヌの『80日間世界一周』に刺激されて世界旅行に出かけ、36年には日本に滞在しています。⇒:Wiki「ジャン・コクトー」#生涯。おフランスからやってきたお偉い芸術家として厚遇され、藤田嗣治らとスモーやカブキを見物し、尾上菊五郎の称賛を受けている。遁世どころじゃありません。
「神の傑作には謎の歯車があるが、その一つを社会は何かの間違いと見なすので、このような人間が生きることを許さないのである。
『今や暗殺者の時』というランボーの福音★に帰依するかわりに、若者たちは、『愛は新たに作り直されるべきだ』という一節☆を記憶に留めた方がよかっただろう。危険な実験。それらが芸術の分野では容認されるのは、世間が芸術など本気にしていないからであって、実生活ではそれらは断罪される。
〔…〕
社会の悪徳が、私が自己を撓(たわ)めぬことを悪徳とする。私は身を退く。フランスでは、カンバセレスの素行とナポレオン法典の長命◆のため、この悪徳〔《同性愛》――ギトン註〕によって徒刑場送りになることはない。しかし私は、大目に見ようという扱いは承服できないのだ。それは、愛と自由に対する私の愛を傷つける。」
山上昌子・訳『白書』,pp.104-105.
★「今や暗殺者の時だ」:アルチュール・ランボー『イリュミナシオン』「陶酔の午前」章の終行。「暗殺者」を、薬物ハシッシュの隠語と解釈するのが一般的。
☆「愛は新たに作り直されるべきだ」:ランボー『地獄の季節』「錯乱Ⅰ」の「地獄の夫」の言葉。
◆「カンバセレスの素行とナポレオン法典の長命」:ナポレオン法典によって法律の近代化・合理化が徹底したので、フランスでは市民革命以後、《同性愛》が処罰されたことはない。カンバセレスは、ナポレオンに重用された政治家・法律家で、ナポレオン法典の起草者の一人。豪勢な暮らしぶりと《同性愛》で知られた。
↑これが、この小説の末尾です。まず、援用されているランボーの詩句から見ていきましょう。

「陶酔の午前」を、はしょって引用しますと:
「 陶酔の午前
おお わが善! おお わが美! すさまじいまでのファンファーレ! そのなかでも私はよろめいたりはしない。夢幻的なる拷問台! 前代未聞の仕業とすばらしい肉体に、はじめてながら、万歳だ!〔…〕この毒は私たちの血管の隅々にまで残るだろう。おお今やこの拷問にこれほどまでにふさわしい私たち! 創り出された私たちの肉体と魂とになされたこの超人的な約束を、熱烈に搔き集めよう。この約束、この錯乱を! 優雅、科学、そして暴力! 私たちは約束されているのだ。自分たちのきわめて純粋な愛をたずさえて来るために、善悪の木を闇に葬り、横暴なまでの正直さを追放してもらうことを。〔…〕
ささやかな陶酔の一夜よ、聖なるかな! たとえそれが、おまえによって私たちに授けられた仮面のためだけのものであったとしても、私たちはおまえを肯定する、方法よ!〔…〕私たちは毒を信頼するのだ。わたしたちは、いついかなる日にも、自らの生をそっくり捧げることができるのだ。
今こそは暗殺者たちの時だ。」
アルチュール・ランボー,宇佐美斉・訳『ランボー全詩集』,ちくま文庫,1996,pp.333-334.
青字は、訳書の傍点付き文字。
訳者・宇佐美氏の注釈によると、ランボーのハシッシュ体験に基く詩とする解釈が一般的だそうです。「暗殺者たち Assassins」の語源は、アラビア語の「ハシーシュ hashîsh」=ハシッシュ常用者です。ハシッシュ常用者を刺客として使った中世イスラム教の一派「イスマイリ派」の故事によります。「イスマイリ派」は、、誘拐した青年をハシッシュで陶酔させ、陶酔が醒めると、“命令にしたがえば、また陶酔させてやる”と「約束」して、要人の暗殺を命じたと云います。
ランボーの詩のハシッシュ体験は、性愛行為(おそらく《同性愛》)による肉体の快楽を伴っているように読めます。「イスマイリ派」の陶酔も、青年たちにハシッシュを服用した状態でセックスをさせて、至福を味わわせていました。
しかし、コクトーは、この“ハシッシュ常用者の時だ”に「帰依する」ことは勧めないというのです。では、コクトーが勧める・ランボーのもう一つの詩句のほうを参照してみましょう。
「あの人はこう言うのです。『おれは女たちを愛さない。愛というのは新たに創り直すべきものなのだ。あたりまえのことだがね。今や女たちは安定した地位を欲しがることしかできなくなってしまった。地位さえ得られれば、心も美もそっちのけだ。残るのは冷たい軽蔑ばかりで、今日となっては、それが結婚生活の糧というわけだ。さもなければ、このおれならきっといいお仲間になれたであろうような、幸福のしるしを帯びた女たちが、〔…〕非情な荒くれ者ども〔無感動な俗物の夫たち――ギトン註〕に、まっさきに貪り食われる有様を眼にすることになる……』」
アルチュール・ランボー,宇佐美斉・訳『ランボー全詩集』,ちくま文庫,1996,p.271.
つまり、ここで言っているのは、結婚生活によって「愛」は不毛化し、「心も美もそっちのけ」の「冷たい軽蔑ばかり」になってしまうということでしょう。それでは、不毛化する前の本来の「愛」――つねに「新たに創り直」されるべき「愛」――とは、どういうものなのか?‥ここには書かれていません。
そこで、宇佐美氏の注釈にしたがって、『イリュミナシオン』の「おとぎ話」「精霊」章を参照してみます。
「 おとぎ話
ある君主が、これまでありきたりの寛容さにみがきをかけることにのみ、心をくだいてきたことに、気分を害していた。愛の驚くべき変革を予測し、自分の女たちが、天空とか奢侈とかによって味つけされたあのお愛想よりは、もっとましなことができるのではないか、と疑っていたのだ。彼は、真実が見たかった、本質的な欲望と満足の時を、知りたかった。〔…〕
彼を識った女たちは、すべて殺されてしまった。なんという美の楽園の蹂躙であろう!」
アルチュール・ランボー,宇佐美斉・訳『ランボー全詩集』,ちくま文庫,1996,p.321.
青字は、訳書の傍点付き文字。

ドラクロワ「サルダナパル王の死」
敵との決戦に敗北したサルダナパル王は
宮殿に火をかけ奴隷を含む全財産を破壊
することを命ずる。命乞いする妾姫たち
に向ける彼の視線は、自分の財産を眺め
る無表情な眼である。
この「君主」が予感した「愛の驚くべき変革」とは、自分が寝た女はみな殺してしまうことなのです。『千夜一夜物語』の王様のように、自分が寝た女はすぐに殺して、毎日別の女と寝ようとするのです。ところが、新しい女が現れることはなかった。女は、殺されながら「君主」を祝福し、翌晩にはまた生きて現れるのです。
「狩や酒宴のあとで、彼は自分につき従う者を、ことごとく殺戮した。」「高価な珍獣ののどを掻き切って殺しては、楽しんだ。宮殿を炎上させた。人びとに躍りかかっては、ずたずたに切り刻んだ。」
宇佐美斉・訳『ランボー全詩集』,ちくま文庫,p.322.
「君主」は、破壊に次ぐ破壊に狂奔するのですが、そのたびにやはり、“のれんに腕押し”のような結果になります。彼が破壊した物も人も、消滅するけれども消滅しない。依然として同じものが存在しつづける。「群衆や、黄金の屋根や、美しい獣たちは、それでもまだ存在した。」また、彼がどんな残虐を行なおうとも、民衆が不平を言うことはなく、彼を諫めようとする臣下もいなかったのです。
「愛」の、欲望の本質は、破壊なのかもしれません。しかし、かりに破壊を無限に続けることができたとしても、それで人は満足を得ることができるでしょうか?――この・一見荒唐無稽な寓話が問いかけているのは、そのことなのです。
「ある夕べ、彼は誇らかに馬を駆っていた。得もいわれない、打ち明けるのも憚られるほどに美しい、ひとりの精霊が現れた。その顔だちと立居振舞からは、多様で複雑な愛の約束が、言語に絶する、まさに耐えがたいほどの幸福の約束が、浮かび上がっていた! 君主と精霊とは、おそらく本質的な健全さのうちに、消滅した。これで死ねないなどということが、あっていいものだろうか。それゆえ、彼らは一緒に死んだのである。」
宇佐美斉・訳『ランボー全詩集』,ちくま文庫,pp.322-323.
青字は、訳書の傍点付き文字。
「精霊」との出会いは、「君主」が飽くなき欲望によって求めていた本質的な愛の対象との出会いを思わせます。
しかし、本質的な愛の対象との結合によって、「君主」自身も、その対象も、即座に消滅してしまいます。論理的には、そうならざるをえない。もしも何かが残ったならば、完全な満足があったとはいえないからです。
完全な「愛」が実現されたときには、人も世界も、即座に消滅してしまうのです。しかし、そのようなことは起こらない。完全な「愛」、本質的な「愛」などというものは、不可能である。
そこで、この“精霊との結合”もやはり、ほかのすべての場合と同じく“のれんに腕押し”の結果に終ります。「君主」も「精霊」も、その時消滅したけれども、やはりそのまま存在した。そして、「君主」は自分の宮殿で高齢になるまで生きてから、ふつうに薨(みまか)った。「精霊」は、どうなったか? 「精霊」とは彼自身のことでした。「君主」である彼自身が「精霊」であったのです。
「高尚な音楽というものが、われわれの欲望には欠如している。」
宇佐美斉・訳『ランボー全詩集』,ちくま文庫,p.323.
つまり、こういうことが言いたいのでしょう。「本質的な愛」「本質的な“出会い”」――そのようなものは、現実には不可能なのだ、と。「高尚な音楽」とは、そうした「本質的なもの」の言い換えです。
つぎに、「精霊」章を参照しましょう。
「 精霊
彼〔=「精霊」――ギトン註〕は愛情であり、現在である。〔…〕彼は愛情であり、未来である。力であり、愛である。激怒と倦怠のなかに立つわれわれは、それらが、嵐の空を、恍惚の旗のはためくなかを通過してゆくのを見る。
彼は愛である。〔…〕驚異的な、思いがけない理性であるような愛だ。そして永遠である。宿命的な資質によって愛される機械だ。〔…〕おお われらの健康の享受、われらの諸能力の躍進、彼への、ただ己れのためにのみわれわれを愛する彼への、われわれの手前勝手な愛情と、そして情熱……
〔…〕そして崇拝が去ってしまうと、鳴りひびく、彼の約束が鳴りひびくのだ――『下がりおれ、そこの迷信ども、古い肉体ども、所帯ども、世代ども、そんな時代こそは崩壊してしまったのだ!』
彼は立ち去ることなく、空から再び降臨することもないだろう。〔…〕罪の贖〔あがな〕いを果たすこともないだろう。なぜなら、彼がいて、彼が愛されていることで、それはすでに成就されているのだから。
〔…〕
彼の目指すところ、彼の意図するところ! 彼の通りすぎたあとから、すべての古い拝跪も労苦も起立させられる。
彼の陽光! 鳴り響いてうごめくいっさいの苦しみの、より強烈な音楽のなかへの解消だ!
〔…〕
おお 彼とわれわれ! 失われた慈愛よりもさらに思いやりに満ちた誇りだ。
おお 世界よ! 新しい不幸をうたう澄んだ歌声よ!
彼はわれわれすべての者を知り、すべての者を愛した。この冬の夜、そのすべを知ろうではないか。〔…〕彼に呼びかけ彼の姿を眼にし、そしてまた彼を送り返すすべを。そしてまた、潮流の下にまで、雪の降り積む荒野の頂きにまで、彼の意図するところ、彼の息、彼の肉体、彼の陽光を追い求めてゆくすべを。」
宇佐美斉・訳『ランボー全詩集』,ちくま文庫,pp.382-384.
青字は、訳書の傍点付き文字。

「精霊」は、キリストのイメージが背景にあるようにも読めます。しかし、『聖書』に書かれたイエス・キリストとは、かなり異なるイメージでしょう。「彼への、ただ己れのためにのみわれわれを愛する彼への、われわれの手前勝手な愛情」「思いやりに満ちた誇り」‥等々の箇所に、「精霊=キリスト」への・ランボーの特異な解釈がうかがわれます。
なにかとても近代的な、合理的・進歩主義的な感じもします。ここに表れたランボーは、ひじょうに健康そのもので、未来を真直ぐに見ているように思われるのです。古い「迷信」や「所帯」や、束縛された「肉体」を、日々脱ぎ捨てつつある・この世界では、「崇拝」も「拝跪」も「労苦」も、神の「降臨」も「贖罪」も、必要がなくなった‥‥
いや‥ランボーは“進歩”を讃美してなどいない。彼は皮肉で書いているのだ。そう言う人もいるかもしれない。たしかに、「宿命的な資質によって愛される機械」「新しい不幸をうたう澄んだ歌声よ!」といった句にはアイロニーが感じられます。しかし、そうしたアイロニーの色も交えながら、ここに描かれた世界は、なんと希望に満ちていることでしょうか。その希望をもたらしているものが、キリストのように降臨する、いや、もはや降臨する必要もなく現在している、われわれの背後からも脇からもすり抜けて過ぎてゆく愛なのです。
見るべきは、このオプティミズムです。「おとぎ話」章で“不可能”とされた真実の「愛」は、すでに存在していて、この世界のすみずみを歩き回っています。
コクトーが、小説の最後で云っていた「愛と自由に対する私の愛」とは、ランボーがオプティミスティックに語った“真実の愛”への希求の、もうひとつの――より現実的で苦渋にみちた――表現なのかもしれません。
ジャン・コクトー『白書』――神と愛の狭間で ――――終り。
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]
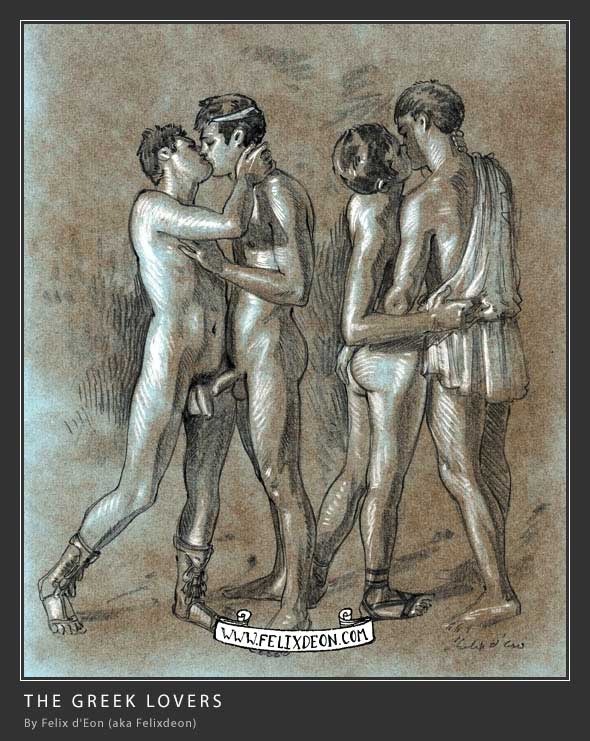
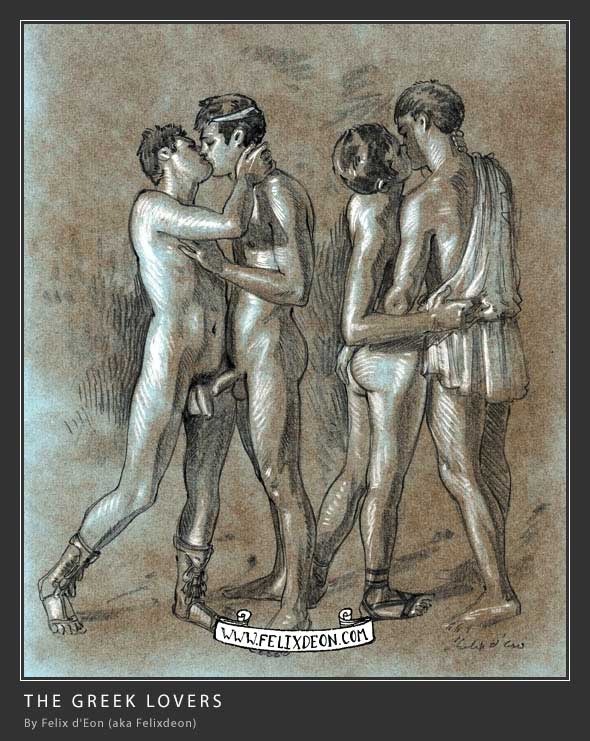
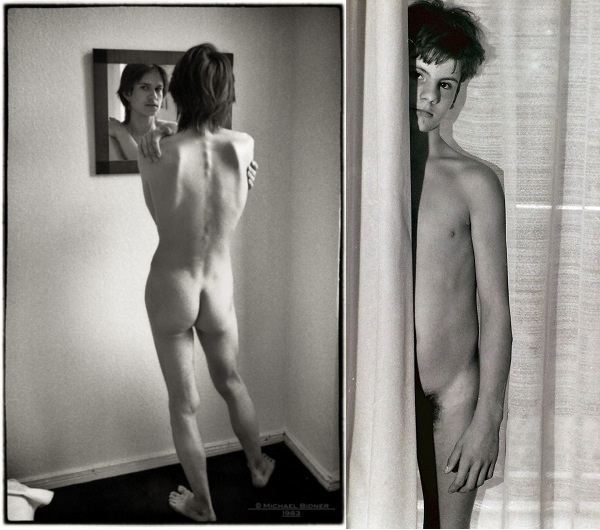


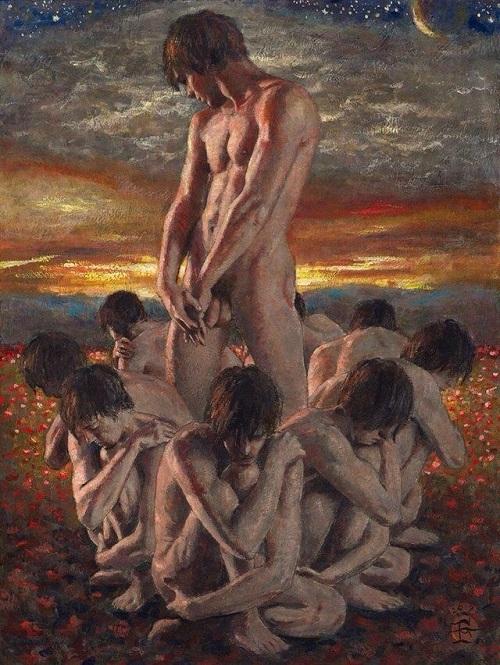







 彡
彡