04/11の日記
04:20
【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(4)
---------------
.

トゥーロン、「航海術の神」像
こんばんは。(º.-)☆ノ
【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(3)からのつづきです。
おもに①のテクストを使用し、場合によって②で補います:
①⇒ ジャン・コクトー,山上昌子・訳『白書』,1994,求龍堂.
②⇒ ジャン・コクトー,江口清・訳「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,1999,国書刊行会,pp.33-59.
【9】Ⅹ神父
「運命はぼくを、新しい生活へと導いた。ぼくは、悪い夢から出てきたのだ。最悪のところに落ち込んで、不健全なぶらつき癖がついてしまっていた。男たちへの愛というものを考えると、これは、女たちへの愛が、逢曳きの家や、歩道での出会いであったのに等しいことなのである。」
江口清・訳「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.48;山上昌子・訳『白書』,p.71.
「不健全なぶらつき癖」と言っているのは、「若いパン屋、肉屋、サイクリスト、電報配達人、アルジェリア歩兵、船乗り、軽業師」など、街角で見かけるあらゆる若い男に「アルフレッド」のおもかげを認めて(江口訳,p.48)、満たされない思いに沈み、幻影を追いかけるようにして街をさまようことだったと思われます。
たしかに、実在しないものを追いかけ続けることに「健全」さは認められないでしょう。しかし、当時の同性愛者にとって、そこから脱して、いったいどんな「健全」な「男への愛」がありえたでしょうか?
けっきょくコクトーは、宗教の導きのもとに「最悪のところ」からの脱出口として、同性愛を断って異性愛に向かうべく努めることになります。もちろんそれは一時的な気休めにしかならないのですが、この章は、そうした一時的な寄り道、コクトー自身のつもりでは“正道”へと向かったわずかな時期だった――ということになります。
「私はⅩ神父を知っており、尊敬していた。この人の軽やかさは奇跡のようだった。彼は至るところで重いことがらを軽くしていた。私の私生活については何も知らなかったが、ただ、私が不幸だということを感じ取っていた。彼は私に話をして力づけ、カトリックの優れて聡明で高邁な人々に紹介してくれた。
〔…〕清らかな人々と交際して、どの人の顔にも大いなる平安の色を認め、神を信じない者の愚かさを知った私は、神への道を辿った。
確かに教義は、官能の行く手を阻むまいという私の決心とは折り合いがつかなかった。しかし、このところの暮らしから私に残ったのは苦い思いと飽き果てた気持ちだったので、それこそこれまでの道の方が間違いだった証拠だと、そんな考えに私は飛びついたのだ。極悪の酒の後に飲んだこれほどの水、これほどのミルクは、私に清澄な純白の未来を見せてくれた。
ためらいを覚えると、ジャンヌとローズのことを思い出してそれを払いのけた。普通の恋愛が無理というわけではない、と私は考えた。家庭を築き、正道に戻ることを妨げるものは何もない。結局のところ、私が自分の性向に屈してしまうのは努力を厭(いと)うからではないのか。努力なくしては、立派なものは何も存在しえない。私は悪魔と戦おう。そしてきっと勝ってみせる。
なんと崇高なる時期! 教会が私を優しく揺すってくれていた。私は懐〔ふところ〕深い家庭の養子だという気がした。」
山上昌子・訳『白書』,pp.71-73.
「コルク栓が水面に浮かび上がるように、私は天に昇っていった。ミサでは、〔…〕私は聖母マリアの御加護を願って熱烈に祈った。『めでたし、マリア様』と私はつぶやいた。『あなたは清浄そのものではないでしょうか。〔…〕人間がみだらと思う事柄など、あなたは、私たちが花粉や原子の愛の行為★を見るようにしかご覧にならないのではありませんか。私は御子キリストの地上の下僕(しもべ)たる神父様方の命に従いますが、主の慈愛が〔…〕古い刑法の規定☆によって阻まれるようなものでないことはよくわかっているのです。アーメン』」
山上昌子・訳『白書』,p.73.
★「原子の愛の行為」:古い化学では、化学反応は、元素ないし原子が親和力によって結合する現象だと考えられていた。
☆「古い刑法の規定」:同性愛は、当時はまだフランス以外の多くの国々の刑法で犯罪とされていた。
カトリックの教義は、「官能の行く手――つまり《同性愛》――を阻むまいという私の決心」とは矛盾するものでしたが、コクトーは、↑このような一種汎神論的な理屈によって、なんとか折り合いをつけようとしていました。《同性愛》は“悪”であり、避けるべきであるけれども、広大無辺な「神の慈悲」の前では、ごくささいなことにすぎないのだ、と。
「初めは、すべてが一種の法悦のうちに運んでいた。驚くべき熱誠が新参の信者をとらえる。熱が冷めてみると、朝起きて教会へ行くのがつらくなる。〔…〕ドアから出ていった悪魔が、陽光に化けて窓から入ってくる。
パリで徳行を積むのは不可能である。気が散りすぎるのだ。私は海へ行くことに決めた。そこで、教会と小舟だけを行き来して暮らそう。気を逸らせるようなことからは一切離れて、波の上で祈ろう。
私はTホテルに部屋をとった。
着いたその日から、Tでは、その暑さが享楽と脱衣を勧めるのだった。」
山上昌子・訳『白書』,p.75.
Tにある教会は、いつ行っても人影がなく、人けのなさが、信仰の熱意を冷めさせました。漁民たちは宗教には関心がなく、ここでは、パリでのような「聡明で高邁な」多くの信者との交流は、望むべくもありませんでした。

「教会より小舟の方が好ましかった。私はできる限り沖に漕ぎ出(い)で、そこでオールを放して海水パンツを脱ぎ、四肢をばらばらに投げ出して長々と横になったものだ。
太陽は自分の役を心得ている昔なじみの恋人である。まず太陽の力強い手が体の至るところに押しつけられる。人は抱きしめられ、がっしりとつかまれ、仰向けに引っくり返される。そして、不意に我に返って私は茫然とすることがあった。下腹に宿り木の珠のように白い液が溢れている。
目算は大きく狂っていた。私は自分が嫌になった。」
山上昌子・訳『白書』,pp.75-76.
「私」は「立ち直ろうと努め」て神に祈るのですが、
「しまいには、私の祈りはただ神に赦(ゆる)しを乞うだけのものになってしまった。〔…〕『神よ、〔…〕あなたは何でもわかって下さるのです。すべてはあなたが望み、あなたがお作りになったのではなかったでしょうか。肉体も、性も、波も、空も、ヒュアキントス★を愛して花に変身させた太陽も。」
山上昌子・訳『白書』,p.76.
★「ヒュアキントス」:太陽神アポロンに愛された美少年。二人で円盤投げをしていた時に、アポロンが誤って投げた円盤に当たって命を落とした。アポロンは彼の死を悼んで花(ヒヤシンス)に変えた。ただし、古代ギリシャでヒュアキントス(ヒヤシンス)とは、アイリスまたはパンジーのことだという。⇒:wiki:「ヒュアキントス」
このような汎神論的な祈りによって、自分の行状を正当化することになってしまいます。「私」の信仰は、当初の意図とは異なって、ますます汎神論的な方向へ、‥この世のすべては「神の望んだもの」であり、罪などはない、という考え方に近づいていきます。
ふりかえって見れば、パリで教会のミサに熱を上げていた時から、コクトーの信仰は、自分の“罪深さ”と深刻に向き合って、超越的な神の前に自分のいっさいを投げ出す――というようなものではありませんでした。人間・自然・神の予定調和をオプティミスティックに信じる汎神論的な傾向をもっていたのだと思います。それが、いま海岸の開放的な環境と太陽に照らされて、彼の中心を占めるようになったのです。
そして、ここに新たな‥‥ある意味で理想的な「おとこ」との出会いを迎えることになります。

ステファノ・リッチ「アポロンとヒュアキントス」
【10】「H」
「私は海水浴用に人けのない小さな浜辺を見つけてあった。砂利の上に小舟を曳き上げ、浜に打ち上げられた海藻の間で体を乾(ほ)したものだ。
ある朝そこへ行くと、身に何もつけずに泳いでいる青年がいて、気にさわっただろうかと私に尋ねた。私の返事が率直だったので、彼は私の嗜好に気づいた。間もなく私たちは並んで寝そべった。彼は隣村に泊まっていた。肺結核の徴候が幾らか見られたので養生しに来ているということだった。
太陽は感情の昂りを早める。私たちは途中の段階を跳び越した。心を逸(はや)らせる事物から遠く離れて、自然のただ中で何度も会ったおかげで、私たちは愛を語ったこともないのに、はや愛し合うようになった。
Hは泊まっていた宿を出て、私のホテルに移った。彼は物書きだった。神を信じてはいたが、教義に対しては子供じみた無頓着を誇示していた。」
山上昌子・訳『白書』,pp.76-77.[一部改]
「H」は、コクトーに自分の主張を繰り返し語ります。教会というものは、形式的で堅苦しいボワロー(17世紀フランスの古典主義文学者)の韻律法のような「精神の韻律法を人に強いる」。古い教義に固執して「一歩も動かぬ……教会に片足を置き、片足を現代生活に置くなんて、わざわざ引き裂かれて生きようというのと同じじゃないか。」
「神は愛を愛する。ぼくらは愛し合うことで、律法のやむにやまれぬ峻厳さの行間を読む力があることを、キリストに対して証明することができるんだ。」
山上昌子・訳『白書』,p.77;江口清・訳,『書物の王国』第10巻,p.51.
この自由思想家の青年は、そう言うのです。異性間であろうと同性間であろうと、人と人が愛し合うことは神の意志にかなっている。同性愛は悪徳であるかのように『聖書』に書かれているのは、大衆を納得させるための律法者の工夫にすぎない。どこにでもあるようで、しかもごく少数の人間しかしないようなことを取り上げて非難すれば、大衆は自分が「正義」の側に立てるので、喜んで教えにしたがうからだ、と。
自分は神に従わないのではない。むしろ、積極的に神の真意を探って、それに服従するのだ、と。
「彼は私の良心の呵責を気の弱さだとして、まるで取り合わなかった。私の抑えた態度を非難していた。僕はあなたを愛している、と彼は何度も言うのだった。あなたを愛して、大いに結構だと思っているんだ。
私たちが神話の神々のように半ば地上で、半ば水中で暮していたあの場所でなら、夢は長続きしたかもしれなかった。しかし、彼の母親が戻ってくるよう求めていた。私たちは一緒にパリへ帰ることに決めた。」
山上昌子・訳『白書』,p.77
「H」の母親はヴェルサイユに住んでおり、「私」はS近郊の父の館で暮していたので、「私たち」はパリのホテルに部屋を借りて、そこで毎日会いました。パリに帰ると、「H」には女友達が多いことがわかりましたが、「私」は気にとめていませんでした。というのは、同性愛者ほど「女との交際」を好むからです。中性的な性質なので、女性とは話が合うのです。逆に、「女たらしの男」に限って、女性を基本的に軽蔑しているので、「使用に及ぶ」時以外は女とは付き合わない、むしろ男の友だちが多いのです。
ですから、「H」に女友達が多いのは「女たらし」ではない証拠だと、「私」は思って、安心していました。
ところが、そうしているうちに、思わぬ不祥事が発覚します。
ある朝、ヴェルサイユから架けてきた「H」の電話の声が、いつもと違っているのを「私」は不審に感じます。
「本当にヴェルサイユからかけているのかと尋ねた。すると彼は狼狽し、大急ぎで、今日4時にホテルで、と約束して電話を切った。骨の髄まで凍りついたようになり、何が何でも知りたいというおぞましい偏執に突き動かされて、私は彼の母親に電話をかけた。息子はこの数日、帰ってきていない、仕事で遅くまで出ているので、仲間のところに泊まっている、という返事であった。」
山上昌子・訳『白書』,p.79.
これをきっかけに、「H」にかんして「私」が認めていた数々の状況が、ジグゾー・パズルの断片のように組み合って新しい意味を獲得し、「H」の隠しごとを明るみに出したのです。
「4時までどうやって待てばよいのか。〔…〕真相は一目瞭然だった。ただの女友達と思っていたⅤ夫人は彼の愛人なのだ。二人は夕方落ち合い、彼女の家で夜を過ごしているに違いない。こう確信すると、私の胸は猛獣の爪が突き立ったようになった。」
山上昌子・訳『白書』,pp.79-81.
それでもなお、コクトーは、すべては自分の思い違いで、4時に会えば、彼はきっと自ら身の潔白を証明することだろうと期待したのです。
ところが、「H」は、かんたんに事実を認めてしまいました。そして、男を愛するのと女を愛するのとは「まったく別物」なんだから、君は気にしなくていいんだ、などと言います。
「彼は、かつて女を愛していたことがあり、今また抗(あらが)い難い力に動かされて女と関係しているのだと告白した。君はつらく思うことはない、全く別物なんだ、君を愛している、自分が嫌になる、でもどうにもならない、〔…〕この性の二重性は結核のせいと考えてくれなくてはいけない。」
山上昌子・訳『白書』,p.81.
バイセクシュアルが結核の症状だとは、前代未聞の呆れた言い訳ですが、「H」は、そう言うのです。

「私は、女たちか私かどちらかを選んでほしいと言った。」
a.a.O.
もちろん、「私」のこの対応は、“自分との関係を続けたければ女と手を切れ”という意味で、「H」に決断を迫ったのです。コクトーは、「H」が彼を「愛している」なら、当然に、女とは縁を切るように努力すると答えるだろうと思っていました。
ところが、「H」の返事は逆でした。
「彼は言った。『約束しておいて、それを破るということになりかねない。別れた方がいい。君が苦しむだろうから。苦しめたくないんだ。空約束や嘘より、別れてしまった方がまだ君の苦痛が少ないよ』」
a.a.O.
さっきは、自分は女と付き合うけれども「君は気にしなくていい」、などと言っていたのに、それが相手に通じないとなると今度は、「君を苦しめたくないから別れる」などと言う。「H」はまったく自分の都合がすべてで、相手の男のことなど何とも思っていない、ということがわかります。これで「愛している」などと言われた日には、へそが茶を沸かしてしまいます。
「私はドアを背に立っていた。顔は真っ青で、彼に恐怖を与えたほどだった。『さよなら』と私は生気の失せた声でつぶやいた。『さよなら。君がぼくの生活のすべてだった。君以外には、ぼくは何もすることがないよ。ぼくはどうなるのだろう。どこへ行こう。どうやって夜を待とう。そして夜になったら夜明けを、明日を、明後日を、どうやって待ったらいいんだろう。一週一週どうやって過ごしていけばいいんだろう。』涙の向こうには霞んで揺れている部屋しか見えなかった。〔…〕
爪を噛んでいた彼は、とつぜん睡眠状態から脱け出たように目覚め、ベッドから飛び降りて、私を抱きしめ、赦しを乞うた。そして、女たちは追い払ってしまうと誓った。」
山上昌子・訳『白書』,pp.81-83;江口清・訳,『書物の王国』第10巻,p.52.
こうして、コクトーは、かろうじて「H」を繋ぎ止めましたが、「H」の“情婦”はひとりではなく複数だということも、これではっきりしてしまいました。
しかし、「H」とコクトーの幸福な関係は、次の章にも続いていきます。そして次の章では、「Ⅹ神父」も顔を出します。
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]





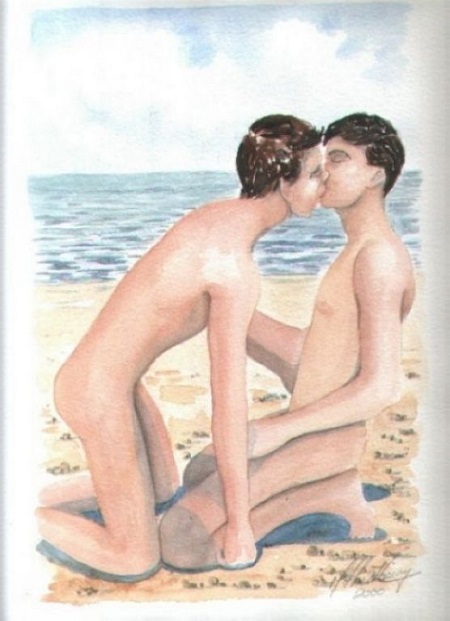


 彡
彡