03/17�̓��L
23�F10
�y�K�Ǐ�150�z�X�s�m�U�w�G�e�B�J�x(10)�\�\�\�u�����v�Ƃ́A�����Ȃ݂ɍӂ���l�̖����H
---------------
.
 �@
�@
�X�s�m�U�̉Ɓi���C���X�u���t�j�@�X�s�m�U�́@�@
���C�f���x�O�̂��̉ƂɊԎ肵��(1660-63) �@�@
�w�G�e�B�J�x�̎��M���͂��߂��B�@�@�@�@�@
�@�����́B(º.-)���
�@�y�K�Ǐ�150�z�X�s�m�U�w�G�e�B�J�x(9)����̂Â��ł��B
�@�y38�z�u�����v�́A�ǂ��������Ă����̂��H
�@�l�Ԃ́u�F���v�Ƃ������H�A�u��������v�Ƃ��������́A�����ꂽ�u���_�v�̓����ɂ����鐄�_�ł͂Ȃ��A�O�ւƌ������u���_�ْ̋��v�ɂق��Ȃ�܂���B
�@�u�����v�́A�ǂ��������Ă����̂��H �������ɗ����̂��H �������ɂ́A����t�����X�̓N�w�ҁE�����ƃW����=�N���E�}���^���́����̏��q���Q�l�ɂȂ邩������܂���B
�u�����݂͂ȁA�O�����瓞�����Ă����̍s���̗͂𐧌�����X���Ɏx�z����Ă���B���͌X�������ʂł��낪���ē����B���������̌X�����������B�������A�����Ȃ�l���O�����炨�̂�ɍ�p���閳���̌����Ɂg�N���͂����āh�R���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă��A������Ƃ����Đ����͂������Ȃ����͂ȑ��݂ł���킯�ł͂Ȃ��B�k�c�l�g�̂͂����q���r�Ȃ��ŋ@�\����B���Ƃ��Δn����������Ƃ����B���̓������~�߂邱�Ƃ��ł�����͉̂����Ȃ��B�����������ɂ��āA���̂��̂̂��̂͒�R��͂�\�o����̂ł���B�k�c�l�������A�k�c�l��Ȃ��ł͂����Ȃ��Ă��A���͏����݂Ƃ͕ʂ̉����ł���B�k�c�l�������̑��݂̂Ȃ��ɋ������悤�Ƃ��邱�Ƃ����Ȃ����{���A���̗~�]�́A�P�ɖ��͂̌��ʐ��������̂Ƃ��Ĕے�I�Ȃ������Ő������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�w���k�u�R�i�g�D�X�v�\�\�M�g�����l�͖{���I�ɂȂɂ������̋C�ɓ��������̂̎����ɂ���̂ł͂Ȃ��B����͋N���I�Ȃ��̂ł��Ȃ���A���������{�\�I�́A���邢�͂����̂Ȃ��ɂ���b���̂悤�Ȃ��̂ł��Ȃ��B�����͂��̂�ɑ����̂��Ƃ�v�����A���̂��߂ɋ�Y��������B�k�c�l
�@���Ƃ������݂͑S�ʓI�ɓw���k�u�R�i�g�D�X�v�\�\�M�g�����l�Ȃ̂��I �������A���̗͂����ł͎������������ٓI���݂��x���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������邽�߂̐g�̂̓w�͂ɂ́A�O��������ɓ���������̂𗝉����邽�߂̐��_�ْ̋����Ƃ��Ȃ��B�k�c�l���������ĕʂ̗́A�ʂ̌X�����K�v�ł���A���̏ꍇ���ɂ��߂��́A�^�Ȃ���̂�^�Ȃ���̂ɂ���Đ^�Ȃ���̂Ƃ��Ċ��m���邱�Ƃ��ł��鐸�_�̗͂��K�v�ƂȂ�B�^�̊ϔO�͐g�̂����̂�����w���k�u�R�i�g�D�X�v�\�\�M�g�����l����悤�ɂ��̂�����m�������̂ł���B�v
�W����=�N���E�}���^���C���������E��w�t�F�����[���ƃX�s�m�U�\�\�\�q�i���r�̌����x,2011,�ȕ���,pp.21-24.
�@�u�����v�́A�g�m�肽���Ƃ����~�]�h�Ȃ̂ł��k�w�G�e�B�J�x��S���E�t�^�S�l�B
�@�Ƃ�����u�z���v���u����v�ɗ�����āA�O���瓞����������Ɂu�ꑮ�v����ق��ɌX�������Ȏ��Ȃɑ��āA���ʂ�����Ƃ���g�w�́h�ł��B������A���I���ꂽ�g�����I�u���ʊT�O�v�h�����ł́A�������Ȃ��̂ł��B�������A�u�g�́v�����ڐڐG���鏔�u���́v�Ƃ̊W��ʂ��āA�g�^�h�Ȃ�������g��ށh�����ʂ������B�Ȃ��Ȃ�A�����u�����v�\�\�X�s�m�U���u�����v�\�\�́A������`����M�p��������Ȃ��A�育�����̂��钼�ڌo���ɂ���āg�^�h�Ȃ���̂����݂Ƃ肽���ƔO�肷�邩��ł��B
�@�Ȃ�قǁA���������A�[�I�T���̑啔���́A�u��\�S�v�ȔF���ɂ����B���Ȃ���������܂���B�o���́A�u�g�́v�̃L���p�V�e�B��������ł��傤�B����ł��Ȃ��A�s���̛�(�Ƃ�)�ɉB���ꂽ�킸���Ȍ������Ƃ߂āA�u�����m�v���u�\�S�v�������߂āg�O���h���u������̂ł��B
�@���������u�z���m�v�ɂ́A���Ȓ��S�A�g�l�Ԓ��S�h�̔F���ɂȂ�₷�����_������܂��B���̂��߂ɁA�g��ށh�ɂ��F���́A�[�l�����ꂽ�䉾�b��g�l�ו��ށh�ɂȂ�₷���̂ł��B�u�e�[�u���v�u�֎q�v�́A���̎��̂̐����ɂ���ʂł͂���܂���B�g�l�Ԃ��e�[�u���Ƃ��Ďg�����̂��u�e�[�u���v�ŁA�֎q�Ƃ��Ďg�����̂��u�֎q�v���h�Ƃł���`����ق��͂���܂���B
�@�g��ށh�ɂ��F���́A���ӂɂ��\�ʓI�ȓ��������ɒ��ڂ��ĕ��ނ������ʂɂȂ�₷���A�܂��A�ړI�_�Ȃǂ̐l�Ԃ̎��ȔF���𓊉e�������̂ɂȂ�܂��B

�X�s�m�U�̕����i���C���X�u���t�j�@����������
���I�ł����ς��ɂȂ��Ă��܂��قNj������̕���
�ŁA10�ΔN���̊w���J�Z�A���E�X�ƕ邵�Ă����B
�@�������A�u�����v�́A���ڔF�����邱�Ƃ��ł��܂���B�g��ށh�ɂ���ĔF������ق��A���E�𗝐��I�ɔc��������@�͂Ȃ��̂ł��B�����ŁA�u�����v�́A���Ȓ��S�A�l�Ԓ��S�́g�l�ו��ށh�ɂȂ邱�Ƃ�����A�Ώۂ��ꎩ�̂̓������A���Ȃ̐g�̂ɂ�����u���ʂ�������v�ɂ���ē��肵�Ȃ���A�אS�ɒT�����Ă䂭���Ƃɂ��A�u�\�S�v�ȔF���ɒB���悤�Ƃ���̂ł����B
�@�����u�������������R�Ȋw�i�Ƃ��ɁA���w�A�����w�ȊO�́A���w�A�����w�A�V���w�A�c�j�́A���̂悤�ȔF���̓w�͂ł������ƌ����܂��B
�u�`�������_���A�l�ԂƎ������̂��̂Ƃ��q�����ł͂Ȃ��A����䂦�A���������ԐړI�ȔF���ɗ������̐l�Ԃ́A���E���艞���̂��鉽���Ƃ��Č��o�����Ƃ͂Ȃ��A���E�Ƃ̊W�ɂ����Ď����̈ʒu��������m���߂邱�Ƃ��o���Ȃ��ł��낤�B����ɑ��āA�o���́A�����̖{���ł͂Ȃ��삵�������̈���ɂ��A�m���ɖ��ʂ������A�f�ГI�ł���A�w�肪�Ȃ��x����ǂ��A���ƌ����Ă��������̂��̂ƒ��ړI�ɐڐG������̂ł���A�l�Ԃ̂����ɗႦ�D���̋C�����䂫�N���A�l�ԂƐ��E�Ƃ����炩�̎d���Ō��ѕt����͂����B�v
�����X�q�w�j��̓N�w�x,1978,�݂������[,p.174.
�@�������ăX�s�m�U�́A�A����A�����i�`���j�ɂ��F�����u��\�S�v�Ȃ��̂ł���Ƃ��A����̐g�̂Ə��ΏۂƂ̐ڐG�i�͂��炫���������j�ɂ��F���������A�u�\�S�m�v�ƂȂ邱�Ƃ��ł���ƍl�����̂ł��B
�@���̂悤�Ȓ��ڑ̌��̏d���́A�������n���̏��X���������̂Ȃ��ɂ��������R�Ȋw�����̏ɂ��h�����Ă����͂��ł��B���Ƃ��A�����g�������w�̕��h�ƌ����郌�[�E�F���t�b�N�i�ˁF�w�G�e�B�J�x(5)�y21�z�j�́A���l�ł���A�]�ɂɃ����Y�������Č����������삵�A���܂��܂Ȃ��̂�`���Ă��܂����B�������r�̐����ώ@�������ɁA�����Ȑ�����忂��Ă���̂����������A���̊ώ@���n�߂��̂��A�������w�����̚���ƂȂ����̂ł����B���[�E�F���t�b�N�ƃX�s�m�U�́A�ׂ蒬�Ƃ����Ă悢�����ɏZ��ł���A�W����=�N���E�}���^���́A�Q�l�̂������Ɍ𗬂��������̂͂܂������Ȃ��ƌ����Ă��܂��i����q�j�B
�@�X�s�m�U�́A�g��ށh�ɂ��F�����A����ꍇ�ɂ��u�����m�v�ƂȂ肤�邱�Ƃ�F�߂Ă��܂����B����u�T�O�v�́u�Ό��ɂƂ���Ȃ��l�ɂ̂ݖ��āE�����ł���v�k��Q���E�藝�S�O�E�����P�l�ƌ����Ă���̂́A���̂��Ƃ��Ӗ����܂��i�ˁF�w�G�e�B�J�x(9)�y36�z�j�B
�@�y39�z�u�����v�̃_�C�i�~�Y��
�@�����ŁA�w�G�e�B�J�x�S�̂ŁA�u�����v�u�����m�v�Ɍ��y�����藝�𑍗����Ă݂����Ǝv���܂��B���e�I�ɂ��u�����v�������Ă��Ă��A�u�����v�Ƃ������t���o�Ă��Ȃ��ꍇ�́A�����Ƃ��č̂��Ă��܂��A����ł������悻�̌X���͌��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�������̂����A�k��Q���l�̏��藝�́A�s���R�t���E���A�u�C�f�A���v�܂����g��ށh�ɂ���ĔF�������u�����m�v�Ɋւ�����̂ł��B
�@�����ς�l�Ԃ��u����v���e�[�}�Ƃ���k��R���l�ɂ́A�u�����v�Ɍ��y�����藝������܂���B
�@����ɑ��āA�k��S���l�ɂ́A�Ђ��傤�ɑ������Ƃ��킩��܂��B���܂葽���̂ŁA�Q���ڂɕ��ނ��܂����B�k��S���l�k��T���l���u�����v�̏��藝�́A�Љ�Ȃ����l�ԗϗ��Ɋւ�����̂ł��B
�@�@��Q���A�藝29�����A�藝37�A�藝38,�n�A�藝39,�n�A�藝40,����1,2�A�藝41,42�A�藝44,�n2.
�u�����m�v�̑Ώۂ́F�u���ʊT�O�v�A���_�A�i���ՊT�O�j
�u�����m�v�́A�u�\�S�v�ȔF���A���ׂĂ̐l�Ԃɋ��ʂȔF���B
�u�����v�̖{���́F�Ώۂ��u�K�R�I�Ȃ��̂Ƃ��ā��i���̑��̂��ƂŌ���v�F���ł͂Ȃ��A�u�C�f�A���v���g��ށh��F������B
�A�@��S���A�藝18�����A�藝24,26,46�A�藝48�ؖ��A�藝50,�����A�藝65,�n�A�藝66,�����A�藝72�����G�t�^8,16,23,25.
�u�����̎w�}�v�̓��e�́F���݈ێ��i�����Nj��j�B�����I�ȗ��v�Nj��́g�F�����邱�Ɓh�ɓ������B
�u�����̎w�}�v�e�_�F�����ɂ͈��ŕ�A�u�������Ԃ�E�����т�E�����݁v�̔ے�A���ʂƎ��P�I���A�w�M���͎���I�ׁB
�i�t�^�j�F���R���J�����錠���A�u����E�p�J�v�̔ے�A�����I�����̂��߂̋Z�p�B
�B�@��S���A�藝35,�n1,2,�����A�藝36�����A�藝37����1,2�A�藝51,52,53,54,58�A�藝59,�����A�藝60,61,62�A�藝63,�n�A�藝66�����A�藝73�G�t�^3,4,5,9.
�u�����̓����v�̌��ʁF�{����̈�v�A�������A���e�ƗF��A���R��Ԃ���Љ�_��ցA����̑�s�i����I�~�]�͋������ɔ�����j�A�~�]�̗������A�S�̕����i�g����ɂ��P�s�h�̔ے�j�A���R�A���Ƃɂ�鎩�R�B
�u�����v���琶���銴��F�u�D�ӁE���_�v�A�ō��́u�����v�G�����Ȃ�����F�u�����E����v
�i�t�^�j�F�����I�~�]�A�~�]���������E�����m�̊����͎����������炷�A�����I�������m�I�F�����u�P�v�A�������Ƌ���̈Ӌ`�B
�C�@��T���A�藝7�A�藝10�����A�藝20�ؖ�(�藝15)�A�藝38.
�u�������琶���銴��v�̋����A�u�����v�̐����K���F���e�E�����Ɉ��ŕ�A�u�\�S�v�Ȏ��ȔF���Ɗ���̔F�����_�ւ������I���A�����I�F���̌��ʁF����Ǝ��̍����B
�@�u�����v�Ƃ͗��_�I�F���ł���Ƃ���@�ƁA�u�����v�ɂ��Љ���E�l�ԗϗ����q�ׂ��A�`�Ƃł́A�u�����v�̈Ӗ��ɈႢ������̂ł��傤���H ���͓������Ǝv���܂��B�J���g�Ȃ�A�u���_����(��������)�v�Ɓu���H�����v����ʂ���Ƃ���ł��傤����ǂ��A�X�s�m�U�ɂ́A���̂悤�ȋ�ʂ͂���܂���B
�@�@�ł��A�X�s�m�U�́A�u�����v���A�l�Ԃׂ̊肪���ȁg���Ȓ��S�I�F���h�g�l�Ԓ��S�I�F���h�����z���邱�Ƃ��q�ׂĂ���A���̂��Ƃ��A�A�ȉ��̎Љ�ϗ��̏�ʂł��u�����v�̓����ɂ��A�d�v�ȈӖ��������Ă��邩��ł��B
�@�l�Ԃ́A���ȕۑ��́i�R�i�g�D�X�j���g�����I�{���h�Ƃ��Ă��܂�����A�������u�����v������č����I�ȏ���������ꍇ�ł��A��́A���ȗ��v�̍����I�ȒNj��\�\�Ƃ������ƂɂȂ炴������܂���B���l�̂��߂Ɏ��Ȉێ�����ȂǂƂ����̂́A���ꎩ�̖����ł��k��S���E�藝�Q�T�l�B
�@�������A�u�����v�͂��̍������ɂ���āg���Ȓ��S�I�F���h�����z���邱�Ƃ��ł��܂��B�����I�v�l�ɂ��A�l�ԂɂƂ��čł����v�ɂȂ�̂́A�u�����v�ɓ����ꂽ���̐l�ԂȂ̂ł��k���E�藝�R�T�E�n�P�A���^�X�l�B��������A�l�Ԃ������I�ȋ����Љ�A�s���R�t�ȋ����Љ�ւ̓W�]�����܂�܂��B
�@�܂��A�������Ƃ���A�����I�ȗ��v�Nj��́g�F���h�ƃC�R�[���ł���A�Ƃ����E�����ЂƂ̏d�v�ȋA���������܂��F
�u�k�藝�Q�U�l����ꂪ�����ɏ]���ēw�͂��邱�Ƃ́A���ׂĔF������Ƃ������Ƃł���B���_��������p���邩����A���_�͔F���ɖ������̈ȊO�͎����ɂƂ��ėL�v�ł���Ɣ��f���Ȃ��B
�@�k�藝�Q�V�l�����́A�F���ɂ��������������̂������P�ł���A�܂������F��������܂��Ă�������̂��������ł���ƔF�߂�B
�@�k���^�S�l�����Đl���ł����Ƃ��L�v�Ȃ��̂́A�m�����邢�͗������ł��邾�����������邱�Ƃł���B�����Ă��̓_�ɂ̂ݐl�Ԃ̍ō��̍K�����邢�͎���������B�k�c�l�����ɂ���ē������l�Ԃ̋��ɂ̖ړI�A����������ō��̗~�]�́\�\�\�ނ͂��̗~�]�ɂ��ƂÂ��Ă���ȊO�̂�����~�]�䂵�悤�Ƃ���\�\�\�A�ގ��g�Ɣނ̒m�I�F���̑ΏۂƂȂ邷�ׂĂ̂��̂��\�S�ɔc������悤�ɔނ����肽�Ă�~�]�ł���B�k��S���l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.332-333.
�@
�u���Ƃ��X�s�m�U�͎��R�̂�����Ȃ��@�ׂȗl���̉��ɂ��g���́h���Ђ����Ă��邱�Ƃ�����Ă���B�k�c�l�ЂƂ̐�͂ЂƂ̗���ł��邪�A�������Ȃ��������̕\�ʂŁA�����ꂽ�����̎��̂悤�ɋY��A�ꌩ��ȏ����ȋ��F�̓_��������Ȃ����l�ɗ�������B
�@�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�������X�s�m�U�́A���t�̗��q�I�E�����I�\�����m�F�����t�@���E���[�E�F���t�b�N�k�f���t�g�o�g�̐����w�҂ŁA�͂��߂Č������Ŕ������̐��E�������Ƃ����l�̌��t�Ɋւ���ώ@��m���Ă����B�w�l�Ԃ̐g�̂́i�{�����قɂ���j�����̌̂ō\������Ă��āA���̌̂̂ЂƂЂƂ�����߂ĕ����I�ɍ\������Ă���B�x�i�w�G�`�J�x��2���v��1�j�B�v
�W����=�N���E�}���^���C���������E��w�t�F�����[���ƃX�s�m�U�\�\�\�q�i���r�̌����x,2011,�ȕ���,pp.4-5,50.
�@���[�E�F���t�b�N�ɂ��Ă��w�G�e�B�J�x(5)�y21�z�Ō��܂������A�}���^���ɂ��ƁA�X�s�m�U�̗F�l���ď��Ȃ̒��ɁA���[�E�F���t�b�N�ɂ���čs��ꂽ���t�̊ώ@�ɂ��ďq�ׂ����̂����邻���ł��B
�@�u�l�Ԃ̐g�̂́A�قȂ����{���������������̌̂���g�D����Ă���v�Ƃ��k��Q���E�v���P�l���̂��ߐg�̂̊e�����͂��ꂼ��قȂ�������ɂ���ē�������Ă���Ƃ����k��R���E�藝�P�V�E�����l�i�ˁF�w�G�e�B�J�x(8)�y35�z�j�́A���[�E�F���t�b�N�̔�������G�����ꂽ�C���X�s���[�V�������������Ƃ��킩��܂��B�X�s�m�U�́A���܂��܂ȁu�{���v���������������A�̉t�̒���忂������Ă����Ԃ��A�l�Ԃ̐g�̑S�̂ł����Ă���ƍl�����悤�ł��B
�@���������āA�g�l�ԁh�Ƃ��������S�̂Ƃ��Ă܂Ƃ܂�������Ċ������Ă���̂́A�g����h�g���_�h�Ƃ������悤�ȑ��c�m������̂ł��Ȃ���A�g�_�h�̂悤�ȑ��݂��O�����瓝�����Ă���̂ł��Ȃ��B����͒[�I�ɁA�s�_���Ȃ킿���R�t�S�̂��A�O������̓����������I�Ȓ������͂��Ȃ��܂Ƃ܂��Ă���̂Ɠ������Ƃ��B�X�s�m�U�́A�����l���Ă����̂��Ǝv���܂��B
�@����́A�g�L�@�́h���g�L�@�́h�Ƃ��Ă܂Ƃ܂邵���݂ɂق��Ȃ�܂���B�g�̓��́u���������v�̓��������ɂ���āA�������悤�Ƃ���X�����i�ނƁA�t�ɁA�e�����i���j���A�ア�������������āg�܂Ƃ܂�h�����悤�Ƃ����g�h�̎��ȕۑS�@�\�������̂ł��B���̃_�C�i�~�b�N�ȓ������A�u�R�i�g�D�X�v�Ƃ����g�h�́u�����I�{���v�ɂق��Ȃ�܂���B
�@������g�h�̑����猾���A�����������邱�Ƃ́A�i���������������ɉ������Ă��炦��A�Ƃ����������I�ȍl������Ɂj���ꎩ�̂��A���g�́g�����́h�����߂�L�v�ȍs�ׂȂ̂ł��B
�@���́A�������̒��z���̂́A�ŋߐV�^�R���i�E�C���X�̂��߂ɗ��ŋN���Ă��錻�ۂ�m���Ă���ł��B�؍��̐V�^�R���i�Ђ́A��緂ɖ{���̂���I�J���g�@�����c�̒��̊������A��緎s�Ƃ��̎��ӂɍL�܂������Ƃ���N���Ă��܂����A���̑�緎s�́A�����̕ێ��`�̃��b�J�A�Ȃ����i�V���i���Y���̐��n�ƌ����Ă悢�ꏊ�ł��B�W�隬�̌����ɂ́A���������������ƒՍL�X�̘V�l���A���������Ԃ낵�Ă��܂��B���̂������A�^�}�u���ɖ���}�v�̈ꕔ�ł́A�u��緃E�C���X�v�ȂǂƌĂ�ŕ̂݁A��緈ȊO�̏ꏊ�͈��S������R���i�Ђ��C�ɂ���K�v�͂Ȃ��A�Ȃǂƍ��ʓI�Ȍ����������ɂ���l�������قǂł��B����������Ɠ����ɁA���܌����Ɍ�����̂́A��ʂ̉��������Ɛl�I��������緂ɏW�܂��Ă䂭���ۂł��B���̗���ɉ�����đ哝�́i�������^�}�����j���A�����Ɍ����āA��緂��~�����ƌĂт����Ă��܂��B
�@�����炳�܂Ȓn���`���~�ނ킯�ł��ᔻ�����킯�ł��Ȃ��̂ɁA�N���w������ł��Ȃ������̎肪�����L�ׂ��Ă䂭�B�����{�k�Ђɂ������āA�u�J(���Â�)�v���ǂ��̂Ɨ�X���������A���˔\�𗁂т��H�i��i��ŐH�ׂ�A�Ƃ����悤�ȁg���_�h���܂���ʂ������{�Ƃ͑ΏƓI�ȏ��A���ɂ͂���܂��B
�@�������A�����������Ƃ͐��E���ǂ��̍��ɂ�����̂��Ǝv���܂��B�����A���鍑�X�i�����A���{�A�d�j�̏ꍇ�ɂ́A�����I�C�f�I���M�[��g���������h�̉A�ɉB����āA�����ɂ����Ȃ��Ă���̂ł��傤�B

�@�y40�z���R��ԂƋ����Љ�
�u���̔��l�k��S���E�藝�R�V�E�����Q�\�\�\�M�g�����l�̖ړI�́w���сx�Ɓw�߉߁x�A�w���`�x�Ɓw�s�@�x�̉𖾂ł���B���̉𖾂͐l�Ԃ́w���R��ԁx�Ɓw�s����ԁx��Δ䂵�Ę_����_�̐i�s��ʂ��ē�����B�v
������Y�w�Ɩ����\�\�\�X�s�m�U�G�l�x,2004,���s��,p.135.
�@�����ɂ́A�X�s�m�U�̎Љ�_��_�A���Ƙ_��������Ă��܂��̂ŁA�������ڂ������Ă��������Ǝv���܂��B
�u�k�藝�R�V�E�����Q�l�k�c�l�l�Ԃ����R����ƍ��Ə�Ԃɂ��āA�Q�C�R�q�ׂĂ����˂Ȃ�Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�l�����R�̍ō��̌����ɂ���đ��݂��Ă���B���������Ċe�l�͎����̖{���̕K�R�����瓱�����������̂����R�̍ō��̌����ɂ��ƂÂ��Ď��s����B���̂��Ƃ���e�l�́A���R�̍ō��̌����ɂ��ƂÂ��ĉ����P�ł���A�������ł��邩�f���A�����������̈ӂ̂܂܂Ɏ����̗��v���͂���k��R���藝�P�X�ƂQ�O������ꂽ���l�A����ɕ��Q����k��R���藝�S�O�E�n�Q������ꂽ���l�B�܂������̈�������̂��ێ����A�����̑���������̂�ے肵�悤�Ɠw�͂���k��R���藝�Q�W������ꂽ���l�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����l�Ԃ������̓����ɂ���Đ������Ă�����A����ł��A�k���̕��̒藝�R�T�E�n�P���l���̐l�ɂ܂�������Q�������邱�ƂȂ��ɁA���̂悤�Ȏ������g�̌��������邱�Ƃ��ł����ł��낤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������l�Ԃ́A�k���̕��̒藝�U���l�l�ԓI�\�͂Ɠ����͂邩�ɂ��������������ɗ�]���Ă���̂ł��邩��k���̕��̒藝�S�E�n�ɂ��l�A���������āk���̕��̒藝�R�R���l�����ΈقȂ����ق��ւЂ��܂킳���B���Ȃ킿�A�k���̕��̒藝�R�S���l�������ɓG�ΓI�ɂȂ�B���̂悤�ȂƂ������A�������ɉ������������Ƃ��ނ�ɂ͕K�v�ł���̂Ɂk���̕��̒藝�R�T�E�����ɂ��l�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������āA�l�X���S��a���Đ����A�������ɏ��������Đ������邽�߂ɂ́A�ނ�����R�����������āA���l�Ɋ�Q��^����悤�Ȃ����Ȃ�s�ׂ��Ȃ��Ȃ��Ƃ����ۏ��������ɂ����Ƃ��K�v�ł���B�k�c�l�k��S���l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.350-351.
�@�܂��A�ŏ��ɏo�Ă����u���R�̍ō��̌����v�Ƃ������t�ł����A���Ƃ̂ق��ɏo�Ă����u���R���v�Ɠ����Ӗ��Ǝv���܂��B�������A�u���R���v���̂��A�X�s�m�U��������ǂ������Ӗ��Ŏg���Ă���̂����d�v���ɂȂ�킯�ł�����A�����˂�����ōl���Ă݂Ȃ���Ȃ�܂���B
�@���́k�藝�R�V�E�����Q�l�́A�����ƑO�̂ق��̒i���ŁA�u�����v�Ƃ������t���o�Ă���ӏ�������܂��̂ŁA�������Q�Ƃ��܂��傤�F
�u�k�藝�R�V�E�����Q�l�k�c�l�����̗��v��Nj����ׂ��Ƃ������̌����́A�k�c�l�����������ɂ������Ă����Ă��������Ɠ����������A�����́A�����ɂ������Ă������Ă���Ƌ�����B�ނ��e���������͊e���̓��A���邢�͔\�͂ɂ���ċK�肳���̂ł��邩��A�l�Ԃ́A�������l�Ԃɂ������Ă����Ă������������͂邩�ɑ傫���������A�����ɂ������Ă����Ă���B�k��S���l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.349.
�@������́A�u�j�{���ւ���@���v�ɑ���ᔻ���q�ׂ��ӏ��ł��B�X�s�m�U�̌��_�́A����̓j�E���ւ��ׂ��łȂ��A�l�Ԃ��u���������̗��v���͂����āA�v�������u�����̎v���܂܂ɗ��p������A�c�c�����Ɂc�c�D�s���Ȃ悤�ɂƂ肠�������Ɓv�͋������A�Ƃ������Ƃɂ���܂��B�Ȃ����Ƃ����ƁA�u�����������ɑ��Ă����Ă��������v�\�\�\�ҏb���l�Ԃ��P���ĐH�ׂ�Ƃ������Ƃł��傤�\�\�\�u�Ɠ����������v�A�����������ɑ��Ď����Ă���B�������A�l�Ԃ̔\�͓͂��������͂邩�ɑ傫���̂�����A����ꂪ�����Ă����u�����v�̂ق����A�����������Ă����u�����v���͂邩�ɑ傫���A�Ƃ����̂ł��B�i�u���v�́A�k��S���E��`�W�l�ɂ��A�u�́v�Ɠ����Ӗ��ł��B�j
�@�܂�A�X�s�m�U�̌����u�����v�Ƃ́A���Ȃ��Ƃ��E���́k�����Q�l�ł̎g�����ł́A�قƂ�ǁg���́h�g�r�́h�Ɠ����悤�ȈӖ��ɂȂ�܂��B
�@��������ƁA�u���R�̍ō��̌����v�ƌ����A�u���R���v�ƌ����A�������A���Ȃ���͓I�ȃC���[�W�ōl����������܂���B���b�N�����A�z�b�u�Y�́g���R��ԁh�́A�g���l�����l�ɑ��Đ키�h�����\�\�\�Ƃ��������̂ɋ߂���������܂���B
 �@
�@
�u�e�l�����R�̍ō��̌����ɂ���đ��݂��Ă���B���������Ċe�l�͎����̖{���̕K�R�����瓱�����������̂����R�̍ō��̌����ɂ��ƂÂ��Ď��s����B���̂��Ƃ���e�l�́A���R�̍ō��̌����ɂ��ƂÂ��ĉ����P�ł���A�������ł��邩�f���A�����������̈ӂ̂܂܂Ɏ����̗��v���͂���k��R���藝�P�X�ƂQ�O������ꂽ���l�A����ɕ��Q����k��R���藝�S�O�E�n�Q������ꂽ���l�B�܂������̈�������̂��ێ����A�����̑���������̂�ے肵�悤�Ɠw�͂���k��R���藝�Q�W������ꂽ���l�B�v
�@�u�����̖{���̕K�R�����瓱�����������́v�Ƃ́A�u�����̑��݂ɌŎ����悤�Ƃ���w�́v�i��R���E�藝�U�`�X�j���Ȃ킿�u�R�i�g�D�X�v���瓱���o�����u�Փ��v�u�~�]�v�u�ӎu�v�Ȃǂ��u����v�ł��傤�B�u�P�v�Ƃ́A���ꂼ��̐l�ɂƂ��āu�L�v�v�ł�����́k��S���E��`�P�l�A�u���v�Ƃ͂��̖W���ɂȂ���̂ł��k���E��`�Q�l�B
�@�����ŁA�u���R��ԁv�ł͊e�l�́u�����̈ӂ̂܂܂Ɏ����̗��v���͂���v�u�����̈�������̂��ێ����c�c�悤�Ɠw�͂���v�B�����Łk��R���E�藝�P�X�l������ƁA�u��������̂��ێ��v����Ƃ́A�u��������́v���u�ی�v���邱�Ƃł���̂��킩��܂��B�����܂ł́A�����ł��傤�B
�@���������́A�u���Q�v������A�u�����̑���������̂�ے肵�悤�Ɠw�́v�����������_�ɂ���܂��B�Ƃ����̂́A���̒i���ŁA
�u�����l�Ԃ������̓����ɂ���Đ������Ă�����A����ł��A�k���̕��̒藝�R�T�E�n�P���l���̐l�ɂ܂�������Q�������邱�ƂȂ��ɁA���̂悤�Ȏ������g�̌��������邱�Ƃ��ł����ł��낤�B�v
�@�ƌ����Ă��邩��ł��B���́u�ł��낤�v�́A�����ł͐ڑ��@�ł��B�������z�Ɖ��߂���A�u���R��ԁv�ɂ́u�����̓����v�͂��肦�Ȃ����ƂɂȂ�܂����A�����Ƃ���͌����Ȃ���������܂���B�ނ���A�u�����̓����v�̂����u���R��ԁv�Ƃ����̂́A��l�ɒl���܂��B�g���Ɓh�̖����i���܂������H�j�E���������a�ȎЉ�̉\�����l�����邩��ł��B
�@�Ƃ������A�u���Q�v�k��R���藝�S�O�E�n�Q�l���A�����̑Ώۂ��u�ے�v���邱�Ƃ��A����Ɋ�Q�������邱�ƂɂȂ�܂��B
�@��������ƁA�l�X���u�����̓����v�ɏ]�킸�A�u�����ɗ�]���āv�u�Ђ��܂킳��v�Ă���E�܂��������u���R��ԁv�ł́A�g���݂����h���u���Q�v�ɂ���āA�ی��Ȃ���Q�������������ƂɂȂ�ł��傤�B
�@�����Ƃ��A�u��������́v�͔�̂��Ƃɒu���킯�ł�����A���ꂼ��C�ɓ������҂��W�߂�ꂽ�O���[�v���m�ŁA�������邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�l�X���u�����̓����v�ɏ]���Ă���ꍇ�\�\�\�u�����R��ԁv�ƌĂт܂��傤���\�\�\�ɂ́A�ǂ��Ȃ�ł��傤���H �u���Q�v�́A���Ȃ��ł��傤�B���������A�S�����u�����v�ɓ�����Ă���A�Η����邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��̂ł�����k��S���E�藝�R�T�C�n�P�C�n�Q�l�A��Q��������҂͂��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B���������āA��Q�ɕ��邱�Ƃ����肦�Ȃ��B�u�����݁v�́H ��͂蓯�����R�ŁA�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����Ƃ��A�g�����Ȑl�h�Ƃ����̂́A������̂ł��B���̏ꍇ�ł��A�u�����v�ɓ�����Ă���A��Q�͉����Ȃ��ƌ����܂��B�Ƃ����̂́A�u�����v�ɓ����ꂽ��Ԃɂ��āA�X�s�m�U�́A�����̂悤�Ɍ����Ă��邩��ł��F
�u�k�藝�P�W�E�����l�k�c�l�l�Ԃɂ́A�����̑��݂��ێ�����̂ɂ�����l�Ԃ�������_�ň�v���Ă���Ƃ������ƈȏ�ɁA���l������̂�]�ނ��Ƃ͕s�\�ł���B�l�Ԃ̂��̂悤�Ȗ]�݂ɂ���Ă�����l�Ԃ̐��_�Ɛg�͓̂������āA����������Ȃ鐸�_�A��Ȃ�g�̂��`�����A��������������̂��A�����ɂł��邾���e���̑��݂��ێ����悤�Ɠw�͂��A�܂���������̂������ɔނ�̂��ׂĂɋ��ʂȗ��v��v������悤�ɂȂ�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�̂��Ƃ��������ɏ]���Đ����悤�Ƃ���l�ԁA����������A�����̓����ɏ]���Ď����ɗL�v�Ȃ��̂����Ƃ߂Ă���l�Ԃ́A�����ȊO�̐l�����̂��߂ɗ~���Ȃ��悤�Ȃ��̂��A���������̂��߂ɓw�͂��Ă��Ƃ߂邱�Ƃ͂Ȃ��B�k��S���l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.324.
�@�������A���̂悤�ɁA�Љ�̍\�����S�������S�Ɂu�����̓����v�ɏ]���Ă����u���R��ԁv�\�\�\�Ƃ����z��́A���܂�ɂ��������ꂵ�Ă��邩������܂���B
�@�������A�u������l�Ԃ̐��_�Ɛg�͓̂������āA����������Ȃ鐸�_�A��Ȃ�g�̂��`���v����Ƃ����̂́c�c�A�ȂE�T���L���B��O�������Ȃ��悤�ȁA�ƂĂ�����ȎЉ�ɂȂ�悤�ȋC�����܂����
�@�����ŁA��⌻����������Ԃ��l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�Ȃ�قǁA�u�����̓����v�Ɋ��S�ɏ]���l�����邩������Ȃ��B�������A�啔���̐l�́A���܂��܂Ȋ������u�����v�ɂ��u����v�ɂ��]���Ă���B�܂��A�Ȃ��ɂ��u����v�̂����ނ��܂܁A�u�����v�ɂ͂܂������]��Ȃ��l������B���������u���R��ԁv���l������ł��傤�B
�@���̏ꍇ�ɂ́A�u���Q�v�Ƃ��A�u�����݁v�̑Ώۂ�ے肷��Ƃ����������Ƃ������Ă��܂��B�����Ă��܂��A�Ƃ����̂��ςł����A����ꍇ�ɂ́A�������������̂��u�L�v�v���Ɓ\�\�����Ƃ��Ă��u�P�v���ƌ��邱�ƂɂȂ�B
�@�������ɁA�u���܁v����u���݁v�Ԃ��ƁA�u�����݁v�͑��݂ɍی��Ȃ����傷��B�u�����݁v�ɂ��u���v�ŕ�A�Ƃ����̂��u�����̓����v�ł��k��S���E�藝�S�U�l�B�������A�u����v��ς���ȂǂƂ������Ƃ́A�ȒP�ɂł��邱�Ƃł͂���܂���B�u���v�ɕς���ꂽ�Ƃ��Ă��A������u���ށv�C����ς�������قǂ��u���v�ɂ܂łȂ�Ƃ͌���Ȃ��B����͋C����ς���O�ɁA�����炪����R�ɂȂ����Ǝv���āA��Q�������Ă��邩������܂���B��������Q����̂Ȃ�悢���A����́A�����̔�̂��Ƃɂ���u������ҁv�Ɋ�Q�������邩������Ȃ��B
�@���������Q��h���ɂ́A����ɏ����Ȋ�Q�������邩�A������C���������ċ��ꂳ����̂��L����������Ȃ��B
�@�����A���̏ꍇ�ɊԈႦ�Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́A����������i�����Ƃ�������Ă��A������u���`�v�Ƃ��čs�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����܂ł�����́A�u�����݁v�̔��I���A�܂����u���Q�v�Ȃ̂ł��B�i�������ɂ��̏ꍇ�A����ւ̃��A�N�V�������A�u�����݁v�u���Q�v�Ƃ�������̂܂܂ɍs����Ƃ͌���܂���B����Ȃ����邷�ׂẮA�u�����v�ɂ���čs�Ȃ����Ƃ��ł��邩��ł��k��4���藝59�l�B����������͂����܂Łu�����v�s�ׂ�u���Q�v���A�u�����v���哱�Ȃ�����s���čs�Ȃ��̂ł����āA�s�ׂ̈Ӗ����u���Q�v�łȂ��Ȃ�����A�u���`�v�u���炵�߁v�ɕω�����킯�ł͂���܂���j

�@�u���R��ԁv���u���`�v�͑��݂��܂���B�e�l���A�����̍l�����u�P�v�u���v�����߂Ă��邾���ł����āA���ՓI�ɒʗp�����u�P�v���u���v���u���`�v�����肦�Ȃ��̂ł��B�X�s�m�U���A�����̂悤�ɏ����Ă���Ƃ���ł��F
�u�k�藝�R�V�E�����Q�l�k�c�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���R����̂��Ƃł́A�P�ł���A���ł���A���ׂĂ̐l�X�̓��ӂɎx�����Ă�����̂����肦�Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�e�ՂɔF��������B�Ƃ����̂́A���R����̂��Ƃɂ�����̂͂��ׂāA���������̗��v�������v���߂��炵�A���������̋C�܂܂ɂ���āA�����l�I�ȗ��v�����Ƃ߂�Ƃ��������ɂ����āA�����P���A�܂����������肷��B�k�c�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂��Ƃ���A���R����ł́A�߂Ƃ������͍̂l�����Ȃ��B�k��S���l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.352.
�@����ɁA���R����ł́u���L���v�͑��݂��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�s���R�t�̕��ɂ́A�N���̂��̂ł���A�Ƃ����悤�Ȑ����͖������炾�B
�u�ނ��낷�ׂẮA������l�̏��L���Ȃ̂ł���B�v
�@���������āA�ޓ��Ƃ��A�N���̂��̂��u�D���v�Ƃ������Ƃ́A���肦�Ȃ��B
�u����������A���R����ł͐��`�Ƃ��A�܂����`�ɔ�����Ƃ�������悤�Ȃ��Ƃ́A�܂������N���肦�Ȃ��̂ł���B�k��S���E�藝�R�V�E�����Q�l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.353.
�@�������āA������u�����v���u����v�́g������ԁh���l���邱�Ƃɂ���āA�X�s�m�U���u���R��ԁv�̃C���[�W�́A���Ȃ��̉��������̂ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�Ƃ���ŁA�X�s�m�U�̍l�����u���R��ԁv�ɂ́A�����ЂƂd�v�ȓ���������܂��B����́A�����قǐG�ꂽ�A�l�X���O���[�v���Ȃ��Ă���Ƃ����_�ł��B�Ɨ������l�̏W���Ƃ��������A��������̎푰�����ї����Ă���悤�ȏ�ԂȂ̂ł��B���͂�����A������x�́u�����̓����v�������V�̂��ƂɁA�����́A�܂��͏����̐l�тƂ�����Ă���C���[�W�ł��B
�@�Ȃ��A�u���R��ԁv�̍ŏ�����A�Ɨ������o���o���̌l�ł͂Ȃ��A���̂悤�ɃO���[�v�ɂȂ��Ă���̂��Ƃ����ƁA�l�Ԃɂ́g�s���R�t�̋��Ёh�����邩��ł��B�g�s���R�t�̋��Ёh�̂��Ƃł́A�l�Ԃ͌Ǘ����Ă͐������Ȃ��B���̂��Ƃ́A�����̕����ŁA���͂�����Əq�ׂ��Ă��܂��F
�u�k�藝�R�T�E�����l�Ƃ��낪�l�Ԃ������̓����ɏ]���Đ������邱�Ƃ́A�܂�ł���B�ނ���ނ�̂������ł͓i�݂������₦�Ȃ����A�������ɕs�a���܂��������̂�����ł���B�����A����ɂ�������炸�A�k�c�l�l�Ԃ̋����Љ��́A��Q�����A�͂邩�ɑ����̗��v�����܂�Ă���̂�����ł���B
�@���������ĕ��h�Ƃɂ��k�c�l�A�l�ԓI�Ȃ��Ƃ���������킹��̂��悩�낤���A�܂��_�w�҂ɂ͂��̐l�ԓI�Ȃ��Ƃ���킹�Ă����̂��悩�낤�B�܂��l�Ԃ��炢�Ȏ҂ɂ͂ł��邾���A�k�c�l�l�Ԃ̂��A��b���ق߂�����������̂��悩�낤�B�Ƃ��낪�ނ�́A���������̕K���i��l�ԓ��m�̋��͂ɂ���Ă���߂ėe�ՂɎ��������̂��߂ɗp�ӂ��邱�ƁA�����Ă������ɗ͂����킹�邱�ƁA���ꂪ�Ȃ���A������Ƃ��납�狺�ЂƂȂ��Ă��܂�댯�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����������o������킩��ł��낤�B�k��S���l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.343-344.
�@�����̏��q������ƁA�����قǁk�藝�R�V�E�����Q�l�̍ŏ��Ō����u�ی�v�Ƃ������Ƃ��A�l�Ɛl�Ƃ̊Ԃ̕s������x�z��O��Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��킩��܂��B�O���[�v���������݊Ԃɂ́A�i���͂Ȃ��̂ł��B�����A���͂ƒq�b����葽�����҂��A���̎҂̃��[�_�[�ƂȂ��āu�ی�v���Ă����Ԃƍl����ׂ��ł��傤�B
�@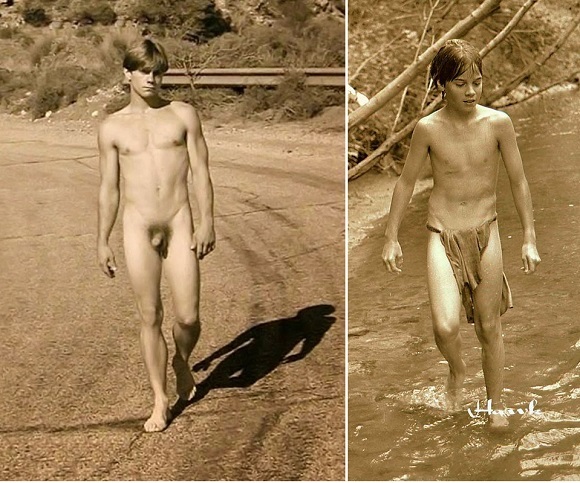
�@���̂悤�ȃX�s�m�U���u���R��ԁv�̃C���[�W�́A���ڂɒl����Ǝv���܂��B�����A����́A�Љ�Ƃ��Ă͂��܂�ɂ��s����ł��傤�B
�@�O���[�v�ƃO���[�v�̂������ŁA���������N���邩�킩��Ȃ��B�u����v�I�ɂȂ��Ė\�͂��ӂ邤�O���[�v��}���邽�߂ɍs�Ȃ����Њd���A�푈�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ͒������Ȃ��͂��ł��B�݂̂Ȃ炸�A�O���[�v�̓����ł��A���V���w���̂����������A����ƕ������N����ł��傤�B���V���u�����̓����v�ɏ]���ČĂт��������Ѝs���ł����Ă��A���������́A�u���Q�v�̊���ɓ�������Ďc�s�s�ׂɋy�Ԃ�������Ȃ��B�����āA�u���Q�v�͔j����A�j����u���Q�v���ĂсA�O���[�v�͗����W�U���J��Ԃ��B����A���O���[�v�S�̂��E�������ď��ł��邩������܂���B
�@�����Ŏ���́A�X�s�m�U�̍l�����g�Љ�_��h���������Ǝv���܂��B�g�Љ�_��h�ɂ���āA���Ƃ̂Ȃ����肵���Љ������邱�Ƃ͉\���H �������̊S�́A�����ɂ���܂��B
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@


 �@
�@
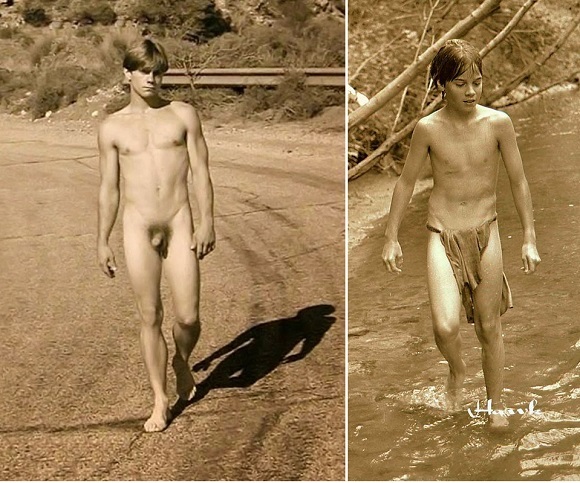
 �c
�c