02/17�̓��L
09�F12
�y�K�Ǐ�150�z�X�s�m�U�w�G�e�B�J�x(3)�\�\�\�Ȋw�̎����ɂ�����u�_�v�́A���邩�H
---------------
.
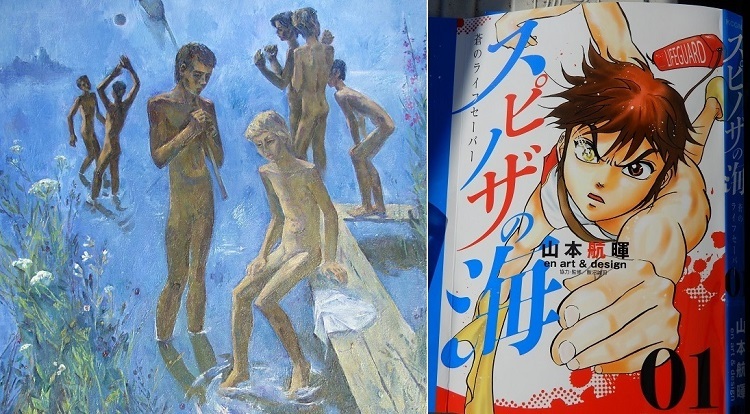 �@
�@
�@�����́B(º.-)���
�@�y�K�Ǐ�150�z�X�s�m�U�w�G�e�B�J�x(2)����̂Â��ł��B
�@�y10�z�g�K�R���h�ɁA���܂��������͂Ȃ��B
�@�O��̃e�[�}�F�s���R�t���A�������������������悤�B
�@�O��̍Ō�́A
�@�_�ɂ��l�Ԃɂ��A�u���R�ӎu�v�͖����B
�@�Ƃ������Ƃ������B�������ɂ́u�l�ԁv���C�ɂȂ邪�A�u�_�v�͂ǂ����H ���傤�́u�_�v����͂��߂悤�B
�u�P�@�X�s�m�U�͐_���[�l������T�O�A�܂�_���l�ԂɎ��Ă���Ƃ���T�O�����₷��B�k�c�l
�@�_�͗~�]�⊴��͎����Ȃ��B�_���N�����������葞�肷�邱�Ƃ͂Ȃ��k�c�l�_���{������A���Q������A���i���邱�Ƃ��Ȃ��B�_�͉��◧�@�ҁA�ٔ����̂悤�Ȃ��̂ł��Ȃ��i�_�͖��߂��o�����Ƃ͂Ȃ����A���]��s���]�𗝗R�ɁA���蔱�����肵�悤�Ɩ͍����邱�Ƃ��Ȃ��j�B
�@������A�_�̍s�����A�l�Ԃ̍s�����������ۂ̖��^�Ő������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�k�c�l
�@���̂��Ƃ��疾�炩�ɂ������_�ł��������B�X�s�m�U�̌����ɂ��A�F���ɂ͉��̖ړI���Ȃ��B�F���ɂ͕��������Ȃ��i���邢�͐�[���Ȃ��j�ƌ����Ă��悢��������Ȃ��B
�@�Q�@�P�Ƃ����ڂɊW����̂��A�_���i�X�s�m�U�̌����ɂ��������j���R�ӎu�������Ȃ��Ƃ������肾�B�v
�`���[���Y�E�W�����b�g�C�Ί_����E��w�m�̋��ȏ��X�s�m�U�x,2015,�u�k��,�I�����`�G592,pp.58-60.
�@�܂�A�s�_�C�R�[�����R�t�́A�g�ړI�h�Ȃ����u�������v�������Ȃ��B�X�s�m�U�̍l���ł́A�u�K�R���v�́A�Ȃɂ����̕��������������̂ł͂Ȃ��̂��B
�@�������́A�u�K�R���v�Ƃ����ƁA��������̕��������������̂��ƁA���O�ɍl���Ă��܂��X��������܂��B�}���N�X��`�҂��g�j�I�B���_�h��炪�A���������������Z��������������������Ȃ����A���ꂾ���ł͂Ȃ��A�ނ�ɔ�����g�ߑ㉻�_�ҁh�����āg�����ېV�_�ҁh�����āA�������傭�������Ƃ������Ă���B�Љ�͐i������A�����́A�Ȋw�́A���E�́A�����Ɍ������Ĕ��W���Ă���B�c�c���������A�u�ېV�v�Ƃ����R�g�o���A�V�������Ƃ͂������Ƃ��d�Ƃ�����������ӂ�T���Ă���B
�@�������A�s�_�C�R�[�����R�t�́u�K�R���v�ɂ́A�������ȂǂȂ��B���̐��E�̖@���́A�e�Ƃ����͂������ƁA�������̕��͉̂����x�e/���œ����o���ƌ����Ă��邾���ŁA�����ɂ͕��������ړI���Ȃ��B�F���S�̂ɂ��A���������^�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�F���̖@���́A���������鑬�x�ł͉^���ł��Ȃ��A�������̕���������2�̃G�l���M�[�ɓ]������ƌ����Ă��邾���ŁA�����牽���ǂ��Ȃ�Ƃ����悤�Ȍ��߂�ꂽ�������͂Ȃ��̂��B
�@����܂łɔ����������R�@���̒��ŁA�B��A���������������@���́A�u�G���g���s�[�͑��傷��v�Ƃ����M�͊w��Q�@���������낤�B�������A���̈Ӗ��́A�F���S�̂�����Ɍ������Ă���A�����͋ώ������ăX�[�v�̂悤�ɂȂ��Ă��܂������������Ă���A�Ƃ����������B����ꂪ�g�߂Ɍ��錻�ۂ́A����Ƃ͋t�ɁA���X���萶������A������l�Ԃ�����������A�����₳�܂��܂ȕ������������ɕ��G�ȑg�D���čs�����肵�Ă���B�������傭�A�����̐��E�́A�l�Ԃ��C�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ȁg�������h������Ă͂��Ȃ��̂��B
�@���̂悤�ɍl���Ă݂�ƁA�X�s�m�U�́A�������ɁA���낵���̂悤�ȁA�܂��ÂȐ��E�������Ă���悤�ȋC�����܂��B�g���������Ȃ��h�Ƃ������Ƃ́A�ǂ��Ɍ������Ă��邩�킩��Ȃ��A�ڂ̑O���܂��Âʼn��������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�����B�������́A���������͂ǂ����Ɍ������Ă���̂��ƐM�������A�g�������h�������Ăق����A�Ǝv���B���ꂪ�A�������ɂ������悤�̂Ȃ��l�ԂƂ������̂̐��ȂȂ̂ł��傤�B����Ȃ�A����ł悢�ł͂Ȃ����B�g�������h�����������Ƃ�������A�g�������h������Ƃ���������ϔO�i�z���m �C�}�M�i�`�I�j�A����͂���ł悢�̂��B�������邱�Ƃ��L�v�ȏꍇ������A�����A�ق�Ƃ��͂���Ȃ��̂͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ����m���Ă���悢�B�X�s�m�U�́A���������̂ł��B
�@������A�_�́s���R�ӎu�t�������Ȃ��B
�@�c�c�������āA�u�K�R���v�ɂ͕������Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�A�ނ���u�K�R���v�̂ق�����A�s���R�t�̃C���[�W�ɋ߂Â��Ă����悤�ȋC�����܂��B�g�s���R�t�C�R�[���u�K�R���v�h�Ƃ����Ӗڂ̃p���h�b�N�X���A�����炩�����ł�����̂ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B

�u�X�s�m�U�́A�_���ӎu�������Ƃ�ے肷��̂ł͂Ȃ��A�_�̈ӎu�͐_�̒m����含�ł���Ƃ��A�_���������ǂ����������Ƃ����ӎu�������Ƃ́A�_������͂��̂悤�Ȃ��̂ł���Ɨ����Ȃ����F�����邱�Ƃɓ������Ǝ咣����B�v
�`���[���Y�E�W�����b�g�C�Ί_����E��w�m�̋��ȏ��X�s�m�U�x,2015,�u�k��,�I�����`�G592,p.60.
�@�܂�A�X�s�m�U�̍l���ł́A�u�ӎu�v�Ƃ́A����ɔF�����邱�Ƃɂ����Ȃ��B�u�ӎu�v�Ɓu�F���v�̂������ɈႢ�͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�u�_�v�ɂƂ��Ă��ׂẮg�K�R���h������B�_���A�u�����������v�Ǝv���āA�u���������v�Ƃ��Ă��G�d���邢�́A�u����͕K�R�I�ɁA�������v�Ɨ������āA�u��������(�����Ȃ���)�v�Ƃ��Ă��A�ǂ�����܂������������ƂȂ̂��B
�@�u���l�`����ꂿ������B�v�ƌ����ċ����q�ɑ��āA��l�͌����F�u��ꂽ��Ȃ��āA���Ȃ�������ł���H�v�d�������A�q���̌������Ƃɂ��A�����̈ꂩ�͐^��������B�q���̌��̉����̈ꂩ�́A�_�̌��t�����炾�B
�u�܂��A�X�s�m�U�͂����咣����B�_�̈ӎu�́A���̂�������̂Ɠ��l�ɁA�_�̖{����{������K�R�I�ɐ�������̂ł���A�������k�M�g�����\�\�\�s�_�����R�t�̒��Ɂl����I�Ȍ����������Ă���B�_�͕K�R�I�ɐ_���s������悤�ɍs�����邪�A����͐_�̖{���Ȃ����{���̂����ł����āA�_�����R�ȁi�܂�A�����̂Ȃ��j�ӎu�������Ă��邩��ł͂Ȃ��B�v
�`���[���Y�E�W�����b�g�C�Ί_����E��w�m�̋��ȏ��X�s�m�U�x,2015,�u�k��,�I�����`�G592,pp.60-61.
�@�������A����Ȃ�A�_���s���R�t�Ƃ͉��Ȃ̂��H �_�́A�����Ȃ�Ӗ����s���R�t�Ȃ̂��H
�u�������A�X�s�m�U�́A�_�͂܂������ʂ̈Ӗ��Ŏ��R�ł���Ƃ��咣����B�Ȃ��Ȃ�A�_�͎��Ȃ̗L��l�����S�Ɏ��Ȍ��肵�Ă��邩��ł���B�v
�`���[���Y�E�W�����b�g�C�Ί_����E��w�m�̋��ȏ��X�s�m�U�x,2015,�u�k��,�I�����`�G592,p.61.
�@���́g���Ȍ���h�̈Ӗ��ł��s���R�t���A�O��ɏڂ��������k��`�V�l�ł��傤�F
�u���R�Ƃ�������̂́A�݂�����̖{���̕K�R���ɂ���Ă̂ݑ��݂��A���ꎩ�g�̖{���ɂ���Ă̂݊�������悤�Ɍ��肳�����̂ł���B��������ɔ����āA�K�R�I���邢�͂ނ��닭������Ă���Ƃ�������̂́A���̎d���ő��݂��A��p����悤�ɑ��̂��̂ɂ���Č��肳�����̂ł���B�k��P���A��`�V�l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.4-5.
�@�s�_�C�R�[�����R�t���s���R�t�Ƃ́A�s�_�t���g�̖{���ł���E�����̂Ȃ��u�K�R���v�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�u�X�s�m�U�́w���R�x�̒�`�i��`�V�j�k�c�l
�@�X�s�m�U�͎��Ȍ��茠�Ƃ��Ă̎��R�Ƃ����T�O���Ă���B�k�c�l
�@�_�́A���̖{���̕K�R���ɂ���đ��݂��i�藝11�j�A���̖{���̕K�R���݂̂ɂ���čs������̂�����i�藝11�j�A���S�Ɏ��R�ł���i�X�s�m�U�͂����ŁA�s�����A�����ނ��ƁA���邢�͉����̌����ɂȂ邱�ƂƑ����Ă���j�B�܂��A���S�Ɏ��R�Ȃ̂͐_�݂̂ł���i���̂��ׂĂ̂��̂͐_���琶�܂�Ă��邩��ł���j�B�v
�`���[���Y�E�W�����b�g�C�Ί_����E��w�m�̋��ȏ��X�s�m�U�x,2015,�u�k��,�I�����`�G592,p.76.
�@����ł́A�l�Ԃ��s���R�t�ɂ��ẮA�ǂ��Ȃ̂ł��傤���H
�u�X�s�m�U�́w�G�`�J�x�̌㔼�ŁA�l�Ԃ̎��R�������悤�ȈӖ��Łi�܂��X�̍s������X�̖{���𗝗R�Ɍ��肳���͈͓��Łj�\�ł���Ǝ咣����i��S���̒藝68, ��T���̒藝36�̔��l�j�B�v
�`���[���Y�E�W�����b�g�C�Ί_����E��w�m�̋��ȏ��X�s�m�U�x,2015,�u�k��,�I�����`�G592,pp.76-77.
�@�܂�A�l�Ԃɂ��s���R�t�͂���B����́u�K�R���v�Ɛ藣���Ȃ����̂����A����ł��A�l�Ԃ��s���R�t�͂���B����́A�w�G�e�B�J�x�̌㔼�ɏ�����Ă���B
�@�������Ă悤�₭�A�X�s�m�U�̍l����l�Ԃ��s���R�t�\�\�\���̎��������ނ��Ƃ��ł��܂����B
�@�����ŁA�W�����b�g���w�E����k��T���E�藝�R�U�E�����l��������ƌ��Ă݂����Ǝv���܂����A���̂܂��ɁA�w�G�e�B�J�x�̑O���ƌ㔼�̊W�ɂ��āA�Q�l���Œ��ׂĂ����܂��B
�@
�@�@�q���X�c�F���x���N�u�_�E�R�X�^�Ɨc���̃X�s�m�U�v
�@�@�E���G���E�_�E�R�X�^�́A���_�����̐M�����߂�
�@�@���Q�̃|���g�K������A���X�e���_���ɂ���Ă���
�@�@���_���l�B�������A���n�̃��_�������Q��j��
�@�@����Ď��������B�X�s�m�U�W�̎��������B
�@�y11�z�w�G�e�B�J�x�̍\�z�̕ϑJ
�u�ނ̎咘�́w�G�e�B�J�x�ł��邪�A�ނ� 1662�N�̏I��荠���炻��������n�߁A��63�N�̂͂��߂ɂ͑�P���́u�_�ɂ��āv�̑��e���ނ̃A���X�e���_���̗F�l�����̂������ʼn���Ă����k�c�l 65�N3���A�F�l�ɂ��Ă������k�c�l���猩�āA���̎����ɂ͑����i�����Ă����悤�ł���B
�@���̎����́w�G�e�B�J�x�͂R�����琬����̂Ƃ��č\�z����Ă����B����́w�G�e�B�J�x�̑O�g�A�w�_�A�l�Ԃ���ѐl�Ԃ̍K���Ɋւ���Z�_���x�̎��Ƃ��Ă̐_�A�l�Ԃ���ѐl�Ԃ̍K���ɑΉ�������̂ł������B���N 6���ɂ͂��̑�3���̏I���̂Ƃ���������Ă���A�قڊ����ɋ߂Â��Ă����̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A���N�H�ɂ͂���𒆒f���āA�w�_�w�E�����_�x�̎��M�Ɏ�肩�������B���̏����ɂ͖�5�N�̍Ό����������A70�N�ɏo�ł��ꂽ�B�X�s�m�U�͂��̌ソ�����Ɂw�G�e�B�J�x�̎��M���ĊJ���A�R�����琬����̂��T���ɉ��߁A1675�N�Ɋ��������邱�Ƃ��ł����B�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.2-4.
�@�܂�A�w�_�w�E�����_�x�ɂ�钆�f�̌�ɁA�w�G�e�B�J�x�̍\�z�ύX�Ȃ����g�[���������悤�ł��B�͗��Ă��r���Ă݂�ƁF
�u�_�ɂ��āv�@�@�@�@�@���u��P�� �_�ɂ��āv
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u��Q�� ���_�̖{���ƋN���ɂ��āv
�u�l�Ԃɂ��āv�@�@�@�@�@�u��R�� ����̋N���Ɩ{���ɂ��āv
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u��S�� �l�Ԃ̗�]���邢�͊���̗͂ɂ��āv
�u�l�Ԃ̍K���ɂ��āv�@���u��T�� �m���̔\�͂��邢�͐l�Ԃ����R�ɂ��āv
�@�����\�z�́u��Q�� �l�Ԃɂ��āv����Q�E�R�E�S���Ɋg�[����A�u��R�� �l�Ԃ̍K���ɂ��āv�́A�l�Ԃ̎��R���e�[�}�Ƃ����T���ɉ��߂��Ă��܂��B
�@�������ꂽ�w�G�e�B�J�x������ƁA��T���̃e�[�}�́u�l�Ԃ̎��R�v�ŁA�u�����v�̂͂��߂ɂ́A�����̂悤�ɏ�����Ă��܂��B�������A�u��T���v�̓��e�Ɂu���R�v�Ƃ����R�g�o�́A�قƂ�Ǐo�Ă��Ȃ��̂ł��B��T���S�̂́A�ނ���l�Ԃ̋��ɂ̍K���������Ă���悤�Ɍ����܂��B
�u�Ō�Ɏ��́A���������R�ւƓ������@���邢�͂��̎�i�Ɋւ���ϗ��w�̑��̕����ɂ���B����䂦�A���̕��ł͗����̔\�͂ɂ��Ę_���A�������̂��̂�����ɂ������ĉ����Ȃ����邩�A����ɐ��_�����R���邢�͎����Ƃ͉��ł��邩�������ł��낤�B�k�c�l�k��T���A�����l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.413.
�u�w�G�`�J�x��T���ł͂Q�̘b�肪�o�Ă���B�ŏ��̘b��́A�����͉�X�̎I�Ȋ�����ǂ̒��x�A�܂��ǂ̂悤�Ȏ�i�ŏ��ł�����i�Ȃ�����߂�j���Ƃ��ł��邩�Ƃ������̂��i�X�s�m�U�͂�������R�ɓ������@�Ƃ��ĕ`�ʂ��Ă���j�B���̘b�����舵���ہA�X�s�m�U�͐S���Ö@����Ă���B
�@�Q�Ԗڂ̘b��́A�l�Ԃ����R���̂��́i���邢�͐l�Ԃ̎����j�ɂ��āA�܂��A�����҂͖��m�Ȏ҂��ǂ�قNj���������舵�����̂ł���B�v
�`���[���Y�E�W�����b�g�C�Ί_����E��w�m�̋��ȏ��X�s�m�U�x,2015,�u�k��,�I�����`�G592,p.241.
�@�w�_�w�E�����_�x�o�łƁA�w�G�e�B�J�x�����̂������ɁA��̋��a�h��������̐��ςƃf�E�E�B�b�g�s�E�������N���Ă��܂��B���҂��Ă������R��`�̃��[�_�[���A����𐁂����܂ꂽ���O�ɂ���Ė��c�ɉ���E���ꂽ���������������ɁA�X�s�m�U�́A�l�ԂƂ������̂ɂ��āA��肢�������v����[�߂��ł��傤�B��Q�`�S���̊g�[�́A����ƊW�����邩������܂���B
�@�������A�s���R�t�Ɋւ��ẮA�ǂ��������̂ł��傤���H
�@�������ɁA��T���̕W��́A���\�z��R���́u�l�Ԃ̍K���v���u�l�Ԃ̎��R�v�ɕύX����Ă��܂��B�u��S���v�܂ł́A�n�[�h�ȁA���̂Ȃ��_���I��㈁A�@�B�I�Ȉ��ʊW��͂̏Փ˂��v�킹��l�@���܂����Ă���̂ɑ��A�u��T���v�ł́A����ɑ���u�S���Ö@�v�ȂǁA�\�t�g�Ȗʂ������܂��B

�A���X�e���_���A�܂̓�
�@����ł��A�k��S���E�t�^�l�̍Ō�̂Ƃ���ł́A�����̂悤�ɏ����Ă��܂��B���́k�t�^�l�́A�w�G�e�B�J�x�̐����ߒ��ŁA���ԓI�ɍŌ�ɂł����������Ƃ���Ă���̂ł��B�X�s�m�U�́A���������A�ǂ��������̂��A�l�Ԃ��s���R�t�ƍl���Ă����̂��H �w�G�e�B�J�x�������Ɠǂ݂���ł䂭�K�v�����肻���ł��B
�u�R�Q�@�������l�Ԃ̔\�͂́A����߂Đ�������Ă�����̂ł���A�܂��O���̌����̗͂ɂ���Ă�����Ȃ����킳��Ă���B�k�c�l
�@�����A���Ƃ������̗��v���l���������Ƃ����v���ɑΗ����邱�Ƃ������Ă��A�����́A���������̐Ӗ����ʂ��������ƁA�����̗͂͂������������قǏ\���łȂ��������ƁA�܂�����ꂪ�S���R�̈ꕔ���ł���A���̒����ɏ]���Ă��邱���Ȃǂ����o���Ă���Ȃ�A��Âɂ���ɂ�����ł��낤�B�������̂��Ƃ𖾗āE�����ɔF������Ȃ�A�m�I�F���ɂ���ċK�肳�������̂��̕����A����������A�����̂��悫�����́A����Ɋ��S�ɖ������A���̂����A���̖������Ŏ�����悤�ɓw�͂���ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A�����ɂ͒m�I�F���̂�邷�������K�R�I�Ȃ��̈ȊO�ɂ͉����~�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����A�܂���ʂɁA�^�Ȃ���̂̂����ɂ����S�̕��a�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A����ꂪ���̂��Ƃ𐳂����F������Ȃ�A���ꂾ���ł����̂�肷���ꂽ�����̓w�͂́A�S���R�̒����ƈ�v����̂ł���B�k��S���A�t�^�l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.411-412.
�@�����ŁA�����قǏh��ɂ��Ă������k��T���E�藝�R�U�E�����l��ǂ�ł݂�Ƃ��܂��F
�u�k�藝�R�T�l�@�_�͎������g���̒m�I���������Ĉ�����B
�@�k�藝�R�U�l�@�_�ɂ������鐸�_�̒m�I���́A�_���������g��������_�̈����̂��̂ł���B���������̏ꍇ�̐_�͖����ł��邩����̐_�ł͂Ȃ��A�i���̑��̂��Ƃōl�@�����l�Ԑ��_�̖{���ɂ���Đ��������_�ł���B����������A�_�ɂ������鐸�_�̒m�I���́A�_���������g�������閳���̈ꕔ�ł���B
�@�@�@�@�k�n�l�@���̋A���Ƃ��āA�_�͎������g�������邩����ɂ����Đl�Ԃ������A���������Ă܂��A�l�Ԃɂ�������_�̈��Ɛ_�ɂ������鐸�_�̒m�I���Ƃ͓������̂ł���Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�@�@�k�����l�@�ȏ�̂��Ƃ�������́A���������̋~�ς��邢�͎����A���邢�����R�����ɂ��ƂÂ��Ă��邩�𖾗Ăɗ�������B���Ȃ킿����́A�_�ɂ�������s�ς́A�i���̈����邢�͐l�Ԃɂ�������_�̈��̒��ɂ���B�������̈����邢�͎����́A�����ɂ����ĉh���i�O�����A�j�ƌĂ�Ă��邪�A����͕s���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�k�c�l
�@�k�c�l�����̐��_���A���̖{���Ƒ��݂Ɋւ��āA�ǂ̂悤�ɂ��āA�܂��ǂ̂悤�Ȏd���ŁA�_�I�{�����琶���Ă��邩�A�����Ă������_�Ɉˑ����Ă���̂ł��邩�A�Ƃ������Ƃ����炩�ƂȂ�B�k�c�l���́A��P���ɂ����Ă����������k���������Đl�Ԑ��_���l�A�{���Ƒ��݂Ɋւ��Đ_�Ɉˑ����Ă��邱�Ƃ���ʓI�Ɏ���������ǂ��k�c�l��������̖{�����̂��̂���A���̂��Ƃ����_����ꍇ�قǁA�����̐��_�����������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł���B�k��T���l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.452-454.
�@�l�Ԃ́A�ق��̐����╨�̂Ɠ����悤�ɁA�s�_���Ȃ킿���R�t�̈ꕔ�ł�����A�l�Ԃ̐_�ւ́u�m�I���v�́A�u�_���������g�������閳���̈��v�̈ꕔ�ł��邱�ƂɂȂ�܂��B�����āA�u�_���������g�������鈤�v�́A�u�l�Ԃɂ�������_�̈��v���ӂ���ł��܂��B
�@�X�s�m�U�́A�l�Ԃ��s���R�t���A�����i�ō��̍K���A��сj���A���́g�_�̎��Ȉ��h�A���Ȃ킿�_�Ɛl�Ԃ̂������̑o�����́E����́u���v�̒��ɂ���Ƃ���̂ł��B
�@�����āA�u��������̖{�����̂��̂���A���̂��Ƃ����_����ꍇ�قǁA�����̐��_�����������邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ܂ŏq�ׂĂ��܂��B��������̒��ɁA�s�_�t�̑��݂Ɓs�_�t���s���R�t�ɑ��鈤�������сB�g�_�́A�ו��ɂ����h�苋���h�Ƃ������Ƃł��傤���H
�@�������A�����ɐl�Ԃ��s���R�t������Ƃ����Ӗ��́H�d�d
�@��͂�A�X�s�m�U�́g���_�h���L���ꂽ�u��T���v���A�ꑫ���тɗ������悤�Ƃ��Ă�����悤�ł��B�@
�@�܂��́A�u��P���v����͂��߂邱�ƂƂ��܂��傤�B
�@�y12�z�g�_�̑��ݏؖ��h�̓��
�@�X�s�m�U�ɂƂ��āA�u��P���v�ŏ��̓�ւ́A�g�_�̑��ݏؖ��h�ł������낤�B�u�_�͑��݂���v�\�\�\���ꂪ�����Ȃ��N�w�́A���_�_�ɂȂ��Ă��܂��B���_�_���g�s�����h���̂́A19���I���Ƀj�[�`�F���u�_�͎��v�ƂԂ������Ă���̂��Ƃ��B����܂ŁA���[���b�p�ɂ́A�u�_�͑��݂��Ȃ��v�ƊJ���������N�w�҂͂��Ȃ������B
�@�L���X�g���M���l�тƂ̐S�ɂ��݂킽���Ă������E�ł́A�g�_�̑��݁h��M���邱�Ƃ́A���₷���B�������A����𗝘_�ŁA�s�����t�ŏؖ�����ƂȂ�ƁA���ɂ�������Ȃ��ƂɂȂ�B
 �@
�@
�@�N�w�j��A�_���u�w���ݘ_�I�ؖ��x�ɂ͂������o�[�W���������邪�A��{�I�ɂ́w�_�ɂ͑��݂���Ƃ������Ƃ��K�R�I�ɑ�����x�ƔF�߂����Ă����āA�w������_�͕K�R�I�ɑ��݂���x�ƌ��_����B���͂��́A�v�l�K�R���猻���ւ̈ڍs�ł���B���̒��Łw�����ށA�������ɑ��݂��Ȃ��悤�Ȑ_�͐_�Ƃ͌����Ȃ��Ȃ��Ȃ��x�Ɣ[����������Ƃ����āA�w������_�͌����ɑ��݂��Ă���̂��x�ƌ������낤���B�k�c�l
�@����͓��R�̋^�f���Ǝv���B�v
���C�w�X�s�m�U�̐��E�\�\�_���邢�͎��R�x,2005,�u�k��,����V�� 1783,p.93.
�u�_�����݂��邱�Ƃ��ؖ�������@�́A �`���I�ɎO����(�ƃJ���g���܂Ƃ߂�)�B �����͒ʏ�A ���ݘ_�I�ؖ�(ontological argument)�A �F���_�I�ؖ�(cosmological argument)�A �ړI�_�I�ؖ�(teleological argument)�ƌĂ��B
�@[���ݘ_�I�ؖ�] �����̐_�w�҃A���Z�����X���莮�������_�̑��ݏؖ��B�w�_�͊����ł���B�Ƃ���ŁA���݂��Ȃ��_�Ƒ��݂���_���ׂ��ꍇ�A ���炩�ɑ��݂���_�̕��������ł���B���������āA�_�͑��݂���B�x���̏ؖ��ɑ��ẮA�J���g���ᔻ�����B�v
�u���ݘ_�I�ؖ�
�@�_�̑��݂̏ؖ��@�̈�B���̂����Ȃ���Ȃ鑶�݂Ƃ����_�̊ϔO���l����ƁC�_�͊T�O�I�ɑ��݂��邾���łȂ����݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����l���Ȃ���C���̂����Ȃ���Ȃ鑶�݂Ƃ����ϔO�ɖ������邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��Ȃ�C�T�O�I���݂������݂̂ق����C����Ȃ鑶�݂ł���͂�������C�Ƃ������́B�A���Z�����X����o���C�f�J���g���Ǝ��̗��ꂩ�瓯�l�̏ؖ����o�����B�A���Z�����X�ɑ��Ă̓g�}�X�E�A�N�B�i�X���ᔻ���C�f�J���g�́w�Ȏ@�x�ɑ�����̔��_�ւ̓��قŁC���̃g�}�X�̔ᔻ��_���Ă���B�J���g���C���̏ؖ��@��ᔻ���Ă���B�v
�@�������A�X�s�m�U�̏ꍇ�ɂ́A�g���ݏؖ��h�̃n�[�h���͒Ⴉ�����̂ł͂Ȃ����d�Ƃ����C�����܂��B�Ƃ����̂́A�s�_���Ȃ킿���R�t�Ƃ������Ƃł���A���̉F���̑��݂�ے肷��l�͂��Ȃ��ł��傤����A���������f�p�Ȏ��݊��̏�ɗ����āA�u����͐_����B�v�Ɛ�����������킯�ł��B�f�J���g�̂悤�ɁA���Ɍ����Ă鐢�E�͈��������ǂ킩���Č����Ă��錶�e�ł͂Ȃ����H �n�ʂ�����A�ق�Ƃ��͖����̂ł͂Ȃ����H ����A�����v���ċ^���Ă���g���h�����́A��ɂ���B���v���A�䂦�ɂ�ꂠ��B�d�d�ȂǂƂ܂�肭�ǂ����������˂�C�́A�X�s�m�U�ɂ͂��炳��Ȃ��̂ł��B
�@�������̑f�p�Ȑ������o��M���āA����ɗ��r���A�����ɗ����̌��ĂĂ���ɍl���Ă䂭�\�\�\���������̂��A�X�s�m�U�̂����Ȃ̂��Ǝv���܂��B
�@�������ɁA�w�G�e�B�J�x�́u��P���v�ł́A�g�_�̑��ݏؖ��h������Ă��܂����A�g���ݏؖ��h���̂ɂ́A�傫�ȗ͓_�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����H
�@�Ⴊ�悢���ǂ����킩��܂��A�X�s�m�U�́A�g�R�̐_�̑��ݏؖ��h�Ǝ��Ă���Ǝv���̂ł��B�u�ق�A�����̎R���g�R�̐_�h���B�v�ƌ���ꂽ��A�N���A���̎R�̑��݂�ے肷�邱�Ƃ͂ł��܂���B�����A���́A���̎R�ɐ_�i�����邩�ǂ������\�\�\�Ƃ������b�ł��B
�@�u�s���R�t�����Ȃ킿�_�ł���B�v�ƃX�s�m�U�͌����܂��B�N�w�I�Ș_�̓��ۂ͂Ƃ������A���o�I�ɂ͒N���A�g�s���R�t�����݂���h�Ƃ������Ƃ�ے�ł��܂���B��������A���͂ނ���A�s���R�t�́A�_�ƌĂԂɂӂ��킵���̂��H ���̑�F���́A�_�ƌĂ��ɂӂ��킵���A�ǂ�Ȑ�����@�\�������Ă���̂��H�d�����������Ƃł͂Ȃ����B
�@�܂�A�l�Ԃ��s���R�t���s���R�t�̒��̂��܂��܂Ȍ��ۂ��A�ǂ̂悤�ɑ��݂��A�ǂ̂悤�ɓ��������Ă���̂��H�\�\�X�s�m�U�ɂƂ��ẮA������̂ق����A�g�_�̑��݁h���̂��̂����d��Ȗ��Ȃ̂��Ǝv���܂��B���������āA����ɑ��ẮA���̒���S�̂������ɂȂ��Ă���̂ł��B
�@�����ЂƂA�X�s�m�U�̏ꍇ�̓��F�́A�g�������_�����݂���Ƃ�����A�����������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��h�Ƃ����_���W�J�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��B���������ϓ_����A�͂��߂Ɂu�_�v�̊�{�I�Ȑ����E��������`����A�����������̂́A�s���R�t�S�̂ł���ق��Ȃ����Ƃ�������A����ɁA�s�_�����R�t�̒��ŋN���邳�܂��܂Ȍ��ۂ��W�J����Ă����܂��B
�@�܂�A
�Z�@�u�_�v�����݂���Ƃ�����A�s���R�t�ƃC�R�[���̐_�ȊO�ɂ́A���肦�Ȃ��B
�@�Ƃ����ے�I�Ȍ����ɁA���傫�ȑ_��������̂ł͂Ȃ����H ����������ۂ�����܂��B�ł�����A������̐l�тƂɁA���̒��삪�g���_�_�h�̂悤�Ɍ������̂��A�������̂Ȃ����Ƃ�������������܂���B
�@�������A�w�G�e�B�J�x��ǂݐi�߂Ă����ƁA�s���R�t�ɑ���X�s�m�U�̈،h���A���������Ŋ������܂��B�R�g�o�ƕ��͂́A���w�̋��ȏ��̂悤�ŁA�������������Ȃ��_�����X�ƂÂ������ł����A�ЂƂ܂Ƃ܂�̒��ɓ���āA��䍂��Ȃ��痝�����悤�Ƃ��Ă���ƁA���҂̎咣�̑S�̂���A�s���R���Ȃ킿�_�t�ւ̈،h�\�\�\�X�s�m�U�́u�_�ւ̒m�I���v�ƌ����Ă��܂����\�\�\���A�܂�����Ȃ��������܂��B
�@�g�s���R�t�C�R�[���u�K�R�v�h�̘_�����A������l�߂Ă䂯�䂭�قNJ�������̂́A�s���R�t�ւ̈،h�A�_�ɑ��鐒�����̊���ł��B
�@�Ƃ���ŁA�w�����x�ɂ́A�_�������ŁA�u�킽���͑��݂���B�v�ƌ������Ă���ӏ�������܂��B�g�}�X�E�A�N�B�i�X���A�w�X���}(�_�w��S)�x�́g�_�̑��ݏؖ��h���������̖͂`���ŁA���������p���Ă��܂��F
�u��R�� [I, Q. 2, Art. 3]
�@�_�͑��݂��邩�H
�@�_�����g���F�w���͑��݂���҂ł���B�x(Ex. 3:14)�Ƌ��Ă���B�v
�u�_���[�Z�ɂ��Ђ��܂Ђ���͉�͗L�č݂�҂Ȃ�k���������E�o���y�L 3:14�l�v
�u13 Moses said to God, �gSuppose I go to the Israelites and say to them, �eThe God of your fathers has sent me to you,�f and they ask me, �eWhat is his name?�f Then what shall I tell them?�h
�@�k�o�G�W�v�g�L 3��13�߁@���[�Z�͐_�Ɍ������A�w�l���Ă݂Ă��������B�����C�X���G���тƂ�̂Ƃ���֍s���āA�ނ�Ɂu���Ȃ������̕��c�̐_���A�������Ȃ������Ɍ��킳�ꂽ�B�v�ƌ����ƁA�ނ�́A�u���̕��́A���Ƃ��������O�ł����H�v�Ɛq�˂�ł��傤�B����������A���͔ނ�ɉ��Ɠ�����̂ł��傤���H�x�l
�@14 God said to Moses, �gI am who I am. This is what you are to say to the Israelites: �eI am has sent me to you.�f�h
�@�k14�߁@�_�̓��[�Z�Ɍ������A�w�킽���́A�킽�����݂�҂ł���B���Ȃ����C�X���G���тƂ�Ɍ����ׂ��́A�����ł���F�u�킽�����݂邪�A�������Ȃ������Ɍ��킳�ꂽ�̂��B�v�x�l�v
�@���́A���̕����́A�ނ������炳�܂��܂ȓǂݕ�������Ƃ���ŁA�m�h�u(�V������)�̖���A�����Ƃ��܂��܂ł��B�S�̂�����́A�e�@�h�̐������A������ŁF���V������E�ҏW�ψ��@���o�v�e�X�g�@���_�̋���A��
�@���{�����A������ƐV������ł͈���Ă��邭�炢�ł��B�����ł́A�p����̂�܂����B�gI am who I am.�h�́A�قƂ�ǃw�u���C�ꌴ���̒������ł��B
�@�Ӗ��[�ȉ��߂͂��낢�날��悤�ł����A���͂��̉ӏ���ǂނ��тɁA�Ȃɂ��A�_�����[�Z�����炩���Č����Ă���悤�ȋC������̂ł��B����ȃg���`���J���Ȃ��Ƃ������āA�C�X���G���l�������[������Ƃ́A�Ƃ��Ă��v���Ȃ�����ł���
�@�������A�g�}�X�E�A�N�B�i�X�����p���Ă��邭�炢�ł�����A����́g�_�̑��݁h�̂�������ł��B�i���ꎩ�̂́A���ݏؖ��ł͂���܂���j
�@�ǂ����A�X�s�m�U�́A���̍����ɒ����ɉ����āA�_�����Ă���悤�Ȃ̂ł��B
�@�y12�z�Ȋw�Ɩ������Ȃ��̂́A�ǂ�ȁu�_�v���H
�@����ɍs���A���S�ɋA��A�Ȋw�̂��ƂȂǂ�������Y��Đ_�Ɍ������ċF��B�ƂɋA���ė���ƁA�����ւ��āA�_�̂��Ƃ͖Y��Ď������͂��߂�B����Ȃ��Ƃ������́A�����������܂ő�����̂��H
�@�X�s�m�U�͍l����B������������d�˂Ă��A�_�̑��݂������ė��Ȃ��̂��Ƃ�����A�c�c���������ӂ��ɂ���ƁA�ǂ����Ă��_�̑��݂��ؖ�����Ă��܂��悤�ȁA�Ȋw�Ƃ��������Ȃ��������A���Ă�悢�̂ł͂Ȃ����H �����������������Ă���A�Ȋw�͐_�̑��݂Ɩ������Ȃ��B�������Ȃ������łȂ��A�Ȋw�͏@���ƈ�v����I
�@
�@�@Kimi Schaller
�@�����ŁA�g�����h�ł͍ŏ�����u�_�v���o�����̂ł͂Ȃ��A�@�܂��A�u���́v�Ƃ������̂��l����B�u����(�X�u�X�^���`�A)�v�Ƃ́A�g�^�ɑ��݂�����́h�g���̏������肸�ɂ��ꎩ�g�ő��݂�����́h�Ƃ����悤�ȈӖ��ł��B
�@�A�u���́v���A�u�L��č݂���́v�\�\���݂��邱�Ƃ��{���ł���悤�Ȃ��̂Ƃ��āA��`����B
�@�B���ɁA�u�_�v���`����B�u�_�v�Ƃ������̂���������Ƃ���A���̂悤�Ȃ��̂łȂ���Ȃ�Ȃ����낤�A����������`������B
�@�C���̒�`���牉㈂���ƁA�u�_�v�Ƃ��u���́v�ɂق��Ȃ�Ȃ��\�\�\���Ƃ������B���������āA�u�_�v�́A���݂��邱�Ƃ�{���Ƃ�����̂ł���B
�@��������A�_�̑��݂��ؖ������̂ł͂Ȃ����H �X�s�m�U�́A���̂悤�ȁg�헪�h�𗧂ĂāA�_���͂��߂܂��B
�u�P�@���Ȍ����Ƃ́A���̖{�������݂��ӂ��ނ��́A����������A���̖{�������݂���Ƃ����l�����Ȃ����̂̂��Ƃł���B
�@�Q�@�����{���������̂��̂ɂ���Č��肳�����̂́A���Ȃ̗ނɂ����ėL���Ƃ�����B���Ƃ��A���̂͗L���ł���Ƃ�����B�Ȃ��Ȃ�A�����͏�ɂ��傫�ȑ��̕��̂��l���邱�Ƃ��ł��邩��ł���B�����悤�ɁA�v�z�͑��̎v�z�ɂ���Č��肳���B�����A���͎̂v�z�ɂ���Č��肳��Ȃ����A�܂��v�z�͕��̂ɂ���Č��肳��Ȃ��B
�@�R�@���̂Ƃ́A���ꎩ�g�ɂ����đ��݂��A���ꎩ�g�ɂ���čl��������̂̂��Ƃł���B����������A���̊T�O���`�����邽�߂ɑ��̂��̂̊T�O��K�v�Ƃ��Ȃ����̂̂��Ƃł���B�k��P���A��`�l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.3.
�@���e�����|��̂������h�E�Ȃ̂ŁA�y�����z�͂��������o���܂��A�y�����z�́A�������Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�U�b�N�������ƁA�k��`�P�l�́u���Ȍ���(causa sui)�v�Ƃ́A�k��`�R�l���u����(substantia)�v�A���Ȃ킿�u���ꎩ�g�ɂ����đ��݂��A���ꎩ�g�ɂ���čl��������́v�ƃC�R�[���ł��B�܂�A�k��`�R�l�́A�u���́v�Ƃ͎��Ȍ����ł���ƒ�`���A�k��`�P�l�͂�����āA���Ȍ����Ƃ́A�u���̖{�������݂��ӂ��ނ��́v�ɂق��Ȃ�Ȃ��ƌ����Ă���킯�ł��B
�@�k��`�Q�l�ł́A�u�L���Ȃ��́v�ɂ͂Q��ނ����āA�u���́v�Ɓu�v�z(cogitatio)�v���ƌ����Ă��܂��B�u�v�z�i�R�M�^�`�I�j�v�́A�g���E�̑�v�z�h�̂悤�ȋ����Ӗ��ł͂Ȃ��A�f�J���g�́u���v��(cogito)�A�䂦�ɂ�ꂠ��v�́u�v���v�A�܂肨�悻�l���邱�Ƃ̂��ׂĂ��܂�ł��܂��B�p��� thought �Ɠ����L���Ӗ��ł��B
�u�R�@���̂Ƃ́A���ꎩ�g�ɂ����đ��݂��A���ꎩ�g�ɂ���čl��������̂̂��Ƃł���B����������A���̊T�O���`�����邽�߂ɑ��̂��̂̊T�O��K�v�Ƃ��Ȃ����̂̂��Ƃł���B�k��P���A��`�l
�@�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�T�@�l�ԂƂ́A���̂̕ϗl�A����������A���̂��̂̂����ɑ��݂��A�܂����̂��̂ɂ���čl��������̂̂��Ƃł���B�k��P���A��`�l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.3.
�@�k��`�R�l�́u���ꎩ�g�ɂ����đ��݁v����Ƃ������Ƃ̈Ӗ��́A�k��`�T�l�ƕ��ׂĂ݂�Ƃ킩��܂���
�u���́v�F�@���ꎩ�g�ɂ����đ��݂���@���ꎩ�g�ɂ���čl������
�u�l�ԁv�F�@���̂��̂̂����ɑ��݂���@���̂��̂ɂ���čl������
�@�܂�A�u�l��(modus ���[�h)�v�́A���̂��̂̓����Ɋ܂܂�Ă���d�d�����̂܂��ɁA�������傫�Ȃ��̂����Ȃ炸���邪�A
�@�u���́v�́A�����������Ƃ��Ȃ��A�����Ɋ܂܂��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�u���́v�̊O���ɂ͉����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�@�}������ƁA�������Ȃ�ł��傤�B

�����}�F�@���̂Ɨl��
�@�܂�A�u�l�ԁv�Ƃ́A�k��`�Q�l�́g�L���Ȃ��́h�̂��Ƃł��B�g�L���Ȃ��́h�ɂ́A��Ɍ�������́\�\�̐ς̂�����́A���Ȃ킿�u���́v�ƁA��Ɍ����Ȃ��u�v�z�v�Ƃ�����̂ł����B�u�ϔO�v�u���O�v�u����v�A������������Ɍ����Ȃ����̂́A�݂ȁA�L���Ӗ��ł́u�v�z�v�ɂӂ��܂�Ă��܂��B�u�v�z�v�́A����u�ϔO�v���ʂ́u�ϔO�v���܂݂��ނ��Ƃ��ł��܂�����A�g�L���Ȃ��́h�ł��B
�@����ɑ��āA�u���́v�\�\�\���ꎩ�g�ő��݂�����́\�\�\�́A���̂��̂Ɋ܂܂�邱�Ƃ͂���܂���B�u���ꎩ�g�ɂ����đ��݂�(id quod in se est)�v�́A���̐l�̖|��ł́A�u���ꎩ�g�̓��ɂ���v�ƂȂ��Ă��܂��B�u���́v���u���́v���܂ނƂ������Ƃ����肦�܂���k�藝�Q�l�B�������傭�A�u���́v�́A�����̑傫���������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��k�藝�W�l�B
�@�������A�u���́v�́A�u���́v�ȊO�̗L���Ȃ��̂��܂݂��ނ��Ƃ͂ł��܂�����A�u�l�ԁv���܂ނ��Ƃ͉\�ł��B�܂�A�u�l��(modus)�v�\�\�\���̂Ǝv�z�\�\�\�́A�u���́v�̂��܂��܂ȁu�ϗl(modificatio)�v�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��k��`�T�l�B
�@�������āA�C���[�W�I�ɂ͂����A�u���́v�Ƃ́A���܂��܂ȕ��̂��ӂ��݂������̂��́A�܂�F���S�̂̂��Ƃł͂Ȃ����A�Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂��B�����A�u���́v�����łȂ��A�u�v�z�v�u�ϔO�v���A�u���́v�ɂ͊܂܂�Ă��܂��B���邢�́A���ׂẮu���́v���݂����u���́v�̂ق��ɁA���ׂẮu�v�z�v��u�ϔO�v���݂����u���́v������B�u���́v�̐����A������Ȃ̂��A��������̂��́A���̒i�K�ł͂܂����肵�Ă��܂���B
�@���̂ւA�X�s�m�U�̉F���ς̂������낢�Ƃ���ł��B�B���_�ł��B�S�_�ł��Ȃ��A��҂������Ă��܂���
�@�������A�X�s�m�U�́u���́v�́A�u���́v�́u���[�h(�l��)�v���Ƃ����̂ł��B�u���́v�\�\�\�s�_���Ȃ킿���R�t�\�\�\�������Ƃ���A���ʂɗ��g�̂悤�Ȃ��̂��Ƃ���܂��B���͔̂g�ł���d�d�܂�ŃA�C���V���^�C���Ȍ�̕����w��\������悤�ȃC���[�W�ł��B
�@�����ł��Ƃ��A���q�Ƃ����u���́v(���[�h�j�́A���q�Ƃ����ʂ́u���́v�Ɋ܂܂�A���q�͐l�ԂƂ����u���́v�Ɋ܂܂��B���̐l�Ԃ��܂��A�܂��̑�C���܂߂��n���Ƃ����u���́v�Ɂd�A����ɑ��z�n�Ƃ����u���́v�Ɂd�A��͌n�Ƃ����u���́v�Ɋ܂܂�Ă���A�Ƃ����悤�ɁA���́g�ӂ��ށh�W�́A����Ȃ��L�����čs���܂��B
�@�X�s�m�U�̎���̉Ȋw�̍l���ł́A�F���͖����ł�������A�ǂ��܂ōL�����Ă��A�u���́v�̂܂��ɂ́A������܂ޕʂ́u���́v������킯�ł��B
�@�������Ƃ��u�v�z�v�ɂ��Ă������āA�d�d�X�s�m�U�̍l����g�F���h�ɂ́A�����ɏd�Ȃ�����������́u�v�z�v���A�ӂ��܂�Ă���B�����A�����́u�v�z�v���l����_�l��V�g�̂悤�ȋ[�l�I�Ȃ��̂́A���Ȃ��킯�ł��B
�u�k�c�l���̂����̂��̂���Y�o����邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��k�c�l�k��P���A�藝�U�A�n�l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.10.
�@�����قǂ́A�k��`�R�l�Ɓk��`�P�l�̊W���G�c�Ɍ����Ă��܂����̂ł����A�Ă��˂��Ɍ����ƁA�����́k�藝�l����ĂȂ��邱�ƂɂȂ�܂��F
�@�u���̂Ƃ́A���ꎩ�g�ɂ����đ��݂��A���ꎩ�g�ɂ���čl��������́v�܂�A���̂��̂Ɋ܂܂�邱�Ƃ��Ȃ����̂ł���k��`�R�l
�@�@�@�@�@�@�@��
�A�u���̂́A���̂��̂ɂ���ĎY�o����Ȃ��v�k�藝�U�E�n�l�܂�A�u���́v�́u���Ȍ����v�ł���B
�B�u���Ȍ����Ƃ́A���̖{�������݂��ӂ��ނ��̂ł���v�k��`�P�l
�A�{�B�@�u���̂Ƃ́A���̖{�������݂��ӂ��ނ��̂ł���v
�u���̖̂{���͑��݂��邱�Ƃł���B�k��P���A�藝�V�l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.11.
�@�y13�z�X�s�m�U�́g�����E�F���h�H
�@�����ł悤�₭�A�u���́v�Ƃ͂ǂ��������̂Ȃ̂����A�������n�b�L�����Ă��܂����B�u���́v�Ƃ́A�u���݁v��{���Ƃ�����̂̂��Ƃł���B
�@�X�s�m�U�ɂ����炸�A�u���́v�Ƃ����R�g�o�́A���������Ӗ��̃R�g�o�Ȃ�ł��ˁB�g�ق�Ƃ��ɑ��݂�����́h�Ƃ��g�^���݁h�Ƃ������������܂��B�������̏펯�ł́A��Ɍ����镨�̂��l�Ԃ��A�݂��u���́v�ł��傤�B�f���p�\�R���̉�ʂɉf��l���╗�i�́A�u���́v�ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@�������A�l�Ԃ⓮�A�����u���́v���ǂ����́A�Ȋw�I�Ɍ����Ă��^�₪����܂��B���Ԃ̃X�P�[�����Ƃ�ƁA�������̐g�̂͐V��Ӂi������ցj�����Ă��܂��B10�N���炸�ŁA���g�������������ւ���Ă��܂��܂��B�ɂ�������炸�A��l�̐l�Ԃ��A���܂�Ă��玀�ʂ܂œ����l�ԂƂ��đ��݂���̂��Ɓ\�\�l�Ԃ��u���́v�Ȃ̂��ƁA�����l����̂Ȃ�A�t�ɁA����Ă䂭�����̂ق����A�u���́v�ł͂Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@�ނ����̐l�́A�l�Ԃ����Ԃ������A���������ڂ낢�₷������ӂ�Ȃ��̂́A���s����A����Ȃ��̂��u���́v�ł͂Ȃ��ƍl���܂����B��敧���ł́A�قƂ����܂������u���́v���A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��ł��傤���ˁB
�@�X�s�m�U�̏ꍇ�́A�g���̂Ƃ͕��l���h�Ƃ��g�l�Ԃ��h�Ƃ��ŏ����猾�킸�ɁA�u���́v�Ƃ������̂�����Ƃ�����A����́A�����������̂ł���͂����A�Ƃ�����`������킯�ł��B
�@���̒�`�ɂ��A�u���ꎩ�g�ɂ����đ��݂�����́v�ŁA�u���ꎩ�g�ɂ���čl��������́v�ł�����k��`�R�l�A��ɁA�ق��̂��̂ɂ͊܂܂�Ȃ��悤�Ȃ��̂ł��B�܂�A�u���́v�̊O���ɂ͉����Ȃ��B�܂��A�u���́v�͖����ł���B
�@�u�l��(���[�h)�v�i�u���́v�Ɓu�v�z�v�j�́A�u���́v�̒��Ɋ܂܂�Ă�����̂ł��B
�@��������ƁA�u���́v�Ƃ����̂́A�Ȃɂ������Ђ�����߂��S���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
 �@
�@
Sacrevoir�@�@�@
�@�������A�u���́v�̓����ɂ́A�u�l�ԁv�ȊO�̂��̂͊܂܂�Ă��Ȃ��B�Ƃ����̂́A�L����̂͂��ׂāu���ꎩ�g�̓��ɂ��邩�A�܂��́A���̂��̂̓��ɂ���v�k�����P�l�B���������āA�u���́v���u�l�ԁv�ȊO�ɂ́A�������݂��Ȃ�����ł��i���C�w�X�s�m�U�̐��E�x,�u�k�Ќ���V��,p.82�j�B
�@��������ƁA�d�d�Ȃɂ������Ђ�����߂��S�����Ƃ���ƁA�u���́v�́A����������Ȃ��̂��H �������A�������X�s�m�U�̂������낢�Ƃ���Ȃ�ł����A�ȏ�̒�`�i�k��`�T�l�܂łƁA�������瓱�o���ꂽ�藝�Q�j�������ƁA�u���́v�́A��������Ƃ��l�������ł��B
�@�u���̂`�v�ɂ́A�u�l�ԁv��1,��2,��3, ...,�����@�������Ă���B
�@�u���̂a�v�ɂ́A�u�l�ԁv��1,��2,��3, ...,�����@�������Ă���B
�@�u���̂b�v�ɂ́A�u�l�ԁv��1,��2,��3, ...,�����@�������Ă���B
�@�@�@�@�@�d�d�d�d�d�d�d�d
�@���������g�����E�F���h�݂����Ȃ��̂��l�����Ă��܂��܂��i�w�X�s�m�U�̐��E�x,p.87�j�B�u���́v�́u���́v�̐��E�A�u�v�z�v�u�ϔO�v�́u�ϔO�v�̐��E�A�d�d�Ƃ����悤�ɁA�u�����v���Ƃɕʂ́g�S�́h������\�\�u���́v�����顡�
�@���������ɁA�X�s�m�U���A�����܂ōl�����̂��ǂ����͂킩��܂���B�u�_�v�̒�`�����������ƁA�����܂����́g�����E�F���h�͏��ł��A�B��E�����E�i�����s�_���Ȃ킿���R�t���E�����o���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�������u�_�v�����݂��Ȃ���A�F���͖����ɂ�������̐��E�ɕ��Ă��܂��c�c�Ђ���Ƃ���ƁA�X�s�m�U�́A�����l���Ă����̂�������܂���B
�@�y14�z�u�_�v�̏o���A�g���̐��E�h�̌��o
�@�u�����v�Ƃ����R�g�o���o�Ă��܂�������A�u�����v�̒�`�����Ă����܂��F
�u�����Ƃ́A�m�������̂Ɋւ��Ă��̖{�����\��������̂Ƃ��ĔF��������̂̂��Ƃł���B�k��P���A��`�S�l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.3
�@�u�����v�ɂ��ẮA�u��Q���v�ŋ�̓I�ɏo�Ă���̂ł����k��Q���E�藝�P�C�Q�l�A�u�����v�u�v�ҁv�Ƃ����Q���u�����v������܂��B���̍l�����́A�f�J���g����p���ł��܂��B
�@�u�����v�Ƃ����ƂP�����̂悤�Ȍ������ł����A�N�w�ł����u�����v�͂R�����ł��B�܂�A�g�̐ς�����h�Ƃ������Ƃł��B�܂�A�u���́v�̐����ł��B
�@�u�v�ҁv�́A�g�l������h�Ƃ��������ł��B�܂�A�u�v�z�v�u�ϔO�v�ł��B�X�s�m�U�̏ꍇ�ɂ́A�u����v��u�~�]�v�̂悤�Ȃ��̂܂Łu�ϔO�v�Ɋ܂߂Ă��܂��܂��B���傤�̑O���̘b�̂Ȃ��ŁA�u�ӎu�v���A����Ȃ�ϔO�i�F���j�ɂ����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł�����ˁH
�@�u�����v�Ɓu�v�ҁv�ɂ��ẮA�f�J���g���q�ׂĂ��܂��B�Ƃ��낪�A�X�s�m�U���l���Ă����u�����v�́A���̂Q�����ł͂Ȃ���ł��B�u�����v�u�v�ҁv�ȊO�ɂ��A�����ɂ���������u�����v������B�����A�c�c��Ȃ��ƂɁc�c�u�����v�u�v�ҁv�ȊO���u�����v��l�Ԃ͔F���ł��Ȃ��Ɓi�u�_�v�́A���ׂĂ��u�����v��F���ł���j�B�F���ł��Ȃ��̂�����A���������ǂ�ȁu�����v�Ȃ̂��F�ڂ킩��Ȃ�����ǂ��A�Ƃɂ�����������A�����ɂ�������ơ��
�@�킩�����悤�Ȃ킩��Ȃ��悤�Șb�ł�����ǂ��A�X�s�m�U�͑�܂��߂ł��B
�@�܂�A�X�s�m�U�̊�{�I�ȍl���Ƃ��āA�������g����h�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���肷�鍪�����Ȃ�������A����͖������A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��炵����ł��B�����炭�A�����F������u�_�v�̒m��������������A�F���̑Ώۂ������łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤�B�Ƃق����Ȃ��l���ł����A����Ӗ��œO�ꂵ�Ă��܂��B�l�Ԃ̒m�\���悤�Ƃ���l�����d�d�ƌ������炢����ł��傤���B
�@�����ŁA���́g���������u�����v�h�Ƃ������Ƃ�O��ɂ��āA�u�_�v�̒�`�́A�����̂悤�ɂȂ�܂��F
�u�_�Ƃ́A��Ζ����̑��ݎҁA����������A���̂��̂��̂��i���E�����̖{����\�����閳���ɑ����̑������琬�藧���̂̂��Ƃł���B�k��P���A��`�T�l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.4.
�@�X�s�m�U�́u�_�v���A�������̂��ׂĂ��u�����v���������I���݂Ƃ��Ē�`���܂����B�������A�u�_�v�̊e�u�����v�����ꂼ�ꂷ�ׂĖ�����ł��B�u�����v�܂�̐ς������A�u�v�ҁv�܂�ϔO�̃X�P�[���������ł��B���ׂĂ��ӂ����u���́v�Ȃ�A�����Ȃ炴������܂���B
�@�������A�����������łȂ��A�u�ЂƂ���������Ȃ���́v�ƒ�`����A���_���ɂȂ�܂��B���̏ꍇ�A�u�_�v���u�����v���ƂɂЂƂ肸���邱�ƂɂȂ�A�u�_�v�̐l���͖����ł��B�܂�A�}���_���̉F���ɂȂ�B
�@�X�s�m�U�́A�u�_�v�̑����͖������ƒ�`�����̂ŁA��_���ɂȂ�܂����B�u�_�v�͗B��ł���A�u�_�v�ȊO���u���́v�͑��݂��܂���k�藝�P�S�l�B�܂�A�s�_�C�R�[�����R�t�ł��B�Ȋw�Ɨ�������B��_���l����Ȃ�A�s���R�t�ƃC�R�[���ɂȂ炴������Ȃ��̂ł��B
�@�������A�u�_�v�́A�B�ꂩ�A���������̂ǂ��炩�ŁA�L�����́u�_�v�ɂ��邱�Ƃ͂ł��܂���B���_���́u�_�v�ɂ́A����͂Ȃ��̂ł��B
�@�}���_���F���̏ꍇ�Ȃ�A���肤�閳�����̊e�u�����v���ƂɁA�e�P���u���́v���u�_�v�����݂��邱�ƂɂȂ�܂��B�܂�A�����Ȃ�܂��F
�u�����`�v�F�u���̂`�v���o�u�l�ԁv��1,��2,��3, ...,�����p�@
�u�����a�v�F�u���̂a�v���o�u�l�ԁv��1,��2,��3, ...,�����p
�u�����b�v�F�u���̂b�v���o�u�l�ԁv��1,��2,��3, ...,�����p
�@�@�@�@�@�d�d�d�d�d�d�d�d
�@�u�����v�̂����Q�́A�l�Ԃɂ��F���ł��āA�ЂƂ́u�����v�A�����ЂƂ́u�v�ҁv�ł�����A��̓I�ɏ����Ɓ������Ȃ�܂��B�u�����b�v�ȉ��́A�F���s�\�ł��B
�@�u�����v�F�u���̊E�v���o�u���́v��1,��2,��3, ...,�����p�@
�@�u�v�ҁv�F�u���_�E�v���o�u�v�z�v��1,��2,��3, ...,�����p
�u�����b�v�F�u���̂b�v���o�u�l�ԁv��1,��2,��3, ...,�����p
�@�@�@�@�@�d�d�d�d�d�d�d�d
�@�������A�B��_������ƁA����疳�������u���́v���u�_�v�����̂��āA�S�u�����E�v�𑩂˂邱�ƂɂȂ�܂��F
�@�u�����v�b�@���@�b���o�u���́v��1,��2,��3, ...,�����p�@
�@�@�@�@�@�b�@�R�@�b
�@�u�v�ҁv�b�@���@�b���o�u�v�z�v��1,��2,��3, ...,�����p
�@�@�@�@�@�b�@�ȁ@�b
�u�����b�v�b�@��@�b���o�u�l�ԁv��1,��2,��3, ...,�����p
�@�@�@�@�@�b�@���@�b
�@�d�d�d�d�b�@�_�@�b�d�d�d
�@�������Đ��������s�_�����R�t�́A�B����u���́v�ł��B�����āA�u���́v�Ƃ́A���݂�{���Ƃ���̂ł�������A�u�_�v�́A���݂�{���Ƃ���A���Ȃ킿�K�R�I�ɑ��݂���F
�u�k�藝�T�l�@���R�̂����ɂ́A�����{�����邢�͓���������������邢�͑����̎��̂͑��݂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�k�藝�U�l�@��̎��̂��瑼�̎��̂��Y�o����邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��B
�@�@�@�k�n�l�@���̋A���Ƃ��āA���̂����̂��̂���Y�o����邱�Ƃ͂��肦�Ȃ����ƂɂȂ�B�k�c�l
�@�k�藝�V�l�@���̖̂{���͑��݂��邱�Ƃł���B
�@�@�k�ؖ��l�@�k�藝�U�E�n���l���̂͑��̂��̂���Y�o���ꂦ�Ȃ��B����䂦����͎��Ȍ����ł��낤�B���Ȃ킿�A�k��`�P�ɂ��l���̖{���͕K�R�I�ɑ��݂��ӂ���ł���B����������A���̖{���͑��݂��邱�Ƃł���B�����Ă��̒藝�͏ؖ����ꂽ�B
�@�k�藝�P�P�l�@�_�A���Ȃ킿���̂��̂��̂��i���E�����̖{����\�����閳���ɑ����̑������琬�藧���̂́A�K�R�I�ɑ��݂���B�k��P���l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.10-11,18-19.
�@�������āA�X�s�m�U�́g�_�̑��ݏؖ��h���������܂����B�ǂ��ł��傤���ˁH �u�K�R�I�ɑ��݂���v�Ƙ_����āA�Ȃ�قǁA�������ɑ��݂���Ȃ��A�Ǝv���܂������H ���ɂ͂�͂�A�g���̉F���͑��݂���h�Ƃ����f�p���݊��Ɏx����ꂽ�_�̂悤�Ɏv���܂�����ǁd�B�u�_�v�͂����s���R�t�S�̂ƃC�R�[�����A�Ƃ����ق��ɃA�N�Z���g������悤�ȋC�����܂��B
�u�k�藝�P�S�l�@�_�ȊO�ɂ͂����Ȃ���̂����݂����Ȃ����A�܂��l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�@�@�k�n�P�l�@���̂��Ƃ��玟�̂��Ƃ�����߂Ė��ĂɋA������Ă���B�܂���P�ɁA�_���B��̂��̂ł��邱�ƁA����������k��`�U�ɂ��l���R�̒��ɂ͂�����̎��̂������݂��Ȃ��A����������͐�Ζ����ł����Ƃ������Ƃł���B�k�c�l
�@�k�藝�P�T�l�@���݂�����̂͂��ׂĐ_�̂����ɂ���B�����Ă����Ȃ���̂��_�Ȃ��ɂ͑��݂����Ȃ����A�܂��l�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�k��P���l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.25-26.
�@
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
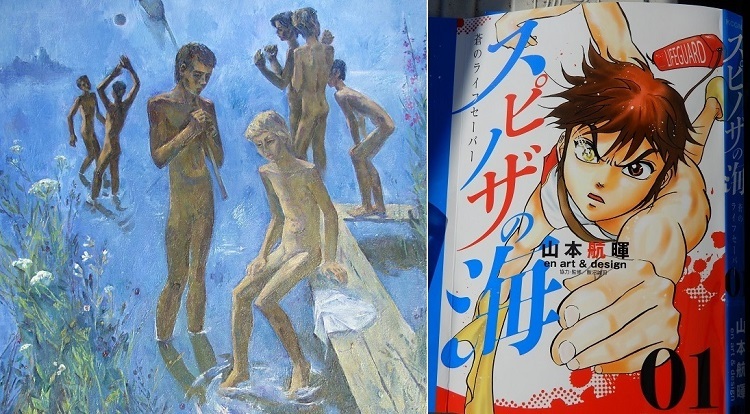 �@
�@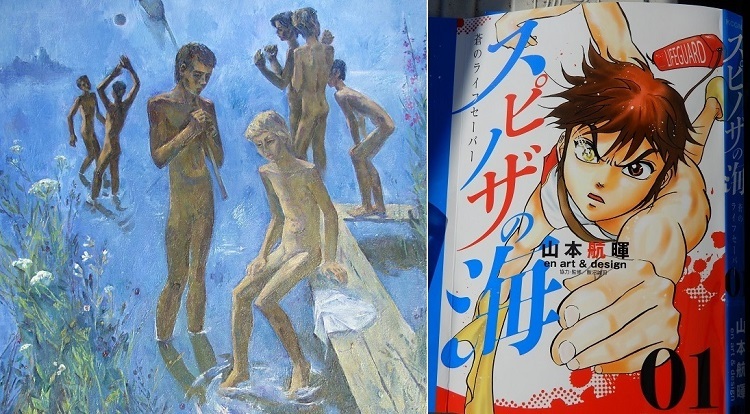 �@
�@


 �@
�@


 �@
�@

 �c
�c