04/05�̓��L
22�F02
�y�{���z���Ɖ_�Ɣg�̂����\�\�\�w���Ǝ��l�x(3)
---------------
.
 �@
�@
�k�C���]�s���@�V���o���@�@
�@������ (º.-)���
�@�{���̓��b���i�w���Ǝ��l�x���Ƃ肠���Ă��܂��F
�@���Ɖ_�Ɣg�̂����\�\�\�w���Ǝ��l�x(1)
�@���Ɖ_�Ɣg�̂����\�\�\�w���Ǝ��l�x(2)
�y�V�z���z�Ƃ��Ắu���v�́A�I�y�����H
�u���̃`���[�i�^�͓��̂Ȃ��ւ����Ę҂�グ�����炩�炾�����˂�o�����B
�@���̌��Ԃ��璩�������炫��˂��Ę҂Đ���̊�̉��ʂ��͂�����A�e�ŕ����o�����A�܂����̊�ɂ���������̐Ԃ┒�̓������o�����B
�@�`���[�i�^�͂����Ƃ肻�̐��������O��Ȑ��������B���ꂩ�瓴�̂����܂�ʂ��ĉ̂₤�ɂ��炫�����C�̐��Ɵlj�����̓V���ɂ��T������V�q�̍��������B
�@�i����͂��̊���R�{�k�䂶���l�̊C�����R�ɐ��k���Ál���A���̐��������₦�₦�����č��_��ɂ��Ȃ����Ă����̂��B���ꂾ�̂ɂ���͂��T���o�čs���Ȃ��B���̓��̊O�̊C�ɒʂ��錄�Ԃ͐h�k����l���O���̂������Ƃ��ł���ɉ߂��ʁB�j
�@�i�������A�������B�킽���̍߂������킽�����̎��k�̂�Ёl�����������������B�j
�@�`���[�i�^�͂��Ȃ����܂����̂Ȃ����ӂ肩�ւ茩���B���̂Ƃ������̒��͐��̂Ȃ��̔��h�Ɏ��k���l���Đ��܂��������炬�甽�˂����B�v
�@�����N��́s�Ɂt�̃e�N�X�g�́A�Â�1956�N�Łw�{�V�����S�W�x���{�ɂ��Ă��܂��B���̂��߁A���������A�����̑��e�Ƃ͈قȂ镔��������܂��B��̈��p���ł́A�u��(����)���v�Ȃǂ��A�����ł��B�M�g���̈��p�́A�w�V�Z�{�S�W�x���{�Ƃ��A�K�X���S�W�́w�Z�ٕсx���Q�Ƃ��āA�����̌��e�N�X�g�ɍ��킹�Ă��܂��B�����N��ƈ��p�����قȂ�̂́A���̂��߂ł��B
�@���āA���̖`�������́A���łɂP��ǂ�ł��܂�����i���������j�A�Ӗ��s���ȉӏ��͂Ȃ��ł��傤�B�����ŁA���炽�߂čl���Ă݂����̂́A���́u�`���[�i�^���v�̐��́\�\�\�A���S���[���Ƃ���A���̚g���Ȃ̂��Ƃ������Ƃł��B
�@�ꌩ���Ė��炩�Ȃ悤�ɁA���̍�i�́A�`�����炷�łɁA�ߑ�̈�ʂ̏����⓶�b�Ƃ́A�������قȂ��Ă��܂��B�ӂ��̐l�Ԃ��A�ӂ���A���̂悤�ɓƂ茾���������Ƃ͂��肦�܂���B�u�`���[�i�^�v�̓Ƃ茾�́A�����܂ł��A����Ƃ��ẴZ���t�ł���A����A�I�y���̃A���A�̂悤�Ȃ��̂ł��B���������Ȑg�U����܂����ĘN�u����A���̂܂܃I�y���������ɂȂ�悤�ȃZ���t�Ȃ̂ł��B�܂�A�O��̕��J�s�l���̌������ł����A�g�V���{���v�l�h�Ɋ�Â����A���Y���ł͂Ȃ��A�g�A���S���[�v�l�h�ɂ��Â��^�C�v�̕��͂Ȃ̂ł��B
�@�������A�w���Ǝ��l�x�́A�ŏ�����Ō�܂ŁA���̃^�C�v�̕��͂Ő�߂��Ă��܂��B���̂悤�Ȃ��̂́A�{���̎U����i�ł͒������Ƃ����܂��B�����ċ�����A�w�߂���Ԃ����Ɠ��x�Ƃ��̉���ł����w�}���������Ə����x�����邭�炢�ł��傤�B�w�߂���Ԃ����Ɠ��x�̑��e�́A�u�����͂₵�̖�v�u�R�j�̎l���v�̊e�����`�Ɠ����s10-20 �C�[�O���� ���F�r�t�Ƃ������e�p���ɏ�����Ă���A1921�N�㔼�`1922�N���߂���̐����Ɛ��肳��܂��B1921�N6-7��������k����Ə����l�́A�Y�Ȓf�Ђł����A���͂�����ƃI�y�����̃Z���t�ł��B
�@�����̑Δ䂩��l����ƁA�w���Ǝ��l�x���A���́s��i���t�t�\�\1921�N8���\�\�ɋ߂������̐����ł͂Ȃ����A�Ƃ������������Ă��܂��B�������A���������̋c�_�́A���Ƃɉ܂��傤�B
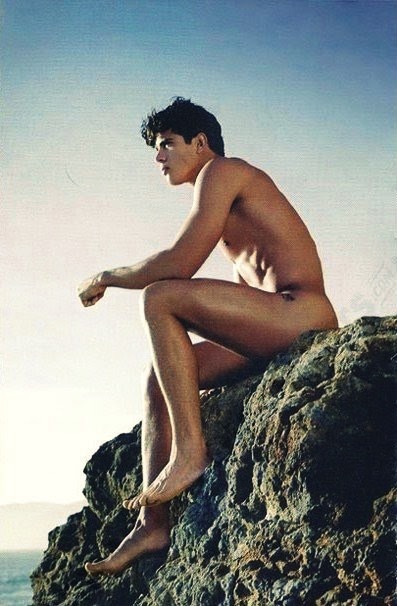
�@����̈��p�ɂÂ������ŁA�u�킩���́v�X�[���_�b�^���A���A�̊O�ɓo�ꂵ�܂��F
�u���̂Ƃ����͓��̊O�Ől�̎�X�����߂��ĂԂ̂��ア���B���͊O���̂������B
�@�i�h�ӂׂ��V�������`���[�i�^��B�����̗͂�����Ă킽���͂��܂ւɋ�������Ђɘ҂��B�j
�@����������艩���̑������͂�����l�̗��h�ȐN���O���g�̐��ۂɂ��͂��Ă�B
�@�i���������Ƃ��ӂ̂��B�j�v
�@�u����(�悤�炭)�v�́A��������ɂ����Ă����^�̃l�b�N���X�ł��B�l�b�N���X�̗ւ���A���肪����Ă���̂������ł�(�y�摜�z�ˁF�����j�B�����炭�A�̂̃C���h�Œj������ɂ����Ă������̂Ȃ̂ł��傤�B���M�Ȑg���������X�e�C�^�X�E�V���{���̈Ӗ�����������������܂���B
�@�`���[�i�^�ɂ����Ȃ�u��������Ђɘ҂��B�v�ƌ����X�[���_�b�^�ł����A�`���[�i�^�ɖ���āA��������ɗ������̎�������܂��B���̕���́A�����̏�ʂƂ��ẮA���A�̒��̃`���[�i�^�ƁA���A�̊O�̃X�[���_�b�^���A��́u���ԁv��ʂ��Č�荇���A���̉��\�����̃V�[�������ł��B���̎��_�܂ł̎����̐i�s�́A�����ς�X�[���_�b�^�̌��ɂ���āA�q�ׂ���̂ł��F
�u�i����B����̎����̋��Ђ̘��ɁA�킽�����o�ĉ̂����B�����Ă݂�Ȃ͑�ւ�킽�����ق߂��B
�@������̂����l���A���^�͍�������Ę҂āA�킽�����X���Ă��Ԃ�̍������ɂ̂ڂ������̑������킽���ɔ킹�āA�킽�����܂߂�l��̘�������ЁA���Ԃ�͉������̕��̐Ⴀ��R�̘[�ɋ������B�킽���͎Ԃɂ̂����Ă킽�����̂��������̂̂��������Ɏ��̂₤���˂Ђ݂�Ȃ̂ق߂邱�Ƃ�A�킽���߂�Ԃ̉J�ɂ���Y��ċ���炵�Ă���A��X���Ă킽���͒��҂̃��_�X�̉Ƃ�熂��Ă��炫�炵�����̘I�݂Ȃ���킽���̕n������e�̂��Ƃɖ߂�Ƃ����V�q�̍�������̉_�����T�肭�炭�Ȃ����̂ł킽������������ӂ���ł��A�N���U�~���_�̐X�Ŏz���Ђ��Ђ�����Ă��̂����B
�@�@�i�킩���̂̃X�[���_�b�^�͓��ɕ������Ă��`���[�i�^�V���̉̂��ʂ��ݕ����Ă���������̂̋��ׂɂ������Â����l���A���^�𓌂̚��ɋ��点���j�@�킽���͂ǂ����ӂ킯�������ӂ�ւĎv�ӂ₤�ɕ����Ȃ������B�����č������̑��͂�ɍ����Ėウ���B�l�ւČ���Ƃ킽���͂��T�ɂ��܂ւ̋���̂�m��Ȃ��ł��̓����̂�̖��ɖ�������l�։̂Ђ���Ă͖������B�����Ă��̂����͂���_���炢���̓��̂Ђ�܂̂܂ǂ�݂̂Ȃ��ŕ������₤�ȟ�������B�����ŘV�����间�̃`���[�i�^��B�킽�����͂���������D�����Ԃ��ĊX�̜A��ɍ��肨�܂ւƂ݂�Ȃɂ�т₤�Ǝv�ӁB���̂��������̂��̂������Ԃׂ��킪�t�̗���B���܂ւ͂킽�����������炤���B�j�v
�@�u�����̑����v�́A�Q�������ł����A�M���V���ŁA����̋��Z�̗D���҂Ɏ�����ꂽ�g���j���h�ɂ�������̂ł��傤�B�u�����v�́u���v�́A�����̌`���̂ЂƂŁA��Ƌr�C�������A���A�����̂悤�Ȏ����E�s���̌��܂�͂Ȃ����̂������ł��B
�@�u�����̋��Ёv�Ƃ�������������A�{�������z�Ƃ��������A�ǂ��������̂Ȃ̂��A�����͂��邱�Ƃ��ł��܂��B�����̂悤�ȍ����I�Ȃ��̂��A�ق���̂́g���h�ƍl���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�u���̎G���䔭�s�ɏA�āA���Ȃǂ܂Ŗ��ɂ��ĉ��������̂́A���k�܂��Ɓl�ɐJ�k�������l���Ȃ������܂����A�O�Ɏ��̎���ŏo�����w�t�ƏC���x���A�����ꂩ�炠�Ƒ����܂ŏ����t���Ă�����̂��A�����݂͂�ȓ��ꎍ�ł͂���܂���B�������ꂩ��A���Ƃ������������Ǝv���ċ���܂��A����S���w�I�Ȏd���̎x�x�ɁA�����ȕ��̋�����Ȃ��ԁA�����̋�������A�@��̂���x���ɁA���낢��ȏ����̉��ŏ�������Ēu���A�ق�̑e�d�ȐS�ۂ̃X�P�b�`�ł�������܂���B�k�c�l�o�Ŏ҂͂��̑̍ق���o�b�N�����W�Ə����܂����B���͂т��т����̂ł����B���p�������������߂Ƀu�����d�̕��ŁA���̓����܂����ď������̂���R����܂��B�k�c�l���͂ƂĂ����|���Ȃ�Ƃ��ӂ��Ƃ͂ł��܂���B�����Č����Ď��͂���Ȃ��Ƃ����ʼn]���Ă��̂ł͂Ȃ����Ƃ́A����Љ�����A�܂��悭���ׂĉ�����Δ���܂��B���̃X�P�b�`�̓�O�ҁA�ǂ�����ł��Ȃ����̂ł����A�����グ�₤���Ǝv�Ђ܂����B�������炱��ǂ͂ǂ���o�������Ɖ]�ӂ��Ƃ��A��ւ�킽�����̓���ɂ����܂����B����Ȃ�ЂƂ��ǂ��v�ӂ��A�ق��̐l�����̂Ɣ�r���Ăǂ����炤���ȂǂƂ��Ӊ}�ȍl���킽�������ꂵ�߂܂��B�킽�����͖{���ɂ���ȂɎア�̂ł�����A���Ă��悤�������܂��B�ǂ������炭���Ȃǂ͍\�͂Ȃ��ł��T��ɂ����ƒu���ĉ������B�k�c�l�v
�{������[200] 1925�N2��9���t �X���ꈶ�� ���B
�@
�@�w�t�ƏC���x�Ɓw�����̑��������X�x���o�ł�����ŁA���̓��l���ւ̌f�ڂ̗U���ɑ��āA���̂悤�ɏ����Ă��܂��B����̐X����͓����܂����w���ł����A�����́A��������������_�ł́A���肪���h�ȑ�l�̎��l���Ǝv���Ă��܂����B
�@�u���ꎍ�ł͂���܂���B�v�́A���̎莆�ł͌����ɂ������Ȃ��͂���܂���B�������A�����ł͂Ȃ��A�����͓�����̂ق��̎��l�̍�i���܂߂āA���ׂāA����Ȃ��̂��u���ꎍ�ł́v�Ȃ��ƍl���Ă����̂��Ǝv���܂��B���̊�g���X�制�Ă̎莆�ł́A���ꂪ�����Ƃ͂�����Ə�����Ă��܂��F
�u�킽�����͊�茧�̔_�w�Z�̋��t�����ċ���܂����Z���N�O������j�₻�̘_���A�����̊����邻�̂ق��̋�ԂƂ��ӂ₤�Ȃ��Ƃɂ��Ăǂ����������Ȋ����₤�����Ă��܂�܂���ł����B�k�c�l�킽�����͂��Ƃŕ�����Ƃ��̎d�x�ɂƂ��ꂼ��̐S���������̂Ƃق�Ȋw�I�ɋL�ڂ��Ēu���܂����B���̈ꕔ�����킽�����͕��ɂ��Ȃ���N�̏t�{�ɂ����̂ł��B�S�ۃX�P�b�`�t�ƏC���Ƃ����Ƃ��肵�Ċ֍��Ƃ��ӓX���玩��ŏo���܂����B�F�l�̐搶���R�Ƃ��Ӑl�����W�Ɩ��������܂����B ���Ƃ��ӂ��Ƃ͂킽�������m��Ȃ��킯�ł͂���܂���ł����������Ɏ����̂Ƃق�L�^�������̂����������܂܂ł̂��͂��������̂ƍ�����ꂽ�͕̂s���ł����B�k�c�l�v
�{������[214a] 1925�N12��20���t ��g�ΗY���� ���B
�@���̎莆�ł́A���Ԃŏo�ł���Ă���ق��̎��l�����̎��W���u���܂܂ł̂��͂��������́v�ƌĂ�ł���̂ł��B
�@���̂Q�ʂ̎莆�́A�{�������g�̎���ɂ��ďq�ׂ��M�d�ȋL�q�Ƃ��āA�����̘_���ň��p����Ă�����̂ł��B�������A���̑����́A�u����S���w�I�Ȏd���̎x�x�ɁA�c�c���낢��ȏ����̉��ŏ�������Ēu���A�ق�̑e�d�ȐS�ۂ̃X�P�b�`�v�u���Ƃŕ�����Ƃ��̎d�x�ɂƂ��ꂼ��̐S���������̂Ƃق�Ȋw�I�ɋL�ڂ��Ēu���܂����v�Ƃ��������ɒ��ڂ��āA�u�X�P�b�`�v�Ȃ����u�L�^�v�Ƃ��Ă̎���Ƃ����A�����̓��قȎ��ς���������Ă��܂����B
�@�������A�悭�ǂ�ł݂�ƁA�����́A���������u�Ȋw�I�v�ȁu�L�^�v�s�ׂ��܂��u���ꎍ�ł́v�Ȃ��Ə����Ă���̂ł��B�������u���v��u���|�v��ʂ��A�Ӗ��̂Ȃ����́A�����l�Ȃ��̂ƍl���Ă����̂łȂ����Ƃ͖��炩�ł��B����ǂ��납�A�ق�Ƃ��́u���v�͉��l�̂�����̂��ƍl���Ă��邱�Ƃ��A�����̎莆�S�̂̍s�Ԃ���A�����������܂��B�P�ɁA�ގ��g�̏��������̂��܂߂āA���ԂŁu���v�Ƃ��Ă��Ă͂₳��Ă�����̂��u�݂�ȓ��ꎍ�ł́v�Ȃ��̂ł��B
�@���������āA���̂Q�ʂ̎莆�ɂ�������ɓI�g�ے�I�]���h�̗����ɂ���A���z�Ƃ��Ắu���v���A�ϋɓI�Ɍ�������͂Ƃ��āA�w���Ǝ��l�x�́A�����ւ�d�v���Ǝv���܂��B�����ł́A�Ñ�C���h���̑����̂��ƂɁA�M���V���ōs��ꂽ�悤�ȁg���̋��Z�h�ɂ��Č���A����́A�u�����̋��Ёv�ƌĂ�Ă���̂ł��B
�@���������{���̎��ς��A1926�N�ɔ_�w�Z���t�����߂��\�\�\�����ɁA�u�����ȕ��v�����邽�߂ɓ����ɏo��v���f�O�����\�\�\���Ƃ́A���ω����������悤�ł��B����̕��j�������������ȂǂŁA�����̏��������̂��A���߂炢�Ȃ��u���v�ƌĂ�ł��܂��B�������A�ӔN�ɂ͕��ꎍ��̌X�������߁A�w���ꎍ�e�\�сx�w���ꎍ�e��S�сx�w���ꎍ����e�x�Ƃ����A���ꂼ��啔�̕��ꎍ�W���c���Ă��܂��B�����I�ȌÂ��`���́u�����v�𗝑z�Ƃ���u���v�̗��O�́A���U�����Â���ꂽ�̂��Ǝv���܂��B
�y�W�z�s���Ƃt�������炷�h���ƕs�K
�u����̎����̋��Ђ̘��ɁA�킽�����o�ĉ̂����B�����Ă݂�Ȃ͑�ւ�킽�����ق߂��B
�@������̂����l���A���^�͍�������Ę҂āA�킽�����X���Ă��Ԃ�̍������ɂ̂ڂ������̑������킽���ɔ킹�āA�킽�������k�فl�߂�l��̘��k���l�������ЁA���Ԃ�͉������̕��̐Ⴀ��R�̘[�ɋ������B�킽���͎Ԃɂ̂����Ă킽�����̂��������̂̂��������Ɏ��̂₤���˂Ђ݂�Ȃ̂ق߂邱�Ƃ�A�킽���߂�Ԃ̉J�ɂ���Y��ċ���炵�Ă�k�c�l�v
�@�X�[���_�b�^�̉̂����u�����v�́A�����̒��O����J�߂�ꂽ�����łȂ��A�����ɂ����u������̂����l���A���^�v�\�\�\�O�`�����s�I���\�\�\�������F�߂āA�X�[���_�b�^�Ɂg�j���h��A�`�����s�I���̌���\�������A�����A�����Œ��ӂ��ׂ��_�́A���̕���̒��Łu���l�v�ƌĂ�Ă���̂��A���^�����ŁA�X�[���_�b�^�́A��x���u���l�v�Ƃ͌Ă�Ă��Ȃ����Ƃł��B�����ɂ��A��Ҍ����̎��ς����f���Ă���Ǝv���܂����A���̂��Ƃ́A�̂��قǘ_���܂��B
�@�u�킽���߂�Ԃ̉J�v�́A���łɌ����u����v�Ɠ��l�̌Ñ�C���h���̑����ŁA���T�ł͂����A�V�n�̏j�����ĉh���ɋP���悤�����A�u�Ԃ̉J�v���~��ƕ\�����܂��B���̎��̃X�[���_�b�^�̐S�����́A�u�킽�����̂��������̂̂��������Ɏ��̂₤���˂Ђ݂�Ȃ̂ق߂邱�Ƃ�A�킽���߂�Ԃ̉J�ɂ���Y��ċ���炵�Ă�v�Ə�����Ă��܂��B�܂�A���͂��痁�т�����]���ƁA�j���́u�Ԃ̉J�v�̂Ȃ��Łu����Y��v�A�����́u�����v�ɐ����Ă����A�Ƃ����̂ł��B
�@�������̂��̂́u���������v�A�̑傳�ɐ����Ă��܂��i���V�b�N�Ȏ��Ȍ��z�Ƃ́A������������������܂���B�������A�����̉̂��g�����̉́h�Ƃ��āA����ɐ����Ă����Ԃł��B�܂�A�u�����v�Ƃ��̍�Ҍl�Ƃ̌��т������ɋ�����ԂȂ̂ł��B���т�����]���́A�u�����v�ɑ���]���Ƃ������́A�X�[���_�b�^���̐l�ɑ���]���ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@���̂��Ƃ��A����̂��̐�̓W�J�ŁA�d�v�ȈӖ��������ƂɂȂ�܂��B

�u��X���Ă킽�����k�c�l�n������e�̂��Ƃɖ߂�Ƃ��k�c�l�N���U�~���_�̐X�Ŏz���Ђ��Ђ�����Ă��̂����B
�@�@�i�킩���̂̃X�[���_�b�^�͓��ɕ������Ă��`���[�i�^�V���̉̂��ʂ��ݕ����Ă���������̂̋��ׂɂ������Â����l���A���^�𓌂̚��ɋ��点���j�@�킽���͂ǂ����ӂ킯�������ӂ�ւĎv�ӂ₤�ɕ����Ȃ������B�����č������̑��͂�ɍ����Ėウ���B�v
�@�X�[���_�b�^�́A�u��X���v�Ɂu�~���_�̐X�v���畷�����Ă����b�����ɋ��|���o���A���̂܂܉Ƃւ͖߂邱�ƂȂ��A�u���͂�v�Œ��܂Őg�ウ���Ă����B�����́A�s�Ɂt�̃e�N�X�g�������̌��e�N�X�g�Ə�������Ă���ӏ��ł��B�{���̌����e�N�X�g�ɒ����ēǂ�ł����܂��B
�@�u�~���_�̐X�v�̘b�������A���������ɒN�����A�����\�������Ă����̂��A����Ƃ��A�u�X�v���̂��̂̐��Ȃ̂��́A�킩��܂��A�O�҂��ƍl���Ă悢�ł��傤�B���Ƃ̂ق�����ǂނƁA�X�[���_�b�^�́A�ނ������ґz�Ǝ���ɂӂ����Ă������̍���̉��ɓ��A�������āA�����Ƀ`���[�i�^�����H����Ă��邱�Ƃ�m��܂���ł����B�������A�ق��̐l�тƂ͂����m���Ă��āA�܂��A�X�[���_�b�^�����̏�ɂ���̂����Ă����̂ŁA���������^�����������̂�������܂���B
�@�Ƃ������A���́g�\�h�́A�X�[���_�b�^�́u�����v���g���ށh�Ƃ��Ĕ�����̂ł��B
�@�X�[���_�b�^���A���́g�\�h�ɃV���b�N�����̂́A���́u�����v���A�����́u�����v�Ƃ��Ď]���𗁂сA�L���V�ɂȂ��Ă������炾�A�ƁA�����������Ă͍l���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@��i�̗ǂ�����҂̍˔\�ɋA���āA��҂��ق߂邱�ƁG�t�ɁA���l�́u�����v�̙��ނ��ƒf���āA�g�U��ҁh����邱�Ɓ\�\�\���̂�������A�u�����v�ƁA�i�^�́j��Ҍl�Ƃ̌��т��������̑O��Ƃ�����̂ł��B
�u�l�ւČ���Ƃ킽���͂��T�ɂ��܂ւ̋���̂�m��Ȃ��ł��̓����̂�̖��ɖ�������l�։̂Ђ���Ă͖������B�����Ă��̂���������_���炢���̓��̂Ђ�܂̂܂ǂ�݂̂Ȃ����������₤�ȟ��������B�����ŘV�����间�̃`���[�i�^��B�킽�����͂���������D�����Ԃ��ĊX�̜A��ɍ��肨�܂ւƂ݂�Ȃɂ�т₤�Ǝv�ӁB���̂��������̂��̂������Ԃׂ��킪�t�̗���B���܂ւ͂킽�����������炤���B�j�v
�@�X�[���_�b�^���u�����̋��Ёv�ʼn̂����u�����v�́A���̖��̏�ŃC���X�s���[�V�������č쎍�������̂Ȃ̂ł����A���ܔނ́A�j���̋��������߂����ɔ��́g�\�h�����Ռ��̂��߂��A�u���̂����v�́u�܂ǂ�݂̂Ȃ��ŕ������₤�ȟ�������B�v�ƌ����̂ł��B
�@���������Ɂu�����v�����̂��A����Ƃ��A�V���b�N�̂��܂�u�������₤�ȟ�������v�̂��́A�͂����肵�܂���B������ɂ���A���̎��ɉ��炩�̃C���X�s���[�V�������āu���̂����v���ł������������Ƃ͂܂������Ȃ��\�\�\�ƍl���Ă悢�ł��傤�B
�@�������A��قɊ�������̂́A����ɑ���X�[���_�b�^�̔����ł��B�X�[���_�b�^�́A�u����������D�����Ԃ��ĊX�̜A��ɍ��肨�܂ւƂ݂�Ȃɂ�сv��Ƃ����g�܍߁h�����ӂ��Ă���̂ł��B�Ȃ��A����قǂ܂ł́g�܍߁h�Ɯ������K�v�Ȃ̂ł��傤���H
�@�������ɁA�X�[���_�b�^�ɑ��钮�O�̏]�ƌj���̎��^�́A���́u�����v���X�[���_�b�^���g�́g���̂ł���h�Ƃ����s���ƍ�҂̌��т��t��O��ɂ��Ă��܂����B���̑O�A����������A���邢�́u�~���_�̐X�v�̐��������悤�ə��ނȂ������\�ł��������Ƃ�����A�Պ��̑O����Ă��܂��܂��B
�@�������A���ꂾ���Ȃ�A�X�[���_�b�^�͌j����Ԃ��āA�D���̉h�_���������Ă��炦���ނ��ƁA�Ƃ��l�����܂��B�����Ƃ��A�j����Ԃ����ɂ��A�X�[���_�b�^�ƌ�ւ�����̌j�����l�A���^�́A���������ɂ͂��Ȃ��F
�u�������̕��̐Ⴀ��R�̘[�ɋ������B�v
�@����́A�ǂ������ĖK�˂Ă䂭���Ƃ��ł��Ȃ��悤�Ȑl�Ֆ����̏ꏊ��������܂���B�܂�A�X�[���_�b�^�́u�����v�́A���łɎ��Ԃ��̂��Ȃ����ʂ������炵�Ă��܂��Ă���̂ł��B
�y���z���@�w�����̑��������X�x�́u�L�����v�ɂ́A
�u🈪�@�����͌������U�ł�����ł��ޓ��ł��Ȃ��B
�@�@�����̍ēx�̓��Ȃƕ��܂Ƃ͂��Ă��A�������ɂ��̒ʂ肻�̎��S�ۂ̒��Ɍ��͂ꂽ���̂ł���B�̂ɂ���́A�ǂ�Ȃɔn�����Ă�Ă��A����ł��K���S�̐[���ɉ��Ė��l�̋��ʂł���B�ڋ��Ȑ��l�����ɕL��s���ȏ�ł���B�v
�@�Ə����ꂽ����������܂��B�u�����v�̓��b���A�u�U(���͂�)�ł��ˋ�ł��v�Ȃ��A�Ƃ����͉̂���Ƃ��Ă��A�u�ޓ��v�ł͂Ȃ��Ƃ����͓̂��˂ŁA�ǂ����āA�����ŋ}�ɂ���Ȃ��Ƃ������̂��킩��܂���B�������A���́u�L�����v���A�w���Ǝ��l�x�����������ƂŁA�����ōl�������Ƃɂ܂��S��Ȃ��珑���ꂽ�̂��Ƃ�����A�����ł������ł��B���Ƃ��A���̓��b�W�Ɏ��^���ꂽ�u�����͂₵�̖�v�́A���[�e�������N�̋Y�ȁu�����v�Ɏ��Ă���_������܂��B�����́A�ǎ҂���A����͖{���ɂ��܂����������̂��H �N���̙��ނ���Ȃ��̂��H �ƌ����邱�Ƃ��A���������Ɋ뜜���Ă����̂ł��傤�B
�@���̓_���猾���Ă��A�w���Ǝ��l�x�̐����́A1921�N�ł͂Ȃ��A�w�����̑��������X�x�̏���i�������グ�����ƁB�o�ł̌v�悪�����オ�������_�Ȍ�A�Ȃ����u�L�����v�쐬�O��Ǝv����̂ł��B
�@�Ȃ��A�����������ŁA�u�U�ł�����ł��ޓ��ł��Ȃ��v�����Ƃ��āA�u�������ɂ��̒ʂ肻�̎��S�ۂ̒��Ɍ��͂ꂽ���̂ł���v�Ƃ����s���S�̐^���t�������Ă���̂��d�v�ł��B����ɂ��ẮA�g�ߑ㕶�w�h�̓����Ƃ̊W�ŁA�ʓr�̍l�@��K�v�Ƃ��܂��B
 �@
�@
�@�������A�X�[���_�b�^���u�D�����Ԃ��ĊX�̜A��ɍ��v���āg�܍߁h���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv�����R�́A�u�A���^�𓌂̚��ɋ��点���v���Ƃ����ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@���̂��Ƃň��p����悤�ɁA�A���^�́A�X�[���_�b�^�Ɍj����������ɂ������āA���̌��t�ł͂��܂���N�u���Ă���̂ł��F
�u���������Љ_���䂶�g���炷���̂��������U���ɂ����ӃX�[���_�b�^�v
�@�܂�A�X�[���_�b�^�́A����_��g�́u�����v���u���U���ɂ����Ӂv�҂Ƃ��Ď]�����Ă���̂ł��B�������A�X�[���_�b�^�̎��ȔF���͂��̂悤�Ȏ҂ł͂Ȃ��A
�u�킽���́c�c���̓����̂�̖��ɖ�������l�։̂Ђ���Ă͖������B�����Ă��̂���������_���炢���̓��̂Ђ�܂̂܂ǂ�݂̂Ȃ����������₤�ȟ��������B�v
�@�Ƃ����̂ł��B�܂�A�����ɂ��킽���Ė��̏�Łu���v�ɂ��炳��u�_�v�߁u�g�v�̉����Â��Ă��Ă��A�������Ă����́u�����v���������Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��A������́u�܂ǂ�݂̂Ȃ��Łv�͂��߂āu���̂����v�����B����������́A���̉��ɂ���u�`���[�i�^���v�̋Ⴖ��̂́u�ʂ��ݕ��v���ł������A�ƃX�[���_�b�^�͎v���Ă���̂ł��B
�@�܂�A�X�[���_�b�^�̎��]�Ǝ��ȔF���̊Ԃɂ́A�傫�ȃM���b�v������̂ł��B
�u�i�����������l���A���^�́A
�@�@�ǂ����Ә�ł��܂ւ��ق߂��炤�B�j
�@�i�킽���͂��܂�̂��ƂɐS������āA���̟������C���S���Ȃ������B����ǂ�������
�@�@�@���������Љ_���䂶�g���炷���̂��������U���ɂ����ӃX�[���_�b�^
�@�@�@���������Ȃ炤�Ǝv�З��n���������ӌ`���Ƃ炤���S�傷��
�@�@�@�������̐��E�Ɋ��ӂׂ��܂��ƂƔ��Ƃ̖͌^������₪�Ă͐��E������ɂ��Ȃ͂��ނ阬���ҁA
�@�@�@�v�҃X�[���_�b�^�@�Ɓ@�������ӂ��Ƃł������Ǝv�Ӂj�v
�@�u��(��)�v�́A�T���X�N���b�g��u�K�[�^�[�v�̊���ŁA���Ƃ��Ƃ́A�u����v��ʂ��Ӗ����܂��B�����ł́A�o�T�̒��̉C���̕����������܂��B���̋��`�́u��v�́A�Ȍ��ȕ\���ŋ����̃G�b�Z���X���q�ׂ���A���ɁE��F���������鎍��ł��i�ˁF�u��v�@�ˁF�u�K�[�^�[�v�j�B�������A�����ł́A���T�ł͂Ȃ��{���́u����v�̈Ӗ��Ŏg���Ă���悤�ł��B�O�̈��p�����Ɂu�l��̘�v�Ƃ������悤�ɁA�����͂S�s�̂͂��ł�����A�s�Ɂt�̃e�N�X�g�̍s�����͌��ł��B
�@�P�s�ڂ�
�u���������Љ_���䂶�g���炷���̂��������U���ɂ����Ӂv
�@�̕����ł����A�u���v�u�_�v�u�g�v�́u�����v���u���U���ɂ����Ӂv�Ǝ]���Ă��܂��B�������A����玩�R���̉S���u�����v���Ƃ��ĉ̂��̂��A�����Ƃ�ȊO�̕��@�Łu���U���ɂ����Ӂv�̂��́A�����ł͖��炩�ł͂���܂���B
�u���������Ȃ炤�Ǝv�З��n���������ӌ`���Ƃ炤���S�傷��
�@�������̐��E�Ɋ��ӂׂ��܂��ƂƔ��Ƃ̖͌^������v
�@�Q�`�R�s�ڂ́����̕����ł́A�u���v��u���n�v�A���Ȃ킿���R�E�́A�u�����Ȃ炤�Ǝv�Ёv�u�������ӌ`���Ƃ炤���S��v���ĕω����Ă䂭�B�܂�A�g���R�E�h�́A���R�̏d�Ȃ荇���̌��ʂƂ��ĕϑJ����̂ł͂Ȃ��A�g���R�E�h�Ȃ����g���R���h���g���A���̈ӎv�Ɨ\�z������Ă��āA����̈ӎv�܂��͊o��Ɋ�Â��ĕω����Ă��������ʂ��A�u�������̐��E�v�Ȃ̂ł���\�\�\�Ƃ����v�z���q�ׂ��Ă��܂��B
�@�����āA�X�[���_�b�^���u�����Ӂv�̂́A���́u�������̐��E�v�Ɂu���Ӂv�悤�ȁu�܂��ƂƔ��Ƃ̖͌^�v�ɂق��Ȃ�Ȃ��ƌ����̂ł��B
�@�u���Ȃ��v�ɂ́A�@�K������i�K���j�A��������i�����j�\�\�\�Ƃ����Q�̈Ӗ�������܂����A�����ł́A�A�̈Ӗ��ł��傤�B�܂�A�u�������̐��E�v�ƂȂ��Ď�������悤�ȁA�u�܂��ƂƔ��Ƃ̖͌^�v�B
�@���◤�n���A�u�����Ȃ炤�Ǝv�Ёc�c�S�傷��v�̂́A�u�������̐��E�v�ł��傤���H ����Ƃ��A�u�܂��ƂƔ��Ƃ̖͌^�v�̂ق��ł��傤���H �P�s�ڂŁA�X�[���_�b�^�́u�����v�́A���E�_�E�g�A�܂�n���Ƃ����u���v��u���n�v�̈ꕔ���S���u�����v���̂��̂ł���A�Ƃ���Ă������Ƃƍl�����킹�܂��ƁA���́u�����v���\������u�͌^�v�Ƃ́A�u���v��u���n�v���g���u�Ȃ낤�Ɓv�~���関���́u�������v�ɂق��Ȃ�Ȃ��ƍl�����܂��B
�@�܂�A�X�[���_�b�^�́A�����̐l�ԂƂ��Ă̗��z�▲���A�����̐��E�̃��[�g�s�A�Ƃ��ĉ̂����ł͂Ȃ��A�g���R�E�h���̂��̂���ޖ����̎p�\�\�\���ꂱ�����u�܂��ƂƔ��Ƃ̖͌^�v�ł���\�\�\���A�l�Ԃ́s���Ƃt�ɂ��ĉ̂��o���Ă���̂��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�u�������̐��E�Ɋ��ӂׂ��܂��ƂƔ��Ƃ̖͌^������₪�Ă͐��E������ɂ��Ȃ͂��ނ阬���ҁA
�@�v�҃X�[���_�b�^�v
�@�A���^�̂������X�[���_�b�^�́A����A�u���v��u���n�v�̈˗������u�v�ҁv�ł����āA���E�_�E�g�̉S���Ƃ���́u�͌^�v�����邱�Ƃɂ���āA�u���v��u���n�v���A�����Ȃ肽���Ɗ肤�A�����́u�܂��ƂƔ��v�́u�������v�������킯�ł��B�u���v��u���n�v���ӎv���Ă͂��Ă��A��̓I�Ɂu�������v�Ƃ��ĕ`�����Ƃ��ł��Ȃ������̎p���A�X�[���_�b�^���A����ĕ\�����邱�Ƃ��ł���̂́A�X�[���_�b�^���s���Ƃt���g�p���邩��ł��B���Ȃ킿�A�ނ́u�����ҁv�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@�X�[���_�b�^���s���Ƃt�ɂ���ĕ`���u�͌^�v�́A�g���R�E�h�ɑ��āA����炪���낤���関���̐��E������܂��B�u�͌^�v���Ȃ���A���Ƃ��u�܂��ƂƔ��v�Ɍ������o��������Ă����Ƃ��Ă��A�Ӗڂ̓w�͂��d�˂邱�Ƃɂ����Ȃ�܂���B�g���R�E�h�́A�u�͌^�v�Ƃ��Ē��ꂽ��������ڕW�Ƃ��邱�Ƃɂ���āA�u�܂��ƂƔ��v��̌��������E�Ƃ��Đ������邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�������āA�X�[���_�b�^�̎������u�͌^�v�́A�u�������̐��E�v�Ƃ��Ď������邱�ƂɂȂ�܂��B���Ȃ킿�A�u���E�v�͂₪�āA�X�[���_�b�^�̕`�����u�͌^�v�Ɂu���ȂӁv�\�\�K������悤�ɂȂ�̂ł��B
�@�ɏq�ׂ�ꂽ�A���^�̎v�z�́A���̂悤�ɗ������邱�Ƃ��ł��܂��B����́A�g���R�E�h���g���A�u�܂��ƂƔ��v�Ɍ������ĕω����Ă������Ƃ���ӎv������Ă���̂��\�\�\�Ƃ����m�M�ɂ��ƂÂ��Ă��܂��B�������A���R���̂܂܂ł́A���̈ӎv�͕K�������������Ȃ��B�l�Ԃ��s���Ƃt�ɂ���āu�����v���A�u�͌^�v�������Ď������Ƃ��͂��߂āA�u�܂��ƂƔ��v�́A�u�������̐��E�v�Ɏ������邱�ƂƂȂ�̂ł��B
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@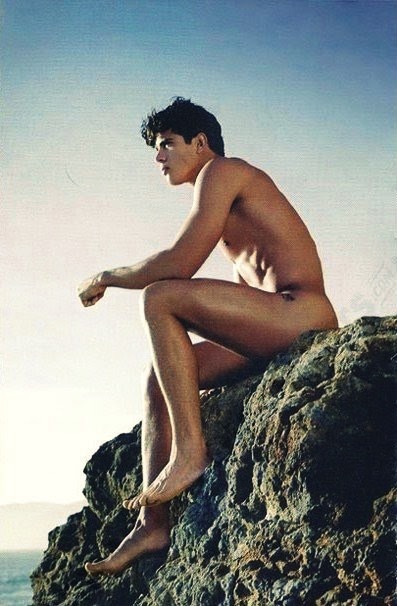


 �@
�@
 �c
�c