02/13�̓��L
00�F03
�y�{���z�G�R���W�[�̌��c���H
---------------
.

����䏬�w�Z�Ձi�����_����j
�@�����́B(º.-)���
�@�w��炮�堕����x�́s�����t���������܂����B����͂Q��ڂ̉��� version 3 �ł����Aversion 2 ����啝�ɏ����ς��Ă��܂��B�ˁF�w��炮�堕����x�s�����t
�@�^�C�g�����A�w�e�����v�Ƃ�f�̔w���x����A�w�{���́s���������Ƃ������݁t�x�ɕς��܂����B
�@�Ȃ��}�������Ȃ�����... �Ǝv���܂����H�@�ł��A�u���������Ƃ������݁v���āA������Ƃ����t�b�T�[�����ۊw�̐��p��Ȃ�ł��悗 �ǂ������Ӗ��Ȃ̂��́A�����̂ق��ɏ����Ă���܂���
�@�s�����t�̉������I���āA�����e�i�Q���Łj�̐��Ȃ������������̂ŁA�����炠����ŁA�������ɋC�Â������ƂƂ��A����͐��肫��Ȃ��������ƂƂ��A���s���ɏ����Ă��������Ǝv���܂��B
�i�P�j�G�R���P���W�X�g??
�@���炭�O����P���a����́A���R�ی�^���̊���̂悤�ɂȂ��Ă��܂��āA�d
�@��O���ɂ́A�u�J�j���}�P�Y�v�̒��҂Ƃ��āA���ȂƗ����S�̐��ҁA
�@�풆���ɂ́A���U�����̐S�̗F�A�d�O�X�R�[�E�u�h���̎��ȋ]���̐��_�Ƃ��c
�@���ɂ͈�]���āA�u�V��������̃}���N�X��I�v�ƌĂт������J���I���_�A���R�����������Y�͂����߂�_�Ƌߑ㉻�̎u�����]����A
�@���܂܂��P�W�O�x�߂����āA�G�R���W�[�̐��҂ł��傤�����
�@�Ȃ�ƖZ�����Ƃ������A�֗��Ȃ��̂��ƌ������A�ǂ��ɂł��Ղ�グ���Ă��܂����ʓI�Ȃ��̂�����̂�������܂���...
�@�܂��A�����������Ƃɔ������������̂��A�́E�g�{�������Ȃǂ́A�u���ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂����F
�u�{���̉Ȋw�⎩�R�ρA�G�R���W�[�̎v�z�͂ǂ������Ƃ���ɂ��邩�Ƃ������Ƃ�������Ă��������Ƃ������܂��B�k�c�l�w�O�X�R�[�u�h���̓`�L�x�Ƃ�����i������܂��B�k�c�l
�@���̒��ɕ\��Ă���{���̉Ȋw�ρA���R�ς�v�Ă݂�ƁA���R�Ƃ����͕̂ς������Ƃ����l�������Ƃ������܂��B�ڂ����̌�����������ƁA�V�R���R�Ƃ����͕̂K�������ŏ�̎��R�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���ꂪ�{���̉Ȋw�ςł���A���R�ς̂ƂĂ��傫�Ȓ��̈�ł��B���R�͉ςł���A�V�R���R�����������R�������Ƃ������Ƃł��B
�@������̑傫�Ȓ��͉����Ƃ����܂��ƁA�l�Ԃ��A�������A�A�����A�������Ƃ��Ă͕������Ƃ����l�����ł��B�k�c�l
�@�ڂ��Ȃ�A���̂��ƂƁA�V�R���R�͓��������Ƃ��ł���A�V�R���R�����������R��l�Ԃ����邱�Ƃ��ł���Ƃ�����̍l�������G�R���W�[�̎v�z�Ƃ��Ď��o���Ƃ������܂��B�g�ł͎��o���Ȃ��B���ɂ��悤�Ƃ�������ی삵�悤�Ƃ��A�ڂ��Ȃ���������܂���B�����������o�������ŏ�̎v�z���Ƃ͂����Ƃ��v��Ȃ��B�ڂ������ݍŏ�̃G�R���W�[�̎v�z�����o�����Ƃ���A���ܐ\���グ����ɒ����A�������邱�Ƃ��ł���Ƃ������܂��B�v
�g�{�����u�{�V���������v(1990�N�u���j,in�Fders.�w�{���̐��E�x,2012,�}�����[,pp.182-188.
 �@
�@
�@�g�{���Ƃ������āA�M�g���Ȃǂ͐V��������ł�����A�{���𐳖ʂɗ��ĂāA�u���ɂ��悤�Ƃ�������ی삵�悤�Ƃ��v�i���邱�Ƃɂ͑�^���Ȃ̂ł�����ǂ�...
�@�����Ƃ���ɂ��ƁA���܉Ԋ��Ƃ������Ƃ����̂�����ŁA�{���t�@���̐l���������S�ɂȂ��ău�i�т̕ۑS�Ƃ��A�G�R���W�[�^����������ɂȂ��Ă��邻���ł��B�����ւ\�Ȃ��ƂŁA�������ɂ���Ă������������Ɓd�A�������琺���𑗂肽���C�����Ȃ�ł�����ǂ��d
�@���_�͑�^���Ȃ̂ł�����ǁA���̂��Ƃ̂Ƃ���ƌ������d�A�������ق�Ƃ��ɁA�����I�ȈӖ��ł̃G�R���W�[�̐��҂��������Ƃ�����... �^�₪�Ȃ����Ƃ��Ȃ��̂ł��B
�@�Ȃɂ���g�S�N�O�̐l�h�ł��B���N�A��Q����������A�J�����������菭�Ȃ�������d�A���̂��тɔ_�����ɂ߂�����d�A������������ɐ������{���̔O���ɁA�܂��������̂́A�l�Ԃ����R�ɉ������̂ɔ�������A���R��ی삵���肷�邱�Ƃł͂Ȃ��A�ނ���A���R���������������邱�Ƃ������Ǝv���̂ł��B
�@�����炭�u�i�ۑS�Ƃ������ƂŃ~���P���������o���Ƃ�����A�w�i�\�����сx�����肪�T���ɂȂ��ł��傤�F
�u�����ǂ��Ɛ����ĂԂȂ̗t���`���`������Ƃ��Ȃǂ��i�\�͂������ꂵ���Ă��ꂵ���ĂЂƂ�łɏւĎd���Ȃ��̂��A�������傫�����������A�͂��͂����������Ă��܂����Ȃ��炢�܂ł����܂ł����̂ԂȂ̖����グ�ė����Ă��̂ł����B
�@���ɂ͂��̑傫�����������̉��킫�������y���₤�Ȃӂ�����Ďw�ł�����Ȃ���͂��͂��������ŏЂ܂����B
�@�Ȃ�قlj������猩����i�\�͌��̉��킫��~���Ă�邩�����͌��L�ł����Ă�邩�̂₤�Ɍ����܂������߂��ł͂��������Ă�鑧�̉��������܂������O���s�N�s�N�����Ă��̂��킩��܂�������q����͂���ς肻������ɂ��ďЂ܂����B�v
�{���w�i�\�����сx
�@�����̂�����ł��傤�ˁB�u�i�Ƃ������̔�������m���Ă����i�\�Ƃ����l�́A���͂̂ӂ��̑�l��������́A��������������Ȃ��Ǝv���Ă���l�ŁA�q�ǂ�����������o�J�ɂ���Ă���\�\�\���������Ƃ��낪�A�����̎��R�ی�^���́g�j�h�Ƃ������A���ɑ���₳�����́g�j�h�݂����Ȃ��̂ɁA�ƂĂ��悭�ʂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�������A���̕����͂������Ă悢�Ƃ��Ă��A�{���Ƃ����l�S�̂̂Ȃ��Ō���ƁA�ނ̓u�i�т�ۑS���ׂ����ƍl���Ă������ǂ���...
�@���́w�i�\�����сx�̃X�g�[���[�ł��A�i�\���A���āA�ނ̎��������ςȌ����Ƃ��Ďc���Ă����̂́A�u�i�ł͂Ȃ��āA���̗тȂ�ł��ˁB�y�w�������č�������Ȃ����߂ɁA���̍��������ȏ�Ɉ炽�Ȃ��A���̂��߂Ɏq�ǂ������̗V�я�Ƃ��Ċ��D�Ȍ����ɂȂ��ł����A���������Ƃ���͂������ɁA���̌�̎���̐��{�̐A�ѐ���Ƃ͋t�̕�����ł��o���Ă���B
�@����ł���͂�A�������i�\�ɐA���������̂́A�u�i�ł͂Ȃ����Ȃ�ł��B
�@��茧�Ńu�i�̐A�тƌ����A�����_��ɗǂ����{������܂��B�o�X�ʂ�ŁA�����w�̂ق�����g�܂��Ή��h�ւ䂭�r���̍�̍����\�\�\�l�X�Ə���䏬�w�Z�Ղ̂������\�\�\�~���P�����u���Ȃ�n�_�i�f�A�E�n�C���Q�E�v���N�g�j�v�ƌĂ�����Ȃ�ł����A���R�Ƃ��ꂢ�ɐA����ꂽ�u�i�̎����т�����܂��B����琄�����āA�����炭���ԂŁg�u�i�ѕۑS�h�Ƃ������Ƃ�������悤�ɂȂ���O����A��ĂĂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������ɁA�����_��͂��������_�ł��ڂ������\�\�\�Ɗ��������ł���...
�@�������A�����֍s���Č���ƁA�u�i�̐A�т͂Ȃ��Ȃ�����_������Ƃ��v���܂��B�t�B�[���h�A���w�̐搶�ɐu���ƁA�u�u�i�͂��������Ȗ��B�v�ƌ�����ł��ˁB�a���Q�ɂ���₷���悤�ł��B�t�����ɂ�������H���Ă܂����A�����Ԃ��������A������A�R�Ɏ������Ă���u�i�̂悤�ɂ��ꂢ�Ȕ��ɂ͂Ȃ�Ȃ���ł��B

�����_��̃u�i�A�с@���̌����͏���䏬�w�Z��
�@�����́A�u�i�Ƃ������ɑ��Ăǂ�ȃC���[�W�������Ă����̂��ƌ����ƁA������Ȃӂ��ɂ������Ă��܂��B�w�i�\�����сx�Ƃ͂��Ȃ肿�����C���[�W�ł��F
�u���������̑���̉e���։f��
�@���̐����Ȍ��̖��u������
�@���k�Ȃ�l�̖ؗ��̔����S�V�b�N���L��
�@�~��₤�Ȓ��̃W���t�H��
�@�݂��͂ЂƂ����@���炵��Ƃ���
�@�Â����n�̞��k�Ԃȁl�₵
�@�߂������ɂ͂��炤�Ƃ���
�@�@�@�@�@�@�c�c���ɂ������������ԗ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�������z�ӂ��̐��z���J�X�e�[���c�c�v
�w�t�ƏC���E��Q�W�x#179,1924.8.17.�k�k�����ς��̐�����Ɂl�k�����e(��)�l���B
�@�~�Y�i���́A�u�����S�V�b�N���L�v�ƌĂ�ł���̂ɔ�ׁA�u�i�̂ق��́A�u�Â����n�̞��k�Ԃȁl�₵�^�߂������d�v�ƌ����Ă��܂��B
�@���������A�L���ǂ���ł́����������̂�����܂����F
�u�������i�܂����́j�Ɠ�Ƃ��܂Ƃ�
�@�C���̐�m�킪��������
�@��݂킽��𤂖�C���ӂ���
�@��ƞ��i�Ԃȁj�Ƃ̂���Ђ����߁v
�w�t�ƏC���E��P�W�x�u���̌����A�v���B
�@�����ł��A�u�i�ɑ��ĕ����ꂽ�g�Â��h�g���n�̐X�h�Ƃ����}�C�i�X�̃C���[�W���A�����́u��m�v�����̃G�]�̖���I�Ȓ�Â��ӂ��A��Z���ɑ���悤�Ȏv��������������ĂĂ��܂��B
�@�܂�A�����Ƃ����l�ɂƂ��āA�u�i�́A�Â��A�Ë��Ńu���ȃC���[�W�Ȃ�ł��B�ނ���A���������_�ɂ����A�ނ̂�����肪�������B
�@������A�{�������R�ی�̌���ɗ��Ă�̂Ȃ�d�A���b�I�Ȗ��邢�a�₩�ȃC���[�W������O�ʂɏo���̂ł͂Ȃ��A���������g����Ȃ��Â��h�Ƃ������d�A�@����Ă��@����Ă������Ď��Ȃ��ɎR�n�̕Ћ��Ő��������邵�ԂƂ��Ƃ������A���������ʂɂ��ڂ������������̂��Ǝv���܂��B
�i�Q�j�@�t�b�T�[���Ɓu���������Ƃ������݁v
�@���ۊw�ɂ��ẮA���N�����X����͉��������Ă����������ɁA��ɓ���₷���悢�{�����낢��o�Ă���̂��킩��܂����B
�@���N�O�c�c�P�O�N���炢�O���ȁH�c�c�傫�����X�̏��I�Ō������ɂ́A�t�b�T�[���Ƃ����ƁA�����œ���n�[�h�J�o�[���A�^�������I�ȃW���[�i���X�e�B�b�N�Ȗ|��{�����Ȃ������ł��B
�@����A�T�������p���悤�Ǝv���āA�t�b�T�[���́w�����Ȋw�Ƃ��Ă̓N�w�x�A�O�ɌÏ��Ŏ�ɓ���Ă��������|�N�Y����Q�Ƃ��Ă݂���ł����A
�@�܂��d��ꂪ�Ђǂ��Ďg�����ɂȂ�Ȃ��̂��킩��܂����B���傤�nj����������Ă����̂ŁA�����ł���������ād�A�������傭���̕����̈��p�́s�����t�ɂ͓���Ȃ����ƂɂȂ�����ł�����ǂ��d
�@���ē��{�Ɍ��ۊw���Љ���̂́A���s�̐��c�剺�̓N�w�҂����Ƃ��A���c�N�w�̉e�������l������������ŁA�t�b�T�[���̌��ۊw�{���̃X�W���Ȃ��Ȃ��`���Ȃ������悤�ȋC�������ł��B
�@���ۊw�́A���c�N�w�Ƃ͐^�t�Ȃ��̂ł����硡� �ꌩ����ƃJ���g�Ɏ��Ă�悤�ȋC������t�b�T�[���̒��������܂����A�J���g�Ƃ��S�R�Ⴂ�܂��B
�@�u���z�v�u���z�_�I�v�Ƃ��u�J���g�ł��k�c�l�F���ɍۂ��Ă���ꂪ���A�v���I���Ȍ`����T�O�ɂ������v
�w���ۊw���T�x,�k����,2014,�O����,p.330,�u���z�I�^���z�_�I�v.
�@���Ȃ킿�A�J���g�́u���z�I�v�u���z�_�I�v�́A�u���I�v�u�A�E�v���I���v�Ɠ������ƂŁA�u�o���I�v�̔��ӌ�ł��B
�@�@�J���g�̌����u���z�I�v�ȊT�O�A�u���z�_�I�v�Ȏv�l�Ƃ́A�u���v�u�}�`�v�Ȃǂ̐��w�I�ϔO��_���w�I�ϔO�̂��ƂŁA�����́A�u��V�I�i�A�E�v���I���j�ȊϔO�\�\�\�܂�o���ɂ���ē�����̂ł͂Ȃ��A���Ƃ��ΐ_�ɂ���ė����ɐA������ꂽ�Ƃł��������������Ő����I�ȁA���������ē����_�ɂ���đn�����ꂽ���E�̑��݂̗��@�Ƃł����������̂ƑΉ����Ă��肾���炱���q�ϓI�Ó�����L���Ă���ϔO�\�\�\�Ƃ݂Ȃ���Ă����v
�ؓc���w���ۊw�x,1970,��g�V��,p.19.
�@�����ꂪ�J���g�̗p��B�������A�������t���A�t�b�T�[���ł͕ʂ̈Ӗ��Ŏg���܂��B�t�b�T�[���́u���z�I�v�Ȏ����ɂ́A�J���g�̌����u�o���I�v�������A�u�A�E�v���I���v�ȊT�O�\�\����}�`�\�\���A�Ƃ��Ɋ܂܂�܂��B
�@�������A�J���g�ł́u���z�I�v���u���z�_�I�v�������̂��A�t�b�T�[���ł́A���̂Q�̗p��݂͌ɋt�̈Ӗ��ɂȂ�̂ł��B�u���z�I�v�u���z�_�I�v�̑Η��́A�t�b�T�[�����ۊw�̃L�[�T�O�ƌ����Ă悢�̂ł���
�@�u���z�I�v�Ƃ́A�u�t�b�T�[���ł́A�ӎ��ɂƂ��Ă̑Ώۂ��ׂāv�u�ӎ��k�c�l�̓��ɏ������Ă��Ȃ����̂��ׂāv�̂��ƂŁA�O�E�̐X�����ۂ��A�g������h�̒��̃C���[�W��v�l���A���ׂāu���z�v�ł���B
�@�t�b�T�[���̌����u���z�_�I�v�Ƃ́A�u����̒��z�I�Ȃ��̂�����ɒ��z���āA����̈Ӗ����l����\���I��ρv
�w���ۊw���T�x�u���z�I�^���z�_�I�v
�@�@
�@���悭�킩��Ȃ���������܂��A�ڂ����̓M�g���́s�����t��ǂ�ł��������B�Ƃ������A�p��̈Ӗ����J���g�ƑS�R�Ⴄ��ł�����A�ӂ��̓N�w�̂���Ńt�b�T�[����ǂ肵����A���������������킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�@�܂��A���ۊw�ł悭�g����u�o���v(experience, Erfahrung�j�Ƃ������t���A�J���g��ӂ��̓N�w�Ƃ͈Ⴄ�Ӗ��Ŏg���Ă��܂��B
�u�J���g�̌����o�������R�Ȋw�I�o���ł���̂ɑ��āA�t�b�T�[���̌����o���͎��R�Ȋw�ɂ��C�f�A������̂����̂��ɕ��������o���ł���B�v
�w���ۊw���T�x�u���z�_�I�����_�v
�@�܂�A�g�Ȋw�ȑO�h�g�v�l�ȑO�h�̒��ρE�����܂܂́e�o���f�Ȃ̂ł��B�܂���킵���̂ŁA�s�����t�ł́u�o���v�Ƃ������t������āA�ł��邾���u�̌��v�Ƃ������œ��ꂵ�܂����B
�@�������߂́A��ɂ����p�����ؓc���搶�̊�g�V���ł��B�����A�����Ȃ肱���ǂނ̂͂������߂��܂���B�Ȃɂ����发���A���ۊw�ł��t�b�T�[���ł��A�P���ǂ�ŊT���ɓ���Ă���A��肩�������ق����悢�Ǝv���܂��B���܂́A���X�̐V���E���ɂ̏��I�ɁA��ʌ����̓ǂ݂₷�����发�������������ł���悤�ł�����B
�@�t�b�T�[���̓��发��ǂ�ł���ƁA���U�̂����ɉ��x���l�����̘g�g�݂��ϓ]���Ă���Ə�����Ă��܂��B�܂��d�A���ۊw�I�Ҍ��ȂǂƂ����O�㖢���̑�Z������Ă̂����̂ł�����A���s���낪�d�Ȃ�̂����R�ƌ���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@���܁A�Ƃ肠���������E�����̕ϑJ��}�������Č���ƁA�������Ȃ�ł��傤�F
1891�N�w�Z�p�̓N�w�x
�@�@�@�S����`
1900�N�w�_���w�����x��P��
�@�Aa�@�_����`
1901�N�w�_���w�����x��Q��
�@�Ab�@�_���w�̏��T�O�ƐS���̌��̑��֊W�@�S����`�ւ̋t�߂�H�@���u���ۊw�v�̏o��
1913�N�w�C�f�[���T�x
�@�B�@���z�_�I�]��@���@�����ӎ��̋L�q�I���́ˑΏۂ���������\���̕���
�@�u�S���w��`�v�Ƃ́A�ؓc�搶�̐����ɂ��ƁF
�u�P�X���I�̔����k�c�l���R�Ȋw�ɔ͂��Ƃ��������I���@�����A�k�c�l�Ȋw�I�S���w�ɒE�炵�Ĉȗ��A�ڂ��܂������W���Ƃ����S���w�́A���w�I�v�l���_���w�I�v�l���o���I���݂ł���l�Ԃ̐S�����ۂ̈��Ȃ̂ł��邩��A�����S���w�I�Ɍ������A�k�c�l���w�I�ϔO��_���w�I�ϔO�̌o���I�S���w�I�N���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ł��邵�A�����Ȃ�A�k�c�l���_�I���Ȋw�́A����ɂ͂��������̉Ȋw�̊�b�w�̖�����S���w�������邱�ƂɂȂ�A�ƍl�����̂ł���B�v
�ؓc���w���ۊw�x,p.19.
�@���Ƃ��A�u���v�Ƃ������̂�l�Ԃ��ǂ�����čl���o�����̂��Ƃ����ƁA�u���z�ƌ��v�̂悤�ȁE�������ɈقȂ���̂���ׂāg��������h�Ƃ����s�ׂ��ŏ��ɂ����āA��������A�P�Ƃ��Q�Ƃ����R���̊ϔO���������āA����ɁA�����A�����A�Ƃ����悤�Ɋg�����Ă䂭�ƍl����킯�ł��B
�@�S���w��`���̂��̂́A���݂ł͂�����Ă��܂����A�ŋ߂悭�ǂ܂��{�Ō����ƁA�A�����J�̔F�m����w�\�\�W���[�W�E���C�R�t�w�F�m�Ӗ��_�x�Ȃǁ\�\�\�ŁA�u��^���v�u�O�^���v�Ƃ������l�Ԃ̌���ɋ��ʂ��镁�ՓI�X�L�[�����A�l�ԂƂ���������ɔ����������Ȑ����K������������Ă���̂́A�S����`�̓`�����v�킹�܂��B�̏�Ő������Ă���`���p���W�[�ɂ́u��v���u���v�������킯�ł��B�u��v�u���v�́A�������s����l�ԂƂ�����ɓ��L�̐��E�F���̃X�L�[���ł��B�܂��A�y��̔����ȗ��A�l�ԂɂƂ��Đg�߂ɂȂ����u����v�Ƃ�������̌`�Ԃ��A�u���v�Ɓu�O�v���čl����Ƃ����������̎v�l�X�L�[���ɍ���Ă��܂��B
�@���́A���Ƃ��ƃM�g�������ۊw�ɊS���������̂́A���̂ւ�Ȃ̂ł��B�F�m�S���w���烉�b�Z���A�t���[�Q�ցA����Ƀt�b�T�[���ւƊS�͔��ŁA�w�_���w�����x�ɃA�^�b�N���Ă݂��킯�ł��d�B���������܂���ł�������
�@�����́A�܂������ۊw���A�̂���̈��Ǐ��̋{���ɊW���Ă��悤�Ƃ́A�v���Ă��݂܂���ł������c
�@�o�[�g�����h�E���b�Z���ƃt���[�Q�̖��O���o�܂������A���̂Q�l�́A�u�_����`�v�̂ق��̒��S�l���ł��B���b�Z���Ȃǂ͓O��I�ɘ_���I�Ȑl�ŁA�l���Ȋw���Љ�Ȋw���A�����͎��R�Ȋw�Ɠ����悤�ɂȂ�B���������Ƃƌ�������Ƃ��A�q�ϓI�ȕ��@�ŏs�ʂł���悤�ɂȂ�B���܂͂܂������Ȃ��Ă��Ȃ��̂́A���R�Ȋw�Ō����g�����̖������h�̒i�K�ɁA�l���E�Љ�Ȋw�����邩�炾�B�c�c�ƒf�����Ă��āA�m���̖{���ŗ����ǂ݂��ăr�b�N���������Ƃ�����܂��B�d
�@���������킯�ŁA�_���I�ɂ��߂�A�푈�ȂǂƂ������̂́A����������̐l�ԓ��m���E�������ȂǂƂ����̂́A�܂������s�����������Ƃ��Ȃ킯�ŁA���b�Z���́A��P�����ɂ͂����������͂��Ȃ��A�h�C�c�Ɛ킢�����z�͐킦�������낤�d�@�Ɣ������ʂ��āA�Y�����ɓ�������Ă��A�Y�����̒��ł������ƒ��q�ɗ]�O���Ȃ������Ƃ����̂͗L���Șb�ł��B
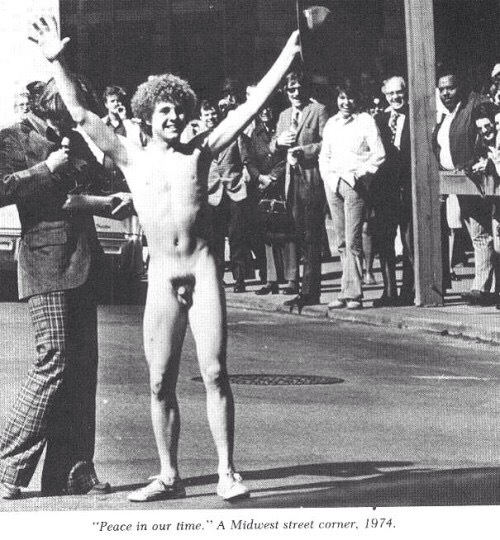
�@���́u�_����`�v�ł�����ǂ��A�u���v��u�}�`�v�Ƃ��������O���A�S���w�Ŋ�b�Â��悤�d�A�l�Ԃ̐S�̓����̂����ɂ��悤�ȂǂƎ��݂�͖̂��ʂȂ��ƂŁA���O�͗��O�Ƃ��đ��݂���̂��A����Έ��́g�C�f�A�h�Ƃ��đ��݂���B������A�_���l�Ԃ̐S�ɐA�������Ȃǂƍl����K�v���Ȃ��B
�u�t�b�T�[���͂����k�w�_���w�����x�P���V�́\�\�\�M�g�����l�Ń{���c�@�[�m�́w�^�����́x�̐���O���ɒu���āA�^�Ȃ���̂͐�ΓI�ŁA�s���ꎩ�́t�^�ł���A���f������̂��l�Ԃł���A�V�g�ł���_�X�ł���A�^���͓���ł���Ǝ咣���Ă���B�v
�w���ۊw���T�x,p.250�u�l�ގ�`�v
�@��ΓI�ɐ^�Ȃ闝�O�́A�^������^�ł���A������A�l�Ԃ̐S�̓����A���邢�͎����ȂǂƂ������o���I�����ɂ���Ċ�b�Â��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��\�\�\�ƁA���̎����i�Aa�j�̃t�b�T�[���͍l���Ă��܂����B
�@�t���[�Q�A���b�Z���Ȃǘ_���w�̐l�тƂ́A����ł��A���Ȋw�𐬂藧�����Ă���^���A���O�A�T�O���A�ł�����菭���́g�����h�ɏW�Ċ�b�Â���w�͂𑱂��Ă��܂����B�S���w�𐬂藧�����邽�߂ɂǂ����Ă��K�v�Ȃ̂́A�u�[���ƂP�v�u�_�Ɛ��v�̂悤�ȁA���������̊�b�I�ȗ��O�ŁA���Ƃ́A����������Ƃ��Ę_���I�ɑg�ݗ��Ăčs���A�������w�ł��A���Θ_�����w�ł����ł��\�z�ł���B�����āA�����̊�b�I�ȗ��O���A�t���[�Q�ɂ��A�W���_���瓱���o�����Ƃ��ł��A�W���_�́A�_���w���瓱���o����̂ł����B�i�����Ƃ��A�t���[�Q�̂��̑s��ȓw�͂́A���b�Z�������������s�W���_�̃p���h�N�X�t�ɂ���ēڍ����Ă��܂��̂ł����A�ׂ������ƂȂ̂ł����ł͂ӂ�܂���j
�@�������āA�_���w�����w���A�����ɂ���Ċ�b�Â�����S���R�Ȋw���A���̂������Q���R�̖���ɏW��Ă��܂��܂���
(i) �` �� �`�@�@�`�ł���Ȃ�A�`�ł���B�@
(ii) �` �� ��` �� Ø�@�`�ł���A���`�łȂ��A�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B
(iii) �` �� ��` �� ���@�`�ł��邩�A�`�łȂ����̂ǂ��炩�ł���B
�@�u�`�v�ɂ́A���Ƃ��A�u�\�N���e�X�́A�����͎��ʁv�u�Q�_��ʂ钼���͂P�{�����Ȃ��v�̂悤�Ȗ��肪����܂��B
�@(iii)�i�r�����j�́A�����Ă悢�Ƃ�����������܂��i�u���E�A�[�̒��ϐ��w�j�B�r���������A�s�W���_�̃p���h�N�X�t�͐����Ȃ��Ƃ���܂��B
�@�������A�t�b�T�[���́A�Ab �̎����ɂ́A���łɂ���������������͗���Ă����悤�ł��B�_���w�̐l�����������g��b�Â��h�́A�l���Ă݂�����܂ł���m�b�ŁA���������Ɏ����������w���l������}�`���v�������ׂ��肷��ߒ������������̂ł͂���܂���B
�@�@ �́w�Z�p�̓N�w�x�ŏq�ׂ��悤�ȐS���w�I�Ȑ����\�\�i����́A�o���I�����ɂ���āA�A�E�v���I���k���I�l�ȗ��O�̐^�U����b�Â��悤�Ƃ�����̂ŁA�s�\�Ȋ�Ă��Ƃ��āA�Aa �Ŕے肳�ꂽ�j�\�\�ł͂Ȃ��A�l�Ԃ̈ӎ��̓������̍����ɑk���āA���R�Ȋw�A���w�A�_���w�Ȃǂ̂��܂��܂ȗ��O�A����A�c�t�b�T�[���̌������Ō����Ɓu�C�f�A�I�Ȃ��́v���A�Ȃ����ɕ����Ԃ̂��A�������������͂Ȃ��������A�g�����Ƃ��ł���̂��d�@�Ƃ������ƂɊS���ڂ��Ă����悤�Ɏv���܂��B
�@����d�u�C�f�A�I�Ȃ��́v�����ł͂Ȃ��A���悻���ׂĂ̑Ώۂɂ������鎄�����̔F���\�\�m�o����镨�̂�A�g�̉��̐��E�̂ł����Ƃ�A�|�p��i�̊Ϗ܂Ɏ���܂Ł\�\���悻�A����Ƃ�����F�����˒��ɓ���āA���̍����̂����݂𖾂�݂ɏo�����Ƃ��Ă����̂ł��B
�@���������Ƀt�b�T�[���́A���̇Ab �` �B�̎����ɁA��w�̍u�`�ł́A���̂̒m�o��A�|�p��i�i�����ɊG��ł����j�̊Ϗ܂Ȃǂɂ��ĕ��͂�i�߂Ă��܂������A����炪���\���ꂽ�̂́A�����ƌ�̎������A����̈�e�ɂ���Ăł����B
�@�u�C�f�A�I�Ȃ��́v�́A���Ԃ������I��Ԃ��Ȃ��g�i���̑��݁h�ł����A�����̕�����Ԃɑ������镨�̂Ƃ������ƂɂȂ�ƁA����͎��Ԃ̗���̒��ő������Ă�����̂ł�����܂��B�u�C�f�A�I�Ȃ��́v�ł͕K�v�̂Ȃ������s���ԁt�̕��͂��A�ǂ����Ă��K�v�ɂȂ�̂ŁA�t�b�T�[���� �Ab �̎����i1904-05�N�j�ɁA�u���I���Ԉӎ��̌��ۊw�v�Ƃ����u�`�����Ă��܂��B
�@�|�p��i�̊Ϗ܂ɂ��Ă̍u�`�ł́A������Ȃ������낢���Ƃ������Ă��܂��B�G������鎞�ɁA�������̊�̑O�ɂ���ΏہA���邢�͔O���ɂ���Ώۂ́A���̂R���ƌ����̂ł��F
�i���j�J���o�X�̖��z�ƁA���̏�ɓh��ꂽ�G��B
�i���j�F�A���A�`�ȂǁA�`���ꂽ�Ƃ���̂��́B
�i���j��Ƃ��`�������̑ΏہB�M�A�ʕ��A�l���A�R�ȂǁB
�@�i���j�́A���Ƃ��A�����ɓ\��t�������C�P�U���̏ё���Ȃ�A�v���ŃM���`���ɂ�����ꂽ���C�P�U�����̐l�ł��B���̊G������l�́A������G��̍������Ƃ��Č���̂ł��Ȃ���A���ꂢ�Ȃ��悤�Ƃ��Č���̂ł��Ȃ��A���C�P�U�����̐l�Ƃ��Č���̂ł��B�M���`���ɂ�����ꂽ���C�P�U���Ƃ����̂́A����Ȃӂ��Ȑl�Ȃ̂��A�����ɂ����������ł���Ȃ���킢�A�Ƃ��A�Ȃ��Ȃ��X�^�C���X�g�ł����Ă邶��Ȃ����A�Ƃ��v���Ȃ��猩��킯�ł��B
 �@�@
�@�@
�f���t�B���E�f���{���u�t�����X�����C�P�U���v�@�@
�@�����I�ȈӖ��ŕ����Ƃ��Ď��݂���̂́A�����܂ł��i���j�ł��B�������A���������Ⴆ�Δ��p�w�Z�̊w���ŁA���G��̎g�����A��������w�Ԃ��߂ɂ��̊G�����ɗ����̂łȂ�������A�i���j�́A�G�����Ă��鎞�̎������̔O���ɂ͂���܂���B�������A�������́A200�N�ȏ�O�Ɏ����C�P�U���������Ԃ��Ėڂ̑O�ɂ���Ǝv���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���ꂪ�G���Ƃ������Ƃ͓��̂ǂ����ɂ͂����āA�i���j�����O���Ă���킯�ł͂���܂���B�i���j�Ƃ������݂̑Ώۂ́g�藧�h�́A�ꎞ�I�Ɂg���ʂɓ�����Ă���h�A����g�G�|�P�[����Ă���h�ƌ����܂��B�i���j�́A�����I�ȈӖ��Ŏ��݂���Ώۂł͂���܂����i�����I�Ɏ��݂���̂́A�G��̕\�ʂ̕��q�\���ƌ��G�l���M�[�Ǝ������̊�y�ю��_�o�ł��j�A��͂莞��̓���_�ɋǍ݂���̂ŁA�u�C�f�A�I�Ȃ��́v�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�i���j�ɂ��Ă��A���������G�̑O�ɗ����Č������Ă��鎞�ɂ́A��͂�g�G�|�P�[�h����Ă��܂��B
�@���̂悤�Ȓm�o�̂��������A�t�b�T�[���́u�������ϗl�v�ƌĂт܂����B
�u�������ϗl�̗�Ƃ��Ă͉摜�̒m�o����������B���Ƃ�����l���̏ё�����ς�Ƃ��A����ꂪ�ΏۂƂ���͎̂��݂̓��̐l���ł���A��ʏ�̐F����ł͂Ȃ��B����k��ʏ�̐F����\�\�\�M�g�����l�ɂ��Ă͑��ݗl���͒��������ꂽ�܂܂Ɉӎ�����Ă���ƃt�b�T�[���͏q�ׂĂ���mIdeen�T226.�n�v
�w���ۊw���T�x,p.328�u�������ϗl�v
�@�������āA�����I�ȕ��̂�|�p��i�́g�m�o�h���܂߂Ę_���鏀�������������ŁA�B�i�w�C�f�[���x��P��, 1913�N�j�Ńt�b�T�[���������グ���̂��s���ۊw�I�Ҍ��t�Ƃ������ۊw�̕��@�������킯�ł��B
�@�Ƃ���ŁA�������ās���ۊw�I�Ҍ��t��莮�����Ă݂�ƁA�܂��܂�����ł͕s�\���Ǝv����悤�Ȃ��Ƃ������Ɍ���Ă����̂ł��B�N�����������Ƃ̂Ȃ����A�̉���T�����Ă݂���A���̐�ɂ܂��܂��������̍B���⊄��ڂ������ė����\�\�\�Ƃ����悤�Ȃ��̂ł��B
�@���̂ЂƂ́A�w�C�f�[���x�̂��߂Ɏ��s�����g���Ԉӎ��h�̕��͂ɂ�������Ă��܂����B���������������̈ӎ��́A�g���݁h�\�\�g���܁h�Ƃ������̂��Ƃ炦�邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���H�g���݁h���܂��Ƃ��ɂƂ炦�邱�Ƃ��ł��Ȃ���A�ߋ����������킩��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�@�������̓���̈ӎ��\�\�g���R�I�ԓx�h�̈ӎ����A�������܂��āg���z�_�I�ӎ��h�Ƃ��A����ɂ���ɏ��������āA�������́g���݁h���Ƃ炦�A�g���݁h�̈ӎ��̌���ʼn����s���Ă���̂������Ƃǂ��悤�Ƃ��Ă��A�������łɁg���݁h�͉߂���������ł���A�˂ɂ��łɉ߂������Ă䂭�g���݁h�ɂ́A�ǂ�Ȃɒǂ������Ă��ǂ����܂���B
�@��݂ɂ���������قǂ���݂Ȃ��A�N�w�̃h���E�L�z�[�e�Ƃ���������t�b�T�[���\�\�\���������Ƃ���͋{���Ɏ��Ă��܂��\�\�\�́A�ǂ����ǂ����Ȃ��̂����疳�ʂȓw�͂͂�߂āA�����ƃX�}�[�g�ȕ��@���l���悤�d�Ƃ͂��܂���B������֍s���čs���~�܂�Ȃ�A����ǂ͂����炩��d�ƁA������߂邱�Ƃ�Y�ꂽ�l�̂悤�ɁA�ǂ��܂ł�����ɂނɁg���݁h��ǂ������Ă䂭�̂ł��B
�@���������ɁA�t�b�T�[���̓h�C�c��̑��L�����������ōl�Ă��ĉ��ǂ������̂��g���āA�ӎ��̉��̉��܂ŕ��͂�i�߁A��������₭������낤�Ɠw�͂����悤�ł��B
�@�u���������Ƃ������݁i���x���f�B�Q�E�Q�[�Q�����@���g�j�v�Ƃ́A���́g�˂ɂ��łɉ߂������Ă��錻�݁h�g�������������ďo����Ƃ̂Ȃ����݁h�̂��Ƃł��B
�@�@�ǂ��Ă��ǂ��Ă��ǂ����Ȃ�
�@�@�ӂ肩�����Ă��ӂ肩�����Ă�
�@�@���݂͂˂ɂ��łɂ����������Ă���
�@�@�ӂ肩���肩�����ǂ肫�݂̎c�荁��������
�@�@�����邢�܁@�Ǝ�����
�@�@�u�킽���v�͎����܂����邭
�@�@�����������i���������Ђ�������
�@�@�ǂ������Ő���������
�@�@�����܁@�Ɛ����邢��
�@�@�����邢�܂��삯�����Ă䂭
�@�@�a�r���Čt���i����j�ɂӂ݂��߂�
�@�@�����͂����p�Ȃ���
�@�@�����킽���Ɨ����ǂ܂�킽��
�@�@�s�݂̂˂���ɂ͂��݂̍���
�@�@����͌����đO�ɂ͂��ǂ�Ȃ�
�@�@���݂͌����Ă��܂𗣂�Ȃ�
�@�@皁��i���������j�̎}�ɍs���đj�܂�
�@�@���m��ʊ[�i�ނ���j���T���Ȃ���
�@�@���ǂ�����؈��ɂ�
�@�@�������łɂ��݂͂��Ȃ�

�T�C�J�`
�@�������A�u���������Ƃ������݁v�̖��́A���Ԃ����̖��ł͂���܂���B�s�Ԏ�ϐ��t�Ɓs���ҁt�̖��A�s���E�t�̔����̖��A�������́s�ӎ��̗���t�̔����A��ςƋq�ς̕����A�u����v�Ɓu���فv�̍\���A�d���X�������肪��������ق��Ă��܂��B�����āA�J��Ԃ��J��Ԃ��s���ۊw�I�Ҍ��t�����s���Ă��A�������́g���܁h�́A���܂��ǂ����Ȃ����̐�ɂ���̂ł��B
1916�N�` �t���C�u���N��w�֓]�o
�@�C�@�I�����A�������E�A�u���������Ƃ������݁v�̕��͂�
�u���łɁw���ԍu�`�x�ȗ��A�t�b�T�[���͈ӎ��𗬂�Ƃ݂Ȃ��A���̗���́w�₪�āx�w���܁x�w���������܁x�̊e�ʑ��̂��̍����I������\���A����ہA�c���̗p��ŕ\���Ă����B���̈ʑ��̗��������݂̋�̐����`�Â����k�c�l���̌���ۂ��j�Ƃ��铝��I���ϖ삷�Ȃ킿�ՑO�Ƃ����鎞�ԓI���݂́A����ۓI���܂̗������鑊��悵�Ă���B�w���܁x���ݓI�ł�����̂́w���������܁x�ւƈڍs���A�w�₪�āx����ł��낤���̂��w���܁x�ւƂ���Ă�����B�܂�w�ՑO�x�́A�w���܁x�𒆐S�j�Ƃ��A�w���������܁x���ݓI�ł��������̂Ɓw�₪�āx��������̂��܂ޓ���I��̑Ԃł���A���������̈ʑ��̗������铝��ł���Ƃ��납��w����錻�݁x�Ƃ��Ă���B�k�c�l
�@���̂悤�Ɂw�����錻�݁x�́A����ۓI�j�ʑ��𒆐S�Ƃ��āA�\���I-�c���I�ʑ����Â����ӕ��Ƃ��Ă���̓I�ȓ���ł��邪�A�����Ɂw���ܓI�Ȃ��́x����d�̈Ӗ��Ō����������B�܂���P�ɁA�w���~�܂�`���x�Ƃ��Ă̌��݂ł���A��Q�ɁA����čs�����Ԉʒu���݂ł���B�܂茴��ۂ���c���ւ̗����ɂ�������炸�A�˂Ɂw���܁x�̌`�����P��I�ȗ��~�܂�`���Ƃ��Ďc��B��������ɑ��A���e�Ƃ��ė���䂫�A�ω����Ă��������́w���܁x������킯�ŁA���́w���܁x�̂ق��́A���~�܂�`���������蔲�����ꋎ���Ă������Ԉʒu���Ӗ����Ă���B�k�c�l
�@���~�܂�w���܁x���A������т��ė���Ă������̂ɍ����i�X�^���v�j���������Ƃɂ���āA���ꂽ�w���܁x�������܂��̂����Ɏ��Ԉʒu�w���܁x�ւƓ]�����Ă����B���Ԉʒu�w���܁x�����~�܂錻�݂��Ƃ����Ă������Ƃɂ���āA�͂��߂Č����s�\�̌ʓI���Ԉʒu���߁A���̎��Ԃ̌ʐ��ɂ���Ēm�o�܂��͂��̂Ƃ��̑̌��Ώۂ̌ʐ������藧�B�k�c�l�m�o�Ώۂ̓��ꐫ�����ԓI�Ɍ����I�ɍ\������Ă���̂ł���B�k�c�l
�@�����錻�݂́A�w���~�܂邱�Ɓx�Ɓw����邱�Ɓx�����ꂳ��Ă��錴���I�ȏo�����ł���B�k�c�l���Ȃɂ���Ĕc�������̂́A���Ȃ��Ă��錴���ݓI����ł͂Ȃ��A�������łɗ��ꂽ���ԉ���������ɂ����Ȃ��k�c�l���Ȃ����Ƃ��ɂ͂������łɎ��ԉ���������Ɖ����Ă��邩��ł���B�k�c�l
�@���Ȃɂ����鎩��̎��ȕ���A���Ȃ��鎩��Ɣ��Ȃ���鎩��Ƃ̊Ԃɐ��藧�����k�c�l���Ȃɂ���Ă��̋�������������̂ł͂Ȃ��A�k�c�l���Ȃ��\�ɂȂ�̂́A���łɁA���Ȍ��ݑ��k���u�����錻�݁v�\�\�\�M�g�����l�ɂ����āA����̎��Ȏ��g�ւ̌��I�u���肪�w����邱�Ɓx�ɂ����Ĕ������Ă��邩��ł��v��B
�u�܂����Ȃɂ���ē�̎��䂪���ꉻ�����̂łȂ��A�k�c�l�@�\���鎩�䂪�P��I�ɗ���Ă��邱�Ƃɂ���Ċu���肪���łɂ������ˋ�����Ă���A����͎���ƍ��ꂵ�Ă��邩��A���Ȃɂ���Ď���̓��ꐫ�̊o�F���\�ƂȂ�̂ł���B�v
�V�c�`�O�w���ۊw�Ƃ͉����x,1992,�u�k��(�w�p����),pp.205-210.
�@�w�����錻�݁x���A�v�ٓI�ɋK�肷��̂łȂ��A���ۊw�I�ɉ𖾂��ċL�q���邱�Ƃ́A�ł��Ȃ����̂��낤���H����́A�w�����~�܂邱�Ɓx�Ɓw����邱�Ɓx��I�ɋL�q���邱�ƂłȂ���Ȃ�Ȃ��B�u�w���g�ɂ��ƁA�t�b�T�[�����g�́A�k�c�l����������s�\�ȍ���Ȃ��̂Ƃ݂͂Ȃ��Ȃ��ŁA�W���I�ɂ�����v�҂��Ă������Ƃ��Ă����B������Ƀt�b�T�[�����k�c�l�L�q�̉\�����߂����ĕs��������A�܂��˂��k�c�l�����̍l���ɕs�����ł������k�c�l
�@�t�b�T�[���̈Ӗ��ł̔��Ȃ��Ƃ����āw�����錻�݁x�̓��ꑊ�̗����ւ̓��́A�t�b�T�[���̂��̍Ō�̎��݂ɂ�������炸�A�s�\�ł��邱�Ƃ����Ƃ߂�ꂽ�B�v
�V�c�`�O�w���ۊw�Ƃ͉����x,pp.214-216.
�@�ǂ�ۂ��M�g���Ȃ�ɂ܂Ƃ߂�ƁA�������Ȃ�ł��傤�F
�@�s���������Ƃ������݁t�Ƃ́\�\�\
�@�������̈ӎ��Ɛ��E�����������݂�����Ă��鍪���I�g���܁h�B���������g�Ƃ̊u������ė��ꑱ���A�������P�Ɂg���܁h�ɂƂǂ܂�ԓI�Ȃ��́B����́A����̓��ꐫ�Ǝ��Ȉӎ��A�g���́h�̌ʐ��A�����̋�ʁA��ςƋq�ς̍��قݏo�������I�ȏ�ł���B
���@�@�@�@��
�@�u���������Ƃ������݁v�Ƃ����^�[�����s�����t�̃^�C�g���Ɏؗp���Ȃ���A���̈Ӗ���������Ă��Ȃ������̂ŁA�ق�̊T���ł����A�����ŏ����Ă݂܂����B
�@���́A�s�����t�̂����܂��̂ق��ň����������̕��ꎍ���A���܂������ł����ɓK���ɂ���������ďI���Ă��āA��ϐ\����Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł����A
�@���͂��̎��A�t�b�T�[���́u���������Ƃ������݁v�œǂ݂Ƃ��̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���̂ł��B�������A�M�g���Ƃ��Ă͂܂��A�\���ׂ̍����Ƃ���܂ŗ������y��ł��Ȃ��̂ŁA���̉��߂�O�ʂɗ��ĂĊӏ܂������ɂ́A������Ƃ܂�����������Ȃ��C�����܂��B�Ȃ̂ŁA����́u�тƂ̂Ȃ���v������Ŏ~�߂Ă����܂�������ł����
�u�������߂̂���Ȃ��āA�@�@�@ �t�ׂƌ��������̌��́A
�@�͑��i�����j���Ђ����ĐႰ���A�@���U�߂��������z��Ȃ�B
�@���ɂ͐��Ⴏ�ނ�A�@�@�@�@ ���͔��̐Ԃ₵�A
�@�Ⴐ�̐��͂���߂��āA�@�@�@ ���U�Ђ�����ɂ܂�ԂȂ�B�v
�{���w���ꎍ�e��S�сx���k��e�l
�@�ˁF�{���́s���������Ƃ������݁t�ց\�\�\�w�S�ۃX�P�b�`�x�_����
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]


 �@
�@ 

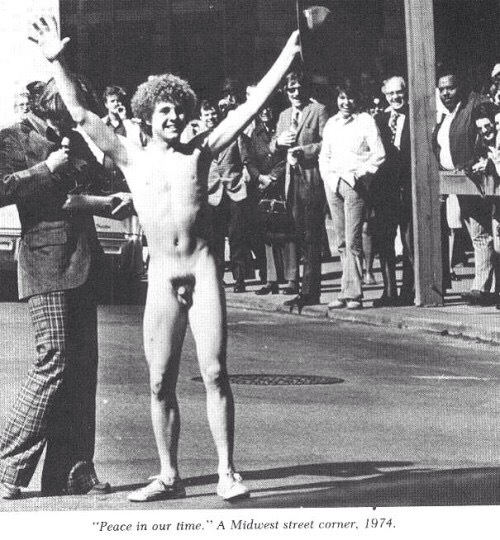
 �@�@
�@�@
 �c
�c