08/28�̓��L
20�F21
�y���[���V�A�z�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�m�[�g(13)
---------------
.
 �@
�@
�@�����́B(º.-)���
�@�y���[���V�A�z�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�m�[�g(12)����̂Â��ł��B
�@�@�}���N�X/�G���Q���X�̋����w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�́A�ҏW���r�̑��e�̏�Ԃň₳�ꂽ�������̒���ł��B���e�I�ɖ������ŁA���܂��܂ɖ�������咣���܂�ł��܂����A���ꂱ�������̍�i�̖��͂ł�����܂��B�܂��A���e�����łȂ��A�`���ʂł��傫�ȍ��ׂ��͂�e�N�X�g�ł��邽�߁A����͂������ѕʍ\���E�f�Ђ̏����Ɏ���܂ŁA�ҏW�҂̉����K�v�Ƃ��Ă���A�Ŗ{�ɂ���đ��ق�����܂��B�����ł́A�A���E�Җ�C���я��l�E���w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,2002,��g����. ���e�N�X�g�Ƃ��Ďg�p���܂��B
�@��L��g���ɔł���̈��p���A���̓}���N�X�̕M�ՁA����ȊO�i�����j�̓G���Q���X�̕M�ՁB���e�̖����ӏ��͉����t���ŁA�NjL�E�}���͎Α̂Ŏ����܂��B
�u�G���Q���X�̕M�ՃG���Q�}���N�X�̕M�����X�̕M�Ձv
�u�l�Ԃ������ʂ���̂́A���Y�����݂����Ȋ��������Ƃɂ���Ăł���B�v
�u�l���������������ʂ���̂́A�����p�������Y���邱�Ƃɂ���Ăł���B�v
�@���́u�m�[�g�v�́A����̓��e��v�邱�Ƃ��A���҂�̎v�z��`���邱�Ƃ��ړI�Ƃ��Ă��܂���B�����܂ł��A���l�̎v���̂��߂̏��^�ƁA�K�������e�N�X�g�ɂƂ���Ȃ��R�����g���c�����߂̂��̂ł��B
�@�y34�z�u�{�_�O�Q�v�\�\�u���L�v�Ɩ@
�u���@�́A���I���L�Ǝ��������āA���R�����I�ȋ����̂̉�̂��琶���Ă���B���[�}�l�̏ꍇ�A���I���L�Ǝ��@�̔��W�́A����ɐi���H�Ə�E���Ə���A���������炷���ƂȂ��I��������A����́A�ނ�̐��Y�l���������ē������̂ł��葱��������ł���B
�@�i�����I�j
�@�H�ƂƏ��Ƃɂ���ĕ����I�ȋ�����������̂��ꂽ�ߑ�̏������̏ꍇ�́A���I���L�Ǝ��@�������ƂƂ��ɁA����Ȃ锭�W���\�ƂȂ�V���ȋǖʂ��n�܂����B�����ɍL�͂ȊC��f�Ղ��c�ŏ��̓s�s�A�}���t�B���́A�����ɊC��@�������グ���s�s�ł������B���߂̓C�^���A�ŁA�����ő��̍��X�ŁA�H�ƂƏ��Ƃ����I���L������ɔ��W������ƁA�����܂��A�o�������̃��[�}���@�����炽�߂č̗p����A���Ђɂ܂ō��߂�ꂽ�B
�@���̌�A�u���W���A�W�[���傫�ȈЗ͂����Ɏ���A�ނ�̗͂���ĕ����M����œ|���ׂ����u���W���A�W�[�̗��Q�̖ʓ|���݂�悤�ɂȂ������A�����鍑�X�Ł\�\�t�����X�ł� 16���I�Ɂ\�\�@�̖{�i�I�Ȕ��W���n�܂����B���̔��W�́A�C�M���X�������ǂ̍��X�ł��A���[�}�@�T��y��ɂ��čs��ꂽ�B�C�M���X�ł��A���@�i���ɓ��Y���L�̏ꍇ�j���d�グ�Ă�����ŁA���[�}�@�̏��������̂���ꂴ������Ȃ������B�\�\�i�@���܂��@���Ɠ��l�A�Ǝ��̗��j�������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�j�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,pp.204-205.
�����u�A�}���t�B�v�F10-11���I�ɉh�����i�|������̊C�`�s�s�B���̊C���@�̓C�^���A�S�̂ɗL���ŁA�n���C�ł͑D�ЂɊւ��Ȃ��d��ꂽ�B�i��Ғ��j
�����u�����I�ȋ����́v�F�����ł͎x�z�҂̋����́A���Ȃ킿���[�G�������w���̂ł��낤�B

�A�}���t�B�̏��
�@�u�ނ�̐��Y�l���������ē������̂ł��葱�����v�\�\�����Łu���Y�l���v�͍L���Ӗ��Ŏg���Ă���B�펯�I�ȈӖ��ł́A���Y�̂����݁A���Ƃ̂����݁A�Ƃ����قǂ̈Ӗ��B��i�Ƃ̔�r�Ō���A�����́i�M���V���̓s�s��A���[�}�����j����̂��邱�ƂȂ������������Ƃ��A���H�Ɣ��W���A�����Ȃ������������A�Ƃ������ƂɂȂ�B���҂�̃V�F�[�}���炷��A�u���@�̔��W�v�Ƃ����ӎ��`�Ԃ̕ω����A���H�ƂƂ����y��̕ω��������炷���Ƃ͂Ȃ��B�g�_�Ƌ����̂̉�́h�Ƃ����T�O���͂����肵�Ȃ����߂ɁA���҂�̈ڍs�̘_���͖������B
�u���@�ɂ����ẮA�����������L���W�͈�ʓI�ӎu�̌��ʂł���Əq�ׂ���B�g�p�Ɨ��p�̌������̂��̂��A����ł́A���I���L��������������O��I�ɓƗ����Ă��܂��Ă���Ƃ���������\�����Ă���A�����ł́A�����������I���L���̂��̂��P�Ȃ����I�ӎu�A�����ɑ���C�ӏ����� die willkürliche Disposition�Ɋ�Â��Ă��邩�̂悤�Ȍ��z��\�����Ă���B�����ۂɂ́A���� das abuti �́A���I���L�҂������ނ����L���A���������Ĕނ̏����� jus abutendi �����l�̎�ɓn��̂߂Ă������̂łȂ���A�ނɂƂ��Ĕ��ɖ��m�Ȍo�ϓI���E�������Ă���B�Ƃ����̂́A������������ die Sache �́A�ނ̈ӎu�Ƃ̊W�ł�������A�Ȃ�畨���ł͂Ȃ��B����ɂ����ď��߂��A�������@�Ƃ͓Ɨ����A�����ƂȂ�A���������L���ƂȂ�̂�����B���i�N�w�҂��������O�ƌĂԈ�W�j
�@�N�w�҂����ɂƂ��Ă̊W�C�R�[�����O�B
�@�ނ�́w�l�ԂȂ���́x�̂��ꎩ�g�ɑ���W�����m�炸�A���̂��߁A�����錻���I�W�́A�ނ�ɂƂ��Ă͏����O�ƂȂ�B
�@�\�\���@�k�������ldas Recht ��P�Ȃ�ӎu�ɊҌ�����E�@���Ƃ́E���̌��z�́A���L���W������ɔ��W���Ă����ƁA�K�R�I�ɁA�N�����E���������ۂɎ����ƂȂ��E���̕����ɑ���@�I�����������Ƃ��ł���A�Ƃ����Ƃ���܂ōs���B
�@���Ƃ��A�����ɂ���āA����n���̒n�オ�����Ȃ��Ă��܂��ꍇ���A���̒n���ɑ������L�҂͂������ɖ@�I�������A�g�p�E������ jus utendi et abutendi ���܂߂Ď����Ă���B�������A����Ŕނɉ������ł���킯�ł͂Ȃ��B�k�c�l���̓y�n���k�삷��ɏ\���Ȏ��{��L���Ă��Ȃ�����A�����Ȃ̂ł���B
�@�@���Ƃ����̓������z����A���̂��Ƃ����������B���l�����݂ɏ��W�����Ԃ��ƁA���Ƃ��Ό_������Ԃ��Ƃ́A�@���Ƃ����ɂƂ��Ă��E�ǂ̖@�T�ɂƂ��Ă��E���悻���R�I�Ȏ��Ԃł���Ƃ������ƁB�����āA�@�T�ɑ��āA�����k���I�ȁl���W�́A���Ԃ����Ȃ����C�ӂł���A���̓��e���܂������_��҂����̌l�I�k���l�ӂɂ䂾�k�˂�ꂽ�l���̂ƌ��Ȃ���邱�Ƃł���B���\�\�\�\�\�\
�@�H�ƂƏ��Ƃ̔��k�W�l�ɂ���ĐV�����k����l���`�ԁA�k��l���Εی���ЁA���X��ЁA�����`������邽�тɁA�@�́A���̂ǁA���������Y�l�����@�̂Ȃ��ɉ�����������Ȃ������B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,pp.205-208.
�����u�����́v�F�����ł��A�x�z�҂̋����̂��Ȃ킿���[�G�������w���̂ł��낤�B�������A�_�Ƌ����̂ɓǂ݊������ق����g�ڍs�̘_���h���悭�킩��̂͂������B
���c�c���F�͏o�ł̌������Q�Ƃ��ĉ���B
�����u�n�オ�����Ȃ��Ă��܂��ꍇ�v�F��翂ȏꏊ�ɂ�������A�����Ă����肵�āA��肪�Ȃ��Ȃ����_�n���l���Ă݂�悢�B���̓y�n�́A���v���o�Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�����Ə����̗ǂ��y�n����������̂ŁA�N���A�n����Ď�悤�Ƃ͂��Ȃ��̂ł���B�����ŁA���L�Ҏ��g���k�����Ƃ��Ă��A�y�n���ǂ̔�p��ق��l�̘J�����x�������肪�Ȃ���A���̓y�n�͗V���Ă����ق��͂Ȃ����ƂɂȂ�B�������悤�ɂ��A�����肪���Ȃ��B���邱�Ƃ��A�݂����Ƃ��A�g�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��E���̂悤�ȓy�n�́A���L�҂ɂƂ��č��Y�i���L���j�̈Ӗ��������Ȃ����A������Ƃ����āA�u���L���v�����ł���킯�ł͂Ȃ��B
�@�@���L���̐�ΐ��A�A�_������R�B�������u�@���Ƃ̌��z�v���ƌ����̂����A���́u���z�v�ɉ����čٔ����s���A�����̖\�͂���������Ă���ȏ�A�P�Ȃ�u���z�v�ł͂Ȃ��B
�@�y35�z�f�́\�\�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�������_
�u��1�́w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�������_���k�c�l�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�ɂ݂��������_�̘_���ƍ\�����A�����I�ɍč\�����悤�Ǝ��݂����̂ł���B
�@�}���N�X�E�G���Q���X�������ςƂ����A�w���Y�}�錾�x�Ȃǂŏq�ׂ��Ă���w�x�z�K���̋@�ցx�Ƃ������肪�L���ł��邪�A��e�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�ɂ͂��̖����k�c�l�̑��ɁA�����Ƃ͈��̗��v�����̂ł���Ƃ�����肪�ڂɂ��B�����ł́A�������ȂĎЉ���̈�@�ւƊς�����A�Љ�S�̂̓����ԂƂ��Ĉ������p����ɂȂ��Ă���B�v
�w�A������W�x,1997,��g���X,��11��,�u�B���j�ςƍ��Ƙ_�v,p.323.
�@
�@�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�Ɍ��ꂽ�����_�́A�Ĉ�I�Ȍ`�ɐ�������Ă���킯�ł͂Ȃ��A����e�̐�����A�����̍l�������Z�W���܂��܂ɍ����荇���Ă���A�����_�Ƃ������u�����ρv�ƌ������ق����悢�B
�@�P���Ȍ���������A�����ɂ͎���㋐㋑㋒㋓��������B
㋐�@�����́A�x�z�K������x�z�K�����x�z���邽�߂ɐ݂����u�@�ցv�ł���B�܂�g�x�z�K���̓���h�ł���\�͑��u�ł���B
㋑�@�����́A���l����Ȃ�s���Љ�o���o���ɂȂ��Ă��܂�Ȃ��悤��������@�\��L����u�����́v�ł���B�������̌�����̂́A����̌l���K���̗��Q�ł͂Ȃ��A�Љ�S�̂̋������Q�ł���B�����́A���̋������Q���u���ՓI���Q�v���Ȃ킿�u���I�v�Ȃ��̂Ƃ��Ď咣����B�����́A�u���I�v�����̖��ɂ����āA�������̓��ꗘ�Q�̊Ԃ̕�����A�K���Ԃ̑Η��₷��B
㋒�@�����́A���̖{���ɂ����Ďx�z�K���̗��v���\���Ă���̂����A�����I��ɂ��Ďx�z���s�Ȃ����Ƃ���A�������Ɉێ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�I��Ȗ\�͓I�x�z�͉i�������Ȃ��B������㋑�̊O����܂Ƃ��B���Ȃ킿�A���̓����@�\���ʂ����A��Ɏx�z�K���ɕ�d����̂ł͂Ȃ��A������x�̒���@�\������B����ɉ����āA��x�z�K���ɂ́A�����́g�Љ�S�̂̓����ł����\�ł���h�Ƃ������z��������B
㋓�@�������A㋒�́g���z�h�́A�[�ւɂ���āu������@���o���v���Ƃ��ł���悤�ȁg�܂ڂ낵�h�ł͂Ȃ��B���l�̑��ݓI�u���Ȋ����v���Ȃ킿���Y����������𒆐S�Ƃ��鏔�����̗��ݍ����Ɍ����I�����������Ă���B�P�Ȃ錶�z�ł͂Ȃ��A�����̏��l�̏��W���u���ۉ��v�����E�a�O�Ԃɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@���[�j���́A㋐����������Ɏ咣���A㋑�ȉ��������B���[�j���͈�e�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x������@��Ȃ��������A�A�����ɂ��A㋑�ȉ��́A�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�݂̂Ȃ炸�A�}���N�X�E�G���Q���X�̌���̒���ɂ��U�������B���[�j���́A�����x�z�������������߂ɁA�s���̈������Ƃ͌̈ӂɖ������A�g�U�}���N�X�h���Ղ�グ���̂��B
�@���[�j���𐒔q���āA㋐�����ς�����I�ɐM�����͎҂��������]�L�̋��|�������o���������̂́A�_���I�K�R�Ƃ����ق��Ȃ��B�ނ�́A�x�z�K���v�����^���A�̖��̂��ƂɁA��x�z�K���u���W���A�Ƃ݂Ȃ����l�тƁ\�\������́A�S�l���\�\��}�������̂��B���[�j���́w���ƂƊv���x�ɏ����ꂽ�u�v�����^���A�����v�̋���I�K�p���̂��̂ł������B���Ɂu�X�^�[������`�v�ƌ������A�X�^�[������l�������̂ł͂Ȃ��A�����̓��[�j���ƃ{���V�F���B�L�S�}�ł������B
�@㋐�����������ɂ���A�I��Ȗ\�͓I�x�z����������������邱�ƂɂȂ�B�������A�{���́A�����Ȓ����̈ێ����������������̊�b�ł��邵�A�x�z�K���ɂƂ��Ă����v�Ȃ̂��B���������_�Ɛ��Y�́A�����Ȓ������Ȃ���Εs�\���B�{���V�F���B�L�̎����ɂ���āA���q�̃E�N���C�i���ł��Ђǂ���Q�����̂́A���R�ł��i�`�X�̂����ł��Ȃ��B
�@�Ƃ��낪�A���[�j���̎���Ɂw�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x����������A㋑�ȉ������J����Ă��܂����B�������������U�m�t�͏l������Ǖ����ꂽ���A���Ƃ̍Ղ肾�����B���[�j����㋐�����ς�M��\�A�̎x�z�w�A����ё��̍��X�́u�}���N�X��`�v�҂ɂƂ��ēs�����������ƂɁA�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�������ς́A㋑�ȉ������S�Ȃ̂��B
�u���z�I�Ƃ����`�e�������Ă��悤�Ɠe��������̋������v�����̂Ƃ��������K��v�́A�u�}���N�X�������`���(��)�����[�j����`�v�҂ɂƂ��ēs���������B�������A�u��N�ɂ�����}���N�X�E�G���Q���X�̕��T�ɂ����v�����̂Ƃ��Ă������Ƃ������p���������Ă���A�]���ă}���N�X�E�G���Q���X���k�c�l"������������"��������"�������@��"���ւƈڍs�����̂��ƒP���Ɍ�����킯�ɂ͂����Ȃ��v
�w�A������W�x,1997,��g���X,��11��,�u�B���j�ςƍ��Ƙ_�v,pp.324-325.
�u�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�ɐ����Ă��������_�̏�����k�c�l
�@��@���z�I�ȋ����̂Ƃ��Ă������Ƃ����K��
�@��@�s���Љ�̑����Ƃ��Ă������Ƃ����K��
�@�O�@�x�z�K���ɑ����鏔�l�̋����̂Ƃ��Ă������Ƃ����K��
�@�l�@�x�z�K���̎x�z�@�ւƂ��Ă������Ƃ����K��v
�w�A������W�x,1997,��g���X,��11��,�u�B���j�ςƍ��Ƙ_�v,pp.342-343.
�u���z�I�����̂Ƃ��Ă������Ƃ����_�q�́A�G���Q���X�̊��e�̗��O�Ƀ}���N�X�������݂������Ȃ��A����������Ă��G���Q���X������Ȃ鏑���݂��k�����āl�Ǖ₷��Ƃ��������G�ȉߒ���H���Đ������Ă�����̂ł���A���e�����̕��͂ɃQ�V���^���g�E�`�F���W�������Ă���������B�v
�w�A������W�x,1997,��g���X,��11��,�u�B���j�ςƍ��Ƙ_�v,p.325.
�@�����ŁA�A�����ɏ]���āA�u���z�I�����̂Ƃ��Ă������v�_�����̒����e�N�X�g�����ǂ��Ă��������B���e�̌����͌�ɂ��āA�܂��́A�Y�������̎��M�@����ǂ������Ă݂�B
�@�܂��A{8}a=[16] ��������i��g���ɔ�,p.64-�j�AⒶ�̏��q���n�܂�B�u���L�v�̔����Ƃ��̌`�Ԃ̔��W���A���n�Љ�̉Ƒ���������N�����Ă��镔���ł���B���̔��W�̃L�[�T�O�́u�����v�Ɓu����v�B�u�����v�Ɓu����v�̔��W�̂Ȃ��ŁA�u�l�Ȃ����X�̉Ƒ��̗��Q�v�Ɓu����������Ă��鏔�l�S���̋����I���Q�v���������A�����������悤�ɂȂ�F��
�uⒶ���L�́A�ȂƎq���������v�̓z��ł���悤�ȉƑ��̓��ɁA���łɂ��̖G��A���̍ŏ��̌`�Ԃ������Ă����B�Ƒ����ɂ�����A�ܘ_�܂��ɂ߂đe��Ő��ݓI�ȓz�ꐧ�A���ꂪ�ŏ������L�ł���B����ɂ��Ă����̍ŏ������L�́A�k�c�l���L�Ƃ͑��l�̘J���͂��ӂ̂܂܂ɂ��邱�Ƃ��Ƃ����ߑ�̌o�ϊw�҂����̒�`�ɂ܂������K���Ă���B�Ƃ�����A�����Ǝ��I���L�Ƃ́A�������Ƃ��k�قȂ�l�\���ł���\�\��҂ɂ����Ċ����̐��Y���Ƃ̊W�Ō����\�킳��Ă�����̂��A�O�҂ɂ����Ă͊����Ƃ̊֘A�Ō����\�킳��Ă���̂ł���B
�@����ɂ����A�����Ɠ����ɁA�X�̌l�Ȃ����X�̉Ƒ��̗��Q�ƁA����������Ă��鏔�l�S���̋����I���Q�Ƃ̖��������݂���悤�ɂȂ��Ă���B�������A���̋����I���Q�Ƃ����̂́A��������P�ɕ\�ۂ̓��Ɂw���ՓI�Ȃ��́x�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��A
�@��
�܂��͌����̓��ɁA�J�������Ă��鏔�l�̑��݈ˑ����Ƃ��Ď�������̂ł���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.64-66.
�@Ⓐ�̏��q�̓r���́��̉ӏ�����A�E���O�ɁA�{���Ɠ����G���Q���X�̕M�ՂŁA�����́u�����݁v���s�Ȃ���iⒷ�j�BⒷ�ɑ����āA���̂܂ܗ��O�ɁA�}���N�X�̕M�Ղŏ�������Ⓒ���s�Ȃ���B
�@���̂��ƁA�G���Q���X�̕M�ՂŖ{���������p�����iⒹ���j�BⒹ�́A���̓��e���炵�āA�}���N�X�̗��O��������Ⓒ���āA���̉e���̂��ƂɁAⒶⒷ�Ƃ͂��قȂ��ӂœW�J����Ă���B���������āA�G���Q���X�ɂ��{�����M�́AⒹ�̑O�ł������f���A���O�������݂̂��ƂōĊJ���ꂽ���Ƃ��킩��B
�uⒹ�����čŌ�ɁA�����͎��̂��Ƃɂ��čŏ��̗���A���������ɒ��Ă����B���Ȃ킿�A�k�c�l����ȗ��Q�Ƌ��ʂ̗��Q�Ƃ̕������������A�����������J�����������R�ӎu�I�ɂł͂Ȃ����R�����I�ɕ�������Ă������A�l�Ԏ��g�̍s�ׂ��l�ԂɂƂ��đa���ȁA�R�I�ȈЗ͂ƂȂ�A�l�Ԃ�������x�z����̂ł͂Ȃ��A���̈З͂̕����l�Ԃ��x�z�������������A�Ƃ������Ƃł���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,p.66.
�@�u�����v�ɂ��u���L�v�̔��W�Ɨ��Q�̕����Ɋւ�����j���q�́AⒹ�ł�������I��i�܂����n���ォ��o���������肾���j�A���̂��Ƃɂ́A�L���ȁu���͎������A�ߌ�͋������A�c�c�v�́g���q�̓I���[�g�s�A�h�Œ��߂�������E�g�����J������̉���h�̏��q�������B�g���q�̓I���[�g�s�A�h�� {8}b=[17] ���I���Ă���B
�@���āA���O�����݂́A���̂悤�ɂȂ��Ă���B�܂��A�G���Q���X�̗��O������Ⓑ�́A�u����I���Q�Ƌ����I���Q�v�̕����Ƃ����{���̏��q�ɃR�����g����`�ŁA�u�����I���Q�v�����������������邱�Ƃ��q�ׂ�B�Ƃ����̂́A�u�����I���Q�v�́A�����́u�S�̓I���Q�v�Ƃ��u�ʓI���Q�v�Ƃ��قȂ�E�����I�Ȏp����炴������Ȃ�����ł���B���̈Ӗ��ŁA�u�����I���Q�v�i��m�c�E�s�s���Ƃ�ꐧ�������C���[�W���悤�j�́A�l�тƂ̌����I�E����I�ӎ��₻�̑��a���璼���ɏo�Ă���u�ʓI���Q�v�u�S�̓I���Q�v�Ƃ͈قȂ�E�u�����I�v�Ȉӎ��`�Ԃł��������B
�@�܂��A���̂悤��Ⓑ�̓��e����A�Ȃ������Ŗ{���̎��M�����f����ė��O�ɒ��X�Ə����݂������̂����A�Ȃ�ƂȂ��킩���Ă���B�{���̏��q�͂܂����n����Ȃ̂ɁA���_�I�Ȉӑz�̓W�J�ɑ�����āA���O�ł́A�����������o�ꂵ�āA�c�_�̒��S�ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂��B
 �@
�@
�uⒷ�܂������A����I���Q�Ƌ����I���Q�Ƃ̂��̖�������A�����I���Q�������Ƃ����`��������A�����̌ʓI���Q�Ȃ�тɑS�̓I���Q����藣���ꂽ�����I�Ȏp���Ƃ�B
�@�����ē����Ɍ��z�I�ȋ������Ƃ���
�Ƃ͂����Ă��A�k�c�l�e�X�̉Ƒ��W�c�╔���W�c�̂����Ɍ��O����A���ƌ��A����A���Ȃ��K�͂������₻�̑��̗��Q�Ƃ������R�сA�����ĂƂ�킯�A�k�c�l���ł������ɂ���ď����Â����Ă��鏔�K���\�\������ނ̐l�ԏW�c���Ƃɕ�����A���̂����̈�K�������̑S�K�����x�z����\�\�Ƃ������ݓI�ȓy��̏�ł̂��Ƃł���B
�@�������玟�̂悤�Ȍ��_���o�Ă���B���吭�E�M�����E�N�吭�̊Ԃ̓����A�I�����̂��߂̓����A���X�A�����̓����ɂ������̓����́A���܂��܂ȊK���Ԃ̌����I�ȓ��������������`�Ԃ��Ƃ��čs����Ƃ���́A���z�I�ȏ��`�Ԃɂ����Ȃ��B
�@���������A���ՓI�Ȃ��̂Ƃ����̂́A�����I�Ȃ��̂̌��z�I�`�ԂȂ̂�
�k�c�l�����Ă���ɁA�k���̏��K���ɑ���l�x�z����ڎw���ǂ̊K�����\�\�v�����^���A�[�g�̏ꍇ�k�c�l�ł����\�\�܂������Đ��������k�����́l��D�悵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������̗��Q�����x�͕��ՓI�Ȃ��̂Ƃ��Ď����k�c�l���߂ł���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.66-68.
�@Ⓑ�̌��_�Ƃ��āA�u�x�z����ڎw���ǂ̊K�����\�\�v�����^���A�[�g�̏ꍇ�c�c�ł����\�\�܂������Đ������͂�D�悵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������̗��Q�����x�͕��ՓI�Ȃ��̂Ƃ��Ď������߂ł���v�ƃG���Q���X�͏����i�܂����܂������Ƃ̂Ȃ��ߌ��h�M�����I�j�B������A���������E�꓁�S�f�I�Ɍ����Ă��܂��A�g�����͊K���x�z�̓���B�x�z�́A���邩�A����邩���B�u���W�������낤�ƃv�����^���A���낤�ƁA�������͂�����Ȃ���A�x�z���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��h�Ƃ������ƂɂȂ�B�������A���������������͂��Ă��Ȃ����Ƃɒ��ӂ������B������爬��A�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�u���������̗��Q���c�c���ՓI�Ȃ��̂Ƃ��Ď����v�\�\�l�тƂɐM��������\�\���߂ɂ́A�������킪���̂Ƃ���K�v������d�d�Ƃ����̂��B
�@�i�܂�A�u���W���A�W�[���A���̋������Q�k�K�����Q�l���u���Չ��v���邽�߂ɂ́A�s���v���ɂ���Č��͂����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ����A�Ƃ����̂��B�����ɂ́A�g���Y�͂̔��W�ɂƂ��Ğ~���ƂȂ��������x��ł��j�邽�߂Ɏs���v�����N�������h�A�Ƃ��������Ƃ͈قȂ�E�s���v���̗��j�I���i�̗���������B�j
�@�������������邽�߂ɂ́\�\���l���x�z���A�������邽�߂ɂ́\�\�u���Ր��v���d�v�ȃ������g�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B��������A�u�����I���Q�v�\�\�������̌����闘�Q�\�\�́u���z�I�v���i�܂ł́A���ƈ���Ǝv���邪�A�G���Q���X�͂����Ɍ����y��ł͂��Ȃ��B
�@�u�����ē����Ɍ��z�I�ȋ������Ƃ��āv�Ɓu���������A���ՓI�Ȃ��̂Ƃ����̂́A�����I�Ȃ��̂̌��z�I�`�ԂȂ̂��v�́A���̗��O������Ⓑ�ɑ��āA����ɍs���O�̏����݂Ƃ��āA�Ȃ���Ă���B�}���N�X�̏�����Ⓒ�����āA�G���Q���X�������̏�����Ⓑ���������̂Ǝv���A�����ŁA�G���Q���X�̕M�Ղł͏��߂āA�u���z�I�������v�Ƃ��Ă������d�Ƃ����K�肪������B
�@Ⓑ�̂��Ƃɑ����āA�}���N�X�̕M�Ղ�Ⓒ�̏����݂��s�Ȃ���F
�uⒸ���܂��������l�������ς�ނ�̓���I�ȁ\�\�k�c�l���������̋����I���Q�Ƃ͈�v���Ȃ����Q���A�Njy���邩�炱���A�\�\���̂����k����I���Q�\�\�M�g�����l�͔ނ�ɂƂ��āw�a���ȁx�A�ނ炩��w�Ɨ��ȁx�����k�@���A�N�w���l�Ƃ��āA��d�ɂ�����I�ŁA���Ɠ��́w���Ձx���Q�Ƃ��āA�܂���ʂ邱�ƂɂȂ����B���邢�́A���吭�̏ꍇ�̂悤�ɁA�ނ玩�g�������k����ƕ��Ղ́l��ɕ���̒��œ�����������Ȃ����ƂɂȂ�B����䂦�A���ʂł́A�����I���Q����ь��z�I�ȋ����I���Q�k�������l�ɑΗ������k�c�l������A�������ꗘ�Q�̎��H�I�������܂��A�����Ƃ������z�I�ȁw���Ձx���Q�ɂ����H�I�Ȓ���Ɛ����K�v�Ƃ��邱�ƂɂȂ�B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.68-71.
���c�c���F���̂P���́A�͏o�ł̌������Q�Ƃ��ĉ����B

�@�}���N�X�̏����݂́A����܂ł̃G���Q���X�̍s�_�Ƃ͂��َ��Ȋp�x������𑨂��A���~�N���ȕ����ɓ��@�������Ă���A�܂��A�a�ł���B���̌����Ƃ����|�́A���l�́u�������Q�v����u�����v�����邾���łȂ��A���̓����ɂ��ڂ�������A�Ƃ������Ƃɂ���悤���B�s�s���Ƃ̓����ł́A���܂��܂Ȕh���̑������₦�Ȃ��������A���m�I�Ȑꐧ�����̓����ł��A�����ł������낤�B�����̔h���́A�l�i��Ƒ��j�́u����I���Q�v�ƌ����čςނ悤�ȒP���Ȃ��̂ł͕K�������Ȃ��������A�����̘g�������͂ł���ꍇ���������ł��낤�B�Ⴆ�A�M���V���E���|���X�����̃}�P�h�j�A�h�B�����́A�u����I���Q�v�ł���Ȃ���A�u�Ɠ��́w���ՓI���Q�x�v�Ƃ��āu�܂���ʂ��Ă��� gelten�v�B����䂦�ɁA�u�����v�Ƃ����u�����v�������u�������Q�v�ɝh�R���邾���̎������A���Ր����A�l�тƂ̈ӎ��ɑ��ċy�ڂ����Ƃ��ł���̂��B
�@���̏ꍇ�A�u�����v�́A�������l���o���o���ɕ��Ă��܂��̂�h�����߂ɂ́A�������̔h���\�\�g���Ր����咣������ꗘ�Q�h�\�\�̂������Łu����Ɛ���v���s�Ȃ�˂Ȃ�Ȃ��B�u����Ɛ���v�́A�A�e�l�̂悤�Ȗ��吭�̏ꍇ�ɂ́A���J�I�ȃ��[���ɑ����čs���A�M�����a���Ȃ�A�����Ԃ̗͊W�Ɠ����ɂ�邱�ƂɂȂ邾�낤�B�ꐧ�����Ȃ�A���̋C�܂���Ō������邱�Ƃ����낤�i�C�܂���́A�܂Ɠ��l�ɐl�q���Ă���䂦�ɁA����Ƃ��ċ@�\������B�C�܂��ꂪ�C�܂���ł��邽�߂ɂ́A�ӂ���͌����I�Ȍ��͂������Ȃ��_���I�ȉ����]�܂�����������Ȃ��j�B
�@���吭�A�ꐧ�����A������ɂ����Ă��A�u�����v������@�\���ł���̂́A�u�����v���u���z�I�v�ȁu���ՓI���Q�v�Ƃ��Đl�тƂ̈ӎ����x�z���Ă��邩�炱���ł����B�i�{��Ⓐ�ŏq�ׂ��Ă����悤�ȁE���l�̌����I���݈ˑ����Ɋ�Â��u�������Q�v�ł���A�Ƃ��������ł́A���ꂼ�ꂪ�u���Ձv�������u���ꗘ�Q�v�̂������Œ�����s�Ȃ��ɂ͕s���������A�Ƃ������Ƃł��낤�j
�@���āA�ȏ�̏����݂��āA�G���Q���X�͖{���̎��M���ĊJ����iⒹ�j�B�����ł́A�u�����I���Q�v���u�����v�Ƃ��āu�������v����E�u���ۉ��v�̋@�����q�ׂ���B�u���z�̋����̂Ƃ��Ă������v�Ƃ����}���N�X�̎w�E���A�G���Q���X�́A�u���ۉ��_�v�ɂ���Ď~�߂��̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�ȏ��ⒶⒷⒸⒹ��ʂ��āA�u�����v���A�x�z�K���̗��Q�ɏ]�����Ĕ�x�z�K����}������Ƃ����@�\�́A���Ȃ��Ƃ��\�ʏ�͌���Ă��Ȃ����Ƃɒ��ӂ��悤�B
�@�ȏ�Ńe�N�X�g�����̋@�����ЂƂƂ���ǂ����̂ŁA�����ōŏ��ɖ߂��āA���e�����Ă䂭�ƁAⒶ�̖{���ɑ����ď��ߏ����ꂽ������Ⓑ�ł́A�����̌ʗ��Q�Ƃ��S�̗��Q�Ƃ�����āu�����Ƃ��Ď����I�Ȏp�Ԃ��Ƃ�v�u�����I���Q�v�́A�Ƃ͂����i�܂������j���z�I�ȊϔO�Ȃ킯�ł͂Ȃ��A
�u�w��Ɏ��ݓI�ȓy��A�܂�A�c�c���ƌ��A����A���Ȃ��K�͂������₻�̑��̗��Q�Ƃ������R�т̂����ɁA�����ĂƂ�킯�A���ł������ɂ���ď����Â����Ă��鏔�K���x�Ƃ��������ݓI�ȓy��̂����ɁA�����I���Q�������Ƃ��������I�Ȏp�Ԃ��Ƃ�̂ł���]�X�B�v
�w�A������W�x,1997,��g���X,��11��,�u�B���j�ςƍ��Ƙ_�v,p.344.
�@�܂�A�G���Q���X�̂��Ƃ̕��ł́A���l�̊Ԃ̌����I�Ȋ����́u���݈ˑ����v����A�����I���Q���u�����v�Ƃ����p���Ƃ��Č���Ă���Ƃ����u���ݓI�v�Ȗʂ��d������Ă���킯�ŁA
�@Ⓑ�̂��ƂɃ}���N�X�̏�����Ⓒ���s�Ȃ��A������āu���z�I�������v�u�����I�Ȃ��̂̌��z�I�`�ԁv�Ƃ����G���Q���X�̑}���Q����Ⓑ�ɑ��čs���ď��߂āA�u���z�I�����̂Ƃ��Ă������v�Ƃ����V�������e���������Ă���B
�u�G���Q���X�������������낵�������kⒶ�l�ł́A�Љ�I�����̐����m�����Ă���Ƃ���ł́A�X�l�Ȃ����X�̉Ƒ��̓���I���Q�ƁA�Љ���S�̂̋����I���Q�Ƃ̖��������݂���悤�ɂȂ��Ă���Ƃ������ƁA�k�c�l���́w�������Q�x�Ƃ����̂͌����ĒP�Ȃ��ϓI���e�ł͂Ȃ��ƁA�k�c�l�w�J�������Ă��鏔�l�̑��ݓI�ˑ����Ƃ��Ď�������x�̂��Ƃ������ƁA���̂�������k�c�l�P�Ȃ錶�e�ł͂Ȃ����Ƃ�����k�c�l
�@���O�����݂̍ŏ��̌`�kⒷ�l�ɂ����Ă��A�k�c�l�����ƂȂ��Ď����I�Ȏp�Ԃ��Ƃ鋤�����Q�́A�����܂ŁA���ݓI�ȓy��ɍ������Ă���Ƃ������Ƃ̎w�E�ɃA�N�Z���g��������Ă���܂��B
�@�����ő����̕��X�́A�w�[�Q���̌含�����_��A�z�����ł���܂��傤�B����I���Q�Ƌ����I���Q�Ƃ̖����Ƃ����_�_�ɂ���A"���ՓI�Ȃ���"�]�X�Ƃ����_�_�ɂ���A�������Ƀw�[�Q���̌含�����_�Ɛ[���W������܂��B�v
�w�A������W�x,1997,��g���X,��11��,�u�B���j�ςƍ��Ƙ_�v,p.349.
�@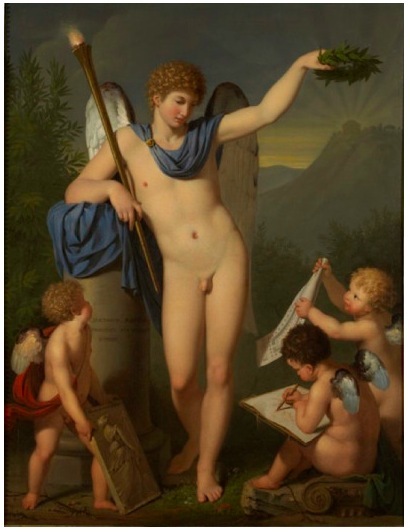
�@�w�[�Q���ɂ��A�u�s���Љ��k�c�l�ɂ����Ă��k�c�l�e�l�̓o���o���ȃA�g���Ƃ��đ��݂ɑΗ��������A���l�̖��l�ɑ���킢�����o����B�k�c�l
�@�s���Љ�̐����Ƃ��Ắw���l�͂��̂ꎩ�g�̗��v��ړI�Ƃ��鎄�I�l�i�x�ł���v���A�u�e�l���e�X�̗��ȓI�ȖړI���������悤�Ɛ}�邱�Ƃɂ����āA����Ί��������āw�S�ʓI�ȑ��݈ˑ��̑̌n�x���`�������B�k�c�l
�@�w�[�Q���̂����s���Љ�́A�P�Ȃ�o�ς̉����ł͂Ȃ��A�i�@����������s�����܂ށw�含�����x�ł���B�v
�A���w�}���N�X��`�̗��H�x,��1974,������,2009,�������[,pp.165-166.
�u�G���Q���X�Ƃ��ẮA�������̌�����Ə̂����"����"�Ȃ���̂́A�����I���݈ˑ��Ɋ�Â������I���Q�Ƃ������ݓI�ȓy��ɍ������Ƃ����ʂ�����������_���Ă���̂ɑ��āA�}���N�X�́A�����Ƃ���́w�����I���Q�x�Ȃ���́A�Ђ��Ắg���ՂȂ���́h�����ۂɂ͌��z�I�ł���Ƃ����ʂɃA�N�Z���g��u���Ă���B�v
�w�A������W�x,1997,��g���X,��11��,�u�B���j�ςƍ��Ƙ_�v,pp.350-353.
�@{8}b=[17] �ɂ��ẮA�ȏ�B���̕��������Ă������B
�@���̋K��u�s���Љ�̑����Ƃ��Ă������v�ɂ��ẮA{91}c=[70] �ɁA
�u�����Ƃ́A�c�c�ꎞ��̎s���Љ�S�̂����������`�Ŏ��Ȃ������`���ł���v
�@�Ƃ����L���Ȍ��\������B�O����܂߂Ĉ��p����ƁF
�u�����Ƃ́A�x�z�K���̏��l�����������`�Ŕނ�̋��ʂ̗��Q�������ʂ��A�����Ĉꎞ��̎s���Љ�S�̂����������`�Ŏ��Ȃ������`���ł��邩��A���ʂ̏����x�͂��ׂ������ɂ���Ĕ}���A�����I�Ȍ`������������邱�ƂɂȂ�B��������A�@�������������ӎu�ɁA���������̎��ݓI�ȓy�䂩������������ꂽ���R�ӎu�ɁA��Â����̂ł��邩�̂悤�Ȍ��z��������B�����Ȃ���x�́A�@�k�������ldas Recht �����l�ɁA�@���ɊҌ������B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,pp.203-204.
�@�ƂȂ��Ă��āA���́u�����̌`���v��ʂ��ĊѓO�����̂́A�u�x�z�K���̏��l�v�́u���ʂ̗��Q�v�ɂق��Ȃ�Ȃ����Ƃ��q�ׂ��Ă���B�܂��A�����ŋ�g�����@�I�_�����A�u�����v���A�����I���`�����A���ׂĈ��́u���z�v�Ƃ��āA�u���ݓI�ȓy�䂩�������������v�āu�����v���Ă���B
�@{88}c=[58] �ɂ́A
�u����ɑ��ăv�����^���A�����́A�l�i�I�ɂЂƂ��ǂ̎҂Ƃ��ĔF�߂��邽�߂ɂ́A�ނ玩�g�̂���܂ł̐��������\�\����͓����ɂ���܂ł̎Љ�S�̂̐��������ł�����\�\���A�܂�J�����A�p�~���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������āA�v�����^���A�����́A�Љ��̏��l������܂Ŏ����������A�k�ցl�S�̓I�\���Ƃ��Ă����`�ԁA���Ȃ킿�����ɑ��Ă��܂��A���ڑΗ����闧��ɗ����Ă���̂ł���A�ނ�̐l�i�I�݂����S�����邽�߂ɂ́A������œ|���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,p.180.
�@�Ƃ����N�_��������A������������ьォ��̑}�������������ƁA
�u�Љ����܂Ŏ����̑S�̓I�\���Ƃ��Ă��� in der die Individuen der Gesellschaft sich bisher einen Gesamtausdruck gaben �`�ԁA���Ȃ킿�����v
�@�ƂȂ�B�܂�A�u���W�����Љ�́A�u�����v�ɂ����āA���̑S�̓I�\�����^������B�������A���́u�S�̓I�\���v�́A��x�z�҂ɂƂ��Ă͋\�ԓI�ȕs���ȑ��ł���A�����������e�ɂ����Ȃ��B
�@{10}b=[24] �̖��������ɂ́A
�u���̗��j�ς́A����䂦���̂��ƂɊ�Â��Ă���B���Ȃ킿�A�����I�Ȑ��Y�ߒ����A��������ړI�Ȑ��k�����l�̕����I�Ȑ��Y����o�����āA�W�J���邱�ƁA�����Ă��̐��Y�l���ƘA�ւ��Ȃ��炱��ɂ���đn�o���ꂽ����`�Ԃ��A���������Ďs���Љ���A���̂��܂��܂Ȓi�K�ɂ����āA����т���̎��H�I�|�ϔO�_�I�ȋ����A�܂������ɂ������S���j�̊�b�Ƃ��Ĕc�����邱�ƁA�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,pp.86-87.
�@�Ƃ���B�Ō�̕����́A��������������ƁA
�u�s���Љ���A���̂��܂��܂Ȓi�K�ɂ����āA����т���̎��H�I�|�ϔO�_�I�ȋ����A�܂������ɂ����āA�S���j�̊�b�Ƃ��Ĕc�����邱�Ɓv
�@�ƂȂ�B�܂�A���j��̂��܂��܂Ȓi�K�́u�s���Љ�v���A���̎��ۏ�̎p�A���Ȃ킿�ϔO�_�I�i�C�f�I���[�M�b�V���j�ȁu�����v�ł���u�����v�̎p�ɂ����āA�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@{91}a=[68] �ɂ́A
�u�s���Љ�́A�ΊO�I�ɂ͍����I�Ȃ��̂Ƃ��Ď��Ȃ������o���A�Γ��I�ɂ������Ƃ��Ď��Ȃ�Ґ�����������Ȃ��v
�@�Ƃ������q������B�u�����v�́A�s���Љ�Γ��I�Ɂu���Ȃ�Ґ��v�����p���A�Ƃ����̂��B
�@�u�x�z�K���ɑ����鏔�l�̋����̂Ƃ��Ă������v�Ƃ����E��O�̋K��́A�����̉ӏ��ŁA�Ñ������A���������A�ߑ������ɂ��Ă��ꂼ��q�ׂ��Ă���B�����̋��ʍ��́A��x�z�K���ɑR����K�v��A�����̂�����Č�������Ƃ����_�ɂ���B
�@���Ƃ��A�Ñ������i�s�s���Ɓj�ł́A�����i���R�l�j�́A�z�ꂽ���ɑ���u�З͂�ۗL����v���߂ɁA�u���������L�Ƃ����`���Ɍq������Ă���v�i{3}c�j�B�܂�A�ނ�́u�|���X�I�����v�ł����āA�|���X�𗣂��i���Ƃ��A�Ǖ������j�ނ�����L���Y���L�͐��藧���Ȃ��Ȃ�B
�@���������ɂ�����u�x�z�K���̋����́v�́A�u�y�n��L�̃q�G�����q�[�I�Ґ��Ȃ�тɂ���ƘA�ւ��镐���]�m���v�ŁA���ꂪ�u�_�z���x�z����З͂��M���ɗ^�����B�v�i{3}d�j
�@�ߑ������ł́A�u���W���A�W�[�́u���͂�n���I�ɂł͂Ȃ������I�Ɏ��Ȃ�g�D���邱�Ƃ�]�V�Ȃ�����v�u���I���L�̋����̂���̉���ɂ���āA�����͎s���Љ�ƕ���ł����̊O���ɂ�����ʂȈ�����ƂȂ����B�������A�����́A�u���W���A�������c�c�ނ�����L�Ȃ�тɗ��Q�̑��ݓI�ȕۏ̂��߂ɐg���䂾�˂�g�D�̌`���ȏ�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B�v�i{91}b=[69]�j
�@���������A
�u����K�������l�����荞�A��������O�҂ɑ���ނ�̋����I���Q�ɏ����Â����Ă��������Љ�I�ȊW�́A���ł��A�����̏��l���������ϓI�ȏ��l�Ƃ��Ă̂݁A�������ނ炪�������Ȃ̊K���̐����������̂Ȃ��Ő����Ă�������ł̂ݏ������������Љ�ł����Ȃ��A�ނ炪���l�Ƃ��Ăł͂Ȃ��ɊK���̈���Ƃ��ĎQ��������W�ł������B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,,p.181.
�@�܂�A�u�����v�͎x�z�K���̋����̂ł��邩��Ƃ����āA�x�z�K���̌l�́A�������ӂ̐l�i�Ƃ��āA�܂邲�Ƃ����ɏ����ł���킯�ł͂Ȃ��A�����܂ł��u�K���̈���Ƃ��ĎQ���v�ł��邾���ł���B�����ł́A�u�l�i�I�l�v�Ɓu���R�I�l�v�́u�����v�������Ă���B
�u�l�i�I�l�Ƌ��R�I�l�Ƃ̘����́A�T�O��̋�ʂȂǂł͂Ȃ����j��̈ꎖ���ł���B���̋�ʂ́A������قɂ��邲�ƂɈقȂ����Ӗ������B
�@�Ⴆ�ΐg���́A18���I�ɂ́A�l�ɂƂ��ĉ���������R�I�Ȃ��̂ł���A�Ƒ��������ꏭ�Ȃ��ꂻ���ł������B�k�c�l
�@��̎���ɂƂ��đO�̎���Ƃ͋t�ɋ��R�I�ƌ�������́A���������Ă܂��A�O�̎��ォ���̎���ֈ����p���ꂽ���v�f�̂����ŋ��R�I�ƌ�������̂ł��A����́A���Ă̐��Y���͂̈��̔��W�ɏƉ����Ă�������`�Ԃł���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,p.184.
 �@
�@
�u�]������������������Љ�̑�p���\�\�������̑��\�\�ɂ����ẮA�l�i�I���R�́A�x�z�K���̏��W�̒��ň琬���ꂽ���l�ɂƂ��Ă����A�������ނ炪�x�z�K���̌l�ł���ꂽ�Ԃ����A�������Ȃ������B����܂ŏ��l�������ւƌ���������������̋����Љ��k�����Ȃǁ\�\�M�g�����l�́A��ɏ��l�ɑ��Ď����������B�����ɂ܂�����͈�K�������K���ɑR���Č����������̂������̂ŁA��x�z�K���ɂƂ��Ă͂܂��������z�I�ȋ����Љ�ł��������肩�A�V���Ȟ~���ł��������B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,p.175.
�@�������āA�u�x�z�K���̏��l�̋����́������v�Ƃ�����O�̋K��́A�u���z�I�����́������v�Ƃ������̋K��ƌ��Ԃ��ƂɂȂ�B
�u���Ȃ킿�A�����ł́A�x�z�K���ɑ����鏔�l�̗��v�����́A����ւƎЉ���̑S�̂���������Ƃ������ƁA���̂�����ŁA��x�z�K���ɑ�����҂ɂƂ��ẮA���̋����̂͌�������̋����Љ�A�Ȃ��������Љ�̑�p���ɂ����Ȃ��Ƃ������ƁA���̂��Ƃ��猶�z�����̂Ƃ��Ă������Ƃ����K�肪������Ă���v
�w�A������W�x,1997,��g���X,��11��,�u�B���j�ςƍ��Ƙ_�v,p.354.
�u��l�̋K��ł���w�x�z�K���̋@�ւƂ��Ă������x�Ƃ��������́w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�ł͌��t�ʂ�ɂ͏o�Ă܂���܂���B�k�c�l
�@���̋K�肪�����ɖ��ĂȌ`�ŏo�Ă���̂́A��O�т̐��}�b�N�X�̉ӏ��ɂ����Ăł���܂��v
a.a,O.
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@


 �@
�@
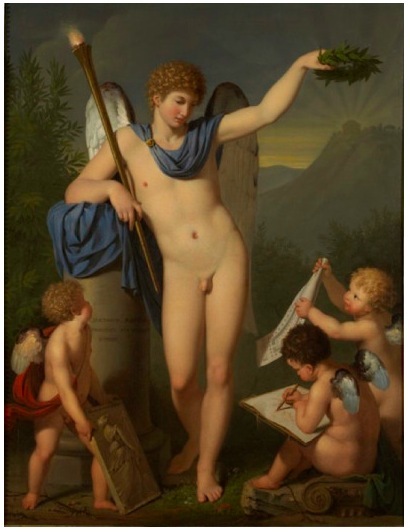

 �@
�@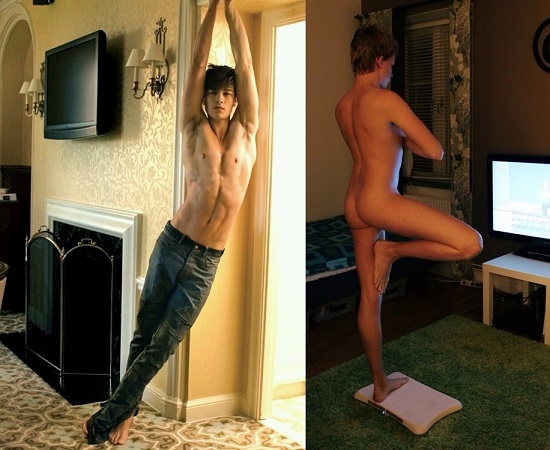
 �c
�c