06/12�̓��L
16�F36
�y���[���V�A�z�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�m�[�g(2)
---------------
.
 �@
�@
�@�����́B(º.-)���
�@�y���[���V�A�z�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�m�[�g(1)����̂Â��ł��B
�@�@�}���N�X/�G���Q���X�̋����w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�́A�ҏW���r�̑��e�̏�Ԃň₳�ꂽ�������̒���ł��B���e�I�ɖ������ŁA���܂��܂ɖ�������咣���܂�ł��܂����A���ꂱ�������̍�i�̖��͂ł�����܂��B�܂��A���e�����łȂ��A�`���ʂł��傫�ȍ��ׂ��͂�e�N�X�g�ł��邽�߁A����͂������ѕʍ\���E�f�Ђ̏����Ɏ���܂ŁA�ҏW�҂̉����K�v�Ƃ��Ă���A�Ŗ{�ɂ���đ��ق�����܂��B�����ł́A�A���E�Җ�C���я��l�E���w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,2002,��g����. ���e�N�X�g�Ƃ��Ďg�p���܂��B
�@��L��g���ɔł���̈��p���A���̓}���N�X�̕M�ՁA����ȊO�i�����j�̓G���Q���X�̕M�ՁB���e�̖����ӏ��͉����t���ŁA�NjL�E�}���͎Α̂Ŏ����܂��B
�u�G���Q���X�̕M�ՃG���Q�}���N�X�̕M�����X�̕M�Ձv
�u�l�Ԃ������ʂ���̂́A���Y�����݂����Ȋ��������Ƃɂ���Ăł���B�v
�u�l���������������ʂ���̂́A�����p�������Y���邱�Ƃɂ���Ăł���B�v
�@���́u�m�[�g�v�́A����̓��e��v�邱�Ƃ��A���҂�̎v�z��`���邱�Ƃ��ړI�Ƃ��Ă��܂���B�����܂ł��A���l�̎v���̂��߂̏��^�ƁA�K�������e�N�X�g�ɂƂ���Ȃ��R�����g���c�����߂̂��̂ł��B
�@�y�S�z�u�{�_��v�\�\��Ō����O�ςƁA�T�����ĉ𖾂��ꂽ�u�����v�ƁB
�u�����I���E�̒��ς̏ꍇ�v�t�H�C�G���o�b�n���u�ނ̈ӎ��⊴��Ɩ������鎖���ɂԂ���B�v���̖������������邽�߂��u��d�̒����k�c�l����k�c�l�w����ɖ����Ȃ��́x���Ŏ悷�鐢���I�Ȓ��ρA������͎����́w�^�̖{���x���Ŏ悷�鍂���́A�N�w�I�Ȓ��ςł���B�k�c�l
�@���ӁB�k�c�l����ɖ����Ȃ��́A�����I�ȊO�ς��A�����I�����̂�萸���Ȍ����ɂ���Ċm�肳�ꂽ�����I�����̉��ʂɒu�����Ƃ����Ȃ̂ł͂Ȃ��A���Ȃ̂́A�k�c�l�N�w�҂́w�ዾ�x��ʂ��čl�@����Ƃ����d���ł����A�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�v
�A���E�Җ�C���я��l�E���w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,2002,��g����,pp.44-45.
�@�����Œ��҂�́A�t�H�C�G���o�b�n�́u������`�v�ɂ�錻���̌����c�c���E��c��������@���A�ꕔ�C�����������Ŏ����B����́A����I�E�����I�ȊO�ς��̂܂܂ƁA���[���i�T���̌��ʂƂ������A��҂�D�ʂɂ����u��d�̒��ρv�ł���B
�@�����A��҂́A�t�H�C�G���o�b�n�Ƃ͈���āA���ςƂ������A���Ȃ藝���I�A���O�I�Ȃ��̂ɂȂ肪���ł��邱�Ƃ́A�������Ă����Ă悢�B
�@�@�@�C�����ꂽ�u��d�̒��ρv�F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�u����ɖ����Ȃ��́v�������I�O�ρB�����I�Ȓ��ρB
�@�u�����I���E�̒��ρv�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�����I�����̐����Ȍ����ɂ��m�肳�ꂽ�u�����I�����v�B
�u�ނ��Ƃ�܂��Ă��銴���I���E�́A�k�c�l�����̐��ʂł���Ƃ��������Y�ƂƎЉ��Ԃ̎Y���ł���Ƃ������ƁA�������A�����I���E�͗��j�I�e����ɂ������Y���ł����A�����̐��ʂł���Ƃ����Ӗ��ł����Ȃ̂��k�c�l����́A���ォ�琢��ւƑ�����n��S�̂̊����̐��ʂł����āA����̊e�X�͐�s���鐢��̌��̏�ɗ����A���̎Y�Ƃ�������g�����A�ω������~���ɑ��i�̂��Ɓj���Ă��̎Љ����ϗe�����Ă����̂ł���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,p.44.
�@���́u�ω��v�u�ϗe�v�̂Ȃ��ŁA�l�Ԃ����́u�~���v���ω�����B�Ƃ������Ƃ́A�u�����v���ω�����B
�@�u����̊e�X�͐�s���鐢��̌��̏�ɗ��v�\�\�Ƃ͌���Ȃ��B�V��������Ɏp���ꂸ�A�̂ċ�������́A�Y����Ă��܂����́A���������F����������Ȃ����̂���������B
�u���̑�]���́w�l�ԂƎ��R�Ƃ̓���x�Ȃ���̂́A�Y�Ƃ̏�ʂŐ̂��猵�����Ă���A�Y�Ƃ̔��W�̍���ɉ����Ď��ゲ�Ƃɕʗl�ȍ݂���Ō������Ă����Ƃ������ƁA�������܂��l�ԂƎ��R�Ƃ́w�����x���A�l�Ԃ̐��Y�͂������̓y��̏���\�������W�𐋂���܂ł͌�����������Ƃ��������A�k�c�l�H�ƂƏ��ƁA�����p�i�̐��Y�ƌ����́A���ꎩ�g�����z�₳�܂��܂ȎЉ�I���K���̕Ґ��������Â��邪�A�t�ɂ܂����̉c�܂���ɂ����ẮA���z�⏔�K���̕Ґ��ɂ���ď����Â�����B�k�c�l
�@�H�Ƃ⏤�Ƃ��Ȃ�������A��̂ǂ��Ɏ��R�Ȋw�����肦�悤�H ���́w�����x���R�Ȋw�Ƃ����ǂ��A���̑f�ނǂ��납�ړI������A���ƂƍH�Ƃɂ���āA�l�Ԃ����̊����I�����ɂ���āA���߂���ɓ����̂ł���B�k�c�l
�@����قǂ܂łɁA���̊����A���̊Ԓf�Ȃ������I�ȘJ���Ƒn���A���̐��Y�������A�����������銴���I���E�S�̂̊�b�Ȃ̂��v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.46-47
�@�u���Y�v�u���z�v�u�����v�ƊK���Ґ��̊W�B�u���z�v�Ƃ�����́A�����ɂ����o�Ă��Ȃ��B�������A�}���N�X�̉��M�ɂ��A���̏��W�́A�g�l�ԂƎ��R�̓���^�����h�́u���ゲ�Ƃ݂̍���v�Ƃ��Č��邱�ƂɂȂ�B�P�Ȃ�g���Y�W�ƊK���h�Ƃ������������ł͂Ȃ��B
�@�y�T�z�u�{�_��v�\�\���j�c���́u���O��v�ƂS�̌_�@�B
�u���j�ɂƂ��ẮA���O����m�肷�邱�ƁB����͂܂�A�w���j��n��x���Ƃ��ł��邽�߂ɂ́A�l�Ԃ����������ł��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����O��ł���B�������Ă��邩��ɂ́A���͂����Ă��Œ���A���H�A�Z���A�핞�A���̑���̂��̂������Ɋ܂܂�Ă���B����䂦�A���̗��j�I�s�ׂ́A�������~�����[���������i��n�o���邱�ƁA�܂�A�����I�������̂��̂̐��Y�ł���B���̂��Ƃ́A�������A���j�S�ʂ̍��{�����Ƃ������ׂ����j�I�s�ׂł����āA�k�c�l
�@�����Ȃ���j�I�c���ł����Ă��A���̈Č��́A���̍��{���������̈Ӌ`�y�є͈͂̑S�̂ɂ킽���Ċώ@���A����𐳓��Ɉ������Ƃł���B�k�c�l�t�����X�l��C�M���X�l���A�k�c�l�Ƃ��������j�L�q�ɗB���_�I�ȓy���^���悤�Ƃ���ŏ��̎��݂��s�Ȃ����B�Ƃ����̂́A�ނ炪�s���Љ�̗��j�A���ƂƍH�Ƃ̗��j�����߂ď���������ł���B
�@���̈Č��́A�ŏ����~���̏[�����A�������ɐV�����~����n�o����Ƃ������ƁA�k�c�l�[�����ꂽ�ŏ����~�����̂��̂��A���Ȃ킿�[���̉c�ׂƂЂƂ��ъl�����ꂽ�[���̗p��Ƃ��A�V�����~���֓����Ƃ������ƁA�\�\�����Ă��̐V�����~���̑n�o�Ƃ͑��̗��j�I�s�ׂȂ̂��Ƃ������Ƃł���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.51-53.
�@�P�i�ڂ́u�����I�������̂��̂̐��Y�ł���v�̕t�߂ɁA���}���N�X�̏������݂�����B
�u�n���w�I�A�����w�I�A���X�̏��W�B�l�Ԃ̐g�́B�~���A�J���B�v
�@�܂�A�u���̗��j�I�s�ׁv�ł���u���������̐��Y�v�́A����ł́A�n���A�y��A�����Ȃǂ̊�����A�����ł́A�u�g�́A�~���A�J���v�Ƃ����l�Ԃ̑��̍s�ׂ���A�l����K�v������A�Ƃ������ƁB�܂肻��́A�s�l�ԂƎ��R�Ƃ̕�����Ӂt�ɂق��Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�@�g�~���̏[���͐V�����~���ݏo���h�\�\����́A�s���{�t�́i�g��j�Đ��Y�Ɠ������z�ł͂Ȃ����H �������A���ꎩ�̂͗��j�ђʓI�ȉ^���ł���B�s���{�t�̉�]�́A���̂ЂƂ́E�s�a�O�t���ꂽ�����ɂ����Ȃ��B
�@�����Ƃ��A�}���N�X/�G���Q���X���A���{��`���L�̌��ۂ��A�ߋ��ɑk�点�ē��e���Ă���̂łȂ����ǂ����A�悭��������K�v������B�ނ�̈ӎ��ƂāA�t�H�C�G���o�b�n��Ɠ��l�A�����̎���́u�����I�������Y�v���狐���ȉe�����Ă���͂��B
�@
�u��O�̊W�́A�k�c�l���������̏��߂���A���j�I���W�ւƐi�ݓ�������k�c�l�ɐB���n�߂�Ƃ������ƁA�k�c�l�Ƒ��B�����͗B��̎Љ�I�W�ł��������̉Ƒ��́A��ɁA���債���~�����V�����Љ�I���W���A�����đ��債���l�����V�����~�����n�o����悤�ɂȂ�ƁA��̏]�ʓI�ȎЉ�W�ɂȂ�B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,p.54.
�@�u�l���̑����v���u�~���̑���v���u�V�����Љ�W�̑n�o�v
�@���W�̓��͂Ƃ��āA�l�Ԃ́u�~���v���d�����Ă��邱�Ƃ��A���j�ρE�Љ�ς̓����ł͂Ȃ����H �܂�A�q�ϓI�E�@���I�ȗ��j�ςł͂Ȃ��B���������l�Ԃ��~�����Ȃ���A�����Ȃ���j�����肦�Ȃ��B�i�}���N�X/�G���Q���X�����Ă�܂Ȃ��E�@���Ƃ́u�ӎv��`�v�ɁA���ĂȂ����H�j
�@�������A�������낤���H �l�͓`���Ɓs���R�t�ɂ��������Ă̂��~������A���������Љ������̂ł͂Ȃ����H
�@�����́A�u��S�̈Č��v�Ɩ������Ă��Ȃ����A��������A����ɂ�����ƌ�����B
�u���̐��Y�́A�J���ɂ�����{�l���g�̂���ɂ��搶�B�ɂ����鑼�l�̂���ɂ���A���̂��k�c�l��ʂł͎��R�I�ȊW�Ƃ��āA���ʂł͎Љ�I�ȊW�Ƃ��ā\�\������B�Љ�I�Ƃ����Ӗ��́A�k�c�l�����̏��l�̋����������ɗ�������Ă���Ƃ������Ƃł���B�������玟�̂��Ƃ�������B���̐��Y�l���Ȃ����Y�ƒi�K�́A������̋����̗l���Ȃ����Љ�̒i�K�ƌ��т��Ă���B�����Ă��̋����̗l�������ꎩ�g��́w���Y�́x�Ȃ̂ł����Ƃ������ƁA�����Đl�Ԃ�������ɂ����鐶�Y���͂��傫�����Љ�I�ȏ�Ԃ������Â���̂ł���A����䂦�A�w�l�ނ̗��j�x�͏�ɎY���y�ь����̗��j�Ƃ̊֘A�ŁA��������_�����˂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�k�c�l
�@�������āA���������̏��߂��炷�łɁA�~������ѐ��Y�̗l���ɂ���ď����Â����A�l�Ԃ������̂��̂Ɠ����ɐ������Ă���A�l�ԑ��݊Ԃ̗B���_�I�ȘA�ւ�������B�k�c�l
�@�l�Ԃ����͔ނ�̐��Y����������Ȃ����䂦�ɁA���������̗l���ł�������������Ȃ����䂦�ɁA���j�����B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.54-56.
�@�y�U�z�u�{�_��v�\�\�Љ�I�u���Ɓv�_
�u����͈ӎ��Ɠ����N�ł���B����́A�k�c�l���̐l�Ԃ����ɂƂ��Ă��k�c�l�����g�ɂƂ��Ă��܂��ŏ��Ɏ������������I�Ȉӎ��ł���B�����Č���́A�ӎ��Ɠ��l�A���̐l�Ԃ����Ƃ�����ɑ����~���ƕK�v����A���߂Đ�����B
�@���̊��ɑ��鎄�̊W�����̈ӎ��ł����B
�@�ӎ��́A�������āA���������̏��߂��炷�łɁA��̎Љ�I���Y���ł���A�k�c�l
�@�ӎ��́A��������́A�P���ł��g�߂������I���ɂ��Ă��̈ӎ��ł���A�k�c�l�����Ɏ��R�ɂ��Ă̈ӎ��ł���B���̎��R�͐l�Ԃ����ɂƂ��āA�����͂܂������a���ȁA�S�\�ŕs�N�̈З͂Ƃ��ė��������A�l�Ԃ������k�c�l�ƒ{�̂悤�Ɉؕ�����B����䂦�ɁA���̈ӎ��͏����ɓ����I�Ȏ��R�̈ӎ��Ȃ̂ł��邪�i���R�@���j�A
�@����͎��R���܂��قƂ�Ǘ��j�I�ɕϗe����Ă��Ȃ����炱���ł����B
�@�\�\���������ʂł́A���͂̏��l�Ƃ̌����W�ɓ��炴������Ȃ��K�R���̈ӎ��ł����āA�l�͂��������Љ�̒��Ő����Ă���Ƃ������Ƃɂ��Ă��Љ�I�ӎ��̒[���ł���B���̒[���́A���̒i�K�̎Љ�����̂��̂Ɠ����x���ƒ{�I�����I�ł���B����͒P�Ȃ�Q���ӎ��ł���A�k�c�l����膗r�i����悤�j�ӎ��Ȃ��������ӎ��͂���Ȃ锭�W�Ɛ��n�𐋂��Ă������A����������炷�̂́A���Y���̌���A�~���̑���A�����Ă���痼�҂̍�����Ȃ��l���̑���ł���B
�@����ɔ������������\�\�{���I�ɂ͐��I�s�ׂɂ����������ɂ����Ȃ������̂����\�\���W���Ă����A�₪�Ď��R�I�ȑf���i���Ƃ��Ά̗j�A�~���A���R���X�ɂ���āA�k�c�l�u���R�����I�v�ɐ������������s�Ȃ���悤�ɂȂ�B�����́A�����I�J���Ɛ��_�I�J���Ƃ̕���������ꂽ�u�Ԃ���A���߂Č����ɕ����ƂȂ�B
�@�C�f�I���[�O�̍ŏ��̌`�ԁA�m���������ɐ�����B
�@�k�c�l�\�\���̏u�Ԃ���A�ӎ��́A���Ȃ𐢊E������������āu�����ȁv���_�A�_�w�A�N�w�A�����A�����������`���ւƈڂ邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B�������A�����̗��_�A�_�w�A�N�w�A�����A���������̏��W�Ƃ̖����Ɋׂ�ꍇ�ł����A���̂悤�Ȃ��Ƃ��N���肤��̂́A�����ς猻���̎Љ�I���W�������̐��Y�͂Ƃ̖����Ɋׂ��Ă��邱�Ƃɂ���Ăł���B�\�\�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.57-60.
�@�}���N�X�́w�p���E�m�[�g�x�ł��łɁA�_�z�I�ꑮ�i�s��n�t�Ƃ̈�̐��j������J���ւ̓]���A���邢�͎������������Y�҂̎Љ�ւ̓]�������q���Ă���B�������A�����ł͈�i�ނ��āA��蒊�ۓI�ȃ��x���ŁA�u�l���̑����v���u�V�����~���v����������� �Ƃ����A�ւ��q�ׂ�B�����������ۓI�ȃ��x������n�߂Ă���B
�@�������A�u�{�_�O�Q�v�ŁA����̓I���x���i�̎�Ɣ_�z�A�����s�s�A�c���t�g�Ə��l�K���������j�ɂȂ��Ă��A�u�~���v�u����v�u�����v�̓L�[�T�O�ł���Â���B
�u���̎��R�@�����邢�͎��R�ɑ��邱�̈��̊ւ�荇���́A�Љ�`�Ԃɂ���ď����Â����A���܂��t�ɎЉ�`�Ԃ������Â���B�ǂ��ł������ł��邪�A�����ł����R�Ɛl�ԂƂ̓��ꐫ�́A���R�ɑ���l�Ԃ����̋nj����ꂽ�ւ�荇�����ނ瑊�݊Ԃ̋nj����ꂽ�ւ�荇���������Â��A�����āA�l�ԑ��݊Ԃ̋nj����ꂽ�ւ�荇�������R�ɑ���ނ�̋nj����ꂽ�W�������Â���A�Ƃ�����Ɍ����Ă���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,p.59.
�@�l�ԂƎ��R����̐��i�u���ꐫ�v�ƌĂ�ł���j��ۂ��Ă�������ɂ��āA�u�nj����v�g��襐��h�̖ʂ��������Ă���̂͑傫�ȓ�_�B�������A�l�ԂƁs���R�t�̊ւ�荇���ƁA�l�ԑ��݊Ԃ̊ւ�荇���Ƃ̑����������鎋�_�͊w��ł悢�B
�@�u���R�Ɛl�ԂƂ̓��ꐫ�v����A�_�z�̐l�i�I�ꑮ���B�������A�J���ߒ��ɂ����鎩�����A�̎�Ƃ́E�܂��_�z���݊Ԃ́u�a�C���������Ƃ����W�v�B�����͓������Ƃ���̊e�ʁB�i�p���E�m�[�g�jVd.�w��^���̑O�Ɂx�A���x�����w�o�ϊw�Ǝ��R�N�w�x�B
�@�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�ł́A�w�p���E�m�[�g�x����ނ��āA�u�nj����ꂽ�v�ʂ���������悤�ɂȂ��Ă���B�u���Y�͎����`�v�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B�O�߂̐l�퍷�ʐ��������Q�ƁB
�u�����Ƃ��A���̂悤�Ȃ����k�o�E�A�[�́u�������_�v�̂悤�ȊT�O���͂��߂Ƃ��āA�������̓N�w��v�z���A�����́u���W�v�Ƃ̖����Ɋׂ邱�Ɓl�́A�k�c�l�������k�c�l�����I�Ȉӎ��Ƒ��̏������̎��H�Ƃ̊ԂɁA��������Έꍑ���ɂ����鍑���I�ӎ��ƕ��ՓI�ӎ��Ƃ̊ԂɁA������������i�����̃h�C�c�ł̂悤�Ɂj���Ƃɂ���Ă��N���肤��B�\�\���̏ꍇ�A���̍����ɂ́A�k�c�l�����I�ӎ������ł������Ƃ��Č��ۂ���̂ŁA�������܂����̍����I�ȕ��A���Ɍ����Ă���悤�ɉ�������B�k�c�l
�@�����͂�����̉������炽����̌��_�邾���ł���B�k�c�l���Y�͂ƎЉ�I��Ԃƈӎ����A���݊ԂŖ����Ɋׂ����Ƃ����肤�邵�A�܂������Ȃ炴������Ȃ��Ƃ������ƁA�\�\�Ƃ����̂��A�����ɔ����āA���_�I�����ƕ����I�����A����ƘJ���A���Y�Ə����Ƃ��A�ʁX�̌X�l�ɋA������\���A���⌻�������^�����邩��ł���\�\�A����炪�����Ɋׂ�Ȃ��Ȃ�\���́A�������Ăєp�~�����Ƃ������Ƃ̂����ɂ����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B�k�c�l
�@�k�������A�u���[�m�ɑR����V���e�B���i�[�̏��T�O���l���������ʉ����ꂽ�l�̕\�ۂȂ̂ł���A�ɂ߂Čo���I�Ȟ~������\�\���̐��Y�l������т���ƘA�ւ�������`�Ԃ́A���̘g���œ��������Ȃ��\�\�ɂ��Ă̕\�ۂȂ̂��Ƃ������Ƃł���B���̂悤�ȁA��������o�ϓI�����̊ϔO�_�I�\���́A�k�c�l���H�I�Ȉӎ��̂����ɂ����݂���B�܂�A���Ȃ����������A�����Č����̐��Y�l���Ɩ����Ɋׂ��Ă����ӎ��́A���X�̏@����N�w�����łȂ��A�����������`������̂ł���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.60-63.
�@�u���Y�́v�Ɓu�Љ�I��ԁv�Ɓu�ӎ��v�̂������̖����\�\�Ƃ����ُؖ@�I���W�̘_���i�̒[���j���q�ׂ���B�������A���̘_�����o�Ă��������̗��j�I�W�i�Ȃ܂̎�����ԁj�ɂ������ڂ��ׂ��ł���B�u���W�̘_���v���A�ǂ���������v�قɂ���ďo�Ă����悤�Ɏv���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�u�������_�v�Ƃ́A�o�E�A�[�F�u�������W�Ƃ̖����A�a瀁A������ʂ��Č����s�f�ɔᔻ�E���v���A�����Đl�Ԃ́w���Ȉӎ��x�W��������̂Ǝ咣���ꂽ�B�v�ip.249.��(21)�j�B�o�E�A�[�́A�u�����I�ӎ������Łv�N�w�́u�������_�v�������I�E�@���I�ӎ��̏��W�i�����A����̌����K��������j�Ɠ������Ă���悤�Ɏv���Ă��邪�A�ق�Ƃ��́A�h�C�c�̒x�ꂽ�ӎ���x���i�h�C�c�l���g�̎Y�ƓI���H�́A����ƒނ荇���Ă���̂����j�A�������́u���H�v�i�C�M���X�A�t�����X�̎Y�Ɣ��W�A���Y�K����J���҂̌����I�ȗv���^���j�Ƃ̊ԂŁA�܂�u���ՓI�ӎ��v�Ƃ̊Ԃň����N�����Ă��閵���Ȃ̂��ƁB
�@���̏ꍇ�A�o�E�A�[�́u�������_�v�́A�������C�M���X�A�t�����X�̍H����J���҂̎��H���琶�܂�Ă��Ă���Ƃ����o���ɂ͎v���y���A�������������E�ōł������ȁu���ՓI�ӎ��v���Ǝv������ł���B���̎��A�v�z�Ƃ��ẮA�h�C�c�̒x�ꂽ�ӎ��̕�������������Ă���B�����́E�G���Q���X���`�����G�́A�����\���Y��B�t���������l�����A�t�����X�̃T���L�����b�g�̂悤�ɍ���ŖX�q��U���Ă��邪�A�����ɉE��ł̓T�[�x��������A�E��牺�����������ɂ́A�}���N�X�̎��Łu�@���v�u�C�f�I���M�[���̂��́v�Ə�����Ă���B
�@���̂悤�ɁA�����͂���߂č������Ă���B���W�������Y�͂��A�Â����Y�W�Ɩ������j�ӂ���A�Ƃ����悤�ȒP���Ȃ��Ƃ́A�ӂ��͋N���Ȃ��̂��B
�@�Ō�̒i�����c�c�V���e�B���i�[�ɂ��ďq�ׂ��Ƃ���ł́A�u�ӎ��v�Ɓu���Y�l���v�̖������A��藧�������Ę_���Ă���B
�@������A�@�V���e�B���i�[�̂悤�ȃG�Z�g�l�h�ɂƂ��Ắu�ɂ߂Čo���I�Ȟ~������v���Ȃ킿�u��������o�ϓI�����v������A�����ɁA�A�V���e�B���i�[���g���܂ށu���������ʉ����ꂽ�l�v�́u���̐��Y�l������т���ƘA�ւ�������`�ԁv�u�����̐��Y�l���v�����邪�A�A�́A�@�́u�~������v�́u�g���Łv�����u���v���Ȃ��B���̂��߂ɁA�A�̔��W�́A�������Ė����n�ł���A�����������i���Ȃ킿�A�l�i�I�ɉ������A���K�I�~���̂܂܂ɍs������j�u�l�v�Ƃ͂Ȃ肦�Ȃ��ł���B�A�A���Ȃ킿�����̃h�C�c�l�́A�s�O��ȁu��������̌l�v�ł���ق��Ȃ��B���ꂪ�A�x�ꂽ�g�h�C�c�s���Љ�h�̌���ł���B
�@����ł́A�ނ�h�C�c�l�̔��W���u�����v���Ă���@�Ƃ́A���Ȃ̂��H
�@�}���N�X/�G���Q���X�ɂ��A����́A�V���e�B���i�[�̂悤�ȁg�����͓������Ă���Ǝv������ł���h�C�c�̃C�f�I���[�O�����h���g�̊ϔO�I�ӎ����痧���オ��u���@���A���N�w�A�������v�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�}�����ꂽ�l�тƂ́A�}���������Ă��邠�����́A�@���Ƃ����A�w�����ŏǂ̌��z�Y���Â���B�u�~���v���u�����v���ꂽ�N�w�҂������A�ϔO�_�I�N�w�Ƃ����E��⍂���ȃA�w���Y����B���́A�������Ă���u���H�I�Ȉӎ��v���Ȃ킿�u���Ȃ����������A�����Č����̐��Y�l���Ɩ����Ɋׂ��Ă���ӎ��v���̂��̂��A�h�C�c�ł́A�u���@���A���N�w�A�������v���u�`���v���Ă���̂ł���B
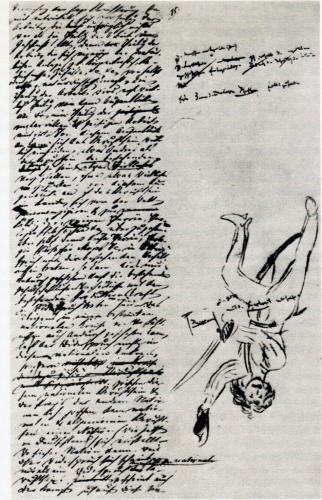 �@
�@
�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x���e�̂P�ŁB�@�@�@
�u��q�̈�̖����������̓��ɂ���A�������̂��̂͂܂��Ƒ��ɂ����鎩�R�����I�������ɁA�����ČX�̑Η����������Ƒ��ւ̎Љ�̕���ɁA��Â��B�\�\�����ɔ����āA�����ɂ܂��z���A�������ʓI�ɂ����I�ɂ��s�����ȁA�J���Ƃ��̐��Y���̔z�������݂���悤�ɂȂ��Ă���A�������������L�����݂���悤�ɂȂ�B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.63-64.
�@�����ł͂��߂āA�u���Y�W�v�����y�����B�u���L�v���������ꂽ����A�T�O���ꂤ��悤�ɂȂ����̂��B�������A�܂��u���Y�W�v�Ƃ�����͗p�����Ă��Ȃ��B�u���Y�l���v�Ƃ�����́A���łɏo�Ă��邪�A�ʂ̈Ӗ��ŗp�����Ă����B
�u���L�́A�ȂƎq���������v�̓z��ł���悤�ȉƑ��̓��ɁA���łɂ��̖G��A���̍ŏ��̌`�Ԃ������Ă����B�Ƒ����ɂ�����A�ܘ_�܂��ɂ߂đe��Ő��ݓI�ȓz�ꐧ�A���ꂪ�ŏ������L�ł���B����ɂ��Ă����̍ŏ������L�́A�k�c�l���L�Ƃ͑��l�̘J���͂��ӂ̂܂܂ɂ��邱�Ƃ��Ƃ����ߑ�̌o�ϊw�҂����̒�`�ɂ܂������K���Ă���B�Ƃ�����A�����Ǝ��I���L�Ƃ́A�������Ƃ��k�قȂ�l�\���ł���\�\��҂ɂ����Ċ����̐��Y���Ƃ̊W�Ō����\�킳��Ă�����̂��A�O�҂ɂ����Ă͊����Ƃ̊֘A�Ō����\�킳��Ă���̂ł���B
�@����ɂ����A�����Ɠ����ɁA�X�̌l�Ȃ����X�̉Ƒ��̗��Q�ƁA����������Ă��鏔�l�S���̋����I���Q�Ƃ̖��������݂���悤�ɂȂ��Ă���B�������A���̋����I���Q�Ƃ����̂́A��������P�ɕ\�ۂ̓��Ɂw���ՓI�Ȃ��́x�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��A
�@���������A���ՓI�Ȃ��̂Ƃ����̂́A�����I�Ȃ��̂̌��z�I�`�ԂȂ̂�
�܂��͌����̓��ɁA�J�������Ă��鏔�l�̑��݈ˑ����Ƃ��Ď�������̂ł���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.64-66.
�@�Ƒ��̓����ł́u���L�v���������ɂȂ�Ȃ��Ƃ悭�����邪�A�}���N�X/�G���Q���X�́A����ȊÂ����Ƃ͌����Ă��Ȃ��B�ނ�ɂ��A�Ƒ��̓����ɂ͎x�z���Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�P�ɁA�O���i�����Ȃǁj�̎x�z�������I�ɂ����y�Ȃ��A�Ƃ��������Ȃ̂��B
�@��́u�����I���Q�v�ɂ��āA�ȉ����A���O�ɒ����������݂�����F
�u�܂������A����I���Q�Ƌ����I���Q�Ƃ̂��̖�������A�����I���Q�������Ƃ����`��������A�����̌ʓI���Q�Ȃ�тɑS�̓I���Q����藣���ꂽ�����I�Ȏp���Ƃ�B
�@�����ē����Ɍ��z�I�ȋ������Ƃ���
�Ƃ͂����Ă��A�k�c�l�e�X�̉Ƒ��W�c�╔���W�c�̂����Ɍ��O����A���ƌ��A����A���Ȃ��K�͂������₻�̑��̗��Q�Ƃ������R�сA�����ĂƂ�킯�A�k�c�l���ł������ɂ���ď����Â����Ă��鏔�K���\�\������ނ̐l�ԏW�c���Ƃɕ�����A���̂����̈�K�������̑S�K�����x�z����\�\�Ƃ������ݓI�ȓy��̏�ł̂��Ƃł���B
�@�������玟�̂悤�Ȍ��_���o�Ă���B���吭�E�M�����E�N�吭�̊Ԃ̓����A�I�����̂��߂̓����A���X�A�����̓����ɂ������̓����́A���܂��܂ȊK���Ԃ̌����I�ȓ��������������`�Ԃ��Ƃ��čs����Ƃ���́A���z�I�ȏ��`�Ԃɂ����Ȃ��B�k�c�l�����Ă���ɁA�k���̏��K���ɑ���l�x�z����ڎw���ǂ̊K�����\�\�v�����^���A�[�g�̏ꍇ�k�c�l�ł����\�\�܂��������k�����́l�������͂�D�悵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������̗��Q�����x�͕��ՓI�Ȃ��̂Ƃ��Ď����k�c�l���߂ł���B
�@�܂��������l�������ς�ނ�̓���I�ȁ\�\�k�c�l���������̋����I���Q�Ƃ͈�v���Ȃ����Q���A�Njy���邩�炱���A�\�\���̂����k����I���Q�\�\�M�g�����l�͔ނ�ɂƂ��āw�a���ȁx�A�ނ炩��w�Ɨ��ȁx�����k�@���A�N�w���l�Ƃ��āA��d�ɂ�����I�ŁA���Ɠ��́w���Ձx���Q�Ƃ��āA�܂���ʂ邱�ƂɂȂ����B���邢�́A���吭�̏ꍇ�̂悤�ɁA�ނ玩�g�������k����ƕ��Ղ́l��ɕ���̒��œ�����������Ȃ����ƂɂȂ�B����䂦�A���ʂł́A�����I���Q����ь��z�I�ȋ����I���Q�k�������l�ɑΗ������k�c�l������A�������ꗘ�Q�̎��H�I�������܂��A�����Ƃ������z�I�ȁw���Ձx���Q�ɂ����H�I�Ȓ���Ɛ����K�v�Ƃ��邱�ƂɂȂ�B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.66-71.
�����F���̂P���́A�͏o�ł̌������Q�Ƃ��ĉ����B
�@���������́A���K���̗��Q���߂��铬�����c�Ƃ����P�������ꂽ�����͖�肾���A�����v��Ȃ��Ɠ����̓����ɂ͕s�s�����������̂��낤�B���܂͒ʗp���Ȃ������B��������A���u�K���v�́u�����ɂ���ď����Â����Ă���v�Ƃ������z���ǂ��B�u�x�z�v�Ɓu���L�i���l�̘J�����x�z���邱�Ɓj�v�́A�u�����v(�����I���Ɓj�Ɋ�Ă���A���邢�́A�u�����v��ʂ̌��t�Ō����������ɂ����Ȃ��B�܂�A�����̔w�i�ɂ́A�l�Ԃ��W�c�Ƃ��ās���R�t�Ƃ́s������Ӂt���s�Ȃ��A���̌`�Ԃ����W���Ă䂭(�u���R�����I�Ɂv���u�ЂƂ�łɁv)�A�Ƃ������j�ђʓI�ȁg�����h�Ȃ����^��������B
�@�u�������͒D��v�K�R�_���A�u�v���̎���v�Ƃ�������ȗ��j�I�i�ꎞ�I�j�����̎Y���B��������A���̌�̃}���N�X�M�Ղł̏������݂��������낢�B�u�������͒D��v�������܂��A������L���s�a�O�t�ݏo���Ƃ����̂��B
�u�����čŌ�ɁA�����͎��̂��Ƃɂ��čŏ��̗���A���������ɒ��Ă����B���Ȃ킿�A�k�c�l����ȗ��Q�Ƌ��ʂ̗��Q�Ƃ̕������������A�����������J�����������R�ӎu�I�ɂł͂Ȃ����R�����I�ɕ�������Ă������A�l�Ԏ��g�̍s�ׂ��l�ԂɂƂ��đa���ȁA�R�I�ȈЗ͂ƂȂ�A�l�Ԃ�������x�z����̂ł͂Ȃ��A���̈З͂̕����l�Ԃ��x�z�������������A�Ƃ������Ƃł���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,p.66.
�@����ł́A�����A���Ƃ��u���R�ӎu�I�Ɂv�s����A�s�a�O�t�͂Ȃ��Ȃ�̂��H �d�d����͑傫�Ȗ�肾���A���̂��Ƃ̍s�_�ŁA����ɖ�艻����̂ŁA�����ň������B���́A�u���R�ӎu�I�Ɂv��������Ƃ́A�i���z�I�ɂł͂Ȃ��u�����I�v�ɁA�܂�A�����܂܂ɂ́j�ǂ��������ԂȂ̂��A�Ƃ������Ƃł���B
�u�������A�܂�J���������������n�߂��ƁA�e�l�͎����ɉ�������������r���I�������̈�����悤�ɂȂ�A���ꂩ�甲���o���Ȃ��Ȃ�B�ނ́A�t�A���v�A���邢�͖q�l���邢�͔ᔻ�I�ᔻ���̂ǂꂩ�ł����āA�����̎�i�����������Ȃ������ł��葱����������Ȃ��B�\�\����ɂЂ������A���Y��`�Љ�ł́A�e�l�͔r���I�Ȋ����̈�Ƃ������̂��������A�C�ӂ̏�����Ŏ��������Ƃ��ł���B���Y��`�Љ�ɂ����Ă͎Љ���Y�̑S�ʂ��K�����Ă���A�܂��������̂䂦�ɉ\�ɂȂ邱�ƂȂ̂����A�k�c�l�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.66-67,69-70,73-74.
�@���̈���������Ɂu�������v���Ƃ��ł��邾�낤���H�I �Ƃ����^�₪���邪�A����͒u���Ă��A�u���Y�̑S�ʂ��K���v����Ƃ����u�Љ�v�Ƃ́A�����������Ȃ̂������ł���B����́u�����v�łȂ��ĉ��Ȃ̂��H �u�����v�́A���K�����ꂼ��̗��Q�Ƃ͕ʂɁA�u�����v�Ǝ��̗��Q�Ȃ����g�����h�����B����䂦�A�u�����v�͌����Ď��Ȃ̖����i���Ƃ��u�푈�v�u��팠�v�j��������Ȃ��B�u�����v�����g�̎�l�Ƃ��đՂ��x�z�K���̗��v�ɔ����Ăł��A�u�����v�͎��g�̖����ƌ��͂��g�����悤�Ƃ���Փ������B
�@���邢�͂����A�u���Y�̑S�ʂ��K���v����u�Љ�v�Ȃ���̂��A�u�ӎ��v�I�ȁu�����v�ł��A���ӎ��I�Ȏs��@�\�ł��Ȃ������ł��肤��ƌ����̂Ȃ�A����͂ǂ�Ȃ��̂ł���̂����A������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�u�Љ�I�����̂������������P���A����ꎩ�g�̐��Y�����A�����𐧌䂷�������ۓI�ȋ������Ɖ������������Ì��k�c�l�A���ꂪ�A�]���̗��j�I���W�ɂ����Ă͎�v�_�@�̈���Ȃ��Ă����A���������L�ɂ����ā\�\���L���k�c�l�l�Ԃ������g�ɂ���č��ꂽ�d�g�݂����A�₪�āA�ŗL�́A���L��҂ݏo�����l�X�����Ӑ}���Ȃ������悤�ȓ]��_���Љ�ɗ^�����k�c�l�Љ�I�З́A���Ȃ킿��d�ɂ��{�����ꂽ���Y�́\�\����͂��܂��܂ȏ��l�������̓��ɏ����Â���ꂽ�����ɂ���Đ�����\�\�́A�������̂��̂����R�ӎu�I�łȂ����R�����I�ł��邽�߂ɁA���̏��l�ɂ́A�ނ玩�g�̘A�������͂Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�a���ȁA�ނ�̊O���Ɏ��������������Ƃ��Č�����B�ނ�͂����������̗������s������m�炸�A���������Ă��͂₻����x�z���邱�Ƃ��ł����A���ɁA���₱���������̕�������Ǝ��́A�l�Ԃ����̈ӎv�⓮������Ɨ��ȁA����ǂ��납���̈ӎv�⓮�����ꎟ�I�Ɏ�ɂ���A��A�̓W���Ɣ��W�i�K���{������̂ł���B(�{)
�@���������łȂ���A�Ⴆ�����L�������������j�������A���܂��܂Ȏp���Ƃ�Ƃ������Ƃ�A�k�c�l���Ƃ��A���v�Ƌ����̊W��ʂ��đS���E���x�z����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��A�ǂ̂悤�ɂ��Đ�����̂��H�k�c�l
�@�������Ȃ���A�y���k��]�I�Ȑ��Y�W�l�̔p�~�A���I���L�̔p�~�ƂƂ��ɁA�܂����Y�̋��Y��`�I�K���ƂƂ��ɁA�����Ă����Ɋ܂܂�邱�Ƃ����A�l�Ԃ������������g�̐��Y���ɑ��Ċւ�荇�������̑a�����̍���ƂƂ��ɁA�����W�̈З͖͂��ɋA���A�������A�l�Ԃ����́A�����A���Y�A�ނ�̑��ݓI�Ȋւ�荇���݂̍�����A�Ăю��������̎x�z���ɒu���悤�ɂȂ�B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.69-70,73-74.
�@�u�����v�ɂ���Đ������s�a�O�t�̘_�q�A�����B�g�J������h�Ƃ����l�Ԃ̊������A�u�a���ȑR�I�З́v�Ƃ��ė���������s�a�O�t�Ԃ́A����ł́u�����v�Ƃ��āA�����ł͎��{��`�u�s��@�\�v�ƂȂ��Č��ۂ���B�����O�̒i�ł́A�u�����v����ɔO���ɒu���Ă����̂ŁA�s�a�O�t�̃��J�j�Y���́A�u�����v�ɂ���āu�������Q�v�Ɓu���ꗘ�Q�v���Η����A���̑Η����u�����v�ݏo���B������A�u�����v�̌Œ艻���p�������A�u�����v���s�a�O�t���Ȃ��Ȃ�Ƃ����_���������B
�@�����ł́A�a�O���ꂽ�u���Y���v�Ƃ����u���ۓI�ȋ������v�ɒ��ڂ��A�s�a�O�t�Ԃ̏œ_�́A�u���I���L�v�Ɓu�s��v�Ɉڂ�B
�@�u�{�����ꂽ���Y�́v���Ȃ킿�u���Y�͔��W�v���̂��̂��u�Љ�I�З́v�ł���A�s���ۉ��t���������͂Ƃ��ė��������Ƃ��Ă���B
�@�u���R�����I��[�P������]�����v�������s�a�O�t��������A�u���R�ӎu�I�v�������Ȃ�s���ۉ��t���s�a�O�t�������Ȃ��A�Ƃ�����{�I���z�́A�����A�s��A���Y�ߒ��̋�ʂȂ���т��Ă���B�傢�ɋ^�₾���d�B
�@�l�тƂ��u�����̗͂������s������m�v��A�u����������(!!!!)�v�����������(�A�\�V�G�[�V�����ɂ����)�u�x�z�v���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A�u���ۓI�ȋ������v�́u����v�����̂��ƌ����B�����ɂ́A�g�l�тƂ̌��z���o�߂�A�Љ�͐��퉻(�{���ɉ�A)����h�Ƃ����A�u�h�C�c�E�C�f�I���[�O�v�̎v�����݂����������Ă���̂ł͂Ȃ����H �������A�d�d
�@�u�c�c�����W�̈З͖͂��ɋA���A�c�c�l�Ԃ����́A�����A���Y�A�ނ�̑��ݓI�Ȋւ�荇���݂̍�����A�Ăю��������̎x�z���ɒu���悤�ɂȂ�v�\�\�����͏�������ׂ����̂�����B�s�a�O�t�̖����Ȃ������z�Љ�ɂ��A�u�����v�͂���̂��ƌ����B�܂�A���������́g�ߎЉ�h�ł͂Ȃ��B���������ł͂Ȃ��ȏ�A���炩�̌`�Ԃ́u�����v���K�v���B
�@�������A���́u�����v�i�����̃p���O���t�ł́u���E����v�ƌĂ�ł���j�́A���i�����A�s������Ƃ͌���Ȃ��B���ۖ��Ƃ��ă}���N�X/�G���Q���X�̔O���ɂ������̂́A�S�X�v�����ɋ߂��悤�������I���z�����@�\�ł�������������Ȃ��i�w�t�����X�̓����x����������K�v������j�B�������A����ł͘b�ɂȂ�Ȃ��B���邢�́A��{�͏��i�����ɔC���邪�A���炩�̐l�דI�@�\���A�u�����W�̈З́v�����āA�j��I�ȁg���h��h�~����A�Ƃ����悤�ɂ��ǂ߂邩������Ȃ��B���ꂪ�����I�ȁu�����v�s�a�O�t�Ԃ̌��o�Ɋׂ�Ȃ����߂ɂ́A����I����@�\�Ɋւ��āA��قǂ̍H�v���K�v���낤�B
�u(�{)���́w�a�O�x�k�c�l�́A��̎��H�I�ȑO��̉��ł̂ݎ~�g���ꂤ��B�k�c�l�l�X���k�c�l�v�����N�����悤���k�ς��������l�З͂ƂȂ邽�߂ɂ́A���ꂪ�l�ނ̑命�����܂������́w�����L�ҁx�Ƃ��āA�����������ɁA���O����x�Ƌ��{�\�\�ǂ�������Y�͂̋���ȏ㏸�Ƃ��̍��x�Ȕ��W��O��Ƃ���\�\�̐��E�Ƃ̖����ɂ����āA�n�o���Ă��܂��Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�ʂ̖ʂ��炢���A���Y���͂̂��̂悤�Ȕ��W�k�c�l�Ȃ��ɂ́A���R�A���������Չ������ɂ������A����䂦�A�����ɔ����ĕK�v�����߂���R�����ĔR���A�k�����I�����Ȃǂ́l�Â����������Ƃ��Ƃ��h�v��B�u����ɁA���Y���͂̂��̑S�ʓI���W�ɔ����Ă̂ݐl�Ԃ����̑S�ʓI���������������B�\�\�k�c�l�w�����L�x�̑�O�Ƃ��������������鏔�����̂����ɓ����I��������k�c�l�A�ǂ̍��������������̕ϊv�Ɉˑ������k�c�l�����Ă��ɂ͐��E�j�I�ȁA�o���I�ɑS�ʓI�ȏ��l���A�ǒn�I�ȏ��l�ɂƂ��đ��点�邱�ƂƂȂ�\�\�k�c�l���̂��ƂȂ��ɂ́A(��)���Y��`�͋ǒn�I�Ȃ��̂Ƃ��Ă��������������A�k�c�l�y���I�E���M�I�ȁw���x�̂܂܂ł���Â���ł��낤�B������(�O)����̂ǂ̂悤�Ȋg������A�ǒn�I�ȋ��Y��`��p�~����ł��낤�B���Y��`�́A�o���I�ɂ́A��v�ȏ������̍s�ׂƂ��āu�ꋓ�I�v�������I�ɂ̂݉\�Ȃ̂ł����āA���̂��Ƃ́A���Y���͂̑S�ʓI�Ȕ��W����т���ƘA�ւ��鐢�E�����O��Ƃ��Ă����B
�@�k�c�l�f���n�̘J���ґ�O�k�́l���̂܂������s���I�ȏ�Ԃ́A���E�s���O��Ƃ���B�v�����^���A�[�g������䂦�A���H�I�E�o���I�Ȏ����Ƃ��Ă̐��E�j��O��Ƃ���B�v
�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,��g����,pp.72-73.
�@�g�����Љ�h�̑O��Ƃ��āA���Y���͂̏\���Ȕ��W���Ȃ��ƁA�����I�����Ȃǂ́u�Â������v����݂�����A�Ƃ��Ă���B�������A�����I����������ɋ����I�ɂ���g�K�v�h�̍ł�����̂́A���Y�������E���z�@�\�̉^�c�ł͂Ȃ����H ���̓_��������Ă���B
�@�܂��A�u���Y�͎����`�v���̂��A�u�Љ��`�v���Ƃ����剻����ق��ɓ����₷���B�d�d���̌��ʁA���Y�͑���ɐ������邩�ǂ����́A�S���ʖ�肾���i���ۂ̗��j�I�o�߂ł́A�قڂ��Ƃ��Ƃ����s���Ă���j�B
�@�������A���E�̍��X���o�ϓI���������Đ����I�ɑ��݈ˑ�����悤�ɂȂ�̂ƕ��s���āA�u�ǂ̍��������������̕ϊv�Ɉˑ�����v�悤�ɂȂ邱�ƁA�����āA�u���E�j�I�ȁA�o���I�ɑS�ʓI�ȏ��l�v���S�n���I�K�͂Ō��o���邱�Ƃ��A�K�v�ȑO������Ƃ��Ă���_�́A���ڂɒl����B
�@�u�ǒn�I���Y��`�v�i�I�E�G���̋��Y��`�R���j�[�Ȃǁj�̔ے���傫�Ȍ��B���j�����Ă��Ȃ��B�����Ȃ�V�����Љ�\���̂��A�N���̖��@�ňꋓ�Ɍ��o�����̂ł͂Ȃ��A�Â��u����v�̖Ԃ̖ڂ̂������ɁA�V�������W�����X���Ɛ����Ă������Ƃɂ���āA�Ō�ɂ́i�����A�����I�J�^�X�g���t�B�[���o�āj�S�Љ�����̂��B�u�ǒn�I���Y��`�v�̍ĕ]�����K�v���B���Ƃ��A�������������܂苤�Y��`�ɏ��������Ȃ����Ƃ��̐S���A�ȂǁB
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@


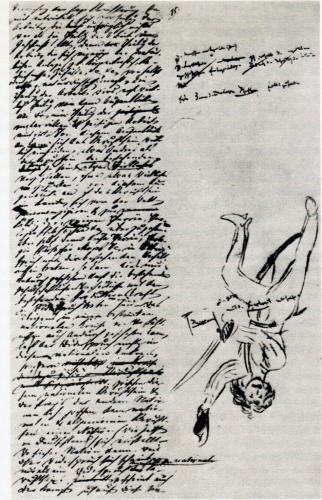 �@
�@


 �c
�c