06/06の日記
18:04
【ユーラシア】『ドイツ・イデオロギー』ノート(1)
---------------
.

こんばんは。(º.-)☆ノ
⇒:このシリーズの最終回 【ユーラシア】『ドイツ・イデオロギー』ノート(14)へ。
これから数回にわたって、カール・マルクス,フリードリヒ・エンゲルス『ドイツ・イデオロギー』を抄録します。これは、共著として構想された著作の序論と、本文の最初の部分であり、著者らによって何度か手を加えられた上、大幅に組み直す途中の・編集しかけの状態で遺されたので、用紙の並べ方からして定説がありません。
ここでは、廣松渉・編訳,小林昌人・補訳『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,2002,岩波文庫. をテクストとして使用します。
故・廣松渉氏は、草稿の詳細な検討の結果として、“『ドイツ・イデオロギー』は、マルクスとエンゲルスの共著というより、エンゲルスが主導して執筆し、マルクスがそれに手を加えたものだ”(エンゲルス主導説)という新説を提起。この訳書は、廣松氏が自説を説明するために出版した独日対訳本(廣松渉・編訳『ドイツ・イデオロギー 手稿復元新編輯版』,1974,河出書房新社.)をもとにしています。じっさい、草稿の大部分はエンゲルスの筆跡です。
これに対して、最近の有力説(マルクス口述説)は、テクストの・より詳細な観察から、マルクスが口述し、エンゲルスが筆記したとしています(『季刊 経済理論』57-3,2020.10.,pp.109-112: 大村泉「橋本直樹書評へのリプライ」)。
つまり、筆跡だけでは、主に誰の構想ないし思想が記されたものか、決定的なことは言えない、――ということになります。
私は、“エンゲルス筆記”は間違えないとしても、マルクスが一方的に祖述してエンゲルスが筆記した……という「マルクス口述説」には疑問を感じます。
たとえば、二人で討論して、その過程と結果をエンゲルスが筆記した。あるいは、口述するマルクスに対し、エンゲルスが時々反論や補足を述べて、マルクスが再考する、といった形で考察を進め、その過程を逐一エンゲルスが筆記してゆく、―――そのようなものではなかったかと思うのです。
通常一人で書いている時の“書きながらの訂正”は、エンゲルスよりマルクスのほうが顕著に多いという・二人の執筆のクセに対し、このテクストでは、通常のエンゲルスの6倍、通常のマルクスと比べても2倍の“書きながらの訂正”があるそうです。それが「マルクス口述説」の根拠になっているのですが、別の考え方もできるのではないか? ‥‥むしろ、“討論しながらの書下ろし”を想定したほうが、通常のマルクスと比べても訂正が多いことを、説明しやすいと思います。
マルクスが一方的に口述し、エンゲルスが書記に徹してそれを文字にしたという・大村氏らのイメージは、(そういう部分も本テクスト中にありうることは否定しませんが)内容にも沿っていないと思います。たとえば、歴史的変遷の叙述には、『パリ・ノート』の認識(たとえば、封建制解体期における小商品生産者,ヨーマンリーへの注目)からの後退が見られます。『ドイデ』以後の資本論草稿では、むしろ『パリ・ノート』の線に戻っている。
廣松氏によるテクスト配列で読むかぎり、「序論」から「本論一→三」、「附録」へと進むにしたがって、当初混沌として曖昧だった概念が整理されて、「生産力の発展、桎梏としての生産関係」という「史的唯物論」の“定式”に近づいてゆくようにも見えます。しかし、だからといって、当初の叙述は最終的な「定式」に至る途上の不完全な姿である……とは考えるべきでない。むしろ、「混沌」のなかから、「定式」思考にとらわれない本源的発想を汲み取りたい。←これを、本「ノート」の基本的視角とします。
『ドイツ・イデオロギー』岩波文庫版からの引用中、青字はマルクスの筆跡、それ以外(白字)はエンゲルスの筆跡。草稿の抹消箇所は下線付きで、追記・挿入は斜体で示します。
「エンゲルスの筆跡エンゲマルクスの筆跡ルスの筆跡」
「人間を動物から区別するのは、生産するみたいな感じでことによってである。」
「人間が自らを動物から区別するのは、道具を用いて生産することによってである。」
この「ノート」は、著作の内容を要約することも、著者らの思想を伝えることも目的としていません。あくまでも、私個人の思索のための抄録と、必ずしもテクストにとらわれないコメントを残すためのものです。
【1】「序論の第1草案」―――敬愛すべきフォイエルバッハ
「ドイツ・イデオロギー」、つまり、ドイツ特有の哲学思考、観念的思考に対する批判を目的とする本著『ドイツ・イデオロギー』は、ヘーゲル左派の3人の思想家を、それぞれ揶揄しながら批判ないし攻撃します。フォイエルバッハ批判はその筆頭に置かれているので、フォイエルバッハが“悪の権化”として槍玉に挙がっているのかというと、‥それは少し違う。むしろ、著者ら(マルクス、エンゲルス、モーゼス・ヘス)は、フォイエルバッハから受けた巨大な影響を、まだ脱し切れていないのです。
フォイエルバッハの「人間哲学」の基底は、後年に至るまで、マルクス、エンゲルスそれぞれの構想の底で、いきいきと生命を保っていたと言ってもよい。
「われわれは、〔…〕ドイツ哲学ならびにイデオロギー総体について若干の一般的論評をあらかじめ誌しておこう。〔…〕われわれはこの論評をただちにフォイエルバッハに向ける。なぜなら、彼こそが、少なくとも一歩前進を成し遂げた唯一の人物であり、当人の作品にまともに立ち入ることのできる唯一の人物だからである。」
廣松渉・編訳,小林昌人・補訳『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,2002,岩波文庫,p.23.
訳者註にしたがって、フォイエルバッハ本人の論著からの引用を掲げる。これは、フォイエルバッハの主著『キリスト教の本質』に対するマックス・シュティルナーの批判に、フォイエルバッハが答えたもの。ここでフォイエルバッハは、自著の要点をとてもわかりやすく説明している。まさに、“啓蒙主義”の真面目だ!
「『フォイエルバッハにとって、個体は絶対的な、すなわち真の、現実的な本質である〔…〕
フォイエルバッハにあっては、類とは抽象物を意味するのではなく、もっぱら個々の、それだけで固定化された自我に対して、汝、つまり他者、一般に私の外部に実存する人間諸個体を意味する。』」
廣松渉・編訳,小林昌人・補訳『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,2002,岩波文庫,p.272.
この「私」以外の「人間諸個体」とは、後段に書かれているように、現在生きている人々だけではない。将来生れてくる人間たちをも含んでいるのだ。――過去の人間も含んでいるはずだが、フォイエルバッハは、それは言わない。フォイエルバッハは、過去よりも未来に眼を注いでいるのだ。
「『それゆえ、フォイエルバッハがたとえば、個体は制限されているが類は制限されていないと言う場合〔…〕』」
a.a.O.
人間誰しも、自分は欠点のある卑小な存在だと感じる。もっといろいろなことができたらよいのに、もっと幸福ならよいのにと、誰しもが願う。しかし、そう思うのは、‥自分の不完全さが気になるのは、他の人間たちのなかに、自分にできないことをする人間がいると思うからだ。自分より幸福な人がいると思うからだ。人類全部を見わたせば、あれこれのできる人間、あれこれの幸福を享受している人間が必ずいるはずだ。いま生きている人間のなかにいなくても、将来の人間には、きっといるはずだ。‥‥そう考えると、かえって、少し救われるのではないだろうか? それが「類」ということなのだ。人間は、個人としては不完全だが、「類」としては限りなく完全なのだ。
「類」とは他人のことだ。太宰治は、「世の中とは他人のことだ」と言ったが、そういう・“我れ”を責める口実としての「他人」ではなく、‥‥フォイエルバッハが見るのは、“我れ”を安心させ、勇気づける根拠としての「他人」なのだ。
マルクスは、フォイエルバッハとともに、「人間は類的存在である。」と言う。人間は、どんなに孤独でペシミスティックな人であっても、どこかで「類」に支えられている。そのことに気づけば、“人類の無限発展”“進歩”という考えが、なぜ人々を夢中にさせたのか、その考えを信じることができなくなったわれわれが、いかに不幸になったのか、よくわかるはずだ。
フォイエルバッハは、“我れ”と“他の人間”との連帯に、「ナショナリズム」という枠をはめることを拒否し、一気に人類全体――将来の人間を含んだ――に広げようとする。
「『類の思想は個々の個人にとって存在するものであり〔…〕必要不可欠なものである。〔…〕われわれは、自分たちが制限されており不完全であると感じる。〔…〕われわれは、自分たちが道徳的にだけでなく感性的にも、つまり空間的・時間的にも制限されていると感じる。然り、われわれは、これら諸個人は、特定のこの場所、制限された哀れなこの時間の中でだけ存在するのである。そうである以上、制限のない類の思想、すなわち他の人間たち、他のいろいろな場所、他のもっと幸福ないろいろの時間という思想においてでなければ、一体どこで、われわれはこの制限されているという感情から自分たちを救い出すべきなのか?
それゆえ、神性の代わりに類をおかない者は個人の中に空隙を残すことになる。この空隙は必然的に神の表象によって、つまり人格化された類の表象によって再び満たされる。ただ類だけが、神性や宗教を止揚することができ、またそれらに取って代わることができる。』」
廣松渉・編訳,小林昌人・補訳『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,2002,岩波文庫,pp.272-273.

【2】「序論の第1草案」―――《自然史/人間史》の出発点
「われわれはただ一つの学、歴史の学しか知らない。歴史は二つの側面から考察されることができ、自然の歴史と人間の歴史とに区分されることができる。しかし、両側面を時間によって切り離すことはできない。人間が生存する限り、自然の歴史と人間の歴史は相互に条件づけあうのである。自然の歴史、いわゆる自然科学には、われわれはここでは関説しない。しかし、人間の歴史には、立ち入っておくべきであろう。〔…〕」
廣松渉・編訳,小林昌人・補訳『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,2002,岩波文庫,p.24.
歴史の「両側面」――すなわち「自然の歴史」と「人間の歴史」――「を切り離すことはできない。」「自然の歴史」は、人類が誕生した時点で終るわけではない。それ以後は、「自然の歴史と人間の歴史は相互に条件づけあ」って進むようになる。
「自然の歴史」とは「自然史」:気象学、地質学、植物相、生態学など、時間とともに変化する自然の実態だ。自然科学の中でも、物理、化学など、いつでも・どこでも通用する「法則」を探究する学問とは違う。マルクスが研究を志したのは、自然科学全般ではなく、「自然史」に関係する部門だった。
人類誕生以後も、自然は変化している。自然自身の変化もあるが、人間の活動の影響を受けた部分も少なくない。
しかし、残念ながらマルクスもエンゲルスも、まだ自然科学をよく知らない。「自然の歴史」について語るのは、まだ無理なのだ。
そこで、以下ではもっぱら「人間の歴史」について考察することになる。
「われわれが出発点とする諸前提は何ら恣意的なものではなく、ドグマでもなく、仮構の中でしか無視できないような現実的諸前提である。それは現実的な諸個人であり、彼らの営為であり、そして、彼らの眼前にすでに見出され、また彼ら自身の営為によって創出された、物質的な生活諸条件である。それゆえ、これらの諸前提は純然たる経験的手法で確定することができる。」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,p.25.
「物質的な生活諸条件」:「物質的」は「素材的」とも訳しうる。《自然》そのもの、人間の影響を受けて変化した《自然》、および、人間が意識して《自然》から切り取り加工した物質や条件。これらが、人間が生活を営むための「素材」、すなわち、その時々の歴史的社会のメカニズム(諸形態)が機能するための「素材」である。
「人間史全般の第一の前提は、いうまでもなく、生きた人間諸個人の生存である。これらの諸個人が自らを動物から区別することになる第一の歴史的行為は、彼らが思考するということではなく、彼らが自らの生活手段を生産し始めるということである。第一に確定されるべき構成要件は、それゆえ、これら諸個人の身体組織と、それによって与えられる身体以外の自然に対する関係である。われわれは、ここではもちろん、人間そのものの肉体的特質についても、また人間が眼前に見出す自然的諸条件、すなわち地質学的、山水誌的、風土的その他の諸関係、についても、立ち入ることはできない。〔…〕歴史記述はすべて、この自然的基礎ならびにそれが歴史の行程の中で人間の営為によってこうむる変容から、出発しなければならない。
〔…〕人間は自らの生活手段を生産することによって、間接的に自らの物質的な生そのものを生産する。」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,pp.25-26.
考古学でも、自然人類学でも、人間と類人猿を区別する指標は、“道具を作ること”とされる。つまり、自ら(ないし他の人間が)加工した道具を使って生産を始めること。これが「人間の歴史」の開始点。
「生産」とは、道具を使って自然を加工することである。拾った石で木の実を割ったり、芋を掘り出して川の水で洗うのは、ゴリラやニホンザルも行なう。しかし、自ら加工した道具を使って加工するとき、加工は、意識性(計画性)の一段高いレベルに上がる。
“人間の身体的営為”と“人間と自然との関わり”、つまり《人間と自然の物質代謝》が、歴史的発展の基本要件だ。
「自然的諸条件、すなわち地質学的、山水誌的、風土的その他の諸関係」は、訳者によれば、別の頁でのマルクスの追加指示「地質学的、水理学的、等々の諸関係」(p.53)に基いている。「山水誌」「水理学」は、河川と灌漑か。
同じ注記により、「人間そのものの肉体的特質」は、「人間の身体、欲求、労働」に修正される。「欲求」が重要。

Gaston Goor
「人間たちが生産手段を生産する様式は、さしあたりは、すでにそこにあって再生産されなければならない生活手段そのものの特質に依存する。
この生産の様式は、 〔…〕すでに、これら諸個人の活動の一定の方式なのであり、自分たちの生を発現する一定の方式、諸個人の一定の生活様式である。諸個人がいかにして自分の生を発現するか、それが、彼らの存在の在り方である。彼らが何であるかということは、それゆえ、彼らの生産と合致する。すなわち、彼らが何を生産するか、ならびにまた、彼らがいかに生産するかということと合致する。それゆえ、諸個人が何であるかということは、彼らの生産の物質的諸条件に依存する。」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,岩波文庫,pp.26-27.
「この生産の様式は、……自分たちの生を発現する一定の方式……である。」――原始社会の人間たちは、《自然》との一体性のなかで、本源的労働に近い生活を行なっていた。労働の《疎外》はわずかだった。ただし、完全な「本源的労働」、まったく《疎外》されていない労働というものは、原始共産主義社会であろうと未来の共産主義であろうと、ありえない。人間が人間として《自然》と交渉するかぎり、《疎外》はゼロではない。《疎外》ゼロをめざすなら、人間であることをやめなければならない――というのが、「人間労働とは意識的な物質代謝である」というマルクスの“公理”からの帰結である。
「生産手段」――道具と土地――(土地にしても、人間がその上で生活することによって変容を加えてはじめて生産手段となる)――は、出現するやいなや呪術的性質を帯びる。なぜなら、道具の制作と使用じたいが、人間の《自然》からの相対的独立であり、人間と《自然》とのあいだに距離ができることであり、したがって最初の《疎外》の現出であったから。動物は自然を恐れない。人間が、《自然》とは別の自分を意識した時に、《自然》は脅威的な姿で人間の前に立ち現れた。道具は、ハックにせよタビにせよ、《自然》の威力を分有する神であるからこそ、人間はそれを手にして《自然》の前に立つことができるのだ。
「諸個人が何であるかということは、彼らの生産の物質的諸条件に依存する」「おまえはブルジョワだからブルジョワだ」――この教条的恫喝が、どうやって出てくるのかが示されている。
生産労働は、最初の人間たちにとって、「自分たちの生を発現する……方式」であったという・労働の本源性に関する認識――この段階では《疎外》はまだそれほどでない――は、すぐれたものである。しかし、そこから「ドイツ・イデオロギー」によって論理のみで導出される結論を、絶対視すべきでない。
たとえば、原始の人びとが《自然》の中で“輝く石”を見つけた時の驚き、それが人間の加工によって輝きを増すことを知った時の喜びを、「生活手段の生産」一般に解消することはできない。この驚きが、人間のあらゆる文化を生み出すことになるのだ。
「この生産は、人口の増加とともに初めて現れる。人口の増加は、これはこれで諸個人相互間の交通を前提にしている。この交通の形態はこれまた生産によって条件づけられる。
したがって、事実は、一定の様式で生産的に活動している一定の諸個人が、この一定の社会的・政治的諸関係に入り込むのである。〔…〕社会的編制と国家は、いつも一定の諸個人の生活過程から生じる。ただし、ここでいう諸個人とは、〔…〕行動し、物質的に生産し、そして活動しているそれゆえ、一定の物質的な、彼らの恣意から独立な、諸制限・諸前提・諸条件の下で活動している、そのような諸個人である。」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,岩波文庫,pp.27-28.
「一定の物質的な、彼らの恣意から独立な、諸制限・諸前提・諸条件の下で」――つまり、人間たちの「生産」その他の活動は、《自然》を前提としつつ《自然》からの制約を受けると同時に、「伝統(Überlieferung)」を前提としつつ「伝統」の制約を受けている。
「人口の増加」→「生産」の拡大→諸個人間の「交通」形態→「人口の増加」→ ‥‥ というスパイラルな関係が、「生産」や「交通」の形態(段階)を決めるという“条件づけ”の関係にもなっている――そういう「史的唯物論」が着想されている。しかし、マルクス/エンゲルスは、↓次節で見るように、「史的唯物論」の“発展理論”が、安易に「図式」ないし「処方箋」として受け取られてしまうことを強く警戒してもいるのだ。
「交通」という多義的な概念。この段階ではかなり曖昧。のちに、「分業」「生産諸関係」「生産の様式」などの語に引き継がれてゆく内容を、混然と含んでいると思われる。
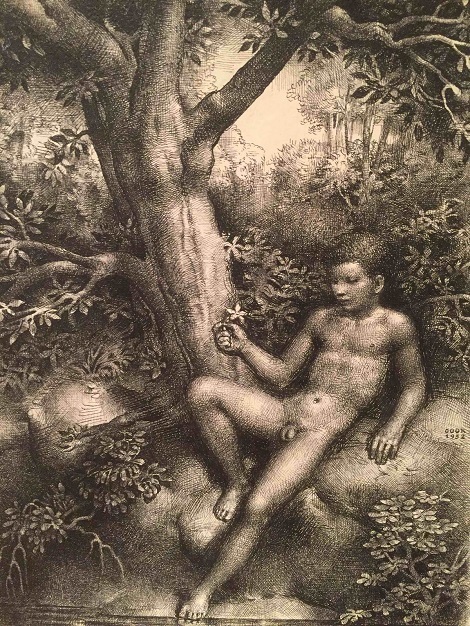
Gaston Goor
【3】「序論の第1草案」―――歴史は、「図式や処方箋」を与えない!
「これら諸個人が抱く表象は、自然に対する彼らの関係、彼ら相互間の関係、彼ら自身の特質、このいずれかについての表象である。どの場合でも、これらの表象が、彼らの現実的な諸関係と活動の、彼らの生産の、彼らの交通の、彼らの社会的・政治的な関わりの、〔…〕意識的表現だということは明らかである。〔…〕
理念、表象、意識、の生産は、当初は直接に、人間たちの物質的活動や物質的交通、現実的な生活の言語に編み込まれている。表象することや思考すること、つまり人間たちの精神的交通は、ここではまだ、彼らの物質的な関わり合いの直接的な流出として現われる。一民族の政治、法律、道徳、宗教、形而上学、等々の言語に表わされるような、精神的生活についても同様である。人間たちの表象や理念等の生産者は、人間たちである。しかも、自分たちの物質的生活の生産の様式によって、また自分たちの物質的交通と、より上層への――社会的・政治的編制への――交通の成長によって、条件づけられている人間たちである。ただし、自分たちの生産諸力の一定の発展によって、またそれに照応する交通の一定の発展――交通の最上層にまで及ぶ発展――によって条件づけられている、現実の行動している人間たちである。意識とは意識された存在以外の何ものでもありえない。そして、人間の存在とは、彼らの現実的な生活過程のことである。」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,岩波文庫,pp.28-30.
「一定の様式で生産的に活動している一定の諸個人」(p.28),「生産の様式」――これらを、ここで、「唯物史観」における「生産様式」のような確定概念と解するべきではない。「生産の様式」とは、より具体的なさまざまな内実を孕んだ語と見るべき。
“書きながらの訂正”によって「ただし」以下に変更されている部分。訂正前:「物質的交通」は、「より上層」の「交通」すなわち社会的・政治的編制へと成長する。つまり、原始部族社会からの「国家」の形成・成立。
訂正後:「生産諸力の一定の発展」に、「交通の一定の発展――交通の最上層にまで及ぶ発展」が「照応」している。「交通」の発展程度(「社会的・政治的編制」にまで達するかどうか)は、「生産力」発展の程度に照応するという“「照応」の論理”。「生産力」教条主義に近づいている。この近くには、「生産力」程度による人種差別正当化の論理も書かれている(pp.25-26.):
「人間が眼前に見出す自然的諸条件、すなわち地質学的、山水誌的、風土的その他の諸関係、〔…〕これらの諸関係は、しかし、人間の本源的・自然発生的な組織、とりわけ人種的差異を条件づけるだけでなく、連綿と今日まで続く人間のあらゆる発展ないし未発展を条件づけている。」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,岩波文庫,pp.25-26.
つづく 31ページでは、さらに教条化して、土台決定論を述べ、「意識諸形態」の自立性を否定する。その根拠は、あまりにも硬直した決めつけであることが見て取れる↓:「人間の頭脳における茫漠とした像ですら、〔…〕生活過程の、必然的な昇華物なのである。」このような論理のみの帰結を絶対と信じるイデオロギーは、いったい彼らのいかなる「現実的生活過程」の「必然的昇華物」であるのか?!
土台決定論。しかもその土台の変化は、「法則」によって決定されているという。決定するものが土台であるか、他のものであるかにかかわりなく、決定論自体が不当である。
「現実に活動している人間たちから出発し、そして彼らの現実的な生活過程から、この生活過程のイデオロギー的な反映や反響の展開も叙述される。人間の頭脳における茫漠とした像ですら、〔…〕生活過程の、必然的な昇華物なのである。道徳、宗教、形而上学、その他のイデオロギーおよびそれに照応する意識諸形態は、こうなれば、もはや自立性という仮象を保てなくなる。〔…〕これらのものが発展をもつのではない。むしろ自分たちの物質的な生産と物質的な交通を発展させていく人間たちが、こうした自分たちの現実と一緒に、自らの思考や思考の産物をも変化させていくのである。〔…〕
こうして、思弁のやむところ、〔…〕人間たちの実践的な活動、実践的な発展過程の叙述が、始まる。」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,岩波文庫,pp.31-32.

『ドイツ・イデオロギー』草稿の1頁。
二人は、似顔絵描きの才能もあったらしいw
左はブルーノ・バウアー? 右はフォイエルバッハ?
しかし、↓つぎの段落で著者ら自ら述べているように、“法則”が歴史を作るのではない。歴史的現実から抽象されるものは、その・一回かぎりの歴史的現実にのみ通用するアウトラインにすぎない。他の国、他の地域の歴史的発展には、また別のアウトラインが存在する。地球上でただ一つの歴史が進行するのは、ただひとつの資本主義が世界全体を覆った時からだ。資本主義どうしは、たがいに無関係に同時に存在することができない。併存する資本主義は、つながりあうようになり、争い合い、遠からず一方が他方を呑み込んでしまう。
「現実〔的な歴史〕が叙述されれば、自立的な哲学は、棲息の場を失う。それに代わって登場しうるのは、たかだか、人間の歴史的発展の考察から抽象されるごく一般的な結論の総括ぐらいでしかない。この抽象されたものは、それ単独では、つまり現実の歴史から切り離されては、全く無価値である。それはただ、他の人々に歴史の考察のための歴史的史料を整理しやすくし、史料の個々の成層を順序づける輪郭を与えるのに役立てることができるだけである。抽象されたものは、しかし、哲学のように、それに従えば歴史の各時代がうまく切り盛りできるといった処方箋や図式を与えてくれるものでは決してない。むしろ、史料の考察や整理に、さまざまな成層の現実的・事実的な連関の探求に、着手するそして〔…〕、現実的な叙述に着手する、その場面から初めて困難が始まる。この困難が除去される条件となる諸前提は、〔…〕各時代の各個人の現実的生活過程と実践的営為とを研究することを通して、初めておのずから明らかになる。われわれはここで、これら抽象されたものの若干を取り出し――それをわれわれはイデオロギーに対置して用いる――それを歴史的事例に即して説明することにしよう。」
『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,岩波文庫,pp.32-33.
これが「序論の第1草案」の結語であることに注意しよう。
最後の1文で言っているように、「人間の歴史的発展の考察から」「抽象されたもの」とは、このあとの「本論」で展開されている“社会発展史”の叙述にほかならない。
つまり、後世の“「マルクス主義」者”たちが「唯物史観」の定式化だ、「歴史の発展法則」だと持ち上げて絶対化した「公式」は、当のマルクス/エンゲルスによれば、「それ単独では、つまり現実の歴史から切り離されては、全く無価値である。」歴史を理解するための「処方箋や図式を与えてくれるものでは決してない。」単に「史料を整理しやすくし、史料の個々の成層を順序づける輪郭を与えるのに役立てることができるだけである。」
すなわち、歴史を構成する「さまざまな成層の現実的・事実的な連関」は、各別に探究されなければならない。「公式」にあてはめて理解しよう‥などと考えてはならない、と言うのだ。
つまり、これから述べるのは、普遍的な歴史の「発展法則」などではなく、たまたま西欧世界で生起した歴史過程を整理して、アウトラインを抽出したものにすぎない。これをもって、個々の歴史現象のつながりや因果関係を判断することができる‥などと思ってはならない。これはあくまでも、ヘーゲルらが描く観念的な“精神史”に対して、それは違う、そうじゃない、と言うための対抗馬を立てたものにすぎない。ヘーゲルを否定したうえで、もしも、こちらのほうを「法則」視するならば、ヘーゲルにも劣らないドグマを築き上げてしまうことになるだろう、と警告しているのである。
ヘーゲルのドグマを“逆立ち”させれば正しくなるのではない。いかなるドグマも有害であり、あってはならないのだ。
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]





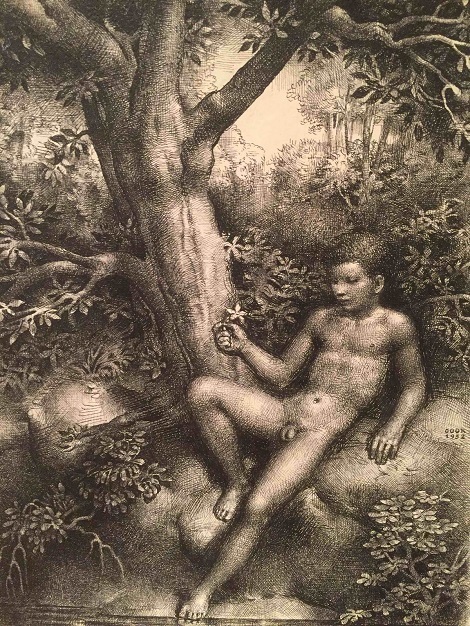

 彡
彡