07/30�̓��L
20�F47
�y�K�Ǐ�150�z�f�J���g�w���@�����x(2)�\�\�\�g�l���鎄�h�Ƃ͉��҂��H
---------------
.
 �@
�@
�O�F���`�[�m�u�������q�̋A�ҁv�i1619�j�@�@
�@�����́B(º.-)���
�@�y�K�Ǐ�150�z�f�J���g�w���@�����x(1) ����̂Â��ł��B
�@�y�T�z�����^���Ă���A�Ƃ������Ƃ͋^�����Ȃ��i��S���E�O���j
�@1628�N9���A�f�J���g�̓I�����_�Ŗk���̃t���l�P���ŁA�v���ɐ�O���邽�߂̉B�ِ����ɓ������B�P�N��ɂ̓A���X�e���_���Ɉڂ����w���E�_�x�̎��M���͂��߂邪�A1933�N�Ɋ��������E���̓V���w�C���w�C���w����l�̐����w�C�썰�_�ɋy�Ԓ���́A�f�J���g�̐��O�ɂ͏o�ł���Ȃ������B�܂���K�����C�ٔ��̔������`�����A�R�y���j�N�X�����@���R��ɂ���Đ����ɒf�߂��ꂽ���Ƃ�m�����f�J���g�́A�R�y���j�N�X�ȏ�ɓO�ꂵ�ăA���X�g�e���X�F���ς�ᔻ�������̏��̏o�ł��A�f�O�����̂��B
�@�w���E�_�x�̍[�T�́A�w���@�����x�́u��T���v�ŏЉ��Ă���A�������s�n�����t�������āB
�@�t���l�P���ōŏ��̂X�����ԁA�f�J���g�́A�u�ق��̂��Ƃ͉������Ȃ��Łv�v���ɂ�����O�����B���̎v���́A�w���E�_�x�œW�J���ꂽ�s��Ȏ��R�w�̌n�̊�b�ƂȂ�E���ɂ̓N�w�����̔������߂������̂������B�܂�A�g�V�����s��ȓs�s�h�����݂��邽�߂̐������ɐ旧���āA�Â��s�s�̎c�[���Ō�̈�Ђ܂ŏ������|�����߂��Ƃɂق��Ȃ�Ȃ������B
�u�����킽���́A�����^���̒T���ɂ̂g��肽���Ɩ]��ł����̂ŁA�k�c�l�ق�̏����ł��^��������������̂͑S���A��ΓI�Ɍ��Ƃ��Ĕp�����ׂ��ł���A���̌�ŁA�킽���̐M�O�̂Ȃ��ɂ܂������^�����Ȃ��������c�邩�ǂ�����������߂˂Ȃ�Ȃ��A�ƍl�����B
�@�������āA���o�͎��ɂ킽���������\������A���o���z��������Ƃ���̂��͉̂������݂��Ȃ��Ƒz�����悤�Ƃ����B
�@���ɁA�w�̍ł��P���Ȃ��Ƃ���ɂ��Ă����A���_���܂������Č�T�����i��������_�j���������l������̂�����A�킽�����܂����̂���Ƃ���������肤��Ɣ��f���āA�ȑO�ɂ͘_�Ƃ݂Ȃ��Ă������������ׂċU�Ƃ��Ď̂ċ������B
�@�Ō�ɁA�킽���������ڊo�߂Ă���Ƃ��Ɏ��v�l�����ׂĂ��̂܂ܖ����Ă���Ƃ��ɂ�����ꂤ��A���������̏ꍇ�^�ł�����͈̂���Ȃ����Ƃ��l���āA�킽���́A����܂Ŏ����̐��_�̂Ȃ��ɓ����Ă������ׂẮA���̌��z�Ɠ����悤�ɐ^�łȂ��Ɖ������悤�A�ƌ��߂��B�v
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,pp.45-46.
�@�u���o���z��������Ƃ���̂��́v�\�\�܂�A������́A�������̂��ׂāA�����������o�ɂ���đ̌����Ă���E���̐��E���ׂĂ��A���݂��Ȃ����A�܂��́A�܂������v���������đz������Ă��鋕���Ȃ̂��ƍl���邱�Ƃɂ����B�A���w�A�_���w�̏��藝���A���ׂāu�U�Ƃ��Ď̂ċ������v�B�����āA�u�ڊo�߂Ă���Ƃ��Ɏ��v�l�v�͂��ׂāA�u�����Ă���Ƃ��v�Ɍ����u���̌��z�v�Ƌ�ʂ̂Ȃ����̂ŁA�����Ɂu�^�ł�����͈̂���Ȃ��v�Ɖ��肵���B�܂�A�F���̑��݂��A�����œ����悤�Ȃ����Ȃ�@�����A�g�̉��ŋN���Ă��鏔���ہA�������̐��E�������A�Ȃɂ������g�^�킵���h������āg�^�ł��鎑�i�Ȃ��h�����ׂẮg�U�h�ł���A�Ƃ��Ď̂ċ����Ă䂭�̂ł��B
�@���̂悤�ɂ��āA���ׂĂ��g�^���h�����������ɁA�����c����̂�����̂��ǂ����H ����ł��ǂ����Ă��^�����Ȃ����̂��A��������̂��ǂ������A������߂悤�Ƃ����킯�ł��B
�@���̂��Ƃɗ���̂��A�����̗L�����u���v���A�䂦�ɁA��ꂠ��v�Ƃ�����ꌴ���́g�����h�Ȃ̂ł����A�������A�������́A���́g�^�����Ȃ��Ō�̋��ɂ̌����h�ɑ��Ă��A�g�^���h�̊�����������Ǝv���܂��B�Ȃ��Ȃ�A�g���ׂĂ��^���h�ƁA�f�J���g���g�������̂����硡�
�u���������̂�����ŁA���̂��ƂɋC�������B���Ȃ킿�A���̂悤�ɂ��ׂĂ��U�ƍl���悤�Ƃ���Ԃ��A�����l���Ă������̂킽�����K�R�I�������̂��łȂ���Ȃ�Ȃ��A�ƁB�����āw�킽���͍l����A�䂦�ɂ킽���͑��݂���k�������i�I���j�E�A�̃j�����݃��l�x�Ƃ��������^���́A�k�c�l���łŊm���Ȃ̂�F�߁A�����^�����A���߂Ă����N�w�̑�ꌴ���Ƃ��āA���߂炤���ƂȂ��������A�Ɣ��f�����B
�@���ꂩ��A�킽���Ƃ͉����𒍈ӂԂ����������A���̂��Ƃ�F�߂��B�ǂ�Ȑg�̂������A�ǂ�Ȑ��E���A�����̂���ǂ�ȏꏊ�������Ƃ͉��z�ł��邪�A������Ƃ����āA�����͑��݂��Ȃ��Ƃ͉��z�ł��Ȃ��B
�@���ɁA���������̂��̂��^�������^�����ƍl���邱�Ǝ��̂���A����߂Ė��ؓI�ɂ���߂Ċm���ɁA�킽�������݂��邱�Ƃ��A������B�t�ɁA�����킽�����l���邱�Ƃ���߂邾���ŁA���ɂ��đz���������ׂĂ̑��̂��̂��^�ł������Ƃ��Ă��A�킽�������݂����ƐM���邢���Ȃ闝�R�������Ȃ�B�v
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,pp.46-47.
�@�u�����͑��݂��Ȃ��Ƃ͉��z�ł��Ȃ��B�v�\�\�\�ق�Ƃ��ɁA�����ł��傤���H �u�ǂ�Ȑ��E���c�c�����Ƃ͉��z�ł���v�Ƃ������Ƃ́A�����ȊO�̐l�A�F�l�����A�Ƒ������A�����̈�����l�тƂ́u���݂��Ȃ��v�Ɖ��z�ł���̂ɁA�u�����v�����́u���݂��Ȃ��v�Ɖ��z���邱�Ƃ��ł��Ȃ��A���f�J���g�͌����B�ق�Ƃ��ɁA�����ł��傤���H
�@��ς̖�肾�Ƃ��A�����̖�肾�Ƃ������Ă��܂�����܂łł����A�����炭���̕��͂�ǂ�ł���F����i���{����g���l�тƁj�̑啔���́A�f�J���g�̎v�l���A������ƈَ��Ȃ��̂Ɋ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�f�J���g�̑z��Ƃ͋t�ɁA�����̗F�l���Ƒ����A���m��ʑ��l�������A�݂Ȃ��݂ȍ��̂܂ܑ��݂��Ă��āA�u�����v���������݂��Ȃ����E�Ƃ����̂́A�ނ��뉼�z�ł��鐢�E�ł͂Ȃ��ł��傤���H ���Ƃ��A���Ȃ���������A�s���̎��̂ŖS���Ȃ����Ɖ��肷��A�����������E�ɂȂ�܂��B���ꂪ���z�ł��Ȃ��Ƃ�����A���̐��E�ɑ��邠�܂�ɂ������ȕ��J�ł͂Ȃ����H�d�d���ɂ́A�����v����̂ł��B
�@�u�킽���͍l����v�u�l���Ă��邱�̂킽���v�Ƃ́A�g�킽�����^���h�g�^���Ă������̂킽���h�ɂق��Ȃ�܂���B�u�킽���v�̎v�l���A�����������g�^���h�A�g�^�h�ł͂Ȃ��Ƃ��Ď̂ċ����Ă䂭���Ƃɂ���āA�u�킽���v�͂����܂ŗ����̂�����ł��B�u�킽���v�̎v�l���A�����������A�����邪�܂܁A���l�ɋ������邪�܂܂Ɂg�M����h�g�M�߂���h�v�l�ł������Ƃ�����A���̂悤�Ȓn�_�ɗ��邱�Ƃ͂Ȃ������͂��ł��B
�@
�@�킽�����^���Ă����A�䂦�ɂ킽���͑��݂��Ă���B

�@�������A�g�^���Ă����h�̂́A�ق�Ƃ����u�킽���v�ł��傤���H �u�ǂ�Ȑg�̂������A�ǂ�Ȑ��E���A�����̂���ǂ�ȏꏊ�������v��ԂŁA�����g�^���h����������ɖ苿���Ă���B������u�킽���v���ƁA�Ȃ�������̂��H
�@�f�J���g�́A���̖{���t�����X��ŏ����Ă��܂��B�k �l�̒��̃J�^�J�i�́A�����ł̓��e����ł����A���e����ł��������Ƃł��B���ׂĂ̓����ɂ͐l�̌`�������āA�l�̂̂Ȃ�����Ƃ������̂͊ϔO�ł��܂���B�u�킽���͍l����v�u���Ȃ��͍l����v�u�ނ�͍l����v�Ƃ������Ƃ͌����Ă��A���҂ł��Ȃ����̂��A�����u�l����v�\�\�\�Ƃ������Ƃ͂��肦�܂���B
�@�����f�J���g���A�t�����X��ł͂Ȃ��A���{��⒆����ōl���Ă����Ƃ�����d�d�A����A�h�C�c�ꂾ�����Ƃ��Ă��A���������Ⴄ���Ƃ��l����ꂽ�Ǝv���̂ł��B�i�h�C�c�ꌗ�̓N�w�҃j�[�`�F�́A�u�f�J���g�́w���v���A�䂦�ɂ�ꂠ��x��ᔻ���A���ꂪ�C���h=���[���b�p��̕��@�ɗR��������̂ł���v�Ƃ��A�u���̂Ȃ�����A���Ƃ��E����=�A���^�C��̐��E�ł́A������v�l���\�ł��낤�Ƃ����v���J�s�l�w���t�Ɣߌ��x,�����܊w�|����,p.312�j
�@�t���C�g�̐[�w�S���w�̗p����u�G�X(Es)�v������܂��B�u�G�X�v�́A���Ƃ��ƂR�l�̒P���̐l�̑㖼���ŁA�p��́uit�v�ɂ�����܂����A�����ł́u��l�́v�Ŏg����ꍇ�����ɂȂ�܂��B�h�C�c��̔�l�̂��u�G�X�v�́A�p��́uit�v��肸���ƍL���Ӗ��Ŏg���܂��B
�uEs�͉p���it�ɂ�����B�O����̔�l�̑㖼���́A�����Ύ��R���x�z�����l�i�ȗ͂�\�����̂ł��邪�i���Ƃ��� it rains�j�A����Ɠ����悤�ȈӖ��ŁA�l�Ԃ̐S�����A�ӎ��I�ɓ������邱�Ƃ̂ł��Ȃ����m�̗͂ɂ���ċK�肳��Ă��邱�Ƃ�\�����߂ɁA�G�X�Ƃ����p�ꂪ�g����B���̈Ӗ��ł́A�����I�ȏՓ��̂悤�Ȃ��̂ł���B�k�c�l
�@�S�̑��u�́A�G�X�A����A������Ƃ����O�̌n�A���Ȃ킿�R������Ȃ���̂ƍl������B�k�c�l�G�X�́A�����ނ˖��ӎ��ɑΉ�������̂Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B�v
�@�u�G�X�v�́A���Ƃ��ΐl�Ԃ̊��o�E�������ۂ�\���̂Ɏg���܂��F
�@Es hungert mich.�@�@�@[���ꂪ]������B�i���͕������j
�@Es träumte mir heute nacht.�@�@[���ꂪ]��ӂ킽���ɖ��o���B�i��ӎ��͖��������j
�@�^���E���R�Ȃǂɂ�錻�ۂ�\������ꍇ������܂��F
�@Es gibt immer Ausnahmen.�@�@[�����]�˂ɗ�O��^����B�i�˂ɗ�O�͂�����̂��j
�@Es tut mir Leid, aber ich habe keine Zeit.�@�@[���ꂪ]�킽���ɒɂ݂��Ȃ��i�\����܂���j�A���Ԃ��Ȃ���ł��B
�@���₢��d�d�A�u�l����v��������A�h�C�c��ɂ͂����Ƃ������\��������܂��F
�@Es dünkt mich, man hat uns vergessen.�@�@[���ꂪ]�����l����A�l�͉�X��Y�ꂽ�ƁB�i�ڂ���͖Y����Ă��܂����悤�ȋC�������j
�@�u�l����v�Ƃ����E�ӂ��̓����́u�f���P��(denken)�v�ŁA�u�킽���v�u���Ȃ��v�ȂǁA�l�����������ɂ��āA�uIch denke,...�v�i�c�c�Ǝ��͎v���j�Ƃ����悤�Ɏg���܂��B�Ƃ��낪�A�u�f�����P��(dünken)�v�́A��l�̂��u�G�X�v�����ɂ��āA�d�d�u�����l����v�̂ł͂Ȃ��A�Ȃɂ��ڂɌ����Ȃ��t���C�L�̂悤�Ȃ��̂��A���̂��Ƃ��l���Ă���\�\�\�Ƃ����\���ɂȂ�܂��B
�@���̃h�C�c��̂悤�Ȃ̂́A��퓌�m�I�ȕ\���Ȃ�ł��傤�B�������A���m�̌���i���m�ɂ����A���A�W�A�A�C���h����A�����A�W�A�̈ꕔ�܂łӂ��ނł��傤�j�ł́A�ӂ��͏�Ɏ�ꂪ�ӎ�����܂��B�܂�A�ǂ�ȓ���ɂ��A���Ȃ炸�s�҂�����܂��B�s�ׂɂ͂˂��s��́A�ӔC���������̂ł����āA����̂Ȃ��s�ׂƂ����̂́A���肦�Ȃ��킯�ł��B
�@�������āg�s��̂��A�˂Ƀn�b�L��������h�g�N�������̂����A�����܂��ɂ��Ȃ��h�ނ�̍l�����́A�������ɁA�����̎Љ�ł͗L���Ȃ��̂ł��傤�B
�@�������A�f�J���g�́u���v���c�c�v�̂悤�ȁA���v�ґz�̉ʂĂɒB�������n�ɂ����Ă��A�����Ȃ̂��ǂ����́A��l�̗]�n������܂��B�����̎Љ���A���E���A�F�����ׂĂ��A�u�U�v�Ƃ��ď������������ƂŖ苿���Ă���A�ǂ��܂ł��u�^���Â���v�u�^���v�B�������u�s�ҁv��z�肷�邱�Ƃ́A�͂����ēK�Ȃ̂��H �f�J���g�́A������������A�قȂ郌�x�����������Ă���̂ł͂Ȃ����H
�@�������A�f�J���g�̂��̋ɖk�̐��E�ɂ́A
�u�ǂ�Ȑg�̂������A�ǂ�Ȑ��E���A�����̂���ǂ�ȏꏊ�������v
�@�Ƃ����̂ł��B�����́u�g�́v�����l�́u�g�́v���Ȃ��A�����⑼�l���ʒu���ׂ��u�ꏊ�v�����������悤��䩔��Ƃ�������B����A���̋�ԑS�̂��A����I�Ŏ~�܂�Ƃ���̂Ȃ��u�^���v���͂��ł���B�����ɁA�u�킽���v�u���Ȃ��v�̂悤�ȁu�s�ҁv��F�߂邱�Ƃ��A�͂����Ăł���̂��낤���H
�@
�@�f�J���g�́A
�u���������̂��̂��^�������^�����ƍl���邱�Ǝ��̂���A����߂Ė��ؓI�ɂ���߂Ċm���ɁA�킽�������݂��邱�Ƃ��A������B�t�ɁA�����킽�����l���邱�Ƃ���߂邾���ŁA���ɂ��đz���������ׂĂ̑��̂��̂��^�ł������Ƃ��Ă��A�킽�������݂����ƐM���邢���Ȃ闝�R�������Ȃ�B�v
�@�ƌ����܂��B�������A�u���̂��̂��^�������^�v�����Ƃ́A�����Ŏv�l���~�߂Ȃ���A����������u�^���v�������g���^�����Ɂ\�\�\���Ȃ킿�u�^�����́v�̑��݂Ɂ\�\�\�u�^���v�������邱�ƂɁA�s��������������Ȃ��͂��ł��B�f�J���g�̂悤�ɁA���̈����O�Ŏv�l���~�߂闝�R�́A�����Ȃ��B
�@�����A�u�킽�����l���邱�Ƃ���߂�v�A���Ȃ킿�u�^���v���Ƃ���߂�Ȃ�A�Ƃ���ɁA�u���đz���������ׂĂ̑��̂��̂��v�������A�u�킽���v�́u���݂���v���Ƃ���߁A�u�킽�������݂����ƐM���邢���Ȃ�v���Ղ������Ă��܂��ƁA�f�J���g�͌����܂��B
�@�Ɍ��I�g�v�l�����h���o���f�J���g�ɂƂ��āA����ȑO�́d�g���E�Ǝ��Ȃւ̗��h�ȑO�́E�f�p�Ȑ��E�M�߂ɂƂǂ܂邱�Ƃ́A�u�킽���v�Ƃ����u���݁v�����������Ƃł������̂ł��傤�B
�@�������A���̋Ɍ��ɂ������f�J���g�����o�������̂��A�u�킽���v�́u���݁v�A�u���݁v�����u�킽���v�ł������̂��ǂ����́A�Ȃ���l�̗]�n������Ǝv����̂ł��B
�@�����l���Ă݂�ƁA�Ɍ��́g���i�h����Ŏ悳�ꂤ��e�[�[�́A�f�J���g�̌����悤�ȁF�u���v���A�䂦�ɂ�ꂠ��v�\�\�����ł͂Ȃ��悤�ɂ��v���Ă��܂��B������A�킽�������ɒ莮������F
�u�Ȃɂ����^���Ă���B�䂦�ɁA�Ȃɂ��͑��݂���B�v
�@���邢�́A
�u�Ȃɂ����^�����݂���B�v
�@�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B
�@�܂�A�u���݂���v�Ƃ������Ƃ��A��������Ƃ���A����́A�����u�^���Ă���v�u�ǂ��܂ł��^���Â���v�Ƃ������ƈȊO�ɂ͂��肦�Ȃ��悤�Ɏv����̂ł��B
�u�Ȃɂ��͑��݂���B�v
�@�Ƃ����F���\�\���������N���F������H�\�\�́A�u�u�킽���v�͑��݂���v�ȏ�ɏd�v�Ȃ��Ƃ��ƁA���ɂ͎v����̂ł��B�Ƃ����̂́A���ꂪ���ɂ̏o���_�ƂȂ��āA���傤�ǃr�b�O�E�o���ɂ���ĉF�������������悤�ɁA���̐��E�̂��ׂĂ��A�\�\�\�������A�V���ȁg�^���h�̑����̂��ƂɁ\�\�\�������̂܂��ɐ������Ă���Ǝv���邩��ł��B
�u�_�݂̂��k�M�g�����\�\�\�����́l���̂ł���Ƃ������Ƃ́A�k�c�l���̐��E�����R�̌����Ȃ�w��Ȃ���l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B���̐��E�̊O�ɍl��������̂́A���z�I�Ȑ_�ł��낤�ƁA�ފ݂ł��낤�ƁA���E�̈Ӗ���ړI�ł��낤�ƁA�\�ہi�z�����j�ł����Ȃ��B�����́A���̎��R�����E�Ɍ����������A��������h���������̂ł���B�k�c�l
�@�����́A���̐��E�����R���̂��̂̌�����₤���Ƃ͂ł��Ȃ��B�k�c�l���̂悤�Ȗ₢���̂��̂����̐��E�Ɍ����������̂ł��邩��B����ꂪ�����i�f�J���g�̂悤�Ɂj�^���Ƃ�����A���̂��Ƃ����̐��E�Ɍ���������B�v
���J�s�l�w�T���U�x,1994,�u�k�Њw�p����,pp.169-170.
�@�f�J���g���u�^���v�̎��s�ɑ��āA�f�J���g�̎v�z�����O�ꂵ���Ƃ������X�s�m�U�̌��n����ᔻ����ƁA�����̂悤�ɂȂ�ł��傤�B
�@�f�J���g���A�u�킽���v���g�s�ҁh�Ƃ��đz�肵�A�ǂ��܂ł��u�킽���v�̍s�ׂƌ��Ȃ����u�^�����Ɓv�u�^�����݂���v�����F����́A�X�s�m�U�̌��n���炷��A�������āu�킽���v�̎��R�ӎu�ɂ��s�ׂł͂Ȃ��A�u���̐��E�Ɍ���������v�K�R�I���ʂȂ̂ł��B�u�킽���v�͎���̈ӎu�Łu�l���v�Ă���̂ł͂Ȃ��A�u�킽���v�́u�l���v�́A���́u���E�v�̈��ʘA���̂Ȃ��ɂ���B���Ȃ킿�A���̐��E���u�킽���v�����čl���Ă���i�f�����P���j���Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B
�u�����̂��Ƃ���킽���́A���̂��Ƃ�m�����B�킽���͈�������ł���A���̖{���Ȃ����{���͍l����Ƃ������Ƃɂ��������āA���݂��邽�߂ɂǂ�ȏꏊ���v�����A�����Ȃ镨���I�Ȃ��̂ɂ��ˑ����Ȃ��A�ƁB���������āA���̂킽���A���Ȃ킿�A�킽�������܁A���݂�����̂ɂ��Ă������́A�g�́k���́l����܂�������ʂ���A�������g�́k���́l���F�����₷���A���Ƃ��g�́k���́l�����������Ƃ��Ă��A���S�ɂ��܂���܂܂̂��̂ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��A�ƁB�v
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,p.47.
�@�������f�J���g�́A�g�l�Ԃ����_�i�썰�j�������ł͂Ȃ��h�Ƃ������m�̃e�[�[�\�\�\���������g���S�_�h����b�Â�����\�\�\���A�����Ă���̂ł����A��L���u���v���A�䂦�ɁA��ꂠ��v��F�߂�A���R�̋A���ł���悤�ɂ������܂��B�������A�f�J���g�����ɂɌ��o�����u�^���ҁv�́A������u�����v���Ɩ������ɒf��ł���قNJm���Ȃ��̂ł͂Ȃ������͂��ł��B�ނ���A���������u�Ȃɂ��́v�Ȃ̂����肵�������قǁE�����܂��ŁA���݂ǂ���̂Ȃ����̂ł������͂��ł��B���̂��Ƃ́A���łɌ����Ƃ���ł��B
�@�f�J���g�́A���́E���݂ǂ���̂Ȃ��u�Ȃɂ��̂��v���A�u�����v�ł���Ƃ��A�u�킽���v�ł���Ƃ��������ŁA����
�u�{���Ȃ����{���͍l����Ƃ������Ƃɂ��������āA���݂��邽�߂ɂǂ�ȏꏊ���v�����A�����Ȃ镨���I�Ȃ��̂ɂ��ˑ����Ȃ��v
�@�̂��ƌ����܂��B�������A���̂悤���u�����v�u�킽���v�̃C���[�W�ɂ́A�ނ���䩔��Ƃ����u�Ȃɂ��̂��v�̂����܂���(ambiguity)�������g���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�g�v�l�����h�̋ɖk���f�J���g�����o�����u�킽���v�Ƃ́A���̂悤�Ȃ��̂ł����B�͂����Ă���́A����l�Ԃ��u���_�v�Ȃ����u���v�Ƃ����悤�Ȃ��̂ł��肦���̂ł��傤���H ���́A���̓_�ɑ傫�ȋ^���������������܂���B

�@�Ƃ���ŁA�l�Ԃ��u���_�v�i�Ȃ����u���v�j�́A�u�g�́k���́l����܂�������ʂ���v���u��̎��̂ł��v���āA�u���̖{���c�c�͍l����Ƃ������Ƃɂ��������āA���݂��邽�߂ɂǂ�ȏꏊ���v�����A�����Ȃ镨���I�Ȃ��̂ɂ��ˑ����Ȃ��A�c�c���������āA�A�c�c���Ƃ��g�́k���́l�����������Ƃ��Ă��A���S�ɂ��܂���܂܂̂��̂ł���v�Ƃ����f�J���g�̐l�Ԋρ\�\�Â߂Č����A�g�u���_�v�́u�g�́v�Ɉˑ����Ȃ��h�\�\�\�́A�͂����āA�u���v���A�䂦�ɁA��ꂠ��v����_���K�R�I�ɓ�����Ă���̂ł��傤���H �f�J���g�̕��͂�ǂނƁA���̂悤�ɂ������܂��B
�@�������A���̐l�ԊςȂ����u���_�v�ς́A�g�v�l�����h���s�Ȃ��ȑO���f�J���g�������ɉۂ��Ă����b��I�u�����v�\�\�u�R�̊i���v�i�O���y�S�z�Q�Ɓj�\�\�\�Ɏ��Ă��Ȃ��ł��傤���H
�@�u�R�̊i���v�Ƃ́A
�@�u��P�̊i���v�F�u�킽���̍��̖@���Ɗ��K�ɏ]�v���A�u�ł��ǎ�����l�тƁv�́u�ł������Ȉӌ��v�ɂ��������āu�������Ă����v���ƁB
�@�u��Q�̊i���v�F�u�ǂ�Ȃɋ^�킵���ӌ��ł��A��x����Ɍ��߂��ȏ�́A�c�c��т��ď]�����Ɓv�B
�@�u��R�̊i���v�F�u�����ɑł����v���āu�����̗~�]��ς���v�悤�ɓw�߂邱�ƁB
�@���Ȃ킿�A�����͂�������A�u�킽���v���������ӎu�i���_�j�ɂ���āA�����̍s���Ɓu�~�]�v�𐧌䂵�čs�����Ƃ��O��ƂȂ�܂��B�Ƃ��ɁA�u��Q�E��R�̊i���v�����s����ɂ́A�u���_�v���ӎu���肵�������ց\�\�\���ꂪ�ǂ�ȕ����ł���A�u�g�́v�̝y�I���邱�ƂȂ��\�\�\���R���u�g�́v�����������邱�Ƃ��ł��Ȃ���Ȃ�܂���B
�@����́A�g�u���_�v�́u�g�́v�Ɉˑ����Ȃ��h�Ƃ����l�Ԋς�O��Ƃ�����̂ł��B
�@�������Ƃ���ƁA�f�J���g�́A�g�Â��s�s�̎c�肩���́A�Ō�̈�Ђ܂ł����S�ɏ��������h�Ȃǂƌ����Ȃ���A���͂�������ƁA�Â������̔p�ނ��^�э���ŁA�V���������̊�b�Ƃ��Ďg���Ă���\�\�\��������Ȃ���Ȃ�܂���B�������ɁA����͂�����ƈӒn�����E��������������������܂���B�������A���ɂ́A�ǂ����Ă����������������c��̂ł��B
�@�y�U�z�_�̑��݂��ؖ�����B�i��S���E�㔼�j
�u���̌�킽���́A��ʓI�Ɉ�̖��肪�^�Ŋm���ł��邽�߂ɂ͉����K�v���l���Ă݂��B�k�c�l�����āA�w�킽���͍l����A�䂦�ɂ킽���͑��݂���x�Ƃ������̖���ɂ����āA�킽�����^��������Ă���ƕۏ�����̂́A�l���邽�߂ɂ͑��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��A�킽��������߂Ė����ɂ킩���Ă���Ƃ����ȊO�ɂ܂����������Ȃ����Ƃ�F�߂��̂ŁA���̂悤�ɔ��f�����B
�@�킽������������߂Ė����������ɑ����邱�Ƃ͂��ׂ��^�ł���A�������ʓI�ȋK���Ƃ��Ă悢�A�������A�킽�������������ɁE��������̂�������������߂�̂ɂ́A�����炩�̍������A�ƁB�v
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,pp.47-48.
�@��Ғ��ɂ��Ɓip.117 (8)�j�A�Ō�́u�킽�������������ɁE��������̂�������������߂�̂ɂ́A�����炩�̍������v�Ƃ́A���Ƃ��u�����v�ł����Ă��A������u�����v�ɑ����悤�Ƃ���ƍ���̐�����ꍇ������A�Ƃ����Ӗ��ł��B
�@���Ƃ��A�g�̂̒ɂ݂̊��o�\�\�\�u�ɂ��v�Ƃ����m�o�́A����ȏ�͂Ȃ��قǁu�����v�ɁA�܂�n�b�L���Ƒ������܂��B�������A�ǂ����ɂ��̂��A�݂̂����肩�A���̂����肩�A����Ƃ��w���̋ؓ��ɂȂ̂��A�Ƃ��������Ƃ��͂����肵�Ȃ��ꍇ������܂��B�܂�A�u�ɂ݁v�����邱�Ƃ́u�����v�����A���ꂪ�u���v�Ȃ̂��́u�����v�Ɍ��킯���Ȃ��ꍇ�ł��B
�@����́A�����قǖ��ɂ������̋^��F�u�^���āv����̂͒N�Ȃ̂��H �ق�Ƃ����u�킽���v�Ȃ̂��H �u�킽���v���Ƃ�����A�����u�킽���v�Ƃ͉��҂��H �d�d�Ƃ����g���킯�h�̍���ɑΉ�����ł��傤�B
�@�Ƃ���ŁA�O������J��Ԃ����x����������Ă���̂ł����A�����ł��A�f�J���g�̌����_���K���u�킽���������A�����������������邱�Ƃ́A���ׂ��^�ł���v�ɂ́A�܂₩��������悤�Ɏv���܂��B
�@�O���y�P�z�Ō����u��Q���v�ł́A���́u�_���K���v�́A�����̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�u��P�́A�킽�������ؓI�ɐ^�ł���ƔF�߂�̂łȂ���A�ǂ�Ȃ��Ƃ��^�Ƃ��Ď���Ȃ����Ƃ������B����������A���ӂԂ������f�ƕΌ�������邱�ƁA�����ċ^���������͂��ޗ]�n�̂܂������Ȃ��ق����������������_�Ɍ������̈ȊO�́A�����킽���̔��f�̂Ȃ��Ɋ܂߂Ȃ����ƁB�v
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,p.28.
�@������Â߂Č����A
�@���邱�Ƃ��炪�A���������������_�Ɍ����̂łȂ���A������^�ł͂Ȃ��B
�@����Ƃ�F
�@���邱�Ƃ��炪�^�ł��邽�߂ɂ́A����́A���������������_�Ɍ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���邢�́A
�@���邱�Ƃ��炪�^�ł���Ȃ�A����͕K���A���������������_�Ɍ����B
�@�ƒ莮�����邱�Ƃ��ł��܂��B���Ȃ킿�A�u���������������_�Ɍ����v���Ƃ́@���ꂪ�^�ł��邽�߂��K�v�����ł��B
 �@
�@
�@�Ƃ��낪�A���́u��S���v�ł́A
�u�킽���������A�����������������邱�Ƃ́A���ׂ��^�ł���v
�@�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��Ă��āA�u�����������������v���邱�Ƃ́@���ꂪ�^�ł��邽�߂��\���������Ƃ���Ă���̂ł��B
�@�K�v�������A�\�������i�Ȃ����K�v�\�������j�ɂ���ւ���Ă���I�I�I
�@
�@�����Ƃ��A���̎��̒i���ȉ���ǂނƁA�f�J���g�́A���ꂪ�Ȃ��\�������ł��肤��̂���_���Ă���悤�Ɍ����܂��B�u���_�v�Ƃ��Ă��u�킽���v�̑��݂Ƃ�����ꌴ������A�u�_�̑��݁v�Ƃ����e�[�[���o���A��������A����́g���ؐ��̒藝�i�K�v�\�������j�h���ؖ����Ă��邩�̂悤�Ȃ̂ł��B�����炭�A�f�J���g�Ƃ��ẮA�\���ɘ_��������Ȃ̂ł��傤�B������A���Ɍ��Ă��������Ǝv���܂��B
�u�����Ă킽���́A�킽�����^���Ă��邱�ƁA���������Ă킽���̑��݂͂܂��������S�ł͂Ȃ������k�c�l�ɔ��Ȃ������A�����������S�ł��鉽�����l���邱�Ƃ��킽���͂��������ǂ�����w�̂���T�����悤�Ǝv�����B�����Ă���́A�����ɂ킽����芮�S�Ȃ���{������w�ɂ������Ȃ��A�Ɩ��ؓI�ɒm�����B�k�c�l�킽���̑��݂������S�ȑ��݂̊ϔO�ɂ��ẮA�k�c�l���̊ϔO���A�킽�������^�Ɋ��S�Ȃ���{���ɂ���Ă킽���̂Ȃ��ɒu���ꂽ�A�v�ƍl����ق��Ȃ������B�u���̖{���͂������A�킽�����l�����邠���銮�S�������ꎩ�̂̂����ɋ�Ă���A�܂�ꌾ�ł����ΐ_�ł���{�����B
�@����ɉ����āA�킽���͎��̂悤�ɍl�����B�킽���́A�����̎����Ȃ��������̊��S����F�����Ă���̂�����A�킽���́A��������B��̑��ݎ҂ł͂Ȃ����k�c�l�A���̂����������S�ȑ��ݎ҂��K���Ȃ���Ȃ炸�A�킽���͂���Ɉˑ����A�킽���������ׂĂ̂��̂͂������瓾���͂����A�ƁB�v
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,pp.48-49.
�@�u���v���A�䂦�ɂ�ꂠ��v�Ƃ��������ł́A��b�Â����Ă���̂��u�킽���v�̑��݂����ł��B��������A���́u���E�v��A���̐l�X�̑��݂��������̂́A�ǂ̂悤�ɂ��ĂȂ̂��H
�@�f�J���g�͂܂��A�u�킽���v�̑��݂���A�u�_�v�̑��݂��A�����܂��B�u�킽���v�́u�^���Ă���v�̂�����A�u�킽���v�̑��݂͊��S�ł͂Ȃ��B�\�\�\����́A�����قǎ����f�J���g�Ɍ������^��F���ׂĂ��^���u�킽���v�́A�������g�̑��݂����u�^�v��Ȃ��ł͂����Ȃ��͂��d�d�ɑΉ����܂��B�f�J���g���A�����������悤�ȋ^����A�����Ă͂���̂ł��B
�@�Ƃ��낪�A�u�킽���v�̑��݂͊��S�ł͂Ȃ��ɂ�������炸�A�u�킽���v�͊��S�ȔF���������Ƃ����肤��i���肦�Ȃ��Ƃ�����A���������^���̔F���͕s�\�ł��j�B�s���S�Ȏ҂��A�Ȃ��A�����������S�Ȃ��̂̊ϔO����������̂��H �c�c�u�킽���v�ȊO�ɁA�u�킽���v�������S�ȉ��҂������݂��āA���̉��҂����A�u�킽���v�̒��Ɋ��S�ȊϔO���u�u�����v�\�\�\�����l����ق��Ȃ��ł͂Ȃ����B���́g���҂��h���A�u�_�v�ł���B
�u�킽������ɋK���Ƃ��Ē�߂����ƁA���Ȃ킿�A����ꂪ����߂��������������������邱�Ƃ͂��ׂ��^�ł���Ƃ������Ǝ��́A���̗��R�ɂ���Ă͂��߂Ċm���ƂȂ��k�c�l�B�_������A���݂��邱�ƁA�_�����S�ȑ��ݎ҂ł��邱�ƁA�����̂����ɂ��邷�ׂĂ͐_�ɗR�����邱�ƁB���̌��ʂƂ��āA�����̊ϔO��T�O�́A�����������ł��邷�ׂĂɂ����āA���݂ł���A�_�ɗR��������̂ł���A���̓_�ɂ����āA�^�ł������肦�Ȃ����ƂɂȂ�B�k�c�l�����̂����ɂ����āA���݂ł����^�ł��邷�ׂĂ̂��̂����S�Ŗ����ȑ��ݎ҂ɗR�����邱�Ƃ��A�����m��Ȃ�������A�����̊ϔO���ǂ�Ȃ������Ŕ����ł����Ă��A�����̊ϔO���^�ł���Ƃ������S���������Ă��邱�Ƃ�ۏ��邢���Ȃ闝�R���A�����ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�@�k�c�l�����̖��ؐ��ɂ��ȊO�A�������Ă��̂��Ƃ�M���Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�k�c�l���Ƃ��A�����͎��ɖ����ɑ��z�����邯��ǁA������Ƃ����đ��z�����Ă���Ƃ���̑傫���ł���Ɣ��f���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂������́A�����Ƀ��C�I���̓������M�̓��̂ɐڂ����킹�����̂�z���ł��邪�A������Ƃ����Ă��̐��ɃL�}�C���Ƃ�������������ƌ��_���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ����̂��A�����́A����ꂪ���̂悤�Ɍ�����z�������肷����̂��^�ł���Ƃ́A�������ċ����Ă��Ȃ�����ł���B
�@�����������́A�����̂��ׂĂ̊ϔO�܂��͊T�O�́A�����^���̊�b�������Ă���͂����Ƌ�����B�܂��������S�ł܂������^�ł���_���A�^���̊�b�Ȃ��ɂ����������̂����ɔz�������Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ�����ł���B�v
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,pp.54-56.
�@�Ō�̕������f�J���g�́A�u��������������������v�Ƃ́A���o��z���͂ɂ���Ăł͂Ȃ��A�����ɂ���đ�������u�ϔO�܂��͊T�O�v�̏ꍇ�łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ��Ă��܂��B�u�����ɂ���āv�Ƃ����g���ڂ�h�����������Ƃɂ���āA�g�^���ł��邱�Ɓh���K�v�\�������Ƃ��āA���܂܂ł��͖{���炵���Ȃ��Ă��܂����B

Hippolyte Moulin
�@�������A����ɂ��Ă��A�ȏ�́g�_�h�ɂ͋^�₪����܂��B�ׂ������Ƃ͂����Ă��A�S�̂Ƃ��Ę_�������X�����ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@���@�u�킽���v�������́A���S�ȑ��݂ł���_���^�������̂ł���B�@���@�䂦�ɁA�u�킽���v�͊��S�ȗ���́i�����j�������Ă���B�@���@���������āA�u�킽���v�������������������������������̂́A���ׂ��^�ł���@���@�Ƃ��낪�A�u�킽���v���g�͕s���S�ȑ��݂ł���B�s���S�ȑ��݂ł���u�킽���v�����S�ȊϔO�������Ƃ��ł���̂́A���S�ȑ��݂ł���_�����݂��āA������u�킽���v�ɗ^��������ł���B�@���@�u�킽���v�������́A���S�ȑ��݂ł���_���^�������̂ł���B�@���@�䂦�ɁA�c�c
�@�Ƃ������X�����ɂȂ��Ă��܂��āA���ǁA�u�����������������������̂��^�v�Ƃ��K�v�\�������̒藝���A�g�_�̑��ݏؖ��h���A�_�̊��S�����A�����̊��S�����A�ǂ����������ЂƂ_����Ă��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�@�����Ƃ��A���́g�_�h�ߒ��̓r���ɂ͂��܂ꂽ�����̕����́A�w�Ƃ�������Ɍ����Ăł����A�܂��Ƃ��Ș_�ƂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�u�킽���͊w�҂����̂����Ƃ��P���ȏؖ��̂������ɖڂ�ʂ��Ă݂��B�����āA���ׂĂ̐l�������̏ؖ��ɋA���邠�̑傫�Ȋm�����́A�킽������ɏq�ׂ��K���ɏ]���Ė��ؓI�ɂƂ炦����Ƃ������Ƃɂ�����Â��Ă���̂ɋC�����A�܂��A�����̏ؖ��̂Ȃ��ɂ́A���̑Ώۂ̑��݂��킽���ɕۏ�����͉̂����Ȃ����ƂɋC�������B�v
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,p.51.
�@���Ƃ��A�u�O�p�`�̓��p�̘a�� 180���ł���v�Ƃ����藝�́A���������ɎO�p�`�������Ċp�x�𑪂��Ă݂�Ƃ����g�����h�ɂ���ďؖ�����̂ł͂Ȃ��A�\�\�\��������A�������Đ��m�� 180���ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B�\�\�\�A���_���u���������������������v���ۂ��A�Ƃ������Ƃ����ɂ���āA�u�^�v���ǂ��������f����Ă���̂ł��B���̏ꍇ�A�������ɁA�u���������������������v���Ƃ́A�u�^�v�ł��邱�Ƃ��K�v�\�������ł��B
�@�������A����͂����܂ł��g���_�h�̐�������ۏ�������ɂ����܂���B���_�̐������́A�O��̐������A�d���ɓI�ɂ́u�����v�̐������\�\�u�����v������邩�ǂ����\�\�Ɉˑ����Ă��܂��B�����āA�f�J���g���u���v���A�䂦�ɂ�ꂠ��v�́A���ꂾ���ł́u�����v�Ƃ��Ă��܂�ɂ��s�\���ł��傤�B�i���Ƃ��A�X�s�m�U�w�G�`�J�x�́A�u��P�� �_�ɂ��āv�����ŁA�W���ڂ̒�`�ƂV���ڂ̌����𗧂ĂĂ��܂��B�j
�@���āA���̂ւ�ŁA����܂Ő܂�ɂӂ�ďq�ׂĂ������̍l�����A�f�J���g�̎咣�Ƃ͕ʂɁA�܂Ƃ߂Ă����̂��悢�ł��傤�B�����̎��I�ȋ^�`�ɁA�߂��z���Ă܂ł���������͂Ȃ��̂ŁB�����ł܂��A�g������h�Ƃ��đI���J�s�l���̘_�l����f�Ђ����p���āA�肪����ɂ������Ǝv���܂��B
�u�X�s�m�U�͂����l�����Ƃ����Ă����B����ꂪ������̂�\���k�z���A���f�\�\�\�M�g�����l�ł͂Ȃ����Ƌ^���A���́w�������x���𖾂��悤�Ƃ���ӎu�́A���ꎩ�̂��̎��R�j�ɂ���đ�����Ă���A�����Ɍ��������̂��A�ƁB�R�M�g�́A���R�z����ǂ��납���̎��R�j�̏������̌��ʂł���B�v
���J�s�l�w�T���U�x,1994,�u�k�Њw�p����,p.187.
�@�u�w�������x���𖾂��悤�Ƃ���ӎu�v�Ƃ́A�f�J���g�̏ꍇ�ł����ƁA�u���@�v�ɂ�����^�U���ᖡ���u�^���v���Ɓ\�\�ɑΉ����܂��B�u���R�j�v�́A���́u���E�v�Ƃ������Ƃł��B�����A�����ɁA�f�J���g�̏ꍇ�Ƃ͈قȂ��āA���́u���E�v�͈�����̗��j�I���E�ł��邱�Ƃ��܈ӂ���Ă��܂��B�u�R�M�g�v�́A�u���v���v�̂���(���e����)�B
�@����܂ʼn��x����������Ă����f�J���g��
�u�킽���������A�����������������邱�Ƃ́A���ׂ��^�ł���v
�@�Ƃ����e�[�[�́A�u�^���v�Â���Ƃ����T���̎p���ɍ���������܂��B�u�����̊w��v���A���ɂ��g���ɂ���ĈقȂ�M�O�E���K���A���R���E���A�������g�������A���ׂĂ��u�^���v���炱���A�u���ؐ��v�����߁A�u���������������������邩�ǂ����v���ᖡ����̂ł��傤�B�u�^���v�́A�u�^���v�����߂邩�炱���u�^���v�̂ł����A�t�ɁA�u�^���v���炱���u�^���v�����݂���A�u�^���v�Ƃ́A�u�^���v���Ƃɂ���Đ��ݏo����鉽���̂��ł���A�Ƃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����āA���̂悤���u�^���v�́A���́u���E�v�\�\�\�u���R�j�v�I�ߒ��\�\�\���̂��̂ɓ������Ă��܂��B�f�J���g���u�^���v�����߂��u�^�v�������Ƃ��A�u���E�v���̂��̂������u�^���v�����́A�ЂƂ̌���ł������A�ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���ׂĂ��^�������g�v�l�����h�̉ʂĂɁA�f�J���g���������̂́A���������^����������ꂽ���Ƃ̋���ɖ苿���A���́u���E�v���̂��̂��u�^���v�̐��������A�ƍl���邱�Ƃ��ł���ł��傤�B
�@���́u���E�v�̉ʂĂ��Ȃ��u�^���v�́A�u���E�v���g�Ɍ������Ă��܂��B�f�J���g�́g�v�l�����h���A�f�J���g���z���Đ�܂Ő����i�߂�A�u�^���v�́A�u�킽���v���g�ɂ܂ŋy�Ȃ��ł͂��Ȃ����ƂƁA����͑Ή����܂��B�������A�u���E�v�́u���E�v���g�ɑ����u�^���v�Ƃ́A�s���Ȍ��y�t�ł���A�s���Ȗ����t�ɁA�d���Ȃ킿�p���h�b�N�X�Ɉ������܂��B
�@�N���^�l�݂͂ȉR�����ƁA����N���^�l���������B���̌��́A�^���U���H
�@�Ƃ����u�N���^���̃p���h�b�N�X�v�Ɠ����ł��B
�@�킽�����^���Ă���Ƃ������Ƃ́A�͂����Đ^�Ȃ̂��낤���H �킽���́A���Ȃ��Ƃ��u�킽�����^���Ă��邱�Ɓv���^���Ă���B���������āA�킽�����^���Ă��邱�ƁA�͐^�ł���B�������A�u�킽�����^���Ă��邱�Ɓv�́A�^���Ă���킽�����g�ɂƂ��Ă����^�킵���̂�����A�U�ł���B���������āA�킽���͋^���Ă��Ȃ��B�Ƃ��낪�A�킽���́A�u�킽�����^���Ă��邱�Ɓv���^���A�ے肵���B���������āA���͋^���Ă���B�������A�c�c
�@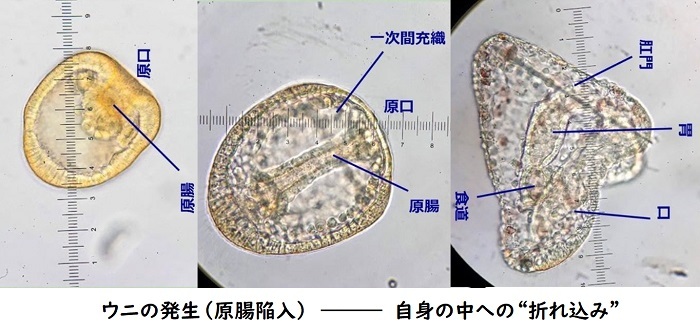
�@�� WEB247�ihttp://blog.livedoor.jp/web247/archives/53378518.html�j
�@�����炭�A�f�J���g�́A���̋��낵���p���h�b�N�X�́g㩁h�ɂ͂܂邱�Ƃ�����āA�u�^���킽���v�ɂ܂ʼn��^���y�ڂ����Ƃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�������A20���I�̘_���w�Ɛ��w��b�_�́A������_���̌n�ɂ����āA�g�������̂ق���сh���������Ȃ����Ƃ������Ă��܂��B�J���g�\���̃p���h�b�N�X�A���b�Z���̃p���h�b�N�X�A�Q�[�f���̕s���S���藝�A�d�݂Ȃ��̗�ł��B�g�ق���сh�́A�s���Ȍ��y�t�Ɗւ���Č���܂��B
�@�u�^���v�����߂��u�^�����Ɓv�́A�u���E�v�̎��Ȏ��g�ɑ����u�^���v�Ƃ����A�u���E�v���̂��̂̎������̌���ɂق��Ȃ�܂��A�����u�^���v�̒n�_�ɂ����āA�u���E�v�͎��Ȏ��g�̓������g�܂ꍞ�ށh�B�s���Ȍ��y�t�ɂ���s���Ȗ����t�������āA�����ɁA䩔��Ƃ������R�ȁu���E�v�̂����Ȃ��ɁA�g�܂ꍞ�h�s���ٓ_�t�������܂��B�g�܂荞�h�܂ꂽ�s���ٓ_�t�̒��ŁA�s���Ȗ����t�����y���A�₪�Ă���͉�Ԃ��A�u�^���v�̑̌n����������̂ł��B�u�^���̌n�v�́A�u�^���v��{���ɂ��Đ������܂��B
�@�������āA�F���Ƃ́A�g�܂荞�h�܂ꂽ�s���ٓ_�t���Ƃɐ������������u�^���̌n�v����Ȃ�g�^���̐X�h�ɂق��Ȃ�܂���B����s�\�Ȗ��������u�^���̌n�v�����݂��܂��B�i���J�s�l�w�T���U�x,pp.346-349.�Q�ƁB���J���̂����u�����́v���A�����ł����u�^���̌n�v�ɑ������܂��j
�@�y�V�z���R�w�̑̌n�I�\�z�i��T���j
�@�O�߂ł́A�f�J���g�������Ȃ�������Ă��܂��܂������A������Ƃ����āA���́g�ߑ�N�w�̑c�h�ɑ��Ĉ،h��Ȃ��킯�ł͂���܂���B�o���_�̂������Ƃ̕����̘_�ɂ͖�肪�����Ă��A��������̌n�I�ɓW�J����Ă䂭�\�z���̑s�傳�͊���݂͂����ł��B�ނ���A�_���I�ȕs������c�݂́A���҂̍\�z�̊m�������������̂Ƃ����Ă悢���炢�ł��B
�@�l���w�́A���w�╨���Ƃ͂������āA�_�������������ׂĂł͂Ȃ��̂ł��B�}�b�N�X�E�E�F�[�o�[�́w�v���e�X�^���e�B�Y���̗ϗ��Ǝ��{��`�̐��_�x�ɂ��Ă��A�}���N�X�́w���{�_�x�ɂ��Ă��A���������Ƃ̃e�[�[��_���镔���́A�͂����茾���ĉ��������̂ł��i�E�F�[�o�[�ɂ��Ă��H���C�Y�w�}�b�N�X�E���F�[�o�[�̔ƍ߁x���Q�ƁB�������A�����̖{�Ɋւ���l�b�g���́A�E�B�L���ӂ��߂ĕs���m�ł��B�����œ��肵�ēǂ܂Ȃ��Ƃ��߂ł��B�w���{�_�x�́A��P���ɐ��`���w�́u�N���[�����̖@���v��K�p���Ă݂Ă��������j�B�������A�ނ�̍\�z�Ƒ̌n�̉��l�́A����ɂ���ď��������Ȃ��Ă͂��Ȃ��B
�@���āA�u��T���v�́A�K�����C�ٔ��������ŏo�ł�f�O�����w���E�_�x�̂����܂��ȓ��e���Љ�Ă��܂��B�u��S���v�ł́A�u�l���鐸�_�v�Ƃ��Ă��u�킽���v�̑��݁A�������u�_�v�̑��݂���������܂����B��������A���́u���E�v�S�̂́A�ǂ̂悤�ɂ��āg�č\�z�h�����̂ł��傤���H
�u�w�҂̂������Ŏ�����Ă��錩���Ɏ^�������蔽�����肵�Ȃ��ł��ނ悤�A�킽���͂��̌����E�͂�������w�҂����̘_�c�ɂ䂾�˂Ă��܂��A�������̂悤�ȐV�������E�ŋN����͂��̂��Ƃ�������낤�ƌ��S�����B
�@���ɐ_�����A�z����Ԃ̂ǂ����ɐV�������E���\������̂ɏ\���ȕ�����n�������Ƃ��A���̕����̂��܂��܂ȕ��������܂��܂ɖ������ɗh�蓮�����āA���l���z��������قǂ̍��ׂ���J�I�X�����肾�����Ƃ���B���̌�͂����A�ʏ�̋��͂��������R�ɗ^���A�_���g����߂��@���ɏ]���Ď��R�������ɂ܂������ꍇ�́A���̐V�������E�ł���B
�@�������Ă킽���͂܂��A�V�������E�̕����ɂ��ċL�q���A�k�c�l���ɂ킽���́A���R�̏��@�����������������B�k�c�l�����̖@���́A�_�������̐��E��n�������Ƃ��Ă��A���ꂪ����Ȃ��悤�Ȑ��E�͈�Ƃ��Ă��肦�Ȃ��悤�Ȗ@���ł��邱�Ƃ��������Ɠw�߂��B�v
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,pp.59-60.
�@�܂�A�f�J���g�́A�u�킽���v�ƂƂ��ɑ��݂��邱�ƂɂȂ����u�_�v�ɁA�V�n�n�����A���������ǂ�点�Ă݂�A�Ƃ����v�l����������킯�ł��B��������ƁA�u�_�v���A�V�������E���������낤�ƁA�����̐��E�݂͂ȁA���ɂ���E���̐��E�ƁA��������̂��̂ɂȂ�ƌ����̂ł��B
�@�u�_�v�́A�܂��V�����u���E�v�̍ޗ��ɂȂ镨����n�����A����������_���ɍ������Ė���`�ȃJ�I�X�������܂��B�������A�u�_�v����������̂́A�����܂łł��B���̂��Ƃ́A�u���R�̏��@���v�ɂ��������ăJ�I�X���̏��������^������������ɔC����̂ł��B
�@�w�����x�ɏ����Ă���悤�ȁg�V�n�n���h�Ƃ́A�����Ԃ������܂��B�K�X�_����]���āA�P���n���ł��������Ă䂭���܂�z������Ƃ悢��������܂���B
�u���̌�킽���́A���̃J�I�X�̕����̑啔�����A�����̖@���ɏ]���āA�ǂ̂悤�ɂ��Ĉ��̎d���ŕ��сA�A�Ȃ��āA�����̓V��Ɏ������̂ɂȂ�͂������������B���̊Ԃǂ̂悤�ɂ��Ă��̂��镔�����n�����A���镔�����f���Ɯa�����A�ق��̂��镔�������z�ƍP�����`������͂������������B�v
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,p.60.
�@�����ŁA�f�J���g�́A�u���v�̖{���ƁA���߁A���˂ɂ��ďڂ����q�ׁA�F����ԂƓV�̂̎��́A�ʒu�A�^���A�����ɂ��Đ��������B�����݂͂ȁA�s�ς̎��R�@���ɏ]���āA�u�V�������E�v�Ő�����͂��̂��̂ł��B
�u���������Ă킽���́A���̂��Ƃ�m���Ă��炤�̂ɏ\���ɏq�ׂ��Ǝv�����B����́A�����̂��邱�̌����E�̓V��ƓV�̂̂Ȃ��ɂ́A�킽�������܋L�q�������E�̓V��ƓV�̂̂Ȃ��ɂ悭�����`�Ō���Ă��Ȃ����́A���Ȃ��Ƃ����ꂦ�Ȃ����Ȃ����̂́A�����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B�v
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,p.61.
�@���́u�V��v�Ɓu�V�́v�Ɋւ��镔���́A�w���E�_�x�ł́A�s�n�����t�ŏq�ׂ��Ă����悤�ł��B�w���@�����x�� 7�N��Ɍ��������w�N�w�����x�̓��e���Ƃقړ����ł��傤�B
�u�Ȋw�I�ȑ��z�n�N���_�̍ŏ��̒҂Ƃ��čl������̂́A�t�����X�̓N�w�҂ł��郋�l�E�f�J���g�ł���B�ނ� 1644�N�ɁA���̂悤�ȑ��z�n�N����������B�k�w�N�w�����x1644�N�o�Ł\�\�\�M�g�����l
�@�F���̓G�[�e���Ƃ��������Ŗ�������Ă���B�G�[�e���̒��ɕ���ł��镨���ɂ́A���̌��f�A�����Ȍ��f�A���˂���Â��ĕs�����Ȍ��f�̂R��ނ̌��f���������B�͂��߂͂����̌��f���F���ɋϓ��ɑ��݂��Ă������A�G�[�e���̉^���ɂ���ĉQ���i�Q���j�������A���̒��S�Ɍ��̌��f���W�߂��đ��z�����������B���̉��ɓ����Ȍ��f�ƕs�����Ȍ��f����]����悤�ɂȂ�A�s�����Ȍ��f����f����a�������������B�v
�@�u�Ȋw�I�ȑ��z�n�N���_�̍ŏ��̒v�ł����������ɁA���łɁA���ݒ���Ƃ���Ă���s���_���t�ɂ�鑾�z�n�a�����q�ׂĂ����̂ł�����A�f�J���g�̌d��ɂ́A�܂���������ӂ�ق��͂���܂���B
�@���n���_�́u�Q�����v�^���ɂ���āA�u���S�Ɍ��̌��f���W�߂��đ��z�����������B�v�\�\�\�܂�A���z�����S�ɂ����āA���̎����n���Ə��f�������]�^�����Ă���s�n�����t�̉F���ł��B�������A�Ȃ����z�����S�ɂȂ���Ȃ�Ȃ��̂����A�����@���ɂ���Đ�������Ă��܂��i�u���̌��f�v�͌y������Q�̒��S�ɏW�܂�A�Ƃ����f�J���g�̐������������̂��ǂ����́A���ɂ͂킩��܂��j�B
�@�u�J�I�X�v����A���R�@���ɂ����]���āA�V�������E���a��������A�����Ȃ�͂��d�d�Ƃ����z����q�ׂ邱�Ƃɂ���āA�����̎��R�E���A�����͂����A�Ɛ��������f�J���g�́u���@�v�́A���������̂ł��B����ł́A�@�����ْ̈[�R�⊯���A���_�ł��Ȃ��ł��傤�B�i�����Ƃ��A����قNj�����A�f�J���g���g�A�w���E�_�x�̏o�ł͌��������̂ł�����ǂ��j
�@�f�J���g�́A�R�y���j�N�X�����A�K�����C�����A�P�����Q�����������Ă���ƌ����܂��B�R�y���j�N�X���́A����ɁA�ϑ����ʂ̐����Ƃ��āA�^�����Ă���̂͑��z�ł͂Ȃ��n�����Ƃ��������ŁA�F���̂����݁i�u�P���V�v�Ȃǁj�ɂ��ẮA�A���X�g�e���X�̂܂܂Ȃ̂ł��B�R�y���j�N�X���A�K�����C���A�g�Ȃ��h���z�͒��S�ɂ����āA�n���͎��Ă���̂��H�d�Ƃ����A�g�����h��₤�^��ɓ����邱�Ƃ͂ł��܂���B
�@���āA���̂����f�J���g�́A�n����̏����ۂɂ��Č��܂��B�u�d�́v���Ȃ������邩�A�����̊����A�G�ߕ��A�n�`�A�C�Ɖ͐�A�����z���̌`���A���܂��܂ȉ������ƐA���̐����B�Ƃ��Ɂu�̖{���v�ɂ��ďڂ����q�ׁA�u�D���K���X�ɕς��v���w�����ɒ��ڂ��āA���B���p�I�ȍl�@���q�ׂĂ���悤�ł��B
�@�f�J���g���u�̖{���v�ɊS���������̂́A���ꂪ�l�̂̐����������J�M���ƌ��Ă�������ł��B�S���̒��ł͂��炢�Ă���̂́A�u���Ȃ��̈��v�v���ƍl���Ă����̂ł��B�u���Ȃ��v�Ƃ́A�������╒�����̔��y���N���̂Ɠ������̂ł��B�����o���܂��A���X�ɔM�������܂��B�������āA�����̐l�тƂ��g�����́h�̍�p�A���邢�͐_�̗^�����u���o�I���v�̂͂��炫���ƍl���Ă������ۂ��A�����ɕ����I�Ȍ��ۂƂ��Đ������悤�Ƃ����̂ł��B
�@�������A�l�Ԃ̐g�̂��A�����ɕ����I�ɂ͂��炢�Ă���̂ł����āA�@�B�Ɠ����ł���B�l�Ԃ��u���_�v�\�\�u���܂����v�́A�����Ƃ͂܂������ʂɁA�g�̂���Ɨ����đ��݂���B���̂悤�ɁA�f�J���g�̎��R�w�E��w�́A�u���v���A�䂦�ɂ�ꂠ��v�̌`����w����̈�т����_���I�A���Ƃ��đ̌n������܂��B
�@�f�J���g�ɂƂ��ẮA�l�Ԃ̐g�̂́A�����Ɠ����悤���u�����@�B�v�ł��B�^���Ɗ��o�A�u�o���Ɛ����A���v�A�܊��̒m�o�Ɣ]���ł̑����A�u�Q���A�������̑��̓��I��O�v�݂͂ȁA�u�����@�B�v�̍�p�ł��B����ǂ��납�A�u�L���v��u�z���́v�����A�u�����@�B�v�̍�p�ɂ����܂���B�u�����@�B�v�łȂ��̂́A�u���_�v�̍�p�ł���u�����v�����ł��B
�@�������u�����@�B�v�Ȃ̂ł�����A�T���ł����ł��A�u�����̊튯�ƌ`������v���I���u�����@�B�v�邱�Ƃ��ł���A���������l�H�@�B�́A���̓����Ƃ܂�������ʂ����Ȃ��Ȃ�A���f�J���g�͏����Ă��܂��B
�����F�܂�A�f�J���g�̋��ɂ̍l���ɂ��A�u�L���v���u�z���v(���������ӂ��̒��ōl���Ă��邱�Ƃ̑啔���́A�f�J���g�̂����u�z���v�Ɋ܂܂�܂��j���A�g�̂̍�p�ɂ����Ȃ��̂ł��B���������āA�g�̂̎��ƂƂ��ɁA�����Ă������̋L���͂��ׂď��ł��܂��B�������N�������������v���o���Ȃ��Ȃ�B�������g�v���h�Ƃ����S���I�Ȃ͂��炫�������Ȃ�܂��B�������āA�g�̂̎����z���Đ����Â������������Ƃ́A�����������Ȃ̂ł��傤�H ���������҂ł��邩���m�炸�A�����Ȃ�S�����������A�g�̂䂷��\�͂�L���Ă͂��Ă��A���䂷�ׂ��g�̂́A���͂⑶�݂��Ȃ��B�d�d���̋��ɂ̍l���́A�f�J���g�̓N�w�Ƃ��Ēʏ헝������Ă����u�g�S�_�v�Ƃ́A�����낵���قȂ��Ă��܂��B�ނ���A�X�s�m�U���w�G�`�J�x�u��T���v�ŏq�ׂĂ����u�l�Ԑ��_�̉i�����v�i�ˁF�y�K�Ǐ�150�z�X�s�m�U�w�G�e�B�J�x(11)�y44�z�Q�Ɓj�ɋ߂��悤�Ɏv���܂��B�����āA���̓��e�́A�傫�ȓ�Ƃ��������悤���Ȃ��̂ł��B
 �@
�@
�@����ł́A������@�B�ƁA�u�����v�����Ȃ����l�ԂƂ́A�ǂ��ŋ�ʂ����̂ł��傤���H �f�J���g�́A�Q�̓_�������Ă��܂��B���̂ЂƂ́A�l�Ԃ��u���Ƃv���g�����Ƃł��B�������A����{�^���������ƁA�u������p�ł����H�v�ƌ����A�ʂ̃{�^���������ƁA�u�����e�i���X���ł��v�Ɠ�����悤�ȋ@�B�́A������ł����܂��B�l�ԂłȂ��Ǝg���Ȃ��u���Ƃv�́A�u�����̎v�l�𑼐l�ɕ\���v������A�u�b����邷�ׂĂ̂��Ƃ̈Ӗ��ɉ����ĕԓ��v������A�u�ЂƑ����̘b��g�ݗ��ĂĎ����̍l����`���v��悤�ȁA���G�ȁu���Ƃv�ł��B
�@��Q�̑���_�́A�@�B�́u�F�����邱�Ƃɂ���ē����̂ł͂Ȃ��A�������̏��튯�̔z�u�ɂ���ē��������ł���v�B�����́A�u�����̍s���ł͂����l�Ԉȏ�̍I�݂����������A�v�ق��̍s���ł́u�܂���������������Ȃ��v�B�l�Ԃ́u�������ǂ�Ȃ��Ƃɏo����Ă��𗧂����镁�ՓI�ȓ���ł���̂ɑ��āA�����̏��튯�͌X�̍s�ׂ̂��߂ɁA���ꂼ�ꉽ���ʓI�Ȕz�u��K�v�Ƃ���v�B�܂�A�@�B�́A���ꂼ�ꌈ�܂������Ƃ����ł��Ȃ��u�튯�v���A���̔z�u�ő����W�߂��Ă��邾���ŁA�����𑍍����ē������悤�ȁg�i�ߓ��h�\�\�u�����v���A���݂��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�@���������f�J���g�́A�l�Ԃ́u�����v���u�����̗͂��瓱���o����邱�Ƃ͂������Ă��肦���A�k�_�ɂ���āl���ʂɑn������˂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��܂��B
�@�Ƃ���ŁA�f�J���g�̂��������u�l�ԋ@�B�_�v�u�S�g�_�v�ɂ��āA���Ƃ��A���{�b�g�̓��̒��ɃR�b�N�s�b�g�������āA�����Ɂu�����v�Ƃ����g���тƁh�����đ��c���Ă���}�Ł\�\�J���J�`���A���C�Y���ā\�\��������邱�Ƃ��悭����܂��B�����g�A�X�s�m�U���������Ƃ��ɂ́A�ᔻ�Ώۂł����f�J���g�ɂ��āA�����������������Ă��܂����B
�@�������A���̂悤�ȗ������A�f�J���g���g�͕s���Ɏv���ł��傤�B�f�J���g���l���Ă���u�����v�i���܂����j�Ɛg�̂̊W�́A����ȒP���Ȃ��̂ł͂Ȃ��悤�ł��F
�u�����́A����ē��l���D�ɏ�肱��ł���悤�ɁA�g�̂ɏh���Ă��邾���ł͕s�\���ł����k�c�l�葫���������̂��߂Ȃ�\����������Ȃ����A����ȏ�ɂȂ��A�����̎��悤������Ɨ~���������A�������Đ^�̐l�Ԃ��\�����邽�߂ɂ́A�������g�̂ƌ������A���ٖ��Ɉ�̂ƂȂ�K�v�������v
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,pp.78-79.
�@�y�W�z�{�������̈Ӑ}�i��U���j
�@�����w���@�����x�́A�w�݂�����������𐳂��������A�������̊w��ɂ������^����T�����邽�߂̕��@�ɂ��Ă̏�������т��̕��@�̎��_�i���܌��w�E�C�ۊw�E�w�j�x�Ƃ��������薼�̒����̍ŏ��ɂ����ꂽ�u�����v�����Ȃ̂ł��B�u�{�_�v�ł́A�u���܌��w�E�C�ۊw�E�w�v�̂R�����_���Ă��܂��B
�@�����w�����x�u��U���v�ł́A1633�N�ɏ����グ���w���E�_�x�̏o�ł�f�O�������R�ƁA����ɑウ���w���@��������ѕ��@���_�x�������Ɍ������闝�R���A�������Ă��܂��B�Ƃ��ɁA�w���E�_�x�����\���Ȃ����R�ɂ��āA�f�J���g�́A���ɒ��X�Ɓg�_�h���Ă���̂ł��B���ꂱ���A�u��T���v�܂ł̓N�w�Ǝ��R�w�ɂ��܂���قǖȖ��ɁA���낢��ȗ��R�������āA�����̗����ٖ����Ă��܂��B
�@�������A�܂Ƃ߂Č����A�@�K�����C�ٔ��ŃR�y���j�N�X�����f�߂��ꂽ���ƁA���̂��߁A�A�o�ł���ƁA�_���ɂ܂����܂�邨���ꂪ���邪�A�����Ƃ��ẮA�_���̂��߂Ɏ��Ԃʂɂ������Ȃ��A�ނ��됶���Ă���c��̎��Ԃ́A�����ς猤���ɂ������������A�\�\�Ƃ������Ƃɂ��܂��B
�@�܂��A�w���@��������ѕ��@���_�x���������闝�R�ɂ��ẮA�u���܌��w�E�C�ۊw�E�w�v�̂R���삾���Ȃ�A�u�������Ę_���̎�ɂȂ�v�Ȃ�����Ȃ̂ŁA���\���Ă����c���������S�z���Ȃ��Ƃ������ƁB�����A���ꂳ�����܂��������\���Ȃ��ł���ƁA���Ԃ̐l�́A�f�J���g�͉����悩��ʎv�z������Ă���ɂ������Ȃ��ƁA�z���͂������܂������Ă��܂��B�������\���Ȃ��ƁA�������āA����ʋ^�����������Ă��܂��̂ŁA���̏�͂ނ���A�ꕔ�Ȃ�Ƃ����\�����ق��������A�Ɣ��f�����̂��A�ƌ����܂��B
�@�Ƃ���ŁA���̒����ٖ��̓r���ɁA�Ȋw�Ǝ����A�����Č��������\���邱�Ƃ̈Ӗ��ɂ��āA�f�J���g�̍l������莮�����ďq�ׂĂ��镔��������܂��B�������ɁA���������p���܂��傤�B
�u�Ƃ���ł킽���́A����قǂɏd�v�s���Ȋw���k�V���A���������w�A�����w�Ɏ���̌n�I���R�w�\�\�\�M�g�����l�̒T���ɑS���U�Ă悤�Ɗ�āA�킽���̌��������������A�l���̒Z���Ǝ����̕s���Ƃɂ���ĖW����ꂳ�����Ȃ���A���̓������ǂ��ĊԈႢ�Ȃ����̊w�₪���������͂����Ǝv��ꂽ�̂ŁA���̂Q�̏�Q�k�l���̒Z���Ǝ����̕s���\�\�M�g�����l�ɑ��Ď��̂��ƈȏ�ɂ悢��͂Ȃ��Ɣ��f�����B
�@����́A�����̔����������Ƃ��ǂ�Ȃɂ����₩�ł��A���ׂĂ𒉎��Ɍ��O�ɓ`���A�����ꂽ���_�̎����傪����ɐ�ɐi�ނ悤�ɑ������Ƃ��B���̍ہA�e�����v���������u�m�肦�����ׂĂ����O�ɓ`����̂ł���B��̎҂����B�����n�_�����̎҂��n�߁A�������đ����̐l�̐��U�ƋƐт����킹�āA�����S�̂ŁA�e�l���ʁX�ɂȂ���������͂邩�ɉ����܂Ői�ނ��Ƃ��ł���悤�ɂ���̂ł���B
�@�����������ɂ��ẮA�m�����i�߂ΐi�ނقǁA���ꂪ�K�v�ɂȂ邱�Ƃ��킽���͔F�߂Ă����B�k�c�l
�@�킽���ɂ����̎��_�k�w�c�c���@�̎��_�i���܌��w�E�C�ۊw�E�w�j�x�\�\�\�M�g�����l����������������̗��R�́A���̂��Ƃł���B�킽���ɕK�v�ȁA���������l�̏��͂Ȃ��ɂ͂ł��Ȃ������������ɂ��邽�߁A�������Ă������Ƃ����v�悪���X�܂��܂��x������̂����āA�k�c�l������蒷��������l�������k�c�l�ǂ������_�ł���炪�킽���̌v��Ɋ�^�ł��邩���������邱�Ƃ��킽�������܂�Ȃ�����ɂ��Ȃ������Ȃ�A�����̂��Ƃ��A�킽�����Ȃ�����������͂邩�ɗǂ������Ɏc�������ł��낤�ɁA�Ƃ������v���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂ���������ł���B
�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,pp.83-84,98.
�y�K�Ǐ�150�z�f�J���g�w���@�����x�\�\�\�I��B�@�@�@
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@


 �@
�@
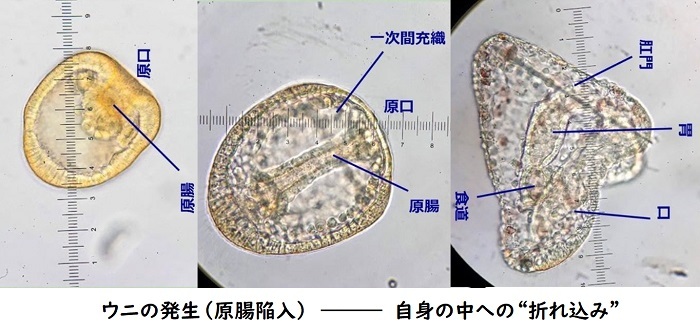

 �@
�@
 �c
�c