05/31�̓��L
06�F56
�y�K�Ǐ�150�ԊO�z�h�D���[�Y�w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x(2)
�\�\�\�ӎ��Ƒ��݁A�{���Ɛ����A���O�ƌ����̐�
---------------
.
 �@
�@
�R�����s���s���`�R�A�x�t���@�@
�@�����́B(º.-)���
�@�h�D���[�Y�w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x(1)�\�\�\�q�ǂ��A���ӎ��A�A�����t�Ȑg�� ����̂Â��ł��B
�@�y�S�z�s�ӎ��t�́A�����ɂ��Đ����邩�H
�@�O��́A�h�D���[�Y���X�s�m�U�N�w�́s���ӎ��t�ɂ��Č������܂������A����ł͋t�ɁA�s�ӎ��t�Ƃ������̂́A�Ȃ����݂���̂ł��傤���H
�@�u���݁v�ɂ����Ă��u�v�ҁv�ɂ����Ă��B����s���́t�ł����s�_���Ȃ킿���R�t�̒��ŁA���̓����ɔg�̂悤�ɂ����悤�������ɁA�s�ӎ��t�Ƃ������̂��A�Ȃ�������̂ł��傤���H �Ȃɂ䂦�ɁA�܂������ɂ��āA�������́A���R��F���ɂ��āA���ꂱ��l���A�N�w����ȂǂƂ������Ƃ��ł���̂ł��傤���H
�u����ɂ��Ă��A�ӎ��ɂ͈ӎ����ꎩ�g�̌������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�k�c�l(�w�������́A������̂������Ɣ��f���邩��k�ӎ��l��������Ƃ߂�k�w�́E�ӗ~�E�Փ��E�~�]�l�̂ł͂Ȃ��B���ɁA�������͂�����̂����Ƃ߂Ă��邩�炱���A���ꂪ�����Ɣ��f����̂ł���x[E�VP9Sc]�j�B�ӎ��͏Փ��̉ߒ��ł���ΐ��i�����j�����̂ł���A�k�c�l
�@�Ƃ�����k�c�l�Փ��Ƃ͂܂����k�c�l���ȑ����̓w�́i�R�i�g�D�X�j�ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B����ǂ����̓w���k�R�i�g�D�X�\�\�M�g�����l�́A�o��������̑Ώۂɉ����Ă��܂��܂ɈقȂ����s���Ɏ���������藧�Ă邩��A���̂���悤�́A�Ώۂ��������Ɉ����N�����ϗl�i�A�t�F�N�`�I�j�ɂ���Ă��̂nj��肳��Ă���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������̃R�i�g�D�X�����肷�邱�������G���ɂ��ϗl�����A���̃R�i�g�D�X�Ɉӎ��������錴���łȂ���Ȃ�Ȃ�[E�VADf1Ex]�B���������������ϗl�́k��������Ɍp�N���Ă���̂ł͂Ȃ��l���̏o��̑��肪�������ƂЂƂɑg�ݍ��킳�邩�A����Ƃ����ɂ��̎����������Ă��܂��悤�Ȃ��̂ł��邩�ɉ����āA���傫�Ȃ��邢�͏����Ȋ��S���ւƎ��������ڍs�����铮���i������߂����j�ƕs���Ɍ��т��Ă��邽�߂ɁA�ӎ��́A���������k���S���́l���傫�ȏ�Ԃ��珬���ȏ�Ԃւ́A��菬���ȏ�Ԃ���傫�ȏ�Ԃւ̐��ڂ́A�A���I�Ȋ���̋N���Ƃ��Č���Ă���B
�@�ӎ��́A���̑̂�ϔO�Ƃ̌��̂Ȃ��Ŏ������̃R�i�g�D�X���邳�܂��܂ȕϓ��⌈������̂������Ă���̂ł���B���̖{���ƍ����Ώۂ́A���ꎩ�g�Ǝ��̗��҂��Ƃ��Ɋ܂ލ����̑S�̂��������Â���悤�������肷��B�k�c�l�ӎ��́A�͔\�̂�菬���ȑS�̂�����傫�ȑS�̂ւ́A�܂����̋t�́A�����������ڂƂ��������ڂ̊���Ƃ��Č���Ă���̂ł���A�ǂ��܂ł��ߓn�I�Ȃ��̂Ȃ̂��B�k�c�l
�@�j�[�`�F�͌����ɃX�s�m�U��`�I�ł���B�ނ͏����Ă���B�w��v�ȑ唼�̊����͖��ӎ��I�ɂȂ���Ă���B�ӎ��͂ӂ��k���Ȃ玄�Ƃ����l�ЂƂ̑S�̂������̑S�̂ɏ]�����悤�Ƃ���Ƃ��ɂ�������Ă��Ȃ��B�Ȃɂ����܂�����́A�������������̑S�̂ɑ���ӎ��A���̊O���ɂ�����݂ɑ���ӎ��Ȃ̂��B�ӎ��́A���������g������ɍ��E����Ă��܂��悤�ȑ��݂ɑ��Đ��܂��̂ł���A�����Ɏ����������g��g�ݓ���Ă䂭��i�Ȃ̂ł���x�ƁB�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[,pp.39-41.
���́A�����̃C�^���b�N�A�̖T�_�t�������B
�@�u�R�i�g�D�X�v���Ȃ킿�u���ȑ����̓w�́v�́A�s�l���t�\�\���\�\�́g�����I�{���h�ł���[E�VP6,P7]�B�l�Ԃ́u�Փ��v�Ȃ����u�~�]�v�́A�u�l�Ԃ̖{�����̂��́v�ł���[E�VADf1]�A���������āu�R�i�g�D�X�v���̂��̂ł���Ƃ�����[E�VP9Sc,ADf1Ex]�B
�@�������́A���邱�Ƃ��u�悢�v�Ƃ��u��邢�v�Ƃ����f���A���̔��f�ɂ��������ā\�\�\���Ȃ킿�Փ��I�ɂł͂Ȃ��ӎ��I�Ɂ\�\�\�s�ׂ�����A���邢�͍s�ׂ��邱�Ƃ���߂��肷��d�d�������͂ӂ��A���̂悤�Ɏ������s�����Ă���Ǝv���Ă��܂��B�������A�����́A�u�����v�u��邢�v�Ƃ����g���f�h�́A���邱�Ƃ��������A�������Ȃ��Ƃ����u�Փ��v�̌��ʂƂ��āA�u�Փ��v�𐳓������邽�߂ɐ����Ă���̂ł��B
�@�������Ƃ���ƁA���������s�ӎ��t�Ƃ������̂́A�g���f�h�ɂ����Đ�����̂ł͂Ȃ��A�u�Փ��v�ɂ����Đ�����B�u�Փ��v�����ӎ��ɗN���N����ߒ��Ő����Ă���̂��s�ӎ��t�ł���\�\�\�s�ӎ��t�Ƃ́A�u�Փ��̉ߒ��Łv�]���Ɂu������v�����ՁA�Ȃ����g���邵�h�Ȃ̂��A�ƍl���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�Ƃ���ŁA�u�Փ��v�Ƃ́A�u�R�i�g�D�X�v���Ȃ킿�u���ȑ����̓w�́v���̂��̂ł��B�����āA�u�R�i�g�D�X�v�́A�O���̕��̂�̂��������ƐG���������A�������Ɂu�ϗl(�A�t�F�N�`�I)�v��������̂ɉ����āA��̓I�ȍs���ɋ�藧�Ă���d�d���Ȃ킿�u�Փ��v�ƂȂ��Č���܂��B���������āA�������́u�R�i�g�D�X�v���s���Ɍ����Č��肷��A�O���̂��̂ɂ��u�G���v�Ɓu�ϗl�v�������A�������́u�R�i�g�D�X�v�Ɉӎ���������u�����v���A�ƌ���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@���������u�G���v�Ɓu�ϗl�v�́A��������Ɏ������̒m�o�⊴�����h�����邾���ł͂���܂���F
�u���̏o��̑��肪�������ƂЂƂɑg�ݍ��킳�邩�A����Ƃ����ɂ��̎����������Ă��܂��悤�Ȃ��̂ł��邩�ɉ����āA
�@���傫�Ȃ��邢�͏����Ȋ��S���ւƎ��������ڍs�����铮���i������߂����j
�@�ƕs���Ɍ��т��Ă���v
�@���Ȃ킿�A�������i�u�g�́v���u���_�v�j���O�����u�́v�Əo����č��ꂵ�A���邢�͕s�K���ɂ�蕪���E���ł��Ă��܂��E�₦����u�\���v�ߒ��̈�ꑂɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�u�ӎ��́A���������k���S���́l���傫�ȏ�Ԃ��珬���ȏ�Ԃւ́A��菬���ȏ�Ԃ���傫�ȏ�Ԃւ̐��ڂ́A�A���I�Ȋ���̋N���Ƃ��Č���Ă���B
�@�ӎ��́A���̑̂�ϔO�Ƃ̌��̂Ȃ��Ŏ������̃R�i�g�D�X���邳�܂��܂ȕϓ��⌈������̂������Ă���̂ł���B�c�c
�@�ӎ��́A�͔\�̂�菬���ȑS�̂�����傫�ȑS�̂ւ́A�܂����̋t�́A���������c�c���ڂ̊���Ƃ��Č���Ă���v
�@�s�ӎ��t�Ƃ́A�Ȃɂ����܂��u����v�Ȃ̂ł���A�u���ڂ̊���v�\�\�u�ǂ��܂ł��ߓn�I�ȁv����Ȃ̂ł��B�������́A�����̔]���Ɏ����̂悤�ɐ��ڂ��Ă䂭�g���Ƃ̗�h���s�ӎ��t���Ǝv���Ă��܂������ł����A����͍ŏI�I�ȁu���ʁv�����Ă���ɂ����܂���B�������́A�����u�����v�ɂ͊���ӂ����ŁA�u���ʁv���������悤�Ƃ��܂��B
�@�������A�������́A�������s�ӎ��t���Ǝv���ĂƂ炦���R�g�o�́g�l���h���A����ƌ��т��Đ������i�u�s�Ȃ��Ă���v�Ǝv���Ȃ����j�s���ƂƂ��ɁA�������ɔ��Ȃ��Ă݂�A���Ƃ̎���𗝉��ł���͂��ł��B�s�ӎ��t�Ƃ��Đ��������̂́g�{�́h�́A�Ȃ�炩�́u�Փ��v�Ȃ����u����v�ł���A���ꂪ�g�l���h�́u�����v�ł���A�s���̗U���ł����������Ƃ��킩��͂��ł��B
�@�i�������A�l�Ԃɂ́u����(���t���N�V����)�v�̔\�͂�����܂�����A�u�Փ��v���̂܂܂ɍs������Ƃ͂�����܂���B�ނ���u���ʂ̍l���v�ɑ��āu���ȁv����������A����͂�����̂̈����x�A�s����ύX�Ȃ������~���邱�Ƃ��\�ł��B����̂ǂ������傫���قǁA�u�����v�I�ӂ�܂��ɋ߂Â��ƌ����܂��\�\�\����́A�X�s�m�U�Ƃ������A�h�D���[�Y�猻��́g�X�s�m�W�X�g�h�̍l�����ł����j
�@�������āA���������s�ӎ��t�Ƃ́A�s�_���Ȃ킿���R�t���E�̂Ȃ����u�́v�Ƃ��Ă̎��������A�����u�́v�Ƃ̂������ŐG���������A����^�������Ƃ���_�C�i�~�b�N�ȉߒ��Ɛ[�����т��Ă��܂��B���̂悤�ȃh�D���[�Y���X�s�m�U���s�ӎ��t�̂Ƃ炦�����́A����߂Ď��H�I�Ȃ��̂ł��B
�@�s�ӎ��t�Ƃ́A�܂��u�v�z�v�Ƃ́A�������l�Ԃ�������n������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�N������L���i�R�g�o�j�ɂ���ďK���A����̒��ŕ�������悤�Ȃ��̂ł͂������܂���B�s�ӎ��t�́A���R�̒��ł́A�܂��Љ�̒��ł́A�������̐₦������H�̂Ȃ��ɂ���E�˂Ɂu�ߓn�I�ȁv���ڂ̈�ꑂȂ̂ł��B
�@���̂悤�ɍl����A����̍Ō�ň��p����Ă���j�[�`�F�̌��t(�w�����̌n���x)���܂��A�����\�Ȃ��̂ƂȂ�܂��B�j�[�`�F�̂��̌����́A�ꌩ����ƁA�S�̎�`�I�ȖŎ����]�����Ȃ����Ă���悤�Ɏ��ꂩ�˂܂��A�������Ă����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��킩��ł��傤�B
�@�s�ӎ��t�Ƃ������̂́A���E�̊O���琢�E�߂�悤�Ȓ��z�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�������u���݁v�E�̒��ł́s�l���t�ǂ����́g���߂������h���琶���Ă���̂��\�\�\�Ƃ����A�h�D���[�Y���X�s�m�U�̂��̍l�����́A
�@�u���݂͈ӎ��ɐ旧�v�i�}���N�X�j
�@�Ƃ����B���_�̃e�[�[�ɁA�����ɏ]���Ă���悤�Ɍ����܂��B�X�s�m�U�N�w�̑S�̌n�́A�d�d���������Ă܂��h�D���[�Y�̓N�w���A�������ėB���_��ӓ|�ł͂���܂���B����́A���̐߂Ŋm�F���邱�Ƃ��ł���ł��傤�B�������A�����s�ӎ��t�̔����Ɋւ��ẮA�h�D���[�Y�̍l���͗B���_�I���ƌ����܂��B
�u����O���I�ȏ�ԁk�I�ϗl�l�����������g�̊����͔\�̑�����܂ޏꍇ�ɂ́A�����˂Ă����ɁA����𗠑ł����邩�����ŁA���̗͔\���g�ɂ��ƂÂ������ЂƂ̏�ԁk�\���I�ϗl�l�����܂�Ă���B�k�c�l�O���I��Ԃ́A���͂⎄�������g�ɂ������ƂÂ��Ȃ��k�O���Ɉˑ������ɐ��܂�Ă���l�K���ɂ���ė��ł������̂ł���[E�XP1-10]�B
�@����Ƃ͔��ɁA�O���I�ȏ�Ԃ��������̗͔\�̌������܂ޏꍇ�ɂ́A���̏�Ԃ͘A���I�ɑ��̔�\�S�ŗꑮ�I�ȏ�ԂւƂȂ����Ă䂭���Ƃ����ł��Ȃ��B�k�c�l
�@�܂��ɂ��̈Ӗ��ŁA�����k�����̐��l�͎����ł���B����������͕����I�E���w�I�Ȏ��n�̎����ł���A�����ł����āA�k�����I�P���ɂ��l�q�R���r�Ƃ͂܂�ł������B�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[,pp.72-73.
���́A�����̃C�^���b�N�A�̖T�_�t�������B
�u�\���W�̍���Ƃ�����ł́A�_���I���_���������̂������̂ł͂Ȃ��B������肾�Ă��X���A���������ɕ����E���w�I�A�����w�I�������̎Z�i���d�˂Ă䂩�˂Ȃ�Ȃ��̂��B�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[,p.228.
�u���ʊT�O�k�u�w���ʊT�O�x�Ƃ́u�g�̂܂��͕��̑��݂ɋ��ʂȂȂɂ��v�ł����āA����́u���݂���̂ǂ����̓K���E��v��\���I����̊W��\�����Ă���vp.103�\�\�\�M�g�����l�͂��̎������̗͔\�ɉ��������H�I�ȗ��O�ł����k�c�l���ʊT�O�̌`���̒����͏�ɂ������A�����ɂ��Đ��_���w�݂�����̂��܂��܂ȏ�𐮂��A�������݂��Ɍ��т��邱�Ƃ��ł���x���������Ă���̂ł���B���ʊT�O�͂ЂƂ́q�p�r�A�w�G�`�J�x���̂��̂̋�����p�Ȃ̂��B�q�����r�o���g�D���āA�̌����Ƃ����č\���W�����ꂳ���A�͔\����āA�������邱�Ƃł���B�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[,pp.231-232.
�@���Ȃ킿�A�u�����v�͎��R�Ȋw�̐ꔄ�����ł͂Ȃ��̂ł��B�������ɂƂ��āg������h�Ƃ́A�˂ɐV���ȁu�����v�ɑ������邱�Ƃł���A�₦����u�����v���d�˂邱�Ƃɂق��Ȃ�܂���B
�@���̂悤�ɍl����A���Ă킪���̕s���Ȏ��l�����b���e�̂Ȃ��ɏ��������A�����̂悤�ȁA���㑫�炸�Ȍ��t�̈Ӗ����A���悭���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�u�݂�Ȃ��߂��߂����Ԃ�̐_���܂��ق��̐_���܂��Ƃ��ӂ��炤�B����ǂ����݂ق��̐_���܂�M����l�����̂������Ƃł��܂����ڂ�邾�炤�B���ꂩ��ڂ������̐S�������Ƃ���邢�Ƃ��c�_���邾�炤�B�����ď��������Ȃ����炤�B����ǂ������A���܂ւ��ق��ɕ����āA�����ł����Ƃق��̍l�ւƁA�����̍l�ւƂ��Ă��܂ւA���������̕��@���ւ��܂�A�����M�����w�Ɠ����₤�ɂȂ��B�v
�@
�@�@�@Ferenczy Béni (1890-1967)
�@�y�T�z�̂ƍ\���f�A�̂ƑS��
�u�́iINDIVIDU�j�\�\�\�k�c�l�C�ӂ̑����ɂ����đ��݂����l�����������Â��镡�G�ȕҐ����A���̂��Ƃ͎w�������Ă���B
�@�����A�܂� (1) �l���́A�I�E���ٓI�Ȗ{�������B����������A�����͔\�̓x�A���x�I�E����I�ȕ����\�\�\�i���ȕ����ipars aeterna�j[E�XP40]�\�\�\�������Ă���B�ǂ̖{�����A�����ЂƂЂƂ͐�ΓI�ɒP���Łk�����ɂ͕����ꂸ�l�A���̂��ׂĂ̖{���ƈ�v�E�K�����݂�B (2) ���������{���́A�e�l�����L�̍\���W�̂����ɂ��̂�����\������邪�A���̍\���W���i���Ƃ��Ή����ɂ�����^���ƐÎ~�̈��̍\���W�j�A���ꎩ�̂͂�͂�i���̐^���\�\���݂ɂ������i���̐^���ł���B (3) �l���́A���̍\���W�������ɖ����ɑ����̊O���I���������ۂ���Ƃ��A���݁k���݂����l���l�ւƈڍs����B�����̊O���I�������́A����ɂ�������O���I�Ȃ��܂��܂̌���v���̂͂��炫�ɂ���āA�����l���̍\���W�̂��Ƃɂ͂���悤�A���邢�͂���������悤���肳���̂ł���B�l���́A���������O���I���������ʂ̍\���W�\�\�\�����l���̂���Ƃ͑��e��Ȃ��\���W�\�\�\�̂��Ƃɂ͂���悤�A�O�����猈�肳���Ƃ��A���݂��邱�Ƃ���߂�B�k�c�l�ЂƂЂƂ��͔\�̓x���A���ꂪ�l�����̂��̂��{�����Ȃ��Ă��邩����ł��A���ׂĂ��������ɑ��ƈ�v�E�K�����݂邪�A���݂ɂ����ẮA�K�R�I�ɓ�����Ԃɂ͂������ƂɂȂ�B����\���W�̂��ƂɂЂƂ��͔\�̓x�ɋA�����Ă���O���I�������́A���炽�ȍ\���W�̂��ƂɁA�����͔\�̓x�ɂ����D������邱�Ƃ����肤�邩��ł���[E�WAx,E�XP37Sc]�B
�@���������ĂP�́k���݂���́l�́A�˂ɖ����ɑ����̊O���I����������\�\�\�����̕������A�P���l���̌I�E���ٓI�Ȗ{���ɁA���L�̍\���W�̂��ƂɋA�����邩����ɂ����ā\�\�\���藧���Ă���[E�UP13f]�B�����̕����i�ŒP���́k�\���f�́lcorpora simplicissima�j���ꎩ�g�́A�������̂ł͂Ȃ��B�����́A�X�ɂ͖{�����������A�ЂƂ��ɊO�I�Ȍ�������ɂ���ċK�肳��A�ǂ��܂ł������ɑ������g�ƂȂ��Đi�s���邩��ł���B�����́A���ꎩ�g�͌̂ł͂Ȃ����A���̂Ȃ��̖������������������l���̖{��������Â��邵�������̍\���W�̂��Ƃɂ͂���Ƃ��A���̂�����ɂ����Ĉ�̑��݂���̂��������Â����B���݂ɂ������l���̂Ƃ閳���ɑ��l�ȗl���̎������A�����̊O���I�v�f�͂������Â����Ă���̂ł���B�k�c�l
�@�ނ��Q���l�������݂ɂ����ďo��A�����ł́A���҂̍\���W���������ɑ��̕����ɂ͂��炭���A����Ƃ��������ɑ��ƒ��ڂЂƂɑg�ݍ��킳�邩�ɉ����āA�����������j�邱�Ƃ��N����A����������̑������������邱�Ƃ��N���肤��B�������ǂ�ȏꍇ�ɂ��A�ǂ̂悤�Ȃ������ŏo����ƁA�K�������ɂ͍���E�`�����݂�\���W�������B�����ɂ́A�i���̐^���k���R�̖@���l�Ƃ��Ă̍\���W�̍���E�`���̒���������̂ł���B�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[,pp.114-117.
���́A�����̃C�^���b�N�A�̖T�_�t�������B
�@���p�����̌��_�́A�ŏ��̒i���̂������́A�������Ђ����Ƃ���ɂ���܂��B�������茾���A�u�́v���u�́v�A���Ȃ킿�s�l���t�ǂ����́A�u�{���v�ɂ����Ắ\�\�܂����O�̐��E�ł́\�\�u�������Ɂc��v�E�K���v���邪�A�������u���݁v�̐��E�ł́A�u�K�R�I�ɓ�����Ԃɂ͂���v�Ƃ������Ƃł��B
�@���������Ă���́A�h�D���[�Y���X�s�m�U���s�����Љ�t�_�A�s���Ɓt�_�����邤���Ŋ�b�ɂȂ�d�v�ȕ����ł��B���u�l�v���u������Ԃɂ͂���v�Ƃ������_�́A�u���l�̖��l�ɑ��铬���v�Ƃ����z�b�u�Y�̎Љ�ρ\�\�s���R��ԁt��z�N�����܂��B
�@�������A�ǂ����āu�l�v�͌����̐��E�ł͑����̂��H ���������ǂ����āA�����Ȃ�̂��H�d�A���̂������Ƃ̕����Ō����ɂ���u�͔\�̓x�v�Ƃ́A���Ȃ̂��H�d�d�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���̏��q������ǂ�ł��悭�킩��܂���B
�@�����ŁA���p�̌㔼�����\�\�̂ق����b����̓I�ł킩��₷���\�\���ɓǂ݂Ƃ��������ŁA�u�͔\�v�Ƃ����h�D���[�Y�̃^�[���ɂ��ĒT�����A���̂����ɗ����āA���̑�P�i�����U�߂邱�Ƃɂ������Ǝv���܂��B
�u�P�́k���݂���́l�́A�˂ɖ����ɑ����̊O���I�������i�ŒP���́k�\���f�́lcorpora simplicissima�j����c�c���藧���Ă���v
�@���̕����ς́A�s���q�_�t�Ɏ��Ă��܂��A���́s���q�_�t���ƌ����Ă悢�ł��傤�B�����������i�X�s�m�U���s�S�g���s�_�t�ɂ���āA������u���_�v�ł�����j�́A�u�����ɑ����́c�c�\���f������v�����Ă���B
�@�������A�����u�\���f�́v�ɂ͑傫��������܂���B�܂�A�傫���̓[���ł��B�傫�����[���̂��̂�L���W�߂Ă��A�S�̂̑傫���͂�͂�[���ɂ����Ȃ�܂���F
�@0�~����0�@(0���������C����1,2,3,...)
�@���������āA�傫���̂�����̂����ɂ́A�u�\���f�́v���������W�܂�Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�u�́v�́A�����ӂ́u�\���f�́v���琬���Ă����̂ł��B�킩��₷���C���[�W����ɂ́A�u�́v�́A���܂��܂ȑ傫���̐����ŁA�u�\���f�́v�́A�������\�����閳���ӂ́u�_�v���Ǝv���悢�ł��傤�B�u�́v�Ƃ́A�L���ȑ傫�����������W���ł��B
�@0�~�������@(0���������C�����q)
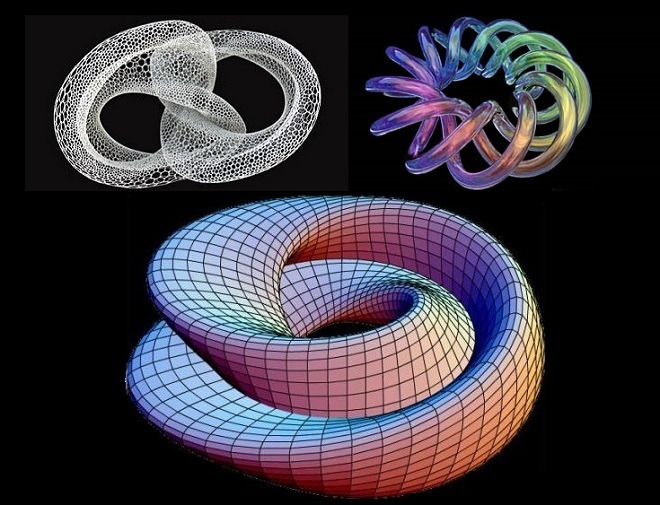
�@�Ƃ���ŁA�h�D���[�Y�́���̈��p���ŁA�u�́v�������Ă����u�\���f�́v�ЂƂЂƂ́A�u�́v�ł͂Ȃ��̂��ƌ����܂��B�d�d���Ƃ���ƁA�u�́v�ł�����̂ƁA�u�́v�ł͂Ȃ����̂Ƃ́A�ǂ����������̂��H
�@�����ɁA�h�D���[�Y���X�s�m�U�̗��_�ɉ������d�v�ȉ��߁\�\�Ȃ����A�V���Ȏv�z�ƌ����Ă��悢�\�\������܂��B
�@�X�s�m�U�̏ꍇ�A�u�́v�i�l�j�Ƃ͉����H�d�Ƃ������Ƃ��A�Ђ��傤�ɂ����܂��ł���悤�Ɍ����܂��B�l���u�́v���\�����Ă���튯��畆�A�����A�̉t�Ƃ��������̂��A�ނ��u�́v�ƌĂ�ł��܂�[E�UL7Sc]�B
�@�������A�u�\���f�́v�Ƃ̊W�ł́A�u�́v���u�́v����䂦��́A�͂����肵�Ă��܂��B�u�́v���A����Ȃ�ꎞ�I���u�\���f�́v�̏W���ƈقȂ�̂́A�u�\���f�́v�ǂ������������Ɂu�ڍ��v���āu����v���A�˂ɂЂƂ́u�`���v�\�\�������\�\��ۂ��ĉ^������_�ɂ���܂�[E�UDf(post Ax2),L6.L7]�B
�@�u�́v�́A���̈ꕔ��������ւ�����ꍇ�ł��A�S�̂́u�`���v���ς�Ȃ���A���ꐫ���ێ����邱�Ƃ��ł��܂�[E�UL4]�B�������āA�����́u�V���(�������)�v����������܂��B�܂��A�u�́v�́A����́u�`���v��ۂ����܂܁A�V���ȕ��̂�������đ傫���Ȃ�����i�����j�A�t�ɁA�������ď������Ȃ����肷�邱�Ƃ��ł��܂�[E�UL5]�B
�@�܂�A�u�́v���u�́v���炵�߂Ă���̂́A�e�u�́v���L���Ă���u�`���v�\�\�ʂ̌��t�ł������u�{���v�\�\�Ȃ̂ł��B
�u�ŒP���́k�\���f�́lcorpora simplicissima ���ꎩ�g�́A�������̂ł͂Ȃ��B�����́A�X�ɂ��{�����������A�ЂƂ��ɊO�I�Ȍ�������ɂ���ċK�肳��A�ǂ��܂ł������ɑ������g�ƂȂ��Đi�s���邩��ł���B�����́A���ꎩ�g�͌̂ł͂Ȃ����A���̂Ȃ��̖������������������l���̖{��������Â��邵�������̍\���W�̂��Ƃɂ͂���Ƃ��A���̂�����ɂ����Ĉ�̑��݂���̂��������Â����B�v
�@�܂�A�u�{���v�Ƃ́A�X�̂��̂ɌŗL�̓����ł��B�u�{���v������Â��Ă���̂́A���̌����u�\���W�v�ł��B���Ȃ킿�A�ǂꂾ���̖������u�\���f�́v���A�ǂ̂悤�Ɂu�ڍ��E����v���āA�����\�����Ă��邩�Ƃ����A���̕Ґ��̂Ȃ肽���ł��B�����āA������܂��ʂ̕\���Ō����ƁA����͌��̗L����u�͔\�̓x�v�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@�h�D���[�Y���u�́v�ɓ��ʂ̒n�ʂ�F�߂Ă��܂��B�X�s�m�U�͂��̓_����₠���܂���������������܂���B
�@�����ɂ��܂��܂ȁs�l���t�̂Ȃ��ŁA���̍\���W�ɂ�����u�́v�Ƃ��Đ����������̂������A�u�́v�Ƃ��Ă��s�{���t�\�\���Ȃ킿�u�`���v�A�������\�\�������A�����̐��E�ɂ�����\���W�́g���߂������h�̂Ȃ��ŁA�����́g�������h��ۂ��Ă������Ƃ���B�h�D���[�Y�̎咣�́A���̂悤�ɓǂ߂܂��B
�@���Ƃ���ƁA���̂悤�ɂ��Ď����́u�`���v���s�{���t��ێ����悤�Ƃ���͂��A���ׂẮu���v�́A�����Ă���͂��ł��B���̗͂������A�u�R�i�g�D�X�v�ɂ������Ȃ��B���ꂱ�����A�u�͔\�̓x�v�ł��낤�B�\�\�\�c�_�̂Ȃ�䂫�́A���̂悤�ɗ\�z���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�y�U�z�{���i���O�j�Ƒ��݁A�̂Ɛ���
�u�w�G�`�J�x�̍��{�I�ȃ|�C���g�̂ЂƂ́A�_�ɂ����k�c�l���������̌����i�|�e�X�^�X�j��ے肵�Ă���Ƃ���ɂ���B�k�c�l�_�̒m���Ƃ����ǂ��ЂƂ��l���ɂ������A����ɂ���Đ_�݂͂�����̖{���ƁA��������A��������̈ȊO�̂Ȃɂ��̂�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�k�c�l����䂦�_�́A�����i�|�e�X�^�X[potestas]�j�����̂ł͂Ȃ��A����ɂ��̖{���ɂЂƂ����͔\�i�|�e���`�A[potentia]�j�����ɂ����Ȃ��B���̗͔\�ɂ���āA�_�͂��̖{�����琶���邢�������̂��̂̌����ƂȂ�A�܂����Ȏ��g�́A���Ȃ킿���̑��݂��{���Ɋ܂܂��悤�Ȑ_�݂�����̑��݂́A�����ƂȂ�̂ł���[E�TP34]�B
�@�l���k�ЂƂЂƂ̐g�̂�_�l���܂��A���̖{���͂P���͔\�̓x�ł���A�_�I�͔\�̈ꕔ���A�P�̓���I�E���x�I�ȕ����ł���B�w�l�Ԃ̗͔\���A�k�c�l�_�A���Ȃ킿���̎��R�̖����ȗ͔\�̈ꕔ���ł���x(E�WP4Dm)�B
�@�����l�������݂ւƈڍs����k���݂����l���ƂȂ�l�̂́A�����ɑ����̊O���I���������A�����l���̖{�����邢���͔\�̓x�ɑΉ�������̍\���W�̂��Ƃɂ͂���悤�A�O�����猈�肳��邩��ł���B�k�c�l���̂Ƃ��͂��߂āA���̖{�����ꎩ�g���R�i�g�D�X���邢�͏Փ��Ƃ��ċK�肳��邱�ƂɂȂ�B�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[,pp.203-204,206.
�@�s�����t�ɐ������g�ł���X�̂��̂́A�l�Ԃ����A�����V�̂��A���ꂼ�ꂪ�A�s�_���Ȃ킿���R�t�S�̂��u�͔\�v�́E�����ꕔ���L���Ă��܂��B
�w�l�Ԃ̗͔\���A�c�c�_�A���Ȃ킿���̎��R�̖����ȗ͔\�̈ꕔ���ł���x
�@���ꂪ�A�e�s�l���t���u�{���v�ł���A�u�͔\�̓x�v�ɂق��Ȃ�Ȃ��B���́A���ꂼ��ɓ��L�́u�͔\�̓x�v�������Ă��܂��B���ꂼ�ꂪ�u�͔\�v�ł�����ǂ����́A���́u�x�v�ɂ���Ă�����ʂ���Ȃ��B
 �@�@
�@�@
�u�l���e�̖{���͂ǂ��ɂ���̂��낤�B�_�k�����l�̗͔\���e�l���̖{�����Ƃ����Ă��̂�����J�W�k�����l����邩����A���̖{���ЂƂЂƂ݂͂ȁA�_�̗͔\�̈ꕔ���Ȃ̂ł���[E�WP4Dm]�B�k�c�l
�@�e�l���̖{���A����́A�k�c�l�k�_�������́l�͔\�̕����A����������Ε����I�ȋ��x�k����x���i�����E�傫���j�̗͔\�l�ł���B�k�c�l���̖{���ЂƂЂƂ��k�ЂƂЂƂ̌��̖{���\�\�M�g�����l�͈����͔\�̓x�ɑΉ����A���̂��ׂĂ��k���́\�\�M�g�����l�{�������ʂ����̂ł���B�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[,pp.195-196.
�@�������A�������������u���݂ւƈڍs����v�ƁA�����ɁA�����ɑ������u�\���f�́v���ۂ��āA���ȓ��L�̕Ґ����ێ����Ă������Ƃ��܂��B���Ȃ킿�A�e���́A���ꂼ����u�����I�{���v�Ƃ����u�R�i�g�D�X(���ȕێ��̓w��)�v�������ƂɂȂ�܂��B
�@�����A�u���݁v�ɐ��܂ꗎ����̂́A�݂�����́g�ӎu�h��U���ɂ���Đ��܂��̂ł͂���܂���B�����܂ł��A�O���̕K�R���ɋK�肳��ĎY�ݗ��Ƃ����̂ł��B�������A��������Y�ݗ��Ƃ���Đ������͂��߂����́A�ǂ��܂ł����Ȃ��u�R�i�g�D�X�v���咣���đ������Â��悤�Ƃ��A����́g�������h�\�\�{���\�\���ێ����悤�Ƃ����u�Փ��v�������Â��܂��B
�@�u�R�i�g�D�X�v�ɂ́A�g���܂Łh�Ƃ������x�͂���܂���B�u�́v���g�͉i�v�ɑ��݂��Â��悤�Ƃ��܂��B�u�́v�̒a�����O�����猈�肳�ꂽ�悤�ɁA�u�́v�̏I��\�\���\�\���܂��O���������Ă���̂ł��B
�@���́A�u���݂ւƈڍs�v�����Ƃ��A�u���̂Ƃ��͂��߂āA���̖{�����ꎩ�g���R�i�g�D�X���邢�͏Փ��Ƃ��ċK�肳��邱�ƂɂȂ�B����k���݂����l���̖{���l�́A���݂ɌŎ�����A���������������L�̍\���W�̂��Ƃɂ���ɋA�����Ă��鏔������ێ����X�V���āA���݂��Â��悤�Ƃ���X�������̂ł���i�R�i�g�D�X�̑�P�̋K��\�\E�WP39�j�B�k�c�l
�@�ЂƂ��т����l�������݂���悤���肳���A���Ȃ킿���̍\���W�̂��Ƃɖ����ɑ����̊O���I���������ۂ���悤���肳���A���̖{���͑��݂ɌŎ����Ăǂ��܂ł��������悤�Ƃ���B
�@���݂ɌŎ�����Ƃ͎�������Ƃ������Ƃł���B���������ăR�i�g�D�X�͖��ی��̎��������̂����Ɋ܂�ł���[E�VP8]�B
�@�k�c�l�X�̑��݂����l���̏ꍇ�ɂ́A���̕ϗl�̗͗��k���̌̂���̐G���ɉ����ĕϗl������͗�(�A�v�g�D�X[aptus])���L�\���̓x�����\�\�\�M�g�����l�k�c�l�����̂́A�k�c�l���̏��l���ɂ�����k�c�l�Y�ݏo�����������̕ϗl�i�A�t�F�N�`�I�j���i�A�t�F�N�g�D�X�j�ł���B���̎�̕ϗl���́A���������đz���k�G���ɂ��\�ۑ��̌`���l�ł���A�I����ł���B��i�A�t�F�N�g�D�X�j�i����j�Ƃ́A�܂��ɃR�i�g�D�X���A���g�ɋN����ϗl�i�A�t�F�N�`�I�j�ɂ���Ă��ꂱ�ꂷ��悤���肳����ۂɂƂ�A���̎p�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�R�i�g�D�X�����肷�邻�������ϗl���ӎ��̌����ł���A���������̕ϗl�̂��ƂŎ��g���ӎ�����ɂ��������R�i�g�D�X���A�~�]�Ƃ���B�~�]�Ƃ͂˂ɉ����ɂ��Ă̗~�]�Ȃ̂ł���[E�VADf1]�B
�@���������킯�ŁA�P���͔\�̓x�Ƃ��Ă��l���̖{���́A�����l�������݂��n�߂��Ƃ�����A�R�i�g�D�X�Ƃ��āA����������Α������悤�Ƃ���w�͂������͌X���Ƃ��ċK�肳��邱�ƂɂȂ�B�k�c�l���̑��݂��ێ����m�����悤�Ƃ���X���ł���B�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[,pp.206-208.
�@�X�s�m�U�́A�Ƃ������͑����Ƀh�D���[�Y�̍l�������Ǝv���܂����A
�@���݁i�����j vs�@�{��
�@�Ƃ��� 20���I�N�w�̊�{�I�Șg�g�݂ɉ����ė�����g�ݗ��ĂĂ��邱�Ƃ��킩��܂��B
�@�u�{���v�Ƃ́A�������茾���Ă��܂��g�C�f�A�h�ł��B�u�P�v�Ƃ��u���v�Ƃ��u�^�v�Ƃ��������̂��A�V��́g�C�f�A�E�h�ɂ͂����āA�����������O�I���u�{���v���A�����̕����I�Ȉߑ����܂Ƃ��Č��ꂽ�̂��A�u���݁v�E�̂��ꂱ��̎������A�Ƃ����킯�ł��B
�@�X�̎����i�X�s�m�U�̌����s�l���t�j���A���Ƃ��Ƃ́g�C�f�A�h�Ƃ��Ă��u�{���v�������Ă���̂ł����āA�s�l���t���u�{���v�Ƃ́A�u�͔\�̓x�v�ł���B�s�����t�ł����s�_���Ȃ킿���R�t�́A�������u�͔\�v�������Ă��邪�A���̑S�̓I���u�͔\�v�̂����ꕔ�����A�s�����t�ɐ������g�ł���e���́A���ꂼ��̓x�����ɉ����ĕ��L���Ă���B���ꂪ�e���̂��u�͔\���x�v�ł���A�e�X���u�{���v�ł���B
�@�Ƃ���ŁA�e�����g�C�f�A�E�h����A�u���݁v�̐��E�ɐ��܂ꗎ����ƁA�d�d���Ȃ킿�A�s�����t�ɔg�������ĂЂ낪���Ă䂭�悤�ɁA�s�l���t�Ƃ��đ��݂��͂��߂�ƁA�e���̂����u�{���v���A�����̂��������Ƃ�悤�ɂȂ�B
�@�u�{���v�Ƃ́A���܂��܂ȁu�͔\�̓x�v�ł���A����Ίe���ɓ��L�́g�������h�Ȃ̂����A�e���\�\�\�܂�g�g�h�\�\�́A��������g�������h���Ƃ��đ��݂��͂��߂�ƁA�����́g�������h���\�Ȃ�����ێ����悤�Ƃ���B����͂��傤�ǁA���ʂɐ������g���A�������Ȃ�����A�\�Ȃ����蓯���`���ێ����ē`����Ă������Ƃ���̂Ɏ��Ă���B
�@�������A�g�ǂ������ӂ��肠���A�������ɉe�����Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�`����̂������g�ǂ������Ԃ��肠���A���E�������ď����Ă��܂����Ƃ�����A����̔g�������̔g�ɋz������ď����邱�Ƃ����邾�낤�B�������A�g���g�Ƃ��ẮA�ł��邱�ƂȂ玩���̌`��ۂ����܂܂ő��̔g�ƍ��ꂵ�āA���傫�Ȕg�ɂȂ낤�Ƃ���B
�@���̂悤�ɂ��āA�\�Ȃ����莩�Ȃ�ێ����A���傫�Ȋ��S���Ɍ��������Ƃ���X���Ȃ����w�́\�\���Ȃ킿�u�R�i�g�D�X�v�\�\�́A���悻�g�Ƃ��đ��݂��邱�ƂɂȂ����s�l���t���ׂĂ��K�R�I�ɂ����u�{���v�ł���ƌ�����B���Ȃ킿�A�u�R�i�g�D�X�v�́A�s�l���t���u�����I�{���v�Ȃ̂ł���B

�u�����������ɂ��̖{���k�u���݂ւƈڍs�v����ȑO�̖{���\�\�M�g�����l��������݂�A���ׂĂ��l���̖{���́A�������ɐ_�I�͔\�̓���I�����Ƃ��ēK���E��v�������B
�@���݂����l���ɂ��ẮA����Ƃ͂킯���������B�k�c�l�����ł́A���������Ă��ׂĂ��͔\�Ԃ̂��������ƂȂ�B���݂����l���ǂ����́A�K�������������ɓK���E��v���݂Ȃ��̂ł���B�w���R�̂����ɂ́A����������Ɨ͔\���傫�������Ƌ������̂��̂����݂��Ȃ��悤�Ȃ����Ȃ�������肦�Ȃ��B�ǂ�Ȃ��̂ɂ��A�����j����悤�ȑ��̂����Ɨ͔\�̑傫�����̂��K�����݂���x[E�WAx]�k�c�l
�@�P���͔\�̓x�Ƃ��Ă��l���̖{���́A�l�������݂��n�߂����̂Ƃ�������͂₻���ێ����悤�Ƃ���w�͂܂�R�i�g�D�X�ł����Ȃ��Ȃ邪�A����͖{���̈�ł́i����I�����Ƃ��Ắj�K�R�I�ɓK���E��v���݂Ă����e�̗͔\���A���݂̈�ɂ����Ắi�ꎞ�I�ɊO���I�������������X�ɋA�����Ă��邩����ł́j���͂�K��������Ȃ��Ȃ邩��ł���B�����Ȃ���������Ԃ̖{���́A���݂ɂ����Ă͎��ȕێ��̓w�͂Ƃ��Ă����A���������������𗽉킷�邩������Ȃ����̂������̗͔\�Ƃ̂��߂������Ƃ��Ă����K�肳�ꂦ�Ȃ��̂�[E�WP3,P5]�B�k�c�l
�@���݂����l���́A�����ƓK�����A�������̍\���W��������݂�悤�ȑ��̑��݂����l���i���Ƃ��A�k�c�l�H�ו��A��������́A�F�Ȃǁj�ɏo��ꍇ������A�K�������ɂ���ɂ�����k�������\�\�M�g�����l�j��Ă��܂�������̂��鑼�̑��݂����l���i�ŕ��A����������́A�G�j�ɏo��ꍇ������B��P�̏ꍇ�ɂ́A�����l���̐G���ɑ���ϗl�̗͗ʂ́A��т∤����Ƃ����Q�̖��x�̏�i����j�ɂ���Ė�������邪�A�����̏ꍇ�ɂ͔߂��݂������Ƃ����Q�̈Â��̏�i����j�ɂ���Ė��������B�k�c�l
�@�߂����k����\�\�M�g�����l�̏ꍇ�ɂ́A�R�i�g�D�X�Ƃ��Ă̎������̗͔\�͂��̋�ɂƂȂ鍭�Ձi�߂��݂���������N�����Ώۂ̊ϔO�j�ɂ����肫��ɂȂ�A���̌����ƂȂ��Ă���Ώۂ�r�����邩�j���ڂ����ʂ����Ȃ��B�k�c�l
�@����k�∤�\�\�M�g�����l�̏ꍇ�ɂ́A����Ƃ͔��Ɏ������̗͔\�͂Ђ낪���āA����̗͔\�ƈ�̂ƂȂ�A������ΏۂƂЂƂɌ��э���[E�WP18]�B���������킯�ŁA�k�c�l�������̗͔\�́A�߂��݂̏�ɂ���Č������݂邠�邢�͑j�Q�����A��т̏�ɂ���đ�����݂邠�邢�͑��i������k�c�l�R�i�g�D�X�͂��̂Ƃ��A����������т𖡂킢�A�����͔\�𑝂����Ƃ���w�́A��т̌����ƂȂ�����k�c�l�������������A�z���k�\�ہl���悤�Ƃ���w�͂ł���A�܂������ɁA�߂��݂��������A�߂��݂̌��������ł�������̂������������A�z���k�\�ہl���悤�Ƃ���w�͂ł�����[E�VP12,P13,�ق�]�B����������i����j�Ƃ́A�G���ɂ��ϗl�̊ϔO�ɂ���Ă��ꂱ�ꂷ��悤���肳��邩����ɂ�����R�i�g�D�X���̂��̂Ȃ̂��B�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[,pp.208-212.
�u�����ɂ��̖{����������݂�A���ׂĂ��l���̖{���́A�������ɐ_�I�͔\�̓���I�����Ƃ��ēK���E��v�������B�v
�@�܂�A�u�{���v(���O�j�̐��E�ł́A���݂͂ȁA�s�_�t�̓����u�͔\�v�L���Ă���B�����Ȃ����邱�Ƃ͂��ׂāA���ꂼ�ꂪ���L���邻���u�͔\�v�̂Ȃ���킴�ł��B�ǂ�Ȍ����s�_���Ȃ킿���R�t�́s�l���t�Ƃ��āu�K���E��v�������v�͂��Ȃ̂ł��B
�@�������A������������A�����̂��̂Ƃ����u���݁v���͂��߂�₢�Ȃ�A���ƌ��͂������ɑΗ��������A�₦�����u�͔\�v�̂��߂������\�\�g�͂̓����h�̉Q���ɂ�����܂��B�e���́A���Ƃ��Ă̎����́u�`���v���ێ������u���݁v���Â��悤�Ƃ���̂ŁA�K�R�I�ɂ������ɑ��킴������Ȃ��̂ł��B
�@�u�{���v�̓K���E��v�ƁA�u�����I�{���v(�R�i�g�D�X�j�̖����E�����B���̓�ʐ��ɁA�ǂ��܂ł��h����ʂ���Ă���̂��A�s�l���t�Ƃ��Ă̌��́E����悤�̂Ȃ��^���ł��B
�u�@�@�@�@�@�s�݂�Ȃނ�������̂��₤�����Ȃ̂������k�c�l
�@�@�@�@�@�@�k�c�l
�@���ׂĂ��邪���Ƃ��ɂ���
�@���U�₭���Ƃ��ɂ����₭����
�@���܂ւ̕���₠������̂�
�@���܂ւɂ��炭�����낵��
�@�܂��Ƃ͂��̂��������邢�̂��v
�����̍s������ꊷ���B
�@�g�����̏��������͎̂����ł��悭�킩��Ȃ��h�ƌ���[�w�����̑��������X�x��]�A���̓��{�̎��l�̗슴�I�ȕ\���́A�X�s�m�U�ɂ���ĉ����ƁA�ӂ����Ȃقǂ悭�����ł��܂��B�i�w�G�`�J�x�̘a��́A�������łɏo�ł���Ă��܂�����[�w�X�s�m�U�N�w�̌n�G�`�J�x1918�N,��g���X]�A�w�t�ƏC���x�u徒�����v�ɂ́A�u�i�`���i�g���v[natura naturans; natura naturata �\�Y�I/���Y�I���R] �Ƃ����X�s�m�U�N�w�p����o�����܂��j
�@
�@�@�@
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@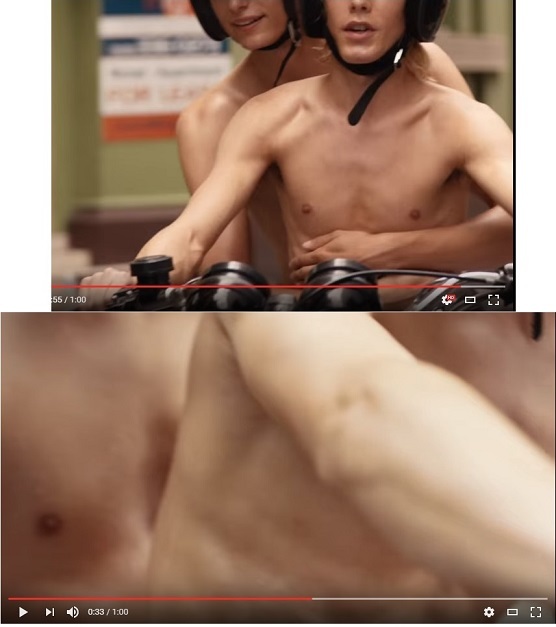

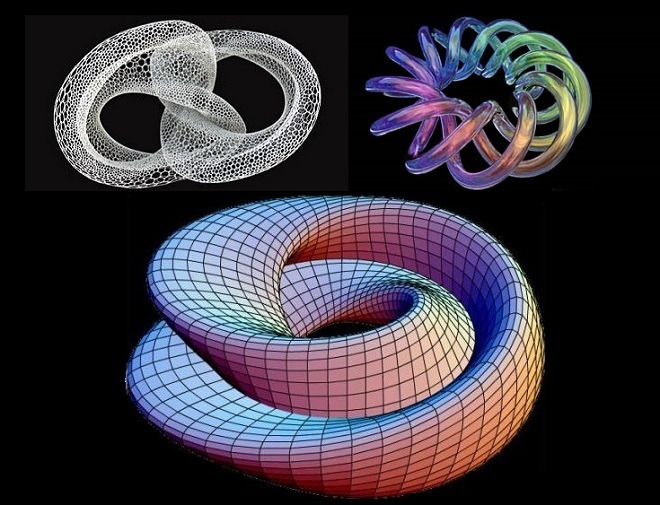
 �@�@
�@�@

 �c
�c