05/12�̓��L
01�F24
�y�K�Ǐ�150�ԊO�z�h�D���[�Y�w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x(1)�\�\�\�q�ǂ��A���ӎ��A�A�����t�Ȑg��
---------------
.
 �@
�@
�X�s�m�U���A�f���E�n�[�N�@�@
�@�����́B(º.-)���
�@�y�K�Ǐ�150�z�̃��X�g�ɂ́A�h�D���[�Y���K�^���̋����w�A���`�E�I�C�f�B�v�X�x���f�����Ă��܂����A����́A�X�s�m�U�i�ˁF�y�K�Ǐ�150�z�X�s�m�U�w�G�e�B�J�x(1)�j�����h�D���[�Y�ւ́g�Ȃ��h�Ƃ��āA���ɖ{�P���̎�y�Ȗ{���������グ�Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B
�@�@�@�W���E�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[.
�@�X�s�m�U���₵�������Ə��ȗނɂ��ẮA������� 17���I���猻�݂Ɏ���܂ŁA���܂��܂ȉ��߂��s�Ȃ��A�܂��A�N�w�����E�̊O�ł��A�Q�[�e�A�}���N�X���烍�}���E�������܂ŁA���{�ł��{������O�ؐ��܂ŁA�L�͂ȕ���̐l�тƂɃC���X�s���[�V������^���Ă��܂����B�������A1968�N�Ȍ�A�t�����X�𒆐S�ɋN�������g�X�s�m�U�E���l�T���X�h�́A�]���i�X�s�m�U�Ȍ�j�̋ߑ�N�w�̘g�g�݂�����������ꂽ�{���̃X�s�m�U���g�̎v�z�̎p���A�����̂��ƂɎN�����Ƃ����܂��B�t�����X���Q���[�A�}�g�D�����A�h�D���[�Y�A�o=�e�E�����[�i�ˁF�w�X�s�m�U����x,�N�Z�W���j��ɂ��E���T�ɑ������X�s�m�U�v�z�̓N�w�I�W�J�A�܂��A�o���o�[���A�C�^���A���l�O���A�A�����J���n�[�g��ɂ�鐭���v�z�Ƃ��Ă̕~���E���W�́A�Đ_�_�Ƃ����_��̃��F�[���ɕ����Ă����X�s�m�U������V�����܂����B
�@�������A���̕����́A���݂��r��ɂ���܂��B���܂��܂Ș_�҂ɂ�闝���̑���͉����ɂ͂قlj����A�`���ꂽ�X�s�m�U�̎v�z���́A���܂������ɖ����Ă���ƌ����Ă悢�B�X�s�m�U���g�̖{���̎v�z���O�ڂ̑O�ɖ��炩�ɂȂ�̂́A�͂����č����I���ɂ��肤�邱�ƂȂ̂��H�d�Ƃ����v����̂ł��B
�u�킽���ȊO�ɂ��A�����̐l�тƂ������̋��Y��`�̃G�s�X�e�[���[�̍\�z�����ē������B�Ȃ��ł��A�X�s�m�U���������҂Ƃ��Ă̓}�g�D�����ƃh�D���[�Y�������k�c�l�B�������܂��A�~�]�Ƃ�����b���疯���`�̊v�V�Ƃ������݂ւƌ������l�Ԃ̗��j�̍č\�z�Ƃ�������Ɏ�肭��ł����B�k�c�l�X�s�m�U�Ɓw�U�W�N�x�A�w�U�W�N�x�ƂƂ��ɂ������X�s�m�U�A�����āw�U�W�N�x�ȍ~�̃X�s�m�U�̍ēlj��A����͓N�w�j�I�ɂ͂����T�u�^�C�g���ł���A�i�D�́w�n���}�x���낤�B�k�c�l����ꂪ�v���O�}�e�B�b�N�Ɂi�����̔ᔻ�I�`����ʂ��āA�}���`�`���[�h�̊����̌o����ʂ��āj���R�̎������������݂��菕�����Ă����悤�ȓN�w�j�ɂƂ��Ăł���B
�@�����͐V���Ȏ����}���Ă���B�w�����I�Љ��`�x�̕����A�k�c�l�l�I���x�����Y���Ƃ��̃G���[�g�����́A�V���Ȑ푈�Ɣj���ʂ��āA���E��V���Ȋ�@�ւƓ����Ă����B�k�c�l�X�s�m�U�̎v�z�̕z�u�́A�ߑ�̎n�܂�ɂ����āw�ٌ`�x�Ƃ��ēo�ꂵ�����A���܂�ߑ�̏I����k�c�l�ɁA���{�I�Ɂw�I���^�i�e�B�u�x�Ȃ��́A���������I�Ɋv���I�Ȃ��̂Ƃ��Ďp�����킷�B�v
�A���g�j�I�E�l�O���u���{��łւ̏����v, in�F�A���g�j�I�E�l�O���C���������E����w�쐶�̃A�m�}���[�x,2008,��i��,pp.10-11.
�u�l�O���̓X�s�m�U�̐i�����N���Ă���B�܂�A�w�i����`�I���[�g�s�A�x����w�v���I�B���_�x�ցA�Ƃ����i���ł���B�l�O���́A�����炭�X�s�m�U���i�|���̊v���ƃ}�T�j�G���Ɏ����Ď���̎��摜��`�����k�₳��Ă���X�s�m�U�̎��摜�i���j�́A�}�T�j�G���̏ё��Ɏ��Ă���A�X�s�m�U�͎������A�����L�����������̊v���ƂɂȂ��炦�ĕ`�����Ƃ����������B�\�\�\�M�g�����l�A�Ƃ�����b�ɁA���̏\�S����N�w�I�Ӗ���^�����ŏ��̐l�Ԃł���v
�W���E�h�D���[�Y�u�����v, in�F�A���g�j�I�E�l�O���C���������E����w�쐶�̃A�m�}���[�x,2008,��i��,p.15.
�u�l�O�����킽�����ł���������̂́A����̂܂�����̒��ςł���A���̒��ς́A�X�s�m�U��`�́w�{���x���̂��̂��A�₦�����V������R��̔F���k�X�s�m�U���w�G�`�J�x�ɂ����āA�ō��̔F���`�ԂƂ���s���ϒm�t�\�\�\�M�g�����l�̑M���̂悤�ɁA�����Ɍ�����悤�ɂ��Ă����̂ł���B����́A�����炭�l�O���̗��_�I�l�@�₩��̎��H���A�����ƈȑO����^���̃X�s�m�U��`�̂��̂ɂق��Ȃ�Ȃ����ƂɗR������i�ق��̑����̓_�ɂ�����̂Ɠ��l�ɁA���̓_�ł��킽���̓h�D���[�Y�ɓ��ӂ���j�̂��낤�B�v
�A���N�T���h���E�}�g�D�����u�����v, in�F�A���g�j�I�E�l�O���C���������E����w�쐶�̃A�m�}���[�x,2008,��i��,p.32.

(��)�X�s�m�U���M�w���摜�x(�E)�i�|����h(1647�N��)�w�}�T�j�G���x
�@1968�N5���A�p���A�J���`�G�E���^���̑����ɒ[����������w�w�������x�́A�����܂����E��Ȋ����A���{�ł͗�69�N�́g����E���c�u���U�h��h�_�Ƃ���ًc�\�����Ă̗��ƂȂ��Č���܂����B���Ƃ��猩��Έꎞ�̔M�a�̂悤��������A�̂ł����Ƃ��A����̕������ۂƎv�z�j�ɗ^�����e���Ƃ����ʂ��猩��ƁA�ɂ߂đ傫�ȈӋ`�������Ă����ƌ��킴������܂���B
�@���āA���V�A�u�\���v���v�́A���[�j�����̃}���N�X��`������ˏo�����āu�Љ��`�v�ƃC�R�[���Ō��сA����ȑO�́u�Љ��`�v���܂�ł������l�Ȓ������قƂ�ǎ��ł����Ă��܂����ƌ����܂��i���J�s�l�w���J�s�l�C���^�����[�Y 2002-2013�x,2014,�u�k�Е��|����,pp.9-11�j�B1917�N�ȑO�ɂ́A�ΐ����A�E�C���A���E�����X���A���V�A�̃i���[�h�j�L���u�Љ��`�ҁv�ł����B
�@1968-69�N�́A�������Ēn���ɖ�����Ă��܂��Ă������������A�ӂ����їz�̖ڂ����邫�������ƂȂ����_�ŏd�v���Ǝv���܂��B����ɂ���āA�X�s�m�U�̉��߂���V����܂����B�l�O�����g�o���_�h�Ȃ�������Ƃ��Ắu�U�W�N�v��������ɋ������A�h�D���[�Y���A�v���ƂƂ��Ď��g��`�����Ƃ��D�g�v���ƃX�s�m�U�h�̎����ɒ��ӂ����N����̂��A�̂Ȃ��Ƃ��Ȃ��̂ł��B
�u���ɂƂ��Ďv�z�j�Ƃ́A�l�X�ȊT�O�̃A�[�J�C���̒�����A�ʔO�Ƃ���Ă��錩���ɑ���I���^�i�e�B���Ȏv�l�̉\�������o�������Ă������H�ȊO�̂��̂ł͂Ȃ��B�����̓ǎ҂́A�{���̏��l�@�ɒʒꂷ��v�l�̌`���r�I����Ȃ��c���ł���Ǝv�����A�������̒������i�X�v�����O�{�[�h�j�ɂ��āA�w�X�s�m�U�́x�Ƃ������肩���������ꂽ�w������̂��蓾��v�l�x��T�����鎎�݂ɑ����o���l�����㌻�ꂽ�Ƃ�����A����͖]�O�̍K�^�Ƃ����ق��Ȃ��B�v
�u���Ƃ����v,in�F���r�Ɓw�X�s�m�U�q�G���̎v�l�r�x,2019,���Ώ��X,p.380.
�@�X�s�m�U�����v�z�̂����ꂽ����҂ł����쎁���������q�ׂ��Ă���悤�ɁA�h�D���[�Y�A�l�O����ɂ���ĊJ�n���ꂽ����̃X�s�m�U�lj��́A������������̓�����ɐ荞�ނ��߂̓����Ƃ��āA�X�s�m�U�̎v�l�����ǂ��ƂȂ̂ł���A�g�����ЂƂ̂��肤��v�l�h�g�����ЂƂ̂��肦���ߑ�h��T�鎎�݂ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@�y�P�z�ӎ��Ɩ��ӎ�
�@�w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x�́A�h�D���[�Y�̂T�т̏��_�������߂������A�{�� 241�y�[�W�� 139�y�[�W�́u�w�G�`�J�x��v�T�O�W�v�Ƃ��Ď����̂悤�ȑ̍قɂȂ��Ă��܂��B�w�G�`�J�x��ǂނ��߂̗p�������A���t�@�x�b�g���ɕ���ł��āA���{���ł͂��ꂪ�A�A�C�E�G�I���ɑg�ݒ�����Ă���B
�@���̂悤�Ȗ{���A���߂̃y�[�W���珇�ɗv��E�Љ�Ă䂭�̂́A���܂�Ӗ��̂��邱�ƂɎv���܂���B�����ŁA���r���[�L���Ƃ��Ă͔j�i�ł����A������̋����̂����ނ��܂܂ɁA�C�ɂȂ����ӏ�����e�ʂɂ܂Ƃ߂Ę_���邱�Ƃɂ������Ǝv���܂��B
�u�����S�g���s�_�̎��H�I�Ӌ`�́A�ӎ��ɂ���ď�O�i�S�̎j�𐧂��悤�Ƃ���q�����I�ϗ��ρr������܂ł��̍����Ƃ��Ă����������A���ꂪ���������Ă��܂��Ƃ���Ɍ����B�k�c�l�S�ɂ�����\���͕K�R�I�ɐg�̂ɂ����Ă��\���ł���A�g�̂ɂ�����͐S�ɂ����Ă��K�R�I�ɎȂ̂ł���B�S�g���n��̂������ɂ͈���̑��ɑ��邢���Ȃ�D�z�����݂��Ȃ��B���Ƃ���A�g�̂����f���ɂƂ肽�܂��Ƃ����X�s�m�U�́A����ɂ���ĉ����������Ƃ��Ă���̂��낤�B
�@����́A�g�͎̂�����������ɂ��Ă��F�����Ă���A�����Ɏv�҂��܂�������������ɂ��Ă��ӎ����Ă����Ƃ������Ƃ��B�g�̂̂����ɂ͎������̔F���������̂�����悤�ɁA���_�̂����ɂ�����ɗD��Ƃ����ʂقǂ��̎������̈ӎ��������̂�����B
�@���������āA�݂�����̔F���̏��^�̐�����z�����g�̗͔̂\�����ނ��Ƃ��������ɂ����ł���悤�ɂȂ�Ƃ���A�����ЂƂ̉^���ɂ���āA�������݂͂�����̈ӎ��̏��^�̐�����z�������_�̗͔\�����ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ邾�낤�B�g�̂̂��������̗͔\�ɂ��Ă̔F���悤�Ƃ���̂́A�����ɂ�������s�I���A�ӎ����̂���Ă���������̐��_�̗͔\�����邽�߂ł���A���͔\���Δ䂷���k�Γ��ɒu���ė�������l���Ƃ��ł���悤�ɂ��邽�߂Ȃ̂��B�k�c�l���ӎ��Ƃ������̂��A�g�̂̂����m�̕����Ɠ������炢�[���v�҂̂����ӎ��̕������A�����ɔ��������̂ł���B
�@����Ƃ����̂��A�ӎ��͂��Ƃ��ƍ��o���N�����₷���ł��Ă���B���̖{����A�ӎ��͌��ʂ͎�ɂ��邪�A�����͒m�炸�ɂ��邩�炾�B�k�c�l����̂����̑̂ɁA����ϔO�����̊ϔO�Ɂw�o��x�Ƃ��A���̗��҂̍\���W�͂ЂƂɑg�ݍ��킳���Ă���ɑ傫�ȗ͔\�������炽�ȑS�̂��\�����邱�Ƃ�����A��������������̍\���������̌�����j�Ă��܂����Ƃ����肤��B�k�c�l�����̒����Ƃ́A���������Ă��������X�̍\���W���ׂĂ̌`���k����l�Ɖ�́k�����l�̒����ł���A�S���R�����̖����̕ϗl���Ƃ����ĂƂ钁���ɂق��Ȃ�Ȃ��̂��B
�@�����������́A�ӎ������Ȃ����������l�Ԃ́A�ǂ��܂ł�������������╪������������ɂ��Ă���ɂ����Ȃ��B����́k�g�̂܂��͕��́l�����̎������̐g�̂Əo�����ƂЂƂɑg�ݍ��킳��Ƃ��A����ϔO�����̎������̐S�Əo�����ƂЂƂɑg�ݍ��킳��Ƃ��A����������������ڂ��A�܂����ɂ��������̂�ϔO�ɂ���Ă��̎��������g�̌��\�����������Ƃ��A�߂��������ڂ���B�������݂͂�����̐g�̂Ɂw�N���邱�Ɓx�A�݂�����̐S�Ɂw�N���邱�Ɓx�����A����������Α��̂Ȃ�炩�̑̂����̎������̐g�̂̂����ɁA�Ȃ�炩�̊ϔO�����̎������̊ϔO�k�������̐S�l�̂����Ɉ����N�������ʂ����A��ɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȋ����ɒu����Ă���̂��B
�@�����������g�̐g�̂�S���A���̌ŗL�̍\���W�̂��Ƃɂǂ̂悤�ɐ��藧���A���̑̂�S�܂��͊ϔO���A�����X�̍\���W�̂��Ƃɂǂ����藧���Ă���̂��A�܂������������ׂĂ̍\���W���������ɂǂ̂悤�Ȗ@���ɂ��������č���╪�����Ƃ���̂��\�\�����������Ƃ́A���������݂�����̔F����ӎ��̏��^�̒����ɂƂǂ܂��Ă��邩����A���ЂƂ킩��Ȃ��B�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[,pp.34-37.
���́A�����̃C�^���b�N�A�̖T�_�t�������B
�@ �@
�@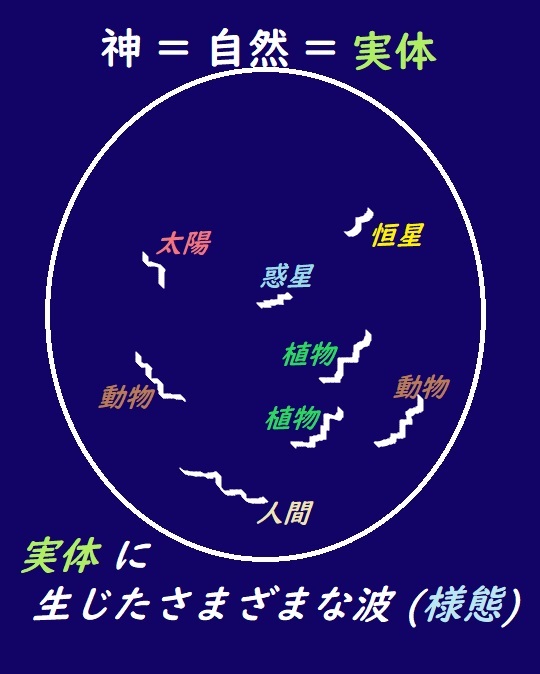
�@�X�s�m�U�́u�S�g���s�_�v�ɂ��ẮA������i�y�K�Ǐ�150�z�X�s�m�U�w�G�e�B�J�x(4)�A�Ƃ��Ɂy17�z�j�ɏ����܂������A�����Ƃ����炢���Ă����܂��傤�B
�@�w�G�`�J�x�̑̌n�ɂ��A���̉F���S�́A���݂�����̂��ׂĂ��܂��ɂ́g�S�́h���s�_���Ȃ킿���R�t�ł���A���������Ă���͖����ł����ĊO���͖����A�B������Ȃ��B�����āA���ꂪ�X�s�m�U�̌n�̓Ƒn�I�ȂƂ���\�\�f�J���g�N�w�y�т��̏�ɔ��B�����ߑ�Ȋw�Ƃ͑傢�ɈقȂ�_�\�\�Ȃ̂ł����A�����s�_���Ȃ킿���R�t�������u�����v�ł���B�l�Ԃ����A�����V�̂��A�܂��ϔO�Ƃ��v�l�ƌ�����悤�Ȃ��̂��܂߂āA���ׂĂ̌X�̎����́u�����v�ł͂Ȃ��āA�s�_���Ȃ킿���R�t�Ƃ����u�����v�ɐ������g�A���邢����(�Ђ�)�̂悤�Ȃ��̂ɂ����Ȃ��B�X�s�m�U�́A
�u�X�̂��̂́w�����̕ϗl�x�Ȃ����w�l���x�ł���B�v
�@�Ƃ����������������܂��iE�TDf5,P14C2,P15,P28,P28Sc�j�B�u�����v�Ƃ́A�u���ꎩ�g�ɂ����đ��݁v������́A�Ƃ����悤�ȈӖ��ł��iE�TDf3�j�B�s�_�t�ȊO�̌X�̎����́A�u���ꎩ�g�ɂ����đ��݁v���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�u�����̕ϗl�v�Ƃ��āA�s�_�t�܂��͑��̌��������ƂȂ��Ă͂��߂đ��݂��邱�Ƃ��ł���B�����Ȃ�����A�u�_�Ȃ��ɂ͑��݂����Ȃ����A�܂��l�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v(E�TP15�j
�@�������āA�s�_���Ȃ킿���R�t���N�_�Ƃ��āA�����鎖�����Y�o����Ă���̂ł����A�s�_���Ȃ킿���R�t�́A�u����(�Ђ낪��)�v�u�v��(�v�l)�v�Ƃ����Q���u�����v�������Ă��܂��B���������āA����ł��s�_�t���炳�܂��܂��u���́v���ݎ��ɐ����A�������s�_�t���炳�܂��܂��u�ϔO�v���ݎ��ɐ����Ă���Ƃ����A�Q�n��̎Y�o�n���邱�ƂɁi��������́j�Ȃ�܂��B���������̂Q�n��́A�����Ɂg�P�P�Ή��h���Ă���A�������傭�̂Ƃ���g�ЂƂ̌n��h�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��iE�UP7�j�B
�@���Ƃ��A�ЂƂ�̐l�Ԃ́A�u�����v�������炢�����u�g�́v�ł���A�u�v���v�������炢�����u���_�v�ł����A�u�g�́v���u���_�v�͊��S�ɑΉ����Ă��܂��B�l�Ԃ��u�g�́v�͂�������̌́\�\�튯�⌌����̉t�\�\����Ȃ�A���̂��ꂼ��͂܂������́i�h�D���[�Y�ɂ��Ε����ǂ��薳������)�u�\���f�́v����Ȃ��Ă��܂��i�ˁF�w���H�̓N�w�x,pp.246,271[��4];E�UL7Sc�j�B�������A�u���_�v���܂��A�u�g�́v�Ɋ��S�ɑΉ������X���u�ϔO�v����Ȃ��Ă��āA�u�g�́v�̊������u���_�v�̊����́A���A���^�C���Ŋ��S�Ɉ�v���Ă���̂ł��B
�@�������͂悭�A���_���g�̂𐧌䂷��Ƃ��A����������A���邢�́A�g�́i���o�튯�j�����_�ɑ��ĕ��̑���^����A���E��F��������A�Ȃǂƍl���܂��B�܂�A�u���_�v���u�g�́v�́A�������ɉe�����p��^���������݂��ƍl����X��������܂��B����́A���̓f�J���g���̍l�����ŁA�f�J���g���ߑ�v�z�̃��W���[�ɂȂ������߂ɁA�ߑ�l�݂͂ȁA�����v�����ނ悤�ɂȂ��Ă���̂ł��B�i���Ƃ��A�╧���ł́A����Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�l���������܂��B�j
�@�������A�X�s�m�U�́u�S�g���s�_�v�́A���́g�e���������h�Ƃ����l���Ƃ͂܂������Ⴂ�܂��B�u�����v�Ɓu�v���v�A�u�g�́v���u�ϔO�v�̂������ɂ́A�����Ȃ���������̂ł��B�e�����p���y�ڂ��Ƃ������Ƃ͈���肦�܂���iE�UP5,P6;�VP2,P2Sc�j�B�܂��������͖�������ǂ��A�����Ɂg�P�P�Ή��h���Ă���A���Ȃ킿�u�������́v�Ȃ̂ł��iE�UP7Sc�j�B���������āA�h�D���[�Y�̌����������A
�u�S�g���n��̂������ɂ͈���̑��ɑ��邢���Ȃ�D�z�����݂��Ȃ��B�v
�@�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̂��Ƃ̎��ۓI�Ȍ��ʂ́A�u�ӎ��ɂ���ď�O�𐧂��悤�Ƃ����q�����I�ϗ��ρr�v�̔ے�ł��B�u���_�v���A�����^����ꂽ���ڂɂ��������āA�u�g�́v��A�u�g�́v�ɋ߂��Ƃ�����u��O�v�ɍ�p���y�ڂ��A�ȂǂƂ������Ƃ͐�ɕs�\�ł��B����l�Ԃ��A�@���⑼�l�̖��߂ɏ]���čs������\�\���邢�͍s����f�O����\�\�ꍇ�ɂ́A�u���_�v���u��O�v���u�g�́v���A���ׂĂ������ɏ]���̂ł��B�ǂꂩ����ɂȂ��đ������A���邢�͐�����Ƃ������Ƃ͂���܂���B
�@�Ƃ���ŁA�u�g�́v�̊������u���_�v�̊����́A���S�Ɂg�P�P�Ή��h���Ă���̂ł����A�u���_�v�̂Ȃ��ŋN�����Ă��邱�������������A�l�Ԃ͂��ׂ��u�ӎ��v���Ă���킯�ł͂���܂���B�������u�g�́v�̒��ł����錻�ۂ��ׂĂ�F���ł���킯�ł͂Ȃ��̂Ɠ������Ƃł��iE�UP23,P24,P27,P28,P29�j�B
�u���������āA�݂�����̔F���̏��^�̐�����z�����g�̗͔̂\�����ނ��Ƃ��������ɂ����ł���悤�ɂȂ�Ƃ���A�����ЂƂ̉^���ɂ���āA�������݂͂�����̈ӎ��̏��^�̐�����z�������_�̗͔\�����ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ邾�낤�B�v
�@���Ȃ킿�A�������́A�������C�Â��Ȃ��ł����u�g�́v�́u�͔\�v��m�邱�Ƃɂ���āA�����ɁA���������u���_�v���s���ӎ��t�́u�͔\�v��m�邱�Ƃ��ł��܂��B����́A�u�S�g���s�_�v�̓��R�̋A���ł��傤�B
�@�X�s�m�U�ɂ��A�u�\�S�v�ȔF���Ƃ́A���̂��Ƃ����́u�����v�ƂƂ��ɔF�����邱�Ƃł��B�������A�������̔F���́A����ӂ��ɂ́A�u�����v��F������Ƃ���܂ł͒B�����Ȃ��B�����A���ʂ������A�������͊�Ō��A�����A�����āA���邱�Ƃɑ��ăC���[�W��ӌ���������ƂɂȂ�܂��B����͂˂��u��\�S�v�ȁu���������v�F���ƂȂ炴������܂���B
�@�Ƃ���ŁA�h�D���[�Y�������ŋ������ďq�ׂĂ���̂́A���́u�����v�Ƃ́A��̓I�ɂǂ��������̂��Ƃ������Ƃł��B�Ƃ�킯�A���������݂�������u�g�́v���u���_�v�ɋN���錻�ہ\�\�瑊�I�ɂ����c���ł��Ȃ��A���݈ӎ��Ɋ�Ă���悤�Ȍ��ہ\�\�ɂ��āA�����������ӂ������Ȃ��ʼn߂����Ă���A�����́u�����v�Ƃ́A�ǂ����������̂Ȃ̂��H ���������u���_�v�u�g�́v�̊����́u�����v�W�́A�����������܂����E�⑼�̐l�тƂƂ̂������́A���G�ŗ����I�ȁu�G���v�ƌ��̃v���Z�X���܂�ł��܂��F
�u����̂����̑̂ɁA����ϔO�����̊ϔO�Ɂw�o��x�Ƃ��A���̗��҂̍\���W�͂ЂƂɑg�ݍ��킳���Ă���ɑ傫�ȗ͔\�������炽�ȑS�̂��\�����邱�Ƃ�����A��������������̍\���������̌�����j�Ă��܂����Ƃ����肤��B�k�c�l�����̒����Ƃ́A���������Ă��������X�̍\���W���ׂĂ̌`���k����l�Ɖ�́k�����l�̒����ł���A�S���R�����̖����̕ϗl���Ƃ����ĂƂ钁���ɂق��Ȃ�Ȃ��̂��B�v
�@���������u�\���W�v�́u�`���v�v���Z�X�̌��ʂƂ��āA���傫���u�\���W�v���`������Ă䂭�ꍇ�ɂ́A�������́u�����́v�͑��債�A���������u��сv�̊�����l�����܂��B���ɁA�u��́v�̃v���Z�X�ɂ���āA���������u�\���W�v�̈ꕔ���j�ꂽ��A���������������̐g�̂�����Ă����u�\���W�v���S�ʓI�ɉ�̂��Ă��܂��i�����S����j���Ђɂ݂܂���Ƃ��ɂ́A�������́A�u�߂��݁v���u����v�̊�����邱�ƂɂȂ�܂��B�i�u����v�́A�s������u�߂��݁v�̊���ł��BE�VP18Sc2�j
�@���������ʏ�̏ꍇ�Ɉӎ�����̂́A���̍ŏI�I�Ȍ��ʁA���Ȃ킿�A�u��сv�܂����u�߂��݁v�̊�����Ȃ̂ł��B�킽�������́A���ʂƂ��Ắs����t��F�����邾���ŁA���́u�����v�W�ɂ����u�\�S�v�ȔF���������Ȃ��̂ŁA�����s����t�́u�����v�ɂ��āA�����Ƃ�ł��Ȃ������Ⴂ�̑z�������Ă��܂��܂��B
�@���������āA�h�D���[�Y�������Ŏ����Ă���̂́A�u���ӎ��v�̉𖾂Ƃ������̐�ɂ́A�l�Ԃ́A���̐l�Ԃ����Ƃ��u�\���W�v���u����v�܂��́u�����v�Ɏ���s�G���t�̃v���Z�X�����邱�ƁA�Ђ��Ắs�����Љ�t�́u�\���v�Ɓu��́v���Ђ��������Љ�I�A�����I�ȃp�[�X�y�N�e�B�����Ђ炭���Q������A�Ƃ������ƂȂ̂��Ǝv���܂��B
�u���������킯�ŁA�c�Ȏ��͍K���ł���Ƃ��A�ŏ��̐l�k�A�_���l�͊��S�������ȂǂƂ͎������ɂ͂܂��l�����Ȃ��B�ނ�͂��̂��Ƃ̌������{�����m�炸�A�����N���Ă���o�������ӎ��������ŁA���̖@���͂��߂Ȃ��܂܂Ђ����猋�ʂ������ނ邱�Ƃ�]�V�Ȃ�����Ă��邽�߂ɁA�Ȃɂ��Ƃɂ�����J���������A���̕s���S���ɉ������s���ƕs�K�̂����ɐ����Ă���̂�����ł���v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[,p.37.
�@���́��u�c�Ȏ��v�̖��ɂ��ẮA�߂����߂āA�����������Ă��������Ǝv���܂��B
�@�y�Q�z�q���Ƒ�l
�@�w�G�`�J�x�́A�X�s�m�U���g���A������Ɉ�ʓI�����������̓@�ɂƂ��ꂽ�����������Ă��邽�߂ɁA�킩��ɂ����Ȃ��Ă���ǖʂ��A��������悤�ȋC������B�ނ̐^�ӂ��ǂ݂Ƃ�ɂ����Ȃ��Ă��܂��Ă���̂��B���̈���A�g�q���Ƒ�l�h�Ƃ������A���邢�́g���n�h�ɂ܂����Q���낤�B
�@�Í����������̎v�z�Ƃ́A�q�������l�ւ̐S�g�́g���B�h�́A����ׂ����Ƃł���A�K�v�Ȃ��Ƃł�����A�Ƃ����O��̂��ƂɎq�����l�@����B���������A�q���͑�l�ɔ�ׂĖ����B�ȁA�������Ԃƌ��Ȃ���A�ے�I�ɔc�����邱�ƂɂȂ�B�X�s�m�U����O�ł͂Ȃ��B
�@�w���q��q���́A�O������̉e����I����Ɂu��]�v���₷�������ł���B����Ƃ͑ΏƓI�ɁA�u�����̓����v�ɂ��������Đ�������u���R�Ȑl�v�Ƃ́A���������u�����v�������n�����j�q�ł���A�ƁB�X�s�m�U�̂��̓I�Ȏv�����݂��A�k���Ș_�̎��w�ɓǂ݂Ƃ�Ă��܂��̂��B
�@���̂��߂ɁA�X�s�m�U�̗��z�Ƃ���g���n�h�Ƃ́A���́A�P�ɑ�l�ɂȂ邱�ƁA�Љ�ɏ������邱�ƂƂ́A�܂������ʂ̂��Ƃ��\�\�\�Ƃ����A�������Ă͂Ȃ�Ȃ���ʂ��A�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���B
�@�h�D���[�Y���܂��A�w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x�ł́A�O�߂Ō����悤�ɁA�u�q�ǂ��v�́u�s���S�v�䂦�̕s�K���������A�u�c�Ȏ��͍K���ł���Ƃ��A�d�d�܂��l�����Ȃ��B�ނ�͂��̂��Ƃ̌������{�����m�炸�A�d�d�Ђ����猋�ʂ������ނ�d�d���̕s���S���ɉ������s���ƕs�K�̂����ɐ����Ă���̂�����ł���v�Əq�ׂĂ����B����ɐ旧���w�X�s�m�U�ƕ\���̖��x(1968�j�ł́A�q�q�ǂ��r��������Ȃ߂Ă���A�u�q�ǂ�����v�́u���́v�Łu�����ȏ�ԁv���Ƃ܂Ō��߂��Ă����F
�u�w�X�s�m�U�������Ό����悤�ɁA�q�ǂ�����͖��͂Ɨꑮ�̏�ԁA�ɓx�ɊO���̌����Ɉˑ����A�ǂ����Ă���т����߂��݂̂ق��𑽂������Ă��܂������ȏ�Ԃł���B����قǎ�����������̊����͂��番������Ă��鎞�͌����ĂȂ��B�x�v
���r�Ɓw�X�s�m�U �������̃|���e�B�N�X�x,2006,���k�o��,p.117 �����B
�@�������ɁA�u���R�Ɨ�]�v�u�I����v�u�����͂̑����v�Ƃ������w�G�`�J�x�̘_���ɂ��������A���̂悤�Ȍ��_���A������������Ȃ���������Ȃ��B
�@�Ƃ��낪���̈���ŁB�w��̃v���g�[�x�ł́A�h�D���[�Y�́A���̂悤�Ɍ����F
�u�w�q�ǂ������̓X�s�m�U��`�҂ł���B�k�c�l�X�s�m�U��`�Ƃ́A�N�w�҂��q�ǂ��Ɂq�Ȃ�r���Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�x�v
�u�w�A���`�E�I�C�f�B�v�X�x�ɂ����Ă��w��̃v���g�[�x�ɂ����Ă��A�~�]�̃[���_�Ȃ����Ɍ��_�Ƃ��Đ₦�����y���ꂽ�̂��A������w�튯�Ȃ��g���x�ł���B�튯�Ȃ��g���Ƃ́A�����b�A������g�D�������ۂ���A�g�̂ɂ����鍷�ى��̉^���̋Ɍ��̂��Ƃł��낤�B�����߂̎�A�������߂̑��A���邽�߂̖ڂƂ������튯�ɑg�D�����ȑO�ɁA�������̐g�͖̂��������̂ł��Ȃ��G�l���M�[�ԂƂ��Ă���������A������g�D���𖢌���̂��̂Ƃ��ď����������Ă���B���l�ɁA��̂⍑����j�⏗�ɑg�D�����ȑO�Ɏ������́A����Εs��㖼���qon�r�k�q���҂��r�\�\�M�g�����l�̏�Ԃ��Ă���A�����ł͑������l�̂Ƃ��Ă̐��̂���悤�����̂܂܂ōm�肳��Ă���B���̎��A�����I�Ȉʒu��^������̂��A������q�q�ǂ��r�Ȃ̂ł���B�v
���r�Ɓw�X�s�m�U �������̃|���e�B�N�X�x,pp.115-116.
�@�܂�A�u�튯�Ȃ��g���v�Ƃ́A�������̗~�]�𐮏����郁�J�j�Y���ɂƂ炦����ȑO�́A�~�]�̖���`�Ȍ����I��ԁA�܂��B�g�Ƃ��āA�Љ�I�K�����O�́A�͂����̐������Ƃ��Ă̎������́u���̂���悤�v���w���Ă���B�������q�q�ǂ��r�����A�u�튯�Ȃ��g���v���Ƃ����̂��B
 �@
�@
�u�������ő��^�|���I�A���܂���̉����ꂸ�A���ʕs�\�ŁA�ے�I�Ȍ_�@���������A�����Ȋ�т����鑽�l���Ƃ��Ắq�q�ǂ��r�B�w�튯�Ȃ��g���͎q�ǂ�����Ɍ��т��Ă���B�k�c�l�튯�Ȃ��g���͎q�ǂ�����̃u���b�N�A�Ȃɂ��Ɂq�Ȃ邱�Ɓr�ł���B�x�m�h�D���[�Y�C�K�^���w��̃v���g�[�x�n
�@�k�c�l�h�D���[�Y�ƃK�^���́A�q�ǂ����튯�Ȃ��g����b��ɂ���Ƃ��ɁA�܂�ł����܂�̂悤�ɃX�s�m�U���Q�Ƃ���B�w�ŏI�I�Ɋ튯�Ȃ��g�̂ɂ��Ă̈̑�ȏ����ƌ����A�w�G�`�J�x�ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���x�A���邢�́w���ׂĂ��튯�Ȃ��g���̓X�s�m�U���]����x�c�c���X�B
�@�����A���̂悤�ȃh�D���[�Y�ƃK�^���̎咣���ʂ�Ƃ�A�k�c�l�X�s�m�U��`�Ƃ́A�[�I�Ɂw�q�ǂ��ɂȂ邱�Ɓx��ڎw���N�w���Ƃ������ƂɂȂ�B���Ƃ���A������g�D�����玩�R�ŁA�K�͂�@�Ƃ����T�O����͍ł������Ƃ���ɂ���q�ǂ��ɂȂ邱�Ƃ��A�X�s�m�U�N�w�̐^�����Ȃ̂��낤���B�k�c�l
�@���̌��u���ǂ�����������悢�̂��낤�B�k�c�l
�@�q�q�ǂ��ɂȂ邱�Ɓr���X�s�m�U��`�ł���Ƃ�������ƁA�q�ǂ��������͂Ɨꑮ�̏�Ԃł���Ƃ����L�q�̊Ԃɂ́A�\�ʏ�̂͂����肵���ꗂƂ͕ʂɁA���ɂ͉���������Ȓ��a�̂悤�Ȃ���������悤�Ɋ������ĂȂ�Ȃ��v
���r�Ɓw�X�s�m�U �������̃|���e�B�N�X�x,pp.116-118.
���́A���p���̖T�_�t�������B
�@�y�R�z�q�ǂ��݂͂ȃX�s�m�U��`��
�@���́A�q�q�ǂ��r�ɑ���X�s�m�U���h�D���[�Y�̕]��������A�Ƃ��������A��쎁�̘_���ɉ����Č��čs�������Ǝv���܂��B
�u�F���Ƃ́A��̂̂����Ȃ���Ƃł͂Ȃ��B�ϔO�����_�̂����ɒ藧���݂邱�Ƃł���B�w�������Ď��������A�����ɂ��ĂȂɂ��Ƃ���藧������ے肷��̂ł͂Ȃ��B�����݂����炪�A�������̂����ŁA���g�ɂ��ĂȂɂ��Ƃ���藧�܂��͔ے肷��̂ł���B�x�i�w�Z�_���x�U,16�͂�5�j�k�w�Z�_���x�̓X�s�m�U�ŏ��̓N�w�_���B1661�N�����M�\�\�\�M�g�����l�B�k�c�l�F���Ƃ́A�ϔO�̎��Ȓ藧�A�ϔO�́w�J�W�x���Ȃ킿���W�ł���A�k�c�l�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,2002,���}�Ѓ��C�u�����[,p.167.
�@�u�S�g���s�_�v���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�X�s�m�U�ɂƂ��āu�v���v�����E�ɑ��݂��鏔�ϔO�́A�N���l�Ԃ��l�����Ƃ��A���������Ƃ������ƂƂ͂������Ȃ��A�s�_���Ȃ킿���R�t�́u�l�ԁv�Ƃ��āA���Ƃ���q�ϓI�ɑ��݂�����̂ł��B�u�����v�����E�ɑ��݂��邷�ׂĂ̕��ɑΉ�����ϔO���A�����ɂ͂���܂��B
�@���������āA�u�F���v�Ƃ́A�l�Ԃ̍s�Ȃ���̓I�ȉc�݂ł��Ȃ��B�����̂ق����A�l�Ԃ��u���_�v�̒����u�ϔO�v�Ƃ��Ď��ȓW�J����̂ł��B
�u�k�藝�P�V�l�_�݂͂�����̖{���̖@���ɂ���Ă̂݊������A���ꂩ�����������Ċ������邱�Ƃ��Ȃ��B
�@�@�@�k�n�P�l�ȏ�̋A���Ƃ��āA��P�ɁA�_���ꎩ�g�̖{���̊��S���̂ق��ɁA�_���O�����炠�邢�͓������犈�������悤�Ƃ��邢���Ȃ錴�������݂��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�B�k��P���l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.35-36.
�@���Ȃ킿�A�N���l�Ԃ��u���_�v���A�s�_���Ȃ킿���R�t���������āA���̌X�́u�l�ԁv�̖{��������Ȃ�Ƃ��J��������ȂǂƂ������Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B�������s���R�t�����҂��ɋ������ꂤ��Ƃ�����A�u���Ȍ����v�Ƃ����s�����t�̖{���iE�TP6L,P7Dm�j�ɔ����܂��B�i������Ƃ����āA�u�����v��ے肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł����B�j
�u������o�����́A�����c�������̂̈ӌ��ɂ�����炸�A���̂����玄�����ɐ��N���Ă���̂ł���A���������o�����ɂ��Ă̊ϔO�̑��̂��������̐��_�Ȃ̂ł���B�F���͂�����̂ł͂Ȃ��A���N������̂ł���B�k�c�l���������āA���ꂩ��̋c�_�ʼn��x���o�Ă����q�ϔO�r�Ƃ������t�́A���̂ɂ��Ď����������Â��閼�̂�m�o����`�ۂ̂��Ƃł͂Ȃ��A���̂��̂������\�����邠��悤���ꎩ�̂̂��Ƃł���Ƃ������Ƃ��A��������Ɩ��L���Ă��������B�v
���r�Ɓw�X�s�m�U �������̃|���e�B�N�X�x,p.120.
�@�������A�������đ��݂����u�ϔO�v���A�������͓��R�ɒm�肤��킯�ł͂���܂���B�ނ���A���������m�邱�Ƃ��ł��Ă���̂́A���̂��������ꕔ�ł���A�������A�������̔F���͑����̏ꍇ�A�u��\�S�v�ȁs�z���m�t�ɂ����܂���B
�@�������́A���܂��܂Ȏ������g��ށh�ɂ܂Ƃ߁A�g���O�h�����āA����ł����̎�����m�����Ǝv������ł��܂��B�������A�g��ށh�́A�ق�̕\�ʓI�ȓ������������������ł���A�g���O�h�́A�Ȃ�炻�̂��̂̓����Ƃ͂������̂Ȃ������L���ł��B���̎�́u��ʊT�O�v�\�\�\�u�l�ԁv�u���v�Ȃǁ\�\�\�́A�����̎��ۂ̂���悤�\�\�\�u�\���W�v��A���̐����A�܂����̕��Ɗւ������\�\�\�������\�����Ă��܂���iE�UP40Sc1�j�B�g���̖̂��O�h�ɂ��F���́A�u�\�S�v�ȔF���ł͂Ȃ��̂ł��B
�u�ÓI�i�X�^�e�B�b�N�j�����`�I�Ȃ����̔F���́A����\���I�łȂ��Ƃ����_�ŕK�R�I�ɔ�\�S�ȊϔO�ł���B���鎖�����A���̂��̂���Ǘ�������������Ƃ��ĂƂ炦��Ƃ��A�킽�������͂��̑�P��̔F���k�s�z���m�t�\�\�M�g�����l�̏�Ԃɂ���B�w�l�ԁx���w�n�x���w���x���A�w���݁x��w���́x�Ƃ������T�O�ł���A�X�s�m�U�ɂ��w����߂č��������ϔO�x�mE�UP40Sc�n�ɂ����Ȃ��B�k�c�l���̂悤�Ȕ�\���I�ŃX�^�e�B�b�N�ȃC�}�[�W�����A�䂳�Ԃ�A��̂��A�g�݊�����́B�����Ă��̂悤�ȗ͂��̂��̂ƂȂ����������̂���悤�B���ꂪ�\�S�ȊϔO�ł���A�X�s�m�U�̎��H�I�F���_�̎��j��͂Ȃ̂ł���B�v
���r�Ɓw�X�s�m�U �������̃|���e�B�N�X�x,pp.123-124.
�@�������́A���̂悤�ȐÓI�ŏ펯�I�E�\�ʓI�Ȍ��t�ɂ�鐢�E�̗����ɑ��āA�ʊ��ɗ����������A������u�䂳�Ԃ�A��̂��A�g�݊�����́v���s�g�����u�j��́v����F���҂��A���Ƃ��A�ꕔ�̎��l�⓶�b��Ƃ̂Ȃ��ɔF�߂邱�Ƃ��ł���ł��傤�F
�u�q���̎��ɁA�[�������Ă���́A�\�\�\��������͂����Ƃ��āA���܂�ɎU���I�ɂȂ�̂�߂��ނł�@�c�c�@�����A���t�͐������邽�߂̂��̂Ȃ̂��A��������̂܁T�����ӂɗp����Ƃ��ӂ��Ƃ́A���ȍ���ł��āv
��������u�͏�ɒ悷�鎍�_�vin�F�w�V�� ��������S�W�x,��S���E�{����,pp.120-121.
�u��A�w���ꂪ�肾�x�ƁA�w��x�Ƃ��Ӗ��������ɂ���O�Ɋ����Ă���A���̎肪�����Ă���T�悢�B�v
��������u�{�V�����̐��E�v(��e), in�F�w�V�� ��������S�W�x,��S���E�{����,pp.154-155.
�u��A�����̖L�������̂��̂Ƃ́A�K�포������ƒm�炸���ČȂ�����݂ċ����邪�@�����̂ł���A�܂蕨�������ꂾ���Ŗʔ�������ʔ�����ԂɌ����鏊�̂��̂ŁA�|�p�Ƃ́A�ʔ�������ʔ������̂��ƂŁA�����Ĉ�ʐ����̏�Ől�X���G��ʐ��E�̂��ƂŁA���͂Ύ��������̋���̔��W�ɂ�Đ�������̂ł���A�k�c�l
�@�����ȑO�A�܂肱�ꂩ�疼����o���˂Ȃ�ʂ��Ƃ́A���ɍ݂閼���ɂ�Đ����邱�Ƃ��́A��������{�̋ꂵ�݂�v����̂ł���B�v
��������u�|�p�_�o�����v(��e), in�F�w�V�� ��������S�W�x,��S���E�{����,pp.139-153.
�u�����ĊԂ��Ȃ��A���̋D�Ԃ��猩�������ꂢ�ȉ͌��ɗ��܂����B
�@�J���p�l�����́A���̂��ꂢ�ȍ�����k�l�܂݁A���ɂЂ낰�A�w�ł������������Ȃ���A���̂₤�ɉ]���Ă��̂ł����B
�@�w���̍��݂͂�Ȑ������B���ŏ����ȉ��R���Ă��B�x
�@�w�������B�x�ǂ��łڂ��́A����Ȃ��ƏK�����炤�Ǝv�ЂȂ���A�W���o���j���ڂ��蓚�ւĂ�܂����B
�@�͌����I�́A�݂�Ȃ����Ƃق��āA�������ɐ����≩�ʂ�A�܂������Ⴍ�����ᰋȂ�����͂����̂�A�܂��ł��疶�̂₤�Ȑ��������o���|�ʂ��ł����B�W���o���j�́A�����Ă��̏��ɍs���āA���Ɏ���Ђ����܂����B����ǂ����₵�����̋�͂̐��́A���f���������Ƃ����Ƃق��Ă�̂ł��B����ł��������ɗ���Ă���Ƃ́A��l�̎��́A���ɂЂ������Ƃ����A�������₢��ɕ������₤�Ɍ����A���̎��ɂԂ������Ăł����g�́A���������ӌ��������āA���炿��ƔR����₤�Ɍ������̂ł��킩��܂����B�k�c�l
�@��l�́A���������̍�������݂̎��������Ȃ���A�܂��������̕��߂���čs���܂����B����̏��ɂ́A�g���₳������Ȃ̂₤�ɔR���ĊA�E��̊R�ɂ́A�����߂���L�k�ł��������₤�Ȃ������̕䂪��ꂽ�̂ł��B�v
�u�@�@�s���z�����ӂ��甗�Ă���Ƃ���
�@�@�@�@�����ɂ�̉���Ƃ����t
�@�킽�����͂͂����������Ă��邢�Ă��̂�
�@�����A�A�y���y���A�킽�����̉����Ƃ�������
�@�킽�����͂���Ԃ炭�Ԃ��
�@���݂����̋����Ȃ܂��Ȃ�����������
�@�ǂ�Ȃɂ킽�����͂��݂����̐̂̑����Ƃ�
�@�����n�̕Ŋ�̌Â��C�݂ɂ��Ƃ߂����炤
�@�@�@�s����܂�Ђǂ����z���t
�@�@�@�@�@�k�c�l�v
�u����̐����@���ׂĂ̂��݂݂͂Ȑ�͂��
�@�Ђ���͂��������Ƃ܂�Ȃ�
�@�����炠��Ȃɂ܂��炾
�@���z�����炭��܂͂Ă��ɂ����T�͂炸
�@����͐�����ʂق��̂܂�����������
�@���Ƃɂ����낢�}�a�G�������_
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�@�i���������@�q�t����
�@�@�@���̒y���o�����_�������Ȃ���
�@�@�@�܂�œV�̋��n�̃T���A�u���c�h�ł��j
�@�@�i����@���ꂢ����
�@�@�@�_���@���n��
�@�@�@�V�̃T���A�u���c�h���@�_���j
�@������ό��̐F�ʂ�����
�@�c�c�����������@�ق߂�Ђ܂ȂǂȂ�
�@���ʂ͂��͂��ω��͂��₩
�@���܂͈�ނ�̌y�����C�ɂȂ�
�@�뉺���x�̐^��n�}�̂Ȃ���
�@���ƂƂ��ď����Ă��܂�
�@�@�@�@�@�k�c�l�v
�@��������̏ꍇ�ɂ́A���t���������錴���̋���ɑk�邱�Ƃɂ���āA�܂��A���t�����y�Ƃ��āA���Y���Ƃ��āA���o�I�Ɉ������Ƃɂ���āA�u�j��́v��n��o���Ă����ƌ����Ă��܂��B���玩�g�̐����ɂ��A�����Ȃ�܂��B�i�ˁF�u�S�ۃX�P�b�`�v�_���� �R�g���́h�Ɩ��O (i)���������j
�@�{���̏ꍇ�ɂ́A�ʏ�͌������Ȃ��悤�Ȍ��t�ǂ������Ԃ��������Ƃɂ���āu�j��́v��n��o���A���E�̏펯�I�ȑg����ے肵�ēƎ��̑g�����������C���[�W���E���\�z����Ƃ�����@�\�\�u�ے�I�]�����I�g���̃��g���b�N�v�\�\����g���Ă��܂��B�������A�������g�A���E�̂��������C���[�W�́A�������l���o���̂ł͂Ȃ��A���E�̂ق��������Ă��āA�����͂������瓦��邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƌ����Ă��܂� �i�ˁF�u�S�ۃX�P�b�`�v�_���� �S�g������h�Ɛ��E (i)�u�S�ہv�j�B
�@�@�i�u�ے�I�]�����I�g���̃��g���b�N�v�ˁF�w��͓S���̖�x�\�\�u���J�j���Ƃ͉��҂��H(6)�y1.13�z �w��͓S���̖�x�\�\�u���J�j���Ƃ͉��҂��H(7)�y2.1�z �y�a�k�T�L�z���R�̐M���A��M�̋L���y4.1�z�j
�@���āA�������Ă悤�₭�A�b���q�q�ǂ��r�ɋ߂Â��Ă��܂����B
�@
�@��ɋ��������l�����́A�ʏ�Ȃ���u�\�S�v�ȔF�����ז����錾��Ƃ������̂��A����t��Ɏ���āA���ʂȊ��o�Ɨ����U�ɂ���āA�u�\�S�v�ȊϔO�ɒB���Ă����Ƃ������Ƃ��ł��邩������܂���B�������A����͖{�l�������Ȃ�����g��V�h�ł����āA�]�l������ɐ^���ł���悤�ȕ��@�ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@����ł́A�������͂����ɂ�����A�u�\�S�v�ȊϔO�ɒB���邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���H �N�����K���o���邱�Ƃ��ł���悤�ȕ��@�͖������̂ł��傤���H �X�s�m�U�́A�ǂ�ȕ��@���q�ׂĂ���ł��傤���B
�@�|�p�Ƃł͂Ȃ���ʐl���A�u�\�S�v�ȔF�����߂������@�Ƃ��āw�G�`�J�x�ɏ�����Ă���̂́A�s���ʊT�O�t�Ƃ�����@�i�ˁF�y�K�Ǐ�150�z�X�s�m�U�w�G�e�B�J�x(9)�y37�z�j�ł��B�s���ʊT�O�t�ɂ��ẮA�u��Q���v�k�藝�R�W�l�Ɓk�藝�R�X�l�ɏ�����Ă��܂����A�����ŏd�v�Ȃ̂́A�k�藝�R�X�l�̂ق��́s���ʊT�O�t�ł��B
�u�k�藝�R�X�l�l�Ԑg�̂Ȃ�тɏ�ɐl�Ԑg�̂��h�������������̊O���̕����ɂƂ��ċ��ʂœ��L�Ȃ��́A�����Ă����̊e���̂̕����̒��ł��S�̂̒��ł������悤�ɑ��݂�����̂ɂ��Ă̊ϔO���܂��A���_�̂����ɂ����ď\�S�ł��邾�낤�B
�@�@�@�@�k�n�l���̋A���Ƃ��āA�g�̂����̏����̂����ʂȂ��̂���葽�����ɂ���A���_�͑����̂��̂����ꂾ���\�S�ɒm�o���邱�Ƃ��ł���B�k��Q���l�v
�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.140-141.
�@
�@�k�藝�R�W�l�̂ق��ł́A�u���ׂĂ̂����ɋ��ʂŁA�����̒��ł��S�̂̒��ł������悤�ɑ��݂�����́v�Ƃ���Ă����̂��A�����ł́A�u���ׂĂ̂����ɋ��ʁv�̕������A�u�l�Ԑg�̂Ȃ�тɏ�ɐl�Ԑg�̂��h���������������O���̕��̂ɂƂ��ċ��ʂœ��L�Ȃ��́v�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�u���ׂĂ̂��̂ɋ��ʁv�ȓ����Ƃ́A�u�����v�����Ȃ�A���̂́g�^���ƐÎ~�h������ł���悤�ȁA�����Ƃ���{�I�ň�ʓI�ȓ����ł��傤�B���̔F�����u�\�S�v�Ȃ̂́A���R�̂��ƂƂ������܂��B
�@�������A������u�l�Ԑg�́v�̏ꍇ�ɂ́A������u��Ɏh������v�u���������O���̕��́v�ɋ��ʂł���悢�̂ł��B����A�ƂĂ����[�J���ȁu�����v�ł���A��ʐ��̒Ⴂ����Ȑ����ł��B���̔F�����u�\�S�v�ł��肤��̂́A�����u�l�Ԑg�̂��h���v���Ă���Ƃ����A����I�E�p���I�ȁg�G���h�̊W�����邩��ł��B
�@���Ƃ��A�����u���́v���l�ԂȂ�A����������킹�Ă��铯���l�⓯���A�܂��A�Z���ȐڐG���d�˂Ă�����l�ǂ�����Ƒ��A�Ƃ������W���l�����܂��B�������̂������ɋ��ʓ_�i�����̍��v�j�������āA�����̓I�ȕR�т��\������̂łȂ���A�i��������ڐG�W�͕ۂĂ܂���A�@�u���ʁv�ȓ��������邱�ƂƁA�A�����I�Ɍ������邱�ƂƁA�B�e�����A�܂��u�\�S�v�ȔF���������ƁA���̂R�́A�قڃC�R�[���ł��B
�u�Q�̑̂́A�݂��̍\���W���ЂƂɑg�ݍ��킳��Ƃ��A��荂���̗͔\�����P�̏W���́A�������z�����P�̑S�̂��\�������k�c�l���ʊT�O�́A�Q�܂��͂���ȏ�̑̂̂������̍\���I������A�����Ă��̂悤�ȍ���ɂ��ƂÂ��\����̓����\���Ă���B�k�c�l���ʊT�O���e�̐��_�ɂƂ��ċ��ʂł���Ƃ������Ƃ́A�����܂ł����̂����ł�����I�Ȃ��Ƃɂ����Ȃ����A���̏ꍇ�ł���͂苤�ʐ��ɂ͑召�͈̔͂�����B���_�ɂƂ��Ă��ꂪ���ʂł���̂́A���̐��_�́k�Ώۂ���l�g�̂����������\���I�����\����̓���ɂ�������Ă��邩����ł̂��Ƃ����炾�B�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,pp.103-104.
�@�܂�A�u���ׂĂ̂��̂ɋ����v����g�^���ƐÎ~�h�̂悤�ȓ����𗝉�����A�Ƃ����k�藝�R�W�l�̕��ՓI�ꍇ�Ƃ͈قȂ��āA���́k�藝�R�X�l�̂ق��́s���ʊT�O�t�́A�l�Ԑg�̂ƕ��̂Ƃ̂������A�l�Ԑg�̂Ɛl�Ԑg�̂Ƃ̂������������̐ڐG�ƁA�g���ʓ����h�ɂ��ƂÂ��u����v��K�v�Ƃ��Ă��܂��B�ނ���A�u����v����ɂ����āA�s���ʊT�O�t�̐����́A�u����v�̓I���ʂɂ����Ȃ��A�Ƃ܂Ńh�D���[�Y�͌����܂��B
�@���̂悤���u����v�́A�u���傫�Ȋ��S���ւ̈ڍs�v���Ӗ����܂�����A����������e�u�g�́v�Ɂu�����́v�̑�������Ȃ����A�e�u���_�v�ɑ����u��сv�̊���������܂��B�����u��сv�̊���A�e�l�ɑ��āA���l�i�܂��͑��̕��́j�Ƃ��u�\���I����v���A�����������u�\�S�v�ȔF�������߂�����U���Ƃ��ē����̂ł��F
�u���̎������́A�݂�����̐g�̂ƓK������̂Əo��Ƃ��A�����ɂ��鉽�����g�Ƌ��ʂł��邩�͂܂��\�S�ɔF������ɂ͂�����Ȃ��Ƃ��A���łɎI��Ƃ��Ă̊�т̊���𖡂���Ă���B�k�c�l�����͔\�A�����k��l����͔\�̑���ɂق��Ȃ�Ȃ����̊�т̊���͎������������k�s���ʊT�O�t�\�\�M�g�����l�Ɍ����킹�Ă����B��т̊�������ʊT�O�̗U���ƂȂ�̂ł���B�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,p.105.
�@�܂��A�k�藝�R�X�l�́k�n�l���q�ׂĂ���悤�ɁA���̂悤�ȁE���̐g�̂╨�̂Ƃ��u�\���I����v���u��葽�����ɂ���v�A�u���_�v�́g�v�҂����\�́h�͂��ꂾ�����܂��Ă䂭�̂ł��B���Ƃ��A��Ɉ��p�����{���̂悤�Ȏ��l�́A�̋��̖�R�⎩�R�̂Ȃ��ɐ��荞��ŁA�����A�����⓮���A�����Ēn���̐l�X�Ƃ̐ڐG�����I�ɐ������̌����邱�Ƃɂ���āA�����̊��ɑ���A����u�\�S�v�ȔF���\�͂�g�ɂ��čs�����ƌ����܂��B
�@�܂��A���肪�����ς�l�Ԃ̏ꍇ�ɂ́A���Ԃ�W�c���\�����ē���I�ȁs�G���t���d�˂Ă䂭�������A�l�ԊW�Ɋւ���v�l�\�͂����߁A����ɂ��L�v�ȏW�c�`�����\�ɂ��Ă���邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��ł��傤�B
 �@
�@
�u�ȏ�̂��Ƃ܂���ƁA�`���ɋ������悤�Ƀh�D���[�Y�͂Ȃ��q�ǂ����X�s�m�U��`�҂ł���Ƃ��A�X�s�m�U��`�Ƃ͓N�w�҂��q�ǂ��Ɂq�Ȃ�r���Ƃł���A�Əq�ׂ����̈Ӗ����͂����肷�邾�낤�B�X�s�m�U��`�҂ł�����莄�����́A���炪��т������݂�����̊����͂����߂���̂ƌ��т����Ƃ��A�܂�Ŏq�ǂ��������ł���悤�ɁA�~�߂悤�Ƃ͂��Ȃ�����ł���B�����ɂ͂��̌����ɒ��z������𐧌����邢���Ȃ�R�����Ȃ��B�k�c�l
�@��l�ɂȂ�Ȃ�قǎ������́A�������̋����⎩�ȋK���ɂ���āA����̗~�]�̌���Ȃ������E���l�ȘA����f�O���Ă��܂��B�w��̃v���g�[�x�̒��Ńh�D���[�Y�炪�m�肵�悤�Ƃ��Ă����̂́A�܂��������̏����Ŋ����I�ȗ~�]�̗���������I�ɉ��������͔\���߂��q�q�ǂ��r�̗����i�삷�邱�Ƃł���A�����ɃX�s�m�U��`�I�Ȏ��̓W�J�������������Ƃł������B�v
���r�Ɓw�X�s�m�U �������̃|���e�B�N�X�x,p.131.
�@�������āA�܂��q�����I�ϗ��r���Љ�̋K�����m�炸�A�D��S�Ɓg�C�ɓ��������́h��T���ӗ~�ɂ��ӂꂽ�q�q�ǂ��r�����A�X�s�m�U�̗ϗ�������Ƃ͒m�炸�Ɏ��H����g�N�w�ҁh�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�\�\�\���������Ă悢�ł��傤�B
�@�������A����ł́g�q�ǂ����h�Ȃ̂��H �g���n�h�͖��Ӗ��Ȃ̂��H ���ʂ܂Ŏq�ǂ��ł���ق����A�����ꂽ�������Ȃ̂��Ƃ����ƁA����͈�ʓI�ɉ߂���l�����ł��B�Ƃ����̂́A�����u�g�́v��u���v�Ƃ́g�o��h�ɂ́A�ǂ��o�������A�����o������邩��ł��B���ʓ_�����������Ȃ��g�����o��h�\�\�\���Ƃ��A�ł̂���쑐�ɏo����ĐH�ׂĂ��܂����Ȃǁ\�\�\�́A�u�߂��݁v���u����v��������āA�u�����͔\�v�����������Ă��܂��A�ꍇ�ɂ���ẮA�u�\���W�v��j�Ď��Ɏ��点��ł��傤�B�u�\�S�v�ȁs���ʊT�O�t���A�v�l�\�͂��A�����炵�Ă͂���܂���B
�@���������āA����ɎI�ɁA������^�����Ă�����̂ƃ����_���ɐڐG����̂ł͂Ȃ��A�g�ǂ��o��h��I�����g�D���邱�Ƃ��K�v�ł��B���̂��߂ɂ́A�u�������̍\���W�𗝉��v���A�u�������瑼�̂������̍\���W�𐄘_�v���āA�ǂ�ȁg�o��h���\���A�ǂ��ɍs���ǂ�ȁg�o��h�����邩��������߂Ă䂭�K�v������܂��B
�@����ɁA�g�ǂ��o��h���u����v���d�˂邱�Ƃɂ���āA����ʓI���s���ʊT�O�t���`�����A�ΏۂƂȂ�u���v��u�l�v�͈̔͂��A���[�J���Ȃ��̂���A���L���̈�Ɋg�債�Ă䂭���Ƃ��\�ɂȂ�܂��B���Ȃ킿�A�u�l�v�Ɋւ��Č����A��芰�e�ɂȂ�A��肳�܂��܂Ȑ�����قȂ�ӌ��̐l�тƂƂ��A�������邱�Ƃ��\�ɂȂ�̂ł��B
�@�����݂͂ȁA�s�����t�̔\�͂ɂق��Ȃ�܂���B�܂�A�g���n�h�ɂ���Đg�ɂ��邱�Ƃ̂ł���\�͂Ȃ̂ł��B
�u�q�����r���ȉ��ɏq�ׂ�悤�ȂQ�ʂ�̎d���Œ�`�����̂����̂��߂ł���A����͐l�Ԃ�����Ȃ���������I�Ȃ̂ł͂Ȃ������k�P���Ȃ����o�����K�v���Ƃ������Ɓ\�\�M�g�����l���A�����ɂ��Ă����Ȃ�̂����A�����Ă���B�q�����r�Ƃ́A(1) �����o����A������������̎������ƂЂƂɑg�ݍ��킳��A�������Ɋ�т̎I��i�������K����������j���N������悤�ȏ��l�ԂƂ̏o����A�I�����������Ă悤�Ƃ���w�͂ł���A(2) ���ʊT�O���A�����������������������Ƃ���悤�Ȃ������̍\���W���A�m�o���������邱�Ƃł���B�������瑼�̂������̍\���W����㈂���i�����ɂ�鐄�_�j�A�܂���������o�����Ă��炽�ȁA���x�͔\���I�Ȋ���i�����������܂������j����������̂ł���B�v
�h�D���[�Y�C��؉��E��w�X�s�m�U�\�\���H�̓N�w�x,pp.105-106.
���́A�����̃C�^���b�N�A�̖T�_�t�������B
�u�X�s�m�U���q�ǂ�����������Ď]�����Ȃ��̂́A��ʂɂ��̎������A�悢�o���ςݏd�˂�Z�p�i���ׁj��m�炸�A���₷�����̏��͂ɏ]�����Đ��_�̓��h�𗈂��悤�ȁA���|�I�ɐ��_�̎コ�ɂ���ē����Â����鎞�ゾ����ł���B��������k�c�l��l�ɂ͑z���ł��Ȃ��悤�Ȋ�т����낢��ȑΏۂƂ̊ԂɌ����A���x�ɖ��������i���鎞������̎����ł��낤�B�k�c�l
�@�������T���Ďq�ǂ��́A�P�Ȃ�w���x�ł͂Ȃ�����k�c�l�����������A��苭�łɂ��Ă����p�Ɋւ��Ă͕K�������n�B���Ă���Ƃ͌����Ȃ��B�k�c�l�X�s�m�U���w�G�`�J�x�̒��ŌJ��Ԃ��i���Ă���̂́A�q���̊Ԃ̙��ߓI�Ȋ�т�������ςݏd�˂Ă��A�l�͔\���I�ɂ͂Ȃ�Ȃ��r�Ƃ������Ƃł���B�k�c�l
�@���o�I�Ɋ�т�g�D������V�X�e�������w�͂����Ȃ�����A���x����������A�^�ɔ\���I�ȏ�Ԃ𑶑������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����_�݂̂��A�q�ǂ��Ɛ��n�����L�\�Ȑl�ԂƂ��Ⴂ�Ȃ̂ł���B�k�c�l�v
���r�Ɓw�X�s�m�U �������̃|���e�B�N�X�x,pp.133-135,140.
�u�X�s�m�U�����ʊT�O�𗝐��Ɠ��u���Ă���mE2P40Sc2�n�B�Ƃ���Ȃ�A�����������̐g�̂Əo��A���̊Ԃɋ��ʂ�����̂̕\�����݂�Ƃ��A���Ȃ킿�\�S�ȊϔO��������Ƃ��A�����ɂ͂��łɗ��������邱�ƂɂȂ�B�k�c�l�X�s�m�U�̗����́A�������̓���I�ȉc���k�c�l�̒��ɁA���łɓ��݂��Ă���B�k�c�l
�@�A�����͌����A�w�X�s�m�U�̗����A����͊���ł���A��тł���x�B�����I�Ȃ��̂͂��ꂪ�k�M�g�����\�\��т́l����Ƃ��Đl�����͂ɂȂ�Ȃ�����́A�����Ď������̍s�������肷��v���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�k�c�l
�@�啶���́q��l�r�ɂȂ�Ƃ������Ƃ́A���g�̑��݈ȑO�Ɋm������Ă����O�ݓI�ȋK�͂⒁���ɂ����܂�悤�Ȍ`�Ɏ���̗~�]�𐧌䂵�A��v���Ă������Ƃł���B�k�c�l���̈Ӗ��Łq��l�r�ɂȂ�Ƃ������Ƃ́A�P�Ȃ郋�[����������w�悫�s���x�w�悫�Љ�l�x�Ƃ��ċ����̂Ȃ�Љ�Ȃ�Ɂq�K������r���Ƃɂ����Ȃ��B
�@���n����Ƃ������Ƃ͓K���ł͂Ȃ��A���҂Ƃ̊Ԃł܂������\�S�ȊϔO���`���Ȃ���A�����ɐ�������\���I�ȗ͂�\�����Ă������Ƃł���A�������������Љ�I�d�g�݂��`����Ă������Ƃ���~�]�ɁA��̓I�����ݓI�Ȏd���Ō`��^���Ă������Ƃł���B�v
���r�Ɓw�X�s�m�U �������̃|���e�B�N�X�x,pp.135,141-142.
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@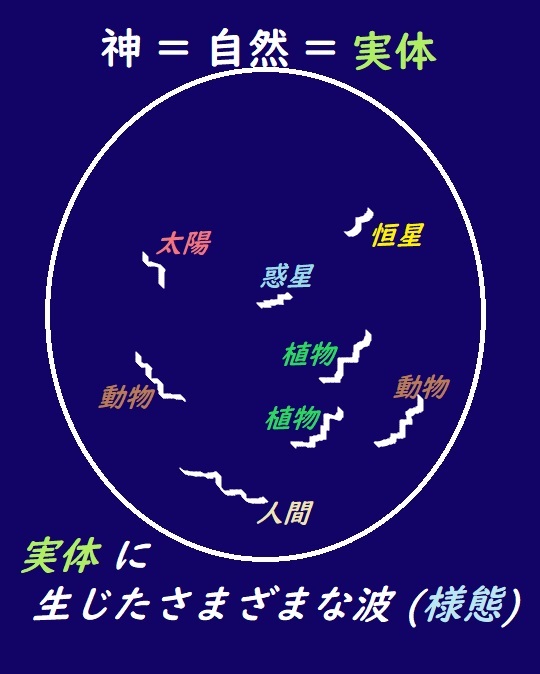

 �@
�@

 �@
�@
 �c
�c