02/14の日記
02:28
【必読書150】スピノザ『エティカ』(2)―――自由か、自由でないか、あなたは知っているか?
---------------
.
こんばんは。(º.-)☆ノ
【必読書150】スピノザ『エティカ』(1)からのつづきです。
【5】自由が牧歌的であったためしはない。
1665年、スピノザは、半分以上書き上げていた(工藤・斎藤訳『エティカ』,中公クラシックス,pp.2-3.)『エティカ』の執筆を中断して、『神学・政治論』を書き、1670年に出版した。この著書は、当時オランダ「共和国のリベラルなリーダー、ヤン・デ・ウィットの庇護のもと」に出版された(上野,pp.3-4)。たしかに、デ・ウィットが政権を掌握したのは 1663年のことだった。デ・ウィット政権が倒れ、デ・ウィットが虐殺された2年後に、『神学・政治論』は禁書(売買禁止)となっている。
スピノザの自由な出版活動は、思想言論の自由を擁護した・この政界最高実力者の存在なしには考えられなかった。スピノザは、リベラル派が政権を掌握したのを見て、いまこそチャンスと喜んで、この進歩的な著書の執筆をはじめたのだろうか?‥そして、保守的な神学者や宗教家の勢力が復活した貴族政権のもとで、一転して禁書とされたのだろうか?
しかし、ことは、そう簡単ではなかった。というのは:
「『神学・政治論』に対する攻撃はたくさんあったが、そのうちでもいちばん激烈だったのは、こともあろうに当時もっともリベラルで進歩的な『デカルト』主義者たちからものだった。哲学の自由、言論の自由の論陣を張っていた人々が攻撃に回ったのである。
第2に、禁書処分を下したのは」絶対主義君主でもなければ、カトリックの宗教裁判でも、カルヴァン派教会の検閲でもなかった。貴族派政権に交替していたとはいっても「自由と寛容の誉れ高いオランダ共和国の、やはり比較的リベラルな市民政府が禁書に動いたのである。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,p.16.
「ご存知のように17世紀といえば、フランスのルイ14世に象徴される絶対主義の時代である。ところがオランダは例外だった。〔…〕新教国オランダ共和国は、海に向かって開けた自由と寛容の新興国家だった。人文主義者エラスムスの国、国際法の父と言われるグローティウスの国である。強大な強権も宮廷もなく、絶対君主も廷臣もいない。近世日本の堺のように『レヘント』と呼ばれる富裕な商人階層が勢力の中心になっていて、〔…〕北部7州の、ゆるやかな連合から共和国は成り立っていた。有名なレンブラントの『夜警』で、誇らしげに集結しながらめいめい勝手なポーズをとっている市警団の、あの雰囲気である。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,p.17.
その自由の共和国の、もっとも自由な黄金時代をもたらした事実上の最高権力者、法律顧問ヤン・デ・ウィットとは:
「この人も有能な議長のようなもので、君主でも何でもない。数学の愛好者であったらしい。彼のあまりにこぢんまりとした住居に、外国からの賓客が驚いたという話がある。
自由と寛容はエラスムス以来、この運河と風車の国の理念だった。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,p.18.
「デ・ウィットは、〔…〕共和派の大政治家であり、この国の黄金時代を築いた人である。〔…〕学問にも深い理解を示したばかりでなく、彼自身も実際に数学を研究し、円錐曲線や確率論の研究で著名な人であった。」
工藤喜作『スピノザ』,新装版,2015,清水書院,p.72.

レンブラント「夜警」(1642)
オランダ共和国の政界には、2つの対立する派閥勢力があった。支配層のなかに派閥ができてしまうのは、自由と民主を旗印にする共和政国家には避けられないことらしい。実質は、どちらも「レヘント」層―――regent 英語で言えばリージェント:海外貿易でしこたま儲けた大商人から成りあがった都市貴族―――なのだが、田舎貴族のオラニエ公を中心とする貴族派“オラニエ派”が、どちらかといえば保守的な愛国主義者で、軍国主義的だったのに対し、ヤン・デ・ウィットを後押しする議会派“共和派”は、自由主義的な平和主義者だった。
宗教に関しても、オラニエ公は、プロテスタントの最大宗派である正統カルヴァン派教会と結びついていた。カルヴィニズムの支持を受けて宗主国スペインと戦い、オランダの独立を勝ち取ったのは、初代オラニエ公・ウィレム1世だったからだ。“オラニエ派”は、民衆の圧倒的支持を受けていた。
これに対して、デ・ウィットら“議会派”の多くは、カルヴァン教会内の反主流派であるレモンストラント派に属していた。絶対的な救済予定説―――誰が天国に行けるかは、神が予め定めている―――を信奉する主流派に対して、レモンストラント派は、全員救済説―――自ら救済を拒否しないかぎり、誰もが天国に迎えられる―――であり、より自由な考え方であった。(工藤喜作『スピノザ』,新装版,2015,清水書院,p.21.)
第1次英蘭戦争のあと、“共和派”は、イギリスのピューリタン・クロムウェル政権と上手に妥協して、オランダ商人の地歩を確保した。“共和派”が政権を掌握し、“オラニエ派”は影が薄くなった。
ところが、前回も述べたように、この勢力関係は、イギリスの政変のあおりを食って、ひっくりかえることになる。イギリスでは、1660年にピューリタン共和政が覆り、スチュアート家の王政が復活する。即位したチャールズ2世は、フランスのルイ14世と密約を交わして、オランダ侵略を開始した。降って湧いた国難が、愛国的なオラニエ公に復活のチャンスを与える。ヤン・デ・ウィットは、民衆クーデターによって辞職を余儀なくされ、それでもおさまらない民衆は、デ・ウィット兄弟を監獄から引きずり出して虐殺した。
オラニエ公ウィレム3世の活躍で、フランスの地上軍は撃退され、英仏艦隊も、オランダ海軍の奮戦により上陸の機会を失った。こうして、1674年には英国と、翌年にフランスと和睦し、オランダは全領土を保全した。さらに、1688年イギリス名誉革命に乗じて、ウィレム3世はロンドンに進軍して無血入城し(英国王に退位を求めていたイギリス議会と、密約があった)、英王ウィリアム3世として即位した。
ウィリアム3世は、イギリス議会の起草した「権利宣言」を承認し、「君臨すれども統治せず」‥‥ここに世界最初の立憲君主制が誕生した。
オランダでは、保守勢力だったオラニエ公が、イギリスに来ると、もっとも自由主義的な君主として迎えられたわけである。当時のオランダの政治が、いかに自由主義的であったかがわかるというものだ。
しかし、“オラニエ派”には、頑固な正統カルヴァン派の聖職者や神学者も含まれていた。
「自由が牧歌的であったためしはない。共和国の自由と寛容は『共和派』と『総督派〔オラニエ派――ギトン注〕』の緊張関係の上に、いわば危なっかしく乗っかっていた。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,pp.17-18.
【6】派閥の争い
ヤン・デ・ウィットらの“共和派”が執権していたころに、時間を戻してみよう。政権から排除されていた“オラニエ派”は、“共和派”を宗教的・道義的に攻撃することで、挽回をはかろうとしていた。
いつの時代でも、“為政者は、政治がへたである”“政策がまずい”といった理詰めの批判よりも、“道義的に許せない”“詐欺師でウソつきだ”“人間失格だ”という攻撃のほうが、人びとを激昂させる。とくに、民衆はそれを聞くと、居ても立ってもいられなくなる。17世紀のヨーロッパでは、この“人間失格”攻撃の最たるものは、“やつらはキリストを否定する”“無神論者だ”というものだった。
大学で“オラニエ派”を支持していたのは、正統プロテスタントの保守的な神学者たちであり、それに対して“共和派”は、
「大学の内外を問わずデカルト主義者がそのシンパだった」。対立は「国中を巻き込み、共和国政府の寛容政策そのものが問われる騒ぎに発展していく。
問題が微妙なのは、神学者の側が『不敬虔』の告発という形をとったことだ。デカルト主義は聖書に反するというのである。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,p.24.
デカルトは、当時のオランダ共和国の自由な雰囲気にあこがれて、フランスから移住してきた進歩的学者のひとりだった。『方法序説』『省察』『哲学原理』など、デカルトの主要著作は、オランダ滞在中(1628-1649)に書かれ、出版されている。当然に、オランダでは、デカルト哲学を信奉する人が増えた。彼らは、「デカルト主義者(cartesianistes)」と呼ばれた。
デカルトの哲学は、ガリレイ以来の近代科学の上に立っていた。十字形の座標軸にグラフを書くやり方は、デカルトが創始したものだ。「われ思う、ゆえに、われあり」の「思う」とは、理性で考えるということだ。そうしたことだけで、当時は、宗教界から白眼視されるに十分だった。
それでいてデカルトは、宗教を正面から否定したりはしなかった。「われ思う、ゆえに、われあり」から直接導かれる第2の真理は、「神は存在する」というキリスト教の根本真理だと言っているくらいなのだ。スピノザのように、人格的な神を否定したり、教会の教理に疑問符をつけたりもしていない。にもかかわらず、カトリック、プロテスタントの別を問わず、神学者や聖職者は、機会あるごとにデカルト主義を攻撃した。
たとえば、デカルトの主張する地動説(デカルトだけが主張したわけではないが)は『聖書』に反すると言うのだ。「太陽が昇った」とか「沈んだ」とか、『聖書』には、いくらでも書いてあるからだ。

「デカルト主義者たちはどんな論理で対抗したのだろう。〔…〕『神学と哲学の分離』、これが彼らの主張だった。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,p.24.
つまり、一種の“政教分離”―――“学教分離”である。デカルト主義者は言う。われわれは聖書にケチをつけるつもりはないし、宗教問題に介入したいとも思わない。ただ、《自然》を合理的に理解しようとしているだけだ。「聖書が神の言葉であるのと同じように、自然もまた神の言葉によって創られた。」だから、両方とも真理だ。
「『真理は真理に矛盾しない』のだから、理性の発見する『自然の真理』が『聖書の真理』を損なうはずはない。だから神学は、余計な心配をしないで哲学に口出ししないでいただきたい〔…〕共和国当局も、この『神学と哲学の分離』の線でことを穏便に処理しようとした。
ところが、この論理には重大な穴があったのである。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,pp.24-25.
神学者たちは言う。なるほど、「真理は真理に矛盾しない。」まことにそのとおり。それならば、聖書に書いてあることを、君らの自然科学に矛盾しないように説明してもらいたい。「燃える柴の中から神の声がした」だとか、「天の軍勢が、そらに現れた」だとか、キリストが「最後の晩餐」で、「この葡萄酒はわたしの血であり、このパンは私の肉である」と言っただとか、みな「真実」なのだから、おまえらの科学で説明してみろ! それとも、キリストはウソをついたと言うのかね?w
そう言われると、デカルト主義者は、きまってこう答える。それらは比喩として書かれているのだ。パンが人肉に変ったりするはずはないが、キリストは、深遠な教理を、そういう比喩の形で言われたのだ、と。
そこで、神学者は、敵は手中に落ちたとばかり勢いづく。それでは、“復活”はどうか? あれも比喩だと言いたいのか? デカルト主義者は、まっ青になって否定する。いや、あれは比喩じゃありません。事実、そういう不思議なことがあったのです。……“復活”が比喩だなどと言ったら、キリストの神性を否定することになる。「三位一体」を否定することになる。これは重大な異端だ。犯罪だ。“人間失格”だ。百年前なら、火あぶりになるところだ。
神学者は、勝ち誇って言う。ほら、説明できないじゃないか。いったい、『聖書』のどれが比喩で、どれが事実だと言うのか? 区別する基準がないではないか。『聖書』は、どれもこれも事実なのだ。「比喩だ」などと言うのは、ごまかしだ、ペテンだ。おまえらはウソつきの詐欺師で人でなしだ!
こうして、……
「『神学と哲学の分離』という公式見解は低迷してゆく一方だったことがわかる。当局の裁定は決まって、できるかぎり哲学の自由を尊重すべきだが、どうしても聖書と両立しない場合は神学に譲るべし、という煮え切らないものだった。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,p.27.
【7】自由の影におびえる自由主義者たち
そうなってくると、これはもう、ごまかしだなどと言われて黙ってはいられない、とことん決着をつけてやろう、という過激派が、デカルト主義のほうにも現れることになる。
「たとえば、ロドウェイク・メイエル(Lodewijk Meijer)〔…〕は言う。〔…〕聖書解釈は、明晰判明ならざるものは受け入れないというデカルトの方法に従う。聖書のどこまでが隠喩なのかを最終的に決定するのは哲学〔けっきょく、自然科学――ギトン注〕である。〔…〕この主張は、『神学と哲学の分離』という住み分け原則の破棄に等しかった。真偽に関してはぜんぶ哲学が仕切るというのである。
〔…〕メイエルは、無からの創造〔神の天地創造――ギトン注〕、三位一体といった教会の信仰箇条はナンセンスであるという結論に至っていた。ここから、聖書なんかなくてもいいじゃないかという恐るべき結論に踏み越えるのはあと一歩である。これがスキャンダルにならないわけがない。神学者たちは、それ見たことか、やっぱりデカルト主義は危険なのだと気色ばむ。
他方、『神学と哲学の分離』を掲げていた本流のデカルト主義者たちは大いに動揺し、自分たちからこの本の発禁処分を当局に願い出る。恐れていたことが現実になったのである。けれども彼らにデカルト主義の急進化を押さえ込む論理はない。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,pp.27-28.
“急進化”の禍は、スピノザにも及ばないではいなかった。
「というのも、スピノザが『デカルトの哲学原理』という処女作を出版する際、熱烈な序文を寄せてくれたのは、いまのロドウェイク・メイエルその人だったからである。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,p.28.
しかも、困ったことに、スピノザの親しい友人たちまでもが、ある意味で“過激化”していた。彼らは、自由な信仰を求め、理性の光を信じて疑わない。スピノザこそが、この混乱に決着をつけて、メイエルをも越えてデカルト主義を徹底してくれるだろう、そして、『聖書』の真理を迷信の闇から救い出してくれると、素朴に信じていたらしい。これは、ある意味で不可能を期待することだったろう。

シュムール・ヒルシェンベルク「破門されたスピノザ」(1907)
メイエルに続いて 1668年、『闇に輝く光』というデカルト主義の急進的な本を出したクールバッハは、ついに当局に逮捕され、翌1669年獄死することになる。クールバッハ逮捕の際、黒幕はスピノザではないかとさえ疑われた。
「アドリアーン・クールバッハ(Adriaan Koerbach)〔…〕によれば、理性の吟味に耐える真理だけが神の言葉である。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,p.29.
これを適用すると、『聖書』のほとんどすべてはウソになってしまう。キリストが水の上を歩いたとか、ひときれのパンをちぎって、数百人分の食料をこしらえたとか、荒唐無稽な話が多すぎるのである。クールバッハは言う:
「キリストはたしかに偉人だったが神の御子であるはずはない。天使や悪魔はフィクションにすぎず、天国や地獄はわれわれの心のうちにあるだけだ。三位一体も聖書に無縁のねつ造であって、そんなことを真理と信じさせようとしても無駄である。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,p.29.
いずれも、科学の眼で見れば当たり前なのだが、当たり前を公言してしまうと、信仰の破壊になる。デカルト主義者の一部が過激化してきたのを、誰よりも喜んだのは、デカルト主義を攻撃する神学者たちである:
「神学者は勢いづき、共和派デカルト主義者たちはあわててトカゲの尻尾切りに奔走する。これを見て共和派たたきのチャンスをうかがう総督派〔オラニエ派――ギトン注〕聖職者たちが説教壇で黙っているはずはない。自由と寛容などときれいごとを言っていていいのか、と言論統制が声高に叫ばれる。そしてそのなか、危険な急進主義の隠れた中心人物のように『無神論者スピノザ』の名がささやかれていた。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,p.30.
「スピノザはこの時期、すでに『エチカ』の執筆を中断し、『神学・政治論』をせき立てられるように書きはじめていた。〔…〕
事態は深刻であった。スピノザはある書簡で『神学・政治論』の執筆動機をこう打ち明けている。民衆が自分に浴びせ続けている無神論者という非難をできるかぎり排撃し、聖職者が誹謗する『哲学する自由』をあらゆる手段で擁護しなければならない。だが何よりも問題なのは、その自由に対し賛成していたはずの人々が、いまや危惧を抱き動揺しはじめていることだ。〔…〕
動揺するデカルト主義者をはじめとする共和派知識人〔…〕彼らは理性の自由を恐れはじめている。こんなことを書いたり述べたりすると不敬虔になってしまわないかと萎縮しはじめている。〔…〕
彼らデカルト主義者たちは思想言論の自由を掲げながら、心の底で、理性は放任しておくとやはりまずいのではないかという不安におびやかされていた。〔…〕
宗教の前で理性が自らの影におびえる、〔…〕この問題の解決には共和国の自由の実験がかかっている。何でも自由に考えさせておいていいのか、と世間は言い出す。それに対してははっきりと、いいのだと言ってやる必要がある。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,pp.22,29-30.
スピノザのまわりで、何かが狂ってしまった。‥哲学と理性の自由は、真理をもたらし、真理の光は、人びとに幸福と平安をもたらすはずなのに、事態は逆に進んでいるかのようだ。自らの知識の乏しさをかえりみずに、理性をとことん推し進めようとする人たちは急進化し、信仰の破壊に突き進んでしまう。それが、神学者や保守的な聖職者にかっこうの口実となって、理性の自由が狭められてしまう。理性の光によって、もっとも福利を受けるべき民衆が、逆に、理性に敵対して攻撃し、もっとも恐ろしい専制政治と迷妄の闇を引き寄せようとしている。。。
「自らの理性の影におびえる」人びとに対して、スピノザが『神学・政治論』の前半(神学論)において示したのは、理性によって『聖書』を全否定する前に、まず『聖書』を研究する必要があるということだった。ここでは、スピノザがユダヤ人として、幼いころからヘブライ語に親しんできた経験が役に立った。
たとえば、預言者モーセが、「神は火である」と言っている箇所について、文字通りに「火」だと理解する必要もなければ、デカルト主義者のように「火」は何かの比喩だとする必要もない。ヘブライ語の「火」には、「怒り」「嫉妬」という意味もあるからだ。「神は嫉妬深い」と読むこともできるのだ。(上野修『スピノザ』,p.38-40,43-44.)
では、「神は嫉妬深い」と『聖書』に書いてある以上、神はほんとうに嫉妬深いのか? そう考える必要もない。『聖書』が真実なのは、モーセがそう思ったという事実についてである。『神学・政治論』で、スピノザは次のように言う:
「哲学〔および科学―――ギトン注〕の目的はもっぱら真理のみであり、これに反して信仰の目的は、〔…〕服従と敬虔以外の何ものでもない。〔…〕信仰は、物語と言語を基礎としもっぱら聖書と啓示とからのみ導きだされねばならない。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,p.57.
信仰の基礎は、神への服従にある。『聖書』から読み取るべきなのは、預言者たちが見た摩訶不思議な現象が、真実だったかどうかではなく、それらを通じて彼らがいかに神に服従する必要を感じ、また、人びとに説くことができたか、ということである。
「信仰は真なる教義よりはむしろ敬虔な教義を、いいかえると精神を服従へと動かすような教義を要求する。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,p.53.
そうだとすれば、『聖書』の内容が、哲学の探求する真理と、いかにかけはなれていようとも、決して信仰の妨げとはならない。
こうしてスピノザは、『神学・政治論』の前半で、科学と信仰を混同して理性を委縮させている混乱に終止符を打ったうえで、後半では、国の政治のうえでは、当局は、何をどこまで自由にさせてよいのか、どうしても禁止しなければならない「不敬虔」があるとすれば、それは何なのか、を論じるのです。
ここでスピノザは、社会契約説に基いて論じているのですが、その結論を言えば(上野修『スピノザ』,p.70-72,78-81.):
〇 第1に、禁止しなければならないのは「行為」のみであって、思想そのものを禁じる理由はないこと。何を考え、何を言おうと、「行為」において法に従っている限り、自由である。法を批判するのも自由である。
〇 第2に、それでもなお、「社会契約を実質的に破棄するような言動」だけは、例外的に禁じなければならない。それさえ自由にできるとしたら、国家そのものの基礎が覆されてしまうからである。
「社会契約を実質的に破棄するような言動」とは、宗教的権威を持ち出して、市民政府が認めた自由を攻撃する「反逆的意見」のことである:
「ヘブライ神政国家は神に統治権があったので、当然、宗教的な『神の法』は国家の法であった。ならば同じ論理で、『神の法』は神政国家が消滅するとともに法的効力としては消滅したことになる。
したがってわがオランダ共和国では、聖書がなんと言おうと、何が正義で何が不正義か、何が敬虔で何が不敬虔かを決定する権限はまっさらの形で共和国の最高権力にある。だから、いまさら宗教的権威を持ち出して市民政府の決定に〔…〕文句をつけるのは統治権を奪おうとすることであり、〔…〕『反逆的な意見』と言わねばならない。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,pp.71-72.
つまり、神学者や保守的な聖職者が市民政府の《自由》を攻撃する言動こそ、国家にたいする「反逆罪」として処罰されなければならないのだ、ということになって、‥‥これはもう、自由思想家の「不敬虔」を攻撃する聖職者のほうが、反逆者になってしまうわけです。それが、一点のスキもない論理で証明されているから、おそろしい。。。
〇 第3に、この思想言論の自由を除去しようとするならば、同時に、共和国の平和と敬虔も除去されてしまうこととなる。
【8】《自由》とは、「必然性」のことか?!
以上、スピノザの時代背景、とくに宗教をめぐる政治情勢にやや詳しく触れたのは、スピノザの《自由》のもつイメージを、少しでも体感的にとらえられたらと思ったからです。
というのは、スピノザが『エティカ』で言う《自由》は、一見して私たちの《自由》のイメージとは、あまりにも異なっているのです。
「自由といわれるものは、みずからの本性の必然性によってのみ存在し、それ自身の本性によってのみ活動するように決定されるものである。だがこれに反して、必然的あるいはむしろ強制されているといわれるものは、一定の仕方で存在し、作用するように他のものによって決定されるものである。〔第1部、定義7〕」
スピノザ,工藤喜作・斎藤博・訳『エティカ』,2007,中公クラシックス,pp.4-5.
【原文と逐語訳】
VII. Ea r e s l i b e r a dicetur, quae ex sola suae naturae necessitate existit et a se sola ad agendum determinatur: n e c e s s a r i a autem, vel potius c o a c t a , quae ab alio determinatur ad existendum et operandum certa ac determinata ratione.
[[自分の本性]の必然性のみ]によって存在し、自分のみによって行動することへと決定されるものは、“自由なもの”と言われる。しかし、他のものから、[ある定められたしかたで存在し働くこと]へと〔決定されるものは〕、“必然的な”〔もの〕ないしむしろ“強制された”〔もの〕〔と言われる〕。
「必然」が2回出てきますが、同じ意味だとすると矛盾しているような感じになります。解説本によると(国分功一郎『スピノザ「エチカ」』,p.71.)、2度目の「必然」は、“世間で一般に「必然」と言われていることがら”という意味で、すぐに「強制」と言い直しています。
つまり、スピノザの定義としては、「自由」に対立する・不自由な状態は「必然」ではなく「強制」と呼ぶことになります。
訳者註でも:
「ふつう、『自由』に対立するものは、『必然』と見なされているが、スピノザの場合、『自由』には『強制』が対立し、『必然』はむしろ『自由』と等置されている。」
スピノザ,工藤喜作・斎藤博・訳『エティカ』,2007,中公クラシックス,p.6.
と説明されています。
「自由」と「必然性」が同じ意味! これは、私たちの《自由》のイメージに、まっこうから反するように思えます。人間の《自由》とは、発射したミサイルが計算通りに飛ぶのと同じように、天体が正確に軌道を描いて運動するのと同じように、「必然」そのものの運動をすることなのでしょうか???
「強制」との違いは、運動(および存在)の原因が、「他のもの」なのか、「みずからの本性」なのか、その点にしか無い――と“定義”されてしまっている! いったいどこが《自由》なんだ?
ひとつの考え方は、この〔第1部〕は「神について」という標題の部だから、ここで定義しているのも、神――《神すなわち自然》の《自由》だ、と考えることです。たしかに、《神すなわち自然》にとっては、「自由」イコール「必然」だというのは、もっともに思われます。
しかし、よく考えてみると、それは解決にならない。《神すなわち自然》とは、この宇宙全部です。そこには当然に地球も含まれ、地球の上にいる人間も全員含まれてしまいます。ですから、《神》にとって「自由」イコール「必然」ならば、人間にとってもそうでなければならない。例外は許されないのです。
そもそも、幾何学のように論理でガッチリ押さえ込むスピノザが、『エティカ』の最初のほうと最後のほう―――第5部「知性の能力あるいは人間の自由について」―――で定義を変えるはずはない。じっさい、『エティカ』には、この「第1部、定義7」以外に「自由」の定義はありません。
ですから、神にとっても人間にとっても、《自由》は「必然」とイコール。スピノザはそう考えていた、と言わざるをえないのです。
ただ、ひとつ鍵になるのは、スピノザは、(人間も神も)「自分の本性」によって活動するだけでなく、「自分の本性」によって存在する、それが《自由》だと言っていることです。
私たちは、母親から生まれたのではなかったか? にもかかわらず、「他のもの」によってではなく、「自分の本性」によって存在するとは、どういうことなのか? ―――ここは、謎解きのカギになるのではないかと思います。しかし、それをいま掘り下げるのは無理ですから、宿題にしましょう。
さて、ここでちょっと考えてみたいのは、前節までに見た《自由》のイメージから、何かを言えないかということです。『神学・政治論』で論じられていた《自由》、また、スピノザが彼の生きた時代と社会の中で呼吸していたであろう《自由》のイメージから、何か言えないだろうか?
たとえば、スピノザは、『神学・政治論』では↓つぎのように、国家の目的は《自由》だ、と断言しています。この《自由》は、明らかに人間の《自由》であって、神の《自由》ではない。
「『私はあえていう。国家の目的は、人間を理性的存在者から、野獣あるいは自動機械にすることではなく、むしろ逆に人間の精神と身体がまったく完全にその機能を果たし、彼自身が自由に理性を行使し、憎しみ、怒り、欺瞞をもって争うことのないように、また相互に敵意をいだくことのないようにすることである。それゆえ、じつに国家の目的は自由である。』」
工藤喜作『スピノザ』,新装版,2015,清水書院,p.197.
「人間を……、野獣あるいは自動機械にすることではなく、むしろ逆に……彼自身が自由に理性を行使〔する〕……ようにすることである。」という部分は、『エティカ』の《自由》の定義と響きあっています。つまり、他からの「強制」によって動かされる「野獣あるいは自動機械」ではなく、自身の「理性の行使」こそが、《自由》にほかならない―――という考えを、ここから読みとることができます。

ヤコプ・ファン・デ・ウルフト
「アムステルダム旧市庁舎」(1653-6)
さらに、『神学・政治論』から、別の引用を見ましょう。こんどは、理想国家としてのオランダ共和国が実現している《自由》の内容が、もっと具体的に述べられています:
「スピノザが当時の共和国の自由をどんなふうに讃えているか、ちょっと見ておこう。〔…〕
『アムステルダム市こそはその〔言論の自由を実現した〕例であり、〔…〕この栄える共和国、この卓越した都市ではあらゆる種類の民族・あらゆる種類の宗派に属する人間がみなきわめて和合的に生活しており、また彼らが人に信用貸しをするにあたってはその人間が富者か貧者か、またその人間の平素の行動が正直か欺瞞的かを知れば足りるのである。』(『神学・政治論』)
何を言ってるんだ。そんなのは金儲けのための自由じゃないか。」
上野修『スピノザ』,シリーズ・哲学のエッセンス,2006,NHK出版,pp.19-20.
たしかにスピノザは、「人に信用貸しをするにあたってはその人間が富者か貧者か、……を知れば足りる」――民族や宗派で差別されることはないのだ、と言って称讃している。「金儲けのための自由」「金持ちのための自由」と言って言えないことはない。民族・宗派で差別されようとされまいと、貧乏人が金を貸してもらえないのは、同じではないか!
しかし、私たちが注目すべきなのは、そのことよりも、民族や宗派で差別されることのない・そのような《自由》な社会が、貸金業者をも巻き込んだ経済的《自由》を基盤にして成立している、という状況ではないでしょうか?
ヨーロッパで近代化が進んでゆく過程で、最初に抬頭した《自由》は、ブルジョワジーの経済的《自由》であったことは、よく知られています。スピノザの生きた17世紀は、まさにそういう《自由》の発祥の時代だったと言えます。表現の自由、政治活動の自由、学問・芸術の自由、……といったさまざまな《自由》は、この経済的《自由》を基盤にして、その上に花開いた。近代的なさまざまな《自由》を、下から押し上げるように力強く推進して行ったのは、ブルジョワジーの経済的《自由》、自由な経済活動だった。これが、じっさいにあった歴史過程です。
たしかに「金儲けの自由」かもしれない。スピノザ自身は、金儲けとは無縁だった。しかし、当時オランダのそういう商業活動、経済活動の《自由》は、彼の《自由》のイメージにも深く刻印されている、と考えることができます。
「金儲けの自由」ということを、もう少し広い立場で見るならば、それは、自分の利益をはかる自由、自らの欲望をみたす自由‥‥ということになるのではないでしょうか?
前回に“赤ずきん”の話を持ち出しましたが、人間はみな自分の利益のために生きている――ということは、スピノザの人間観の基本にある考え方だと言えるでしょう。「自分の利益のために行動する」ということを、悪い意味でだけ考えていたはずはありません。なぜなら、スピノザによれば、「善い」「悪い」は、人ぞれぞれの勝手な判断にすぎないからです。同じことが、評価する人と時と場合次第で、善くも悪くもなる。「自分の利益のために行動する」ことは、いわば人間の本性であって、それは「悪」にも「徳」にもなるのです。
のちほど――次回?――『エティカ』から引用して論じたいと思いますが、「欲望」は、精神的なものも肉体的なものも、「個体」としての人間の「本質」の現れであり、「勇気」も「幸福」も「神への愛」も、ここから生じるものなのです。
《自由》を「欲望」と言い換えると―――スピノザによっても、この2つは同じものではありませんが―――、いくらか「必然性」に近づいてきたような気がします。
《自由》はなぜ「欲望」なのか?‥なぜそれが哲学、倫理学なのか?
これものちほど詳しくやる予定ですが、スピノザによれば、「真なる認識」とは、ものごとを、その「原因」までふくめて認識することです。自由だ、自由だ、と言うが、私たちはなぜ自由を求めるのか?
私たちが「自由」と呼んでいる私たちの感情、身体の状態、社会の状態は「結果」です。「自由」を求める動機まで考えれば、そこに「欲望」のような要素は、常にあるのではないでしょうか? 広い世界が見たい、自由に愛しあいたい、好きなだけお金を儲けたい、……みな、《自由》の動機であり、広い意味での「欲望」と考えられます。
スピノザを理解すると人間観が変わる、いや、人間そのものが変る、とよく言われます。スピノザ自身が、『エティカ』で、そういうことを言っています。中世までの人にとって、知識とはそういうものでした。人間を変化させずに、新しい知識を摂取することはできない。だから、「勉強」とか「情報」などとは言わずに、「修行」と言う。それが、昔の知識人だったことを思い出しましょう。
私たちは、その入り口にさしかかったところです。
【9】「自由意志」は存在するか?
さあ、《自由》につづいて、「自由意志」。こんども大変なことになります。
神にも人間にも、「自由意志」は存在しない。
最初に↑ズバリ結論を言っておきます。
「自分が自由であると思う〈すなわち、彼が自由意志によってあることをなしたり、またしなかったりすることができると思う〉人がいるとすれば、その人は誤っている。このような意見を述べることは、ただ、彼らが自分の行動を意識し、自分がそれへと決定される諸原因を知らないからである。それゆえ彼らの自由の観念は、彼らが自分たちの行動の原因を何も知らないことにある。〔…〕なぜなら彼らはみな、意志が何であるのか、また意志が身体をいかにして動かすかを知らないからである。そして、それを知っていると口ばしり、魂の座席や住居を考えだす人は、嘲笑か不興を買うのが常である。〔第2部、定理35、註解〕」
スピノザ,工藤喜作・斎藤博・訳『エティカ』,2007,中公クラシックス,p.137.
「私たちは自由の話をすると、すぐに『意志の自由』のことを考えてしまいます。そして、人間には自由な『意志』があって、その意志に基づいて行動することが自由だと思ってしまうのです。〔…〕
自由意志は純粋な出発点であり、何者からも影響も命令も受けていないものと考えられています。しかし、そのようなものは人間の心の中には存在しえません。人間は常に外部からの影響と刺激の中にあるからです。」
国分功一郎『スピノザ「エチカ」』,pp.82-83.
人間の意識は、いまある結果だけを認識するのに精いっぱいで、それが生じてきた原因までは、考えが及ばないのがふつうです。そのために、“自分は、何やかやの原因に動かされてではなく、自分の意志で、これをしている”と思ってしまうのだ、とスピノザは言います。彼らが「自由だ」と言っているのは、自分の無知をさらけ出しているだけのことである、と。
「なぜなら」以下の部分は、デカルトを皮肉っているのだと思います。デカルトによれば、人間は精神と身体からなっており、精神が身体を、機械を操縦するように動かしている関係にある。模式的にイメージすると、頭の中にコビトがいて、身体の各部に指令を出している形です。この図式は、私たちの素朴な生活感覚には、しっくりするので、デカルト以後の近代人は、多かれ少なかれ無意識に、この図式で考えているふしがあります。その“頭の中のコビト”が「自由意志」です。
しかし、そんな図式はちゃんちゃらおかしい。頭の中にコビトはいないし、「自由意志」も無いのだ、とスピノザは言うのです。
ただ、ちょっと注意しておきたいのは、スピノザは、“自分は自分の意志で行動している”というような間違った生活感覚は除去しろ、そんなことは考えるな、と言っているわけではないことです。
私たちは、太陽が大空を動いているのではなくて、地球が太陽のまわりを回っているのだ、ということを知っています。それでいて、毎日、太陽を見て、「日が出た」「西に傾いた」「沈んだ」と思い、会話でもそう言います。天文学の知識が、日常の生活感覚を変えるわけではない。この日常感覚を、スピノザは「想像力(イマギナチオ)」と呼んでいます。
「想像力」は、太陽の動き、「自由意志」、そのほかにも間違いだらけの認識ですが、「想像力」が悪いのは、ほんとうのことを知らない場合であって、太陽の動きのように、ほんとうのことさえ知っていれば、「想像力」自体は、間違っていても有益だ、「想像力」は、人間の本性の「欠点ではなく長所」だ、とスピノザは言っています。「この想像の能力が、精神の本性にのみ依存しているならば、つまり〔第1部定義7より〕自由であるならば、なおさらのことそうであろう。」〔第2部、定理17、註解〕(工藤・斎藤・訳『エティカ』,p.120.)
もし、「想像力」は間違っているから、と言って全否定してしまったら、芸術も宗教もありえなくなってしまいます。スピノザは、さきほど見たように、『神学・政治論』で、『聖書』は、真理の記述よりも“物語”として、信仰に対して価値をもつと言っていました。また、彼自身、画家並みの腕で油絵を描いていますし、音楽にも素養があったようです。
そういうスピノザが、「想像力」の価値を否定するはずはないのです。
「精神のうちには、絶対的な意志あるいは自由な意志は存在しない。むしろ精神は、このこと、あのことを意欲するように原因によって決定され、この原因も他の原因によって決定され、さらにその原因も他の原因によって決定される。そしてこのように無限に進む。〔第2部、定理48〕
〔証明〕〔…〕精神は、自分の活動の自由原因であることもできないし、また意欲したり意欲しなかったりする絶対的能力ももつことができない。むしろ精神は、このこと、あのことを意欲するように、〔第1部定理28より〕原因によって決定されなければならない。そしてこの原因もまた、他の原因によって決定され、さらにこの原因も他の原因によって決定される云々。かくてこの定理は証明された。」
スピノザ,工藤喜作・斎藤博・訳『エティカ』,2007,中公クラシックス,p.158.
外部からの影響と無関係に「意欲したり意欲しなかったりする絶対的能力」が、「自由意志」にほかなりません。しかし、人間が、あれこれを「意欲したり意欲しなかったりする」のは、自由意志などではなく、何か原因があって、行動への意欲が「決定され」ているのだと言うのです。
「意志の自由を否定したら人間がロボットのように思えてしまうとしたら、それは人間の行為をただ意志だけが決定していると思っているからです。意志こそが人間の行為の唯一の操縦者であるのだから、その操縦者がいなくなったら、人間には操縦者がいなくなると考えてしまっているのです。〔…〕
一つの行為は実に多くの要因の影響下にあります。それらが共同した結果として行為が実現するわけです。つまり、行為は多元的に決定されているのであって、意志が一元的に決定しているわけではないのです。けれどもどうしても私たちは自分の行為を、自分の意志によって一元的に決定されたものと考えてしまいます。繰り返しになりますが、それは私たちの意識が結果だけを受け取るようにできているからです。
〔…〕
〔…〕現代ほど『意志』『意志決定』『選択』といったものが盛んに言われる時代も珍しい〔…〕
意志をめぐる現代社会の論法というのは次のようなものです。―――これだけ選択肢があります。はい、これがあなたの選択ですね。〔…〕あなたが自分の意志でお決めになった〔…〕ご自身の意志で選択されたことですから、その責任はあなたにあります……。
〔…〕このように意志なるものを信じて疑わない現代社会に、何か私は信仰のようなものを感じます。〔…〕現代社会はある意味で、『意志教』のようなものを信仰しているのではないでしょうか。
実はそのことは意志の概念の歴史を考えてみると分かります。〔…〕古代ギリシャには、意志の概念も、意志に相当する言葉もありません。
〔…〕
意志の概念はまさしく、信仰の中で発見されていきました。それを作ったのは、パウロやアウグスティヌスらのキリスト教哲学であったとアレントは言っています。〔…〕
私はこの意志という概念に現代社会が取り憑かれているという気がしてなりません。何もかもが意志によって説明されてしまう。私たちは意志を信仰しつつ、意志に取り憑かれ、意志に悩まされているのではないでしょうか。」
国分功一郎『スピノザ「エチカ」』,pp.86-87,90-92.
青字は原文の傍点付き文字。
自由だ! 自由だ! 自己責任…… あっ、そこに落とし穴がっ
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]








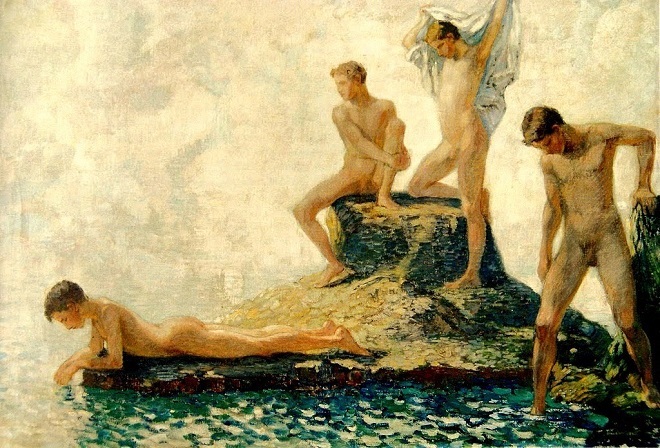

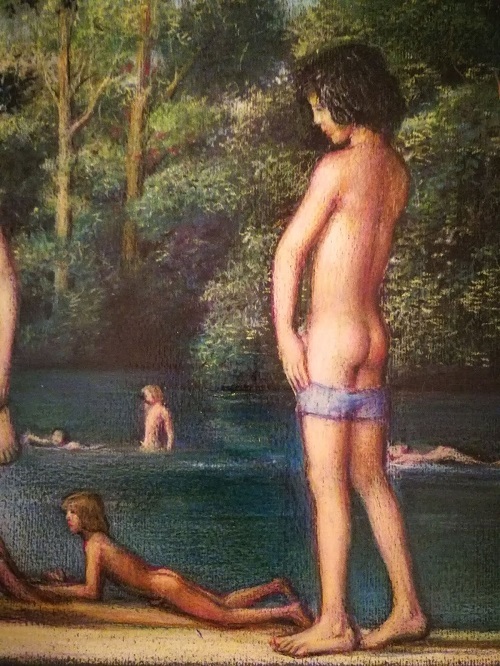
 彡
彡