11/28�̓��L
22�F20
�y�K�Ǐ�150�z�ΐ��w����ǂ̌���x(2)�\�\�\�g���ꂽ�܂܁h�̂͂����̍�
---------------
.
 �@
�@
���R�@�����s�E��R���@�@�@
�@�����́B(º.-)���
�@�y�K�Ǐ�150�z�ΐ��w����ǂ̌���x(1)
�@����̑����ł��B
�@�y�S�z�g��p�����h����̑�\�\�\������z����
�@1907�N5���͂��߁A����́A�A�E����킸���P�N�ŏa���q�포�w�Z��ސE���A�k�C���E���قɈڂ�܂��B
�@���̒��O�ɁA�w�Z�Ő��k�����́g�X�g���C�L�h���g�w���h���Ă��邱�Ƃ���A�w�Z�̑̐��ɔ��R���Ĕ�яo�����悤�ɂ������܂��B�������A����́A�g�X�g���C�L�h���ȑO�ɁA���ق̏��w�Z�ɑ�p�����̐E���m�ۂ��������Ŏ��\���o���Ă���A�Z���͑ސE���ԗ����Ă����Ƃ���A���k�́g�X�g���C�L�h���N�������߂ɁA���\������������Ȃ��Ȃ����̂������ł����B
�@����͂Ȃ��A�̋��̏a�����w�Z��ސE�����̂ł��傤���H
�@�ЂƂɂ́A�A�E�̓�������A���̐E�ɂƂǂ܂�̂͂P�N���x�ƌ��߂Ă������Ƃɂ��܂��B�O����p�����A�E�O��̎莆�ɂ́A���̂悤�ɂ���܂��F
�u�A�E�O�A�^�Ӗ�S�����ɑ������莆�k�c�l
�@�w����S����蓖�����w�Z�ɋ��ڂ��Ƃ锤�ɑ�������B�k�c�l����͎����g���]��ł̎��Ɍ����B�A���A���ȗ��̋����@����鎖�ƁA�C���ɂȂ�Ή����ł���߂鎖�Ƃ́A�S���w�����m�̏��ɂď��������̂ɌւA�k�c�l�x
�@�k�c�l���͏A�E��P�����A�F�l���}�����ւ̎莆�k�c�l
�@�w�k�c�l�䂪�ݐE�͊W�������炴����A��������́A���̒����炴��Ԃɉ��āA�\���ɐl�i�I��b��L����P���Ȃ銴�����̎R�̎q�킪�����ɍ��܂ނ��Ƃ������B���ꎍ�l����\�̖{�\�I�v���Ȃ�A������ɉ���̕�V�����\��������䂪�S��̊�]�Ȃ�A�k�c�l
�@�@�\�͏A�E�ȗ����P�B�������N���܂��\�̔@�����k�̐S���Ђ�����̂��A�\���A�E�ȑO�̞X�J�́A���Q�Ɋ��ꂽ��\���A�ʂ��Ē��r�ɂ��Č��ӂɊׂ炴��������ۂ�̖��Ȃ肫�A���������݂̐S�z�́A�\�͉ʂ��ė\��̂P���N�ʂɂĂ��̐_���Ȃ鋳�d��ނ������ۂ�̖��Ȃ��A�Z��A���l�݂̂悭�ЂƂ�^�̋���҂��肤��ɂ͔邩�B�x�v
��c���O�Y�u�N���t�Ƃ��Ă̑�v,in�F�w�ΐ��ؑS�W�x,��W���w��،����x,1978,�}�����[,pp.214-215.
�@���Ȃ킿�A���������Ɂg��p�����h�ƂȂ��Ă���́A����̈ӗ~���݂����ė]�肠��قǂ̎q�������Ƒ����̎x�����A����́A�Ή��ɖZ�E����܂����B���̂܂a�����w�Z�ő����Ă��A���������͂Ȃ������͂��ł��B�ɂ�������炸�A�g�\��h�ǂ���ɑސE�������R�́A����Ȑl�тƂɂ��W�Q�\�\����͏A�E�O�����т��Ă���܂����\�\�Ƃ����������������A�ގ��g�̓��I�ȗ~���ɋ��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�a���ł̋�����H�Ɏ艞����������Ί�����قǁA����́A�ގ��g�̂��傫�ȁg�ۑ�h�Ɍ������čs�������ӗ~�����Ă��܂����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H ���̂��߂ɁA�g�V�V�n�h�����߂Ėk�C���ւ̈ڏZ�����݂��̂ł͂Ȃ��������H�d
�@���̂ւ������́g���I�h����������邽�߂ɁA�����łӂ����сA�a���g��p�����h����̒��r�ŏ����ꂽ�w�ђ����x����A�ނ̂��Ƃ��E���Ă݂����Ǝv���܂��F
�u�푈�ɏ��������̕������A���������̕��������D���Ă��邩�ǂ����H �k�c�l�ߑ㕶���̓��F�́A���i���ɂ��j���̊��c�i�M���V�A�j�Ɠ������l��̗}����ے肵�Čl�̎��R�����i���Ɓj�ԓ_�ɑ�����B�����āA�I�����k���V�A�l�͎��ɌN��ƍٍ��ȂB�I�l�̍ő命���͂��̈�̎��R���A��������тɏ@����̎匠�҂Ȃ�U�[�ɒD���Ă���B����ɔ����Ă��̓��{�͗������ł���B���{�l�͘I�l�ɔ䂵�āA���Ɋ��{�ƒm��ʑ�������R��^�����Ă����B�Ɖ]���ƁA�ǂ������{���������ŘI��������؍��̂悤�����A����͕\�ʂ̎��B���{�l�͗^����ꂽ���R�ƌ����Ƃ��A�ǂꂾ������ł��邩�B�����ɂ��ĕێ����Ă��邩�B���Ƃ��Ĕޓ��́A���̓V�̎��i���܂��́j�����͂⊯�͂̑O�ɂ����Ԃ�����ɔ����āA����Ƃ���̎�������ɑウ�A���ɑウ��悤�Ȏ��͂Ȃ����B���q�Ȗ��O�Ȃ�܂������̎��A�����Ƃ����l�Ԃ̌����Ǝ��R�Ƃ��\���铰�X�����c�m�܂ł��A���̍��M�Ȃ��͕��i���܂��́j�����Ȃ̗��Q���S�̂��߂Ɏ̂ĂČڂ݂���悤�̎��͂Ȃ����낤���B
�@���N�A�I�����͖�؍��ł��邩���m��ʁA�������Ȃ���\�́A�����̔@���O�S�̑�c�m�𑑗�Ȃ�c��ꗡ�ɗ�����������{�l�����e�ۉJ��̍J�A�v���̌����̐w���ɗ����Đ��˂����i�����j�����邽����l���K�|���m����L���郍�V�A�l�̕����A�p���ēV�̒����ł͂���܂����ƍl����B�k�c�l
�@�J���Ƃ����I�����̈�n���̔_�����́A�Q�[�~���̂��߂ɐ��{�ŗ^��������i���j�̋��������āA���q�i�p���j�킸�߂����i���Ɓj�߂��A�F���i�����j���ďe�ƒe�ۂƂ��w�i�����ȁj�����Ɖ]���ł͂Ȃ����A�e�ƒe�ۂƂ́A��������܂ł��Ȃ��A�ޓ��̒D��ꂽ�����R����߂��ׂ�����ł���̂��B�v
�u�ђ����v, in�F�ΐ��w����ǂ̌��� �H���ׂ��� ���\�сx,1978,��g����,pp.17-18.
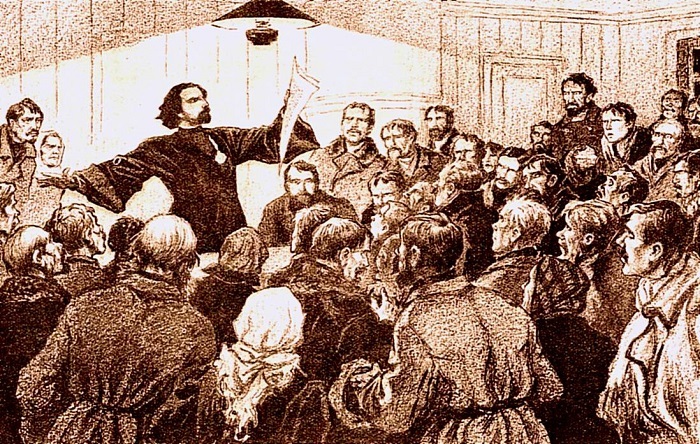
���V�A��P�v���@�Q�菑��N�ǂ���K�|���_��
�@�����ɂ́A�g���R�h�Ɋւ����̎v�z���悭�\��Ă��܂��B��ɂ��A�g���R�h�̖{���́A����C�܂܂ł��A�֗~�����ł��Ȃ��A�����ɑ����R�ɂ���̂ł��B
�@�u�K�|���m���v�́A�����̃��V�A�̐��E�҂ł����A���I�푈���ɖu�������s���V�A��P�v���t�̈������ɂȂ����l���ł��B���I�푈�����{�D���̏�ԂŏI�������̂́A���{��������������ł͂Ȃ��A���V�A�̍����Łs��P�v���t���N��A�푈���p���ł��Ȃ��Ȃ������߂ł����B
�@�K�|���_���́A���O�ƂƂ��Ƀc�@�[���𐒔q���Ă���A�c��̗͂ň������Ȃ��������Ƃ������O�̊�]���ق��Ă��܂����B���̉^�����A���ʓI�ɂ͊v���̓��ΐ��ƂȂ����̂ł��B
�@�������A�v�����i�s���Ă䂭�ƁA�w�������������Љ���`�҂⋤�Y��`�ҁi�{���V�F���B�L�j�́A�����������O�̎v�z�𗝉��ł����A�K�|�����g�c��̃X�p�C�h�ƌ��߂��ċ��e���܂����B���ꂪ�\�A�ł����������ƂȂ������߂ɁA�K�|���̉ʂ��������j�I���т́A������݂��邱�Ƃ�����܂���ł����B�Ƃ��ɓ��{�ł́A������������`��M�A�K�|���݂̂Ȃ炸�g���O�ɍł��߂��h�w���҂��ׂĂ��A�܂�ň����̂悤�Ɍ������l�镗�����A�P���I�߂��ɂ��킽���Ė��������̂ł����B����A���܂ł�����͖����Ȃ��Ă��Ȃ��B
�u�Q�I���M�[�E�A�|���m���B�`�E�K�|��(1870-1906�j�́A���V�A������̎i�ՁB1905�N��ꎟ���V�A�v���ɂ����Ďw���I�Ȗ������ʂ������B
�@�K�|���_���́A�T���N�g�y�e���u���N�̘J���҂��W�߁A�J���ґg�D�����グ���B�g�D�̖ړI�͎Y�Ɗv�����n�܂���������V�A�̘J���҂̌�����ی삵�A�������ƐM�S�����߂邱�Ƃɂ������B
�@���I�푈����1905�N1��22��(�����E�X��1��9��)�A�O���̃[�l�����E�X�g���C�L�ɑ����A�K�|���_���̑g�D�����J���҂������A�~�{�ɂ���j�R���C�Q���ւ̒Q���ړI�ɁA�y�e���u���N�̑�ʂ�Ńf�����s�Ȃ��Ă����B���̗�ɁA�x���̌R�������C���A����l�̋]���҂��ł��i���̓��j�������j�B
�@�Q�菑�̓��e�́A���@�����c�̏��W�A�J���҂̏������̕ۏ�A���I�푈�̒��~�A�e��̎��R���̊m���ȂǂŁA���E�n���E�푈�ɂ������ł��������̃��V�A���O�̑f�p�ȗv�����ق������̂������B
�@���V�A���O�́A���V�A������̉e���̉��A�f�p�ȍc�鐒�q�̊ϔO�������Ă����B���O�́A�c��j�R���C�Q���ɒ��i����A���ׂĂ͉��P�����ƌ����M���Ă����B�s�i�Q���҂͂U���l�قǂɒB�����B
�@���ǂ͌R�������āA�f�����𒆐S�X�֓���Ȃ����j�ł��������A�]��̐l���̑����ɐ��������A�R���͊e�n�Ŕ��̃f�����ɔ��C�����B���C�ɂ�鎀�҂̐��́A�����{���ɂ��� 4,000�l�ȏ�A�T�d�ɊT�Z�����ł��A������1,000�l�ȏ�Ƃ����B
�@���̎����̌��ʁA�c�鐒�q�̌��z�͑ł��ӂ���A�S���K�͂̔����{�^�������̔N�u�������i��ꎟ���V�A�v���j�B
�@�������A�K�|�����c��̃X�p�C�ƌ��Ȃ��l�������A���N�A�ނ͎Љ�v���}���ɈÎE���ꂽ�B�v
�u�I���̔_���͎��Ɂw���R�̖��x�ł���B���݂ł͂Ȃ���ȓz��I�ȋ����ɂ���ɂ��Ă��A������̔@�����R�̈ӋC�́A�₪�Ĉ�̕�����吞�f�����n���ׂ�����O�z�F�ł͂Ȃ����A�l���̍ő�ŋ��Ȃ銈�͂ł͂Ȃ����B���A���N�A���{�l������̖�������߂�����̏\���N�O�́A���R�Ƃ����ō������͕������i���j���ׂ��A�������̎����ɒB���Ă��Ȃ������̂ł͂���܂����B�ђ��̏j�ς�������̏������ƕ�̊Z�𒅂����O�Ԓ����̑����������ꂽ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������낤���B���Ă͌��A�����Ă͌������̂́A���̉��̒m��Ȃ���Ηp�@���m��ʁA�܂��̗p�ӂ������Ă���B���{�l�͋ߑ�̕������ߕ��ɂ��ēZ���Ă���A�I�l�͂����[�������ɑ����Ă���B�k�c�l
�@�X�ɂ��A�w��̎��R�A�M�̎��R�A���_�̎��R�A�����̍����Ȃ鎩�R�́A�I�l�̈���L������Ƃ���ɂ��āA�������ē��{�l�̎����L����Ƃ���ł���B�ɂ�������炸�A���I�E�g���X�g�C���͉��̓��{�ɐ��ꂸ���ĘI�����ɐ��ꂽ�ł��낤���H
�@�\�͉]�����A���{�O�S�̑�c�m�����A��l���K�|���m���̕��������ƁB�����Ӗ��ɂ����āA���{�l�ɗ^����ꂽ���̎��R�����A��̕s���R�̒��ɂ��Đ^�̎��R���Ă����m���k�g���X�g�C�\�\�M�g�����l�̈�V��̕����M���Ɖ]�������o����B�������Ӗ��ɂ����āA�\�͉₩�Ȗ�����̕��������A���Q�ҏ��̊��x�ƂȂ��č��̖�����������A�x�a���҂��S���L�C�̕����A�^�̕����̂��߂ɁA�y���ɗy���ɏj���ׂ��ł���ƍl����c�c�B�v
�u�ђ����v, in�F�ΐ��w����ǂ̌��� �H���ׂ��� ���\�сx,1978,��g����,pp.18-19.
�@
�@�@���V�A��P�v���@�e�����ƌ��������f���̖��O
�@�@�@�@�i�����W�~���E�G�S�����B�`��j
�@�g���R�h�ifreedom, Freiheit, liberté�j�̊T�O�́A���`�I�ł���A�܂����j�I�i���ゲ�ƂɈӖ����e���قȂ�j�Ȃ��̂ł��B
�@�����ȑO�̃��[���b�p���u���R�v�Ƃ́A�z��łȂ����ƁA�܂葼�l�Ɏx�z����Ȃ����Ƃ��Ӗ����܂����B���̔��ʂ������A�u���R�v�Ƃ́A���l���\�\�z����x�z���邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@���̈Ӗ��́u���R�v�����ʉ�����ƁA���Ȃ��x�z���邱�ƁA�����A���Ȃ킿�ߑ�N�w�E�ϗ��w�ł��u���R�v�̊T�O�ƂȂ�܂��B
�@�����A�ߑ�ɂ����鐭���I�u���R�v�́A��������̉���A�ꐧ�ɑ����R�Ƃ��ăC���[�W����܂��B�u���R�v�Ƃ������ɏ�Ԃ����A�u���R�v�����߂Đ키�ӗ~���d�������̂ł��B
�@����̃C���[�W�����u���R�v�́A�����ς��R�̈Ӗ��\�\�����I�u���R�v�������Ƃ����܂��B�������A���������u���R�v�̊T�O�������Ă���l�́A���{�̋ߑ㕶�w�҂̂Ȃ��ł͂ނ��돭���ł����B
�@��؈ȊO�̕��w�ҁA���Ƃ����Ėڟ����́A�ǂ�ȁu���R�v�̊T�O�������Ă����ł��傤���H
�u�w�R���䢂ɍ���̐푈�k���I�푈�\�\�M�g�����l���n���Ĉȗ����Ȑ����ŁA�k�c�l�A��A���Ƃ����L�l�\�\�k�c�l�z�����𐧂��Č���ƍ����̐^���������̏�Ɍ���ꂽ�S�n������B�k�c�l���̎��M���o���J���Ă���ƁA���̔����͂�������ʂɔg�y���ė���B
�@�@�T�A�����Ȃ��ė���ƁA���w�̕��ʂɂ����_���̉e���͗���̂ł���B�k�c�l
�@�@��X�͍����Ƃ��đS���E�̉����܂ł��ʗp����B��M�̉ߋ��ɂ͕��w�Ƃ��Ă͑�Ȃ鐬�����ׂ������̂͂Ȃ����A���ꂩ��͐�������B���ꂩ��͑匆�삪���삳���B�k�c�l���m�̂ɔ�r���꓾����́A���₻��ȏ�̂��̂��o���˂Ȃ�ʁB�o�����Ƃ��o������Ƃ����\�\�C�T���o�ė���B�x�k�Ėڟ��w��㕶�w�̐����x1905�N�l
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@���{�̓��V�A�Ƃ̐푈�ɏ����Ƃɂ�胍�V�A�ƑΓ��Ȉʒu�ɗ������݂̂Ȃ炸�A�������Ď������������V�A���ゾ�Ƃ������M�����悤�ɂȂ�܂����B���k�Ėڟ��\�\�M�g�����l�����w�̔��B������w�i�Ƃ��Ď������w���R�Ȋ����x�Ƃ́A�Γ����ƂƂ��ɗD�z�����������Ƃ������Ƃ𐄑�����̂�����قǓ������܂���B
�@���Ȃ݂ɁA�w���R�Ȋ����x�͟��������������̂ł͂���܂���B�k�c�l��t���l�������I�푈��ɑ�A��K��A�k�c�l
�@�w���s���l�͊F�䂪���E�ł���B�k�c�l�N�ɉ������Ȃ��������i�Ӂj���đ哹��舕�������A�l�͊������Ċ������Ċ���Ȃ������k�c�l
�@�@�l�͖����ł���������A�k�c�l���ߊ|���̐l�k�܂���{�l�\�\�M�g�����l�����낼��Ƃ���߂��Ȃ���s���B�n�C�J���̑����ƘA�������̂����i�����ȁj���Ȃ��B���Ԃ������Ȃ��x�ߐl�̕������Ԃ̒E��������U���Ăĕςȓ��{����P�ƁX�X�ƌĂ�ōs���A�k�c�l�l�͖����X�X���܂�Ȃ��B�x�k��t���l���w���I�L�x1908�N�l�v
�މj���E��,����C�E��w���E���w�̍\���x,2016,��g���X,pp.59,61-62.
�@�Ėڟ������A���I���̖��F�E��A��K��āA���̈�ۂ��L���Ă��܂��F
�u���������F�ɉ������A�܂������������̂��k�c�l
�@�ЂƂ͖��F�Ƃ�����Ԃɑ�������ł��B�����A���F�͑�X�I�ɓs�s�������Ȃ���A�Y�Ɗ�Վ{�݂����荞��ł���Œ��������̂ł����A�����݂͂ȍŐ�[�̂��̂ł���A���Ĕނ��������Ƃ̂Ȃ��������̂ł����B�k�c�l
�@���B�����{�l�ɂ�����������狐��ȓs�s�Ȃ����Y�ƒc�n�ɕϖe������A�ƂĂ����C�Ɉ�ꂽ��Ԃł����B�k�c�l
�@�����ЂƂ̊���������l�^���N�l�ɑ���y���ł��B��i�܂�j�����F�̔��W���ƑΔ䂵�āA�������\�Ȓ����l�^���N�l�̎p���Ƃ���ǂ���ɓo�ꂵ�܂��B
�@�w�݂͊̏�ɂ͐l�������������ł���B����ǂ����̑啔�����x�߂̃N�[���[�ŁA��l���Ă����Ȃ炵�����A��l���ƂȂ����ꂵ���B�k�c�l�x�߂̉ƂɌŗL�Ȉ��̏L���A�����܂��@�Ɋ������̂ŁA�k�c�l�����ɂ����Ȃ������ł���B
�@�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�@�l�͓͂��{�l�̔����������̂ł��邯��ǂ��A���q���x�ߐl�������͒��N�l�ł���Ԃ͂������Ė��f���Ă͂����Ȃ��B�k�c�l�����i���܁j�̌̐Ղ����ɍs�������Ȃ��́A�K�����c��ɗ����t���ɂ��Ȃ��قǗh�ꂽ�B�k�c�l���܂������N�l�̓���������ƒ����Ă�肽���Ȃ������炢�c���Ɏ戵��ꂽ�B�x�k�Ėڟ��w���Ƃ���ǂ���x1909�N�l�v
�މj���E��,����C�E��w���E���w�̍\���x,2016,��g���X,pp.50-51.

������ՁE�{�ۂ���̕��i
�@�܂�A���A�l���ɂƂ��Ă��g���R�h�Ƃ́A�g�A���n�h�i�����j���A���̒n�́g��l�h�Ƃ��āA�u�����ӂ���舕��v����g���R�h�\�\������ł���A�u���Ȃ炵���v�����l�^���N�l���x�z���y�̂��閳��̗D�z���Ȃ̂ł��B����́A�u���R�v�̍ł��ÓT�I�ȈӖ��ɏƉ�����ł��傤�B
�@����͌����Ĕނ�Ɍ��������Ƃł��A���{�Ɍ��������Ƃł�����܂���B������鍑��`���̍������w�́A���̗D�z���̏�ɐ������Ă���\�\�\�ƁA����؍��̔�]�ƁE�މj���͌����܂��B
�@�����āA�������w�Ƃ́A�鍑��`���\�\���̖������x�z���鍑�Ɓ\�\�ɂ̂ݐ���������̂Ȃ̂ł��B
�@�������A���̉s���w�E�ɑ��āA�������́A�c�c�ł��A����ł��A���{�ɂ́g�����ЂƂ̍������w������h�ƌ����āA�����掦���邱�Ƃ��ł��邩������܂���B
�@��́A���Έȏ�Ɂu���R�v�Ƃ������Ƃ𑽗p���܂����A���̈Ӗ�����Ƃ���́A�����ς�O�q�̑�R�̈Ӗ��\�\�\�����ɑ����R�Ƃ����A�ߑ�̐����I�u���R�v�Ȃ̂ł��B
�@����͂��̒Z�����U���A��������k�C���܂ł̋�Ԃ̒��ł������܂����B���N�ɂ����F�ɂ��s�������Ƃ͂���܂���B�������A�ނ������A���F��K�ꂽ��A��t������Ɠ������z�����炵���ł��傤���H
�@����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ǝv���̂ł��B����́A�����l�̘J���҂��u���Ȃ��v�ƌ����Čy�̂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ł��傤�B�����v�����R�́A�Q����܂��B
�@�ЂƂ́A����̎��l�Ƃ��Ă̊��o�ł��B�u���Ȃ炵���v�Ƃ������Ƃł����A��茧�a�����̔_�����A�q���������A�����ň�����ގ��g���A��A�̃N�[���[�ɗ��ʂقǁu���Ȃ炵�v�������͂��ł��B���̂������A����̕��ɂ́A�u���Ȃ��v���Ƃ�p�Ƃ����A�ނ���u���Ȃ��v�Ɍւ�������Ă���悤�ȕ������U�����܂��B
�@�����ЂƂ́A�ނ��A�k�C���ɑ��ĕ�������ۂł��B�k�C�����܂��A�����̓��{�l�̈�ʓI�Ȋ��o�ł��u�A���n�v�i�����j�ł����B������k�C���ɂǂ�Ȉ�ۂ���������ɂ��ẮA�̂��قnj��Ă䂭���ƂɂȂ�܂����A����l�������F�ɑ��ďq�ׂ����z�̂悤�Ȃ��Ƃ́A�܂����������������Ƃ��ł��܂���B�D�z����y�̂̊���́A�܂��������邱�Ƃ��ł��܂���B�i��̓A�C�k�ɂ͐G��Ă��Ȃ��̂ŁA�Ώۂ͂����ς�a�l�ł����j�����Ɍ�����̂́A�ނ���A�Â����n�Љ�́g���K�h���玩�R�ɂȂ����u�͂����́v�l�Ԃɑ��鋤���������ƌ����܂��B
�����u�A���n�v�F�@���I���̒i�K�ł́A���N�����F���A���܂��@�I�ɂ́u�A���n�v�ł͂���܂���ł����B�������A�����̓��{�l�́A�����̒n�������u�A���n�v�ƌĂ�ł��܂��B���̊O�����A�����E���N�̐����Ȑ��{���˂��āA���{�̌��͂����R�ɂ܂���ʂ�悤�ɂȂ����Ƃ����Ӗ��ŁA�����̒n�͂��łɁu�A���n�v�������̂ł��B�������Ƃ́A�k�C���ɂ��Ă������܂��B���Ƃ��Ɠ���ȊO�͓��{�̔Ő}�ł͂Ȃ������ȏ�A�����́u�A���n�v�ƌĂꂽ�̂ł��B
�@�����̓��{�l�̊ϔO�ł́A���{�́s���I�푈�t�ɂ���Ē��N�Ɩ��F���u�A���n�v�ɂ����ƌ�����ł��傤�B
�@�y�T�z�ЊQ�ƕ����̌o������
�@1907�N5���A���قɈڂ�������́A���H��c���ɒZ���ԋ߂����ƁA�����ł��q�포�w�Z�̑�p�����ƂȂ�܂��B8���ɂ͐V���Ђ̗V�R�L�҂����˂܂����A8��25���́s���ّ�t�ɂ��A�Ζ���̏��w�Z�E�V���Ђ��A�Ƃ��ɏĎ����A��͐E�����߂ĎD�y�ֈڂ邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�������A�s���ّ�t�́A��̎Љ�v�z�ɑ��āA�傫�ȃq���g��^���邱�ƂɂȂ�܂����F
�u��O���O�̎��ł���B�r�Ŋ����S���ĂƂ���r�C���z�I���ɓ���ƁA�����̏��������i���悭�j��Ō�Ă��O�l�A�̐a�m���L���B�k�c�l
�@�₪�Ĕޓ��͕����o�����B����́w���x�̎��x�ɏA���āU�L���B���x�̎��̉����邩�͌��i���Ƃ�j�莄�̒m��ʏ��A���m�炤�Ƃ��韆�����߂͖������B�k�c�l�\�\���x�̎��ƌ��ӂ̂́A���ɁA�ߍ��K�����ꖡ�̖����{��`�҂���Ă�����[�����k�s��t�����t�\�\�M�g�����l�̎������̂ł���B
�@���̑����N�������҂͑R�����ꂾ�����ނ�����Ȃ����B���̂Ȃ�Δނ̎O�l�͊Ԃ��Ȃ�������Z���ďo�čs������ŗL��B
�@�\�\�����l�\�N���������ّ���̍ہA�������قɍ݂Đe�����ނ̔ߚ�Ȃ���i��ڌ������B�Ύ��̌�A�Ƃ������O�l�݂̎s���́A������F�����̉��̂����߂āA���k���ƁX�ɓ��������B�@���ɏ������Ƃł���Ƒ��Ⴍ�͎O�Ƒ��̋l���܂�Ȃ��Ƃ͖������B
�@�������͕����ɉ��Č��邱�Ƃ̏o�҂Ȃ��A�s�v�c�ȁA����������������Ȃ錻�ۂ������B����́A�����鐧�x�Ɛݔ��ƊK���ƍ��Y�Ƃ̝������ꂽ�|�ɁA�l�Ԃ̔���������̋p�čł��ԗ��X��ᢘI����ꂽ�����ŗL���B�ޓ��̖ւ�����Ȃ�h���́A�ޓ������ĉ��̌ڗ����Ȃ������̋��X�̈���̂Ă������B
�@�ޓ��͂��U�ޓ��̏����Ȃ����ݕ}���̊�������݂̕K�v�Ƃɝ��āA�y�X�Ƃ��Ĕޓ��̐V�炵���Ƃ����邱�Ƃɋ}�����B�����đ����ޓ����A����̋��X���̂Ă�ਂɂ�����桂́A�w���ۂ�����x�Ƃ��ӈ��ł����B
�@�����͂悭�c���̔��ق̏�Ԃ����l�ɂ������������B�������ꊈ�p�̖��ŗL��B
�@�\�\�����č��ނ̎O�l�̐a�m���A���{�J蓈Ș҂̐V��������Ӗ��[�������k�s��t�����t�̂��Ɓ\�\�M�g�����l���A���U�d�Ɂw���x�̎��x�ƌ����B����������������ꊈ�p�̖��Ŗ�����Ȃ�ʁB�w���ƍI���������炤�I�x���͉�����X�i�Ђ�_�^�j�����ޗ��u�i�R�c�v�j�������ԁA��l�H���ɔ���Ō����B
�@�Ԃ��Ȃ��������|���o���B��������
�@�_���̊X���̔������P���n�߂��X�����ȕ��݂��^�тȂ���A���͂܂����̋����ɏP�͂ꂽ�B�������X���{�l�̈�����A���Z�S�N�̒������j�ɗ{�͂�Ę҂�������̐����ɏA���āU�L���B�\�\������͊W����X���������ɍl�ւ������A�P��w�[���A���A�����̂ŗL��B�ނ̕ւɍ�����ɌŎ����Ă��ێ�I�v�z�Ǝ��g�̒l���݂��Ă������A���Ƃ��Ɛ[�����A�����̂ŗL��B�\�\�����āA���S�P�N�O�̗P���l����h��̖��𔒒n�i�����炳�܁j�Ɍ��ӂ�����ėB�w�i�U���l�i�тƁj�x�ƌ�����ɁA���x����Ɠ�����ɁA�ނ̎O�l�̐a�m�����āA�����{��`�Ƃ��ӌ��t�����ɂ�����S�O���ėB�w���x�̎��x�ƌ��͂��߂��A����������炭�͍����{�l�̓���Ȃ鐫��̈�łȂ���Ȃ�Ȃ����B�v
�u�������x�̎��v1910�N6����, in�F�ΐ��w����ǂ̌��� �H���ׂ��� ���\�сx,1978,��g����,pp.123-124.
 �@
�@
��؉̔�@���ٌ����@�@
�u���ق̐����������Ȃ�����
�@�F�̗��́@���܂̉ԁv�@
�@���̕��͂ɂ́A�㖼���ƁA�g������h��̊W���s���m�ŁA�����ւ�킩��ɂ�������������܂����A�����炭��͕M�Ђ�������āA�����ĞB���ɏ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ŁA�����Ƒ�ӂ��d�����ċ����ɓǂ݂��ނƁA���̂悤�ɗ����ł��܂��B
�@����́A�u��X���{�l�̈�����v�u���Z�S�N�̒������j�ɗ{�͂�Ę҂�������̐���v�ɒ��ڂ��Ă��܂��B�u������͊W����X���������ɍl�ւ������A�P��w�[���A���A�����̂ŗL��v�Ƃ������Ă��܂��B2600�N�̗��j�̒��Ŕ|���Ă������{�l�́u����v�Ƃ́A�����w���Ă���̂ł��傤���H ����́A������A�s���ّ�t�̂̂��̕����̉ߒ��ł́A���O�̂������́u���ݕ}���v�̏���m��܂����B
�u�Ύ��̌�A�Ƃ������O�l�݂̎s���́A������F�����̉��̂����߂āA���k���ƁX�ɓ��������B�@���ɏ������Ƃł���Ƒ��Ⴍ�͎O�Ƒ��̋l���܂�Ȃ��Ƃ͖������B�v
�@���̂悤�ȏł́A�N�����u�����̋��X�̈���̂āv�āA���Ă�]�͂������L�ׁA�K�v�ɉ����Ď��ق��͂���܂���ł����B�����ɂ́A���^�Ɓg���Ԃ��h�̔��ʂ����Ă���]�T���Ȃ��A�ł����o�����߂��K��������܂���ł����B�����A�u���ݕ}���̊���v�Ɓu���݂��K�v�v�������D�悳�ꂽ�̂ł��B
�@���̏��ꌾ�ł����A���p�̏I��ɖ��w����Ă���u�����{��`�v�ɂق��Ȃ�܂���B
�@�s��t�̂̂��Ƃ������ʂȏ̂��ƂŁA
�u�����鐧�x�Ɛݔ��ƊK���ƍ��Y�Ƃ̝������ꂽ�|�ɁA�l�Ԃ̔���������̋p�čł��ԗ��X��ᢘI����ꂽ�v
�@�Ƃ����̂ł��B
�@���́s���ّ�t�̌o���́A�k�C���\�\�u�A���n�v�ɑ�������̈�ۂƗ���������Â����ƌ����܂��B
�@���܂��܂Ȉ��K��C���˂⊵���ɂ܂莖�ɂ���Ă�����߂ɂȂ������n�̋����ȎЉ��́g���R�h�Ɖ�����A����͂����Ɍ��܂����B�ނɂƂ��Ă���́A�l�Ԃ��{�������肩���ł���Ɠ����ɁA���������肩���ł��������̂ł��B����́A���́u�����{��`�v�I�ɂ��āA
�u�ނ̕ւɍ�����ɌŎ����Ă��ێ�I�v�z�Ǝ��g�̒l���݂��Ă������A���Ƃ��Ɛ[�����A�����̂ŗL��B�v
�@�Ƃ������Ă��܂��B�u������ɌŎ����Ă��ێ�I�v�z�Ɓv�Ƃ́A���l�́u���ݕ}���v�́g�����h���̗g����l�����A���邢�́A�u�ϓc���v�u��c���v�Ȃǂ̌��n���Y��`�I�ȑ̐����ق߂��������w�҂̂��Ƃł��傤�B���O�̐S�̒��ɖ����Ă��������{��`�I���[�g�s�A�́A�ϗ��⑺�́g��������h�Ȃǂ��āA�����Ƃ����Ɓu�[�����A���v���̂��ƌ����̂ł��B
�@�s�K�������t�Ȍ�̑�́A���̔��قł̌o�����Ă��ɁA�u�����{��`�v(��̗����́A���Y��`��[�g�s�A�Љ��`���܂�ł���j�ɑ��ė�����[�߂Ă䂭���ƂɂȂ�܂��F
�u�^���b�ɉ����������{��`��ᢒB�y�ё��^���ɑ����̒��ӂ�c�ӎ҂́A��Íŏ��ɟ��̕t��������L��B��͖����{��`�҂ƌ��͂�T�҂��k�c�l�A�����_�ɉ��ẮA�k�c�l�w�lj����̊�訂ȗv�f���܂�ł�Ȃ����ŗL��B�i�B�ޓ��̐��������A�l�Ԃ̍����ɉ����鐶����ԂƂ͔��ɋ����̗L�鐶����Ԃ̎��ŗL�邾���ŗL��j�B�k�c�l
�@�Ⴕ�����������{��`�Ƃ��Ӗ����������Ŕ������i�Ђ��j�߂��Ȑl���L�āA���l�������ނ̖����{��`�ғ��̏����ׂČ���Ƃ���Ȃ�A���x�A�������Ԉ�ւĕʂ̉Ƃɓ��Ę҂���ȋ������S鄂��邾�炤�Ǝ��͎v�ӁB
�@�ޓ��̈��҂ɂ��ẮA�����{��`�Ƃ��ӂ̂͋l��A�}�Ă̐l�Ԃ����|���ł��Ċ��S�Ȃ�l�ɂ܂�ᢒB������Ԃɛ�����A�M��Ȃ铲�ۂɉ߂��Ȃ��B
�@�����҂ɂ��ẮA���ݕ}���̊���̚��ނȂ�ᢌ��𐋂����Ԃ��Ă�Ŗ����{�̏�Ԃƌ��Ă�ɉ߂��Ȃ��B
�@�k�c�l���ɂ����ނׂ����\�Ȃ�l�Ԃƌ����Ă�閳���{��`�҂ƁA��ʋ���Ƌy�їϗ��{�҂Ƃ̊ԂɁA���ꂾ���̑���������̂ŗL��B�l�ނ̖��҂�萂����X�̗��z�͊W�����i���j�ŗL���k�c�l�����{��`�҂Ƃ͕L��w�ł����}�i�������j�Ȃ闝�z�Ɓx�̈��łȂ���Ȃ�ʁB�v

���M�`�]�s�̊C��
�@�y�U�z�u�A���n�v�Ɓg�͂����h�̖��O
�@1907�N9���A����͎D�y�ֈڂ�A�w�k��V��Ёx�ɍZ���W�Ƃ��ďA�E���܂����A�����ł̓����ɗU���ď��M�ֈڂ�A�w���M����x�̑n���ɎQ�����܂��B�������A12���ɂ͎Ђ̓����̂��߂ɑގЂ�]�V�Ȃ�����A����ɋ��H�ւƈڂ�܂��B
�@���M�ł̑؍݂͒Z�������̂ł����A�L�҂Ƃ��Č��M���ӂ邤���Ƃ��ł����悤�ŁA�w���M����x�ɒ��ڂ��ׂ����͂⎍��i���f�ڂ��Ă��܂��B
�u���R�ɑ���|�]�́A�������Ȃ���A���łɔϑ��Ȃ鎀�@�����`�������ێ�I�Љ�ɂ���ẮA�˂Ɏ�嶂̂��Ƃ������A�����̂��Ƃ��������B
�@���ꑼ�Ȃ��A��\�N�������͊��S�N����N�̈��P�I�@���������Čl�̌��\�𑩔�����Љ�ɑ��āA��Ɖ䂪�V�n��ނƂ���l�́A�����܂������̑ԓx���̂�N���̍s���ɏo�Ȃ���Ȃ�ʁB�l�̗͂}���悤�₭���ɂ��������Ă͂��ɂ���ɔ��t���j��̋��ɏo��B�K���Ƃ����K���Ƃ����Љ���Ƃ����A�䂪�����ɔ����A�䂪���鋷�������ɑĖ����Â�k�y�́A�����ɂ����ĘT�����A�������A��������̎�i�������āA����ɂȂ��āA�䂪�E���Ȃ�N���҂𔗊Q����B�����Đl���͉i���̐��ł���B�k�c�l
�@�����ɂ����āA���_�E�ƕ����E�Ƃ��킸�A�Ⴋ�����̊������ɔR���������̕��_���́A�������Ė��l�̋��ɓ���A��݂�����̐V�炵�����j����݂�����̗͂ɂ���Č��݂���Ƃ���B�A���I���_�ƐV�J�n�I��Ƃ́A�����ċ����ׂ����͂�l���ɐA�����Ă���B
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�䂪�k�C���́A���ɁA��X���{�l�̂��߂ɊJ���ꂽ���R�̍��y�ł���B�����ȗ��l�̑��Ղ��ʔ��_�����̎R�A��Õ��������T�̑�X�сA�L���Ƃ��ă��V�A�̓c�����Â��ނ�匴��A�����Q���Ĕ����A�������̊C�A�������̑嗤�I�Ȗ��J�̓V�n�́A�����ɗY�S�u�X����V�������R���������ł��낤�B�ނ�͊F���̏Z�݊��ꂽ�c�敭��̒n���̂ĂāA�E�܂������Ìy�̊C�̑�������肫�����B
�@�k�c�l���M�̐l�̕����͕̂����̂łȂ��A�ˊт���̂ł���B���{�̕����͓ˊтŏ��A�������R���̓ˊт͍Ō�̈�@�ɂ������B������ӂ܂œˊт��鏬�M�l�قNj���ׂ����̂͂Ȃ��B
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�k�C���l�A���ɏ��M�l�̓��F�͉��ł��邩�Ɩ��ꂽ�Ȃ�A�\���S�O���Ȃ�������B�H���A�����S�̂Ȃ��������ƁB�����S���Ȃ����炵�ēs�{�Ƃ��Ă̌����I�Ȏ��Ƃ����B���Ȃ��ƃP�i�X�l�����邪�A�\�́A���̈ꎖ�Ȃ炸�����ɑ��̈ꎖ�A���̒n�ɂĂȂ��\�킸�����ɂ��̒n�ɍs���Ƃ����悤�ȁA������V�����ƂƂ��Đ����ɐR�����M����k�C�l�̋C����A�o��������Ď]������҂ł���B���R�Ɗ����ƁA���̓��������A�ׂɎh�g��č�𒍕����Ȃ��Ƃ��т͐H����̂��B
�@�\�͂����܂ł����̂��Ƃ��Y���҂ł���B�V���̗��Q�l�ł���B�k�c�l�\�͂����������R�Ɗ����̏��M�ɗ��āA�ڂɋ���Ȋ����̊C�̐F�����A���ɑs���Ȃ銈���̐i�s���i�}�[�`�j���āA�S�̂܂܂ɕM�����Ζ����Ȃ̂ł���B�v
�ΐ����u���߂Č����鏬�M�v�i�w���M����x�n�������o�j,in�F�w�ΐ��ؑS�W�x,��W���w��،����x,1978,�}�����[,pp.359-361.
�@������A�k�C���ɑ��Ă�������ۂ́A���J���g���R�h�ȓV�n�A�����ɐ������g���R�h�Ŋ����I�Ȑl�тƁA�\�\�\�Ƃ������Ƃ������悤�ł��B
�@�k�C���Ƃ����u�A���n�v�ɏZ�o���ɂ���đ傫���H�������Ƃ����_�ŁA�������͂�A�g�鍑��`�I�g���h�Ɏx����ꂽ�g�������w�h�������A�Ƃ����K��͂ł��邩������܂���B�������A��Ō�����������t���l�������F�œ����g�A���n�x�z�ҁh�Ƃ��Ắu���R�v�ƁA������k�C�����Ɍ����g���R�̋C���h�Ƃ́A�傫���قȂ��Ă��܂��B
�@�����́u���R�v���g�x�z���鎩�R�h�������Ƃ���A����́u���R�v�́A���K����̎��R�A�x�z�́g���т��h����̎��R�������ƌ�����ł��傤�B��ӏ��ɍS������Đ��_���Œ肷��̂��D�܂Ȃ��Ȃ�A���ł����������āA�V���Ȓn�����߂Ă䂭���R�A���̈Ӗ��ł́u�����S�̂Ȃ����Ɓv���u�k�C���l�̓��F�v���ƁA����͌����̂ł��B
�u�V�����ƂƂ��Đ����ɐR�����M����k�C�l�̋C鮁v
�@�Ƃ́A�܂��ɂ�����w���܂��B
�@
�u�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�Ⴋ�Y���i���Ԃ���j�ŗg����
�@�����O�ڂƒ�����
�@�k��C�i���ق��݁j�݂̊̏�
�@�����n���̏���
�@�^�f���r�i�܂��͂�����j�̐_�̎q��
�@�n���i�����T��j���݂ċ��Џo�i�Łj��
�@���i���́j�L�l�����邪�@�i���Ɓj
�@�����Y�X�����C���Ђ���
�@�퓬�i���T���Ёj�̎q�����ꂽ��
�@�����v�z�ƈ�����
�@�S���ꂵ���M��
�@���U�ƋU�P�ƈ�����
�@�����ꂵ�����肽��
�@�����i���̂�j�ɂ���Đl�͊F
�@���i���́j�{���i�ق₤�j���i�Ȃ����j����
�@���邱�ƒm����ÛY��
�@�z���i�����ׁj�ƂȂ�鍡���̎�
�@���͂����@�����ԗ��X��
�@�V���i����͂��j�����͂���
�@���т̐��͗��i�炢�j�̔@�i���Ɓj
�@���o�ł�����i�܂�j����
�@���Ȃ��牓���唙�i�������j��
�@���q�̖��i�����j��Ɏ����肯��
�@�E���i�߂Łj���Ȃ��͉��̌�
�@�����i���Łj�Ɏ���͉��̕M
�@�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�����������ɐ��ꂽ��
�@�퓬�i���T���Ёj�̎��i���j���͂���
�@�B�����ƂȂ�����Ȃ�
�@����̂܂܂Ȃ�S����
�@�䂪�����ƐM�O��
�@�|�Ђ����݂̂Ԃ�
�@�����i�́U����j�ʐ�������
�@�͂̌��苩�ׂ���
�@�����v�z�͕��ւ�
�@�@�ז��M�͂��U�P
�@���̈�����������
�@���i�������j�̘I�Ə���������
�@���߂�䢂ɗ�����
�@�V�������i��j�͑�����
�@�@�@�@�@�@�k�c�l�@
�@���f�Ƃ��ĊU���Ȃ�
�@���Â̟��i�Ȃ݁j�̋N���i�����ӂ��j��
�@�����i�������Ɓj�߂����i���́j���
�@�i�߂Ƃ���鞺���
�@�C������������v
�ΐ��u����v�i�w���M����x�n�������o�j,in�F�w�ΐ��ؑS�W�x,��W��,1978,�}�����[,pp.362-363.
�@�k�m�̊C������S���́u�_�̎q�v���a�����āA�݂ɏオ���ė���Ƃ����C���[�W�́A�u���R�v�u����̂܂܁v�u�B�����ƂȂ�����v���Ƃ��Ȃ��f�p���Ԑ��_��\���Ă��܂��B�����Ă��́u�_�̎q�v�́A�g���R�h�����߂āu�����v�z�ƈ����v�u���M�v�u���U�ƋU�P�ƈ����v�ɑ��Đ키�̂ł��B
�@���\�[���́u���R�v��`�ƁA�����ւ̒�R�Ƃ����Ӗ��ł́g���R�h�Ƃ��A�_�X�������̂̃C���[�W�ɂ���āA�݂��ƂɌ������Ă��邱�Ƃɒ��ڂ������Ǝv���܂��B
�@�O���A�a�����w�Z�ł�����̋�����j�ɂ��āA
�u�l�ꂽ���̘Ԃő傫���Ȃ点����j�v
�u�傫����������鎖�I ���ꂪ�����̓V�E���I�v
�u�������E����l�̋����r���v�A�q�����u�ł��邾�����l�������Ȃ��悤�Ɂv
�@�S���������Ƃ����܂����B
�@�g���ꂽ�܂܂̗��́h�����́A�܂����g���R�h���̂��̖̂��C�ȍ��̃C���[�W�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@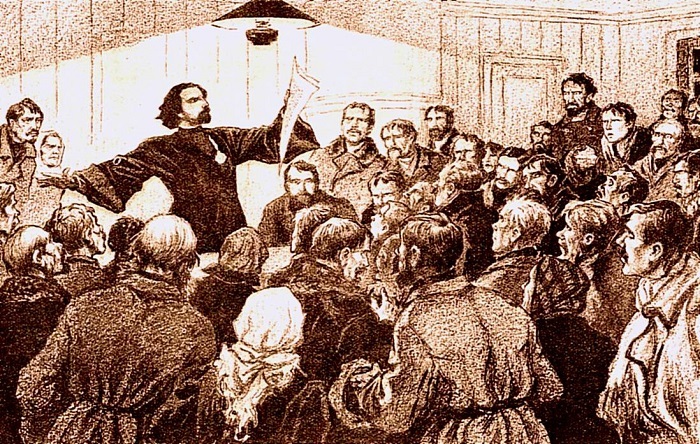


 �@
�@

 �c
�c