10/14の日記
09:26
【必読書150】ドストエフスキー『悪霊』(4)―――“ことば”にならない思想はあるのか?
---------------
.

シャートフ
1988年フランス映画『悪霊』 アンジェイ・ワイダ監督
こんばんは。(º.-)☆ノ
【必読書150】ドストエフスキー『悪霊』(1)
【必読書150】ドストエフスキー『悪霊』(2)
【必読書150】ドストエフスキー『悪霊』(3)
からの続きです。
【12】シャートフ―――「思想の下男根性」「紙でできた人間」
「『ロシアの無神論は駄洒落の域を出たことがないんです。』消えかかった蝋燭を新しいのに代えながら、シャートフがつぶやいた。
〔…〕
『紙でできた人間なんです。何もかも、思想の下男根性のせいですよ』隅のほうの椅子に腰をおろし、両手を膝についた格好で、シャートフは平静に言った。
『憎悪もあるんだな』しばらく黙っていてから、彼はまた口を切った。『もしロシアが何かこうふいに改革されて、〔…〕何かこうふいに途方もなく豊かで幸福な国になったとしたら、真っ先におそろしく不幸になるのはあの連中でしょうね。そうなったら、あの連中、憎悪の対象も、唾を吐き替かける相手も、嘲弄する相手もなくなるんだから! あの連中にあるのは、ロシアに対する動物的な、際限のない憎悪、体質にまでなってしまった憎悪ですよ! 目に見える笑いのかげにひそむ、世人には見えない涙なんてものはありゃしない! あの目に見えぬ涙うんぬんくらいそらぞらしい言葉は、かつてロシアで言われたためしがないな』彼は狂暴と思える声で絶叫した。
〔…〕
『〔…〕わがロシアのリベラリストというのは、何よりもまず下男で、だれか靴を磨いてやる相手はいないかと、きょろきょろしているだけが能なんですよ』」
江川卓・訳『悪霊』,上,pp.261-262.
↑シャートフは、「私」のまえで怒りをぶちまけた。
語り手「私」が、シャートフのアパートを訪ねると、2人の先客がいた。アパートの下の離れに住んでいるキリーロフと、ピョートルの《秘密結社》(テロリスト・グループ)のメンバーシガリョフである。3人は激しく口論していたが、「私」が来たのを潮目に、キリーロフとシガリョフは、挨拶もせずに興奮の態で帰って行った:
「もう階段のあたりから、3人がえらい大声で、しかも一時に口を開き、どうやら言い争っているらしいのが聞えたが、私が顔を出したとたん、みなはぴたりと口をつぐんだ。〔…〕2人〔キリーロフとシガリョフ――ギトン注〕は挨拶もせずに出ていったが、〔ギトン注――2人のうち〕シガリョフのほうは、戸口まで来たとき、見送りに出たシャートフに言った。
『覚えておきたまえ、きみは報告の義務があるんだから』
『そんな報告なんぞぺっぺだ、ぼくはどこのどいつにも義務なんか負っていないぞ』シャートフは彼を送り出すと、ドアに鍵をかった。
『阿呆めらが!』ちらりと私のほうを見て、妙にゆがんだような薄笑いを浮べながら、彼は言った。
彼は怒ったような顔をしていた。〔…〕」
江川卓・訳『悪霊』,上,pp.259-260.
前節で引用したステパン先生との議論では、シャートフは、
「『〔あなたがたは、〕ロシアも、民衆も、愛してなんかいるものですか!』」
と言っていました。しかし、ここではさらに進んで、彼らにとってロシアの民衆は
「憎悪の対象」「唾を吐きかける相手」「嘲弄する相手」
なのだと言います。
「『あの連中にあるのは、ロシアに対する動物的な、際限のない憎悪、体質にまでなってしまった憎悪ですよ!』」
つまり、シャートフの考えでは、“自由主義者”を自認する人びとは、ロシアの民衆(農奴)を「愛している」と言いながら冷笑し、“革命的な”フランスの民衆と引き比べて軽蔑し、「唾を吐きかけ」ている。その本心は、「愛」でも「涙」でもなく「憎悪」なのだ―――と言うのです。
「思想の下男根性」とは、そうした「憎悪」が裏返しになった態度にほかなりません。20世紀の言葉に翻訳するなら、“指導者根性”と言ってもよいでしょう。さまざまな人が、さまざまな“思想”をふりかざして、自分が“人民”の“指導者”になりたがる。レーニン、毛沢東、ジョン・ケネディ、‥みなそうでした。ドストエフスキーの 19世紀には、まだそういう現象は無かったから、「下男根性」と言っているのです。しかし、“思想”も“指導者”も失墜しつくした・この 21世紀には、もはや、内容空虚な純然たる“下男根性”のほかには、何も残っていないのかもしれません。。。
【13】両面役者ピョートル
“民衆”への「愛」と称して、じつは「憎悪」。このシャートフの告発は、はたして当たっているのか?
彼が無意識のうちに見破っていたように、《秘密結社》の“仕掛け人”であるピョートルがシャートフに向けていた感情は、まさに「憎悪」でした。それをピョートルは「愛」であるかのように言いつくろう場面↓を、ドストエフスキーは描いています。
それは、“民衆”への「愛」を語りつつ“革命”という「靴磨き」奉仕を提供する《組織》の活動―――ドストエフスキーとシャートフによれば、実は“民衆”への「憎悪」の発現―――を象徴します。
ピョートルは、県知事に面会して、シャートフが危険な《秘密結社》の首謀者で、工場労働者(農奴)を扇動して“社会転覆”に向わせようとしていると仄めかして、密告します。表向きは、「親友」であるシャートフを「救ってほしいとお願いに来た」と言いながら‥‥
その実、ピョートルは、すべての責任をシャートフ一人になすりつけるための事前準備として、当局に予断を持たせようとしているのです。
ピョートルは、ストライキ中の工場から押収されて県知事室にあった「檄文」ビラを手にとって、県知事に、まくしたてます。しかし、彼の話がふにおちない県知事は:
「『シャートフ? というと何がシャートフなんだね?』
『シャートフというのは、ここに書いてある《一学生》のことなんですよ。この町に住んでいましてね、農奴の出身で、ほら、このまえ頬打ちをくらわした男ですよ』〔とピョートルが言う――ギトン注〕
『わかった、わかった!』レンプケ〔県知事――ギトン注〕は目を細めた。『しかし、失礼だが、彼はいったいどういうことで罪に問われているのかね、それより、きみは何を請願しようというのかね?』
『あの男〔シャートフ――ギトン注〕を救ってくださいとお願いしているんですよ! ぼくはもう 8年前からあの男を知っていましてね、親友といってもいいくらいだったんです』ピョートルは躍起になった。〔…〕『なに、こんなことはみんなつまらないことでしてね、3人半ぐらいでやっている仕事です、外国の連中を合わせたって 10人にもなりゃしない。それよりぼくはあなたの人道主義に、あなたの聡明な頭脳に希望をかけているんです。あなたならわかってくださって、〔…〕気違いじみた男〔シャートフのこと――ギトン注〕の愚かな夢として見てくださる……そう、不幸な境遇のために、長年の不幸のためにあの男はおかしくなったんですよ、まかりまちがっても、途方もない国家的陰謀などとお考えになるわけはない……』
彼〔ピョートル――ギトン注〕はほとんど息を切らさんばかりだった。」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.25-26.

県知事レンプケとピョートル
1988年フランス映画『悪霊』 アンジェイ・ワイダ監督
「『しかし、その男が一人きりだとすると、〔ギトン注―――不穏な扇動ビラを〕どうしてここで撒いたり、地方で撒いたり、H県にまで撒けたのかね、それより、どこから手に入れたのかね?』
『さっきから言ってるじゃありませんか、彼らはせいぜい 5人だって、まあ、10人くらいかな、ぼくが知るわけがないでしょう?』
『きみは知らない?』
『どうして知ってるもんですか? ばかばかしい』
『しかしきみは、シャートフが共謀者の一人だということを、現に知っておったじゃないか?』
『えい!』ピョートルは、尋問者の圧倒的な洞察力を払いのけようとでもするかのように手を振った。『〔…〕……しかしぼくは、シャートフのことをお願いに来たんです。なにしろこの詩も彼の自作だし、彼の手を通じて外国で印刷されているんだから、彼を救ってやらなきゃならないんです。これだけはぼくも確実に知っていますが、檄文のことはほんとに何も知りませんね』
『もしこの詩が彼のものなら、おそらく檄文もそうだろうね。しかし、きみはいったい何を根拠にシャートフ氏を疑うんだね?』」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.26-27.
じっさいには、シャートフは、この「檄文」ビラにも、そのほかの扇動活動にも、何の関りもありません。この「檄文」についても、それを印刷して大量のビラにし、どこかに隠しておくようにとのピョートルの指示に対して、シャートフは、にべもなく断わったのです(下,p.75)。
そこで、ピョートルは、みずから外国で印刷してロシアに持ちこみ、ならず者を雇って撒いているのです。
アメリカから帰還して以来、シャートフは、《組織》からの離脱を申し出ているのですが、ピョートルらは、言を左右にして引き延ばしており、いまだ正式には認められていません。
ピョートルは、最終的に、県知事レンプケに対して、“5日間の猶予”を約束させます。すぐに検挙に出ることは差し控えて、5日間だけ見守ってほしいと。そして、その 5日の間にシャートフを殺害し、彼に一切の責任を負わせてしまおうと企むのです。
ドストエフスキーがピョートルのモデルにしたのは、セルゲイ・ネチャーエフ(1847-1882)というニヒリストの活動家でした。
ネチャーエフは、サンクト・ペテルブルクで、急進的な学生運動に参加していましたが、正式の学生だったわけではありません。当時、スイスに亡命していたバクーニンのもとを訪れ、たくみに取り入ります。
ネチャーエフは、この時 22歳。同性愛の傾向があったバクーニンに、「ボーイ」と呼ばれて可愛がられたといいますから、2人のあいだには、同性愛の関係があったかもしれません。たしかに、ネチャーエフの非情な性格――バクーニンには、それが、たまらなく良かったらしい――は、アルチュール・ランボー、ジャン・ジュネといった、同性愛の美少年を思わせます。彼の詐欺師的な部分も、ある種の同性愛者にはありがちなことです。
ネチャーエフは、バクーニンらに資金を提供させ、多数の扇動ビラやパンフレットを作成し、それらを持って、1869年、ロシアに潜り込みます。
モスクワで、『人民の裁き』という秘密結社を組織して、翌1870年に革命を起こすという自身のプログラムを実行に移しますが、その過程で、メンバーの一学生を“裏切り密告者”と疑い、ピストルで殺害してしまいます。
この《ネチャーエフ事件》によって、約300名が逮捕され、うち87名が起訴されますが、ネチャーエフ自身は、ふたたび国外に逃亡してしまいます。
西ヨーロッパに戻ったネチャーエフは、当時、たがいに仲の悪かったバクーニンとマルクスのあいだを取りもって、『資本論』のロシア語訳の出版を計画したりする。この計画は、バクーニンが『資本論』を気にいらなかったために頓挫するのですが、ネチャーエフは、双方から預かったカネを着服して、ロンドンへトンズラしてしまいます。
1872年には、亡命先のスイスで逮捕され、《ネチャーエフ事件》で懲役 20年の刑を受け、下獄します。ところが、こんどは看守をたぶらかして、獄中からニヒリスト・グループ『人民の意志』を指導し、1881年のアレクサンドル2世暗殺を成功させてしまいます。
長年のこころざし稔って、本人は得意の絶頂。しかし、この事件のためにツァーリ政府の弾圧は厳しくなり、ロシアの自由主義運動、革命運動は“冬の時代”を迎えるのです。
そのせいで、ネチャーエフ自身の脱獄計画も、実行できなくなり、彼は翌1882年に獄死しています。
⇒:ネチャーエフ(Wiki)

「ネチャーエフは自称モスクワ大学の学生〔事実は独学で、小学校教師のかたわらサンクトペテルブルク大学を聴講していた―――ギトン注〕。ロシアで革命運動をしていたが、警察に追われてスイスに逃げてきた男であった。むろん、これも本当か嘘かわからない。〔…〕この法螺吹きにバクーニンは虜になってしまう。〔…〕そんな彼らは共同で7冊ものパンフレットを発行した。同じ監獄に入っていた仲間〔これはバクーニンに取り入るためのウソ。ネチャーエフは、この時までに監獄にいたことはなかったらしい――ギトン注〕、同郷出身ということで、バクーニンも気が緩んだのかもしれないし、何よりも、ネチャーエフの革命への並々ならぬ熱意がたまらなかった。ネチャーエフは革命のためなら、人を殺してしまったって構わない、そんな意気込みであった。
〔ギトン注―――バクーニンが、革命によって実現されるべき幸福とする〕『愛と友情』なんてもってのほか。冷徹・冷酷に、ひたすら革命を生ぜしめる、それが目的だと言わんばかりだ。」
その後、ネチャーエフは、「〔…〕マルクスの『資本論』の翻訳をバクーニンに仕向け、出版社をこしらえて、仲介業者となって、金儲けを企んだのだ。翻訳の前金を〔マルクス側から――ギトン注〕受け取ったのであるが、この前金で、バクーニンは借金をいくらか返済するのみ。バクーニンは実のところ重苦しい『資本論』を翻訳するのが面倒だったようだ。
この間、仲介役だったネチャーエフは、バクーニンを苦しめるような仕事はさせるな、復讐するぞ、という脅しの手紙をマルクス側に送った。」そのせいで、マルクスとバクーニンの仲は、いっそう悪くなった。
ネチャーエフはといえば、「バクーニンからもお金をふんだくって、バクーニンのこれまで書いた文章などを持って、そのままロンドンへ逃亡した。」
森元斎『アナキズム入門』,2017,ちくま新書,pp.104-106.
【14】ロシアの“夜と霧”
ピョートルは、シャートフに、《組織》から離脱するためには、メンバーの承認が必要だと言って、気のすすまない彼を、「同志の集まり」に出席させる。
「『もちろん、きみをそんなところへ引っぱっていくつもりはぼくにはなかった……というのは、きみにいやな思いをさせたくないからで、きみが密告するだろうなんて考えているからじゃけっしてありませんよ。ところが事情があって、どうしてもきみに来てもらわなくちゃならなくなったんです。きみにはそこでしかるべき連中と会ってもらって、きみの脱会をどうするか、きみに預けてあるもの〔印刷機―――ギトン注〕を誰に渡すか、最終的に決めようじゃないですか。〔…〕実を言うと、きみのおかげでだいぶ弁明これつとめなきゃならなくてね。』」
江川卓・訳『悪霊』,下,p.75.
ところが、会合では、出席者たちを巧みにマインド・コントロールして、シャートフが当局に密告しているとの疑いを抱かせるのです。
「『〔…〕それともきみは密告を恐れているんですか? いったいいまぼくらの間に密告者がまぎれこんでいる恐れがあるとでも言うんですか?』〔と、ピョートルが一同に言う――ギトン注〕
ひとかたならぬ動揺がもちあがった。みながしゃべりはじめた。
『諸君、もしそういうことなら』とヴェルホーヴェンスキー〔ピョートル――ギトン注〕はつづけた。『〔…〕ひとつぼくから、ある質問に答えていただくよう提案したいと思います。むろん、諸君に答える気があればですが。つまり、何事も諸君の完全な自由意思です』
『どんな質問だ、どんな質問だ?』みんながいっせいにがなり立てた。」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.134-135.
「『もしわれわれのうちだれにせよ、政治的な暗殺計画を知った場合、その人は、あらゆる結果を見越したうえで、なお密告に行くか、それとも家に引きこもって、事件の起るのを待つか。という質問です〔…〕まずあなたから答えていただきます』彼はびっこのほうに向き直った。
『どうして私が真っ先なのです?』
〔…〕
『イエスですか、ノーですか? 密告しますか、密告しませんか?』ヴェルホーヴェンスキー〔ピョートル――ギトン注〕が叫んだ。
『むろん、密告なんかしやしない!』びっこはその倍も大きな声でどなり返した。
『だれが密告なんぞするものか、むろん密告なんぞしないさ』声々がひびいた。
『では、少佐殿、あなたにうかがいます、密告なさいますか、密告なさいませんか?』ヴェルホーヴェンスキーはつづけた。『ご注意しておきますが、ぼくはとくにあなたにうかがっているのですから』
『密告なぞしませんよ』
〔…〕
『そうとも、手先だった者などここにはだれもいない』ふたたび声々がひびいた。『無用な質問だぞ。みんな答えはきまっている。ここに密告者なんぞいない!』
『なんだってあの人は席を立つの?』女子学生が叫んだ。
『シャートフだわ。シャートフさん、どうして席を立つんです?』主婦が叫んだ。
たしかにシャートフは立ちあがっていた。彼は自分の帽子を手にして、ヴェルホーヴェンスキーを見つめていた。彼に向って何か言いたいことがあるが、ためらっているふうだった。彼の顔は青白く、憎々しげだったが、それでも自制して、一言も発するでなく、無言で部屋を出ていこうとした。
『シャートフ君、そんなことをするときみにとって不利になりますよ!』ヴェルホーヴェンスキーがそのうしろ姿に謎めいた叫びを浴びせた。
『そのかわり、スパイで卑劣漢のきみには有利になるだろうさ!』シャートフは戸口からこうどなり返し、外へ出てしまった。
ふたたび叫びや嘆声がひびいた。
『なるほど、テスト成功か!』だれかが一声叫んだ。
『有効だったわけだ!』別の声が叫んだ。」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.135-137.
しかし、ピョートルが狙った効果は、完璧ではなかった。シャートフのあからさまな行動が、かえって、「密告者なら、猫をかぶっているはずじゃないか」との疑念を生み、彼の嫌疑を曖昧にしたからである。出席者たちは動揺し、「密告者」の疑いは、ピョートルとスタヴローギンに対しても、向けられた。
そこで、ピョートルは、より少人数の“五人組”を集めて、内密の会合を開くことにした。その席で、シャートフによる「密告」の策動を食い止めるため、と称して、そそのかし、口封じの殺害を謀議したのである。
しかし、この2つの会合のあいだに、町では大きな事件が持ち上がっていた。町と河を隔てた近郊の村が放火されて炎上した。しかも、大火事のどさくさのなかで、村はずれの借家に隠れ住んでいたレピャートキン大尉と妹マリアが殺害され、ナイフでメッタ刺しにされた死体で発見された。
マリアは、当県随一の大地主家の御曹司であるスタヴローギンが、学生時代に、冗談半分のように婚礼をあげた“隠し妻”であることが、最近暴露されたばかりだった。(⇒:【4】おもな登場人物参照)
それで、町では、スタヴローギンが、自分の結婚の障害になる邪魔者を消すために、兄妹を殺したのではないかと噂していた。しかし、証拠は無かった。
放火については、折りからストライキ中だった・近隣の工場の労働者が、だれかに扇動されて凶行したとの憶測も、有力だった。
じっさいには、村の放火も、兄妹の殺害も、ピョートルが、スタヴローギンの意を忖度して、脱獄囚フェージカに実行させたものだった。が、そのことはまだ発覚していなかった。

『悪霊』 仏訳本の表紙
さて、“会合”に1時間半遅れてやってきたピョートルは、開口一番、
「『ぼくが口を開く前に、まずきみたちの考えを聞こうじゃないか。何か固くなっているようだが』毒々しい冷笑を浮べて一同の顔をじろりと見まわしながら、彼はうながした。
《一同の代表》という形で、リプーチンが憤懣に声をふるわせながら〔…〕言明した。〔…〕
いまのようなやり方は屈辱的であり、危険である……〔…〕一人の人間だけが行動して、他の者がたんなる将棋の駒でしかないとしたら、その一人がしくじった場合、全員が巻き添えをくうことになりかねない。(そうだ、そうだ、の叫び。一同の支持)」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.387-388.
村の放火と兄妹殺害事件に、ピョートルとスタヴローギンがかかわっているのではないかと、仲間たちも疑っていたのだ。しかも、放火の下手人と目されている工場労働者らを、ピョートルの“組織”が扇動していることは、彼らの間では、公然たる秘密であった。
「『なんとばかげたことを! あの殺人事件はまったくの偶然事だよ、フェージカが物盗りのためにやったんだ』」
江川卓・訳『悪霊』,下,p.389.
ピョートルは思わず、犯行の一部をばらしてしまったのだが、スタヴローギンの“隠し妻殺害”に集中している仲間たちは、気づかない。口論のすえ優勢になってくると、ピョートルは、相手のほうに鉾先を向けかえる:
「『ところで、諸君、今度はぼくのほうからたずねる番のようだが』ピョートルが高飛車に出た。『いったいどういう理由で諸君は許可もなく町に放火したのかね? 聞かせてもらおうじゃないか』
『なんですって? われわれが放火したって? そりゃ、とんだ濡衣だ!』声々がひびいた。
『きみらがつい調子に乗りすぎた気持はわかる』ピョートルは強引につづけた。『しかしだね、〔…〕ぼくがきょう諸君に集まってもらったのはだね、きみたちが愚かにもみずから招いた危険の程度を説明するためなんだ。』
〔…〕
『すると、きみは否定するのかね? しかしぼくは断言するね、町を焼いたのは諸君であって、ほかのだれでもないと。諸君、出まかせはやめたまえ、ぼくは正確な情報を握っているんだ。〔…〕諸君のうち3人までが、なんらの指令を受けることもなく、シュピグーリン工場の連中に放火をそそのかした、その結果が火事となって現われたんだ』」
江川卓・訳『悪霊』,下,p.389.
ピョートルは、かまをかけて言っただけかもしれませんが、ストライキ工場の労働者と話したことのある者は、酒の勢いで、どこどこに火をつけてやれ、というような話になったような気がしてくるのです。そこで、ピョートルは、すかさず、
「『ご心配なく、諸君の行動ならぼくはすっかり承知しているのでね』」
江川卓・訳『悪霊』,下,p.393.
真っ青になったメンバーたちに、ピョートルは、密告をしようとする者がいると告げて、震えあがらせます:
「『ぼくがここにいるかぎり、諸君はぼくの許可なしに行動してはならなかったのだ。けっこうな話さ。密告はもう目前だ、あすにも、いや、今晩にも、諸君は全員検挙されることになる。いいかね。これは確実なニュースだ』
〔…〕
『放火の使嗾者としてだけではなく、五人組として検挙されることになる。密告者は組織の全秘密に通じている。諸君はこういう結果を招来してくれたんだ』
〔…〕
『それはシャートフだよ!〔…〕驚くべきことに、彼には組織の秘密、構成……要するに、すべてが筒抜けになっていることが判明したのだ。以前、事業に加担していた罪を免れるために、彼はわれわれ全員を密告しようとしている。これまでのところはまだ躊躇していたので、ぼくは彼を黙認していた。ところが今度の火事で、諸君が彼にふんぎりをつけさせたわけだ。彼は大きなショックを受けて、もうなんの躊躇もしていない。あすにもぼくらは放火犯人、政治犯として逮捕される』
江川卓・訳『悪霊』,下,p.395.

「五人組」の一人リャムシン(左)
をそそのかすピョートル(右奥)
1988年フランス映画『悪霊』 アンジェイ・ワイダ監督
「一同は黙っていた。
『いよいよあいつを片づけないといかんな!』トルカチェンコが最初に叫んだ。
『とっくにしておかなくちゃいけなかったんだ!』拳固でテーブルを叩いて、リャムシンが憎々しげに口を入れた。
『しかし、どういうふうにやるね?』リプーチンがつぶやいた。
ピョートルが即座にその問いを受けて、自分の計画を開陳した。シャートフの保管している秘密の印刷機を引き渡せという口実で、それが埋めてある人気のない場所に、あすの夜、あまり遅くならないうちに、彼をおびき出し、『そこで片づけてしまう』というのである」
江川卓・訳『悪霊』,下,p.395.
しかも、「『完全に嫌疑を免れる方法がある』」と言う。自刹志願のキリーロフに、自分がシャートフを殺したとの遺書を書かせて、自決させるというのだ。
「シャートフが密告するだろうということは、同志たち全員がもう信じきっていた。しかしピョートルが自分たちを将棋の駒のようにあやつっているということも、やはり信じきっていた。それから、結局あすは全員が指定の場所に勢ぞろいし、シャートフの運命が決せられるのだということも承知していた。自分たちが大きな蜘蛛の巣にかかった蝿のように思われて、腹立たしくはあったが、恐怖に体がふるえた。」
江川卓・訳『悪霊』,下,p.401.
【15】《受胎告知》と《藁の養子》
「五人組」がシャートフの殺害を謀議していたのと同じ時刻ころ、当のシャートフは、まったく思いがけない別のできごとに見舞われていました。
「彼はいつかとろとろと浅い眠りに落ちてふっとわれを忘れ、何やら悪夢のようなものにおそわれた。それは、自分が寝台にロープでぐるぐる巻きにされている夢であった。〔…〕どこやら遠くのほうから、耳に覚えのある、けれど胸のうずくような声が、哀れっぽく彼の名を呼んでいるのである。彼はふいに目をさまして、寝床の上に起きあがった。驚いたことに、門を叩く音はなおもつづいていて、夢で聞いたほどはげしくはなかったが、それでも執拗に、間を置かず叩きつづけている。〔…〕彼はとび起きて、窓の通風口をあけ、頭を突き出した。
『誰だ?』驚きのあまり、文字どおり体をこちこちにして、彼は声をかけた。
『あなたがシャートフなら』きっぱりと鋭い声が下から答えた。〔シャートフの部屋は2階―――ギトン注〕『どうぞ正直にはっきりとおっしゃってくださいな。わたしを中へ入れてくださるかどうか?』
やはりそうだった。彼にはその声がわかった!
『マリイ!……きみなのかい?』
『わたしよ、わたしよ、マリヤ・シャートワなの。でも、ほんとに、これ以上もう1分も馬車を待たせておくわけにいかないから』〔シャートフが入れてくれなければ、ほかへ行かなければならないから、乗って来た馬車を待たせている―――ギトン注〕
『いますぐ……ただ蝋燭を……』シャートフは弱々しげな声で叫んだ。それから、マッチを捜しにとんでいったが、こういう場合いつもそうであるように、マッチはなかなか見つからなかった。蝋燭を燭台ごと床に落としたりしているうち、もう一度下からもどかしげな声が聞えてくると、彼は何もかもほうり出して、くぐり戸をあけるために急な階段を一目散に下へ駆け降りていった。」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.430-431.
(2)【5】で引用した《第一部》に戻るのですが、シャートフは、ロシアの大学を放校になったあと、「開化主義者の・ある商人」にかかえられて家庭教師になり、子どもたちの「お守り」をしながらヨーロッパへ出かけて行ったのでした。
「子供たちにはもう一人、女の家庭教師がついていた。〔…〕向こう見ずなロシア娘だったが、彼女は2ヵ月ばかりで、《自由思想の持主》ということで商人から追い出されてしまった。シャートフも女のあとを追い、ほどなくジュネーヴで彼女と結婚した。3週間ほどの同棲生活ののち、二人は、何者にも束縛されぬ自由な人間同士として離婚した。もちろん、貧乏生活も原因していた。その後の彼は長いこと単身ヨーロッパを放浪して歩いた。」
江川卓・訳『悪霊』,上,新潮文庫,p.51.
この・3週間で離婚した・シャートフのただひとりの配偶者が、マリヤなのです。その・まるで昆虫の空中交尾のようなあっという間の“結婚生活”から、まる3年間というもの、二人のあいだには、ただ一度の連絡もなかった。もっとも、シャートフはアメリカにいた間に一度、彼女のパリの逗留先宛てに手紙を出したのだが、彼女は移転していたために届かなかった。
そのマリヤの突然の来訪に、お人好しで女にモテない男の態度そのまま、あわてて迎え入れたシャートフでしたが、部屋の中は真っ暗です。
「彼は床から燭台を取りあげたが、マッチはなお長いこと見つからなかった。シャートワ夫人は無言のまま、身動きもせず、部屋の中ほどに立って待っていた。
『ありがたい、やっと見つかった!』彼は喜ばしそうに叫んで、部屋を明るくした。シャートワ夫人はざっと部屋の様子を見まわした。
『ひどい暮しをしているとは聞いていたけど、これほどとは思わなかったわ!』彼女はいとわしそうにこう言うと、寝台のほうを向いた。
『ああ、疲れちゃった!』彼女は力の抜けたような顔で、固い寝台の上に腰をおろした。『どうぞ鞄はどこかへ置いて、あなたも椅子にすわってくださいな。まあ、お好きなようでいいけど、なんだか目ざわりなのよ。わたし、仕事が見つかるまでの当座と思って、あなたのところへ来たの。この町のことは何も知らないし、お金もないから。〔…〕
でも、わたしが昔のばかげた関係を復活させるために帰ってきたなんて考えないでよ。わたしは仕事を捜しに帰ってきたので、まっすぐこの町へ来たのも、どこだって同じことだからなんです。わたしは何もあやまりに来たんじゃありませんから、どうか、そんなばかげたことは考えないでくださいよ』
『ああ、マリイ! 言われるまでも、言われるまでもないよ!』シャートフは曖昧な調子で言った。」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.433-434.
マリヤ・シャートワ(マリイ)は、「帰ってきた」と言いますが、彼女はこの町の出身ではないし、ここには生れて初めて来たのですから、シャートフをたよって‥‥あわよくば頼れるのではないかと期待して、来たことは、明らかな状況なのです。
マリイは、「年の頃 25,6歳、かなりがっしりとした体格で、背も〔…〕シャートフより高かった」が、
「この疲れきった顔からは、青春の輝きはとうに消え失せていた。〔…〕あの軽はずみで、無邪気で、あけすけな以前のエネルギーは、いつかもう気むずかしげな怒りっぽさと、幻滅と、シニズムとでもいった感じに取って代られていた。」
江川卓・訳『悪霊』,下,p.437.
マリイは、言い訳のようにシャートフに言う:
「『〔…〕いまわたしがいきなりあなたの住居へ、あなたを訪ねてやってきたのは、ほかにも理由がありますけど、一つには、いつもあなたを卑劣漢とは見ていなかったからなんです、ことによったら、ほかの……人非人たちよりずっとましな人とさえ!……』
彼女の目が輝きだした。彼女はそういう《人非人》たちから、ずいぶんいやな目にも遭ってきたものらしい。」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.434-435.
しかし、彼女の長広舌を聞いているシャートフのほうには、もっと劇的な変化が現れていました:
「シャートフは、〔…〕おずおずとながら、何か生れ変りでもしたように、これまでについぞない輝きを顔に浮べて、彼女の言葉に耳を傾けていた。髪の毛をいつもさかだてている、この気性のはげしい、人づきの悪い男が、ふいに柔和そのもののようになって、顔つきまで晴ればれとしてきた。彼の心の中で、何か思いもかけぬ異常な感覚がうごめいた。3年の別離、破れた結婚生活の3年も、彼の胸から何ひとつ葬り去ることはできなかったのだ。〔…〕
彼にとってはかり知れぬほどの恐ろしさと、同時にはかり知れぬほどの幸福感とが含まれているこの出来事に、彼はあまりにもはげしい衝撃を受け、むろんのこと、彼はもう正気に返ることもできなかった。〔…〕これは夢であった。しかし、彼女があの疲れ果てたような眼差しでじっと自分の顔を見つめたとき、突然彼は、この愛する女性が苦しみ悩んでいること、もしかしたら、だれかに辱(はずかし)めを受けているらしいことを察したのだった。彼は心臓がとまりそうになった。〔…〕
しかし、何よりの心配は、彼女が病気だったことで、このことははっきりそう見てとれた。彼女に対するはげしい恐怖感にもかかわらず、彼はふいに彼女のそばに近づいて、その両手をつかんだ。
『マリイ……ねえ……きみはひどく疲れてるようだけど、頼むから、怒らないでくれよ……たとえば、せめてお茶でも飲むことを承知してくれたらいいんだけど、どう? お茶を飲むと、とても元気がつくけど、どう? 承知してくれないかな!……』
『承知するもしないもないでしょう、もちろんいただくわ、あいかわらず赤ん坊なのねえ。いただけるんなら、ちょうだいよ。あなたのとこはひどく狭いのね。それに、なんて寒いんでしょう!』
『ああ、いま薪を、薪を……薪はあるんだよ!』シャートフはふいにせかせかしはじめた。」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.435-437.
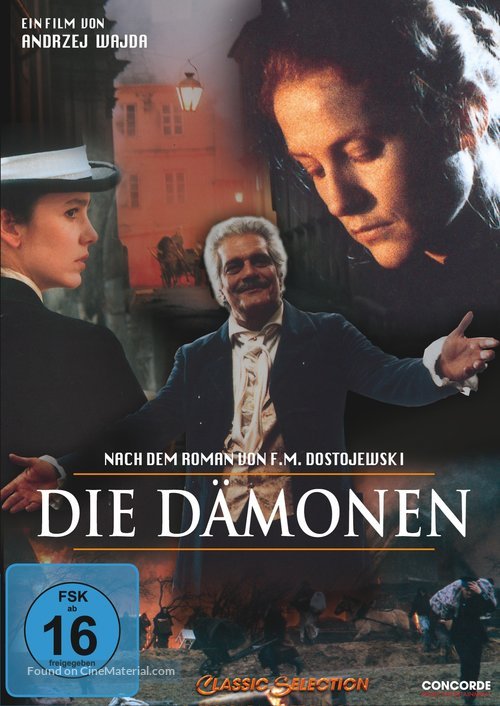
1988年フランス映画『悪霊』 アンジェイ・ワイダ監督
しかし、シャートフの部屋には、お茶もサモワールも無かったので、彼はあわてて出かけて行き、離れにいるキリーロフから、熱いお茶と食事を分けてもらって来る。マリイは、お茶をコップに半分飲んだだけで寝てしまった。
「ふいに妻の呻き声が聞えた。彼女が目をさまして、彼を呼んだのだ。彼は罪ある人のようにとび起きた。
『マリイ! ついうとうとしてしまって……ああ、ぼくはなんてひどい男だろう、マリイ!』
彼女は上体を起し、自分がどこにいるのかわからぬように、驚きの目であたりを見まわしていたが、ふいに腹立たしげに、怒りにかられたようにそわそわしだした。
『わたし、あなたのベッドを占領していたのね。疲れていたものだから、つい気がつかずに眠りこんでしまって。どうしてわたしを起してくれなかったの? わたしがあなたの厄介になるつもりでいるなんて、よくも考えられたわね』
『どうして起せるもんか、マリイ』
『起せたわよ、起さなきゃならなかったのよ!〔…〕わたしは床〔ゆか〕で寝たいわ、いますぐ、いますぐ!』
彼女は立ちあがって、一歩足を踏み出そうとしたが、とたんにはげしい痙攣性の痛みが彼女の力と決意を一時に奪い去ってしまったように見え、彼女は大きく呻いてふたたびベッドの上に崩折れた。シャートフが駆け寄ったが、マリイは顔を枕に埋め、彼の手を取ると、力のかぎりそれを握りしめ、もみしだきはじめた。それが1分ほどもつづいた。」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.452-453.
シャートフは、知り合いの医者を呼んで来ると言うが、マリイは、「くだらない!」と吐き捨てて断わる。その後、マリイは痙攣の発作を3回繰り返した。事態がまったく呑みこめないシャートフは、おろおろするばかりである。
「またしても例の痙攣の痛みにおそわれて、彼女はベッドに突っ伏した。これはもう3度目だったが、今度は呻き声が前よりも高く、ほとんど叫び声に近くなっていた。
『ああ、いやらしい人ねえ! ああ、たまらない人だわ!〔…〕
いったいあなたにはわからないの、何がはじまったのか?』
『何がはじまったんだい、マリイ?』
『わたしが知るもんですか? わたしなんかの知ったことじゃないわ……ああ、呪われた女なのよ! いまからもう何もかも呪われるがいいんだわ!』
「マリイ、何がはじまったのか言ってくれないか……でないとぼくは……これじゃ、わかりゃしないじゃないか』
〔…〕
『じゃ、あなたにはまだわからないのね、これはお産の陣痛じゃないの』彼女は上体を起し、恐ろしい病的な憎悪に顔じゅうをゆがめて、彼を見つめた。『生れる前から呪われるがいいわ、こんな赤ん坊!』」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.458-459.
ようやく事態を理解したシャートフは、「すさまじい勢いで自分の帽子を引っつか」むと、産婆を呼びに駆けだした。といっても、彼がこの町で頼りにできる知人は、キリーロフと、《秘密結社》の「五人組」のほかにはいないのだった。しかも、真夜中である。
彼はまずキリーロフに、ときどき妻のようすを見に行ってほしいと頼んでから、「五人組」の一人のヴィルギンスキーの家へ行って叩き起こす。ヴィルギンスキーの妻は、産婆をしているのだった。そのあと、リャムシンを訪ねて、ピストルを買うように求め、出産の資金を確保しようとした。

キリーロフ以外はみな、すでにピョートルに吹き込まれて、シャートフが彼らを密告しようとしていると信じていたし、そればかりか、晩にはシャートフを密殺する計画に加わっていた。だから、彼の頼みに容易には応じなかったが、それでも、シャートフの必死な哀願の調子が、彼らの考えをわずかに変えた。
ヴィルギンスキーの妻アリーナは、マリイのもとへ走った。リャムシンは、ピストルの代金を半分だけ渡した。
「彼女〔アリーナ・ヴィルギンスカヤ――ギトン注〕はいつも、〈シャートフのような屑は、市民として卑劣な真似をしかねない〉と思いこんでいたが、しかし妻のマリヤの帰宅は、問題を新しい角度から検討させることになった。シャートフのうろたえぶり、助力を懇願し、哀願したときの必死な調子は、裏切者の心中にある転換が起ったことを物語っていた。他人をおとしいれるために自分を売ろうとさえ決意した人間ならば、いま現実に見受けられるの〔シャートフの態度――ギトン注〕とは、まったく別の様子、別の調子をしているはずだと思われた。一口にいうと、アリーナはすべてを自分の目で確かめてみようと決心したのである。〔それゆえに、シャートフの依頼を引き受けてマリヤのところへ行ったのである。―――ギトン注〕」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.471-472.
こうして、助産婦アリーナの介助のもとに、マリヤ・シャートワは、男の子を無事に出産した。
出産は、狭くて汚い・馬小屋のような場所で行われた。まるで、わが子の出産のように我を忘れて奔走した夫は、しかし、“身に覚えがなかった”。つまり、あたかもマリヤの“処女懐胎”のようにして、《キリスト》は生誕したのです。
「赤ん坊をくるみ終えて、〔…〕ほんのちょっとの間、彼女〔助産婦アリーナ――ギトン注〕は赤ん坊をシャートフにあずけた。マリイはアリーナの目をはばかるように、何かこっそりと彼にうなずいて見せた。こちら〔シャートフ――ギトン注〕はすぐに察して、赤ん坊を彼女に見せに行った。
『なんて……かわいい……』彼女は微笑を浮べ、弱々しい声で言った。
〔…〕マリイが赤ん坊について言ったたった二言で、もう輝きわたらんばかりになったシャートフは、しあわせそのもののおめでたい表情でつぶやいた。
〔…〕
『新しい生の出現の神秘ですよ、大きな、説明のつかない神秘ですよ、アリーナさん。〔…〕
二人しかいなかったところへ、ふいに第3の人間が、新しい魂が生れる。人間の手では決してできないような、完璧に完成された魂がです。新しい思想と新しい愛、恐ろしいみたいだ……世界にこれ以上すばらしいものはない!』
『まあ、くだらない。有機体の生成発展というだけで、神秘なんて何もありゃしないじゃないの』アリーナは心から愉快そうに笑った。『そんなことを言っていたら、蝿一匹も神秘になってしまう。〔…〕』
『ぼくは絶対にこの子を養育院なんかへやりやしない!』床を見つめて、シャートフがきっぱりと言いきった。
『養子になさるつもり?』
『この子はぼくの息子なんです』
『もちろん、この子はシャートフですよ。法律上シャートフですよ。なにもあなたが人類の恩人面(づら)をすることもないでしょう。』」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.482-484.
助産婦のアリーナが、最後に言っているのは、生まれた子を、シャートフ夫妻の実子として出生届を出すことに、協力しようという意味です。日本でも、助産婦の作成した母子手帳の父の欄に夫の名が書いてあれば、役所は実子として受理します。ロシアでも同様だったでしょう。
しかし、シャートフ夫妻は、スイスで「離婚した」のではなかったのか?
そこで、ちょっと調べてみたのですが、カトリックと違って、正教会は古くから離婚を認めていました。が、ロシアでは、19世紀以後、民法によって離婚は裁判によらなければならないこととされました(⇒:『近代ロシアの家族法』(PDF),p.123)。したがって、シャートフ夫妻がスイスで、婚姻の3週間後に「離婚した」というのは、事実上の離婚であって、法律上正式には夫婦のままであったと考えなければなりません。

ヘラルト・ファン・ホントホルスト
『羊飼いたちの礼拝』(1622年)
アリーナ・ヴィルギンスカヤは、「『あなたからお金なんてもらいませんよ』」とシャートフに言い残して「大満足の態で引きあげ」ると、家に駆け戻って、この状況を夫に報告した。そこで、夫ヴィルギンスキーも、シャートフがいま「密告」するなどありえないことを、確信することになる。
【16】シャートフと《キリスト》の殺害
「『わたしのほうにかがんでちょうだい』できるだけ彼〔シャートフ――ギトン注〕のほうを見ないようにしながら、彼女〔マリイ――ギトン注〕はふいに別人のような声で言った。
彼はぴくりとふるえたが、それでもかがみこんだ。
『もっと……そうじゃなく……もっと近く』と、ふいに彼女の左手がさっと彼の首に巻きつけられ、彼は自分の額に力のこもった、しっとりとした口づけを感じた。
『マリイ!』
彼女の唇がふるえていた、彼女はじっと耐えているふうだったが、ふいに上体を起すと、目をぎらぎらと輝かせながら、言った。
『ニコライ・スタヴローギンは悪党よ!』
そう言うと、薙ぎ倒されでもしたように、顔を枕に埋めて倒れてしまい、ヒステリカルに泣きじゃくりながら、シャートフの手を自分の手の中で強くにぎりしめた。
この瞬間から、彼女はもうシャートフを自分のそばから離そうとせず、どうしても枕もとにすわっていてくれと言い張った。話はあまりできなかったが、彼の顔から目を離そうとせず、幸福そのもののように彼にほほえみかけるのだった。彼女は突然、まるでばかな小娘のようになってしまった。すっかり生れ変りでもしたようだった。〔…〕」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.485-486.
マリイの陣痛が始まる前に、シャートフは、
「この愛する女性が苦しみ悩んでいること、もしかしたら、だれかに辱(はずかし)めを受けているらしいことを察したのだった。彼は心臓がとまりそうになった。」
と書かれていました。どうやら、マリイが「辱め」を受けていた「だれか」とは、スタヴローギンであったようです。生まれた子の実の父親も、おそらくスタヴローギンなのでしょう。
「彼〔シャートフ――ギトン注〕はキリーロフのことや、二人でこれから『あらためて未来永久に』はじめる生活のことや、神が存在することや、みなが善良だということを話した……そして有頂天になって、またも赤ん坊を引き出してはつくづくと眺めるのだった。
『マリイ』赤ん坊をかかえながら彼は叫んだ。『古いうわごとも、恥辱も、死屍のような思想も、これでおしまいだよ。新しい道に向って、これから3人で働こうじゃないか、ね、ね!〔…〕』」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.486-487.
こうして、著者のアレゴリーでいうと、アメリカ行きで《キリスト》を見失って、《3→2》となっていたのが、マリイの出産によって、失ったものを回復した(《2→3》)ことになります。
ドストエフスキーは、“命数論(めいすうろん)”を信じていたそうです。“命数論”とは、《1》《2》《3》といった数に、それぞれ呪術的な意味があるという迷信です。たとえば、東洋では、《3》,《8》などは縁起の良い数、《7》は縁起が悪いとされますが、西洋では、《7》はラッキー・セブン、《13》は不吉な数です。「数秘術」「運命数」などと云って、さまざまな流派があって、それぞれ占断が違うんですから、信用できるようなもんではありませんw たとえば⇒:カバラ数秘術。しかし、ドストエフスキーが、どの“命数術”を信じていたのか、大真面目に研究している文学者のグループもあります。
おそらく、《2》と《3》にも、何か神秘的な意味があると、ドストエフスキーは考えていたのでしょう。

ピーテル・ブリューゲル『ベツレヘムの嬰児虐殺』
ところが、そうしてシャートフが妊婦に付き添っていると、夜になり、ピョートルの指示を受けた若い“同志”が、シャートフを迎えにやってきます。暗殺計画が自分に向けられているとは夢にも思わないシャートフは、隠して保管している印刷機の受け渡しと信じて付いて行ってしまいます。
「マリイは、『よくもわたしを一人ぼっちにして行けるものだ』と、絶望にかられて憎まれ口をきいた。
『しかしね』と彼は有頂天で叫んだ。『これはもう最後の一歩なんだよ! これから先には新しい道が開ける。そして、古い恐怖のことなんぞ、もうけっして、けっして思い出さなくてすむんだ!』
なんとか彼女を説きつけて、彼はきっかり 9時に帰ってくると約束した。」
江川卓・訳『悪霊』,下,p.489.
マリイが夫の姿を見たのは、これが最後となります。
シャートフの到着を待つ現場では、ヴィルギンスキーが、昨夜からの状況を説明して、計画を中止させようとしますが、ピョートルに阻まれて、まとまりません。シガリョフひとりは、ピョートルに銃口を向けられながら立ち去ってしまいますが、ほかの4人は、ふんぎりがつかないまま、若い“同志”がシャートフを連れて到着します。そして、殺害は計画通りに実行されるのです。
2人がかりでシャートフを抑えつけ、ピョートルが彼の額に銃口を着けて射ったあと、ヴィルギンスキーとリャムシンは、半狂乱になって叫びだしますが、もはや後の祭りです。
「無法きわまる犯罪行為のすべては、思いもかけぬ早さで露顕した。ピョートルが予想したよりも、はるかに早かった。事の始まりは、不幸なマリイが、夫の殺害された晩、夜明け前にふと目をさまし、〔…〕彼がいないのに気づき、言い表わしようもない不安にかられたことであった。」
江川卓・訳『悪霊』,下,p.618.
彼女は、離れへ行ってみて、キリーロフの銃死現場を発見すると、助けを求めて着の身着のままで往来へ駆けだした。
「彼女は自分の部屋へ駆け戻ると、、赤ん坊を引っかかえて、そのまま往来へ駆けだした。湿っぽい朝で、霧がこめていた。〔…〕彼女は、ぬかるんだ冷たい泥道を、息を切らしながら、ひた走りに走り、やがて、よその家の戸をがんがん叩きはじめた。〔…〕
ともかくも彼女が、当人の言うところによると、お産をしてからまだ一昼夜とたたない体で、ろくに着物も着せていない赤ん坊を抱いて、こんな寒さの中を、こんな身なりで、通りを駆けまわっていることに、みなははげしいショックを受けた。〔…〕彼女は恐ろしい声でわめきたて、もがきまわったということである。」
江川卓・訳『悪霊』,下,pp.620-621.

ロシアのアパートの中庭 19世紀と現在
マリイが、キリーロフの死体を見て、なぜ自分の夫も殺されたと判断したのかは、明らかでない。ともかく、彼女は夫の遭難を直感し、確信していた。
人びとの通報で警察が出動し、彼女から事情を聞いたが、シャートフの安否については何も聞き出せなかった。キリーロフの死体とともにあった「遺書」についても、警察は最初から作為を疑った。
「正午近く、彼女は意識不明の状態に陥り、もう二度と意識が戻ることもなくて、三日ほどしてから亡くなった。風邪を引いた赤ん坊は彼女より先に死んだ。」
江川卓・訳『悪霊』,下,p.621.
犯人たちは、シャートフの死体に重しをつけて、殺害現場の公園の池に沈めていたが、うかつにも、シャートフの帽子を現場に遺留していた。通報のあった日の夕方には、警察は、死体を池から引き上げた。
それでも、犯人に関する手がかりは無かった。死体検証の結果から、複数人の凶行であることは推定されたものの、犯人グループをつきとめるのは容易でなかった。まもなく、狂乱状態になったリャムシンが自首したことで、すべてが露見した。殺害に関係した者は、ピョートル以外の全員が検挙された。ピョートルだけは、ひと足早く国外に逃亡したあとだった。
【必読書150】ドストエフスキー『悪霊』―――終り。
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]









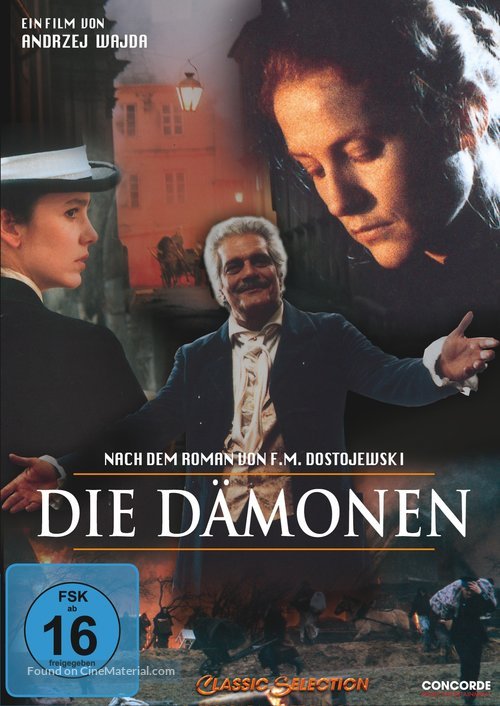




 彡
彡