10/04の日記
19:23
【必読書150】ドストエフスキー『悪霊』(2)―――“思想”のために人は死ねるか?
---------------
.

『悪霊』: ステパン先生の“自由主義”サークル
1988年フランス映画 アンジェイ・ワイダ監督
こんばんは。(º.-)☆ノ
【必読書150】ドストエフスキー『悪霊』(1)を書いてから、ずいぶん日が経ってしまったのですが、ようやく (2) をうぷできる運びになりました。
当初の計画では、《脇スジ》をいくつか拾って、それぞれあらすじをまとめてみようと考えていたのですが、じっさいやってみると、一つの《脇スジ》だけでも、1回の掲載におさまらないくらい長くなってしまいます。自分で納得できるように書こうとすると、短くするのは無理なのです。
そこで、ひとつの《脇スジ》にしぼって書くことにしました:
キリーロフとシャートフ
この二人の登場人物は、『悪霊』の主要な狂言回しではないかもしれませんが、作者の構想の中では、おそらく重要な位置づけを与えられています。とくに、シャートフは、登場人物中唯一、作者にとって肯定的意味をもつ人物だと思われるのです。
なお、この小説に限らず、ドストエフスキーの長篇は、おおぜいの人物が出て来て、それぞれのストーリーが複雑に絡み合うので、誰が誰やら分からなくなってしまいます。
前回 (1) の後半に、主要な登場人物の一覧を載せていますので、適宜参照していただければと思います。
【5】脇スジ――キリーロフとシャートフ
この二人は、それぞれの抱いている思想は正反対です。つまり、無神論と有神論………のように見えます。
もっとも、キリーロフは“無神論者”とは言っても、その言動はしばしば狂気じみていて、ほとんど神がかりに近い。それは、ストーリーの進行とともに明らかになります。
シャートフは、“有神論”とは言っても、教会へ行ってお祈りをするわけではない。神秘めいた虚飾の覆いを剥ぎ取ってみると、その思想は、きわめて無内容である。それでいて、彼は、自らは必ずしも意図しない行動において、生を肯定する人道的・倫理的な態度をとるのです。
しかし、二人には、いくつかの共通点があります。
ひとつは、ふたりとも、貴族地主でもなければ、農奴でもない、中間階層(「雑階級人(ラズノチンツィ)」)であることです。
キリーロフは、ヨーロッパで建築工学を修めて帰国したばかりの技師として紹介されます(pp.168-170)。
他方、シャートフも、大学中退のインテリゲンチャで、商人の家庭教師や雇人をして乏しい収入で暮らしています。
「シャートフは以前は学生だったが、学生騒動がもとで大学を放校になった男だった。〔…〕ワルワーラ夫人の従僕だった故パーヴェル・フョードロフを父に、夫人の農奴として生まれ、夫人には一方ならず恩顧をこうむっていた。」
江川卓・訳『悪霊』,上,新潮文庫,p.50.
大学に入ったのも、ワルワーラ夫人の援助によるものでしょう。しかし、夫人から見ると、シャートフは恩知らずで、大学を放校になったあと、夫人からの手紙に返事もしないで、「開化主義者の・ある商人」にかかえられて家庭教師になり、子どもたちの「お守り」をしながらヨーロッパへ出かけて行った。
「当時の彼は、外国行きがなによりの念願だったのである。子供たちにはもう一人、女の家庭教師がついていた。〔…〕向こう見ずなロシア娘だったが、彼女は2ヵ月ばかりで、《自由思想の持主》ということで商人から追い出されてしまった。シャートフも女のあとを追い、ほどなくジュネーヴで彼女と結婚した。3週間ほどの同棲生活ののち、二人は、何者にも束縛されぬ自由な人間同士として離婚した。もちろん、貧乏生活も原因していた。その後の彼は長いこと単身ヨーロッパを放浪して歩いた。」
江川卓・訳『悪霊』,上,新潮文庫,p.51.

『悪霊』: シャートフ(左)とスタヴローギン(右)
1988年フランス映画 アンジェイ・ワイダ監督
シャートフは、1年ほど前に、“この地方都市”に戻って来て、ステパン先生を中心とするインテリゲンチャのサロンにも出入りするようになった。彼は、
「私たちの仲間内〔ステパン先生を中心とするサークル――ギトン注〕では、いつも陰気くさく、無口だったが、時たま、自分の信条にかかわるようなことがあると、病的に興奮して、ずいぶん思いきった口をたたいた。」
a.a.O.
「ひところ町には、私たちのグループが自由思想と放縦と無神論の温床だという噂が立ち、この噂はその後も強まる一方だった。だが、実をいえば、私たちはそれこそなんの罪もない、愛すべき、純粋にロシア式の、楽しくリベラルなおしゃべりにふけっていただけなのである。〔…〕ステパン先生は、機知に富んだ人の常として、ぜひとも聞き手を必要としていたし、〔…〕酒の間に、ロシアや《ロシア的精神》について、神一般、なかんずく《ロシアの神》について、お定まりの調子のいい議論をたたかわせられる相手がいなくてははじまらなかった。」
江川卓・訳『悪霊』,上,p.58.
シャートフは、「年は 27 か 28 くらい」で、「町はずれに一人で暮らしてい」た(p.52)が、ワルワーラ夫人の養女となって静かに暮らしている妹のダーシャとは、ほとんど行き来がなかった。
「ひどく金にはつまっていたが、〔…〕ワルワーラ夫人には二度と援助を求めようとせず、その日暮らしでなんとか食いつなぎ、商人たちのところに勤めたりもした。」
a.a.O.
キリーロフとシャートフは、ロシアから離れていた間に、相伴ってアメリカへ渡ったことがあり、アメリカ人の開拓民の農場で「汗みどろになって」「何度もなぐられて」働いたあと、そこを逃げ出し、4ヵ月間、呑まず食わずで過ごしてから、ヨーロッパにいたニコライ・スタヴローギンに無心して帰りの旅費を送ってもらい、戻って来たのだった。シャートフは言う:
「『ぼくらは一昨年、なけなしの金をはたいて、3人、移民船でアメリカへ渡ったんですよ。「アメリカ労働者の生活を自ら経験し、その個人的体験によって最も困難な社会的状況に置かれた人間の状態を検証せんがため」にです。〔…〕』」
江川卓・訳『悪霊』,上,p.263.
(おそらく)アメリカ行きの直前に、彼らは、スタヴローギンの勧誘に応じて、ある《秘密結社》に入会していた。過激思想、ないしロシアの社会転覆を目的とする結社のようだが、実体は不明である。結社の全体像は、シャートフらにも知らされることはない。『第1インターナショナル』(国際労働者協会。ヨーロッパの労働者、社会主義者が 1864年に創設した国際政治結社。マルクス、エンゲルスのほか、ラッサ―ル主義の社会民主主義者、バクーニン、およびブランキ主義、プルードン主義のアナーキストらが参加していた。)傘下の地下組織だとの噂もあるが、それはすべて見せかけで、スタヴローギンと、ステパン先生の息子であるピョートル・ヴェルホーヴェンスキーとが、勝手にでっちあげた架空の組織のようにも思われる。
(おそらくは)《秘密結社》への入会のさい、キリーロフとシャートフは、それぞれ別々にスタヴローギンの勧誘を受けており、スタヴローギンから、およそ正反対と思われるような思想を示されて心酔し、それぞれの人生の指針としてしまった。(各思想の内容については、後述)
その結果、キリーロフは、いつでも《組織》が命ずる時に、《組織》の利益のために自刹を敢行することを約束し、そして実際に、ピョートルの巧妙な指示のもと、《シャートフ殺害事件》↓の揉み消しに利用されて命を絶つ。
他方、シャートフは、アメリカから戻ったあとで、《組織》からの離脱を申し出る。しかし、スタヴローギンらは、退会の承認を先延ばしし、シャートフに、地下出版物印刷のための印刷機を預らせるなどして、離脱できないようにする。最終的に、ピョートルは、彼が当局のスパイであるとの虚偽の嫌疑をかけて《結社》の仲間を使嗾し、撲殺する。
つまり、現実に、ふたりの運命を決定的なしかたで裁断するのは、スタヴローギンではなく、ステパン先生の息子であるピョートル・ヴェルホーヴェンスキーなのです。
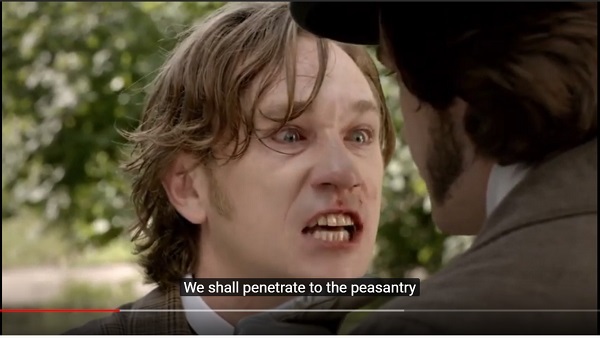
『悪霊』: ピョートルとスタヴローギン(右)
2014年ロシア映画
【6】キリーロフ―――人は“思想”のために死ねるか?
キリーロフは、シャートフが住んでいる同じアパートの離れを借りて暮らしている。彼らは、たがいに著しく隔たった思想と人生観を抱いていることを了解しあっているので、対立することもないが、親しく行き来しているわけでもない。干渉しあわない別々の一人暮らしなのだ。
キリーロフは、「何か著作を書いておられるのか?」という私(『悪霊』の語り手。アントン・ラヴレンチェヴィチ・G)の問いかけに、こう答える:
「『あれはほんとうの話です。ぼくは書いています。〔…〕
なぜ人間があえて自刹しようとしないのか、その原因を探究しているんで、それだけのことなんです。〔…〕』
『あえてしないというのは? 自刹が少ないというわけでも?』
『非常に少ないですね』
〔…〕
『あなたの考えだと、人間に自刹を思いとどまらせているのは何なのです?』私はたずねた。
〔…〕
『ぼくは……ぼくはまだよくわかりません……2つの偏見が思いとどまらせていますね、2つのこと、2つきりです。〔…〕」
江川卓・訳『悪霊』,上,新潮文庫,pp.213-214.
第1の「偏見」は、「痛いこと」だと言う。自刹する人には2種類があって、①「非常な悲しみや憎しみから自刹する人」にとっては、痛いことなど何でもない。しかし、②「思慮をもってやる人たち」にとっては、自刹が「痛い」かもしれないことは、大きな障碍になる。
「『ひとつ想像してみてください』彼〔キリーロフ――ギトン注〕は私の前に立ちどまった。『大きなアパートの建物ほどもある石を想像してみてください。それが宙に吊してあって、あなたはその下にいる。もしそれがあなたの頭の上に落ちてきたら、痛いですかね?』
〔…〕
『山ほどの石、何十億キロのでしょう? 痛いもなにもあるもんですか』
『ところが実際にそこに立ってごらんなさい。石がぶらさがっている間、あなたはさぞ痛いだろうと思って、ひどくこわがりますよ。どんな第一流の学者だって、〔…〕だれもが、痛くはないと承知しながら、だれもが、さぞ痛いだろうとこわがる』」
江川卓・訳『悪霊』,上,新潮文庫,pp.215-216.
キリーロフが言う第2の「偏見」は、「あの世」である。「あの世」が自刹の障碍になるとは、どういう意味か? たしかに、キリスト教は、自刹を重大な罪としており、自刹者は地獄に落ちるとも言う。しかし、キリーロフは、「神罰」のことではないと言う。
このあとのキリーロフの言動は混乱していて、意味を取りがたいのですが、前後対照して解釈すれば、次のようになるでしょう。
自刹を思いとどまらせる第2の原因―――第1が「たいへん小さなこと」だとすれば、第2は「たいへん大きなこと」―――とは、“死後の世界”に対する懐疑ないし恐怖、すなわち「神」の存在である。彼は、
「『みんな一つことを考えては、そのあとすぐ、ほかのことを考える。ぼくは、ほかのことできない。生涯一つことです。神がぼくを生涯苦しめてきたんです』」(p.219)
と、最後に不意に「あけすけになって」、内心を吐露するように言います。人間は、生きている限り、自己の“生”の条件に拘束される。生きている限り、さまざまな恐怖や苦しみを身に受けることになる。生きている限り、完全な“自由”も完全な“幸福”もありえない。では、死後には、それがあるのか? 否、少なくとも生きている限り、人間は“死後”を望み見たとたんに、「神」に直面することになる。“死後”を支配するのは「神」であって人間ではない。だとすれば、いったいどこに“自由”があるのか?

「『人間が死を恐れるのは、生を愛するからだ、〔…〕』と私が口をはさんだ。〔…〕
『それが卑劣なんです。そこにいっさいの欺瞞のもとがあるんだ!』彼の目がぎらぎらと輝きだした。『生は苦痛です、生は恐怖です、だから人間は不幸なんです。〔…〕いまは生が、苦痛や恐怖を代償に与えられている、ここにいっさいの欺瞞のもとがあるわけです。いまの人間はまだ人間じゃない。』」
江川卓・訳『悪霊』,上,新潮文庫,p.217.
つまり、宗教の「神」とは、キリーロフによれば、“死後”に対する「恐怖」の別名なのです。“死後”に対する「恐怖」を克服したとき、すなわちいかなる恐怖もなく自刹したときに、人間は、「神」と宗教を消滅させ、みずからが神となるのです。
「『幸福で、誇り高い新しい人間が出てきますよ。生きていても、生きていなくても、どうでもいい人間、それが新しい人間なんです。苦痛と恐怖に打ちかつものが、みずから神になる。そして、あの神はいなくなる。〔…〕
痛みと恐怖に打ちかつものが、みずから神になる。そのとき新しい生が、新しい人間が、新しいいっさいが生れる。〔…〕
人間は神になって、肉体的に変化する。世界も変るし、事物も、思想も、感情のすべても変る。どうです、そのときは人間も肉体的に変化するでしょう?』」
『悪霊』,上,pp.217-218.
“死の恐怖”に打ちかって自刹することによって、「神」も「あの世」も宗教も必要としない「幸福で、誇り高い新しい人間」が生れる―――というのは、まったく理解できないでもありません。論理的には、そういうことになる。しかし、死んでしまったら、その先がないじゃないか? 「新しい生」は、自刹の瞬間にしか、ないではないか? ‥‥そう思われるかもしれません。
しかし、キリーロフにとっては、「その先」は、あってはならないのです。なぜなら、
「『その先には自由がない。ここにいっさいがあって、その先にはなにもないんです。」(p.218)
つまり、“死後の世界”のようなものに入ってしまったら、そこは「神」が支配しているかもしれない。「神」でなくとも、あらたな恐怖が支配するにちがいない。いっさいは、「ここ」すなわち自刹の瞬間にだけある。
‥‥それでは、まったく虚しいナンセンスではないか。「新しい生」も「幸福」も「自由」も「誇り高さ」も、一瞬にしかなくて、二度と繰り返せないのだとしたら、いったい何の意味があるのか?‥‥
たしかに、『悪霊』のストーリーの・この時点では、“キリーロフ理論”にとって、それが致命的な欠点になっています。しかし、↓のちほど引用しますが、彼は、スタヴローギンとの対話の中で、このアポリアに、一種みごとと言ってよい答えを出します。
死の恐怖を克服した自刹者にとって、“死”は一瞬ではないのです。それは、永久に続く時間となる。つまり、彼は、“死”と「神」を克服するだけでなく、《時間》を克服するのです。生のあいだ他律的にのみ流れていた《時間》は、この“死”の時からは、彼自身の《時間》として永久化します。
キリーロフにとっては、“死”を一瞬と思うこと自体が、生によって強いられた錯覚であり、「欺瞞」なのです。
私たちが、“死”は一瞬だと思うのは、自分が死んだ後も他の人間が生きつづけ、自分以外の社会が営まれつづけ、地球と宇宙が存在し続けると思うからです。では、世界が同時に“自刹”したらどうか? 人類全体が、“恐怖無き自刹”を同時に敢行したら?‥
その場合は、そこで世界は終ってしまう、‥というよりも、その“先”まで存在し続けるものが何もない以上、そこですべては停止する。つまり、《時間》は止まり、人類は、“死”の恐怖に打克った「自由」で「幸福」な「新しい人間」として、《時間》のない世界に永久に存在しつづけるのです。
「『自由というのは、生きていても生きていなくても同じになるとき、はじめてえられるのです。これがすべての目的です』
『目的? でも、そうなったら、だれひとり生きることを望まなくなりはしませんか?』
『ええ、だれひとり』彼はきっぱりと言い切った。」
『悪霊』,上,p.216.
人類が、誰ひとり生きることを望まなくなること、「生きていても生きていなくても同じになる」こと、つまり「自由」になり、「誇り高い新しい」人類に生れ変ること、――それこそがキリーロフの「目的」なのです。
「『痛みと恐怖に打ちかつものが、みずから神になる。そのとき新しい生が、新しい人間が、新しいいっさいが生れる。……そのとき歴史が二つの部分に分けられる――ゴリラから神の絶滅までと、神の絶滅から……』
〔…〕
『……地球と、人間の肉体的変化までです。人間は神になって、肉体的に変化する。〔…〕
最高の自由を望む者は、だれも自分を殺す勇気をもたなくちゃならない。〔…〕あえて、自分を殺せる者が神です。〔…〕だれにでもできるはずです。ところが、だれもまだ一度としてそれをした者がない』
『自刹者は何百万人となくいましたよ』
『ところが、いつもそのためにではない。いつだって恐怖を感じながらで、その目的のためではなかった。恐怖を殺すためではなかった。恐怖を殺すためだけに自刹する者が、たちまち神になるのです』」
『悪霊』,上,pp.217-218.
【7】キリーロフとスタヴローギン
ニコライ・スタヴローギンは、公衆の面前で侮辱したガガーノフの息子に決闘を申し込まれ、キリーロフに介添え人を頼みに来ます。
決闘自体は、キリーロフの適切な交渉と立ち合いのおかげもあって、スタヴローギンの望む結果で終ります。つまり、“決闘”を嘲笑うかのように、見当違いの方角にのみ発砲するスタヴローギンと、怖れのあまり何度狙ってもスタヴローギンに命中させることができない相手とのやりとりの結果、相手は一方的に侮辱されて終ります。
しかし、ここで注目したいのは、介添えの相談のあいだに、スタヴローギンとキリーロフが交わす“自刹論”に関する会話です。
この“自刹論”じたい、かつてスタヴローギンがキリーロフに吹き込んだものなのですが、スタヴローギンは、もうそのことさえ忘れかけていて、「きみはいまでもまだ同じ考えなんですね?」などと訊くのです:
「『ずいぶんピストルがありますね、それも非常に高価なものが』
『非常にね。とびきりのが』
貧乏で、乞食も同然のキリーロフが、といっても、彼は自分の貧窮をまるで気にかけていなかったが、いまはいかにも得意げに、明らかに非常な犠牲を払って手に入れたものにちがいない高価な武器を見せびらかすのだった。
『きみはいまでもまだ同じ考えなんですね?』ちょっと黙ってから、スタヴローギンがいくらか慎重な態度でたずねた。
『同じです』相手の声音でとっさに質問の意味を悟って、キリーロフは言葉少なに答え、テーブルの上の武器を片づけにかかった。
『で、いつ?』〔…〕
『それはぼくの決めることじゃない、ご存じでしょう。言われたときです』〔…〕じっとスタヴローギンの顔を見返している輝きのない彼の黒い目には、何に動ずる色もない、それでいていかにも善良な、人なつこい感情があらわれていた。」
江川卓・訳『悪霊』,上,新潮文庫,pp.446-447.
「言われたとき」とは、《結社》の指令があった時です。指令のあった時に“自刹”することが、キリーロフと《結社》との約束であり、彼の唯一の任務なのです。彼は、《結社》に加入して以来、この“任務”を片時も忘れたことは無かったでしょう。しかし、スタヴローギンは、キリーロフに“自刹の思想”を吹き込んで、この任務に就かせたにもかかわらず、そのことをほとんど忘れかけているのです。
スタヴローギンは、人ごとのように言います。
「『ぼくにも、むろん、ピストル自刹というのはわかります』3分ほどの長い物思わしげな沈黙を破って、ニコライがまた口を切った。『ぼく自身、想像してみたことがある、すると、いつも何かこう新しい考えがひらめくのですよ。たとえば、かりに自分が何か悪事を働いたとする、というより、〔…〕世間の人が〔…〕千年も唾をはきかけつづけるようなことをしたとする、と、ふいにこんな考えが浮かぶのですよ。〈こめかみに一発打ちこめば、それできれいさっぱりじゃないか〉とね。そうなったら世間の人がなんです、千年も唾をはきかけられるのがなんです、そうじゃありませんか?』
『きみはそれが新しい考えだと称されるんですか?』キリーロフはすこし考えてから言った。
『ぼくは……称するわけじゃない……一度そのことを考えたとき、まったく新しい考えを感じたんです』
『「考えを感じた」?』キリーロフは相手の言葉をそのまま引き取った。『それはいいな。いつもあるものなのに、それが突然新しく感じられる考えというのはたくさんありますよ。〔…〕』」
江川卓・訳『悪霊』,上,新潮文庫,pp.447-448.
「世間の人」に軽蔑される苦しさを免れるために自殺する、などというのは、キリーロフにとっては、あまりにもありふれた考えにすぎません。彼に“自刹”と「神」について考えをめぐらすきっかけを与えた当の人物が、それを「新しい考え」だなどと言うのは、彼にとっては、まったく呆れた体たらくにちがいない。
ここに、キリーロフという鏡を通して、スタヴローギンの人物像―――紙のように薄っぺらい、その生きざまが現れているといえます。
問題に対する真剣さにおいて、スタヴローギンは、キリーロフの足もとにも及ばない。しかし、スタヴローギンもまた、この小説の最後に自刹します。
スタヴローギンは、みずから犯した数々の人非人的行為の恥をすすぐために自刹した―――ようにも見えるが、しかし、そうではなかった。
↑上の会話のすぐあとで、スタヴローギンは、また別の想像を持ち出します。月の世界で悪事を犯したとして、地球に移って来てしまえば、自分の悪事を知る者は誰もいない。つまり、死ななくてもよいのです。彼に「唾を吐きつづける」「世間の人」たちさえいなければ。それが、スタヴローギンの考えです。
小説の最後で、彼は、情婦の一人であったダーシャを連れて、スイスの田舎へ引きこもることを計画し、……そうして「世間の人」の目の届かないところで暮らすことを目論んだ……にもかかわらず、ダーシャの返事を待たずに自殺してしまったのです。
スタヴローギンの自刹の動機は、わかりません。書かれていないからです。スイスに逃げても、けっきょく彼を知るロシアの人びととのつながりは無くせないと思ったのか? それとも、最初に計画したリーザとの駆け落ちが、彼女の拒否によって頓挫したため、いわば“二番手”の情婦であるダーシャを誘ったけれども、ダーシャでは、自分はまもなく満足できなくなると予想したのか? ‥‥たとえ“自刹”の動機はどうあれ、“月から地球に移って恥をすすぐ”という、彼の「新しい考え」が、実現できるものではなかったということ―――それだけは、確かなのです。
しかし、キリーロフが目指しているのは、それ以上のことです。彼は、与えられた「いま」の生を、……スタヴローギンのように他人をなぶりつつ欺瞞的に、ではなく……おちついて、つつましく暮らしながら、それとはまったく別に、“理性”と“論理”の帰結するところにしたがって、みずから「神」となるべく自刹しようとする。
「『きみ、子供はすきですか?』
『好きです』とキリーロフは答えたが、かなり気のない調子だった。
『じゃ、人生も好きですね?』
『ええ、人生も好きですよ、それがどうしました?』
『ピストル自刹を決意していても?』
『いいでしょう? なぜいっしょにするんです? 人生は人生、あれはあれですよ。生は存在するけれど、死なんてまるでありゃしません』
『きみは未来の永遠の生を信ずるようになったんですか?』
『いや、未来の永遠のじゃなくて、この地上の永遠の生ですよ。そういう瞬間がある。その瞬間まで行きつくと、突然時間が静止して、永遠になるのです』」
江川卓・訳『悪霊』,上,新潮文庫,p.449.
「突然時間が静止して、永遠になる」瞬間、「地上の永遠の生」がはじまる瞬間、どのようにしたら、そこに到達するのか、キリーロフは、ここではまだ語っていません。彼自身にも、それはまだ分からないでしょう。
しかし、最終的に、それは“自刹”の瞬間、“死”の瞬間であることを彼は知る、―――あるいは、彼の死を《組織》に利用しようとするピョートルの奸策によって思いこまされる―――ことになります。そして、彼は自刹を決行する。。。

【8】キリーロフ―――絶対理性と“超人”の思想
その前に、シャートフとの会話の中では、キリーロフは、“瞬間”について、つぎのように語っています:
「キリーロフははっとわれに返り――奇妙なことに――いつも話すよりはるかに流暢な調子で話しだした。明らかに、彼はもうずっと以前からこの考えをまとめあげ、ひょっとしたら、なにかに書きつけていたのかもしれない。
『ある数瞬間がある、―――それは一度にせいぜい5秒か6秒しかつづかないが、そのときだしぬけに、完全に自分のものとなった永久調和の訪れが実感されるのだよ。これは地上のものじゃない。といって、なにも天上のものだと言うのじゃなくて、地上の姿のままの人間には耐えきれないという意味なんだ。肉体的に変化するか、でなければ死んでしまうしかない。これは明晰で、争う余地のない感覚なんだ。ふいに全自然界が実感されて、思わず、『しかり、そは正し』と口をついて出てくる。〔…〕何より恐しいのは、それがすさまじいばかり明晰で、すばらしい喜びであることなんだ。〔…〕この5秒間にぼくは一つの生を生きるんだ。この5秒間のためになら、ぼくの全人生を投げ出しても惜しくはない、それだけの値打ちがあるんだよ。10秒間もちこたえるためには、肉体的な変化が必要だ。ぼくの考えでは、人間は子供を生むことをやめるに相違ないね。目的が達せられた以上、子供が何になる、発達が何になる?〔…〕
『きみ、癲癇の持病はないのか?』
『ない』
『じゃ、いまにそうなるよ。気をつけたまえ、キリーロフ、癲癇の初期はそんなふうだと聞いたことがある。〔…〕水差しの水がこぼれないうちに、馬に乗って天国を一周してきたマホメットの話を思い出して見たまえ。〔…〕しかもマホメットは癲癇持ちだったんだからね。気をつけたまえ、キリーロフ、癲癇だよ!』
『その暇はないさ』キリーロフは静かに苦笑した。」
江川卓・訳『悪霊』,下,新潮文庫,pp.478-480.
つまり、この時点では、キリーロフは、必ずしも“自刹”を決行しなくとも、再生の“瞬間”に達する方法はあると考えていたのです。彼の“理論”によれば、“死”の恐怖を克服し、“死後の世界”「神」などの仮象を消滅させることさえできればよい―――その時、人は自ら「神」となり、永遠の生を生きる―――のだから。
もしも彼が、この“自刹しなくとも、死を克服できる方法”を見極め、実行することができたとしたら、彼は、新しい宗教の教祖か、ニーチェ流の哲学者くらいにはなっていたかもしれない。
しかし、彼の哲学、ないし“新宗教”の探究は、暴力的に中断されました。しかも、シャートフが心配したような癲癇病の進行によってではなく、《組織》を背景としたピョートルによって強いられた・彼の自刹によって。。。
【9】キリーロフ―――救世主の自己犠牲か? 《組織》に強いられた“死”か?
《結社》の仲間を使嗾してシャートフを殺害した後、ピョートルはキリーロフを訪れる。キリーロフに、自分がシャートフを殺害したとの遺書を書かせ、自刹させるためにである。
ピョートルが、これをキリーロフに納得させうる理由は、①それが《組織》の指示であること―――《組織》じたいがピョートルらのでっちあげた架空のものらしいのだが―――、そして、②死んでしまう以上、後にどんな遺書が残ろうとも、どうでもいいではないか、ということである。

『悪霊』: ピョートルとステパン先生
1988年フランス映画 アンジェイ・ワイダ監督
「『シャートフは来ないさ。で、きみにはこう書いてもらいたいんです、きみらは裏切り、密告のことでいさかいになって、……今夜……彼の死の原因となった』
『彼が死んだ?』キリーロフはソファから躍りあがって叫んだ。
『きょうの7時過ぎ、というより、きのうの7時過ぎだな、もう12時過ぎだから』
『きさまが殺したな!……きのうからもう見抜いていた!』
『見抜けなくて、どうします? ほら、このピストルでね(彼はピストルを取出した。〔…〕いつでも射てるぞといわんばかりに、ずっと右手に持ちつづけていた)。それにしても、きみも奇妙な人だな、キリーロフ君。あのばかな男がこういう最後になるしかないことは、きみ自身承知していたでしょう。見抜くも何もありやしない。ぼくだって何度かきみに噛んで含めるように説明したことですよ。〔…〕』
『黙れ! きさまが彼を殺ったのは、ジュネーヴで彼から唾を吐きかけられたからだ!』
『それもあるし、ほかのこともある。ほかにもいろいろとね。もっとも、感情抜きでやったことですよ。〔…〕』」
江川卓・訳『悪霊』,下,新潮文庫,pp.518-519.
ここで、キリーロフも、すでに用意していた自分のピストルを取り上げ、二人は銃口を向け合って対峙する。しかし、どちらも発射しないまま銃を下ろす。
「キリーロフはテーブルの上へピストルを置いて、前へ後へ歩きはじめた。
『ぼくは、シャートフを殺したとは書かない、いや……いまは何も書かない。遺書なんか書かない!』
『書かない?』
『書かない』
『なんて卑劣なことだ、なんてばかげたことだ!』ピョートルは怒りに真っ青になった。『もっとも、どうせそんなことだろうとは思ってましたよ。べつに不意打ちでも何でもない。〔…〕きみはあのとき、ぼくらに金を無心して、やたらと約束したもんじゃないですか……〔…〕』
『きさまには、すぐ出ていってもらいたい』キリーロフは彼の前にぴたりと足を止めた。
『いや、そうはいかない』ピョートルはふたたびピストルを手にした。『〔…〕もしきみが臆病風を吹かして、あの決意を延ばしたりするようだったら、あのシャートフの悪党と同じように、このピストルできみの脳天をぶち割るまでは、ここから出ていきゃしないですよ、畜生!』」
『悪霊』,下,pp.518-521.
ピョートルが、「ぼくらに金を無心」うんぬんと言っているのは、事実かどうかわかりません。ありもしない出まかせを、でっち上げているようにも見えます。このほか、彼は、あらゆる巧妙な歪曲や欺罔をつぎつぎに言い立てて、キリーロフを脅し、なだめ、おだて上げ、彼の口述する通りに“遺書”を書いて、自刹するよう仕向けるのです。
ところが、キリーロフの部屋の片隅には、小さなキリスト像が置かれ、なんと燈明まで点されていました。
キリーロフは、無神論者ではないのかもしれません。むしろ、信仰が異常なほど深く、「神」に日夜苦しめられるからこそ、宗教と「神」を克服しようとしているようにも思われてきます。
「『ぼくは自分の不信を宣言する義務がある』キリーロフは部屋を歩きまわった。『ぼくにとって、神がないという思想以上に高いものはない。〔…〕人間がしてきたことといえば、自分を殺さず生きていけるように、神を考え出すことにつきた。これまでの世界史はそれだけのことだった。ぼくひとりが、世界史上はじめて、神を考え出そうとしない。永遠に記憶にとどめるがいい』
〔…〕
『だれもが記憶にとどめるのだ。だれもが知るのだ。顕るるためならで、隠るるものなし〔マルコ福音書 4:22 隠れたところでの行ないが、いつの間にか現れて、人々に光明をもたらすこと。―――訳者注〕。これはあの人の言葉だ』
そう言うと彼は、熱に浮かされたような歓喜の面持で、救世主の聖像を指さした。その前には燈明がともっていた。ピョートルはすっかり怒ってしまった。
『すると、きみはまだあの人〔キリスト――ギトン注〕を信じていて、燈明なんぞともしているんですか〔…〕』
『〔…〕聞きたまえ』キリーロフは足を止め、じっと動かぬ、狂信的な眼差しで、前方を見据えた。『偉大な思想を聞きたまえ。〔…〕』」
『悪霊』,下,pp.530-531.
キリーロフは、キリストは処刑されて死んだあと、「天国も復活も見いだすことができなかった。」という話をします。
「『いいかね、この人は地上における最高の人間で、この大地の存在の目的をなすほどの人だった。全地球が、その上のいっさいを含めて、この人なしには、狂気そのものでしかないほどだった。後にも先にも、これほどの人物はついに現われなかったし、奇蹟とも言えるほどだった。〔…〕ところで、もしそうなら、つまり自然の法則が〔…〕この人をも虚偽のうちに生き、虚偽のうちに死なしめたとするなら、当然、全地球が虚偽であって、虚偽の上に、愚かな嘲笑の上にこそ成り立っているということになる。つまりは、この地球の法則そのものが虚偽であり、悪魔の茶番劇だということになる。なんのために生きるのか、きみが人間であるなら、答えてみたまえ』
〔…〕
『〔…〕さあ、これでわかったろう、万人にとっての救いは一つ――この思想を万人に証明することにこそあることが。だれが証明する? ぼくだ! 〔…〕
神がないことを知りながら、同時に自身が神になったことを意識しないのは――不条理そのものだ〔…〕もし意識すれば――きみは皇帝で、もはや自分を殺すどころか、最大の栄光のうちに生きればよい。しかし一人は、つまり最初の一人は、どうあっても自分で自分を殺してみせなければならない。でなければ、だれがそれをはじめ、だれが証明するんだ。ぼくがどうあっても自分で自分を殺すのは、それをはじめ、それを証明するためなんだ。 〔…〕
ぼくは自分ではじめ、自分で結末をつけ、扉を開いてやるのだ。そして救ってやるのだ。このことだけがすべての人を救い、つぎの世代を肉体的に生れ変らせることができる方法なんだ。〔…〕ぼくが自刹するのは、ぼくの不服従と新しい恐ろしい自由を示そうためなんだ。』」
『悪霊』,下,pp.531-533.
キリーロフは、自分がキリストになったかのようです。彼は、自分が「最初の一人」として、“死の恐怖”を乗り越えて自刹することによって、「神がないこと」を全人類に示し、こうして全人類を“生と死の恐怖”から救うことになる。だから、彼は、自刹することによって救世主になる、つまり、「神」になる。彼によって“模範”を示された全人類もまた、「つぎの世代」からは肉体的に変化し、「神」となる。
どうやら、キリーロフは、自分の自刹を、そのように意義づけているのです。
ここまで喋った時に、キリーロフは、突然、ピョートルの指示通りに遺書を書いて自刹することを受け入れます。
「彼の顔色は不自然なほど青白く、彼の目は耐えがたいほど重苦しかった。〔…〕
『ペンをよこせ!』ふいにキリーロフが強く霊感に打たれでもしたように、まったく思いがけなく叫んだ。『口述したまえ、なんでも書いてやる。シャートフを殺したとも書いてやる。おれが滑稽がっているうちに、口述するがいい。高慢ちきな奴隷の思想なんぞ恐くないぞ! 隠れたるものがすべて顕われることが、きさまにもわかるだろうさ! それできさまは圧(お)しつぶされるんだ……信ずるぞ! おれは信ずるぞ!』
ピョートルはさっと躍りあがって、あっという間にインク壺と紙を手渡し、この機会をのがすまいと、成功を念じておののきながら、口述にとりかかった。
〔…〕
『「余、アレクセイ・キリーロフは、」』ピョートルはキリーロフの肩口にかがみこんで、彼が興奮にふるえる手で記していく一字一字を注視しながら、しっかりした命令的な口調で口述した。『「余、キリーロフは、宣言する。本日、10月×日、夕刻、7時過ぎ、大学生シャートフを、その裏切りのゆえに、公園において、殺害せり。〔…〕」』」
『悪霊』,下,pp.534-535.
ピョートルの口述する通りの遺書をしたためたあと、キリーロフは、ピストルを持って隣室に閉じこもった。しかし、ピョートルがいくら待っていても、キリーロフの自決の銃声は聞こえなかった。物音一つしなかった。
いまなら、彼を射殺しても、後で発見した者は自殺だと思うだろう。そう考えて、ピョートルが隣室に入ってみると、そこは真暗だった。キリーロフは、物陰に隠れるかのように、「まるで蝋人形ででもあるかのように、ぴくりとも動」かず、真青な顔で佇立していた。ピョートルが近づくと、キリーロフは、いきなり彼の手に噛みついてきた。
「ようやくのことで彼〔ピョートル――ギトン注〕は指をもぎ放すと、暗闇の中を手で探りながら、後も見ずに外へ駆けだした。その後を追って、恐ろしい叫び声が部屋の中からとんできた。
『いますぐ、いますぐ、いますぐ、いますぐ……』
10度ほども立てつづけだった。しかし彼はいっさんに走りつづけ、もう玄関口まで走り出たとき、ふいに高らかな銃声が聞えた。」
『悪霊』,下,p.543.
ピョートルが部屋の中に戻ると、キリーロフの死体があった。
「弾丸は右のこめかみに射ちこまれ、頭蓋骨を貫通して、左の上端から抜けていた。血と脳味噌のしぶきが散っていた。ピストルは床の上に投げ出された自刹者の手に握られていた。」
『悪霊』,下,p.544.
ピョートルは、キリーロフの遺書が、テーブルの上にそのまま置いてあるのを確かめたあと、火のついた蝋燭をその傍らに立て、ひとりで遺書を書いてから自決したように見せかけ、足音を忍ばせて立ち去った。
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]



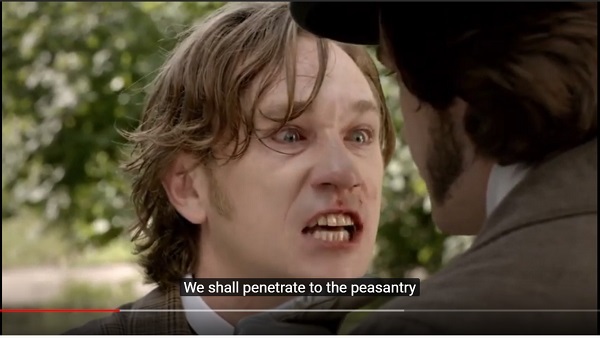







 彡
彡