04/06�̓��L
06�F15
�y�{���z���Ɖ_�Ɣg�̂����\�\�\�w���Ǝ��l�x(4)
---------------
.
 �@
�@
�ɗnjΒ����o�@�@�@
�@������ (º.-)���
�@�{���̓��b���i�w���Ǝ��l�x���Ƃ肠���Ă��܂��F
�@���Ɖ_�Ɣg�̂����\�\�\�w���Ǝ��l�x(1)
�@���Ɖ_�Ɣg�̂����\�\�\�w���Ǝ��l�x(2)
�@���Ɖ_�Ɣg�̂����\�\�\�w���Ǝ��l�x(3)
�y�X�z�u���F�̃��[�g�s�A�v����
�@�O��̍Ō�Ɍ��������A���^���̌㔼�Q�s�F
�u�������̐��E�Ɋ��ӂׂ��܂��ƂƔ��Ƃ̖͌^������₪�Ă͐��E������ɂ��Ȃ͂��ނ阬���ҁA
�@�v�҃X�[���_�b�^�v
�@���ꂾ��������ƁA���������A�u�����ҁv�X�[���_�b�^�́A�l�ԂƂ��āA�����̐S�̒��Ŋ肤�����̐��E���\�\�\�u�܂��ƂƔ��Ƃ̖͌^�v�\�\�\����A���v�̓w�͂Ȃ�A�@���I�ȋ����ɂ���āA�u�₪�Ă͐��E������ɂ��Ȃ͂��ނ�v�d���E�𗝑z�ɋ߂Â��Ă䂭�Ƃ����A���[�g�s�A�v�z���q�ׂ��Ă���悤�ɁA����邩������܂���B
�@�������A�O��A�������ڂ��������������ʁA�����ł͂Ȃ����Ƃ����������Ǝv���܂��B�X�[���_�b�^�́u���v��ׂ��u�͌^�v�Ƃ́A
�u���������Љ_���䂶�g���炷���̂����v
�@�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��B�����āA�u�܂��ƂƔ��Ƃ̖͌^�v�Ƃ́A
�u���������Ȃ炤�Ǝv�З��n���������ӌ`���Ƃ炤���S�傷��v
�@�g���R�E�h�̖����̎p���A�s���Ƃt�ɂ���ĕ\�������̂ɂق��Ȃ�܂���B���Ȃ킿�A�X�[���_�b�^������悤���߂��Ă���u�������̐��E�v�̑��́A�l�Ԃ̍l�������[�g�s�A�◝�z���E�ł͂Ȃ��A�g���R�h���g�̈ӎv�Ɓu�o��v���������āA������u�������v�ɂ������̂łȂ̂ł��B
�@�{�����������w�����̑��������X�E�L�����x�ɂ́A���̂悤�ȉӏ�������܂��F
�u🈔�@�����͐V�����A���悢���E�̍\���ޗ�����₤�Ƃ͂���B����ǂ�����͑S���A��҂ɖ��m�Ȑ₦����x�قɒl�������E���g�̔��W�ł����������b�`�ɟ��˂�����ꂽ���F�̃��[�g�s�A�ł͂Ȃ��B�v
�@�܂�A�����́A���[�g�s�A�I�Ȏv�z�\�\�\���̂Ȃ��ɂ́A�l�ނ̖����������Љ��`�A���Y��`�͂��Ƃ��A�u�ϓc���v�̂悤�ȕ��ÓI���z���f�����k��P��̔_�{��`�v�z���܂܂�邩������܂���\�\�\�ɑ��āA�x��������Ă����悤�Ɏv���܂��B�u�b�`�ɝs�˂�����ꂽ���F�̃��[�g�s�A�v�Ƃ́A���[�g�s�A�v�z���ׂĂł͂Ȃ���������܂��A���Ȃ��Ƃ��A���[�g�s�A�ɑ���y�V�I�ȓ��ꂩ��́A�����́A�قlj����ʒu�ɂ����ƌ�����ł��傤�B
�@�����炭�A�����̂��������l���́A�w���Ǝ��l�x���A���^��������킩��悤�ɁA�g���R�h�̋������A�l�ނ��⏬����[�����o���������v�z�Ɋ�Ă���Ǝv���܂��B�����ɂ����g���R�h�Ƃ́A�l�ԂƂ���������������Ă���g���R�h���܂݂܂��B�܂�A���|�A���K�~�A���͗~�A�U�����Ƃ������A�����̍l���郆�[�g�s�A��W���邩������Ȃ��������ł��B
�@�l�Ԃ������ōl���o�������[�g�s�A�́A�g���Ɖ_�Ɣg�̂����h�ɑR��������̂ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�l�Ԏ��g�����́g���R�h�̈ꕔ���ɂ����Ȃ��̂�����B�\�\�\�����̔��z�́A����Ɍ����A�����������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B
�y10�z�g���h�́A�N�̂��̂ł��Ȃ�
�@�j�����^�́g�h�ɐ���ꂽ�A���^�̎v�z�����̂悤�Ȃ��̂��Ƃ���ƁA�X�[���_�b�^�ɏ]�����т��A�Ԃɏ悹�čՂ�グ�Ă������̐l�тƂ̔F���A�܂��]���ėL���V�ɂȂ��Ă����X�[���_�b�^�̔F���́A����Ƃ͑傫�ȊJ��������܂��B�Ƃ����̂́A�ނ�̍l����Ƃ���ł́A�g���h�Ƃ́A�l�Ԃ̑n��o�����́d�d����ǂ��납�A�l�Ԃ̂Ȃ��ł����ʂȁA�g���l�h�Ƃ����g�I�ꂽ�l�h�̐��ݏo�����̂�����ł��B
�@�������ɁA�A���^���ɂ��A���l����ʂȐl�ƌ��Ȃ��l�����Ȃ��킯�ł͂���܂���B�X�[���_�b�^���A�u�����ҁv�u�v�ҁv�ƌĂ�ł��邩��ł��B�������A�X�[���_�b�^�́u�����v���A���Ɖ_�Ɣg�́u�����v���Ƃ��ās���Ƃt�ɂ��ĉ̂����̂��Ƃ���A����́g���l�h�Ƃ����l�������̂ł��邩������܂���B
�@�A���^�̋C�����]���ɂ�������炸�A�X�[���_�b�^���g�́A�g���h���l�̎蕿�Ƃ݂Ȃ������펯�ɂƂ���Ă����̂ł��B����䂦�ɁA�����́u�����v�́g���l�́h�������u�ʂ��ݕ��v���������ނ��Ƃ̔����т�����₢�Ȃ�A���������A�Ƃ��Ă�������Ȃ��߂�Ƃ������̂悤�ȍ߈����ɂƂ���Ă��܂��̂ł��B
�u�i���h���ׂ����l�A���^�ɍK����A
�@�X�[���_�b�^��A���̂��������͂킽���̂����łЂƂ������܂ւ̂����ł���B���������킽���͂��̓��ɋ��Ă��������̂ł��邩�l�ւ��̂ł��邩�B���܂ւ͂��̓��̏�ɂ�Ă�������̂ł��邩�l�ւ��̂ł��邩�B���T�X�[���_�b�^�B
�@���̂Ƃ��킽���͉_�ł��蕗�ł������B�����Ă��܂ւ��_�ł��蕗�ł������B���l�A���^���������̂Ƃ��ɖ��z������炭���������������������ł��炤�B����ǂ��X�[���_�b�^��B�A���^�̌�Ƃ��܂ւ̌�͂ЂƂ����Ȃ��A���܂ւ̌�Ƃ킽���̌�͂ЂƂ����Ȃ��C�����炭�����ł���B���̌̂ɂ������̉̂����͂��܂ւ̂����ł܂������̉_�ƕ��Ƃ��䂷�镪�̂��̐��_�̂����ł���B�j
�i���T����B����Ȃ�킽���͋����ꂽ�̂��B�j
�i�N�������ĒN���������̂ł��炤�B���炪�ЂƂ������ł܂��_�Ő��ł���Ƃ��ӂ̂ɁB�k�c�l�v
�@�X�[���_�b�^�����A���^����`���������`���[�i�^���́A
�u���̂��������͂킽���̂����łЂƂ������܂ւ̂����ł���B�v
�@�ƌ����āA�܂��A�g���h�ƍ�Ҍl�Ƃ̌��т���ے肵�܂��F
�u���������킽���͂��̓��ɋ��Ă��������̂ł��邩�l�ւ��̂ł��邩�B���܂ւ͂��̓��̏�ɂ�Ă�������̂ł��邩�l�ւ��̂ł��邩�B���T�X�[���_�b�^�B
�@���̂Ƃ��킽���͉_�ł��蕗�ł������B�����Ă��܂ւ��_�ł��蕗�ł������B�v
�u�N�������ĒN���������̂ł��炤�B���炪�ЂƂ������ł܂��_�Ő��ł���Ƃ��ӂ̂ɁB�v
�@�`���[�i�^�́A�X�[���_�b�^���u�������₤�ȟ�������v���́u�����v���������̂������Ƃ��A�ے肵�Ă͂��܂���B�̂����̂łȂ��Ƃ��Ă��A�u�l�ւ��v�B�����āA���̍l�����A�u���̏�v�ɂ����X�[���_�b�^�ɂ������̂�������܂���B
�@�������A�u���̂Ƃ��킽���͉_�ł��蕗�ł������B�����Ă��܂ւ��_�ł��蕗�ł������B�v�\�\�\�u�����v�������Ƃ��A�`���[�i�^���A�X�[���_�b�^���A�u�_�v�Ɓu���v�A���Ȃ킿�g���R�E�h�̈ꕔ�ł������A�Ƃ����̂ł��B�g���h�̃C���X�s���[�V�������鎞�A�l�͎��R�E�̈ꕔ�ƂȂ��Ă���B����́A�g���R�h����̃C���X�s���[�V���������߂āA�l���u���z�v�ɒ��������Ƃ��ł���B�`���[�i�^���な�ɑ����āA���̂悤�Ɍ����Ă��邱�Ƃ���킩��܂��F
�u���l�A���^���������̂Ƃ������z��������炭���������������������ł��炤�B�v
�@��������ƁA�u���v��u�_�v��u�g�v����́u�����v�̎����́A�����̉S���u�����v���g�����Ƃ�h�Ƃ����̂Ƃ́A�����Ⴄ���Ƃ��킩��܂��B�u���v��u�_�v����g�����Ƃ�h�Ƃ������́A���炪�u���v��u�_�v�̈ꕔ�ƂȂ��Ă���̂ł��B
�@�A���^���ł́A���E�_�E�g�́u�����v���u���U���ɂ����Ӂv�������\�\�\���R���̉S���u�����v���Ƃ��ĉ̂��̂��A�����Ƃ�ȊO�̕��@�ʼn̂��̂��́A������Ă��܂���ł����B���܁A�`���[�i�^�����炩�ɂ���Ƃ���ɂ��A����́g�����Ƃ�h�̂ł͂Ȃ��A���炪�u�_�ł��蕗�ł��v�邪�䂦�ɁA�Ƃ��Ɂu�����Ӂv���Ƃ��ł����̂ł��B
�@
�@�������A�`���[�i�^���́A�Â��āA���̂悤�ɂ������܂��F
�u����ǂ��X�[���_�b�^��B�A���^�̌�Ƃ��܂ւ̌�͂ЂƂ����Ȃ��A���܂ւ̌�Ƃ킽���̌�͂ЂƂ����Ȃ��A�C�����炭�����ł���B���̌̂ɂ������̉̂����͂��܂ւ̂����ł܂������̉_�ƕ��Ƃ��䂷�镪�̂��̐��_�̂����ł���B�v
�@�u���v��u�_�v�ƂȂ�A�g���R���h�̈ꕔ�ƂȂ��ĉ̂����Ƃ��Ă��A�l�Ԃ́u�����v�́A�s���Ƃt�Ƃ��Ėa���o����܂��B�s���Ƃt�́A�Ӗ������łȂ��g���h�������Ă��܂��B�l�Ԃ́u�����v�́A�l���ƂɈقȂ�g���h�́u��v�ƁA�قȂ�u�C�v�������ĉ̂��o�����̂ł��B�����ɁA�g���h�ƍ�Ҍl�Ƃ̌��т�������܂��B
�@�u�C�v�Ƃ́A�����́g���h�̂����A���q���������������ł��B���Ƃ��A�u�N(nián)�v�Ȃ�Aián ���u�C�v�ł��B�����ł́A�s�i�u��v�j�̍Ō�̎��́u�C�v�����킹�āu�r�C�v�Ƃ��܂��B���Ƃ��i���p�u�����锑�v�j�F
�u�����G�e�����V(tiān) �@�������G�e���ā@���V�ɖ���
�@�]�����ΑΏD��(mián) �@�]�����@�D���ɑ��v
�@�u�V�v�Ɓu���v�������u-ian�v�ŁA�r�C�ɂȂ��Ă��܂��iā �� á �́A����ɂ͓��������ł����j�B
�@�����Ƃ��A���̂��Ƃ�
�u���̌̂ɂ������̉̂����́c�c�܂������̉_�ƕ��Ƃ��䂷�镪�̂��̐��_�̂����ł���B�v
�@�̕����͓���ł��B�u���̐��_�v�Ƃ́A�u�����v���u�_�ƕ��Ƃ��䂷��v�Ƃ���́u�����v�̐��_�Ȃ̂��H ����Ƃ��A�u�_�ƕ��v�ɂق��Ȃ�Ȃ��u�����v���u�䂷��v�A�u�����v�Ƃ͕ʂ̐��_�Ȃ̂��H
�@�����炭��҂ł��傤�B�X�[���_�b�^���u�����̋����v�Ŕ�I�����u�����v�́A�X�[���_�b�^�l�́u�����v�ł���Ɠ����ɁA�X�[���_�b�^�����A�`���[�i�^�����ӂ��ށu�_�ƕ��v���ׂĂɑ��āA�u�䂷��v�͂��y�ڂ��Ă���u���_�v�́u�����v���Ƃ����̂ł��B
�@�����ł����u���_�v�Ƃ́A���ł��傤���H ���Ắg�����������h�ł́A�����̐l���A���������u���_�v�����̉����āA�g�F�����_�h�ł���Ƃ��g�F���ӎu�h�ł���Ƃ������āA��Ԃ낵�����L���Ă݂���̂���ł����B�������A���ꂪ�{���̖{�ӂɂ��Ȃ��Ă���Ƃ͎v���܂���B���������X���́A���ł��Ȃ��e�N�X�g�̂͂����ɁA�Ȃɂ��ƂĂ��Ȃ��N�w��ǂݍ���ŁA������V���@���̋��c�ɍՂ�グ�Ă��܂��܂��B
�@���Ƃ��A�����ɑ���l�����ł��A��������{�ł́A���ł�����ł����̎����čՂ�グ�Ă��܂��X��������悤�ł��F
�u�������̂Ȃ��ɂ́A�N�������܂�Ȃ���ɁA�@���َ̑����h���Ă��āA����́w��������S�x�Ƃ���B�Ȃ�牘��Ȃ��S�̈Ӗ����B�k�c�l�㐢�ł́A�w�����x�Ƃ���ꂽ�B
�@���́A���̎�������S���A�����܂ʼn\���ƌ��邩�H�A���̂ƌ��邩�H�@�ɂ���B�k�c�l���̐��ɁA�_�͂��Ƃ��A��������̂�F�߂Ȃ������̍��{�I�ȗ��ꂩ�炷��A��������S�����̂ƌ���@�����v�z�͔ᔻ����Ă��A��ނ����Ȃ��B
�@�Ƃ��낪�A����������{�ɂ���ԓ��A�W�A�̕������ł́A��������S�����̂ƌ���@�����v�z�́A�ނ���嗬�h�̒n�ʂ��B�k�c�l
�@���A�W�A�����ł́A�X�����ۂǂ��납�A�{���C���h�ł́w�[���x���Ӗ����Ă����w���k�����l�x��������̉�����A��Ƃ�����̌�����̈悪���݂���Ƃ݂Ȃ��ꂽ�B�����āA�����ɓ���A�Z�����邱�Ƃ����A���̎����ɂق��Ȃ�Ȃ��ƍl����ꂽ�̂ł���B�v
�V�V�ޓ�Y�E���ҁw�{�V�����C�[�n�g���w���T�x,2010,�O����,p.450.
�@�`���[�i�^���̕\���ɂ���u�䂷�镪�̂��̐��_�v�Ƃ́A�A���^�̌����u���������Ȃ炤�Ǝv�З��n���������ӌ`���Ƃ炤���S�傷��v���R�E�́u�������v�̂Ȃ��ӎv�ƁA�������̂��ƍl���Ă͂ǂ��ł��傤���H �܂�A�X�[���_�b�^�́u�����v�́A�������ɔޓƎ��́u��v�Ɓu�C�v�����݂���ꂽ�ނ́u�����v�Ȃ̂ł����A���̂��Ƃ����ǂ�A�u�_�v�Ɓu���v�Ɓu�g�v�̉��Ɋ܂܂�Ă���A�g���R�E�h�̈ӎv�̌���ɂق��Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B���̈ӎv���A�L���X�g���̐l�i�_�̂悤�Ɏ��̉��A���݉����čl����K�v�͂���܂���B����ɁA�g���������X��������h�ƍl����悢�̂ł��B
�@�`���[�i�^�̂����ł̎�ӂ́A�X�[���_�b�^�̉̂����u�����v�́A�ތl�̍�������܂ꂽ�ގ��g�̂��̂ł���Ɠ����ɁA�N�̂��̂ł��Ȃ��g���R�h�̃C���X�s���[�V�����̌`�ۉ��ł���A���ꂪ�s���Ƃt�Ƃ��Č`�ɂȂ������̂ɂق��Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�y11�z�N�ł����u���l�v�ł���
�@���̓��b�̑薼�w���Ǝ��l�x�́u���l�v�Ƃ́A�N���w���Ă���̂ł��傤���H �o��l���́u�`���[�i�^���v�Ɓu�X�[���_�b�^�v�̂Q���ł��邱�Ƃ��猾���ƁA�u���l�v�Ƃ́A�X�[���_�b�^�̂��Ƃ��Ƃ��l�����܂��B���������A���̓��b�ɂ��ď����ꂽ�_���ɂ́A�݂Ȃ��������Ă���܂��B�Ƃ��낪�A���̃e�N�X�g�̒��ŁA��҂́A��x���X�[���_�b�^���u���l�v�Ƃ͌Ă�ł��Ȃ��̂ł��B
�@�u���l�v�Ƃ́A�A���^�̂��Ƃł��傤���H �������l�����Ȃ��͂���܂���B�������ɁA�A���^�́A�u������̂����l�v�u�Â����l�v�ƌĂ�Ă��܂��B�������A�A���^�́A�X�[���_�b�^�̘b�̒��ɂ����o�Ă���l���ŁA��v�Ȗ����͂����܂ł��A�`���[�i�^�ƃX�[���_�b�^�̂Q���Ȃ̂ł��B
�@�u���l�v�Ƃ����A�`���[�i�^�����u���l�v�ƌĂ��ɂӂ��킵����������܂���B�X�[���_�b�^�́u�����v�́A���A�̒��Ń`���[�i�^���Ⴖ���u�����v���č�����̂�������Ȃ����A�`���[�i�^�Ɠ����ɃC���X�s���[�V�������ĕ����̂�������܂���B������ɂ���A�`���[�i�^���܂��u�����v������Ă���̂ł��B�����āA�X�[���_�b�^�́A�`���[�i�^�̌��ɂ���āg���h�ɑ���l�������������A����J�����̂ł��B
�@�X�[���_�b�^�́A�`���[�i�^�Ɍ����āF
�u���̂��������̂��̂������Ԃׂ��킪�t�̗���B�v
�@�ƌ����Ă��܂��B�u���l�v�Ƃ̓`���[�i�^�̂��Ƃ��Ƃ���ƁA�薼�́w���Ǝ��l�x�́A�u���v�u���l�v�Ƃ����Q�l�̐l������ׂĂ���̂ł͂Ȃ��A�u���v�ł���Ɠ����Ɂu���l�v�ł���`���[�i�^���w���Ă���A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B���邢�́A�ЂƂ�́u���v�ɂ���ĕ\�����ꂽ�u���l�v�Ƃ������̖̂{���A�Ƃ������̍�i�̃A���S���J���Ȑ��i�������\���Ă��邩������܂���B�Ƃ����̂́A���̂悤�ɍl�����邩��ł��F
�@�`���[�i�^�́A�Ȃ����A�ɗH����Ă���̂ł��傤���H �������ɁA����̂����Ƃ��ẮA�ނ����l�X�ɍЂ��������炵�����߂ɁA���Ƃ��ėH���ꂽ�̂��Ƃ���Ă��܂��B
�u�킽���͐�N�̐̂͂��߂ĕ��Ɖ_�Ƃ��Ƃ��Ȃ̗͂����݂邽�߂ɐl�X�̕s�K��҂������߂ɗ����́Q�Q�Q�Q�k���������E�T���t���l����\�ݔN���̌A�ɕ������ė��Ɛ��Ƃ̋��������点��ꂽ�̂��B�v
�@�������A�����̂悤�Ȏ���́A���̕���̂��Ƃ̂ق��ŏ��߂Č����̂ł��B����̍ŏ��ɂ́F
�u�k�c�l����͂������o�čs���Ȃ��B���̓��̊O�̊C�ɒʂ��錄�Ԃ͐h�����O���̂������Ƃ��ł���ɉ߂��ʁB�j
�@�i�������A�������B�킽���̍߂������킽�����̎�����������������B�j�v
�@�Ƃ���������Ă��܂���B�u�߁v�u��(�̂낢)�v�ƌ��������ŁA���̎��͕̂s���Ȃ̂ł��B
�@�u���v�����A�ɕ����߂��Ă���̂́A�H��́w���x�ɂ͂Ȃ��A�{���Ǝ��̐ݒ�ł��B���g�͉������Ƃ̂ł��Ȃ����������ē��A�ɗH���ꂽ���́A�g���l�h�Ƃ������̂̑��݂̂��������A�悭�\���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H ���A�̒��̗��́A�킸���ȁu���ԁv��ʂ��āA�O�̐��E�����邱�Ƃ��ł��܂��B�O�ɂ���X�[���_�b�^�̂悤�ɁA���R�ɑ���������A�������܂ōL����C�߂��肷�邱�Ƃ͂ł��܂���B�������A���ꂾ���炱���A����ڂ���˂����ޗz�̌������ꍏ�ƕω����邳�܂��A���܂���Ȃ��ł͂����Ȃ��̂ł��B
�@�O�̐��E���щ�邱�Ƃ��ł��Ȃ����炱���A�g���h�Ƃ����������ŁA�O�̐��E�̎p���u�͌^�v�ɍ��グ�Ȃ��ł͂����Ȃ��̂ł��B�����āA�g���h�����������Ƃɂ���āA���́A���̎��ɂ����A�O�̐��E��V�Ă���u�_�ł��蕗�ł������v�̂ł��B
�@����́g���l�h�̃A���S���[�ł���ƂƂ��ɁA�P�Ȃ�g���l�h�ł��邱�Ƃ������āA�l�ԑ��݈�ʂ̃A���S���[�ł���̂�������܂���B
 �@
�@
�@�������A�{���́A���������g���l�h�Ȃ����g�|�p�Ɓh�Ƃ������ʂȎ��i��ے肵�܂��B�����̋��ɂ̍l���ł́A���ׂĂ̐l�Ԃ��g���l�h�ł���g�|�p�Ɓh�ł��肤��̂ł��F
�u�_���|�p�̎Y��
�@�c�c����̂Ȃ��Ō|�p�ƂƂ͂ǂ����ӂ��Ƃ��Ӗ����邩�c�c
�@�@�@�E�ƌ|�p�Ƃ͈�x�S�т˂Ȃ��
�@�@�@�N�l���݂Ȍ|�p�Ƃ��銴����Ȃ�
�@�@�@���̗D�����ʂɉ��Ċe�X�~�ނȂ��\�����Ȃ�
�@�@�@�R���߂��߂����̂Ƃ��ǂ��̌|�p�Ƃł���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�@�@�n��~�߂Δނ͂ӂ����ѓy�ɋN�v
�u���@���ƌ|�p�ƂƂ͐^�P�Ⴍ�͔���Ɛ肵���k���l����̂ł���
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@����ɍw�ӂׂ��ɂ��Ȃ��܂�������̂�K�v�Ƃ���
�@���܂����͐V�ɐ����������s���@����̔����Αn��˂Ȃ��
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�_���敱�З��Ă����Ă���́\�\�̕\�������āv
�@�u���l�v�Ƃ́A����ł��̂��Ƃł���B�Ȃ��Ȃ�A�g���h�Ƃ́A�u�_�v��u���v��u�g�v����슴���A�����̈ꕔ�ƂȂ�A�g���R���h�̈ꕔ�Ƃ��āu�����Ӂv���Ƃɂق��Ȃ�Ȃ�����B���������\�͂́A�N�����L���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�l�Ԃ́g���R�h�̈ꕔ�Ȃ̂�����B���Ȃ킿�A�E�Ǝ��l�������g���l�h�ł͂Ȃ��B����ނ���A���i�Ƃ��Ă̌|�p�̐���ɖv�����āA�{���̌|�p��Y��Ă��܂����u�E�ƌ|�p�Ƃ͈�x�S�т˂Ȃ�ʁv�B
�@�\�\�\���̂悤�ȍl�����́A�����̐���������ɂ́A�ߌ�����܂�Ȃ��ُ�Ȏv�z��������������܂��A�l�b�g�ɑf�l�����Ƃ�f�l��Ƃ����ӂ�Ă��鍡���̎���ɂ����ẮA����قNjɒ[�ȍl���ɂ͌����܂���B
�@���������킯�ŁA
�u���炪�ЂƂ������ł܂��_�Ő��ł���Ƃ��ӂ̂ɁB�v
�@�����̃`���[�i�^�̌����A�X�[���_�b�^�ƂQ�l�̂��Ƃ����������Ă���̂ł͂Ȃ��A���悻�l�͒N�������ɂ��_�ɂ����ɂ��Ȃ肤��A�����̈ꕔ�ƂȂ��āu�����v���̂����Ƃ��ł���̂��\�\�\�ƌ����Ă���̂��Ǝv���܂��B
�y12�z����������f�����u���v
�u�k�c�l�X�[���_�b�^��
�@�����킽�������O�ɏo�邱�Ƃ��ł����܂ւ�����ʂȂ�킽���͂��܂ւ�����܂����������̂ł��邪���܂͂��ꂪ�ł��Ȃ��̂ł킽���͂킽���̏����ȑ������������₤�B���T�Ɏ���̂��B�j���͈�������ȐԂ�����f�����B���̂Ȃ��Ŋ̉�R�����B�i���̎�͖����ꂽ���S�����Â˂ɊC�ɂ͂���Ƃ�������̂ł���j�v
�@�����ŁA�`���[�i�^�́A�u�����ȐԂ���(����)�v��f���o���āA���A�̊�̊���ڂ���A�X�[���_�b�^�ɗ^����̂ł����A���́u�Ԃ���v�̓o��ŁA����́A�V���Ȓi�K�ɓ���܂��B�������A�܂�����Ȃ��̂́A���́u�Ԃ���v�́A���Ȃ̂��Ƃ������Ƃł��B
�@�����ɂ́A�u������v�܂��́u�@�ӕ��v�Ƃ������̂�����܂��B�n����F�A�@�ӗ֊ω��A�g�˓V�Ȃǂ̕�������Ɏ����Ă���ʂł��B���������Ă��邱�Ƃ�����܂��i���摜�Q�Ɓj�B

�o���}�i���m�� ����~��j

�n����F���i���R�j
�@�����ɂ́A���̂悤�ɐ�������Ă��܂��F
�܂Ɂy����z
�@ �ʁB�_��I�ȗ͂����ʁB�����B������B
�A �������邢�͖���̔]���ɂ���Ƃ��A���̍��̕ω��������̂Ƃ�������ʁB�����ǂ�Ȋ肢�����Ȃ��Ƃ����B�@�ӕ��B
�܂Ɂy����z[����]
�@ ��ʂ̑��́B��������A�����܂��铿������Ƃ�����B�����B������B�����B
�A �@�ӕ��̂��ƁB�����̔]������o���ȂǂƂ�������ŁA�肤���Ƃ͂Ȃ�ł����Ȃ������Ƃ�����B
�@�A�̂ق��̈Ӗ����A���ɊW���Ă������ł��B
�@�������A����̎ʐ^�ł킩��悤�ɁA�u������v�́A�Ԃ��͂���܂��A���ʼn��R���Ă���킯�ł�����܂���B�o�T�����߂Ă䂭�Ƃ��Ɏg����Ƃ������Ƃ�����܂���B
�@�������A���T�ł́A�u������v�u�@�ӕ��v�́A�����ς火���̂悤�ȕ����Ŏg����炵���̂ł��F
�u�������Z�����Ō��F�w�����I�����S�ŗP�@�����C�]�����A㾎�V�g�H�x
�@�ō����Z�F�w栔@�L�l�n���C�s�\���Z�C���R值���@�ӛ����B�ސl���쎷�߁C�����@�ӁC�����i�����V�r�i�C���B�́C���x����C���щ؉ʁC�}�t��T�C�\������C�y�P���������C�F���@�S�C���R����B
�@���Z�I�ޓ������A���F㾎㑬���j�ӗ��U�V�@�C�R��ސl�获�@�ӎ��C���R�����C�ޓ��َ��C���ŕs���B���Z�I�@���@�ӎ��C������j�C�I�s�ӁC�L�����\�C笈ӏ��O�C�F�����ʁB�@���C�@�������S�ŁC�P�@�����C����g�ҍ��s���S��B�x�v
�i�w�囏���S�x�ɑ�110, �u���쒷�Ҙ��v��39�V2.�j
�@����́A�u���v�Ƃ����l�Ɓu��(�u�b�_)�v�Ƃ̖ⓚ�ł��B���̒��ŁA�u�b�_��栂��b�����Ă��܂��B�n�����Ď����̐������ł��Ȃ��Ȃ����l���A�Ƃ���u�@�ӕ��v�ɏ��葘�����B�u���v����Ɏ������Ƃ���ɁA���ł���ɓ���悤�ɂȂ�A���s�ȉ��~�ɒr��z�R�A���x�Ə��A�T���Ɩ����X�ɉʕ��̎���뉀�����o�����B�Ƃ��낪�A�ˑR�ł������������@�́A����̂������A�������ɕ��ꂽ���ƂŁA�u���v���肩�痎���Ė����Ȃ��Ă��܂����B�������āA���������A���Ƃ̂������݂ɂȂ��Ă��܂����B
�@�܂�A�g�@�ӕ���h�Ƃ́A�g�������炵�ē������Ƃ����Ȃ��ŁA���y�ɕ��₨����h�Ƃ����A�ے�I�ȈӖ��Ɏg����悤�ł��B�������Ƃ���ƁA����́A�w���Ǝ��l�x�ŁA�u�����ꂽ���S�����Â˂ɊC�ɂ͂���Ƃ�������v�u�Ԃ���v�Ƃ́A�Ȃ���Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�u�Ԃ���v�ɂ��ẮA����ɁA�����ƕʂ̕��ʂ���A���̈Ӗ���T���Ă݂����Ǝv���܂��B
�@
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@

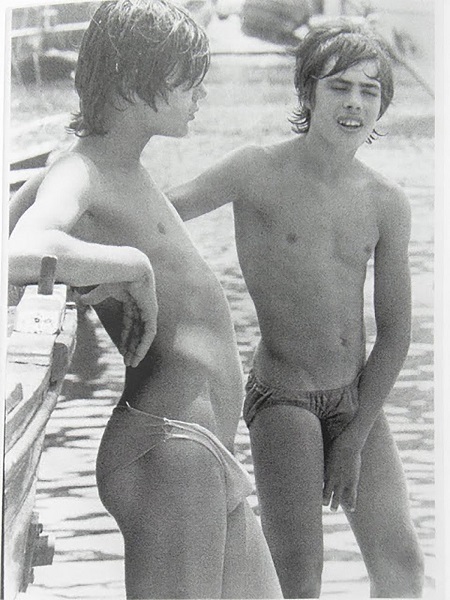
 �@
�@


 �c
�c