08/03の日記
01:23
【ユーラシア】フッサールと宮沢賢治―――宗教と科学の位置(2)
---------------
.
こんばんは。(º.-)☆ノ
前回の話の最初で、フッサールとメルロ=ポンティに関して、“上行の旅”“下行の旅”という言い方をしましたが、これも宮沢賢治の詩について示唆を与えるのではないかと思います。
というのは、これまでも折にふれて指摘しておいたのですが、『春と修羅』(第1集)のはじめに並んでいる諸篇では、東北の閉ざされた冬のなかから、まるで爆発するように起こってくる“春の胎動”が描かれているのと同時に、真白な雪におおわれた自然のなかを彷徨していた作者が、“人間の世界”・“まち”の世界へ戻って行こうとして、なかなかうまく戻れない。戻ろう、戻ろうとして、そのたびに障碍にぶつかって跳ね返される―――そんな状況を感じさせるのです。
『春と修羅』の最初の部分を、なんど読みかえしても、この“戻ろうとして跳ね返されている”ような印象が、ギトンにはいつも感じられるのです。それが何を意味するのか、はっきりとはわからないのですが‥
しかし、それは、作者が“上行の旅”の渦中にあるためだ‥‥と考えると、納得できるようにも思われます。そう考えれば、少なくとも一面の理解は得られそうな気がします。
具体的に詩篇を挙げて言いますと、
【1】「屈折率」、【2】「くらかけの雪」、【4】「丘の眩惑」―――これらで作者は、厚く雪の積もった野原を彷徨しています。日常的なデテールが隠された雪景色のなかで、家や道や畑などの日常生活になじみ深い部分は削ぎ落され、原初の“大地”の本質的な印象がクローズアップされてきます。「現象学的還元」をめざす“上行の旅”に、よく似ているとは言えないでしょうか?
【5】「カーバイト倉庫」では、作者は、雪の野山から出て来て、「まち」へ戻ろうとしています。ところが、作者が町の灯りだと思ったのは、近づいてみると、無人の工場倉庫ののきに吊るされた電球だったのです。日常的な“人の世界”に戻れると思った作者の期待は、裏切られます:
「まちなみのなつかしい灯とおもつで
いそいでわたくしは雪と蛇紋岩(サーペンタイン)との
山峡をでてきましたのに
これはカーバイト倉庫の軒
すきとほつてつめたい電燈です」
「カーバイト倉庫」より。
⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》1.5.1〜
【7】「ぬすびと」では、未明の町と郊外を彷徨してきた作者が、自分の家に戻って来ると、家の店さきに置かれた雨水受けの甕に、自分の長い影が差します。そのようすを見て、作者は自分の家に入って行けないような疑念にとらわれるのです。
作者には、自分が、その甕を盗みに来た泥棒のように感じられます:
「青じろい骸骨星座のよあけがた
凍えた泥の亂反射をわたり
店さきにひとつ置かれた
提婆のかめをぬすんだもの
にはかにもその長く黒い脚をやめ
二つの耳に二つの手をあて
電線のオルゴールを聽く」
「ぬすびと」
⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》1.7.1〜
「『提婆のかめ』──デーヴァダッタの厳しい戒律が象徴するように、父とも、この地方のマジョリティーとも異なる厳格な宗派に身を投じて、家の中では落ち着く場所さえなくなった作者は、自分の家にも入って行けない『ぬすびと』のような存在なのかもしれません。
そうした作者の影ぼうしが、『提婆のかめ』を運び去ってゆくような動きをしているのを、作者は眺め、
しかし、急に思い直したように、遠い南の地で、やはり家族との葛藤に悩んでいるであろう最愛の恋人からの通信に、じっと耳を澄ますのです‥ まるで、こころよいオルゴールの音(ね)を求めるかのように‥」
そして、上の2つの詩篇のあいだに置かれた【8】「コバルト山地」では、↓つぎのように、山野を離れて日常生活に戻っていても、なにかしっくりしないものを感じている作者のようすが映し出されています:
「コバルト山地の氷霧のなかで
あやしい朝の火が燃ゐてゐます
毛無森(けなしもり)のきり跡あたりの見當です
たしかにせいしんてきの白い火が
水より強くどしどしどしどし燃えてゐます」
「コバルト山地」
⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》1.6.1〜
“まち”に戻って、ふだんの世界の中にいても、やはり落ち着いて日常生活を送る状態ではないようです。胸の底から起きてくる衝動は、それ自体が、「水より強く燃える」「白い火」という非日常的な表現でしか表せないように感じられます。
雪の野山にいるときだけでなく、“まち”に戻ってからも、作者は“上行の旅”の渦中にいるのであり、“まち”にいる作者は、“上行の旅”の渦中にあることと、日常生活を送ることとの矛盾・葛藤のなかにいるのです。
数年前に、この同じ部分を論じたときには、ギトンは↓つぎのように書きました:
「厳しいけれども透明な雪景色の山中から下りてきた・この詩人は、人間界に入っていこうとして、その手前で無機質な電灯の下に停滞をよぎなくされたのでした。
しかし、身体の奥底から『どしどしどしどし』湧き上がる・にびいろの冬の太陽にも似た激情は、春の訪れと展開を予期させるに十分なものであったはずです。ところが──まるで、北国の春が幾度となく寒の戻りを繰り返しながら進行するように──作者は、夜明けの凍てついた街路で、遠方からの音に耳を澄ませたり病床の妹を打っちゃって朝の戸外を彷徨わなければならないほどの鬱を抱えているのです。
そしてその原因は、くだんの激情──つまり、なんらかの苦しい「恋」が原因であることが、おぼろげながらも示されてきたのでした。」
「コバルト山地」「ぬすびと」「恋と病熱」の諸篇に示された“沸きあがる激情”が、保阪嘉内への充たされない「恋」によるものだという理解は、現在も変わりません。しかし、同時にこれら諸篇には、作者の“上行の旅”と日常生活世界との衝突の痕が、一貫して刻印されています。保阪に対する恋情の葛藤が、‥その精神状態が、作者をして“上行の旅”に向かわせたとも言えると思います。
作者において、このような葛藤が頂点に達したのは、長詩「小岩井農場」の前後ではないかと思います:
「堀籠さんは温和しい人なんだ。
あのまっすぐないゝ魂を
おれは始終をどしてばかり居る。
【烈しい白びかりのやうなものを
どしゃどしゃ投げつけてばかり居る。
こっちにそんな考はない
まるっきり反対なんだが
いつでも結局さう云ふことになる。
私がよくしやうと思ふこと
それがみんなあの人には
辛いことになってゐるらしい。】
〔…〕
【それはさうだ、この五六日
ずゐぶん私は物騒に見えたらう。
[人生経営ももうだめだと云ひ
ピストルはもってゐる
砒素やひのきのことを云ふ
茶碗は床へ投げつける
そんなやつの家へどうして寄りつかれよう。】
あの人が来なかったのは当然すぎる。]
何もかもみんなぶち壊し
何もかもみんなとりとめのないおれはあはれだ。
〔…〕
もう柳沢へ抜けるのもいやになった。
柳沢へ抜けて晩の九時の汽車に乗る。
十時に花巻へ着き
白く疲れて睡る、
つかれの白い波がわやわやとゆれ…
[寂しい寂しい。二時の汽車へは間に合はないのかな。]
五時の汽車なら丁度いゝ。
学校へ寄って着物を着かへる。
堀篭さんも奥寺さんもまだ教員室に居る。
錫紙のチョコレートをもち出す。
【けれどもみんながたべるだらうか。】
〔…〕
もう帰らうか。こゝからすっと帰って
多分は三時頃盛岡へ着いて
待合室でさっきの本を読む。
【いゝや、つまらない。やっぱりおれには
こんな広い処よりだめなんだ。
野原のほかでは私はいつもはゞけてゐる
やっぱり柳沢へ出やう】」
【 】は【下書稿】から【清書稿】への改訂時の加筆。[ ]は【清書稿】成立後に削除された部分。

栗谷川虹氏は、ここに表れた作者の葛藤を、つぎのように説明しておられます:
「社会の中ではなく、野原のような広いところでなら、賢治の意識は、自由に現実と異空間を彷徨うことができる。ところが現実社会では『いつもはゞけて』いなければならない。〔…〕即ち、飲食物が咽喉につかえるように、対人関係は、常にぎくしゃくとした感情のすれ違いに終止[ママ]していたということであろうか。
『心象』が賢治にとっていかに自然で正常であろうとも、他人にはこの異次元感覚は、異常あるいは狂気としか感じられないであろう。〔…〕この異常な現象が〔賢治の―――ギトン注〕正常な理性の眼にはっきりと見えることは、どうやって説明するのか。〔…〕
この異常を異常と認める理性が、現実社会における対人関係を支えていたはずである。従って、対人関係におけるぎくしゃくしたとりとめのなさは、異常な現象を知覚していたことにあるのではなく、〔…〕『春と修羅』の生活と、教師としての現実生活を、はっきりと区別することの不可能にあった。」
栗谷川虹『宮澤賢治 見者(ヴォワイヤン)の文学』,1983,洋々社,pp.194-195
休日の広い農場を、誰にも邪魔されず、話しかけられることもなく、好きなように歩いている状態では、作者の意識は、現実の農場の路と、異世界体験との間を自由に往復できたわけです。
一方で、現実の農場で歩いてゆく道すじを判断し、また、農作業のようすを見学して教材を得ようとする作者の活動は、現実的な意識によって行なわれています。他方、それと同時に行なわれ、手もとのメモ帖に記録されてゆく“異世界”体験、すなわち《心象スケッチ》は、非現実的な世界を見透す“見者”の意識によって行なわれます。
この“異世界”体験とは、わたしたちの日常世界からかけ離れた“彼岸の世界”の体験などではなく、わたしたちの日常的な意識から、無反省で習慣的な外被を剥ぎ取って行ったときに現れてくる根源的な意識の世界―――賢治の場合には、それはたぶんに前宗教的なアニミスティックな形相で充たされているのでした。
この現実的、非現実的の2つの意識は、たがいに矛盾しないはずはなく、しばしば相克さえしているのですが、そうした意識の分裂も、広い農場をひとりで歩いている状態ならば、誰にも気兼ねなく、どうにでも分裂相克と自己調整を重ねてゆくことができるのです。
しかし、職場に戻ってから、教師としての社会生活の中で、同僚や生徒たちとの関係の中でこのような“きままな彷徨”を続けることはできません。そこに、賢治の直面した矛盾・葛藤がありました。
⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》5.3.4
◇ ◇
この葛藤も、『春と修羅』の「序詩」が書かれ、印刷が開始された 1924年2月ころまでには収束したものと思われます。
というのは、賢治は、「小岩井農場」の最後の章「パート9」を大幅に改訂して、その終結部分を、↓つぎのように書き改めているからです。
(なお、入沢康夫氏の詳細なテキスト・クリティークによれば、この部分の改訂は、原稿が印刷所に引き渡されて印刷が開始された後、《第3段階》で行われています。⇒:ゆらぐ蜉蝣文字 8.1.7〜 これと、2月7日にはすでに印刷途中であったが、「永訣の朝」末尾の修正〔《第3段階》?〕より以前であったという『二荊自叙伝』の“証言”〔ゆらぐ蜉蝣文字 9.3.12〜〕を考え合わせますと、「小岩井農場・パート9」の改訂は、1924年2月7日以後で、おそらく 2月中と推定されます。)
「もうけっしてさびしくはない
なんべんさびしくないと云ったとこで
またさびしくなるのはきまってゐる
けれどもここはこれでいいのだ
すべてさびしさと悲哀とを焚いて
わたくしは透明な軌道をすすむ
ラリックス ラリックス いよいよ青く
雲はますます縮れてひかり
わたくしはかっきりみちをまがる」
「小岩井農場・パート9」より。
ここで作者が「道をまがる」と言っているのは、直接には、往路で通った《農場本部》の前を通るのをやめて、‥そこをショートカットして、まっすぐに《小岩井駅》方面へ向かうことを意味しています。詳しい論証は省きますが、これは、現地を踏査してみれば明らかなことです。⇒:《ギャルリ・ド・タブロ》歩行スケッチの季節(1)(6枚目の写真の説明を参照)
この“《本部》への道”とは、菅原千恵子氏によれば、「本部へ到る真実の道」「自分の目標に到る道」「『絶対真理』のために生きる」道(『宮沢賢治の青春』,角川文庫,pp.178-179)、つまり、何らかの宗教的な境地を象徴しているようです。多くの研究者が、そう考えているようです。‥‥しかし、賢治はここで、《本部》をショートカットして、同僚たちと日常生活が待っている日常的空間へと急いでいるのです。《本部》へ行くのをやめて、日常生活世界のほうへ向きを変えているのです。
こうして、『春と修羅』がほぼ完成した時期に、賢治は“上行の旅”を終え、日常生活との矛盾・葛藤は収束されたのだと思います。
◇ ◇
“収束”の兆候は、すでに、『春と修羅』の半ばあたりから表れていました。その“転換点”として、栗谷川虹氏が注目するのは、1922年9月18日の日付をもつ「東岩手火山」です。
『春と修羅』に収録された「東岩手火山」のテキストの形が、1922年9月という時点ですでにできあがっていたかどうかは、じつのところわかりません。しかし、この詩は詩集出版の約1年前に、1923年4月8日付『岩手毎日新聞』に掲載されており、そこでのテキストは、『春と修羅』収録のものとほぼ同じです。したがって、その時点までには内容が確定していたと言えます。
⇒:東岩手火山(抄)岩手毎日新聞
⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》5.3.4〜
「教師となって約十ヵ月、『東岩手火山』でようやく社会生活そのものが、スケッチの対象とされます。これはまさしく、現実から新しくまっすぐに起とうという決意の実践にほかなりません。
〔…〕『幻想』という言葉が、『小岩井農場』から頻繁に使われだすように、かつて『それこそ尊いのだ』と一度は断言された『心象』は、ここで明らかに相対化されています。
〔…〕
賢治は帰還したばかりです。〔…〕大勢の生徒に囲まれながら、賢治はまだ、異空間と現実のはざまで、孤独にひたっています。」
栗谷川虹『宮沢賢治 異界を見た人』,1997,角川文庫,pp.217-218,220-221.
「月は水銀、後夜(ごや)の喪主(もしゆ)
火山礫は夜の沈澱
火口の巨きなえぐりを見ては
たれもみんな愕くはづだ
(風としづけさ)
いま漂着する薬師外輪山
頂上の石標もある
(月光は水銀、月光は水銀)」
『春と修羅』「東岩手火山」より。
⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》5.3.5〜
「賢治の舞台は、異次元と現実、天と地の中間たる広大な夜の空中に浮かぶ円形舞台です。彼はいま、水銀のような月光を浴びて、この舞台に立っています。」
栗谷川虹,op.cit.,p.223.
深夜の火口壁の上に立って、青い月光を浴びている賢治の姿は、“観客”とみなされた生徒たちから見れば、円形舞台に立つオペラ役者のように見えるかもしれません。
「私は氣圏オペラの役者です
鉛筆のさやは光り
速かに指の黒い影はうごき
唇を圓くして立つてゐる私は
たしかに氣圏オペラの役者です」
『春と修羅』「東岩手火山」より。
「『春と修羅』は、賢治がこの舞台で、星座の青い壮麗を浴びながら、一人演じなければならない観客のないオペラでした。
〔…〕
賢治が衝突したのも、結局、自己という人間の謎の根本であった〔…〕。謎は賢治にも、まず『他界』として現れました。〔…〕
『春と修羅』は、自己の意識に映ずる『他界』の風景を、正確に写しとることによって、この謎を見極めようとすることでした。〔…〕賢治のスケッチは、見せられた未知の事物を、正確に写そうとして得られた未知なる象(かたち)だったといえます。〔…〕賢治は自分が写しているものが、『気圏オペラ』を演ずる自己そのものであると見えたのではなかったでしょうか。〔…〕
小林秀雄は、ランボオは『人間には言葉より古い記憶はないという事に苛立ったのではなかったか』といいます。読者は、賢治の同じような苛立ちを思い出すでしょう。『どんなにわたくしはきみたちの昔の足あとを/白堊系の頁岩の古い海岸にもとめただらう』と。〔…〕言葉より古い記憶、天の子どもたちの足跡、――オペラは独りで演じられなければなりませんでした。意識の限りない明晢だけを頼りに。
〔…〕賢治がオペラの舞台を降りるのは、むしろ新たな詩を書くためでした。〔…〕
『東岩手火山』の末尾で、賢治は観客の方へ向かって歩みだします。」
栗谷川虹,op.cit.,pp.223,225-226.
「言葉より古い記憶」とは、言葉となる以前の根源的な意識の世界と言い換えることもできるでしょう。それを、どこまでも求めてゆく“上行の旅”は、他人からは理解されようのない孤独な旅でもあったのです。
しかし、栗谷川氏によれば、この詩の末尾で、賢治は「気圏オペラ」の舞台を降りて、観客のあいだへと入って行きます。
「火口丘の上には天の川の小さな爆發
みんなのデカンシヨの聲も聞える
〔…〕
東は淀み
提灯はもとの火口の上に立つ
また口笛を吹いてゐる
わたくしも戻る
わたくしの影を見たのか提灯も戻る
(その影は鐵いろの背景の
ひとりの修羅に見える筈だ)
さう考へたのは間違ひらしい」
『春と修羅』「東岩手火山」より。
⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》5.3.29〜
「かつて、『ほんたうにおれが見えるのか』と、昂然と、しかし苦しくも拒絶しなければならなかった『他者』に向かって、これはなんという変わりようでしょうか――、『さう考へたのは間違ひらしい』、と。
『気圏オペラ』の幕はおりました。賢治は衣装をすてて観客の中へおりていきます。」
栗谷川虹,op.cit.,p.227.
それでは、「東岩手火山」以後、“上行の旅”と日常的意識との矛盾は、どのようにして解決されたのでしょうか?
現象学の与えてくれる枠組みによって解釈すれば、賢治は、長い“上行の旅”のすえに、彼自身にとって十分と思える《還元》の高みに達したのだと思います。その高みからは、日常的な《生活世界》の構造を、手に取るように眺めることができます。こうして、『春と修羅』(第1集)出版の時期までには“上行の旅”は終結し、“下行の旅”が開始されるのです。
“下行の旅”のイメージは、この時期に書かれた詩篇にも現れていると思います。それは、眼の前の霧が吹きはらわれて、パッと視野が開けるイメージ、あるいは、これまでは不透明だった世界の底の底まで見透かされて、その深奥から、さまざまな始原の形相が跳び出して来るイメージだと思います。
「風がもうこれつきり吹けば
まさしく吹いて来る劫(カルパ)のはじめの風
ひときれそらにうかぶ暁のモテイーフ
電線と恐ろしい玉髄(キヤルセドニ)の雲のきれ
そこから見当のつかない大きな青い星がうかぶ
(何べんの恋の償ひだ)」
『春と修羅』「風景とオルゴール」(1923.9.16.)より。
⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》8.4.14〜
「劫」とは、古代仏教で、1つの宇宙(あるいは世界)が誕生してから消滅するまでの期間を言います。その新しい「劫」が始まろうとしていると言うのです。古い世界の残りかすを吹き飛ばそうとしているかのような激しい風が吹きすさび、その向こうで、なにか恐ろしい「大きな青い星」が、こちらをじっと見つめています。
「風が偏倚して過ぎたあとでは
〔…〕
すべてこんなに錯綜した雲やそらの景観が
すきとほつて巨大な過去になる
〔…〕
いま雲は一せいに散兵をしき
極めて堅実にすすんで行く
〔…〕
空気の透明度は水よりも強く
松倉山から生えた木は
敬虔に天に祈つてゐる
辛うじて赤いすすきの穂がゆらぎ
(どうしてどうして松倉山の木は
ひどくひどく風にあらびてゐるのだ
あのごとごといふのがみんなそれだ)
呼吸のやうに月光はまた明るくなり
雲の遷色とダムを超える水の音
わたしの帽子の静寂と風の塊
いまくらくなり電車の単線ばかりまつすぐにのび
レールとみちの粘土の可塑性
月はこの変厄のあひだ不思議な黄いろになつてゐる」
『春と修羅』「風の偏倚」(1923.9.16.)より。
⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》8.5.1〜
「劫のはじめの風」がふきすさぶと、複雑な雲におおわれていた空も「すきとほつて」透明になり、「巨大な過去にな」ってしまいます。古い世界の外被を根こそぎ吹き飛ばそうとしているような強風に、木々は恐れおののいています。
まるでこの世界全体が「呼吸」しているかのように、夜空は明暗の交替を繰り返します。
これが、“下行の旅”を開始した賢治の眼に、まず映った世界の姿だったのです。

ついで現れてくるのは、地の底から沸きあがるように、あるいは、この世ならざる彼方から風で飛ばされてきたように出現する文字の列なり、ないし言葉の断片です。
私たちの世界が立ち上がってくる始原の場所から、始原そのままの姿で、しかも、いまや表現可能な言葉の断片となってやってくるさまざまな形相、あるいは、言葉となる一歩手前の“未知の文字”の列なり‥‥
「そらにはちりのやうに小鳥がとび
かげらふや青いギリシヤ文字は
せはしく野はらの雪に燃えます」
『春と修羅』「冬と銀河ステーション」(1923.12.10.)より。
⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》8.14.1〜
「風の透明な楔形文字は
暗く巨きなくるみの枝に来て鳴らし
また鳥も来て軋ってゐますと」
『春と修羅・第2集』#75, 1924.4.20.「北上山地の春」〔下書稿(一)〕より。
これらの言葉や文字列が、「小鳥」や「鳥」とともに現れていることにも、注目してよいと思います。というのは、鳥は、原始信仰的観念のなかでは、この世と“他界”とを行き来する“使い”と考えられているからです。ここで“他界”と観念されているのは、現象学で言えば、私たちの世界認識の基にある始原の領域です。
さらに、“下行の旅”は、列車に乗って全速力で坂を駆けおりるイメージによっても表現されます。作者の乗った乗り物は、“まち”へ向かって、日常の生活世界へ、駆けおりるように走るのです。
『春と修羅・第1集』の最後に置かれた詩篇「冬と銀河ステーション」は、軽便鉄道の機関車が、雪の平原を疾走するイメージで貫かれています。
「あゝ Josef Pasternack の指揮する
この冬の銀河軽便鉄道は
幾重のあえかな氷をくぐり
(でんしんばしらの赤い碍子と松の森)
にせものの金のメタルをぶらさげて
茶いろの瞳をりんと張り
つめたく青らむ天椀の下
うららかな雪の台地を急ぐもの
(窓のガラスの氷の羊歯は
だんだん白い湯気にかはる)
パツセン大街道のひのきから
しづくは燃えていちめんに降り
はねあがる青い枝や
紅玉やトパースまたいろいろのスペクトルや
もうまるで市場のやうな盛んな取引です」
『春と修羅』「冬と銀河ステーション」(1923.12.10.)より。
⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》8.14.6〜
これを、この詩集の巻頭に置かれた「屈折率」と比較してみれば、その対照はあまりにも明白です。同じ雪の上の移動でありながら、「屈折率」では、馴れ親しんだ人の住みか(生活世界)に背を向けて、おぼろげな目標に向かって遅々たる歩みを重ねる“上行の旅”が描かれ、「冬と銀河ステーション」では、人の住む“まち”に向って全速力で駆けてゆく“下行の旅”が歌われます。また、作者の眼に映る風景も、「屈折率」では、いっさいの色と飾りけを除き去ったような、モノクロームの雪景色であったのに対し、「冬と銀河ステーション」は、「ひのき」の梢から燃えるようにかがやき落ちるしずくや、散乱するさまざまな色の宝石に充ちているのです。
“下行”する作者の眼に映るのは、疾駆する列車の車窓のようにめまぐるしく行きすぎる風景と、にもかかわらず次々に明確な形相で現れてくる世界の真の姿、その始原の構造なのでした。
それは、昇りきった超越論的高みから一気に駆けくだり、一気に“日常世界”に回帰する“下行の旅”だったのです。
「ぎざぎざの斑糲岩の岨〔そば〕づたひ
膠質のつめたい波をながす
北上第七支流の岸を
せはしく顫へたびたびひどくはねあがり
まっしぐらに西の野原に奔〔か〕けおりる
岩手軽便鉄道の
今日の終りの列車である
〔…〕
いるかのやうに踊りながらはねあがりながら
もう積雲の焦げたトンネルも通り抜け
緑青を吐く松の林も
続々うしろへたたんでしまって
なほいっしんに野原をさしてかけおりる
わが親愛なる布佐機関手が運転する
岩手軽便鉄道の
最後の下り列車である」
『春と修羅・第2集』#369,1925.7.19.「岩手軽便鉄道 七月(ジャズ)」〔定稿〕より。
作者を乗せた・この暴走列車を運転する「機関手」の名前は「布佐」‥‥めずらしい苗字ではないでしょうか? 賢治の“下行の旅”を先導しているこの機関士、もしかして「フッサール」ではないの?...w
◇ ◇
さて、『春と修羅・第2集』『第3集』およびそれ以後の口語詩では、たしかに『第1集』と比べれば、《心象スケッチ》特有の語彙表現は少なくなります。しかし、なくなってしまうわけではありません。賢治は、世界の深奥の構造を覗き見る《心象スケッチ》を、やめたわけではないのです。むしろ、生活世界そのものの日常的な表現と、始原の構造を暴き出す表現との間を、作者は、自由自在に行き来している観があります。
そして、“晩年”の文語詩篇においてめざされたのは、ことがらの本質を一挙につかみ出し、―――本質に至る過程でのこまかいディテールなどは、大胆に削りとってしまって―――その結論だけを、短い詩形の中に凝縮させて表現しようとする試みだったのではないでしょうか?
【参考】(《心象スケッチ》と本質観取) ⇒:『宮沢賢治の《いきいきとした現在》へ』第5章
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]


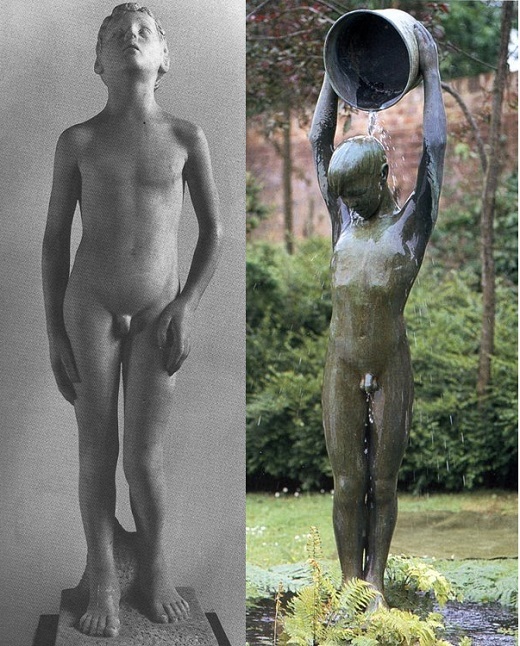






 彡
彡