07/31�̓��L
18�F28
�y���[���V�A�z�t�b�T�[���Ƌ{���\�\�\�@���ƉȊw�̈ʒu(1)
---------------
.

�ӎl���_�Ё@�Ԋ��s
�@�����́B(º.-)���
�@�w�Z�p�̓N�w�x����w�_���w�����x�w�C�f�[���x�܂ł̕��݂ɂ����āA�t�b�T�[�����߂������̂́A
�@�������̂��̂̌�����A�Ȋw�I�v�l�̘g�g�݂������Ă��鍪���̂����݂𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA�������̓���ӎ������������Ă���펯�̊O������Ƃ��Ƃ���菜���A�ӎ��̔������Ă���n���𖾂�݂ɏo�����Ƃ���A������g��s�̗��h�ł����B
�@�킽�������̖����ȂȈӎ��̂����ɁA���x�ɔ��B���Ă��܂����ߑ�Ȋw�́g�q�ϐ��h�g�Ó����h���A�ӖڂɁg�M�h����̂ł͂Ȃ��A
�@�Ȋw�����̑��ʐ��ɂ����Đ����ɗ������]�����邽�߂ɂ́A�m�o�A�v�l�A�z���A���f�Ƃ������킽�������̈ӎ��̂͂��炫�̍����ɑk���āA�����̔������Ă��邵���݂��𖾂���K�v������B
�@���̂��߂ɂ́A�_�o���]�̐����I���J�j�Y���ɂ���Ďv�l�ƊT�O����������Ƃ����g�Ȋw�I�h�Ȑ������A���������~���A�d�d����ǂ��납�A�@���ɂ̂��Ƃ��ĉ^�s���鐢�E�A�F�������݂��A���̒��ɂ킽�����������݂���Ƃ����f�p�ȁg���R�̑O��h�i�u���R�I�ԓx�v�j�������A���������~���i�u���z�_�I�Ҍ��v�j�A���������́g�O��h���킬���Ƃ��ꂽ��Ԃł́E�ӎ��̂������Ƃ̓�����K�˂Ă䂭���ƂɂȂ�܂��F
�u���������|���e�B�ɂ��A�����̓���I�o���͈Ӗ��̌o���ł���A�Q�V���^���g�̌o���ł���B�������A�k�c�l�����͂��łɍ\������Ă���Ӗ��̐��E�ɐ����Ă���A�k�c�l���łɂł����������Ӗ��̐��E�̂����ɐ����Ă��邩����A���̐��E���\�����铭���͌����Ă��Ȃ��B
�@�t�b�T�[���́A�o���̂����ɂƂǂ܂邩���茩���Ă��邱�Ƃ̂Ȃ��o���̍\���́w�����Ɂx��₤���߂ɁA���ۊw�I�Ҍ����s���A���R�I�ԓx���猻�ۊw�I�ԓx�ֈڍs�����v
�쐣���w�o���̃A���P�I���W�[�x,�������[,2010,p.39.
�@�ˁF�{���́s���������Ƃ������݁t�\�\�\�w�S�ۃX�P�b�`�x�_�����y��R�́z(ii)
���@�@�@�@��
�@�������A�w�o���Ɣ��f�x�w�w�̋N���x�Ȃǂ̌������Ńt�b�T�[�������s�����̂́A�g���s�̗��h�ł����B
�@�����ł́A�g��s�̗��h�ɂ���ē��B�����g���z�_�I�ӎ��h�̍��݂���A����I�ӎ��̐��E�����Ղ���A����ꂪ����A�g������܂��̐��E�h�Ƃ��ē��e����ł���s�������E�t�̍\���\�\�\�u���R�I�ԓx�v�ɖ��v���Ă����Ƃ��ɂ͌����Ȃ������\�����A����݂ɏo�����̂ł��B
�@���̌��ʂ����������ςɌ����A�ӎ����A�v���I���Ɏ����Ă�����I�ȁg���ԁh�̍\���A���E�Ƃ����g�n���h�̍\�����A�킽�������̔F�����\�ɂ��Ă���E�������Ƃ̂����݂Ȃ̂ł����B
�@�����āA���������\���Ɋ�Â���ꂽ�ӎ��̂͂��炫����A���Ƃ��u�R�̕ӂ��������O�p�`�́A�R�̊p���������B�v�Ƃ��������O�I�Ȕ��f���܂����܂�Ă���̂ł��B���������Ȋw�I�Ȕ��f���܂ށu�q��I���f�v���A�Ȃ��A�܂������Ȃ��������Ɗm�M�����̂��A���́u���ؐ��v�̋����Ă��鍪���A�N�������炩�ɂ���܂��F
�u�w���������̏q��I���ؐ��́A�ŏI�I�ɂ́A�܂��Ɍo���̖��ؐ��Ɋ�b�Â����Ă���B�k�c�l�o���̐��E�ւ̋A�҂��w�������E�x�ւ̋A���A���Ȃ킿�A���̂����ł���ꂪ��Ɋ��ɐ����Ă���A�܂��A���������̔F���\��Ƃ��������̊w��I�K��ɂƂ��Ă̒n�Ղ��Ȃ��Ă��鐢�E�ւ̋A�҂ł���B�x�iEU,38�j
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�w�������E�x�Ƃ́A�����̓���I�E�����I�Ȍo���̐��E�ł���A���̖��ؐ��ɂ����ė^�����Ă��鐢�E�A���R�I�ԓx�ɂ����鑶�ݐM�O�̂��Ƃɗ^�����Ă��鐢�E�ł���B���������āA�����������E�͕K�R�I�ɁA���m������ѐe�����Ƃ������i�����ƌ�����B�k�c�l
�@�w�������E�́A���ꎩ�̂Ƃ��čł��悭�m��ꂽ���́A���������̐l�Ԃ̐����ɂ����ď�Ɋ��Ɏ����Ȃ��́A�o����ʂ��Ă��̗ތ^�ɂ����ď�Ɋ��ɂ����ɐe���܂�Ă�����̂ł͂Ȃ��낤���B���̂��������̖��m�̒n���́A�P�ɕs���S�Ȋ��m���̒n���ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B���Ȃ킿�A���̈�ʓI�ތ^�ɂ����Ă��炩���ߒm���Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B�x�iHua.�Y,126�j
�@����Ƀt�b�T�[���́A�k�c�l���̎�ϓI�]���ΓI�Ȑ������E���q�ϓI�Ȋw�����b�Â��Ă���A���̒n�Ղ��Ȃ��Ă���ƍl����B�k�c�l
�@�w���X�̊w��́A�������E����A���̂ǂ̎��Ȃ̖ړI�ɂƂ��Ă��̂ǕK�v�Ȃ��̂����o���ė��p����Ƃ����d���ŁA�������E�̎������̂����Ɍ����Ă���B�x�iHua.�Y,128�j
�@�k�c�l�q�ϓI�Ȋw�̐��E�Ƃ́A�k�c�l�����Ȏd���Ő��w������A�q�ω����ꂽ���E�̂��Ƃł��낤���A�����������E�͋ߑ�Ȋw�̔��W�̒��ŁA�����ΐ��E�̐^�̎p�Ƃ݂Ȃ���Ă����B�������A����ɑ��ăt�b�T�[���́A���������q�ϓI�Ȋw�̐��E�A�����Ȋw�̐��E���A�������E�����O�����ꂽ�p�Ƃ��āA���邢�́A�������E�ɓZ�킳�ꂽ�w���O�̈߁x�Ƃ��Ė\���o���A�k�c�l�����������O���̒n�ՁA���O���ɐ旧�������E�A���O�̈߂��͂����ꂽ�������E�֗����A�낤�Ƃ���̂ł���B�v
�w�o���̃A���P�I���W�[�x,pp.20-23.
�w�x���̓t�b�T�[���̒��삩��̈��p�B
�@���������A�킽�������̌o�����E�Ƃ͂����͂Ȃꂽ���������g���O�̐��E�h���`�Â����Ă���悤�Ɍ�����w�ł������A���̌����߂Ă݂�A�����͂킽�������̓���I�ȑf�p�ȏ펯�ɗ��r���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
�@�܂��āA�Љ�Ȋw��l���Ȋw�̂��܂��܂Ȗ{�ɏ�����Ă��闝�_�́A�f�p�ȓ���I���f�̂�������K���Ȃ��́i���̊w�҂ɂƂ��ēs���̗ǂ����́j���g�����āh���āA�����Ƃ��炵���u���_�̈߁v���܂Ƃ킹���̂ł͂Ȃ����Ǝv���邱�Ƃ���������܂��B�����v�����Ƃ́A���R�̂Ȃ����Ƃł͂Ȃ����A���̂悤�Ɍ������Ƃ́A�����Ă܂������ł͂Ȃ��̂ł��B
 �@
�@
�@�Ƃ���ŁA���傤�����ōl���Ă݂����̂́A���ۊw�v���p�[�ł͂Ȃ����āA�{���̗L���ȏ��Ȃɏ����ꂽ���̕������̈Ӗ��ł��F
�u���͂��̖��d�ȁw�t�ƏC���x�ɉ��āA�����̍l���咣���A���j��@���̈ʒu��S���ϊ����悤�Ɗ�悵�A�������Ƃ������܂��܂̐����\���āA�N���Ɍ��Ă���Ђ����ƁA�����ɂ��l�ւ��̂ł��B
�@���̕сX�����T�����������������̂łȂ��̂ł��B���͂�����@���Ƃ₢�낢��̐l�����ɑ���܂����B���̐l�����͂ǂ������Ă���܂���ł����B�w�t�ƏC�{�x�����肪�����Ƃ��ӗt�������Ă�܂��B
�@�o�Ŏ҂͂��̑̍ق���o�b�N�Ɏ��W�Ə����܂����B���͂т��т����̂ł����B���p�������������߂Ƀu�����d�̕��ŁA���̓����܂����ď������̂���R����܂��B�ҏ����A���R���A�����y�V��������]���Č���܂������A���͂܂����A�����������Ȃ��قǁA��������Ă�܂��B���͂ƂĂ����|���Ȃ�Ƃ��ӂ��Ƃ͂ł��܂���B�����Č����Ď��͂���Ȃ��Ƃ����ʼn]���Ă��̂ł͂Ȃ����Ƃ́A����Љ�����A�܂��悭���ׂĉ�����Δ���܂��B�v
�{������[200] 1925�N2��9���t �X���ꂠ��
�@�܂�A����o�ł����w�t�ƏC���x�i��P�W�j�́A�u���j��@���̈ʒu��S���ϊ����悤�v�Ƃ����u���v�̂��Ƃɐ��ɖ₤�����̂ŁA���́u���v�́u���d�v�ł���������ǂ��܂��߂Ȃ��̂ŁA�u���|���Ȃ�Ƃ��ӂ��Ɓv��W�Ԃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂��\�\�\�ƌ����̂ł��B
�@�����ŋ{���������u���j��@���̈ʒu��S���ϊ��v����Ƃ́A�ǂ������Ӗ��Ȃ̂ł��傤���H����̕�������A����́w�t�ƏC���x�u�����v�ɏ�����Ă���咣�̂悤�ł��B
�@�����Łu�����v������ƁA�u���j��@���v�ɊW���Ă���̂́A���̕����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��F
�u�����͓�\��ӌ���
�@�ߋ��Ƃ�����p����
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�����܂ł������U����ꂽ
�@�����ƂЂ���̂ЂƂ�����Â�
�@���̂Ƃق�̐S�ۃX�P�c�`�ł�
�@�@�@
�@�����ɂ��Đl���͂�C����C�_��
�@�F���o�����ׁA�܂��͋�C�≖�����ċz���Ȃ���
�@���ꂼ��V�N���{�̘_�����ւ܂�����
�@�������L�킱�T��̂ЂƂ̕����ł�
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@����ǂ������V���㉫�ϐ���
�@����ɖ��邢���Ԃ̏W�ς̂Ȃ���
�@�����������ꂽ���̂����̂��Ƃ�
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@���łɂ͂₭�����̑g���⎿��ς�
�@�������킽����������҂�
�@�����ς�Ȃ��Ƃ��Ċ����邱�Ƃ�
�@�X���Ƃ��Ă͂��蓾�܂�
�@����������ꂪ�����̊�����
�@���i��l��������₤��
�@�����Ă��U���ʂɊ����邾���ł���₤��
�@�L�^����j�A����Ђ͒n�j�Ƃ��ӂ��̂�
�@����̂��낢��̘_���i�f�[�^�j�Ƃ������
�@�i���ʂ̎���I����̂��ƂɁj
�@����ꂪ���Ă��̂ɉ߂��܂���
�@�����炭���ꂩ����N�����������
�@���ꑊ���̂������n���w�����p����
�@���������؋����܂������ߋ����猻�o��
�@�݂�Ȃ͓��N�����O�ɂ�
�@���炢�ς��̖��F�ȍE���������Ƃ�����
�@�V�i�̑�w�m�����͋C���̂�����̏�w
�@����т₩�ȕX���f�̂����肩��
�@���Ă��ȉ��x������
�@����Ђ͔����I����̑w�ʂ�
�@�����Ȑl�ނ̋���ȑ��Ղ�
�@�������邩������܂���
�@�@�@
�@���ׂĂ����̖����
�@�S�ۂ⎞�Ԃ��ꎩ�g�̐����Ƃ���
�@��l�������̂Ȃ��Ŏ咣����܂��v
�w�t�ƏC���x�u�����v
�@�Q�s�̒i���͌����B�P�s�̒i���͈��p�ҁB

�@�܂��A�u�@���v�ɂ��ẮA�͂����肻��Ɩ��w���ď�����Ă͂��܂��A��̂ق��Ɂu�{�̘_�v�Ƃ����ꂪ����܂��B
�@�u�{�̘_�v�́A�N�w��ʂ̗p��Ƃ��Ắu���̘_�v�Ɠ����Ӗ��ł����A�Ƃ��ɕ����ł́u�{���_�v�̈Ӗ��ŗp�����܂��B�u�{���_�v���A�Ƃ��ɂ₩�܂����c�_����͓̂��@�@�ł��B
�@�y�Q�l�z�ˁF�{���́s���������Ƃ������݁t�\�\�\�w�S�ۃX�P�b�`�x�_�����y��Q�́z(iii)
�@�����������ŁA�u�{�̘_�v���ǂ���̈Ӗ��Ŏg���Ă���̂��͂킩��܂���B����������܂�w �������A������ɂ���A���̑O��Ō����Ă���̂́A�@�����_�A���邢�͏@���N�w�̌����́A���ΓI�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�@���O������莮�����ꂽ�@�����_�́A���ꂱ�������́i���݁j�ŁA�����̓��팩���鐢�E�́u�����v�i���ρj���Ǝ咣���邯��ǂ��A����͋t���Ƃ������Ƃł��B�ނ���A�����Ɍ�����u���ہv�̂ق����{��������̂ŁA�@�����_�\�\�u�{�̘_�v�\�\�́A�����N�������O�����A�u���O�̈߁v�����Ԃ������́A������l���Ă��邻�̐l�́u���T��̂ЂƂ̕����v�ɂ����Ȃ��ƌ����̂ł��B
�@����́A���ꂾ��������A���Ȃ�g�S����`�h�̌X�����������l�����ł��B�����˂��l�߂čs���A���������@���͐l�Ԃ̐����̂͂��炫�����o�������z�ɂ����Ȃ��A�Ƃ����B���_�I�ȏ@���ςɍs�������悤�ɂ��v���Ȃ��͂���܂���B
�@�������A���́u�����v�S�̂̎咣�̃x�[�X�A�Ƃ��Ɂ\�\�\��̈��p�ł͏ȗ����܂������\�\�\�`���́u�킽�����Ƃ��ӌ��ۂ́d�d�v�ȉ��̕������Č��܂��ƁA��҂́A�ނ��땧���N�w�I�ȁg���ߖŁh�I���E�ς�O��Ƃ��Č���Ă���悤�Ɏv���܂��B�����I�Ȉ�ʓI�Ȑ��E�̌����͑O��Ƃ��Ȃ���A�������甭�����g���O���h���ꂽ�����N�w�̗��_�́A���������̎v�z�ƁA�����Ƃ��l�������ΓI�Ȃ��̂ɂ����Ȃ��\�\�\�Ƃ��Ă���̂��Ǝv���܂��B
�@
�@�u�@���v�ɂ��ẮA����ȂƂ���ł����A�u���j�v�ɂ��ẮA��̈��p�́u����������ꂪ�����̊�����v�ȉ��Ŏ��I�ɏq�ׂ��Ă��܂��B���̓��e��v�܂��ƁF
�@��u���Ƃǂ܂�Ȃ����Ԃ̗���̂Ȃ��ŁA�ω������]���Ă䂭�̂́A�l�Ԃ�����╨�����łȂ��A�����������u�ɋL�^�������т��܂������ł���B�u�S�ۃX�P�b�`�v�Ƃ��ċL�^����A���̎��W�Ɏ��^���ꂽ���т��A�u�V���㉫�ϐ��v�Ƃ����悤�ȉi�����Ԃ̒��ł́A�ω����܂ʂ���Ȃ��B������ꂽ���т́A���҂�����҂��C�Â��Ȃ��������ɁA��u�̂̂��ɂ́A�͂��Ȃ�Ƃ����łɁu���̑g���⎿��ς��v�Ă���B�\�\�\����́A����C���N�̉��w�g�����ω����邾���łȂ��A���e�̈Ӗ����ς��Ă��܂����Ƃ��܂�ł���̂ł��傤�B
�@�ω����Ă�܂Ȃ����E�̎p���A���Ȃ��܂ȏu�ԏu�ԂɋL�^���āA���́g���j�h�𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ��Ă��A���������u�L�^����j�A����Ђ͒n�j�Ƃ��ӂ��́v���̂��A���Ԃ̗���̂Ȃ��ŕω����čs���Ă��܂��B
�@�܂��āA�����ɂǂ�Ȓn���w���s���Ă��邩�A�����̒n���w����j�̏������A���݂̎�����ǂ̂悤�Ȃ��̂Ƃ��āg�����h���邩�́A�Ƃ��Ă��\�z���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł����āA
�@�����̎���ɂ́u���炢�ς��̖��F�ȍE���v���������Ă��āA�����̎���ɁA���w�����炻�̉������@�����Ƃ��A�����̎���ɂ����u�����Ȑl�ނ̋���ȑ��Ձv�����������Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ��A�������čr�����m�ȋ�z�Ƃ͌����Ȃ��̂��B
�@�����ƁA���̂悤�ɂȂ�ł��傤�B
�@�t�Ɍ����A�������́A�������̐����Ă��鐢�E���A�������Ċ��S�ɉ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�g�߂Ȗ�R�Ɂu�����Ȑl�ށv���Z��ł��Ȃ��Ƃ��A�u���炢�ς��v�Ɂu���F�ȍE���v�����Ȃ��Ƃ��A�������͒f�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����玄�����̒m��Ȃ������������A2000�N��ɉ��ƂȂ��Ĕ�������邩������Ȃ��B�d�d�d
�@�����ŏq�ׂ��Ă��邱�Ƃ́A�u���j�v�Ɋւ���ȏ�ɁA�u�Ȋw�v�Ɋւ����҂̍l������\��������̂ł��B�u�S�ۂ⎞�Ԃ��ꎩ�g�̐����Ƃ��ā^��l�������̂Ȃ��Ŏ咣����܂��v�Ƃ����u�����v�̒��߂�����Ƃ������錾���́A��҂̎咣���A�n���w�����łȂ��A�S���w�A�����w���ӂ��މȊw�S�ʂɑ��ďq�ׂ����̂ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B
�@��������ƁA�����Ɉ��p�����s����[200]�t�́u���j��@���̈ʒu��S���ϊ��v����Ƃ́A�g�Ȋw�Ə@���̈ʒu��ϊ��h����ƌ��������Ă��悢�悤�Ɏv���܂��B
�@
�@����ł́A�g�Ȋw�Ə@���̈ʒu��ϊ��h����Ƃ́A�ǂ��������ƂȂ̂��H
�@�u�����v�ł́A�킽�������̊�̑O�ɂ���g���ہh�������{��������̂��Ƃ������Ƃ���Ƃ��ďq�ׂ��A�u�Ȋw�v���u�@���v�����Ή�����܂��B
�@�������猾���A�u�@���v�����u�Ȋw�v�̑��Ή��̂ق����A���S�I�ɏq�ׂ��Ă���ƌ����܂��B���҂��A�Ƃ��Ɂu�����v�̌㔼�ŗ͂����ďq�ׂĂ���̂́A�u�Ȋw�v�̂���Η��j�I�ȑ��ΐ��ł��B�����āA�u�@���v�̂ق��́A���O�����ꂽ�@�����_�A�@���N�w�́A�������ɑ��Ή������̂ł����A�����ƈ�ʓI�Ȕ��R�Ƃ��������I�����A�f�p�ȕ����I���E�ς́A�ނ��뒘�҂̋c�_�̑O��Ƃ���Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@�����āA�d�v�Ȃ��Ƃ́A�����́A�u�ʒu��S���ϊ��v����ƌ����Ă���̂ł����āA�u�Ȋw�v��ے肷��Ƃ��A�u�@���v��ے肷��Ƃ������Ă��Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂��B
�@2000�N��ɁA�����Ȑ����̉�����������邩��Ƃ����āA���݂̐����w��n���w���g�܂������h���Ƃ͌����Ȃ��̂ł��B���ꂪ�����̍l�������Ǝv���܂��B
�@�������Ƃ́u�@���v�ɂ��Ă������܂��B������@���́A�Ȃ�炩�̈Ӗ��Łg�B�ꐫ�h�g��ΐ��h��M����̂łȂ���A�j�]���Ă��܂���������܂���B�������A������@���́g���Ȃ��h�ɁA�B���́u�ق��́v�@���������������Ƃ͉\��������Ȃ��B�e�l���ꂼ�ꂪ�M����@���́A�B���́u�ق��̐_���܁v�Ɏ��邽�߂̓������ł����āA���ꂼ�ꂪ�����́g�_�h�ɑ������Ɍ��������Ƃɂ���āA���@���̋��ʂ́g�B��ҁh�Ɏ��邱�Ƃ��ł���c�c���ꂪ�A�{���́g���ΓI�@���ρh�ł͂Ȃ��������H
�@�w��͓S���̖�x�ɂ���A�L���X�g���k�����ƃW���o���j�Ƃ̊Ԃ́A�����̗L���ȉ�b��ǂނƁA�����v���Ă���̂ł��F
�u�w����Ȑ_���܂����̐_���܂����B�x
�@�w���Ȃ��̐_���܂����̐_���܂�B�x
�@�w��������Ȃ���B�x
�@�w���Ȃ��̐_���܂��Ăǂ�Ȑ_���܂ł����B�x�N�͏ЂȂ���]�Ђ܂����B
�@�w�ڂ��ق��͂悭�m��܂���A����ǂ�����Ȃ�łȂ��ɂق��̂�������l�̐_���܂ł��B�x
�@�w�ق��̐_���܂͂����������l�ł��B�x
�@�w�����A����Ȃ�łȂ��ɂ������ЂƂ�̂ق��̂ق��̐_���܂ł��B�x
�@�w�����炳�����Ⴀ��܂��B�킽�����͂��Ȃ��������܂ɂ��̂ق��̐_���܂̑O�ɂ킽���������Ƃ���ЂɂȂ邱�Ƃ��F��܂��B�x�N�͂܂��������g�݂܂����B���̎q�����Ⴄ�ǂ��̒ʂ�ɂ��܂����B�݂�Ȃق��ɕʂꂪ�ɂ������ł��̊炢����������߂Č����܂����B�W���o���j�͂��ԂȂ����������ċ����o�����Ƃ��܂����B�v

�@�u�ʒu��S���ϊ��v����Ƃ́A�ǂ��������ƂȂ̂��H
�@�M�g���͎��̂悤�ɍl���܂��F
�@�t�b�T�[����̌��ۊw�����炩�ɂ����悤�ɁA�Ȋw�́A�������̓���I�Ȉӎ��̐��E�A�u�������E�v����A�s���O���t�ɂ���Ĕ������܂��B�����āA�����Ύ������̏펯�I�Ȑ��E�����A����͐��m�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�܂����������M���A�ƌ����Ĕے肵�A�������悤�Ƃ��܂��B
�@�������A�t�ɁA���������Ȋw���A�g���ۊw�I�Ҍ��h�̍��݂���ᔻ�I�Ɉ����A�Ȋw�I�ȗ��O�I���E�ς����A���̂��ƂɂȂ����u�������E�v�̂ق��Ɏ�����u���Ĕᔻ�����Ƃ��Ă��A����́A�Ȋw��Ȋw�I���E�ς�ے肷�邱�Ƃ��Ӗ����܂���B�ނ���A�Ȋw�́g�������h���ǂ̂悤�ɂ��āg�������h�ƔF�߂���̂��A���̂����݂��A�Ȋw���O������g�݂��ށh�u�������E�v�̎��_�ɂ���āA�܂��Ƃ��ɗ������邱�ƂƂȂ�̂ł��B
�@�܂�A��g�I�Ɍ����A�Ȋw�I���E���A���̂܂�肩��L����݂��ނ��̂Ƃ��āA�u�������E�v������d�d���̂悤�Ɍ�����Ǝv���܂��B
�@�������Ƃ́A�@���ɂ��Ă�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�@
�@�@���A�Ƃ��ɏ@���N�w�\�\�\�L���X�g���_�w�A���邢�͕������w�\�\�\�́A�����ɗ��O�I�Ȃ��̂ł��B�����́A��͂�u�������E�v�Ƃ����f�p�Ȑ��E�ς���A�s���O���t����ė����オ���Ă�����̂��Ǝv���܂��B
�@���������āA�@�����A�Ȋw���A�u�������E�v�̑f�p�Ȍ������s���O���t����Č����������̂ŁA���ꂼ��̑Ó����͑��ΓI�ł���A�ǂ��炩���ǂ��炩��ے肷��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�d�d�d���̂悤�ɍl����ƁA�{���́u�����v�̎咣�ɂЂ��傤�ɋ߂��Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�i���j�������A���ۊw�́A�����̂悤�ȑ��Ύ�`�Ƃ͈قȂ�܂��B�����ł́A�����܂ł��A�u�������E�v�u���O���v�Ȃǂ̌��ۊw�̘g�g�݂𗘗p���āA�{���̎v�z���𖾂��鎅���ɂ��悤�Ƃ��Ă���̂ł��B
�@�����A�u�����v�ɂ����ẮA�@���\�\�\�������ꂽ�g���_�I�@���h�Ȃ����@�����`�ɂ��ẮA�͂�����Ƃ������y������܂���B�u�{�̘_�v�́A���ꂩ���s���O���t���čl���o�������̂ɂ����Ȃ��B����͑��ΓI�Ȃ��̂��ƌ����Ă��邾���ł��B
�@�����āA�u�����v�ɂ����ẮA�ނ���A���ƂɂȂ�u�������E�v�̂Ƃ炦�������̂��A�����I�ȐF�ʂ�ттĂ��܂��B���́g���ߖŁh�I���E�ς́A�Ȋw�Ɩ���������̂ł͂���܂��A���Ƃ͌Ñ㕧���A�Ȃ����Ñ�C���h�N�w�ɂ���Ǝv���܂��B
�@�y�Q�l�z(���ߖ�)�ˁF��炮�堕��� 0.1.2
�@�y�Q�l�z(���ߖ�)�ˁF���o�C���[�g�Ƌ{��(7)
�@�ȏ���܂Ƃ߂܂��ƁA
�@�u�Ȋw�v���A���Ȃ炸�����ے�͂��Ȃ����A������O�������݂��ނ��̂Ƃ��āA���L���g�n���h�Ƃ��āA�u�������E�v������B�����A���́u�������E�v�́A�����̏ꍇ�ɂ͑����ɏ@���I�F�ʂ�тт����E�ł���B�����ƁA����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�����Ă��ꂪ�A�g�Ȋw�Ə@���̈ʒu��ϊ��h����Ƃ����w�t�ƏC���x�̊�Ă̈Ӗ����Ǝv���܂��B
�@�������ߑ�l�̂ӂ��̍l�����ł́A�Ȋw�͏@�����ۂ���ʒu�ɂ���܂��B�������̊�{�I�ȊϔO�́A�Ȋw�̋����鐢�E�ςɋ߂����̂ŁA���̉Ȋw�I�Ȍ����̂����܁A�����܂߂�悤�ɁA�\�\�\�@����M����l�̏ꍇ�ɂ́\�\�\�@���I�Ȍ������ˋ����Ă���̂��Ǝv���܂��B
�@�������A�����́u�����v�́A���̉Ȋw�Ə@���́g�ʒu�W�h���t�ɂ��邱�Ƃ���ĂĂ���̂ł��B
�@�����ɂƂ��ẲȊw�́A�����ɏ@���I�ȁu�������E�v�̂Ȃ�����A���̂���ʂ��Ƃ肠���ās���O���t�������オ���Ă�����̂ɂق��Ȃ�܂���B
�@���̏ꍇ�ɁA�Ȋw���A���L���ʒu�ɂ����āg��ۂ���@���h�Ƃ́A�s���O���t����A�������ꂽ�@���̗��_�⋳�`�ł͂Ȃ��A�����Ƒf�p�ň�ʓI�ȁA�g�@���I�F�ʂ�тт��u�������E�v�h�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@����́A���k�̌Â��`����g���M�h�ƂȂ���悤�ȁA�A�j�~�Y�����܂��n�M�I�ȕ��y���Ǝv���܂��B�����I�M���A�L���X�g���I�M���A�������琶�ݏo����Ă���悤�ȁA����Ώ��M�́g�y��h�ƂȂ肤��f�p�ȏ�I�m�M�̐��E�Ȃ̂ł��傤�B
�@�y�Q�l�z�ˁF�Ìy���ʂ��̐��E
�@���ꂪ�A�w�t�ƏC���x�̂͂��߂̂ق��ɒu���ꂽ�����̎��тɂ���A�u�ЂƂ̌Õ��ȐM�v�̈Ӗ����Ǝv���܂��F
�u�@�@�@�@�k�c�l
�@�ق��ɂ���ȍy��̂ӂ���
�@�O��ȂӂԂ��ł�����ǂ�
�@�ق̂��Ȃ̂��݂𑗂�̂�
�@���炩���R�̐����
�@�@�@�i�ЂƂ̌Õ��ȐM�ł��j�v
�w�t�ƏC���x�u���炩���̐�v
�@�ˁF��炮�堕����y2�z���炩���̐� 1.2.5
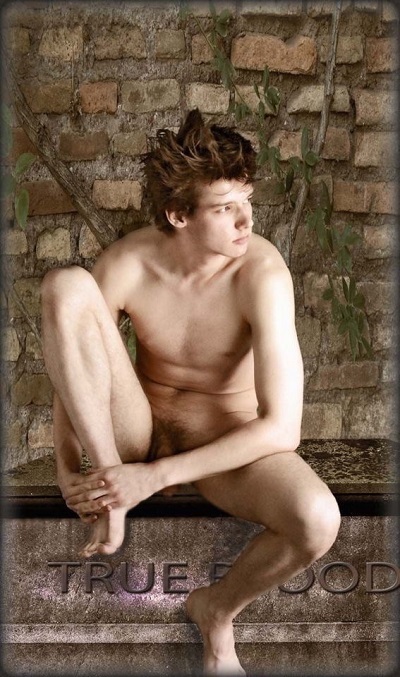 �@
�@
�@�����Ƃ��A�w��P�W�x�o�ňȌ�̕��݂̒��ł́A�u�Ȋw�v�Ɓu�@���v�̈ʒu�W�ɂ��āA�����ɂ͓��h���������Ɛ��@����܂��B
�@�w��͓S���̖�x�k�����`�R�l�ł́A�J���p�l�������������ĔߒQ�ɕ���W���o���j�̑O�ɁA�u�����傫�ȖX�q�����Ԃ����d�w�ҁv������āA�u�`�Ƃ��������Ƃ����Ȃ��b���͂��߂�̂ł����A���́u�w�ҁv�̘b�̂Ȃ��ɁA���̂悤�ȕ���������܂��F
�u�w���܂ւ͉��w���Ȃ�����炤�A���͎_�f�Ɛ��f����ł��Ă��Ƃ��ӂ��Ƃ�m���Ă��B���܂͂��ꂾ���Ă�����^�₵�Ȃ��B�������Ă݂�Ƃق��ɂ����Ȃ���B����ǂ��̂͂���𐅋�Ɖ��łł��Ă��ƌ�������A����Ɨ����łł��Ă��ƌ������肢�낢��c�_�����̂��B
�@�@�݂�Ȃ��߂��߂����Ԃ�̐_���܂��ق��̐_���܂��Ƃ��ӂ��炤�A����ǂ����݂ق��̐_���܂�M����l�����̂������Ƃł��܂����ڂ�邾�炤�B���ꂩ��ڂ������̐S�������Ƃ���邢�Ƃ��c�_���邾�炤�B�����ď��������Ȃ����炤�B
�@�@����ǂ��A�������܂ւ��ق��ɕ����Ď����ł����Ƃق��̍l���ƁA�����̍l���Ƃ��Ă��܂ւA���������̕��@���ւ��܂�A�����M�����w�Ɠ����₤�ɂȂ�B�x�v
�@�@���̖������w�Ɠ����悤�ɂ��āA�u�����v�ɂ���Đ^�U�肷��Ƃ������́u�w�ҁv�̘b�́A�������ɂ͂��܂�ɂ��r�����m�Ɏv���܂��B�������A�O��̕���������A���́u�w�ҁv�̌����u�����v�Ƃ́A��g�ł����ł��Ȃ��A�d�C�����ɂ���Đ��̌��f�g���ׂ�̂Ɠ����u�����v���̂��̂ł��邱�Ƃ������炩�ł��B
�@���Ƃ����āA���́u�w�ҁv�́A��Ȃ��Ƃ������C�̋������l���A���邢�́A�z���𐁂��Ďq�ǂ����x���l���Ƃ��Đݒ肳��Ă���킯�ł�����܂���B�u�����̕��@���ւ��܂�v�\�\�\���������ǂ�ȁu�����̕��@�v�����肤��̂��z����₵�Ă��܂����\�\�\�u�����v�ɂ���ď@������ł���ƁA��Ҏ��g���A���̒i�K�ł͍l���Ă����Ǝv�킴������Ȃ��̂ł��B�ǂꂾ���{�C�ōl���Ă������A�킩��Ȃ��C�����܂����A���Ȃ��Ƃ��A�����������Ƃ��ł����炢���ȂƋ�z���Ă����d�d�����l����ق��͂���܂���B
�@����́A�{���̏��������̂̂Ȃ��ł��A�����Ƃ��������ɂ����A����ӏ����Ǝv���܂��B������t�����������g���Ă��Ȃ������ɁA�悯���ɓ��e�̍�����ۗ����Ă��܂��B
�@�������A���ۊw����q���g���A�����قǂ̐}���ɓ��Ă͂߂čl���܂��ƁA������A�{���̎v�l�̕��݂̒��Ɉʒu�Â��Č��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�u�w�ҁv�̘b�́A�u�@���v���u�Ȋw�v�ɂ���Ċ�b�Â��悤�Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�u�����v�Ƃ����u�Ȋw�v�̕��@�ɂ���āA�u�@���v�̊�{�I�^�����ؖ����悤�Ƃ����b������ł��B
�@�w�t�ƏC���x�u�����v�ł́A���R�Ƃ����f�p�ȏ@���I�u�������E�v���A�u�Ȋw�v���ۂ��Ă����̂ł����A�����ł́A�s���O���t���ꂽ�S���u�Ȋw�v���A�s���O���t���ꂽ�S���u�@���v���ۂ��Ă��܂��B�u�@���v�Ɓu�Ȋw�v�̈ʒu�W���A�u�����v�Ƃ͋t�ɂȂ��Ă���̂ł��B
�@�������A���́E�u�Ȋw�v���u�@���v���ۂ��Ă���c�u�Ȋw�v�́u�@���v����b�Â��邱�Ƃ��ł���Ƃ����}���́A�����̈�т����v�z�ł��A�ŏI�I�ȓ��B�_�ł��Ȃ������Ǝv���܂��B�w��͓S���̖�x�k�����`�R�l���k�ŏI�`�l�ɉ��������ہA�����́A���́u�w�ҁv�̓o�ꂷ���ʂ���������폜���Ă��邩��ł��B
�@�����̎v�z�̕��݂̒��ł́A���́u�w�ҁv�̌����́A�ꎞ�́g��炬�h�ɂ����Ȃ������̂��Ǝv���܂��B
�@
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]


 �@
�@


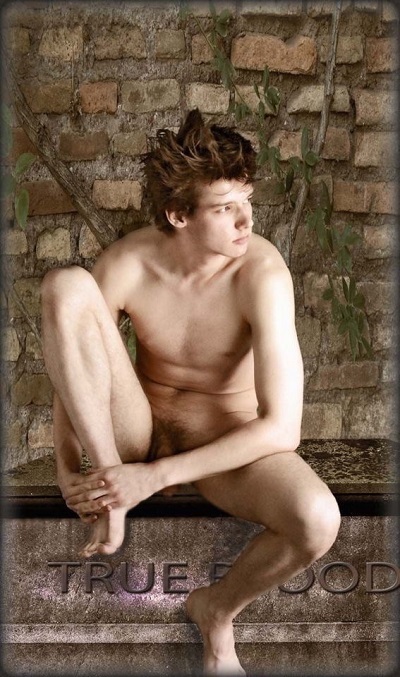 �@
�@
 �c
�c