04/01の日記
20:33
【吉本隆明】の宮沢賢治論――選ばれた者のユートピアか?誰でもの「さいはひ」か?(7)
---------------
.
こんばんは (º.-)☆ノ
〇 吉本隆明「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学―――解釈と教材の研究』,23巻2号,1978年2月号,学燈社,pp.6-29.
↑この論文を検討しています。連載第7回(最終回)。
(ニ)節のさいごで、吉本氏は↓つぎのように述べていました:
「詩語『雨ニモマケズ』のなかの難解な『ヨクミキキシワカリ ソシテワスレズ』の『ワカリ』という言葉はたぶんここ〔<善意>や<無償>の磁場を通って、宗教的な至上世界にいたること―――ギトン注〕に関連していた。それは<察知>そのままの場が<天上>のユートピアへゆくのだというかれのかんがえをあらわしていたと受け取れる。
もちろんここは宮沢賢治自身にとっても危ない通路であった。かれの作品の言葉がしばしば安易な形で宗教的な教説に堕ちてゆくところに通路の危うさがあらわれている。またかれが〔…〕その<無償>や<善意>を宗教的屈折に短絡させようとしたところにもあらわれた。
〔…〕<善意>や<無償>から宗教的な倫理や自己犠牲にと流れてゆく通路は、かれが心弱かったときに早急にいつも駆け抜けてゆく通路であった。」
「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,pp.25-26.
ここで吉本氏が言う宮沢賢治の「<天上>}とは、必ずしも死後の世界ではなく、悟りきった眼には、この世がそのまま<天上>に見えるというようなこと、つまり「『心理学』上の構想」としての賢治の「ユートピア」です。
たしかに、『春と修羅』公刊以前の段階では、宮沢賢治は、仏教の“悟り”ということについて、こう考えていたふしがあります: ふつうの人とは違った感性を持って、この世を「天上」世界のように見る(幻覚する?)ことができれば、それがすなわち最上の“悟り”(無上菩提)だ‥というような。。。
たとえば、「小岩井農場」の〔下書稿〕には、
「馬車の笛がきこえる、
石版画を持って来る。
それから私のこゝろもちはしづかだし
どうだらうこゝこそ天上ではなからうか
こゝが天上でない証拠はない
天上の証拠はたくさんあるのだ
そら遠くでは鷹が空を截ってゐるし
落葉松(ラリツクス)の芽は緑の宝石で
ネクタイピンにほしいほどだし
たったいま影のやうに行ったのは
立派な人馬の徽章だ
騎手はわかくて顔を熱らせ
馬は汗をかいて黒びかりしてゐた。」
という部分があります。
これは、公刊された初版本の「パート3」にあたる部分で、『農場本部』にさしかかったあたりですが、作者の挙げる「ここが天上」である「証拠」は、いずれも感性的なものです。なんでもない風景を、“ぼろぼろの服がビロードのきものに変る”感性で見ているというだけのことです。じっさいのこの場所の写真(↓)を見ると、なんでもない風景だということがよく判ります。⇒:農場への道(3)
とくに目立つ「証拠」は、さいごの「人馬の徽章」です。これは、当時『本部』のそばにあった馬場で、育成中の競走馬を訓練しているようすなのですが、「騎手はわかくて顔を熱らせ/馬は汗をかいて黒びかりしてゐた」と、作者の「天上」意識は、官能的な性欲感覚にまで結びついています。宗教的見地で見れば、これは問題があるはずです。

小岩井農場。 「こゝこそ天上ではなからうか」
賢治の立ち位置から『農場本部』方面を望む。
また、サハリン旅行(1923年8月)の途次の草稿「旭川」では、
「植民地風のこんな小馬車に
朝はやくひとり乗ることのたのしさ
『農事試験場まで行って下さい。』
〔…〕
こんな小さな敏渉な馬を
朝早くから私は町をかけさす
それは必ず無上菩提にいたる」
と書いています。
しかし、「小岩井農場」にしろ「旭川」にしろ、これらの下書き部分は、公刊本には採用されずに除去されています。ですから、賢治は、『春と修羅』公刊あたりを境として、“幻覚を見ることによって<如来>の真知に至れる、悟りに達することができる”というような考えからは脱却していると思うのです。
細かく言いますと、「小岩井農場」の〔下書稿〕は、「こゝこそ天上ではなからうか」以下を削除し、風景描写も大幅に縮めて公刊本のテキストに改稿されています。
そして、帰路には、(公刊本テキストでは)『本部』の手前で、近道(旧網張街道)のほうへ折れて駅へ向かいます。往きに「天上ではなからうか」と言った場所を、あえて避ける経路を選んでいるのです。この長詩の最終行の、
「わたくしはかつきりみちをまがる」
とは、『本部』の前を通らないショートカットのほうへ「まが」るということ、……「こゝこそ天上」だ、との“思いこみ”の場所を回避して、まっすぐに現実世界へ―――同僚が宿直している勤務先へと、向かうことを意味します。
また、「旭川」のほうは、作品全体が割愛されました。
したがって、賢治は、このような“特別な感性を持つことによって、「無上菩提にいたる」ことができる”という、吉本氏の言う「『心理学』上の」「ユートピア構想」からは、晩かれ早かれ離脱したと思われるのです。
◇ ◇
ここで吉本氏は、「宗教的な倫理や自己犠牲にと流れてゆく通路」「かれが心弱かったときに早急にいつも駆け抜けてゆく」「安易な形で宗教的な教説に堕ちてゆく‥通路」の例として、『注文の多い料理店』収録の童話『烏の北斗七星』を挙げていますので、これを検討してみたいと思います。
「つめたいいぢの悪い雲が、地べたにすれすれに垂れましたので、野はらは雪のあかりだか、日のあかりだか判らないやうになりました。
烏の義勇艦隊は、その雲に圧(お)しつけられて、しかたなくちよつとの間、亜鉛(とたん)の板をひろげたやうな雪の田圃のうへに横にならんで仮泊といふことをやりました。」
カラスの「艦隊」の“戦い”を描いたこの童話は、暗い雲の垂れこめた重苦しい空の描写ではじまります。
「烏の大尉はこちらで、その姿勢を直すはねの音から、そらのマヂエルを祈る声まですつかり聴いて居りました。
じぶんもまたためいきをついて、そのうつくしい七つのマヂエルの星を仰ぎながら、あゝ、あしたの戦でわたくしが勝つことがいゝのか、山烏がかつのがいゝのかそれはわたくしにわかりません、たゞあなたのお考のとほりです、わたくしはわたくしにきまつたやうに力いつぱいたゝかひます、みんなみんなあなたのお考へのとほりですとしづかに祈つて居りました。そして東のそらには早くも少しの銀の光が湧いたのです。」
↑“戦い”の前の夜、いいなづけの雌カラスが眠れない夜にうなされて「七つのマヂエルの星」に祈る声を、「烏の大尉」は、自分のねぐらから聞いています。
「マヂエル」とは、北斗七星のことです。大熊座のラテン語名 Ursus Major の Major を賢治流の読み方で読んだ呼称と思われます。『冬のスケッチ』では、大犬座 Canis Major を「カニスマゾア」と呼んでいます。ラテン語の正確な発音は「マヨル」ですが、賢治は「j」を濁って、「マゾア」「マヂエル」などと読んだようです。

「ふと遠い冷たい北の方で、なにか鍵でも触れあつたやうなかすかな声がしました。烏の大尉は夜間双眼鏡(ナイトグラス)を手早く取つて、きつとそつちを見ました。〔…〕その梢にとまつて空を見あげてゐるものは、たしかに敵の山烏です。大尉の胸は勇ましく躍りました。
『があ、非常召集、があ、非常召集』
〔…〕
もう東の空はあたらしく研いだ鋼のやうな白光です。
山烏はあわてて枝をけ立てました。そして大きくはねをひろげて北の方へ遁げ出さうとしましたが、もうそのときは駆逐艦たちはまはりをすつかり囲んでゐました。
「があ、があ、があ、があ、があ」大砲の音は耳もつんぼになりさうです。山烏は仕方なく足をぐらぐらしながら上の方へ飛びあがりました。大尉はたちまちそれに追ひ付いて、そのまつくろな頭に鋭く一突き食らはせました。山烏はよろよろつとなつて地面に落ちかゝりました。そこを兵曹長が横からもう一突きやりました。山烏は灰いろのまぶたをとぢ、あけ方の峠の雪の上につめたく横(よこた)はりました。
『があ、兵曹長。その死骸を営舎までもつて帰るやうに。があ。引き揚げつ。』」
ここに描かれた“山烏との戦い”の実際の状況を読んで、どうお感じになるでしょうか?
「あしたの戦でわたくしが勝つことがいゝのか、山烏がかつのがいゝのかそれはわたくしにわかりません」とまで言って祈った「烏の大尉」が、「敵」を発見したとたん、「勇ましく」胸を躍らせて向かった“戦い”にしては、あまりにも釣り合わない、読者の期待を裏切る“不正義の戦い”ではないでしょうか?
山烏1羽にたいして、里烏19羽が“戦い”をしかけ、必死に逃げる無抵抗の相手をつついて殺してしまう。しかも、「敵」は何も悪いことをしていませんし、こちらに危害を加える兆候さえ見られないのにです。
あまりにもひどい“弱い者いじめ”としか言いようがないと、ギトンには感じられます。童話のプロットのつくり方としては、致命的な失敗であるようにも受けとれます。
しかし、“童話”という結構をはずして、一歩退いて眺めれば、 ……里烏と山烏の“なわばり争い”でしかない、“戦い”の名にも値しない“戦い”を、「見たまま」「そのまま」描いているとも言えます。
皇軍の神佑の“戦い”、あるいは連合国(第1次大戦の)の“正義の戦い”などというものは、一歩退いて“<如来>の視線”で眺めれば、おおぜいで弱い者いじめをしているだけだ、‥という風刺と受けとってもおかしくないほどです。
もちろん、宮沢賢治が、風刺の意図でこの作品を書いたとは思われません。作品全体の重苦しいタッチや、このあと見る“戦い”のあとの厳粛な場面描写は、風刺とは調和しません。
吉本氏は、↑上の「烏の大尉」の独白:
「あしたの戦でわたくしが勝つことがいゝのか、山烏がかつのがいゝのかそれはわたくしにわかりません、たゞあなたのお考のとほりです、わたくしはわたくしにきまつたやうに力いつぱいたゝかひます、みんなみんなあなたのお考へのとほりです」
について、
「宗教的な屈折に短絡」する「危うさの淵にたっている」
と評しています。しかし、もう一歩ふみこんで、そのあと続いて行われる“戦い”という名の弱者迫害との不調和な関係についても、ふれてほしかった気がします。
「夜がすつかり明けました。
桃の果汁(しる)のやうな陽ひの光は、まづ山の雪にいつぱいに注ぎ、それからだんだん下に流れて、つひにはそこらいちめん、雪のなかに白百合の花を咲かせました。
ぎらぎらの太陽が、かなしいくらゐひかつて、東の雪の丘の上に懸りました。
『観兵式、用意つ、集れい。』大監督が叫びました。
『観兵式、用意つ、集れい。』各艦隊長が叫びました。
みんなすつかり雪のたんぼにならびました。
烏の大尉は列からはなれて、ぴかぴかする雪の上を、足をすくすく延ばしてまつすぐに走つて大監督の前に行きました。
『報告、けふあけがた、セピラの峠の上に敵艦の碇泊を認めましたので、本艦隊は直ちに出動、撃沈いたしました。わが軍死者なし。報告終りつ。』
駆逐艦隊はもうあんまりうれしくて、熱い涙をぼろぼろ雪の上にこぼしました。
烏の大監督も、灰いろの眼から泪をながして云ひました。
『ギイギイ、ご苦労だつた。ご苦労だつた。よくやつた。もうおまへは少佐になつてもいゝだらう。おまへの部下の叙勲はおまへにまかせる。』
烏の新らしい少佐は、お腹が空いて山から出て来て、十九隻に囲まれて殺された、あの山烏を思ひ出して、あたらしい泪をこぼしました。
〔…〕
烏の新らしい少佐は礼をして大監督の前をさがり、列に戻つて、いまマヂエルの星の居るあたりの青ぞらを仰ぎました。(あゝ、マヂエル様、どうか憎むことのできない敵を殺さないでいゝやうに早くこの世界がなりますやうに、そのためならば、わたくしのからだなどは、何べん引き裂かれてもかまひません。)マヂエルの星が、ちやうど来てゐるあたりの青ぞらから、青いひかりがうらうらと湧きました。」

花巻市下根子 賢治詩碑付近にて
吉本氏は、“戦い”のあとで、
「あゝ、マヂエル様、どうか憎むことのできない敵を殺さないでいゝやうに早くこの世界がなりますやうに、そのためならば、わたくしのからだなどは、何べん引き裂かれてもかまひません。」
とマヂエルに祈る「烏の大尉」について、
「<善意>や<無償>から宗教的な倫理や自己犠牲にと流れてゆく通路は、かれが心弱かったときに早急にいつも駆け抜けてゆく通路であった。」
と解説しています。つまり、宮沢賢治にとっては、戦争というものは、避けることのできない「自然法則」であり、宗教的な「法性(ほっしょう)」と同じであったという一般的な賢治観(西谷修「戦争」, in:『宮澤賢治イーハトーヴ学事典』参照 ⇒:16/9/25 シベリア出兵)に立脚しておられるようです。
しかし、直前に描かれた“戦い”の異常なありさまと重ねてみると、「わたくしのからだなどは、何べん引き裂かれてもかまひません」という「大尉」の祈りは、あまりにもむなしく響かないでしょうか?
不意に「大尉」の脳裏にうかぶ:「お腹が空いて山から出て来て、十九隻に囲まれて殺された、あの山烏」との想いは、<善意><無償>の象徴とも言うべき『祭の晩』の山男の悲しさを想起させないでしょうか?
自分の身体が「何べん引き裂かれてもかま」わないという“自己犠牲”の表白を、賢治は、いくつかの童話で主人公(たとえば、ジョバンニ)にさせています。しかし、そのどのシチュエーションでも、当の主人公は、じっさいに身体が「引き裂かれ」る目に遭うことなどありえない・安全な立場に身をおいているのです。
逆に、作品の中で“自己犠牲”を敢行するグスコー・ブドリは、その生涯に一度たりとも、この種の“自己犠牲”の大言壮語を語ったことがありません。
この“自己犠牲”の表白は、はたして作者自身の思想だと言ってよいのか? むしろ、作者にとってはカリカチュア(風刺)ではなかったか?‥これは、いちど考えてみなければならないことだと思います。
そういう点から、この童話を読みなおしてみると、吉本氏は言及していない↓つぎのような箇所が目に止まります。
これは、“戦い”の前の「大尉」の独白よりも前の部分で、夜になって月が出たことを書いているのですが、前後の風景と釣り合わず、“戦い”を前にした烏の軍隊の厳粛さともまったく折り合わない・異常な光景が挿入されているのです:
「夜になりました。
それから夜中になりました。
雲がすつかり消えて、新らしく灼(や)かれた鋼の空に、つめたいつめたい光がみなぎり、小さな星がいくつか聯合して爆発をやり、水車の心棒がキイキイ云ひます。
たうとう薄い鋼の空に、ピチリと裂罅(ひび)がはひつて、まつ二つに開き、その裂け目から、あやしい長い腕がたくさんぶら下つて、烏を握(つま)んで空の天井の向ふ側へ持つて行かうとします。烏の義勇艦隊はもう総掛りです。みんな急いで黒い股引をはいて一生けん命宙をかけめぐります。兄貴の烏も弟をかばふ暇がなく、恋人同志もたびたびひどくぶつつかり合ひます。
いや、ちがひました。
さうぢやありません。
月が出たのです。青いひしげた二十日の月が、東の山から泣いて登つてきたのです。そこで烏の軍隊はもうすつかり安心してしまひました。」
ごらんのとおり、<如来>などとはとうてい言えない、ゆらゆらと不気味にゆれる・どす黒い「長い腕」のイメージです。
この童話集『注文も多い料理店』の「序」で作者が言う:
「なんのことだか、わけのわからないところもあるでせうが、そんなところは、わたくしにもまた、わけがわからないのです。」
とは、こういう部分を指しているのだと思われます。
しかし、この「わけのわからないところ」を、これは作者にとっても「不可知」の「聖領域」なのだ―――などと決めつけてしまっては、この作品の本質がわからなくなります。一種の“大宗教論”に足をとられることになるでしょう。
この部分は、作者にとっては、いわば無意識の挿入だったのだと思います。賢治としては、どうしても、こういう場面を入れずにはいられなかったのでしょう。「序」の言い方で言えば、
「もうどうしてもこんな気がしてしかたないのです。ほんたうにもう、どうしてもこんなことがあるやうでしかたないといふことを、わたくしはそのとほり書いたまでです。」
ということになります。
“戦い”と呼ぶには不釣り合いな弱い者いじめを、あたかも正義であるかのように厳粛に執り行う“烏の軍隊”を描きながら、作者のバランス感情は、天の「裂け目」から伸びてきた「あやしい長い腕」が烏たちを拉致してゆく光景、また、襲われた烏たちが、自分が助かろうとして家族同志、恋人同志でぶつかり合うような混乱に陥る状況を描かずにはいられなかったのではないでしょうか?
これも、一歩退いて見れば、“烏の軍隊”に対する風刺と見られなくはありませんが、これを書いた時の作者に風刺の意識があったとは思われません。無意識に、ただ「どうしてもこんな気がしてしかたない」ことを書くという意識であったと思います。
もっとも、賢治が『料理店』の「序」を書いた 1922年12月20日(『烏の北斗七星』の作品日付 1921年12月21日の1年後)までには、挿入部分の風刺的な、あるいはバランス感情的な意味に気づいたはずです。
それでも、「わたくしにもまたわけがわからないのです。」と賢治が「序」に書いたのは、あえて作品意図を隠すためであったと考えます。もしここで“意図しなかった作品意図”をあからさまに書けば、この童話は“反戦文学”になったかもしれませんがw‥、そのような評価は彼にとって心外だったでしょう。
◇ ◇
このように考えてみると、私たちは、この童話が、『祭の晩』や『猫の事務所』と似た構造をもっていることに気づきます。
いま、『烏の北斗七星』と『猫の事務所』の対応関係を表にしてみますと、つぎのようになります。
『猫の事務所』 ―――――――― 『烏の北斗七星』
獅子 ―――――――― マヂエル
かま猫 ―――――――― 山烏
「事務所」の猫たち ―――――――― 「大尉」をふくむ「烏の艦隊」
かま猫に対する“いじめ” ―――――――― 山烏との「戦い」
獅子の出現 ―――――――― 月の出:空の裂目から伸びる「長い腕」
獅子に叱咤された猫たちの混乱 ―――――――― 「長い腕」に襲われた烏たちの混乱
宮沢賢治は、『注文の多い料理店』の広告文のなかで、『烏の北斗七星』について、「戦ふものゝ内的感情」を描いたものだと紹介しています。
しかし、そのような表向きの、いわば意識された作品意図をつきやぶって、無意識にあふれだしてしまうものこそ、私たちの注目に値します。そこには、栗谷川虹氏の指摘する“異界を見る者”としての賢治の視線(⇒:『ゆらぐ蜉蝣文字』5.3.3〜)が見られるからです。
(ホ)宮沢賢治は、『法華経』が説く唯一全知の「如来性」、なかんずくその<察知>の能力をわがものにしようと努力したが、そうした努力も、けっきょくは「心理学」上の「仮設」にすぎず、「不可知論的なユートピアを導くだけだ」という「沸きあがる懐疑」を、賢治はさいごまでふりきることができなかった。――― p.26下段第3段落 〜 p.29
この最後の節で、吉本氏は宮沢賢治の“宗教問題”全般を論じていますが、前の節までの考察とは少し観点がずれてしまっている印象を受けます。
しかし、ともかくまずは、吉本氏の主な論筋を追ってみたいと思います。
「『法華経』が説いている思想のうち宮沢賢治を魅了したのは、宇宙には唯一の如来性があって、あらゆる存在が、それぞれの時間と空間のある状態で何をかんがえ、どういう意志をもっていて、なにをしようとしているか、ことごとく<察知>しているという考えであった。〔…〕
この如来性はけっきょくは実体もなく、生成も死滅もなく、障礙もない虚空のようなものなのだが、〔…〕大乗という概念はこの如来性にむかって、人々をあわれみ包みこみ安楽にさせ済度しながら解脱させることを意味している。
そのためにじぶんの身体を粉末にして使駆するものがあれば菩薩とよばれるべきである。『法華経』が菩薩にむかって説かれた経文だという経文自体の言説を、宮沢賢治は文字通り、信じてやまなかった。〔…〕かれは信じたものになろうとするじぶんの行為の全体性を文字通り信じた。
ここにかれの作品と生涯の悲劇があった。〔…〕宮沢は『法華経』のいうそのままの意味で、菩薩に自分を擬した。現実の生身の生活を、むしろ菩薩という架空の鋳型のなかにはめ込んだ。これはあらゆる理想主義の悲劇とまったくおなじにはちがいない。けれど〔…〕その悲劇はどこにも、もってゆきようがなかったから、自然の景観に流入する感性によって白熱した空虚を紡ぎ出したともいえる。」
「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,pp.26-27.
このへんを読むと、吉本氏の宮沢賢治観は、やはり《第Ⅱ期》のものだな‥という感じがします(⇒:宮沢賢治の読まれ方──3つの時代:『ゆらぐ蜉蝣文字』0.2.2〜)。“聖人伝説”をほぼ額面どおりに受けとったうえで、それは人間として無理をしている‥と否定的に評価します。
しかし、賢治という人は、表向きの禁欲的・聖者的な大言壮語と、じっさいのかなり気ままな生活とのあいだに距離のある人だったことが、しだいに明らかになってきています。私たちは、“聖人伝説”を信じないのと同様に、吉本氏のような賢治観にも違和感を感じます。
賢治にとって気まま(気まぐれ)な生活も、本人の質素な趣味や、同性愛志向、また道義的で聡明な性格のために、周りの人びとには、“大言壮語”との懸隔を感じさせなかったのでしょう。
「現実の生身の生活を、‥菩薩という架空の鋳型のなかにはめ込んだ」という吉本氏の賢治像は、仮想された“聖人”生活を、「現実の生身の生活」だと思ってしまったために生じた虚像と言えます。しかし、これは吉本氏の特徴的な宮沢賢治観であり、《第Ⅱ期》のひとつの極であろうと思います。
「宮沢賢治はあらゆる存在の現に意志していること、おかれている状態、そうする行為をことごとく<察知>している宇宙意志のような如来というかんがえ方を、『化城喩品』にある手段としての超能力というかんがえで独特に組み替えた。〔…〕『心理学』上の超能力の喚起によって、個々の存在がどんな段階でなにを、どのように願望しつつあるか、その願望のうちで、それぞれの存在の仕方に無矛盾な、もっとも望ましい状態はどういうものか。これを幻燈のように念写することができるのではないか。〔…〕というかんがえ方に傾いたといえる。
この意味では『銀河鉄道の夜』はかれの方法で試みたかれの『化城喩品』にほかならなかった。かれはここで『ブルカニロ博士』の超心理学的な実験でジョバンニの幻覚に出現した光景という形で、幻想の銀河鉄道に乗った人々の究極の願望のようなものを照らしだしてみせた。〔…〕『ブルカニロ博士』は宮沢賢治自身であるとともに、宮沢的にかんがえられた<如来>にほかならなかったといえる。そして『銀河鉄道の夜』という作品で実現される光景は、すくなくとも『ブルカニロ博士』だけには自在に統御され見透されているという構想がひとたびはとられた。」
「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,pp.27-29.
つまり、宮沢賢治は、<如来>の「一切種智」の<察知>力を、一種の超能力のように考え、特殊な世界を幻視するような感性、あるいは時空をあまがけるような想像力を身につければ、<如来>に近づける―――最上の“悟り”に至れると考えた‥と言うのです。
そして、そのような<察知>力によって見た世界を描いたのが、賢治の諸作品にほかならないということになります。
そこで重要なのは、「ブルカニロ博士」の存在です。「ブルカニロ博士」とは、作品の世界とそこに描かれた人物すべて、その行動すべてを、「自在に統御」し「見透」している<如来>そのものなのです。
「この構想が『法華経』の理念をあまりに『心理学』上の睡眠幻覚や超能力の問題に引き寄せていることを宮沢賢治自身はたぶん危惧したにちがいない。〔…〕
『ほんたうの考とうその考を分け』るために、科学的な実験のようにたしかな実験の方法がわからなければならぬ。そうでなければ<ほんたうの幸>をもとめるといっても、ただの不可知論的なユートピアを導くだけだ。
その実験の方法はどこにもとめればいいのか。存在するものすべて(自分や自分の考えや汽車やその学者や天の川や、それから歴史や)の状態と、意志や願望や行為のすべてが判り、そして見透すことができるもの(如来性)がはっきりと手につかめなければならないことは確実である。そしてさしあたりそれを『心理学』に類した内的構成にもとめるより仕方がないというのが、宮沢賢治がおそるおそる提示したユートピア思想であった。そしてそっと抹消の線をひいてみせた仮設でもあった。
ここのところで沸きあがる懐疑を捨てて、宇宙意志のようなものと一体になろうとし、<なれる>、<そうなれる>と呪文のように自己に言いきかせながら、そのようにじぶんの短い生涯を追い込もうとした。そこに宮沢賢治のもっとも巨きな動揺が存したのである。」
「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,p.29.
吉本氏の考えでは、『銀河鉄道の夜』に描かれた銀河の世界は、賢治の「無上菩提」の世界にほかならないわけですから、それが単に想像力や超能力で造作された絵空事にすぎないということになると、これはもう賢治の信仰を根底からゆるがすことになります。
そこで、賢治は、自分の想像する世界が“正しい”ことを、物理や化学のような「実験」で証明しなければならないと――吉本氏によれば―――考えることになります。
もちろん、そんな「実験」ができるわけはありませんw
そうすると‥もうひたすら信じるしかない‥ということになって、これはもはや「不可知論」です。どうして正しいのかわからないから正しいのだ‥と「呪文のように自己に言いきかせ」ることになります。あるいは、「宇宙意志のようなものと一体になろうとし」、自分は「宇宙意志」なのだから、自分に見えるものは宇宙の「ほんたう」の姿だ―――と確信することになります。
そういう“狭い世界”の中へ「じぶん‥を追い込もうとした」のが、宮沢賢治の「短い生涯」であった、というわけです。
宮沢賢治は、『銀河鉄道の夜』で、いったん「提示したユートピア思想」に「そっと抹消の線をひいてみせた。」と、吉本氏は書いていますが、これは、この童話の〔第3次稿〕から〔第4次稿〕(最終形)への改稿を指しています。
この改稿で、「ブルカニロ博士」が出てくる場面は全部抹消され、「ほんたうの考とうその考を分け」る「実験」について学者風の男がジョバンニに語る部分も消されます。そして、冒頭の「午後の授業」、ジョバンニがアルバイトをしている「印刷所」の場面、最後の、河岸でカムパネルラの水死を確認する場面、牛乳店への再訪など、地上での生き生きとした生活場面が書き加えられます。
したがって、吉本氏の言うところとはズレるのですが、この〔第4次・最終稿〕への改訂は、「そっと抹消の線をひい」たどころではなく、賢治の大幅な構想変更による確定的な転換と言わなければなりません。

この“大転換”のカナメはやはり、「『銀河鉄道の夜』という作品で実現される光景は、‥『ブルカニロ博士』だけには自在に統御され見透されているという構想」が全面的に放棄されたことでしょう。そのことによってはじめて、ジョバンニは、“絶対者”<如来>の操り人形から、現実の地上で自分の意志をもって生きる生身の少年になったと言えます。
〔第3次稿〕のさいごで、“地上”に降りて来たジョバンニの前に「ブルカニロ博士」が現れて、“じつは心理学(テレパシー)の実験をしていたのだ。”と“種明かし”をすると、ジョバンニは、嬉々としてアルバイト料の金貨をもらって帰ってゆく―――――この場面の嘘っぽさは、銀河での全場面の感動を帳消しにしてしまいます。ギトンは、読むたびにそう感じます。宮沢賢治も、この“嘘っぽさ”が、ずっと気になっていたのではないでしょうか?‥
しかし、吉本氏の言うように、「『ブルカニロ博士』は宮沢賢治自身であるとともに、宮沢的にかんがえられた<如来>にほかならなかった」のだとすれば、〔最終稿〕への転換は、「如来」の否定でなければならないことになります。
「そっと抹消の線をひい」たどころではないのです。
この“転換”の意味は、この作品の構造としても、作者の宗教観の問題としても、もっと考えてみる必要がありそうです。
◇ ◇
以上、いろいろと異論も述べてきましたが、吉本隆明氏のこの論文は、私たちが賢治作品を読むにあたって、さまざまなヒントを与えてくれるものです。
吉本氏は、1970年代以降に現れた新しい賢治資料と、新しい観点からの賢治研究を、十分に吸収していないうらみがあることは否定できないでしょう。そのためか、《第Ⅰ期》の“聖人伝説”と、《第Ⅱ期》の“心理主義”から抜け出せず、足を引っぱられている傾向があります。
しかし、そうした消極面をおぎなってなおあまりある鋭い洞察が、この論文の随所に輝いていることもまた、たしかなのです。
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]







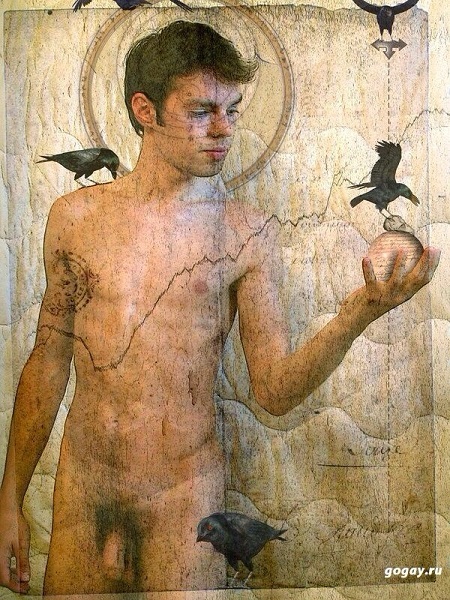

 彡
彡