03/12�̓��L
15�F52
�y�{���z�u�݂�ȁv�ƓƉ�ƃA�C�h���Ɛ��q��
---------------
.
 �@
�@
�@�����́B(º.-)���
�i�T�j�������Ր������Ă����B
�@��i�́A��ƌl�̓����̎�ϓI�c�ׂƂ��đn�삳��A���e�X��l�̓ǎ҂ɂ���ē����ɋ����\�\�\�Ƃ������Ƃ��A�Ñ�E�����̕���Ƃ͈قȂ�ߑ㏬���̓����ł���ƌ����܂��B����������́A�ߑ㎍�̂����ӂ��߂��ߑ㕶�w�̒ʗL���ł���ƌ����Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�W�c�̂Ȃ��œ`���Ƃ��Đ��܂�A�W�c�̏�Ł\�\�������ŁA���邢�͏j�Ղ̏�Ł\�\���ꂽ�O�ߑ�̕��w�ɂ͂Ȃ�������҂Ɠǎ҂̈ӌ��̕���Ƃ�����肪�A�����ɐ����܂��B
�@�����⎍�̂�n�邱�Ƃ́A�����܂ł���҂̌l�I�ȉc�݂ł���B��҂́A���ȂЂƂ�̈ӌ��ɒ����ɏ]�����Ƃ��ނ���]����A��̈ӌ���\�z���đn�삷�邱�Ƃ́g��O�ւ̌}���h�Ƃ��Ĕᔻ�����B
�@���������āA�������đn�삳�ꂽ��i�́A�g�����������̂��ǂ݂����h�Ǝv���Ă���ǎ҂̈ӌ��ɍ��v����Ƃ͌���Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�@��������ƁA���������ɑ�ƂƂ��Đ������̍�i�\���A����炪�����̐l�ɂ���ēǂ܂���Ƃ����݂���Ƃ��������́A�ǂ��l������悢�̂ł��傤���H�d�����炭�A�Q�Ƃ���̂��Ƃ��l�����܂��B
�@�ЂƂ́A���̍�Ƃ̈ӌ����A������̑����̓ǎ҂̈ӌ��ƁA���܂��܍��v���Ă���Ƃ����ꍇ�ł��B�܂�A����̃g�����h�ɍ��v������i�����������ɁA��҂͗z�̖ڂ�����ƌ����܂��B�����Ă��̍�i�������ꂽ���̂ł���A��҂̕]���͍��܂�ł��傤�B��i���g�����h�ɍ��v���邱�Ƃ́A�g��O�ւ̌}���h�Ƃ͈Ⴂ�܂����A���w�́g���O�ҁh���猩��A�g��O��Ɓh������i�����ꏊ�ŁA�������傭�������Ƃ����Ă���悤�ɂ������܂��B
�@������g���d�h�g���d�h�Ȃǂ̌��Ђɂ��g���n�t���h���A���������g�����h�̈��ƍl�����܂��B���ЋƂ������̂��A�L���Ӗ��ŎЉ�̐����̈ꕔ�ł���A��O�̈ӌ��Ƒ�������Ă͂��Ă��A����̃g�����h�̂ЂƂ̗�������o���Ă���ƌ����邩��ł��B
�@����ɑ��āA��Ƃ̂ق����g�����h����肵�āA�����i������̃g�����h�����o���Ă䂭�Ƃ����ꍇ�����邩������܂���B�������A�����������Ƃ��\�ɂȂ邽�߂ɂ́A�����Ȃ��Ƃ����̍�i�͓ǂ܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ɁA�ߑ�ɂ������i�̔��\�`�ԁ\�\�\�R�X�g�Ɖ��i�����v�������x�z����s��@�\�ւ̈ˑ��A���邢�́A�s��O�ɂ����Ă͍��Ƃɂ�鐭���I�Ȍ��ЂÂ��̈З́\�\�\�̕ǂ������͂������Ă��܂��B
�@���̂悤�ɋc�_����ƁA�����炭�����̕��́A���̂悤�Ɍ����Ĕ��_�����ł��傤�B�����ꂽ��i�́A�N��������������͂������Ă���̂��B�X�̓ǎ҂̈ӌ��Ƃ͂������Ȃ��A�����ꂽ��i�́A�����Ȃ��Ƃ������̓ǎ҂ɂ���Ē��ڂ����͂��ł���B�����āA�ǂl�����̊��z�͏��X�ɓ`�����A�������ɑ����̐l���ǂނ悤�ɂȂ邾�낤�B�ނ���A�����ꂽ��i�́A����ɐڂ����ǎ҂̚n�D��ς��Ă䂭�̂��A�ƁB
�@�܂��t�ɁA���̂悤�ɂ��l�����邩������܂���B��҂Ƃ����ǂ��g����̎q�h�Ȃ̂ł���ƁB�ǎ҂Ɠ�������̋�C���z���Đ^���ɐ����A�^���ɍ�i�݂����Ă���Ȃ�A�ꌩ���Ă����Ɏ���̗v�����炩���͂Ȃꂽ��i�Ɍ����悤�Ƃ��A���Ȃ炸�⓯����ɐ�����l�̐S���Ƃ炦��͂��ł���B
�@���āA�����ŃM�g���́A���w�_�c�����悤�Ƃ����̂ł͂���܂���B�����A�{���Ƃ�����Ƃɂ��čl���Ă݂����̂ŁA����Ȑ�����ŏ��ɒ��Ă݂��̂ł��B
�@�{���́A������̎��A�Z�́A���b�̃g�����h����́A���悻�������ꂽ���̂������Ă����悤�Ɏv���܂��B
�@�������ɁA�������܂��g����̎q�h�ł͂���܂����B������̎Љ�₻�̎v���̉e���������Ȃ��琶�����A�v�z������Ă����ƌ����܂��B���̂��Ƃ́A�H�}���ێ��A��ؒ������ɂ���ċߔN�܂��܂����炩�ɂ���Ă��܂����B�������A���Ɣނ̍�i�Ɋւ��ẮA��������̑��̍�Ƃ⎍�l�̏��������̂ƕ��ׂĂ݂�ƁA�قƂ�ǎ������̂��Ȃ����Ƃ��܂����炩�Ȃ̂ł��B�{���́A���{�ߑ㕶�w�j�̂ǂ̌n���ɂ�����Ȃ��Ǝ����̋�����Ƃł���\�\�\�Ƃ������Ƃ́A����ɂ��ł͕��w�j�̏펯�ƌ����܂��B
�@�ǂ����č�i���A�ق��̍�ƂƈႤ�̂��H�d���낢�뗝�R�͂���ł��傤����ǂ��A������傫���̂́A��҂ł��錫�����g���A������̎��⓶�b�̃g�����h�Ƃ������̂��A�܂������C�ɂ����Ă��Ȃ������A�������Ă������Ƃ��傫���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�Ƃ��ɖڗ������˔\�̂Ȃ����}�Ȑl�\�\���Ƃ��Εۍ�Ó��̂悤�ȁA���邢�̓M�g�����܂߂āA���܃l�b�g�ɂ��ӂ�Ă��鐯�̐��قǂ̂a�k��Ƃ�g���㎍�l�h�̂悤�Ɂ\�\�ł���A���̏������̂́A�����Ɠ�����̍�Ƃ̈����ƂȂ炴������܂���B��]�̂����Ƃӎ��̂���{�Ƃ��ď����ȊO�̋Z�ʂ́A�}�l�ɂ͂Ȃ�����ł��B
�@�������A�����ł͂Ȃ��āA��}�ȍ˔\�����҂��g�����h�����đn�슈���������Ȃ����ꍇ�ɂ́A���������ǂ�Ȑ��E�����o����̂��\�\���̂��Ƃ�g�������Ď����Ă��ꂽ�̂��A�{���Ƃ�����ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�����́A����Ƀg�����h�����邾���łȂ��A�����ăg�����h�ɍ���Ȃ���i���Ԃ��āA�g�ǂ�̔w��ׁh�̂悤�ȑ��̍�Ƃ����̏������̂��������Ă���悤�ɂ݂��邱�Ƃ�������܂��B���Ƃ��A���́w�ǂ�ƎR�L�x�́g��Y�̔����h�́A���b���d�ɑ��錫���̒����ƌ����Ă��悢���̂ł��B
�@�{���Ƃ�����Ƃ́A���̖��d�Ƃ������鎩�M�́A���������ǂ����痈�Ă���̂��H
�@�����炭�A�ނ͂����l���Ă����̂��Ǝv���܂��B�������ɁA�{���l�̎Ƃ����g�S�ہh���E�́A�ނЂƂ�̎v���Ȃ��ɂ����ʂ��̂�������Ȃ��B�������A����Ђƌl�́g�S�ہh�́A�����^���ɁA����̂܂܂ɎƂ��ĕ\�����邱�Ƃ��ł����Ȃ�A����͒N�ł��ɒʂ��镁�ՓI�Ȃ��̂��܂�ł���ɂ������Ȃ��A�ƁB

�@���̂��Ƃ����I�ȃR�g�o�ŕ\�������̂��A���������w�t�ƏC���x�̙����ɒu���ꂽ�u�����v�ł������Ǝv���̂ł��F
�u�킽�����Ƃ��ӌ��ۂ�
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�i�����铧���ȗH��̕����́j
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@���i��݂�ȂƂ������
�@���͂������͂������ł��Ȃ���
�@�����ɂ��������ɂƂ���Â���
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�ЂƂ̐��Ɩ��ł�
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�������k�c�l
�@�i���ׂĂ킽�����Ɩ��ł�
�@�@�݂�Ȃ������Ɋ�������́j
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@���̂Ƃق�̐S�ۃX�P�c�`�ł�
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@���U�������ɋL�^���ꂽ�����̂�������
�@�L�^���ꂽ���̂Ƃق�̂��̂�������
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@������x�܂ł݂͂�Ȃɋ��ʂ������܂�
�@�i���ׂĂ��킽�����̒��݂̂�Ȃł���₤��
�@�@�݂�Ȃ̂��̂��̂̂Ȃ��̂��ׂĂł�����j�v
�w�S�ۃX�P�b�` �t�ƏC���x�u�����v���B
�@�g�l�̓Ɖ�I�S�ۂƕ��Ր��h�Ƃ������ɂ��ڂ��āA�u�����v���甲���������Ă݂܂�����
�@�܂Ƃ߂܂��ƁA�����ł̌����̎咣�̗v�_�́A���̂S�ɂȂ�Ǝv���܂��F
�@�@�@����������҂ł���u�킽�����v�Ƃ́A�u�����铧���ȗH��̕����́v�ł����āA�P�Ȃ�Ɖ�ł͂Ȃ��B�ߋ��E���݂̂��܂��܂Ȑl������╨�̎�ς����肱�����I�ȁu���ہv�ł���B
�@�A�@���́u�S�ۃX�P�b�`�v�́A�P�Ȃ�u�킽�����v�ЂƂ�̊��z��L�ł͂Ȃ��A�u�킽�����v���u���i��݂�ȂƁv�������Ɂu���Łv���������u�L�^�v�Ȃ̂ł���A�u���ׂĂ킽�����Ɩ��ł��^�݂�Ȃ������Ɋ�������́v�ł���B
�@�B�@���������āA�u�L�^���ꂽ�����̂������́v�u������x�܂ł݂͂�Ȃɋ��ʁv������̂ł���B�u�킽�����v�̐S�̂Ȃ��ɕ����l�I�Ȏv�O�Ȃǂł͂Ȃ��̂ł���B
�@�C�@�Ȃ��Ȃ�A�u���ׂĂ��킽�����̒��݂̂�Ȃł���₤�Ɂ^�݂�Ȃ̂��̂��̂̂Ȃ��̂��ׂĂł�����v�B���Ȃ킿�A�u�킽�����v�̎�ς̂Ȃ��Ɂu�݂�ȁv�����݂���悤�ɁA�u�݂�ȁv���ꂼ��̎�ς̂Ȃ��ɂ��A�u�킽�����v���܂u�݂�ȁv�����݂���B�����Ă����́A�Ă�łɂ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�u������x�܂ł́d���ʁv����ЂƂ̐��E���`�Â����Ă���B
�@�����́A�����Ƃ��̂悤�Ɏ咣���Ă��܂��B�������A���̎咣�̓X�W���ʂ��Ă���̂ł��傤���H�d���̂����A�[���ł��Ȃ��Ƃ���͂Ƃ��Ƃ�l�߂Ă݂����Ǝv���܂��B
�@�@�́A�����Ă݂�Β��ۓI�Ȍ��O�_�ŁA�ϔO�I�Șg�g�݂ƌ����ׂ��ł��傤�B�l���Ƃ̋�̓I�ȁu�S�ہv�̓��e�������ɂȂ邱�Ɓc�c�����Ȃ��Ƃ��݂��ɗ����ł�����̂ƂȂ邱�Ɓc�c��ۏ�����̂ł͂���܂���B
�@�����ŁA�A���d�v�ɂȂ�̂ł����A�����ō�҂������u���i��݂�ȁv�Ƃ́A��҈ȊO�̐l�Ԃ���Ƃ��đz�肵�Ă���̂��A�����łȂ��̂��B���Ȃ��Ƃ��A���́w�t�ƏC���x���^�̏���i���������A��҂̌����̑Ώۂ́A�����ς玩�R���⓮�A���ł���悤�ł��B��҂Ƒ��̐l�ԂƂ̂������ɂ́A���ɋ����������ۂ��܂��B���ۓI�ɂ͂Ƃ������i���Ƃ��A�m���̏�Ԃɂ����Ēʏ�̈ӎv�a�ʂ̂ł��Ȃ����ɑ����҂̓ƒf�I�Ȏv������Ȃǁj�A��̓I�Ȏ��͂̐l�X�Ƃ̌����ɂ��ẮA�ނ��낻�ꂪ���܂������Ȃ����ƂɔY�ނ悤�����`����Ă���ƌ����܂��B�˂ɍs���Ⴂ�Ɗ����̂Ȃ��ɂ���ƌ����Ă悢�B
�@��҂��A���Ƃ�������ʐ����⎩�R���i�ƌ������邱�Ƃ��ł�������Ƃ����āA���ꂾ���ł́A�u�킽�����v�́s�S�ہt�̌������͕ۏ���Ȃ��ł��傤�B�Ȃ��Ȃ�A���́g�����h���̂��A��҂̒P�Ȃ�v���Ȃ��ł͂Ȃ����Ƃ��m���߂��i�\�\���Ƃ��A����u�������ɔނƂ����������������Ă���v�Ə،�����Ƃ������\�\�͖�������ł��B
�@�������ɁA���^����i�Ɂu�L�^���ꂽ�v�Ƃ��������ƁA�g���R�h�����łȂ��g���ҁh(���̐l�ԁj������Ă͂���̂ł����A��҂̌����u���Łv���̂��A�u�킽�����v�̏���Ȏv���Ȃ��ł͂Ȃ��ƕۏ�����̂́A��������܂���B
�@�C�Ɏ����ẮA�_���I�ɔj�]���Ă��܂��B�����ō�҂������Ă���̂́A�e�l�����ꂼ��A�����ƐڐG�̂��邷�ׂĂ̐l�i����ѓ��A���A���R���j��\�ۂ��Ă���Ƃ������Ƃɂ����܂���B���ꂼ�ꂪ�A���ꂼ��̐l�̏���Ȏv���Ȃ��Ȃ�A�e�l�́s�S�ہt�������ɂȂ�ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�@����ł́A�B�̊m�M�́A���������ǂ����炭��̂��H
�@�����ŁA���炽�߂ćA���������܂��ƁA�����̑Ώۂ́A���̑啔�����g������ʁh���݂��Ƃ��Ă��A���̐l�Ԃ��u�킽�����v�Ɠ��l�ɁA���͂̐��E�ƌ����������Ȃ��琶���Ă���͂��ł���B�����A�u�킽�����v�ȊO�̐l�Ԃ͂��̂��Ƃ��\���Ɉӎ����Ă��Ȃ��B�w�����̑��������X�x�u���v�y�сu�L�����v�ɂ��A�g���Ƃȁh�Ƃ��Ă̊O�ʓI���������A���E�Ƃ̌����ɋC�Â��̂�W���Ă���B
�@�Ƃ͂����A��҈ȊO�̐l���A��҂Ɠ��`�̑��݂Ƃ��Đ����Ă���̂ł����āA�ӂ��Ζ��ӎ��̂����ɍs�Ȃ��Ă��鐢�E�Ƃ̌����ɁA�����C�Â��Ȃ�A��҂̃X�P�b�`�����u�S�ہv�Ɓu������x�܂ł́d���ʂ���v���E�ɂ��邱�Ƃ��A�N�����F�߂�͂��ł���B�\�\�\�����炭�A���̂悤�Ȍ��ʂ����A�����͂����Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@
�@�����l�����邱�Ƃ́A���Ƃ��A�{���j�����`���遫���̃G�s�\�[�h�̂悤�ɁA�ނ́A�l�Ɛl�Ƃ̊Ԃ̃R�g�o�ɂ��R�~���j�P�[�V�������������A�g���R�h�����Ē��ڐl�Ɍ�点�邱�Ƃ��D�\�\�\�Ƃ������Ƃ�����A������Ǝv���̂ł��F
�u�w�܂��A�R�����������Ȃ����x
�@�Ƃ����Z���t���A�����̌������̈�������ƁA�����̓������ł��������q�g�������q�����Ă�����B
�@�����͂���Ƃ��A���́w�C�M���X�C�݁x�̐����ɂ��Ă̎�����A�����ɂ����Ƃ���A��ɂ���āA
�@�w���[�A�܂��A�����Ă݂悤�x
�@�ƌy�����Ȃ���āA���̗��X���̋x�݂̓��ɁA�Ƃ��Ƃ��C�M���X�C�݂̒����Ɉ����ς�o����Ă��܂����Ƃ����B�v
�{���j�w�{�� �n�w�ƕ��w�̂͂��܁x,1977,�ʐ��w�o�ŋ�,p.100.
�@�{���̏ꍇ�ɂ́\�\�\���̕��w�҂�N�w�҂Ƃ������āA��w���łȂ��������Ƃ��傫���Ǝv���̂ł����\�\�\�A�g�o�������h�u�킽�����v�ƈ�ʐl�Ƃ̂������̋������A�������đ傫�����̂Ƃ͍l���Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�킽�����v�̍l���邱�Ƃ́A�Ƃ肽�Ăē�����ƂȂǂł͂Ȃ��A���̐l�X�ɂ��e�Ղɗ��������ɂ������Ȃ��ƁA�͂��߂��猈�߂Ă������Ă����ӂ�������܂��B
�@�����ɃX�P�b�`���ꂽ�u�S�ہv���E�́A����Δ����́g�n���h�ɂ����āu���̂܂܁v�Ƃ炦��ꂽ���̂ɂق��Ȃ�Ȃ�����A����͖��l�ɋ��ʂ���͂����A���ƂȂ́u�ڋ��ȁv�ϔO����苎���Ă��Ȃ��ɓǂ߂A�N�ɂł������ł���͂����ƁA�ނ͌��߂Ă������Ă����̂��Ǝv���܂��F
�u�����͌����ċU�ł�����ł��ޓ��ł��Ȃ��B
�@�����̍ēx�̓��Ȃƕ��܂Ƃ͂��Ă��A�������ɂ��̒ʂ肻�̎��S�ۂ̒��Ɍ��͂ꂽ���̂ł���B�̂ɂ���́A�ǂ�Ȃɔn�����Ă�Ă��A����ł��K���S�̐[���ɉ��Ė��l�̋��ʂł���B�ڋ��Ȑ��l�����ɕL��s���ȏ�ł���B�v
�@�������������̐M�O���A���ۊw�ɂ�镪�͓I�v�l�ɏ悹�Ď���Ƃ��A�������́A�n���́g�g�̐}���h�̋��ʐ�����A����E����́g���ݎ�ϐ��h����b�Â��Ă������Ƃ���A�t�b�T�[�����烁����=�|���e�B�Ɏ��闬���z���N�����܂��F
�u���̃��i�h�������I�i���G���j�Ɏ��̃��i�h���番���u�Ă��Ă��邱�Ƃ͊m���ł���B�k�c�l�������Ȃ��瑼���ŁA���̍����I�ȋ��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ����ꂼ��̃��i�h�������I�i���G���j�ɂ͐�ΓI�ɌǗ���������̂ł���Ƃ��Ă��A���҂̌����������̌������̂����ցA����ݓI�i�C���A�[���j�Ɏu���I�ɓ��荞��ł��邱���k�c�l�����ł́A���݂�������k�����鎩��\�\�\�������l�Ƒ��݂�������k���ʂ̎���\�\�\�������l�Ƃ��u���I�ȋ������̂����ɂ���̂��B����́A�����I�ɓƓ��̎d���Ō������Ă��邱�Ƃł���A�����I�ȋ������ł����āA����͂܂��ɁA���E�i���Ȃ킿�A�l�Ԃ̐��E�Ǝ��ۂ̐��E�j�̑��݂z�_�I�ɉ\�ɂ��Ă���悤�ȋ������Ȃ̂ł���B
�@�k�c�l��荂���̒i�K�Ɋւ��ẮA�k�c�l���͍\���Ƃ����ϓ_���炷��ƁA�����i�h�ƂȂ鎄����o�����āA���Ƃ͕ʂ̃��i�h�A�Ȃ����͐S�������I�Ȏ�̂Ƃ��Ă̑��҂�B�k�c�l�l�Ԃ͊��Ɉ�l�ЂƂ肪�����̂̐����Ƃ����Ӗ���S���Ă���̂ł��邩��i���̂��Ƃ͓����̎Љ�ɂ����Ă͂܂邱�Ƃł��邪�j�A�l�ԋ����̂���ѐl�Ԃ̈Ӗ��ɂ́A���݈ˑ��I���� Wechselseitig-für-einander-sein �k���݂ɓ��ꊷ��\�ȑ��݁\�\�\�M�g�����l�Ƃ������Ƃ��܂܂�Ă���B�����Ă܂��ɂ��̂��Ƃɂ���Ď��̌����݂Ƃ����鑼��̌����݂Ƃ��A�Γ��ɋq�ω������̂ł���A���ł���N�ł���A�����͊F�A���̐l�����̒��̈�l�̐l�ԂƂȂ�̂ł���B�v
�t�b�T�[���C�l�Q�C��E��w�f�J���g�I�Ȏ@�x,2001,��g����,pp.230-232�G�����O�F�E�ҁw�t�b�T�[���E�Z���N�V�����x,2009,���}�Ѓ��C�u�����[,p.292.
�@�����Ńt�b�T�[���́A�����ւۓI�Ȍ����������Ă��܂����A�Ƃ�����ΓƉ�ƂȂ肩�˂Ȃ��g����́h�Ƃ��Ă̎��䂪�`���������ȑO�ɁA�u�l�Ԃ͊��Ɉ�l�ЂƂ肪�����̂̐����Ƃ����Ӗ���S���Ă���v�A�������u���̂��Ƃ͓����̎Љ�ɂ����Ă͂܂邱�Ƃł���v�Ə����Ă��܂��B
�@���Ȃ킿�A�u���҂̌����������̌������̂����ցA����ݓI�i�C���A�[���j�Ɏu���I�ɓ��荞��ł��邱�Ɓv�A�u���݂�����̂Ƒ��݂�����̂Ƃ��u���I�ȋ������̂����ɂ���v�Ƃ����u�����I�ɓƓ��̎d���Ō������Ă���v�u���̍����I�ȋ������v���A�g����h�Ƃ����ӎ��I�ȓ���̂̔����ȑO�ɁA���̕�قƂ��Ă��łɑ��݂��Ă���B����́A�����Ɠ����̂������ɂ������錴���I�ȋ������Ȃ̂��A�ƌ����Ă��܂��B
�@���̂��Ƃ́A�̂��Ƀ�����=�|���e�B���A�Q�V���^���g�S���w�┭�B�S���w�ȂǁA�ŐV�̐S���w�̐��ʂ̏�ɗ����āA����̓I�ɖ��炩�ɂ����m�o�i���t�b�T�[��������Ō����u�u���I�ȋ������v�j�ƈӎ��̍���ɂ���s�g�̐��t��\�����ďq�ׂĂ��邱�Ƃɂق��Ȃ�܂���B
�@���́u�����I�ȋ������v������ɂ��鎖��́u�����̎Љ�ɂ����Ă͂܂�v�A�ƃt�b�T�[�����q�ׂĂ���_���A�������ɂƂ��ďd�v�ł��B�Ȃ��Ȃ�A���������������A�u�����I�ȋ������v�́A�l�Ɛl�Ƃ̂������݂̂Ȃ炸�A�l�ԂƓ����Ƃ̂������ɂ����邱�ƂɂȂ邩��ł��B
�@�l�ԂƐl�ԂƂ̂������A�����Ɠ����Ƃ̂������A�����Đl�ԂƓ����Ƃ̂������ɂ������u�����I�ȋ������v�\�\�\���Ȃ킿�g�g�́h�̓����Ɋ�Ղ����������̋@�\�A�����āA�u���ł���N�ł���A�����͊F�A���̐l�����̒��̈�l�̐l�ԂƂȂ�v���ƁA�܂��A����ȑO�ɂ��łɁA�����́g���̓��������ƂƂ��Ɉ�̓����ł���h�Ƃ������ƁA�c�c�c�t�b�T�[���������ŏq�ׂĂ��邱�Ƃ́A�{���́u�����v�̎v�z�ɁA���ǂ낭�قǎ�������Ă���ƌ����Ȃ��ł��傤���B
�u����ꂪ���z�_�I���ݎ�ϐ��ƌĂԃ��i�h�����̂́A�����܂ł��Ȃ��A�Ȏ@���鎩��Ƃ��Ă̎��̓����ł̂݁A�����Ɏ��̎u�����Ƃ�������A���ɂƂ��đ��݂�����̂Ƃ��č\�������B�������܂����̃��i�h�����̂́A���̎���Ƃ����l�Ԃō\������邻�ꂼ��̃��i�h�̓����ŁA���ꂼ��قȂ��ϓI���o�l���������\���������̂ł�����B���������̂�����ɂ����Ă����̃��i�h�����̂͏�ɓ��������̂Ƃ��āA�������K�R�I�ɓ����q�ϓI���E��ۗL���鋤���̂Ƃ��č\������Ă���̂ł���B�k�c�l
�@�q�ϓI���E�̐S�I�ȍ\���Ƃ́A�Ⴆ�Ύ��̌����I����щ\�I���E�o���Ƃ��ė��������B�k�c�l���̌o���́A���܂��܂Ȓ��x�̊��S���������A�˂ɂ��̊J���ꂽ���K��̒n���������Ă���B���̒n���̂����ɂ́A���ׂĂ̐l�ԂɂƂ��Ă��ׂĂ̑��҂��A�����I�ɁA�S�������I�ɁA�����S���I�ɁA�J����Č���Ȃ��߂Â����Ƃ��ł�����̗̂̓y�Ƃ��Ċ܂܂�Ă���B�����ɂ͂��܂��߂Â���ꍇ�Ƃ��܂��߂Â��Ȃ��ꍇ������A�����Ă��͂��܂��߂Â��Ȃ��̂��Ƃ��Ă��B�v
�t�b�T�[���C�l�Q�C��E��w�f�J���g�I�Ȏ@�x,2001,��g����,pp.233-234�G�����O�F�E�ҁw�t�b�T�[���E�Z���N�V�����x,2009,���}�Ѓ��C�u�����[,p.294.
�@���ꂼ��̎�������l�Ԋe�����A���ꂼ��ɑ��ҁi���̎���j�ɑ��Ă��J���ꂽ���E���u�����Ă���A�l�тƂ́A�����Ȃ��Ƃ��\�I�ɂ́u��ɓ��������̂Ƃ��āA�������K�R�I�ɓ����q�ϓI���E��ۗL���鋤���̂Ƃ��č\������Ă���v�B
�@�ɂ�������炸�A�e���ɂƂ��ās���ҁt�́A�˂Ɋ��S�ɗ�������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�������̏ꍇ�A�����������ās���ҁt�́u�J���ꂽ���K��̒n���v�̂Ȃ��ɖv���Ă���B�����āA�e���ɂƂ��āA�u���K��̒n���v�ɖv���Ă���g���m�h�̑��҂ɋ߂Â��Ă䂭���Ƃ́A�K�������e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��A�u�����Ă��͂��܂��߂Â��Ȃ��v�c�c�l�ԂɂƂ��āA�s���ҁt�͂��ł��A�w�͖ڕW�ł���Â���̂�������Ȃ����
���@�@�@�@��
�@�u�����v�ɂ����āA���̐l�Ԃ݂̂Ȃ炸�L���������A���R���Ƃ̌��������炩��搂��A�u�L�^���ꂽ�����̂������́^�L�^���ꂽ���̂Ƃق�̂��̂������Łd�^������x�܂ł݂͂�Ȃɋ��ʂ������܂��v�ƁA�`���ꂽ�g�S�ہh���E�̕��Ր������������{�����A���̎��ۂ̐����ɂ����ẮA���҂ɑ��ā\�\�\�g�����̍l���邱�Ƃ͒N�ɂł����ʂ���h�Ƃ������M�̂��߂ɁA�ނ��납�����ā\�\�\�����ɓƉ�_�I�ɐڂ��邱�Ƃ����������Ǝv����̂ł��B
�@�Ƃ��ɁA���肪�A�S���������e�����F�l�ŁA�������ɋ����̂Ȃ���������炯�o���Ă���ꍇ�ɂ́A�悯���ɁA�ЂƂ�悪��Ȕނ̐ڂ������ڗ������悤�ł��B
�@�ۍ�Ó��ɑ����������̏��Ȃɂ́A���������ނ̌��_���A�N�̖ڂɂ����炩�ɕ\��Ă��܂��B
�u���͖{���畷�����x���Ȃ��̋A�ȂȂ������̂͌�ꂳ��̌�S���Ȃ�ɂȂ����ׂ��Ƃ̂��Ƃł����{���ł����@�����̊Ԉ�炵�������v�͂�܂��{���ł����@�{���Ɖ��肵�č�����݂Ȃǂ��]�ӋC�ɂ͎��͂Ȃ�܂���B���̕�͎����\�̂Ƃ��Ɏ����܂����B�����牽�܂łǂ��̕�Ȑl�����悭������āT����܂����B�k�ȉ��A�����̐����Ă����ɑ���C�����A�M�̔Y�݁A�w�Z�ł̏���Ζ��̋�J�Ȃǂ�ȁX�ƒԂ������ƂŁc�\�\�\�M�g�����l
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�����Ȃ��̖��͖Y��܂����É����̐l�i���R�N�ł͂Ȃ��j�����Ę_���̘b�Ȃǂ��������ɂ��Ȃ��̌��l�͖{���ɂȂ��Ȃ�ꂽ�̂��Ɖ]�ӂ��Ƃ��܂����B
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�얳���@�@�،o�v
�{������[74]�k1918�N6��20���O��l�ۍ�Ó�����
 �@
�@
�u���͑O�̎莆�ɞ����œ얳���@�@�،o�Ə�����˂Ă��Ȃ��Ɍ䑗��v���܂����B���̓�̎��������Ƃ����̎��������Ƃ����̑O�ɂ͐��m��ʐ��E���������ł��܂����B���̎��̈��̒��ɂ͎��̎O���琢�E���ߋ����ݖ����ɘj�Đ����Ă��̂ł��B����ǂ�����͍������Ə����ċ��邱�̂̂̎������̎����������Ƃł��@�̂̎������̎����ʂ̂�ݕ��͓얳���@�@�،o�Ɖ]�Ђ��̒��ɑO�̗l�Ȕ��_������������钋�����ł��铔�̗l�ɂ܂��T�����肨������������������������肵�Ă��̂ł����B���T�s�v�c�̕�����B�s�v�c�̉��B�s�v�c��̖��ۂ�B
�@�킪�����̓��͎R�쑐�݂Ȑ�������B�R�쑐���łɐ�̎p�Ȃ�Ή䂪�Ȃ��s�v�V�Ȃ����ł悳�����Ȃ��̂ł��������ł͂���܂���B���͉�͐�Εs�v�c�������̂ł����čX�ɂ��̔@���Ȃ���̂Ɖ]�ӑ�����^�֓��Ȃ��B���Ɉ�͐�ł��薳��ł���A��ł��薳��ł���܂������R�����̒��ɂ͐��m��ʗ��]�̏O������܂���̂ł��B
�@���]�̒��ɂ݂͂��߂Ȏ��̎p�������܂��B�{���݂͂��߂ł͂Ȃ��B�H�����߂č����o����H�̎�����ɕs�v�V�̖��p�ł���܂��B�H�����߂邱�Ƃ͂��₵�����Ƃ��B�F���݂ȐH������Ƃ��͔V�͂��₵�������������Ƃł���܂��B����������������Ĝ��R�Ǝ������邠�Ȃ��ɂ��̗l�Ȃ��Ƃ��]���Ă��݂܂���B�v
�{������[76] 1918�N6��27���t�� �ۍ�Ó�����
�u���������ς肠�Ȃ��̌�S��������ЂĂ��Ƃ��]�ӂ��Ƃ��{���ł����B�ǂ������̗l�Ɍy���ɐ�ւ��f�ĂɒB������̂͊Ԉ�ӂ̂����R�ł��B
�@�����Ȃ��͎��̋C����ł����ς�v�ӗl�ɍs�̐i�܂Ȃ��̂���ЂɂȂ�̂ł�����������d������܂���B
�@�Ƃɂ����Ƃɂ���
�@�w���͔n���Ŏキ�Ă����ς艽���Ƃ菊���Ȃ�����͂Ă��҂ł���܂��B�x
�@�Ɖ]�ӎ������Ȃ��ɂ͂�����Ɛ\���グ�Ēu���܂����炱�ꂩ�炳���r�����Ȃ��ԈႪ�N���Ď����ǂ�Ȏ����]���Ă����܂�т�����Ȃ����ʼn������B�v
�{������[83] 1918�N7��25���t �ۍ�Ó�����
���@�@�@�@��
�@�w�t�ƏC���x�u�����v�ɂ����āA�{���́u�S�ہv�Ƃ�����ϓI�̈�ɒ������Ȃ���A�����́u�S�ہv�͎����ЂƂ�̂��̂ł͂Ȃ��A�u������x�܂ł͊F�ɋ��ʂ������܂��v�ƌ����Ă��܂����B�u�S�ہv���E�́A�u������x�܂ł́v�q�ϓI�ȑ��ݎ�ϓI���E�Ȃ̂��ƍl���Ă����킯�ł��B
�@���������ނ̍l���́A�������ɂ��̎��_�ł́A���Ȃ�ϔO�I�Ȃ��̂������ƌ���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�������A�����ƌ�̎����ɂȂ�ƁA�����̎v�z�ɂ͕ω����݂��܂��B
�@�����ɂƂ肠����w�}���������Ə����x�\�\�\���M�����͕s���ł����A�w�t�ƏC���x�̌������͌�Ǝv���܂��B�ȉ��A�g�{�������̉�����Q�Ƃ��Ȃ���A���̓��b���������Ă݂����Ǝv���܂��B
�u�w�}���������Ə����x�̒��ŁA�@���ƕ��w�̖�肪�T�^�I�ɂԂ����Ă���Ƃ��낪����܂��B
�@�}���������Ƃ����������y�ƂƁA���̃t�@���ł���q�t�̖������܂��B�����́A���������e�ƃA�t���J�ɕz���ɍs���Ƃ������̓��A�v�}���������ɁA������A��čs���Ă����悤���ނ̂ł����A�}���������͏����̐\���o��f���ċ����čs���Ă��܂��܂��B
�g�{�����u�{���ɂ�����@���ƕ��w�v,1989�N�u��, in�F�w�{���̐��E�x,2012,�}�����[,p.168.
�u�������B���������A���U�̈ꌾ�ł��V�̍˂��肤��킵�����h����邱�̐l�Ƃ��Ƃ����͂������A�u�̏����ȂԂ����̖��A�悼��ɔR����ق̂ق��A�����Ƃ����邭�A�����Ƃ��Ȃ��������Ђ��A�͂邩�̔��������ɕ�����ƁA�������ꂾ����`�ւ����A���ꂩ��Ȃ�A���ꂩ��Ȃ�A���́c�c�k�ȉ����s���l
�@�w�}���u�����搶�B�ǂ����A�킽�����̑��h�������������܂��B�킽�����͂����A�t���J�֍s���q�t�̖��ł������܂��B�x
�@�����́A�ӂ���̓����Ƃق鐺���ǂ����֍s���āA���킪�ꂽ���ɔ����Ƃ��Ȃ��狩�ԁB
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�w���Ȃ���������Ȃɂ����h�ł͂���܂��B���Ȃ��́A���h�Ȃ������Ƃ�������֍s���ĂȂ���ł����B����͂킽�����Ȃǂ��͂͂邩�ɍ��������Ƃł��B���Ȃǂ͂���͂܂��Ƃɂ����Ȃ��̂ł��B�ق�̏\�����\�ܕ������̂Ђт��̂��邤���̂��̂��ł��B�x
�@�w���T���A�������܂��B�������܂��B�搶�͂����̐��E��݂�Ȃ������Ƃ��ꂢ�ɗ��h�ɂȂ��邨���ł������܂��B�x
�@�}���������͎v�킸���Ђ܂����B
�@�w���T�A������킽�����͂̂��݂܂��B����ǂ�����͂��Ȃ��͂��悢�悻���ł��傤�B�����������͂��炭�ЂƂ͂ЂƂ̑傫�Ȍ|�p�����Ԃ̂�����ɂ���̂ł��B�����Ȃ����B���ӂ̐�����̂Ȃ�����H�̍����Ƃ�ōs���܂��B���͂�����ɂ݂Ȃ��̂��Ƃ����̂ł��B�݂�Ȃ͂�������Ȃ��ł������A�킽�����͂��������̂ł��B����Ȃ��悤�ɂ킽�����ǂ��݂͂Ȃ��̂��ƂɂЂƂ̐��E�������ė��܂��B���ꂪ������l�X�̂������|�p�ł��B�x
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�w�������ւĉ������B����A��čs���Ă����ĉ������B���͂ǂ�Ȃ��Ƃł��������܂��B�x
�@�w���T�����͂ǂ��ւ��s���܂���B���ł����Ȃ����l�ւ邻���ɋ���܂��B���ׂĂ܂��Ƃ̂Ђ���̂Ȃ��ɁA��������ɂ���ł�������ɂ��T�ސl�l�́A���ł���������ɂ��̂ł��B����ǂ��A�킽�����́A�����A��Ȃ���Ȃ�܂���B�����l�����܂艓���Ȃ�܂����B��������ї����܂��B�ł́B��������悤�B�x
�u�}�����������A���Ȃ����A�킽���ɂ��ė���Ƃ������Ƃ́A���܂�Ӗ��̂Ȃ����Ƃ��B�w���͂ǂ��ւ��s���܂���B���ł����Ȃ����l���邻���ɋ���܂��x�ƁB�܂�A���Ȃ����l������A�Y��A��������A���������肵�Ă���Ƃ���ɁA�킽���͂������Ă���B������A���Ȃ����������邻�ꂶ�������|�p�Ȃ�ł��A�Ƃ����ӂ��ɂ����Ƃ��낪����܂��B
�@�k�c�l�`���悤�Ƃ��郂�`�[�t�ƁA�`��郂�`�[�t�ƁA�`����Ă��܂������`�[�t�Ƃ͕ʁX���Ƃ����̂����w��|�p�̖{���ɂ���܂��B���Ȃ炸�����������l�̃��`�[�t�ǂ���ɁA�ǎ҂��Ƃ邩�ǂ����͂܂������ʂȂ킯�ŁA��҂Ɠǎ҂̂������ɂ́A�ڂɂ݂��Ȃ���ǂ�����̂ł��B
�@�Ƃ��낪�A�@���͂�������Ȃ����āA���̐l���l�������Ɓ\�\�M�\�\�͂��ł�������Ƃ����l���A�v���Y���̂��ɂ����Ƃ���B���Ԃ�@���͂����łȂ���A�`���͐��藧���Ȃ����̂��Ƃ������܂��B
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�}�����������A�w���͂ǂ��ւ��s���܂���B���ł����Ȃ����l���邻���ɋ���܂��x�Ƃ������Ƃ��A���̌��t�����ŁA�|�p�Ƃ���@���ƂɃp�b�ƕϐg�����Ƃ������܂��B�k�c�l�����ɋ{���̏@���ƌ|�p�A���w�ɂ��Ă̍ō��̉����@���݂���킯�ł��B�v
�u�{���ɂ�����@���ƕ��w�v, in�F�w�{���̐��E�x,pp.168-170.
�u�w���ׂĂ̐l�Ԃ͐������Ă����O�Ղɂ���Ă��ꂼ��|�p��`���Ă���B���ׂĂ̐l�͐����邱�Ƃɂ����āA�K�����̐Ղ��c���Ă����B���̐Ղ����̐l�ɂƂ��Ă̈�Ԃ̌|�p�ł��邵�A�l�ԂɂƂ��čł������Ȍ|�p�͂����������̂��x�ƁA�}���������͂����܂��B�k�c�l
�@�}���������̌|�p�ςɂ��A�ŏI�I�ɂ��ׂĂ̐l�X�͎����̐����Ă����ՂɌ|�p���c���Ă���̂ł���A�ڂɌ����Ȃ�����ǒN�ł������Ă���B�����́A���Ȃ����l����Ƃ���ɂ��ł�����A�Ƃ����̂��}���������̌|�p�ςł��B�����ɁA����͍�҂ł���{���̌|�p�ςł���A�|�p�ςƏ@���ς���v����Ƃ���ł��B�v
�g�{�����u�{�������v,1990�N�u��, in�F�w�{���̐��E�x,pp.199-200.
�u�|�p�A���w�͎Ƃ�������R�ł��B���̐l�����̂Ƃ�����؎��ɂ������Ă������œ�����i��������悤�ɎƂ��B�܂��A���ꂪ���R�ł��B�k�c�l��i���������l�Ɗӏ܂���l���A�����Ƃ�����悤�ɓǂށA���邢�͎��̍�i���ӏ܂��Ă��ꂽ��A���͂����ɂ��ł����܂��ƁA�|�p�ƕ��w�͖��邱�Ƃ��ł��܂���B�Ȃ����Ƃ����ƁA�ӏ܂���l���A�������l�̃��`�[�t�ɑ����Ċӏ܂��Ă���邩�ǂ����͑S���ʖ�肾���A�S�����R������ł��B�������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�ǂ�ȃ��`�[�t�ł��낤�ƁA������ǂ������ӂ��Ɋӏ܂��悤���A�ǂ������ӂ��ɎƂ낤���A���l�����ʂł͂Ȃ��A������Ƃ��������B������ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ����A�����ے肵����A�|�p�͈��̃t�@�b�V���ɂȂ��Ă��܂��B���̍�i�͂����Ƃ�ׂ��ŁA�����łȂ��z�͂��߂��Ƃ����������ɂȂ��Ă��܂��܂��B�k�c�l
�@�Ƃ鑤���ǂ��Ƃ邩�͑S�����R���Ƃ������Ƃ��A�|�p�𐬂藧�����Ă���Ō�̊�Ղł��B
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�w�������Ȃ���������A�����ɂ��ł�����x�Ƃ����邩�A�����Ȃ����A���ꂾ�����|�p�Ə@���̈Ⴂ���Ƃ����̂��A�{���̂��������������ƂŁA������w�}���������Ə����x�Ƃ�����i�ɂ��Ă���Ƃ����Ă��A���Ԃ�Ԉ�����ǂݕ��ł͂Ȃ��ƁA�ڂ��ɂ͂������܂��B
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�}���������́w������l�͊F�����̐����Ă����Ղ��c���Ă���B����͒�������ƁA��ɋO�Ղ��c���Ă���Ƃ�����̂Ɠ����ŁA�c�������̂����̐l�ɂƂ��Ă̌|�p�ł��邵�A�l�ԂɂƂ��čł����l����|�p�ł���B������A���l���F�A�������ꎩ�̂Ɍ|�p��`���Ă���x�Ƃ������t���A�{���̌|�p�ςł���A����͂��낢��ȂƂ���ɏo�Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�܂�A�{���ɂ��A���ׂĂ̐l�̓A�[�e�B�X�g���Ƃ������ƂɂȂ�B����͔ނ��M���Ď~�܂Ȃ������l�����̍��{���Ǝv���܂��B�{���́A�|�p�Ə@�����t�b�ƃX���[�Y�ɕς��Ƃ���ŊW�Â�����A���������l�����̍��{�͂����ɐ��藧���Ă���Ƃ������܂��B�v
�g�{�����u�{�������v, in�F�w�{���̐��E�x,pp.201-203.
�@
�@�ȏ�A�Ȃ��Ȃ��ƈ��p���Ă��܂��܂������A�g�{���̉����ǂ܂�āA�݂Ȃ���͂ǂ��������ɂȂ����ł��傤���H
�@���́A�M�g���́A�g�{���ɑS�ʓI�Ɏ^������킯�ł͂Ȃ��̂ł��B�����^���ƌ�������悢��������܂���B
�@���w���|�p���\�\�\�܂�A�����œo�ꂵ�Ă���}���������̂悤�Ȑl�̉̏��≉�t�Ƃ��������Ƃ��\�\�\�A��ɂ���ĎƂ����͎��R�ŁA��҂≉�t�Ƃ��A�u�����̍l�������`�[�t�̂Ƃ���ɓǂ�ł��Ȃ��A�����Ă��Ȃ��B�v�ƌ����Ď��邱�ƂȂǂł��Ȃ��c�c����͂܂��������̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��B���ꂪ�����Ă��邩�ǂ����ŁA���̐l���܂Ƃ��ȃA�[�e�B�X�g�������łȂ���������Ƃ������̂ł��B���l�̓ǂݕ����A����͂܂������Ă���Ȃǂƌ����Ă��Ȃ��l�́A�G�Z�E�f�B���b�^���g�̌��{�ƌ����Ă�낵���ł��傤��
�@�������A���̂��Ƃ���~�����ād�A�}�����������u�����́A���Ȃ����l����Ƃ���ɂ��ł�����v�ƌ����ƁA�Ƃ���ɔޏ��͌|�p�Ƃł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A���̂ЂƂ��Ƃŏ@���ƂɂȂ��Ă��܂��\�\�\�Ƌg�{���������̂́A������ƈႤ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�g�{���̌|�p�Ɗς͂�����������Ȃ�����ǂ��A�{���͂����ł͂Ȃ��Ǝv���̂ł��B
�@�܂������ŁA�}�����������̎肾�Ƃ������Ƃ��l���Ă݂����Ǝv���܂��B�ޏ����̂��̂����̂��ŁA�������ɒ��O�͔ޏ��̉̂����܂��܂Ɋ����Ƃ�A���ꂼ��Ɋ������邱�Ƃł��傤�B�����̃R�g�o�����A
�u�搶�͂����̐��E��݂�Ȃ������Ƃ��ꂢ�ɗ��h�ɂȂ��邨���ł������܂��B�v
�@�܂��A��̈��p�ŏȗ����������̃R�g�o�Ō����ƁF
�u���Ȃ��́A�������̂���ɂ�����܂��B���ׂđ���ԂⒹ�́A�݂Ȃ��Ȃ����ق߂ĉ̂Ђ܂��B�v
�@
�@�܂�A���Ȃ炸�����̂���ł���}���������̃��`�[�t���̂܂܂ł͂Ȃ��Ƃ��A�u����ԂⒹ�v�́A���ꂼ��ɎƂ������̂���[���������Ă���̂ł���A�}���������ɂƂ��Ă͂���ŏ\���Ȃ̂��Ǝv���܂��B�������߂����C�����ʼn̂����̂�����A���O���݂Ȕ߂��݂��Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ȂǂƂ͔ޏ��͍l���Ȃ��ł��傤�B
�@�u���͂ǂ��ւ��s���܂���B���ł����Ȃ����l���邻���ɋ���܂��v�Ƃ����}���������̌��t���A�g���ł����̉̂��v���o���Ă����A�����ɓ�����������݂�����͂����B����ɂ���āA���ł������Ă䂭��]�Ăق����h�Ƃ����Ӗ��ɗ������邱�Ƃ��ł��܂��B���邢�́A�ޏ��̉̐����v���o���Ȃ���A�������g�������̐��ʼn̂��Ă݂Ă��悢�ł͂Ȃ����A���Ȃ킿�N�����|�p�ƂȂ̂��c�c�ƁB
�@�������ɁA�����́A�}���������h���邠�܂�A�ޏ������c�����l�̂悤�ɋ��������Ă��܂��Ă��邩������܂���B�������A�}�����������g�́g���c�h�ɂȂ����͖ѓ��Ȃ����A�S����߂��ԓx�ʼn����Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A�������̂悤�ȏꍇ���ӂ��߂āA��̎����͎��R�ł��邱�ƁA������R���g���[�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����ƁA�̂���ƒ��O�Ƃ̂������ɂ͋��������邱�Ƃ��A�ޏ��͒m���Ă��邩��ł��B
�@����������ƁA����͉��y�̉��t�i��{�I�ɁA���t��Ȃǂ��������̒��O�̖ʑO�ōs���܂��j�ƁA���⏬���̑n��i�ߑ�ł́A��{�I�ɁA��҂̌ǓƂȉc�ׂƂ��čs���A���ʂ������A�o�łƂ����I�H���ւĔ��M����܂��j�Ƃ̂�������������܂���B
�@�������A�{���Ƃ�����Ƃ́A�����̎��⓶�b���A���y�̉��t�Ɠ����悤�Ȃ��̂��ƍl���Ă����d�����Ȃ��Ƃ��A���̂悤�Ɋӏ܂���邱�Ƃ����z���Ǝv���Ă����̂ł͂Ȃ����H
�@���̂��ƂŎv��������̂́A���Ƃ��A�ނ́A�w�t�ƏC���x���o�ł��ĈȌ�ł�����ǂ��A�g�̉��̊�茧�Ⓦ�k�ȊO�̒����̎��l�Ƃ̕t����������Ɍ������Ă����ӂ�������܂��B�w�t�ƏC���E��Q�W�x�̂��߂ɗp�ӂ��Ă����u���v�̌��e�ɂ́A�����̂悤�ɏ�����Ă��܂����F
�u�����ł܂��ƂɂԂ����Ȃ���
�@�킽�����̌h������p�g����������
�@�莆��G���������肭�����ꂽ��
�@�����ɂ��낢�남�����������邱�Ƃ�
�@�C������₤�ł͂������܂���
�@���Ƃ���Љ��������������Ƒ����܂�
�@�킽�����͂ǂ��܂ł��ǓƂ�����
�@�M����������������Ђ܂��̂�
�@��������ɂ��킽�����ɂ����Ǝd���������҂Ȃ��邨����
�@���l�ɂȂ�Ɖ]������
�@���e�̂���������W���X�ւ������������ɂȂ�����
�@�킽�������ꂵ�܂��ʂ₤���˂��Ђ������Ƒ����܂��v
�@�����A�����̎��d�̎��l�����́A���܂��܂ȗ��h�ɕ�����āA���ꂼ��̎咣�������đ����Ă��܂����B���O�h�A�V���o�h�A�_�_�C�Y���A�v�����^���A���l�d�@�ȂǂȂǂł��B�����������Ƃ��A�{���͔��ɔς킵���v�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ȃ��Ȃ�A���������|�p�v���́A���Ԃ̎��l�ɑ��Ă��A�ǎ҂ɑ��Ă��A���̕������咣������������̂�����ł��B
�@�|�p�̑n����A�ӏ܂��A�C�f�I���M�[�̂悤�Șg�ɂ͂߂邱�Ƃ��ł���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�d�Ƃ����̂��A�����Ƃ����l�̍l�����������̂��Ǝv���܂��F
�u�C�f�I���M�[���Ɏ����Ȃ���
�@�@�@�@���ϑe�G�̗��_��
�@�@�@�@�@�@�@�@��������Ȃ�v
�{���w���@�����E�S�x���B
�@���������킯�ŁA�}�����������A�Ō��
�u�����k�c�l���ł����Ȃ����l�ւ邻���ɋ���܂��B���ׂĂ܂��Ƃ̂Ђ���̂Ȃ��ɁA��������ɂ���ł�������ɂ��T�ސl�l�́A���ł���������ɂ��̂ł��B�v
�@�ƌ����ď����̂��Ƃ��狎���Ă䂭�̂́A�������ď@���Ƃɕϐg��������ł͂Ȃ��A�ނ���A���������R�ł���|�p�̖{���ɁA�ǂ��܂ł������ł��낤�Ƃ������߂��Ǝv���܂��B�u�܂��Ƃ̂Ђ���̂Ȃ��ɁA��������ɂ���ł�������ɂ��T�ސl�l�v�Ƃ����R�g�o�́A���Ȃ炸�����@���I�ȈӖ��ɂƂ�K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@���ꎍ�u�t�ƏC���v�ɂ���F
�u�܂��Ƃ̂��Ƃ͂����Ȃ͂�v
�@�Ƃ����u�܂��Ƃ̂��Ƃv�Ƃ����\�����A���l�ɁA�@���I�ȈӖ��ł͂Ȃ���������܂���B���Ƃ��A�����������E�̂��̂̂��ɂӂꂽ�����̊������A���̂܂ܓ`����悤�ȁg���̂��Ƃh�Ƃ����Ӗ���������܂���B
�@�����̓}�������������������A�������}���������̉̂���������́A�}�����������̐l�Ƃ�������ɍs���A����ɂ�������������Ǝv���Ă���B�����̉̂����������̂悤�Ɏ�邱�Ƃ́A������R���B�������A�����{�l�Ɋւ��ẮA����͌���肾�B�����̎Ƃ��Ă�������Ǝ����Ƃ́A�Ⴄ���̂Ȃ̂��\�\�\�ƁA�}���������͍l�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���āA�w�}���������Ə����x����g�{�����W�J���Ă�����́A�����ЂƂ���܂��B����́A
�u�����������͂��炭�ЂƂ͂ЂƂ̑傫�Ȍ|�p�����Ԃ̂�����ɂ���̂ł��B�����Ȃ����B���ӂ̐�����̂Ȃ�����H�̍����Ƃ�ōs���܂��B���͂�����ɂ݂Ȃ��̂��Ƃ����̂ł��B�݂�Ȃ͂�������Ȃ��ł������A�킽�����͂��������̂ł��B����Ȃ��悤�ɂ킽�����ǂ��݂͂Ȃ��̂��ƂɂЂƂ̐��E�������ė��܂��B���ꂪ������l�X�̂������|�p�ł��B�v
�@�Ƃ����}���������̃R�g�o�ɂ�����镔���ł��B�܂�A�|�p���u������v�l�̖ڂŌ���A�N�����|�p�Ƃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�������A���̃}���������̔����́A�������⌾������ł͂Ȃ��͂��ł��B���ꂪ�{���̌|�p�ρA���邢�́A�|�p�́A���z�Ƃ��Ă͂�������ׂ����Ƃ����|�p�ς������̂��Ǝv���܂��B
�@�������A�����́A�u���ꂪ������l�X�̂������|�p�ł��B�v�ƌ������Ă���̂ł��B���������A�ނ��A���k�̑����I�ȉ��Z�����サ���Ǝv���鎩�쉉����A�I�[�P�X�g���Ȃ݂̊y�������ł̑f�l���t�ɗ͂�s���������Ƃ��v���N������܂��B
�@���t�̋Z�p��˔\�Ƃ������Ƃ��A�ނ��ǂ��l���Ă����̂��A�悭�킩��Ȃ��_������܂��B�������A�������Ă����Վ����Ă����킯�ł��Ȃ������B���̂��Ƃ́A�w�Z���e���̃S�[�V���x�Ƃ����I�[�P�X�g���t�҂̖җ��K�\�\�\�������A菓����Ă��钹��b�����Ƃ����f�l��ɂ��ẴZ�b�V�����ɂ��\�\�\��`������i�����邱�Ƃ���킩��̂ł��B
�@�Ƃ������A�g�l�݂͂Ȑ������O�Ղɂ���āu�傫�Ȍ|�p�v�������̌��ɑn��B���ꂪ�A�u������l�X�̂������|�p�v�ł���h�\�\�\�Ƃ����̂��A�Z�p�ɂ����Ă��˔\�ɂ����Ă��s���o�́A�ЂƂ�̂����ꂽ���l�̓��B�_�ł������Ƃ������Ƃ͖��L�����ׂ��ł��B
 �@
�@
�u�����̐����̋O�ՁA���ꂪ������l�̎����Ă����Ԃ̌|�p�ł���B�l�ɂ݂͂��Ȃ���������Ȃ����A�����ɂ݂͂���Ƃ��������������܂��B�݂���Ƃ������ƂƁA�݂��Ȃ��Ƃ������Ƃ�����킯�ł����A�}�����������w���ɂ݂͂���x�Ƃ����Ƃ��A����͂ǂ��������Ƃ������Ă��邩�Ƃ����ƁA��̎������s�������ɂ݂錩���ƁA�A�肪���ɂ݂錩���ł͈Ⴄ�悤�ɂ݂��邱�Ƃ����蓾��Ƃ������Ƃ��Ƃ������܂��B
�@�@�@�@�@�k�c�l
�@�܂�A�}���������͋A�肪���̖ڂł݂Ă��āA�����͍s�������̖ڂł݂Ă���B�������|�p���c���Ă��Ă������ł݂͂��Ȃ��B�����ǁA�}���������ɂ݂͂���B�k�c�l�{�����ǂ��߂��ŏI�̂Ƃ���́A���������Ƃ���ɋA������̂��낤�Ǝv���܂��B�v
�g�{�����u�{�������v, in�F�w�{���̐��E�x,pp.206-207.
�@���������܂��āA�����̐����ŋg�{���������Ă���u�s�������v�u�A�肪���v�Ƃ����R�g�o���́A�ے��I�����āA�����������Ƃ��Ă���̂��A�M�g���ɂ͂悭�킩��Ȃ��̂ł��i���j�B�g�{���̕ʂ̖{������ƁA�����̂悤�Ȍ�����������܂��F
�u���̉��҂Ƃ������Ƃ��l����A����̎��́w���i�����j�蓹�̎��x���ƌ������Ƃ��ł���B����Ȍ��t���g���ĂЂ�����ɐV��������\���⌾��������߂����w���H�̎��x�ł͂Ȃ��A�O�ꂵ�ē˂��i�n�_����ǎ҂̈ӎ��̕��ցA�����̌���̕��ւƖ߂��Ă���w�҂蓹�̎��x���ƌ�����B�v
�g�{�����u��������w�݂肵���̉́x�v, in�Fders.�w���{�ߑ㕶�w�̖���x,2008,�V������,pp.158-159.
�@��̍u���́u�s�������v�u�A�肪���v�ƁA���̕��͂́u���H�v�u�҂蓹�v�������Ӗ����Ƃ�����A�u�A�肪���̖ځv�Ƃ́A�|�p�̐[���ɍs���������n�_����A�����̌���Ɛ����҂̓���I�ӎ����ӂ�Ԃ��Č��Ă���ځ\�\�\�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@����ŁA�R�g�o�̈Ӗ��͂��������킩�����悤�ȁd�A����ł��������傭�A���������u�A�肪���̖ځv�Ō���ƁA�u�l�тƂ̐����̋O�Ղ������A��Ԃ̌|�p�ł���v���Ƃ��u������v�\�\�\�Ƃ����b�́A��͂�܂����������ł��܂���
�@�悤����ɁA�|�p���ɂ߂��Ə̂���l���A���܂��玩���ł͌����Ȃ����낤���A���ɂ͂��܂���̂��Ƃ��悭������̂��A�ƌ����Ă���B�d�d����Ȃ��ƌ���ꂽ���āA�łɂ���ɂ��Ȃ��킢�B������ƌ����Ȃ�A�������ɂ�������悤�ɂ��Ă��炢�������c�\�\�\�ƌ��������Ȃ��Ă��܂��܂�����
�@������Ǝv��������̂́d�A�ӔN�̃t�b�T�[�����A�s���ۊw�I�Ҍ��t�̂悤�ȓ�����Ƃł͂Ȃ��āA�ߑ�Ȋw�̋q�ϓI�Ȍ����ɓ�炳���O�́A�f�p�Ȑl�тƂ̎����Ă������E�ɑ��錩�����A�u�������E�v�ƌĂ�ŏd������悤�ɂȂ������Ƃł��B�������Č����A�g�l�тƂ̓���̐����ӎ��������A��Ԃ̓N�w���h�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤��...
�@�������A���ꂪ���������ɂȂ�̂��ǂ������A�悭�킩��܂���...
�@������܂��A�h��ɂ��Ă����ق��Ȃ������ł��ˁA���܂̂Ƃ��롡�
���݁`�@�~ �c
�c
.
�O��|����
�� ��������
�� ���L����������
�� ���̓��L���폜
[�߂�]
 �@
�@ �@
�@


 �@
�@

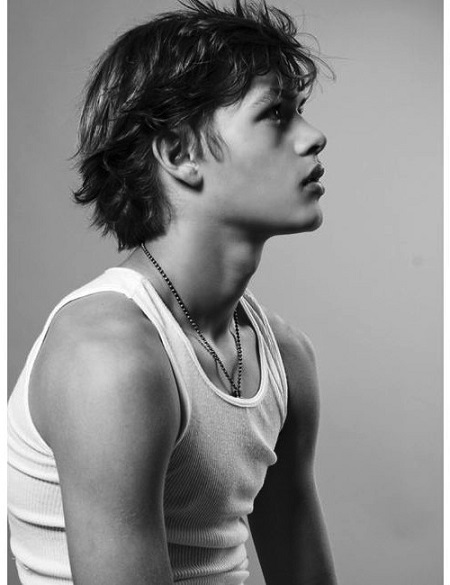
 �@
�@ �c
�c