11/27の日記
09:50
【ユーラシア】トルストイ、グラムシ、15歳のインスピレーション
---------------
.

トルストイ 「ランプの下で」(パステルナーク筆)
こんにつわ(^.^)o
その後‥の近況ですけど、トルストイ読んでますよ。
まだぜんぜん序の口ですけど、‥そもそも小説の描写にかかわる根本的な思想からして、ミヤケンの《心象スケッチ》とは全く違う思想に基づいていることがわかってきました。
「『イワン・イリイチの死』の中」で「イワン・イリイチを診察する医者の表情がこんなふうに描かれている。
『あなたはただわれわれに任せておけばいいんです。〔…〕われわれにはすっかりわかっているんですから』。医者の顔つきはそう語っているようであり、それは被告に対する裁判官の顔つきとそっくりだった、と。
医者のこの自信ありげな冷たい表情の前で、病気をかかえた本人である患者がどれだけ心細い思いをすることか、〔…〕―――経験のある人間にはそれが痛いほどわかるので、この自信に満ちあふれた医者の表情がまざまざと目に浮かぶのである。
しかし、〔…〕ここではじっさいに目に映っている像については一言も語られていないのだ。そして、ここにこそトルストイのリアリズムを理解する重要なポイントがあるのである。〔…〕
表情の向こう側にある医者の気持ちを医者自身の言葉で語らせることによって、その表情がわれわれの脳裏にくっきりと見えてくるという仕組みになっている。つまり、人の目というものは、目に見える部分の向こう側にあるものがわかったときにはじめてよく見えるものなのだ。」
八島雅彦『トルストイ』,pp.184-185.
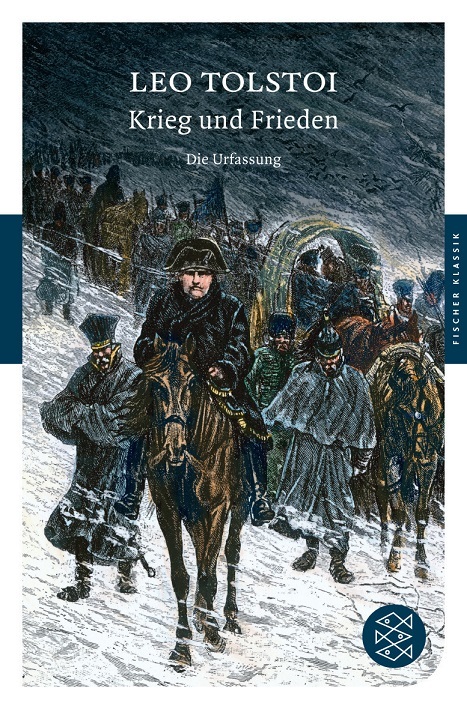
トルストイ『戦争と平和』独訳本
これに対して、ミヤケンの《心象スケッチ》のほうは‥、“目に見えるもの”をそのまま書くという日本の自然主義派の“写生”とはもちろん違うのですけど、それにしても“目に見えるもの”をまず描きます。その描き方で、ふつうの人が見る映像とはかなりちがったもの―――「幻想的」と見られるようなものになることはありますけど、それにしてもあくまでも、私たち生身の人間が、何の思想にも概念にもよらずに感じ取ったナマの《現象》を描くことに、宮沢賢治の努力は向けられているのです。
トルストイの考えるような、“目に見える”外観の“向う側にあるもの”とは、宮沢賢治に言わせれば、それはありのままの《現象》ではなく、ありのままの《現象》を人が(人や銀河や修羅やウニが)さまざまに解釈した結果であって、《本体論》の一部にすぎないのです。
じっさい、ひとりひとりの医者は、患者を診るさいに、いろいろな考え方をしているはずです。“医者はみな同じ見方で見ている。それは裁判官と同じ”とは決めつけられないはずです。先入見を取り払って、虚心に患者の訴えに耳を傾け、患者の気持ちをまず把握しようとする医者もいるでしょう。あんまり患者の数が多すぎて、とてもひとりひとりに注意を払ってはいられないので、問診は機械的に済ましてコンピューターのように診断を下し、それだとミスが出ることも考慮してなるべく無難な処方をする医者もいるでしょう。ひとくちに「医者」と言っても、千差万別のはずです。
ミヤケンの基本思想から言えば、私たちにとって何よりも大切なのは、私たちの心に映った《現象》であって、それは必ずしも個人的なものではない。ある程度までは、見る者に共通する像である。
しかし、《現象》の向こう側に“実在”すると人が言う―――トルストイや、その他多くの哲学者、宗教家がそれぞれに言う―――“真実”とは、さまざまに解釈された《本体論》であって、それは、人により、また時代により変わりうるものだ:
「これらについて人や銀河や修羅や海膽〔うに〕は
宇宙塵をたべ、または空氣や鹽水を呼吸しながら
それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが
それらも畢竟こゝろのひとつの風物です
〔…〕
けだしわれわれがわれわれの感官や
風景や人物をかんずるやうに
そしてたゞ共通に感ずるだけであるやうに
記録や歴史、あるひは地史といふものも
〔…〕
われわれがかんじてゐるのに過ぎません
おそらくこれから二千年もたつたころは
それ相當のちがつた地質學が流用され
相當した證據もまた次次過去から現出し
みんなは二千年ぐらゐ前には
青ぞらいつぱいの無色な孔雀が居たとおもひ
新進の大学士たちは気圏のいちばんの上層
きらびやかな氷窒素のあたりから
すてきな化石を發堀したり
あるひは白堊紀砂岩の層面に
透明な人類の巨大な足跡を
發見するかもしれません」
『心象スケッチ 春と修羅』「序詩」
宮沢賢治が、このことを深く印象づけられたのは、アインシュタインの相対性理論によってであったと思います。
“唯一の真理”と思われていた物理学の基本法則でさえ、ニュートンとラプラスが述べたような硬直した不動の体系ではないのです。アインシュタインによれば、時空の真実の構造は、もっとフレキシブルなものです。時空の枠組みと、その中で運動する物体との関係は、一義的に定義されるような硬直したものではない。物体の存在と運動のしかた次第で、時空の枠組みそのものが延びたり縮んだり曲がったりする。そして、物体の質量や位置のような基本的な属性さえもが、物体の運動と相対的に関係しあって、あいまいに決まる……いや、厳密には不確定になってしまうものでしかないのです(ハイゼンベルク)。
そこで、たとえば法廷における検察官や裁判官を、被告人の目線から宮沢賢治が描写すると、↓つぎのようになります:
「とにかく向ふは検事の立場、
〔…〕
だが何のため、向ふは壇をのぼるのだ。整然として椅子を引いて、眼平らにこっちを見る。
卓に両手を副へてゐる。正に上司の儀容であるが、勿論職権止むを得まい。たゞもう明るく話して来ればいゝのである。しかし……物言ふけはひでない。厳しく口を結んでゐる。頬は烈しい決意を示す。
〔…〕
……いつか向ふが人の分子を喪くしてゐる。皮を一枚脱いだのだ。小さな天狗のやうでもある。それから豺〔やまいぬ〕★のトーテムだ。頬が黄いろに光ってゐる。白い後光も出して来た。こゝで折れては何にもならん。断じてその眼を克服せよ、たかゞ二つの節穴だ。もっともたゞ節穴〔よ〕りは、むしろ二つの覗き窓だ。何だかわたしが、たった一人、居ずまゐ正してこゝに座り、やつらの仲間がかはるがはる、その二っつの小窓から、わたしを覗いてゐるやうだ。〔…〕」
★ 「豺狼当路(さいろうとうろ)」は、悪意を持つ人が国の重要な地位についていることのたとえ。「トーテム」⇒:カナダ、オンタリオ州オッタワのトーテム
このように、あくまでも“見えるもの”にこだわって、相手の「眼」や「両手」や上体の姿勢をつぶさに描き、さらに、相手を客観的にとらえるのではなく、ぶつかりあう二人の人物の相対的な関係の所産として、こちらの人物の《心象》に映じた相手の姿を、「小さな天狗」「豺のトーテム」、相手の眼は「二つの覗き窓」で、その2つの穴から「やつらの仲間がかはるがはる…わたしを覗いてゐる」などと描写します。
つまり、トルストイとはまさに正反対に、客観的な《本体》を見透かす眼ではなく、どこまでも個人の眼で見た相対的な《現象》にこだわって、それを細部まで追究してゆくところに、宮沢賢治の文学的認識の方法があるのです。

『戦争と平和』(1967年 モスフィルム) 仏軍に捕らえられ処刑を待つ人々
しかし、最初に書いたように、以上のトルストイとミヤケンの対比は、あくまでも序の口です。
もっと根本的な部分で比較をする必要があると思っています。たとえば、トルストイがマタイ伝を引いて述べる「非暴力」思想。
ミヤケンも、それに近い考えを持っていたようにも思えますけれども、しかし、トルストイの、いわば超過激な、国家も裁判所も刑罰も否定する「非暴力思想」を、どこまで共有していたのか?
宮沢賢治が、アナーキストであった草野心平に反論した手紙が残っています。この時、草野心平は、サッコ・ヴァンゼッティ事件(アメリカで、アナーキストでイタリア移民のサッコとヴァンゼッティが、冤罪によって死刑に処せられた事件⇒:Wikipedia ⇒:Youtube(Joan Baez:死刑台のメロディ))の真実を訴えていたのですから、それを頭から否定したミヤケンは、“大逆事件”にもつながる国家主義イデオロギーから抜けきっていなかったと見るべきなのかもしれません。
しかし、他方で、窃盗犯で逮捕された教え子のために警察署に交渉して奔走し、その更生のために、サハリンまで出かけて就職口のあっせんをした宮沢賢治は、‥もしかすると、国家の暴力装置が完全に正しいとは思っていなかったかもしれない―――トルストイの「非暴力」主義を、部分的にではあれ共有していたかもしれません。
まぁその探究は、これからの課題です。
「幼年時代から抜け出ようとしている青年男女のみなさん、みなさんの心の中に、私とはいったい何者なのか、私は何のために生きているのか〔…〕という疑問が最初に浮かんだときには、自分自身を信じることだ。それらの問いに対してみなさんの頭に思いつく答えが、幼年時代にみなさんの中に吹きこまれたものと食い違っており、みなさんが周囲のすべての人たちとともに生活しているその暮らしとも食い違っているというときにも、自分自身を信じることだ。その不一致を恐れてはいけない。反対に、みなさんと周囲のすべての人たちとの不一致の中に現れ出たものこそが、みなさんの中にある最良のもの、すなわち神の根源なのであって、その根源が人生において発現することがわれわれの生存の主要なというばかりでなく唯一の意味をなすものなのだ。〔…〕
そんなときに、ものわかりのよさそうな笑みを浮かべて、自分もかつてはそうした問いに対する答えを探したものだが見つけられなかった、それというのも、みんなが受け入れている答え以外には見つけることなどできはしないのだよと言う人々のことは信じてはいけない。」その答えとは、「この社会の役に立つ一員になるように努めるべきだということだったのだ、などと語るような人々を信じてはいけない。」
「私は15のときにそうした経験を持ち、それまでその中で生きてきた他人のものの見方に対する子供らしい従順さから突然目覚め、自分で生きなければならない、自分で道を選択し、自分に生命を与えたかの根源に対して自分の人生に自分で責任を持たなければならないのだと初めて理解したのを覚えている。
私はそのとき自分の人生の主要な目的は、福音書的な意味で、つまり献身と愛の意味でよくなることであると、ぼんやりとではあるが深く感じたことを覚えている。」
トルストイ「自分自身を信じること」(1906-07年), in:八島雅彦『トルストイ』,pp.189-192.
トルストイが死の直前に、思春期の人たちに向けて語った↑この“15歳のインスピレーション(啓示)”ということですけれども、皆さんは自分の15歳の時を思い返してみて、どうでしょうね? 「啓示」はありましたか?
ギトンは、ありましたよ。キリスト教とも「神」とも関係ないし、福音書でもありませんでしたが、ともかくインスピレーションはありました。その内容をここで書くのはやめておきます―――内奥の声は、自己の内奥にあってこそのものですから―――が、周りの大人たちの言うことは、もちろん一切無視しましたし、その後まぁいろんなことがありましたが、その気持ちはいまも変っていませんねw
でも、このさい、トルストイのおかげで思い出したのがよいきっかけですから、きょうは↓、関係する方面のことを、ちょっと書いておくことにしますw

トルストイ『復活』(1965年 イタリア映画) 復活祭の祈り
さいきん、ギトンは、トルストイと並行して、石堂清倫氏の回想記を読み、グラムシの思想に関心をもつようになりました。
じつは、グラムシは、学生の頃に、友人‥というより親友と言ってよい友達が注目していたのですが、ついぞその中身について―――グラムシの思想内容について話してくれたことがなかったので、読みそびれてしまってそのままになっていました。
今読んでみると、なかなか重要な点を衝いているのは、まちがえないようです。
かんたんに言うと、いわゆる“マルクス・レーニン主義”―――じつはマルクスの主義でもレーニンの主義でもないスターリンの主義だったりするのですが、それはいま置いて―――と、それに基づくコミンテルンの指導に対する反論です。19世紀のヨーロッパ、あるいは20世紀初めのロシアでは、実力による革命が有効だったかもしれないが、それ以後の高度化した資本主義国では、むしろ議会を通じた平和的手段による民主主義の拡充と「社会国家」(福祉国家)の段階的改良によって、はじめて社会主義への道が開けるという「構造改良論」です。(もっとも、ギトンは、社会主義がはたして信頼のおける“未来”か?…ということには疑問を持っています。その点は、↓のちほど触れます)
グラムシは、イタリアのファシスト政権下で捕らえられた獄中で、こうした展望を記した「ノート」を残したのでした。
グラムシの思想の中でも、とくにいまギトンが関心を寄せているのは、“ヘゲモニー”という考え方です。
国家は、民衆に強制して権力への“同意”を得るために、社会にさまざまなヘゲモニーを打ち立てます。ヘゲモニーによって、民衆の中に規範は内面化し、一人一人の民衆は、それが当然の常識だとか、自分たち自身の道徳だとか思い込んで、すすんで権力に従うのです。
それは、客観的に見れば、マフィアやヤクザの仁義と何ら異なるものではありません。ただ、国家のヘゲモニーの場合には、より広い“公的”な形で、正統性(支配の正当性)が保証されているのです。
ところで、グラムシは、こうも言っているそうです。国家がヘゲモニーを打ち立てているところでは、かならず、それに対抗するカウンター・ヘゲモニーもまた存在すると。
もちろん、それが「仁義」で結ばれたヤクザ集団のようなカウンター・ヘゲモニーであれば、まったく意味はありませんが、既存の国家の上に、よりいっそうの改良を積み重ね、支配権力(支配階級のための権力)機能の後退と、より“調停”的な未来への展望を開くものであれば、そのようなカウンター・ヘゲモニーの族生こそが、かつての革命運動に替わるものとなるはずです。
というのは、グラムシによれば、“マルクス・レーニン主義”者が“国家は支配階級の支配と抑圧の道具だ”と言うのは、国家の機能の一面を言い当てているに過ぎないのであって、他面において国家は、社会に存在するさまざまな利害を調停する役割を持っているのです。
そしてまた、既存の社会の中でカウンター・ヘゲモニーが成長し、「改良」を積み重ねることによって、その上に立って新たな展望が開けてくると、グラムシは言います。
現在、19世紀のマルクスも、20世紀初めのレーニンも、それらをいくらほじくり返しても、そこから直ちに21世紀の未来を見通す指針が出てこないのは当然でしょう。他方で、いわゆる“ブルジョワ経済学”(近代経済学)のほうでも、ケインジアンを越える図式は現れていません。ケインズ以前の“夜警国家”へ逆戻りして小康を得ようという「ネオ・リベラリズム」が関の山です。あるいは、ケインジアンと「ネオ・リベラリズム」を混合して、とにかく下層民衆にできるだけ沢山シワ寄せを押し付けて全体のつじつまを合わせようという「なんとかミクス」が唱えられていますが、これも、“成功の見せかけ”がそう長続きするとは思えません。
つまり、左右ともに“展望がない”わけですけれども、しかし、さまざまなカウンター・ヘゲモニーを育て、「改良」を積み重ねることによって、かならず新たな展望が現れてくると、グラムシは言うのです。
「改良」は、それ自体が、国家の利害調停の機能を、より多く被支配者を支持する方向へと向けるだけでなく、「改良」の上に立って新たな展望が開かれるという点に、大きな希望があると言うのです。
たしかに、“社会主義革命”の夢(幻想?)が、少なくない数の人たちをとりこにした時代とは違って、今は“展望のない時代”かもしれません。
しかし、かつての時代とは比べ物にならないほど多くの・さまざまな運動が、私たちの社会で行われているのも事実です。核兵器廃絶、原発停止、から自然保護、差別解消、女権拡張、ジェンダーに至るまで、じつにさまざまな運動が、それぞれの方向に進められています。それらは、かつての“社会主義革命”のような、ひとつの目標の下に束ねられるような性質のものではないことが、私たちの時代の特徴です。
かつては、そうした運動を始めようとすると、さる“不屈の伝統”を誇る左翼政党や、理論武装した極左セクトが入り込んで来て、“政治革命の優位”をテコに搔きまわす‥ということがあったようですが、しだいにそんなことはできなくなりつつあります。原発事故の後遺症が残る旧・ソ連、いまだに核兵器に固執する中国と北朝鮮、といった説得力ある反証があまりにも多いからでしょう。
さまざまなカウンター・ヘゲモニーを育て、「改良」を積み重ねることによって、新たな展望が現れる―――しかし、それは必ずしも一つの統一された方向を持った展望である必要はないのだと思います。また、展望の方向が“社会主義”(生産手段の国有化)でなければならないという理由もない。(書き始めるときりがないのでやめておきますが、ソ連の崩壊や北朝鮮の現状を見るまでもない。日本でも“社会主義の実験”は行なわれていました。あの第2次大戦中の総動員体制が、それです!)
さまざまな方向への運動が同時に存在してこそ開かれる未来―――ということから、必然的に、政治体制は民主主義でなければならないことが帰結します。一党独裁のようなシステムは、進歩を阻害するものでしかありません。
“中途半端な「改良」は、支配者・資本家階級を利するだけだ”式の謂れのない誹謗、自称「左翼」の人たちによって繰り返されてきた・この種の誹謗を、もう言わせないこと、社会の進歩を邪魔する彼らの口を、自由な言論の広がりによって塞いでしまうこと―――それが、これからの時代に期待できるもっとも明るい条件の一つではないでしょうか?

とはいえ、グラムシの時代からも、すでに半世紀以上が経過しています。グラムシ以後に、私たちの社会は大きな変動をいくつか経ています。グラムシを読めば、何か現代にそのまま適用できるような妙案が書いてある、というようなことはないのです。
日本で、グラムシがあまり注目されず、ごく少数の人々が熱心に研究している(多くは専門家でないアマチュアが)にとどまるのは、すぐに飛びつくことのできるような“妙案”ではないからかもしれません。
しかも、グラムシの「獄中ノート」の記述は断片的で、それらをつないで、グラムシの思想を組み立てる努力が必要です。あるいは、そもそも統一された思想など、そこにはないと考える研究者もいます(片桐薫氏など)。
他方、マクス・ヴェーバーの理解社会学にも対抗しうるような壮大な体系を背後に負っていると見る研究者もいます(鈴木福久氏など)。この“グラムシ社会学”の再構築は、ギトンにはたいへん魅力的に思われます。
ためしに、ツイッターで「グラムシ」を検索してみましたが、あんのじょう、ごく少数の人が、ちらっと触れているくらいで、グラムシを中心にしているツイッタラやBOT(ギトンの『春と修羅』BOTのような)はありませんでした。
「Gramsci」で海外のツイッタラまで検索したら、もっといろいろ出て来そうですが、大部分はイタリア語かもしれませんね(^^;)
ミヤケンを調べて、どうにかオリジナルな考察を出せるレベルまで来たというのに、この上、トルストイだ、グラムシだ、と到底手が回りそうにないのですが‥
それでも、注目すべき思想家として、ホブズボーム、ピケティなどと並んで、グラムシを念頭に置きたいと思います。φ--)

そして、LGBTについても、このさいいろいろと考え直しているのですが‥
“同性婚”、カムアウト、差別解消―――といったことは、もちろんとても大切なことですし、引き続き日本でも(台湾に先を越されそうですが)努力を続けて行くのがよいと思うのですが、私たちが取り組むべきことはそれだけじゃない、ということを考え始めています。
つまり、大切なのは、権利の拡張だけではない、権利拡張よりもっと大切なのは、それを包摂した意味での“カウンター・ヘゲモニー”を構築することなのだ‥とか。
では、“カウンター・ヘゲモニー”を構築するとは、具体的に何をすればよいのか?………それをこれから、じっくりと考えてみたいのです。。。
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]


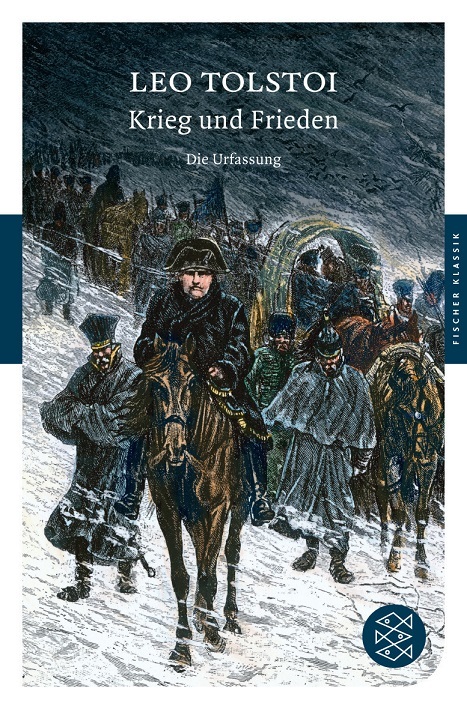




 彡
彡