11/21の日記
03:18
【ユーラシア】トルストイ
---------------
.

犂を挽くトルストイ
おこんにつわ(^.^)y
大正時代の作家やジャーナリストを調べていると、かならず出てくるのが“トルストイの影響”ということです。
言ってみりゃ世界的ブンゴーなんですが、今では影が薄くなってます。日本語訳の全集も、1960年代に一度出たきり、その後出てないんですね。それも、中村白葉とか古い訳者‥英訳からの重訳ではないかしらん。。。 ミヤケンの全集は当時以後4回出てるというのに...
しかし、明治時代末から大正時代、昭和初めにかけては、日本でもトルストイは広く読まれていて、小説だけでなく、その思想が、多くの人に影響を与えていたようなのです。
たとえば、日露戦争当時の『平民社』の非戦論には、トルストイの影響が濃厚です。同じ時期に非戦論を唱えたキリスト者の内村鑑三、斎藤宗次郎らにも、影響があったかもしれません。
トルストイの紹介と言えば、白樺派なのですが、中心は武者小路実篤と有島武郎だそうです。ただ、この方面をギトンはあまりよく知りません。
保阪嘉内が、盛岡高等農林の寮で、宮沢賢治に初めて会った時に、保阪は「トルストイを読み百姓の仕事の崇高さを知って入学した」と自己紹介したので、賢治は驚嘆したそうです。
嘉内がトルストイに傾倒したのは、甲府中学校の大島正健校長の影響があるわけで、札幌農学校のクラーク教頭の下で大島とともに学んだのが内村鑑三。大島は卒業後、内村らが創立した札幌独立キリスト教会で一時期、牧師を務めています。⇒:風の谷(3)
内村鑑三がのちに無教会主義のキリスト教を興したのは、ロシア正教会を激しく批判して破門された☆トルストイの信仰につながります。非暴力主義・非戦論も、トルストイと内村に共通しています。もっとも、内村が直接トルストイの影響を受けたということではないようですが。
☆ 形式的には、破門を宣告したのはロシア帝国の宗務院(聖務会院)で、正教会は「破門したことなどない」と現在では主張しているそうですが、当時のロシア正教会は政教一致の国教で、ピョートル大帝以来、総主教(聖界のトップ)を廃止してツァーリの聖務会院の統制を受けていたのですから、実質は教会による破門。
宮沢賢治は、直接、作品や書簡などでトルストイに言及したことはないのですが、保阪の影響もあってか、“農民芸術”の先駆者として敬意を払っていたようです。
1926年1月に『岩手国民高等学校』(一般公募の市民大学のようなもの)で担当した「農民芸術」講義では、第1回講義で「トルストイの芸術批評」を説明しています(受講生・伊藤清一による筆記ノート)。
ところが、賢治自身の講義メモ「農民芸術の興隆」には:
「Wim. Morris 労働はそれ自身において善なりとの信条 苦楽 苦行外道 狐 トルストイ」
★ 「Wim. Morris」はイギリスの社会民主主義者ウイリアム・モリス。「苦行外道」は、仏教以外の宗教の苦行者。
とあって、トルストイにあまり良い位置づけを与えているとは思えませんね。
それでも、じっさいの『羅須地人協会』での講義では、トルストイとゲーテを並べて高く評価していたようです。受講生・伊藤克己の回想「先生と私達」によれば(『新校本全集』「年譜」,p.335):
「短い期間ではあったが、そこで農民講座が開講されたのである。〔…〕
或日午後から芸術講座(さう名称づけた訳ではない)を開いた事がある。トルストイやゲーテの芸術定義から始まつて農民芸術や農民詩について語られた。」
賢治研究者の間では、賢治はトルストイからも大きな影響を受けていたと考えられていて、『定本宮澤賢治語彙辞典』には:
「トルストイの影響は、賢治がかねて愛読していた『芸術論』が中心と推定されるが、このトルストイズムもまた大正の時代思潮の大きな柱であった。賢治の『農民芸術論』でも柱の役目をしていると言っても過言ではない。」
と書かれています。
じっさいに、そうなのか? ‥自分で確かめるには、トルストイの思想を理解して、内容的にミヤケンの“農民芸術論”にどんな影響を及ぼしているか、見てゆく必要がありそうです。

ヤースナヤ・ポリャーナ(トルストイ家領地)の領主館
ところが、‥ギトンは、ドストエフスキーはかなり読んでいるのですが、トルストイは、じつは1冊も読んだことがないのです。童話絵本の『イワンの馬鹿』も読んだことがなかったですw
ちなみに、ミヤケンの『注文の多い料理店』チラシに「イーハトヴは‥イヴン王国の遠い東」にあると言う「イヴン王国」は、トルストイの“イヴァン王国”の誤植か変形だという説が有力です。『イワンの馬鹿』で、3人兄弟の末弟イワン(原語では Ivan:イヴァン)が王様になった国では、王も国民も、無欲で無抵抗で金銭も軍隊も持たず農業労働に明け暮れているので、悪魔が誘惑するすきがなく、2人の兄の国を破滅させた悪魔も、まったく手が出せなかったと。
しかし、トルストイを読まずに、大正時代は語れない‥ ミヤケンは語れない‥ というわけで、このさいトルストイに取りつくことにしました(^^;)
新しいものを取り入れるときのギトンのやり方は: もうご存知と思いますが、まず、最新の情報を入手して、できるだけ手っ取り早く、一足跳びに相手のピークを押さえてしまいます。宮沢賢治の時代に、そんなことがわかっていたのか?‥というようなことは、とりあえず考えません。
相手の“真芯”が、いちおう掴めたと思ったら、こんどは、ゆっくりと山を下りるようにして、ミヤケンが入手できた情報の範囲では、どういうことが解ったのか‥ といったことを考えていきます。
このようなやりかたをするのは、宮沢賢治の“眼力”というか、人並み外れた理解力の鋭さに信頼を置いているからです。ごくわずかな情報からでも、対象のかなり正確な理解に達することのできる並外れた能力を、賢治は持っていたようです。
モリス流の社会主義も、アインシュタインの特殊相対性理論も、彼は正確な理解に達していたことが、最近になって判明してきています。ただ、彼は決してそれをひけらかさないので、ミヤケンの書いたものを読んでも、正確に理解しているということが、かんたんにはわからないしくみになっているのです。つまり、“デクノボー”のふりをしているわけです。
というわけで、ギトンが“トルストイ”攻略にあたって、指針に決めたのは、↓これです:
藤沼貴『トルストイ・クロニクル』,2010,東洋書店(ユーラシア・ブックレット)
こういう場合によく入門書にする清水書院の「人と思想」シリーズと読み比べてみましたが、断然こちらのほうがいいです。清水書院のほうは: この本が読み終わったら、まず『戦争と平和』に取っつけと‥ そんなことしてたら何年かかるかわかりませんわいw
「トルストイの思想を理解するためには、すでに述べたように、トルストイ思想構築の時期〔1886-98年―――ギトン注〕の著作を『生命論』『クロイツェル・ソナタ』『神の国はあなたの中にある』『芸術とは何か』の順に読むべきであり、それが必要十分条件である。」
『トルストイ・クロニクル』,p.58.
『生命論』『クロイツェル・ソナタ』『神の国はあなたの中にある』『芸術とは何か』は、この順に、トルストイの思想構築の《第1期》《第2期》《第3期》《第4期》を代表していて、順にそれぞれ、「生命」「性」「非暴力」「芸術」をテーマとしています。
「『復活』は〔…〕〔トルストイが書いているうちに―――ギトン注〕次第に拡大発展し、トルストイ思想全体を複合的に表現するものになった。トルストイ思想全体をまとめた論文形式の著作は書かれていないので、『復活』がトルストイ思想を全面的に表現した唯一の作品である。」
『トルストイ・クロニクル』,p.59.
というわけで、数ある長編小説の中では、『復活』を読むのがよさそうです。『戦争と平和』は、トルストイとしてはまだ独自の思想が固まる前の初期の作品で、おもしろいかもしれないけれど、トルストイが“正念場”の思想危機に逢着するより前の作品です。速成コースでピークに達するには、『戦争と平和』を延々と読むのは時間の無駄ですw
ちなみに、『復活』といえば‥ (ギトンは、「カチューシャかわいや」の歌しか知らないんですがw) 宮沢賢治に、『復活の前』という初期短編があります。『復活』(1900年完成・発表)の“前”のトルストイの著作と言えば: 『神の国はあなたの中にある』か『芸術とは何か』あたりになるでしょう。
『復活の前』の内容からすると、『神の国はあなたの中にある』のほうかもしれません。このトルストイの論文は、非暴力主義を主張したものです。
『復活の前』は、“賢治批判”を唱える論客たちから、賢治=ファシストの例証として挙げられているものですから、彼らに反論するためにも、トルストイ研究は有効かもしれないですねw

さて、トルストイの思想構築《第1期》の
「眼目はトルストイ思想の根源である『生命』の追究と説明である。トルストイの説明は下記のようなものであり、難解どころか、むしろ単純である。
『人間の生命は細胞や動植物の生命とは違う。それは生きようとする意志であり、幸福になりたいという願いであり、生きていくための原動力である。しかし、それは自分の幸福のみを望むエゴイスティックなものではない。自我の死によって断ち切られる有限なものであり、恐怖と背中合わせになっている。他人のため、全体的な永遠の生のために生きることによって、真の幸福な生が得られる』。
このことはこの時期に書かれた『生命論』で詳しく説明されている。」
『トルストイ・クロニクル』,p.51.
ミヤケンの日本仏教的な生命観とは、かなり違うようですが、とりあえずミヤケンは忘れて、トルストイを理解したいと思います。まずは、ともかくピークへ‥‥
なお、同じ《第1期》に書かれた『イワン・イリイッチの死』『光あるうちに,光の中を歩け』も、トルストイの生命論の内容を表した小説。
↑この『生命論』とほぼ同じことは、1879年の小論『教会と国家』にも書かれていた。そこでは、人間の生命の「生きようとする意志」「幸福になりたいという願い」を、「生命に与えられる意味」「生命に力、方向を与えるところのもの」と表現し、それこそが「信仰」にほかならないとしていた。
また、「信仰」とは、神と一人の人間との直接の関係であり、その間に「ほかのものが介在してはそれは信仰とはいえなくなる。」「真のキリスト教は宗教的規則を一切必要としない、法律も神話も呪術も必要としない」、したがって、人と神との間に立ちはだかっている「教会こそが真の信仰の最大の障害物ということになる」(八島雅彦『トルストイ』,清水書院,1998,pp.138-140)
しかし、それでは、「真の信仰」とは、どんな内容のものなのか? 生命に、どんな「意味」を与え、どんな「力、方向」を与えるのか?
トルストイによれば、それは神によって与えられるのであり、神以外の者に(たとえばトルストイに)、どんな信仰を持つべきか?‥と訊ねること自体が、信仰の阻害でしかない―――ということになってしまうのだが、
しかし、幸いにして、ヒントはキリストによって与えられている:
『私の信仰はどういう点にあるか』(1883年)によれば、「トルストイにとって、すべての鍵になったのは、マタイによる福音書の第5章にある次の文であった。
『あなたがたも聞いているとおり、「目には目を、歯には歯を」と命じられている。しかし、わたしは言っておく。悪人に手向かってはならない』
悪人に手向かってはならない―――この言葉をそのまま素直に心に受け入れたときに、トルストイの前にまったく新しい世界が見えてきたのであった。〔…〕
悪や暴力は、いかなるときに、いかなる使われ方をしようとも、決して善に転化することはありえないし、人に幸福をもたらすこともありえない。悪や暴力に打ち勝つものはまじりけのない善であり、ただ愛だけである―――キリストの教えをトルストイはそのように理解した。〔…〕
悪に手向かってはならないという教えは、〔…〕悪は決して善にはならないし、愛を生むこともないということを言っているのである。」
八島雅彦『トルストイ』,pp.141-142.
つまり、もし「悪に手向か」うならば、手向かうほうもまた、相手に劣らない「悪」になってしまうからです。
この論旨は、《第3期》の「非暴力」主義に発展してゆくことになります。
しかし、トルストイは、人と人との喧嘩沙汰のような場合だけを念頭に置いているわけではありません。相手一人を傷つける(場合によっては殺してしまう)だけの「悪」は、トルストイによれば、軽いほうなのです。それは、“憐れむべき悪”と言ってもよい。
これに対して、どうしても否定しなければならない巨大な「悪」、「悪や暴力は、いかなるときに、いかなる使われ方をしようとも」とトルストイが言う場合の「悪」とは、
たとえば、国家の暴力装置である 警察―裁判所―処刑場 というしくみを考えてみれば判ります。
犯罪に対する処罰であれ、もっと恣意的に、権力者が政敵や気に入らない人間を消すための手段としてであれ(帝政ロシアでは、こちらも相当に多かった)、裁判所は、悪ないし憎悪と、有形・無形の暴力(強制力)とを常に使用します。しかし、それらが、どんなに正義の装いの下に使用されようとも、悪は最後まで悪だし、暴力が暴力でないものに変化するわけでもないのだ、とトルストイは断じるのです。
したがって、イエスにとっても、トルストイにとっても、人間のこしらえたすべての国家は悪であり、教会も、おそらくは他の宗教の寺院も、すべて悪なのです。それらは、人間に災いをもたらすだけであり、けっして幸福をもたらしはしない―――福音書のイエスが宣べる・この純粋無垢の真理を、トルストイは直裁に受け入れます(八島雅彦『トルストイ』,pp.143-145)
「福音書のキリストの教えは、こうした醜悪な教会そのものの否定ではなかったのか―――そう考えるとき、キリストの教えは、どこにも不明瞭なところのないまったく合理的なものに思われた。
キリストは、神以外の権威を認めず、神の前での万人平等を説いていた。キリストの教えはただそれだけであり、それは〔教会で教えられている“キリスト教”とは異なって―――ギトン注〕神秘的でもなければ不合理でもなかった。〔…〕
キリストの教えは教会と国家の否定にほかならないと考えれば、キリストの教えは首尾一貫しており、どこにもあいまいな点はないとトルストイには思われた。」
八島雅彦『トルストイ』,p.64.
「1887年には『生命について』が書かれた。この著作は一方に教会を意識し、また一方に自然科学、さらに当時流行していたペシミズムの哲学を視野に入れた思想書である。来世を教えることによって現世での服従を説くことの欺瞞性を暴き、自然科学的なものの見方は人を指導する力を持たないことを論証し、この世のあり方を悪と見なす見方が一面的なものにすぎないことを指摘しながら、トルストイは全力を傾けて、キリストの教えが合理的なもので、人に幸福をもたらす教えであることを主張している。
無論のこと、この著作も発禁処分になった。」
八島雅彦『トルストイ』,p.71.
すなわち、トルストイにとっては、自然科学も、また、よりよい国家や制度を求める社会改良も、人間に幸福をもたらすことはないのです。なぜなら、それらはみな、人間と神との関係、すなわち「愛」に対する不信を掻き立て、人間を欲望のとりこにし、そうして人間の他の人間に対する暴力を増大させるからです(八島雅彦『トルストイ』,pp.145-148)
「第1段階で、トルストイは『生命』について説き、真の生命は全体と永遠の生のために生きること、つまり、愛であると主張した。
第2段階では、『愛』の追究がさらに深められる。現代では『愛』という言葉が自分を愛することか、あるいは、家族愛、愛国心のような、エゴイスティックな愛を少し拡大したものを意味している。特に男女の愛こそが最高の愛のように喧伝されている。しかし、多くの場合、男女の愛は性愛であり、自分の欲望を相手に注ぎかけるもっともエゴイスティックなものである場合もあり、しばしば暴力にさえなる。トルストイはこの性愛を激しく否定した。
そのことを示すために書いたのが『クロイツェル・ソナタ』である。」
『トルストイ・クロニクル』,p.58.
「第3段階では、『愛』と『性愛』が混同されているのは、現代の社会が暴力を根源としているからであり、そのもっとも恐るべきものが国家権力と、それから生じる戦争であると言い、絶対非暴力、権力否定、非戦、絶対平和を主張。それを実現するためには、暴力につながらない道徳的な方法によるべきことを説いた。それが後期最大の著作の一つ『神の国はあなたの中にある』である。
この作品を完成することによって、トルストイ思想の体系化はほぼ終了した。」
『トルストイ・クロニクル』,p.55.
“神の国は”あるいは“神は、あなたの中にある”とは、どういうことか?
1907年に若者たちにあてて書いた雑誌論文の中で、トルストイは、
「自分自身の内なる声に耳を傾けよ、ただそれだけに耳を傾けよ」
と書いている。「自分の奥深いところにある普遍的な自分は神そのものではない」が、「最も理性的な自分であり、その声は確かに神から出ているのだ」
大人たちは、君たちに言うかもしれない。家のために、国家のために、あるいは、「人類」のために尽くせと。しかし、そんな声に耳を傾けてはならない。
「人類の歴史は家対家、団体対団体、民族対民族、国家対国家の争いの歴史」にほかならなかった。
「家にしても民族にしても」国家にしても、「全体の一部にしかならないものへの奉仕は善を生み出しはしない。」それは、「人類」への奉仕でも同じことなのだ。なぜなら、「人類」とは「漠然とした観念であり、〔…〕『人類』という観念の前では、人はどうしても恣意的な行動しかとることができない。」「人類」のための奉仕という美名は、しばしば最も激甚な「人間同士の争いを引き起こし」てきた。
だから、「全体」とは、神をおいてほかに無い。「神への奉仕とは何か―――それは、価値の尺度をただ神だけに求め、神の前によりよい自分を築き、自分の中に愛を発現して行くこと〔…〕だから、ただ神の声としての自分自身の内なる善の声に耳を傾けなさい」
八島雅彦『トルストイ』,pp.194-197.
すでに《第3期》の『神の国はあなたの中にある』で、トルストイ思想はほぼ完成していたのだが、その後の《第4期》では、
「さらに加えて、自分が長年かかわってきた芸術は、それ自体独立したものではなく、よい思想、よい生活に奉仕するものであることを主張した『芸術とは何か』を書き上げることによって、トルストイ思想体系の構築は完結する。」
『トルストイ・クロニクル』,p.57.
さて、以上でトルストイ思想の“核”を、ざっと通覧したわけですが、
どうですか?
トルストイと言えば「人道主義」………と、なんとなく思っていたイメージが、ズタズタに破壊されていませんか?w
国家も教会も全否定、しかし、完全な非暴力。社会改良も革新運動もダメ!‥まして、革命など、もってのほか!
ということになると、これはもう、仙人にでもなるほかはないかも... じっさい、トルストイは、中国の老子に関心を持っていて、『老子(老子道徳教)』の翻訳までしています。最晩年には、ついに家出しました―――どこか遠くの荒野で断食して、仙人になるつもりだったのでしょうか?‥途中の駅で倒れて病死しています。
そのトルストイ自身も、最晩年の家出の直前までは、ふつうの生活を……いや、ふつう以上に贅沢な貴族の生活をしていたのです。“トルストイ主義”を徹底して生きることは、トルストイ自身にもできなかったのです。
しかし、だからといって、彼が見つけた“真理”自体は‥それが客観的な真理である以上、その価値が減るわけではない。―――これが大切な点だと思います。とかく、日本人は“言行一致”を求めるあまり、著者の行状次第で、著作の価値が左右されるかのように考えがちです。“真理の発見”と“真理の実践”を、あまりにも短絡しすぎるので、その結果、かえってまともな実践ができなくなるきらいがある。
じっさい、トルストイは、“純粋”なトルストイ主義の実践ではなく、むしろ社会改良的な活動を、ひじょうにまめにやっています。自分の領地を中心に、農民子弟に無料で識字・算数・科学実験などの教育を行う学校設立運動。飢饉の際には、農村に建てた無料食堂が 200を越えたと言います。
しかも、決して自分一人の資金(大貴族トルストイ家の資産は、それだけでも莫大なものですが)で慈善をしているのではなく、他の貴族、地主にも広く呼び掛けて基金を集め、社会運動として行なっているのです。(そのため、帝国政府の弾圧を受けそうになって、学校のほうは閉鎖しています。)
そうした大がかりな事業以外にも、晩年のトルストイは日常的に、自分の領地で、働き手の足りない貧困な農家の農事を手伝っていました。しかも、トルストイ家総出で!(もちろん、領地があるからこそ、できることですが‥)
↑いちばん上の絵画は、その様子を描いたものです。
そこから‥トルストイ自身の行動から分かることは、“トルストイ主義”は、仙人になるための教えではないということです。純粋な実践は不可能です。純粋に実践しようと思ったら、私財を棄てて、放浪のイエス・キリストになるほかはないでしょう。
要は、それを読んだ者各人が、それぞれの事情に応じて、どのような実践に反映させるかを考える必要がある―――そういう理念なのだと思います。
“トルストイの思想は難しい”と言われますが、それは、理屈が複雑で頭が良くないと理解できない、という難しさではないと思います。“核”になる真理そのものは、↑上に書かれたとおりで、きわめて単純です。仏教の“涅槃”の真理のような神秘性もありません。文の意味そのものは、誰にでもわかります。
トルストイの難しさは、その真理を受け入れることの難しさなのだと思います。このような過激な真理を受け入れるためには、受け入れる側の人生観・社会観・世界観を根底から考え直して、“迎え入れ”の準備をしなければならないからです。
その真理が過激なのは、純粋に、このとおりに実践せよ、という意味ではなく、極北の真理は、こうなのだから、たとえあなたの実践がどんなに過激化しても(ただし暴力は禁止)、やりすぎるということは決してないから安心せよ、という意味なのだと思います。

1881年、モスクワに住みついたトルストイは、貧民の多いことに驚き、「民衆から絞り取ったもので財産をこしらえた悪人たちが、その財産を守るために兵隊と裁判官を雇い入れ、そうして安心して好き勝手なことをしている」と嘆いた。そして、1885年初め雑誌に投稿した『では、われわれは何をするべきか』の中で:
「トルストイは、〔…〕土地の私有を廃止し、軍隊を廃止し、税金を廃止する考えを打ち出している。〔…〕
トルストイの主張は何の強制力も持たないし、そこから何らかの組織立った政治運動が生まれてくる可能性もないように見えるが、この著作はただちに発禁処分を受けた。
政府が恐れたのは、自分個人の意志で権力から離脱する人間が一人また一人出てくるという、権力の内部崩壊であったが、トルストイのねらいもまさにそこにあった。
〔…〕無抵抗主義の主張からトルストイ主義という言葉が生まれることになった。〔…〕悪に対する無抵抗と暴力の絶対否定ということが現実社会の中では、軍隊からの離脱、徴兵拒否、裁判制度の否定を意味した。
政府にとって、トルストイ主義は対処のしにくい厄介なしろものであった。」
八島雅彦『トルストイ』,pp.68-70.
“指針”のブックレットと清水書院を、ひととおり読んでみて、ギトンがまず思ったのは、1905年(日露戦争中)の「ロシア第一革命」は、トルストイの思想が浸透して起きたんじゃないか‥ ということでした。
直接、トルストイの思想が広まって、ということではなくとも、それと同じような: 国家も教会も否定する、しかし“神”に対しては誓って誠実、そして非暴力 ‥そういう思想が、農民や一般民衆の間に、広く深く浸透して行った結果だったのではないか、という気がしたのです。
そして、―――トルストイの死後ですが――― 1917年の「ロシア革命」も、3月に帝政が倒れるところ(2月革命)までは、やはり一種の“トルストイ主義”浸透の延長線上で、‥人々は平等(土地の分配)と平和(第1次大戦からの離脱)を求め、同じ思想の浸透を受けた兵士までが、それに合流した結果、帝政国家は無力化してしまったのではないか?‥
もちろん、その後の労農ソヴィエトの族生と、それを掌握したボルシェヴィキの権力奪取(10月革命)は、トルストイが全く予想していなかったシナリオです。しかし、ツァーリの国家と教会が、民衆に完全に見放されて“権力の空白”が生じてしまった―――この事態は、“トルストイ主義”の浸透としか説明できないと思うのです―――、その“権力の空白”があったからこそ、レーニンのような“組織化の天才”に、能力を発揮する機会が与えられたのだと思います。
ところで、そのレーニンが“トルストイ論”を書いているそうです。どんな内容なのか?
‥落伍した前資本主義段階の人道主義者、といったイデオロギー批判だけの代物だったら、レーニンを軽蔑しますが(そんな決めつけ論文は、誰にでも書けますw)、そうではないと期待しているのです。かならずや、“偉大な個性”どうしのぶつかりあいが見られるにちがいない‥‥ 図書館に注文を入れておいたので、届くのが楽しみです。
ところで、おっとっと‥‥ ギトンはまだトルストイを1冊も読んでいないのでしたw さて、いちばん薄そうな『光あるうちに‥』から読み始めますかね。。。
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]




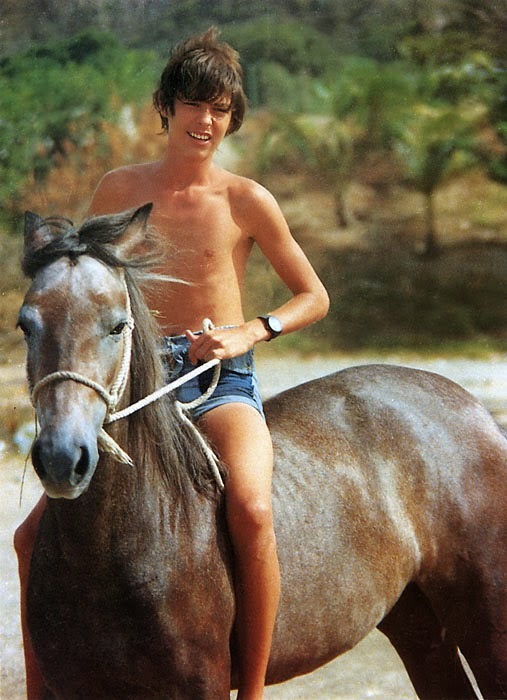

 彡
彡