08/14の日記
05:15
【ユーラシア】グレイト・ゲーム(2)
---------------
.
こんにちわ(^.^)o
「大谷探検隊」を組織した大谷光瑞といえば、
当時、伯爵の爵位を持ち、天皇家と姻戚関係もある・いわば日本の宗教権力の頂点と言ってよい人物でした。
その教団・本願寺派は、江戸時代に幕府の庇護を受けて振るった勢力を、いまだ失ってはいませんでした。全国に張り巡らされた末寺から吸い上げられる潤沢な教団資金の使途は、事実上大谷光瑞の意思に左右されており、大谷個人の家計との区別は曖昧でした。
(そのためか‥、「第3次探検」の終結した 1914年、本願寺派の疑獄事件を機に、大谷家の抱えた巨額の負債が発覚し、光瑞は法主を辞任し、「探検隊」が将来した遺物・古文書類は、売却されて大谷家の負債返済に充てられました。こうして、貴重な西域文化財が、国内外に散逸することとなったのです。『西域 探検の世紀』,pp.204f.)
中央アジアに探検隊を何度も送る莫大な資金を、「法主」の考え一つで好きなだけ注ぎ込むことができるような“宗教権力”が日本にはある―――ということが、外国の人々には、想像できなかったのでしょう。
教団の財政と「法主」個人の財布との区別は曖昧で、大谷光瑞が「こうしたい」と言うだけで、現在の貨幣価値にして数億のお金が、ポンッと送金されてしまうのです。そこには稟議も審査もありませんでした。
北インドで「第1次探検」中の光瑞と知り合った英国インド軍のフレデリック・オコナー大尉は、後年の回想記に、↓こう書いています:
「『私は当地で、日本仏教界の西本願寺法主であり、大変興味深い日本人の大谷光瑞伯爵の知遇を得た。
〔…〕私が初めて大谷伯と会ったのは、〔…〕彼は同行の二人とちょうど〔…〕中央アジアを横断したあと、〔…〕たまたまインドに向かう途中、彼とはブルジル峠近くで偶然に出会い、カシミール渓谷をずっと一緒に旅し、大変仲よしになった。私は大谷伯の広い読書量とアジアの政治・歴史・地理の博識ぶりに、大変感銘を受けた。
ところが当時、私は彼が日本でどんな枢要な人物であるか気づかなかった。』
〔…〕
彼はのちに 1908年、たまたま日本を訪問した際、ただ古い友人とばかり思って京都の西本願寺に光瑞を訪ねたところ、相手が大教団の最高位者である法主で、しかも大歓迎してくれたのにはびっくりしたと語っている。」
金子民雄『西域 探検の世紀』,p.94.
こうして、“浄土真宗・西本願寺”という教団の・まったく私的なプロジェクトだったということが、西域探検史のユニークな存在「大谷探検隊」の際立った特色であり、それは長所にも短所にもなっていると思います。
長所のほうから言いますと、どこの政府のヒモ付きでもない純粋な“学術”目的の探検だったことが挙げられます。
もっとも、“学術”と言うには若干の留保が必要です。
探検隊のメンバーは、おおぜいの地理学者や考古学者を組織したものではなく、わずか数人(「第2、3次探検隊」は2人)の西本願寺派の僧侶を中心とした顔ぶれです。
たしかに、彼らの仏典の知識は豊富で、唐の玄奘(三蔵法師)が書いた『大唐西域記』や法顕の『仏国記』の漢文原書を道案内に携えて行ったほどですから、漢文の読めない西洋人よりも、その点で数歩抜きん出ていました。
しかし、彼らは、考古学による学術的な発掘の訓練を受けていません。また、古美術や古美術品の取扱いに関する知識も不十分でした。そのため、発掘の方法が稚拙で、重要な出土遺物を壊してしまったケースがあるほか(※)
(※)「第2次探検隊」の橘瑞超は、タリム盆地南東部のミーランで「有翼天使像」を発掘しましたが、無理に切り取って日本に持ち帰ろうとしたために、天使像の大部分を破壊してしまい、また、同じ場所にあった「ヴェッサンタラ王・白象寄進図」壁画を全部破壊してしまいました。⇒:〜ゆらぐ蜉蝣文字〜 3.8.2《ミーランの有翼天使像》と橘瑞超
彼らの持ち帰った遺物や美術品が、どこでどんな状態で発掘されたのか、その手掛かりになるような正確な記録も、ほとんど残していないのです。
記録と言えば、一部の隊員がつけていた日記があるくらいで、調査日誌と言えるようなものは皆無です。これでは、まるで宝探しのようなもので、山のように掘り出して持ち帰った美術品、古文書、経典のたぐいも、学術的価値は半減してしまいます。
「日本ではまだ考古学の調査方法が十分確立していなかったので、西本願寺隊も壁画、仏像、古文書、古銭や古物品を熱心に集めたものの、記録と整理に不備があって、発掘品の正確な出土地が不明になるものが多かった。これは前後三回の探検を通しての共通の欠陥だった。」
『西域 探検の世紀』,p.100.

橘 瑞超
さらに、隊員の人選もあまり適切だったとは思えません。大谷光瑞の個人的な好みに左右されたかもしれません。
なかでも、第2次探検隊から参加する橘瑞超は 18歳、真宗中学校を卒業したばかりの少年でした。
「橘瑞超は3年前の 1905(明治38)年4月、名古屋県立中学校の3年生を修了したところで、光瑞に才能を認められて京都に行き、私立真宗中学校に転入した〔…〕光瑞の一字をもらって曜弘を瑞超と改名している。光瑞の大変なお気に入りだったのだろう。
〔…〕いったいどんな風の吹き回しから光瑞は瑞超を抜擢したのだろうか。のちに光瑞が、彼は頭も切れ、豪胆・健康だったからと言っているが、もっと別のなにかヒントがあったのではなかったろうか。〔…〕前回の探検隊員の渡辺哲信と堀賢雄〔「第1次探検隊で、西域を担当した隊員――ギトン注〕は体験も学力もそなえた常識人だった。そのため無謀で突飛な発想に欠ける。
一方の〔…〕瑞超は 18歳〔…〕機知に富み、決断力もある。難局を乗り切るにはデリケートな感情より、ときに強引でしたたかさもぜひ必要だ。
光瑞はときどきとんでもない発想をして人を驚かせたが、西域探検事業がまさにそうだった。」
『西域 探検の世紀』,pp.115-116.
インドで橘瑞超に会った日本の新聞記者は:
「瑞超に初めて会ってびっくり仰天したと言っている。なにしろ西域を探検して来たばかりだから、きっと筋骨逞しく、髯も生やした年齢30歳ぐらいの人物と想像していた。ところがなんと身長わずか5尺2寸(157.5センチ)、全体から受ける印象はまるで18,9の妙麗な処女のような姿だったから、一層驚かされた。」
op.cit.,p.154.
「第2次探検」に同行した野村栄三郎も 1880年生まれで当時 28歳。
「第3次探検」に至っては、日本から行ったのは橘瑞超ひとりで、これに、英国で公募した 18歳の隊員ホッブズと、ロシアで雇った 17歳の通訳の3名で西域に向かったのです。
現地で橘瑞超に会った人々は、“15歳くらいに見える”と書いています。熟練した大人の学者・探検家を組織した各国の探検隊には、彼らは子供の探検ごっこのように見えたことでしょう。
なお、「第3次探検隊」の吉川小一郎は、当初からの隊員ではなく、橘が西域で消息を絶ったため、光瑞が捜索のために派遣した人で、敦煌で橘と落ち合った後、敦煌文書を入手したほかジュンガリア方面を調査しています。
大谷光瑞は、知識、経験よりも、もっぱら若い体力と精神力、したたかさに着目して探検隊員を選んだようでした。
年が若いというだけでなく、橘と野村は、英語も十分に話せなかったようです。カシュガルの英国領事代行は、本国に、こう報告しています:
「『橘はざっと見たところ 15歳ぐらい。彼(野村)はまったく英語を話しませんが、橘はわずかな単語を知っています。彼らはトルコ語〔中央アジアで現地人に通じる外国語のひとつ――ギトン注〕は分かりませんが、二人とも中国語は流暢に話します。
彼らは威張り、なにか困った場合に手助けするように付けた者を、気に入らないと殴りつけたりしたので、彼らは当地で清国人からいたって評判が悪いのです。橘にムズターグ峠を越えることのできない理由を語って聞かせると、小官に生意気な態度をとりました。そこで小官はきびしく叱りつけねばなりませんでした。彼らが金を貸してくれるかと訊ね、すぐに要求に応じて用立ててくれるよう小官に求めたときなど、両名にはきわめてぞんざいな態度がありありと見えました。』」
『西域 探検の世紀』,p.149.
英国人の領事代行は、「二人とも中国語は流暢に話します。」と書いていますが、これは疑問です。中国語を解しない代行が、ちゃんと中国語を話しているかどうか聞き分けられるとは思えないからです。むしろ、漢字は読めても中国語はせいぜい片言だったと見るべきでしょう。
橘らが、中国人や現地人との間でトラブルを生じたのは、コトバが通じないことが大きな原因だったと考えられます。英国領事館だけでなく、ロシア当局、清国当局、いずれとも軋轢を起こしていますが、これも、コトバの問題が大きかったはずです。
また、それ以上に、各国は、橘らは日本のスパイだと疑い、現地の人々の間では、橘らが軍事目的の測量をしているなどの噂が飛び交っていたので、誰もが彼らに警戒心を抱いていたのです。

とはいえ、橘瑞超は、大谷光瑞が見込んだだけのことはあって、発掘の不手際や、人間関係のトラブルは数多く起こしながらも、砂漠でのサバイバルの能力にかけては、ヘディン、スタインら老練な探検家をも凌駕する実績を残したのです。
瑞超が「第3次探検」で単独で行なった“タクラマカン砂漠(タリム盆地)縦断行”について、金子民雄さんは、つぎのように書いています:
「この沙漠縦断のルートも、位置の測定をしていなかったので正確には地図上に描けない。ただチェルチェン〔タクラマカン砂漠の南東――ギトン注〕から天山南路〔タクラマカン砂漠の北縁――ギトン注〕上のブグルを直線で結んだルートが、彼のだいたいの踏破コースと言うことができる。かかった日数は 22日間だった。〔つまり、道のない砂漠を、ただ目的の方角に向かって直線的に踏破したことになる――ギトン注〕
どんな探検家でも、こんな無謀なことはまずしない。冬季とはいえ風がなかったからよかったものの、風に吹かれたらまず助からない。私も以前、この近くの砂漠の南縁部分から少し北側に踏み込んだことがあるが、砂丘の高さがざっと 30メートルにも達し、それは恐ろしい光景だった。
この第3次探検では、瑞超の行動にはしばしば常識では考えられないようなことが多いが、
ただこういった計画の大筋も瑞超単独の判断ではなく、だいたいが光瑞の旅行計画に従って指図どおり動いていたと見る必要がある。」
op.cit.,p.173.
この無謀な“砂漠縦断”も、橘瑞超はもちろん独りで歩いたわけではなく、現地で雇った案内人とおおぜいの人夫、駱駝隊を伴なっていたはずです。おそらく、この時は意思疎通とチームワークも良かったのでしょう。
金子さんの伝える瑞超“少年”の性格と容貌――オトメンで気位が高く、狡猾で、はしっこい(本には「機知に富む」と書いていますが、裏を返せば、ずる賢いということです)――から考えると‥
こういう人は、嫌われるとクソミソですが、うまく行っているときには信望が集中するのです。
オカマにも、こういうイケメン、よくいますねww
とはいえ、リーダーの橘自身の意志がくじけては、“冒険”を遂行することはできなかったでしょう。
瑞超は、法主の指示を完遂するという使命感と、天山南路のクチャ(亀茲)で待っている2歳年下のホッブズ隊員に会いたい一心で、支えられていたのではないでしょうか?
ところが‥ うまくいかないものです。クチャに到着した瑞超を迎えたのは、ホッブズ死去の報でした。
「せっかく危険なタクラマカン縦断をし、未知のタリム河の流路を発見してから天山南路に達して、クチャに急行してみたら、待っているはずのホッブズがなんと天然痘で急死していたことが分かった。
これは瑞超を心身ともに混乱に陥れるに十分だった。現代風の旅行者なら、このあたりで全てを放り出して帰国してしまうところだろうが、それは許されない。」
op.cit.,pp.173-174.
ホッブズの遺骸は、英国領事の手配でカシュガルに運ばれていたので、瑞超はカシュガルに行って、イギリス、ロシア両領事ほか在住外国人らの立会いの下で、ホッブズの葬儀を行ない、ホッブズの給与と所有品を本国の家族に送っています。
また、カシュガルにホッブズの墓碑を建てるために、100ルーブルを現地に託しています。
瑞超は、西本願寺への報告では、ホッブズを「従僕 故 A. O. Hobbs 氏」と書いていますが、決して単なる従者として扱っていたのでないことは、葬儀をはじめとする↑上の手厚い措置によっても判ります。
唯一の同僚隊員を失い、異国の砂漠にひとり取り残された混乱の中で、破局にくじけることなく遺漏のない事後処置を行なっていることは、敬服に値するでしょう。
「光瑞は決して面白半分ではなく、隊員の選考には実際頭を痛めていたにちがいない。探検は頭がいいだけでは適さない。どんな環境にも適応できなければ使いものにならず、神経質な者はすぐノイローゼになってしまう。よい意味で勇気としたたかさがなければ、一日として務まらないのである。」
op.cit.,pp.170-171.
ところで、組織者である大谷光瑞自身が参加した「第1次探検」の北インドでの調査について、最後に触れておきたいと思います。
「光瑞はカシュガル滞在後インドに向かい、1903年(明治36年)1月14日に、長らく謎の地の山であった霊鷲山を発見し、また、マガダ国の首都王舎城を特定した。」
「この山は長らくの間、場所も忘れられていたが、1903年(明治36年)1月14日朝、大谷光瑞が率いる第1次大谷探検隊が朝日に照らされたこの山を仏典上の霊鷲山と同一と確定した。数年後のインド考古局第3代目の長官ジョーン・マーシャルの調査によって国際的に承認された。」
ウィキペディアには↑このように書かれているのですが、金子民雄さんの本では、「第1次探検隊」のこの業績には、まったく言及がないのです(『西域 探検の世紀』,pp.93-96)。
理由として考えられるのは、マガダ国の王都はともかく、“霊鷲山”の発見には考古学的価値が認められないということではないかと思います。
“霊鷲山”は、『法華経』で釈迦が説法した場所とされている山ですが、『法華経』の書かれた年代は、紀元1〜2世紀の間ということで、今日では異論がないようです。
つまり、紀元前6〜4世紀の釈迦死没から数百年以上後のことですから、『法華経』に書かれた“霊鷲山での説法”は、フィクションと考えるほかはないでしょう。
ほかに“霊鷲山”が現れる経典としては、『観無量寿経』がありますが、これも大乗経典ですから、やはり成立は紀元1世紀より後になります。
フィクションの場所を“発見”するというのは……、フィクションの作者が考えたモデル――大乗仏教時代の信仰(虚構)の内容――を再現する以上の意味はないわけで、
釈迦時代の歴史的事実の探求としては、まったく無意味だと言わなければなりません。
さらに言えば、『法華経』が書かれた時点においても、“霊鷲山”が実在の場所だった保証はないのです。フィクションなのですから、架空の地名が書き込まれたとしても少しもおかしくはありません。
それを‥、あたかも“霊鷲山”なる場所が実在したのだと最初から決めつけて“さがす”というのは‥
推理小説ファンが、ロンドンのベーカー街へ行ってシャーロック・ホームズの“住居”を探しまわるのと、それほど違わないように思うのですが。。。
ばいみ〜 ミ 彡
彡
.
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]





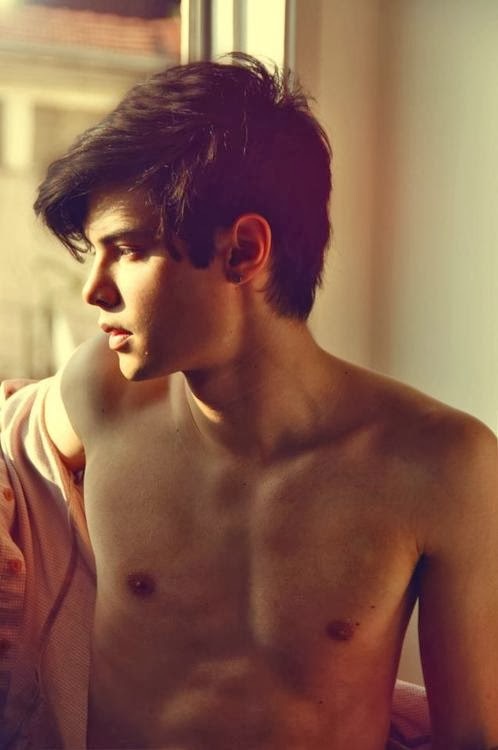

 彡
彡