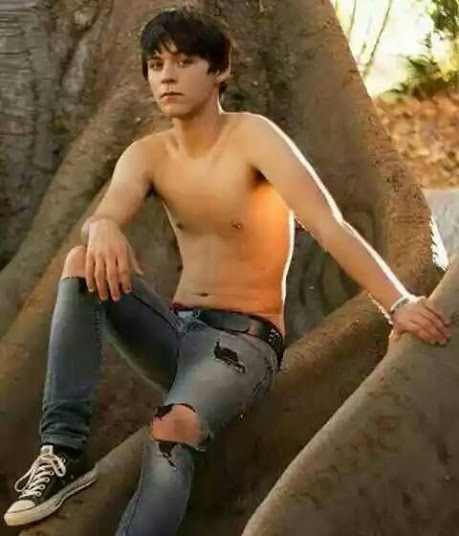03/23の日記
23:05
100年たってようやく‥(13)
---------------
こんばんは。。
「(わたくしはなぜ立ってゐるか
立ってゐてはいけない
鏡の面にひとりの鬼神ものぞいてゐる」(#106〔下書稿(一)〕)
「(おまへはなぜ立ってゐるか
立ってゐてはいけない
鏡の面にはひとりのアイヌものぞいてゐる」(#106〔下書稿(一)手入れ②a〕)
問題は、この「立ってゐてはいけない」だと思います。
「わたくしは」→「おまへは」に変えられているのは、作者の自分に対する言い掛けが、より強く厳しい自戒に変っているからだと思います。
いったい、作者は何を自戒しているのか‥あるいは、恐れているのか?
ギトンの感じた印象を言いますと、作者は、“中心部”の世界の辺境、征服者の世界の端っこから、“境界”をまたいで、向こう側の先住民の世界を眺めている。そして、“境界”──おそらく沼の水面が二つの世界の“境”になっています──の向うに見える‥または見えないものに対して、“恐れ”ないし“恐怖”を抱いているのだと思います。
征服者の世界のはじ、“先住民”の棲む異世界と接する突端に立っていると、“中心部”が膨張し征服してゆくその尖兵の役割を果たすことになるでしょう‥自分がそう望まなくとも、そういう役割をになってしまう‥
だから、「立ってゐてはいけない」.
「鏡の面」とは、何でしょうか?
先住民の《異界》との境界そのものを「鏡」と言っているようにも思えますが、また、作者は、池か沼地の水面を見ているようにも思われます。〔下書稿(二)〕の末尾に:
「アイヌはいつか向ふへうつり
蛾はいま岸の水ばせうの芽をわたってゐる」
とありますから、少なくとも〔下書稿(二)〕の段階になると、この「鏡の面」は、水面のことです。
いずれにせよ、「鏡の面」とは、その面の向こう側にあるものは見えない‥こちら側の世界の像だけが映るということです。
そうすると、「鏡の面には‥のぞいてゐる」「ひとりの鬼神」あるいは「ひとりのアイヌ」とは、水面に映った作者自身の姿とも受け取れます。
しかし、ギトンの印象は、やや違います。むしろ、「のぞいてゐる」という言い方が強く感じられるのです。
水面には作者の姿ももちろん映っているけれども、その背後の木立ちか草むらのまに、アイヌ(あるいは鬼神)の姿が見え隠れしている。猟のためか何か、歩き回ってるのが見える‥‥ということではないかと思います。
とくに、〔下書稿(二)〕のほうでは、その印象が強いです。
「アイヌはいつか向ふへうつり]
は、沼の向こう岸のほうへ回って行って、いまはそちらの森の中にいる、という意味でしょう。
つまり、宮沢賢治の作品の中で、アイヌは決して“亡び去る者”ではなく、現在も、作者と同じ世界の森や林の中で、生きて活動している人々なのです。
そして、彼らの姿を通して、あるいは、アイヌの生活圏にある沼地の水面や、花巻周辺に7ヶ所あるという霊樹の集まったスポットを通じて、“先住民”の過去の世界──「古い宙宇」──の「投影」を見ることができるのです。
以上の結論においては、秋枝さんの議論とも噛み合うと思います。というのは、秋枝さんも、講演の中で↓つぎのように述べておられるからです:
「賢治はそういうもの〔花巻に数ヶ所ある巨樹の場所──ギトン注〕にあるインスピレーションを感じるのである。そこに立っている『わたくし』の意識は『鏡』となり、その面に「鬼神」のまなざしを映し出す。古い記憶の中に埋めこまれた過去の思いが、『わたくし』の意識の中に生き返る瞬間を捉えている。これが語り直される過去の始まり、埋められた過去の再生を思わせる。」
秋枝さんが:
「古い〔種族的──ギトン注〕記憶の中に埋めこまれた過去の思いが、『わたくし』の意識の中に生き返る瞬間‥埋められた過去の再生」
と指摘されている点は重要だと思います。
〔下書稿(一)〕の推敲の過程では、↓つぎのようなテキストも、いったん書かれているのです:
「たたりをもったアイヌの沼は
そらや林をうつして光り
こっち岸では三つの赤い石塚を覆って
南の風にこゞりの枝をそよがせて
沼のこっちに立ってゐる
沼はむかしのアイヌのもので
岸では鏃も石斧もとれる、
そこに水ばせうの芽がうすびかり」
「沼は推敲の一過程では『たたりをもったアイヌの沼』とされ、詩人の想像力を、地上や地下の世界へ、心の暗部へと降り立たせる。そこからは鏃も石斧もとれるとあり、石塚はそれらのアイヌの生活の遺物を埋めたものとも思われる。しかし、〔…〕その沼から生えた『水ばせうの芽のうすびかり』は、アイヌの思いから生じた新たな命のように思われ、美しいイメージである。」(秋枝美保)
ギトンとしては印象の段階なのですが、‥知里幸恵が、自然に抱かれたアイヌの綻びのない世界を、彼女の“現在”にまでも繋がる近過去として描いているのに対し、宮沢賢治にとっては、そうした“完全な世界”は、もう滅び尽くしてしまった太古なのだと思います。それというのも、東北地方に生きた賢治の場合には、現在現実の民族であるアイヌが、知識として入って来るよりも前に、太古の“蝦夷”の言い伝えなどが習俗として染み付いていて、いわば無意識領域の種族的記憶として、そういうものがあったのではないでしょうか。たとえば、身近に古い土器が出土すれば、無意識のうちに“蝦夷”と結びつけて考えてしまう──そういう、知識以前の習俗としてです。
1910-20年代には、盛岡周辺で、縄文時代の土器・石器類がしばしば発掘されていたそうです。そこで、宮沢賢治は、アイヌと言えば、北海道やサハリンで暮らしている現実の人々以上に、かつて東北で暮らし、出土遺物を残した人々を思い浮かべたのではないでしょうか。
しかし、同時に、賢治の場合には、“亡びつくしてしまった”あとの再生の予兆を、仄かにではあっても見ている点に、積極的意義があると思います。
『アイヌ神謡集』も、賢治はアイヌの再生の兆候として見ているのだと思います。その・ゆるぎない胎動は、
「ひとりのアイヌものぞいている」
「アイヌはいつか向ふへうつり」
という・飾らない動きの中に捉えられていると思うのです。
修学旅行での白老“アイヌ部落”訪問について、賢治が書いた『修学旅行復命書』には全く言及が無いのですが(訪問の事実が分かるのは、同行したもうひとりの引率者・白藤教諭の日記によってなのです)、おそらく賢治は、訪問による雑然とした強烈な印象を、すぐにはまとめることができず、付き添った「役場の吏員」の説明にも納得できないものを感じ取っていたからだと思います。
そこで、宮沢賢治の“アイヌ観”は全く消極的なものだと思われるかもしれませんが、決して消極的ではないのだと思います。むしろ、あたかも消極的であるかのように見えるのは、広く深い“先住者”の歴史の流れの一部として、アイヌを見ているからだと思います。賢治にとって、アイヌは、東北地方の“蝦夷”や、手宮洞窟の壁画を描いた古代民族を含む“先住者”たちの滔々たる流れの突端としてあるのであり、東北人である自己の存在と、深部において繋がるものとして理解されていたのです。
ばいみ〜 ミ 彡
彡
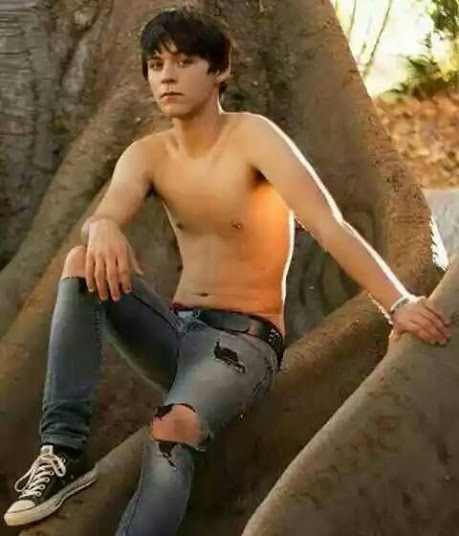
前へ|次へ
□ コメントを書く
□ 日記を書き直す
□ この日記を削除
[戻る]
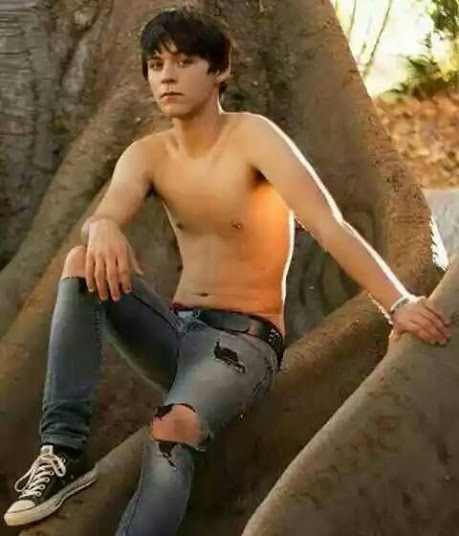
 彡
彡