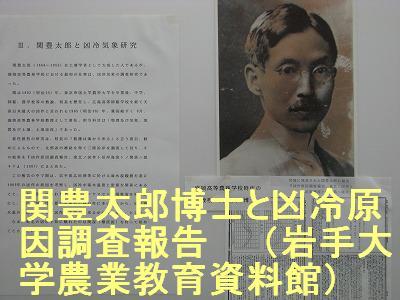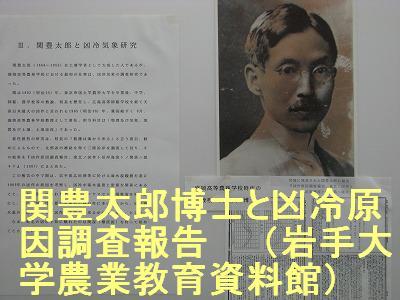ゆらぐ蜉蝣文字
□第7章 オホーツク挽歌
127ページ/250ページ
7.5.13
以上から、関豊太郎の研究成果を、今日の気象知識で再解釈しますと:
オホーツク海気団(日本に梅雨をもたらす)が強く、千島海流(親潮)が関東〜東北太平洋岸に残留する年には、同地方には北東〜東からの冷たい“やませ”風が吹きやすく、“やませ”は気温を低下させるだけでなく、海上から吹く“やませ”は海岸〜内陸部までを濃霧で覆い、日照時間を減少させます。
“やませ”の吹く時季は、梅雨明けであり、戦前の農暦では水稲の開花期でしたから、北上平野(盆地)など稲作を中心とする地方では、“やませ”の濃霧と低温は、凶作をもたらす原因となりえたのです。
なお、“やませ”の影響を受ける地域の中で、北海道、三陸沿岸、北上山間地などは、畑作・牧畜を中心としているので、凶作とはならないのです。
また、日本海側では、低温の気塊と濃霧は脊梁山脈で遮られ、“やませ”のフェーン現象が高温をもたらすので、秋田県などでは、かえって豊作になるとも言われます。
現在の東北の水稲作は、ビニール保温苗代による早稲が中心なので、冷害の影響は昔ほどでないと言えます。
さて、関教授の“凶作原因・潮流説”は、玉利校長の“40年周期説”とともに、発表当初は学会で論難を受け、激しい論争が続きますが、1913年の大凶作を契機に関説の有効性が見直され、凶冷予知を目的とした海洋観測が行なわれるまでになります。
宮澤賢治が盛岡高農で関教授から気象学を学んだのは(1915-18年)、まさに、関説が学会に受け入れられ、他の学者によって発展させられている時期だったのです。
賢治は、関豊太郎がもっとも意気に満ちた時期に、その指導を受ける幸運を得たと言えます。そして、その時期には、関は、土壌分析と石灰施用の有効性に関する研究という新たな課題に取り組んでおり、賢治はそこから生涯にわたる実践課題を受け継いだものと思われます。
. 宗谷挽歌
(根室の海温と金華山沖の海温
大正二年の曲線と大へんよく似てゐます。)
北海道の根室沖、および宮城県の金華山沖は、寒流の強さを測る重要な観測点です。そして、大正2年(1913年)は、関豊太郎説が見直されるきっかけとなった冷害凶作年です。
それらの海水温曲線が似ているとすれば、今年(1923年)もまた冷害となるおそれがあることになります☆
☆(注) しかし、1923年は凶冷年として記録されていませんから、さいわい、この年は大きな冷害にはならなかったもようです:⇒図説:東北の稲作と冷害
さきに見た「津軽海峡」に:
「今日はかもめが一疋も見えない。
(天候のためでなければ食物のため、
じっさいべーリング海峡の氷は
今年はまだみんな融け切らず
寒流はぢきその辺まで来てゐるのだ。)」
と書いていたのも、この“寒流と冷害の関係”を意識しています。
金華山沖の海水温が低ければ、寒流(千島海流)は南のほうにまで残っていると推定できます。夏になっても寒流の勢力が強いことは、オホーツク海高気圧の勢力が根強いことを意味し、それは“やませ”を吹走させ、凶冷の原因ともなりうるのです。★
★(注) なお、オホーツク海気団の勢力の消長は、地球全体の大気の循環に関係しており、何十年かの周期で変動しているとも言われます。そのことから言えば、玉利喜造の“40年周期説”も、古文書の研究によって周期を導き出す手法自体は科学的と言ってよく、決して、“易者だ”などという批判は当たらないのです。
.