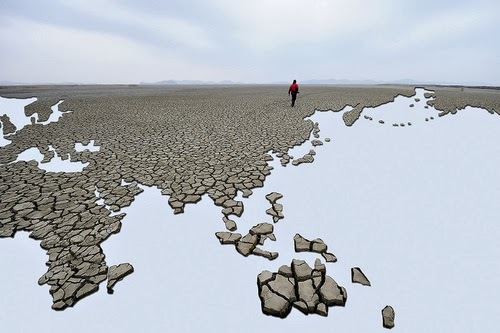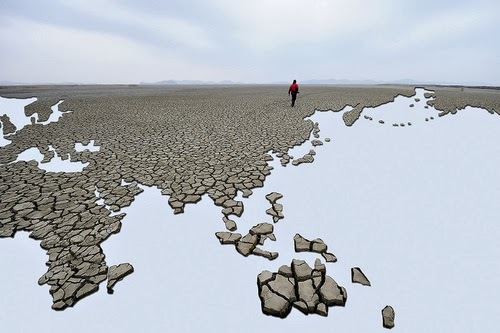ゆらぐ蜉蝣文字
□第6章 無声慟哭
26ページ/73ページ
6.1.25
ともかく、賢治は、自分には《異界》を見る能力があると信じていた。だから、死者とも交感できると。
ところが、最も近い肉親である妹の死に直面して☆、賢治は、死者に同伴して彼岸へ行くことはおろか、臨終のトシと“別れの挨拶”をすることすら、できなかったのです。そのような“心象”さえ、賢治をとらえてはくれなかった。。。
☆(注) 賢治批評の中では、賢治とトシを、恋人にも等しい間柄であったとして、“精神的近親相姦”などと呼ぶ傾向があります。しかし、ギトンは、これは誤りだと考えます。賢治とトシは、単なる近親であり肉親であったに過ぎません。“相姦”は、賢治がフィクションとして描いた“臨終三部作”やトシ挽歌類に引き摺られた見解だと思います。賢治とトシは、恋人のように親しかったわけでもありません。例えば、1921年に賢治が家出して東京に滞在していた間に、トシは母校・日本女子大学に、自分の後任教師の斡旋を頼むために、病いを押して上京しているのですが、賢治には会っていないのです。もし、トシが賢治の“恋人”であったとしたら、この場合誰よりも、東京にいる賢治を頼るはずではないでしょうか。また、トシが下根子の別宅で病床に就いている間、賢治も同所で寝起きしていますが、上述の細川キヨ聞書きによれば、賢治は、夜になると来ていたにすぎません。母も、夜はしばしば来ていました。そして、トシは、「本宅に移ったら自分は死ぬんだ。」と言っていたのに、賢治が本宅へ戻すことに反対した形跡もないのです。賢治は、トシのみならず、一般に女性には優しい性格だった(そのため、後年には、誤解して賢治にアタックする女性もいた)のは事実で、そのためトシにも優しく接していたにすぎません。
この冷厳な現実を、ただちに受け入れることは、彼にはできなかったと思うのです。
そこで、賢治は、死んだ妹と“別れの挨拶”をした、そういう“霊的な会話”をしたというフィクションを創り出したのだと、ギトンは考えます。
この場合、賢治にとっては、詩的創作が唯一可能な手段でしたし、気持ちの動揺を静めるには、そうするほかはなかったのだと思います。
したがって、“臨終三部作”は、これはもう《心象スケッチ》ではなくて《詩》です。見た「そのとほり」の“心象”を記録したものではなく、“死んでゆく妹と交感する臨終日”という虚構世界を、意識して創造したのですから。。。★
★(注) 三部作の作品日付の謎も、これによって解くことができます。『春と修羅』初版本の作品日付は、賢治が“心象”を体験し、スケッチした日付が記されていると考えます。しかし、「永訣の朝」「松の針」「無声慟哭」の三部作は、“心象”のスケッチではなく創作なのです。妹の死という事件は現実であっても、この3つの詩に書かれたことは、じっさいに幻想として見たものでさえなく、創作なのです。そこで、賢治は作品日付を二重括弧でくくった。このように考えます。
しかし、それでは、賢治は、なぜこのフィクションを、“未来形の挽歌”として書いたのでしょうか?
ひとつには、賢治が、もっとも交感したかったのは、臨終間際のトシとだったからだと思います:
トシ「みぞれ取って来て、お兄ちゃん」
賢治「さっきのみぞれをとってきた。あのきれいな松のえだだよ」
トシ「ああいい、さっぱりした。まるで林の中さ来たよだ」
トシ「おら、おらで、しゅとり行(え)ぐも」
賢治「わたくしにいっしょにいけとたのんでくれ。。。」
これらは、トシが死去する前だからできる会話ではないでしょうか?
しかし、これから死んでゆく者と、生の側に残る者との間で“別れの霊的会話”が成立するためには、両者のあいだに“未来の死の確信”がなければなりません。この場合、“死の確信”は、“霊的会話”が成立するためには必要条件なのです。
ところが、賢治をはじめ、家族たちはみな、まさにトシ死去の一瞬前まで、トシの“死の現実”から眼を背け、“死”に直面することを避けていました。“霊的交感”の詩的世界を創り上げるためには、このような都合の悪い事実は、捨象されなければなりません。
.